

橋本吉央
@yoshichiha
福島県に住んでおります。アラフォーです。アラフォーかあ。
本はまあまあ読むのですがプラクティカルなものばかりで、最近はもっと文学・哲学に触れたいなという気持ちです。
シェア型本屋の棚主もやっております。
- 2026年2月25日
- 2026年2月23日
 天国ではなく、どこかよそでレベッカ・ブラウン,柴田元幸読み終わったシニカルで不思議な短編集。抑圧された、弱い立場の苦しみのようなものを文体の中で表現しているように感じた。その中に悲しみが、言葉にはならないがあらわされているような。
天国ではなく、どこかよそでレベッカ・ブラウン,柴田元幸読み終わったシニカルで不思議な短編集。抑圧された、弱い立場の苦しみのようなものを文体の中で表現しているように感じた。その中に悲しみが、言葉にはならないがあらわされているような。 - 2026年2月21日
- 2026年2月20日
 一日の終わりの詩集長田弘読み終わった
一日の終わりの詩集長田弘読み終わった - 2026年2月19日
 実務家ブランド論片山義丈読み終わったおもしろかった。別の本で読んだ「ブランドは、記号と知覚価値の結びつきである」という定義をより砕いてわかりやすくしたのが「生活者の頭の中に浮かんだ妄想」と。 タイトル通り、実務として広報やPR業務をする際におさえておくとよい本だと思う。
実務家ブランド論片山義丈読み終わったおもしろかった。別の本で読んだ「ブランドは、記号と知覚価値の結びつきである」という定義をより砕いてわかりやすくしたのが「生活者の頭の中に浮かんだ妄想」と。 タイトル通り、実務として広報やPR業務をする際におさえておくとよい本だと思う。 - 2026年2月13日
- 2026年2月13日
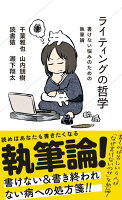 ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論千葉雅也,山内朋樹,瀬下翔太,読書猿読み終わったアウトライナーを使ってバーっと書き出すということがやはり大事なのだろうなと思った。 あとは最終的には、誰かに対して約束していて締め切りがあるということ。これが「書く」という行為のためには大事なのではないかと思う。自分の場合は。
ライティングの哲学 書けない悩みのための執筆論千葉雅也,山内朋樹,瀬下翔太,読書猿読み終わったアウトライナーを使ってバーっと書き出すということがやはり大事なのだろうなと思った。 あとは最終的には、誰かに対して約束していて締め切りがあるということ。これが「書く」という行為のためには大事なのではないかと思う。自分の場合は。 - 2026年2月7日
 真ん中の子どもたち温又柔読み終わった言語と血筋という二つの面から、若い登場人物たちのアイデンティティの苦しみを実直に描いている作品だと思った。 読んでいて共感ではなく発見的な気持ちの方がやっぱり大きかったことを感じて、自分がマジョリティ的なルーツの持ち方をしており、それによるアイデンティティに対する悩みを持たずに生きてきたということを、改めて実感。 琴子が自分なりの中国語の学び方をしていこうとする様子を見て、血筋は自分では変えられないけれど、言語、言葉については自分自身の意思を宿すことができる、というメッセージもあるのかなと受け取った。 きっと、同じように自分のルーツやアイデンティティに悩む人には、なんらかの形で助けになる小説なのではないかと思う。
真ん中の子どもたち温又柔読み終わった言語と血筋という二つの面から、若い登場人物たちのアイデンティティの苦しみを実直に描いている作品だと思った。 読んでいて共感ではなく発見的な気持ちの方がやっぱり大きかったことを感じて、自分がマジョリティ的なルーツの持ち方をしており、それによるアイデンティティに対する悩みを持たずに生きてきたということを、改めて実感。 琴子が自分なりの中国語の学び方をしていこうとする様子を見て、血筋は自分では変えられないけれど、言語、言葉については自分自身の意思を宿すことができる、というメッセージもあるのかなと受け取った。 きっと、同じように自分のルーツやアイデンティティに悩む人には、なんらかの形で助けになる小説なのではないかと思う。 - 2026年2月6日
- 2026年2月1日
- 2026年1月26日
 学びをやめない生き方入門中原淳,ベネッセ教育総合研究所,パーソル総合研究所読み終わったとてもいい本だった。サクッと読める。 自分の体験と照らし合わせても「そうだよなあ」と思うこともあれば「そうなんだけど、できてないなあ」と思うことが両方ある。 上司が学ぶことが、メンバーの学びに対して最も影響が大きい、というのは非常にぐさっと来た。しっかり学び続け、それを共有し続けていくことが大事だなあと実感。
学びをやめない生き方入門中原淳,ベネッセ教育総合研究所,パーソル総合研究所読み終わったとてもいい本だった。サクッと読める。 自分の体験と照らし合わせても「そうだよなあ」と思うこともあれば「そうなんだけど、できてないなあ」と思うことが両方ある。 上司が学ぶことが、メンバーの学びに対して最も影響が大きい、というのは非常にぐさっと来た。しっかり学び続け、それを共有し続けていくことが大事だなあと実感。 - 2026年1月18日
 想像ラジオいとうせいこう読み終わった自分が課題本に設定した読書会の直前の夜にようやく読み終わったのだけれど、けっこう精神に来た。元気が出る本というよりは、元気が要る本ではないかと思う。でも、大切な人を失うこと、それも大きな災害でたくさんの人が同時に亡くなる時に、残された人の想いはどこにどう向かうのかということを、死者の声を想像することでケアしていく、そんな意味があるように感じた本。おもしろかったとかおすすめとか安易に言えないが、読んでよかったな、と思う。
想像ラジオいとうせいこう読み終わった自分が課題本に設定した読書会の直前の夜にようやく読み終わったのだけれど、けっこう精神に来た。元気が出る本というよりは、元気が要る本ではないかと思う。でも、大切な人を失うこと、それも大きな災害でたくさんの人が同時に亡くなる時に、残された人の想いはどこにどう向かうのかということを、死者の声を想像することでケアしていく、そんな意味があるように感じた本。おもしろかったとかおすすめとか安易に言えないが、読んでよかったな、と思う。 - 2026年1月11日
 体力おばけへの道 頭も体も疲れにくくなるスゴイ運動國本充洋,澤木一貴読み終わったまあ、そうだよねという感じの話だった。読みやすくて、運動に苦手意識のある人にはいいんじゃないかなと思う。ジャンプ運動が骨粗鬆症に良いというのは知らなかったので、家族にも伝えようかな。
体力おばけへの道 頭も体も疲れにくくなるスゴイ運動國本充洋,澤木一貴読み終わったまあ、そうだよねという感じの話だった。読みやすくて、運動に苦手意識のある人にはいいんじゃないかなと思う。ジャンプ運動が骨粗鬆症に良いというのは知らなかったので、家族にも伝えようかな。 - 2026年1月10日
 体力が9割 結局、動いた者が勝つ堀江貴文読み終わった健康管理にフォーカスした本だったら、けっこう参考になるのではないか、と思って読んでみたのだが、85%くらいは『多動力』から変わらない感じのホリエモンビジネス書的な感じで、残り15%のうち自分に参考になりそうなのは2%くらい、という感じだった。は〜あ。
体力が9割 結局、動いた者が勝つ堀江貴文読み終わった健康管理にフォーカスした本だったら、けっこう参考になるのではないか、と思って読んでみたのだが、85%くらいは『多動力』から変わらない感じのホリエモンビジネス書的な感じで、残り15%のうち自分に参考になりそうなのは2%くらい、という感じだった。は〜あ。 - 2026年1月7日
 身近な薬物のはなし松本俊彦読み終わった非常に面白かった。多くの人に読んでほしい。 「薬物の違法/合法は医学的にではなく政治的に決定される」「良い薬物と悪い薬物があるのではなく、良い使い方と悪い使い方があるだけ」「悪い使い方をしている人には、何かしらそうさせる困りごとを抱えていると考えるのが大事」 この考え方は依存症に関連して広く言えることなのだと思う。自己責任と意志の強さみたいなものでどうにもならないことが、アルコールや薬物と人類の関わりの歴史を振り返ることでよくわかる本であった。
身近な薬物のはなし松本俊彦読み終わった非常に面白かった。多くの人に読んでほしい。 「薬物の違法/合法は医学的にではなく政治的に決定される」「良い薬物と悪い薬物があるのではなく、良い使い方と悪い使い方があるだけ」「悪い使い方をしている人には、何かしらそうさせる困りごとを抱えていると考えるのが大事」 この考え方は依存症に関連して広く言えることなのだと思う。自己責任と意志の強さみたいなものでどうにもならないことが、アルコールや薬物と人類の関わりの歴史を振り返ることでよくわかる本であった。 - 2026年1月4日
 読み終わった多分、著者は人間的には魅力のある人なのだろうなと思う。端々に、人に対する目線の温かさというか、人を大切にする姿勢を学んできた感じは出てきて、良い言葉もある。 ただ、本全体としては、あまり体系だってもいないし、正直に言って著者の方の個人的な経験も、「まあ、そういうこともあるんじゃない」という感じだし、ちょっと都合よく脚色しているように感じるところもあった。そういうのが好きじゃないのかも。 ホテルの経営をやることになって、人を大切にする経営で財務が良化して、そしたら本社がそれをファンドに売却し、その時に反対して懲戒免職に、みたいな話とか、まあけっこう謎。そうなることは、分かりきっていたのではないのか?サンマリーナホテルの経営エピソードをちょいちょい入れてくるけど、自分がいなくなった後のホテルがぐちゃぐちゃになってしまった一因は自分にもあるのでは?と思ったりする。 あとは、離婚の話も、離婚して、それから改めて今のパートナーと事実婚したということが書いてあったけど、いやあ、なんか嘘くさいな、と自分は思ってしまった。性格が悪いのと、ジェンダー観的に男性を疑がちなのだと思う。
読み終わった多分、著者は人間的には魅力のある人なのだろうなと思う。端々に、人に対する目線の温かさというか、人を大切にする姿勢を学んできた感じは出てきて、良い言葉もある。 ただ、本全体としては、あまり体系だってもいないし、正直に言って著者の方の個人的な経験も、「まあ、そういうこともあるんじゃない」という感じだし、ちょっと都合よく脚色しているように感じるところもあった。そういうのが好きじゃないのかも。 ホテルの経営をやることになって、人を大切にする経営で財務が良化して、そしたら本社がそれをファンドに売却し、その時に反対して懲戒免職に、みたいな話とか、まあけっこう謎。そうなることは、分かりきっていたのではないのか?サンマリーナホテルの経営エピソードをちょいちょい入れてくるけど、自分がいなくなった後のホテルがぐちゃぐちゃになってしまった一因は自分にもあるのでは?と思ったりする。 あとは、離婚の話も、離婚して、それから改めて今のパートナーと事実婚したということが書いてあったけど、いやあ、なんか嘘くさいな、と自分は思ってしまった。性格が悪いのと、ジェンダー観的に男性を疑がちなのだと思う。 - 2026年1月4日
 ラウリ・クースクを探して宮内悠介読み終わったエストニアという小国の、旧ソ連構成国からの独立という歴史的な背景の中で翻弄されながらも、登場人物たちが友情と自分の生き方を考えていく話で、少し引いたところがありながらも登場人物への愛みたいなものが通底していて読んでいて心地よかった。 小川哲が「脱法小説」と評価していたのはどういうことだったのか気になったのだが、それほどよくわからなかった。あたたかい群像劇でありつつ、程よい伏線回収と叙述トリック的な技法がいい味をしている、ということかなあ。 それならそれで、逆にもうちょっとパンチがあってもよかったかもしれない。程よくおさまって終わった感覚もなくはない。
ラウリ・クースクを探して宮内悠介読み終わったエストニアという小国の、旧ソ連構成国からの独立という歴史的な背景の中で翻弄されながらも、登場人物たちが友情と自分の生き方を考えていく話で、少し引いたところがありながらも登場人物への愛みたいなものが通底していて読んでいて心地よかった。 小川哲が「脱法小説」と評価していたのはどういうことだったのか気になったのだが、それほどよくわからなかった。あたたかい群像劇でありつつ、程よい伏線回収と叙述トリック的な技法がいい味をしている、ということかなあ。 それならそれで、逆にもうちょっとパンチがあってもよかったかもしれない。程よくおさまって終わった感覚もなくはない。 - 2026年1月4日
 現実はいつも対話から生まれるメアリー・ガーゲン,ケネス・J・ガーゲン,二宮美樹,伊藤守読み終わった本自体は、けっこう読みづらかった。翻訳がちょっとこなれていない感覚がある。疑問が残ったところを元に、ChatGPTと色々話していたら、だいぶ理解が深まった、気がする。本から理解したことよりも、一段深く理解できた感覚。やはり、本を元にAIに聞いて考える、というのは面白いのではないかな。
現実はいつも対話から生まれるメアリー・ガーゲン,ケネス・J・ガーゲン,二宮美樹,伊藤守読み終わった本自体は、けっこう読みづらかった。翻訳がちょっとこなれていない感覚がある。疑問が残ったところを元に、ChatGPTと色々話していたら、だいぶ理解が深まった、気がする。本から理解したことよりも、一段深く理解できた感覚。やはり、本を元にAIに聞いて考える、というのは面白いのではないかな。 - 2025年12月30日
 暗闇に手をひらく大崎清夏読み終わった最後の方に、山を登ることについての詩や散文が出てくるのだけれど、そこがよかった。「詩人」とか「循環に、混ぜてもらう」とか。朗読会で読みたいな。やっぱり、決意表明のような、意思を示そうとする言葉が好きなのかなあと思う。あと、最後の最後の「私は思い描く」も、色々なことに想いを馳せるきっかけ、記憶と思い出の栞のような詩でよかった。
暗闇に手をひらく大崎清夏読み終わった最後の方に、山を登ることについての詩や散文が出てくるのだけれど、そこがよかった。「詩人」とか「循環に、混ぜてもらう」とか。朗読会で読みたいな。やっぱり、決意表明のような、意思を示そうとする言葉が好きなのかなあと思う。あと、最後の最後の「私は思い描く」も、色々なことに想いを馳せるきっかけ、記憶と思い出の栞のような詩でよかった。 - 2025年12月28日
 本を読んだことがない32歳がはじめて本を読むかまど,みくのしん読み終わった一文一文、声に出して読みながら、一つ一つの描写を味わって登場人物の気持ちを想像して、というものすごく解像度の高い読み方をすることもできる、ということなのだなあと。こういう機会が、「本を読む」という行為でなくても、人生の中で一つでも多く持てると、豊かなのだろうなと思う。 本全体の構成としては、「走れメロス」を読んでいる時の雰囲気で、大体わかって、そのあとはそんなに読まなくても良いかな、という気もしたけど。
本を読んだことがない32歳がはじめて本を読むかまど,みくのしん読み終わった一文一文、声に出して読みながら、一つ一つの描写を味わって登場人物の気持ちを想像して、というものすごく解像度の高い読み方をすることもできる、ということなのだなあと。こういう機会が、「本を読む」という行為でなくても、人生の中で一つでも多く持てると、豊かなのだろうなと思う。 本全体の構成としては、「走れメロス」を読んでいる時の雰囲気で、大体わかって、そのあとはそんなに読まなくても良いかな、という気もしたけど。
読み込み中...



