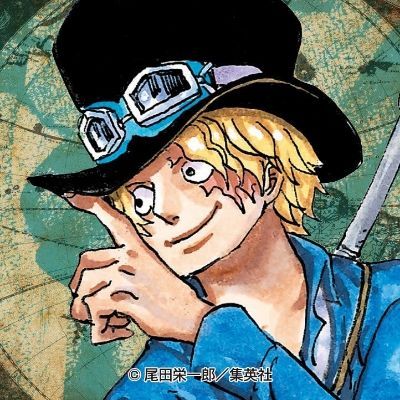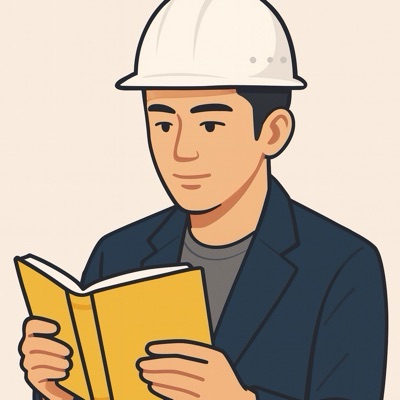人生の経営戦略

87件の記録
- 雨後の月@ybnmp3162026年1月12日■個人の人生を、コンサル的視点で再定義する一冊。 ■日本の衰退が直面しているのはデジタル人材の不足ではなく「自己決定能力の喪失」だという指摘に背筋が伸びる。 ■また、停滞と言われる日本も、治安や食、教育等の「幸福の指標」は世界最高峰。既存のGDPや経済成長率という他者のモノサシに縛られず、自分なりの尺度を再設定する重要性を痛感した。自己決定を放棄せず、自らの人生を経営する覚悟が持てる、深い洞察に満ちた一冊。


- ぱおん先輩@Ricky4444442026年1月3日▼「時間資本」をいかに効率的に「人的資本」に転換できるかが肝。 また、「社会資本」を生み出すのは人的資本で、時間資本を直接的に社会資本に投下しても構築は進まない。 併せて、「金融資本」についても、社会資本から生み出されるものである。 ▼「短期の合理は長期の不合理」、「短期の不合理は長期の合理」 ▼古典や名作と呼ばれるリベラルアーツが最もリターンの期間が長い投資
 ほりとも@tomokobeck2025年10月1日読み終わった人生には春・夏・秋・冬があり、40から50代は人生の夏から秋への移行時期。秋のキーワードは拡げる AI対策には、正解のある仕事を避ける、で対応する 楽しむ人には敵わない、これを意識して人生後半を過ごしたい ユニークな組み合わせ、学ぶは真似ること、ベンチマークの考え方など、経営戦略と聞くと難しく聞こえるが、人生をさらに充実し楽しくするための戦略がわかりやすい
ほりとも@tomokobeck2025年10月1日読み終わった人生には春・夏・秋・冬があり、40から50代は人生の夏から秋への移行時期。秋のキーワードは拡げる AI対策には、正解のある仕事を避ける、で対応する 楽しむ人には敵わない、これを意識して人生後半を過ごしたい ユニークな組み合わせ、学ぶは真似ること、ベンチマークの考え方など、経営戦略と聞くと難しく聞こえるが、人生をさらに充実し楽しくするための戦略がわかりやすい

- ごりやん@goriyan2025年9月2日読み終わった7/10点 ブログを追っていた+他の書籍にも書いてあることを含めると、既知の内容は8割程度。筆者特有の切り口もいくつか見られたので読む価値はあった。
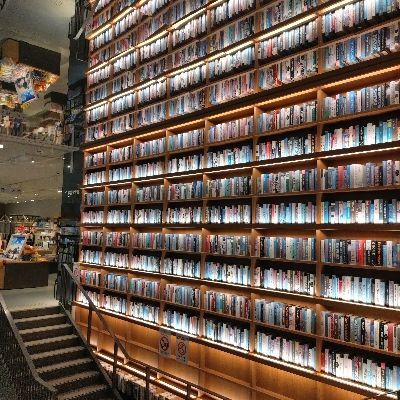 せい@seituka2025年8月25日また読み進めた。 心に残ったものを書く。 楽しんだほうが学べる 興味のないことを苦しんで進める人は、楽しむ人に勝てない。 内発的動機づけがある人が効果が出やすい 打席に立つことに専念する 成功の数は失敗も含めた打席の数に比例する。 失敗は忘れられるが、成功は名誉となる。 ベンチマーク=素直に真似るを実践するとよい 順序は ①課題認識を持つ 自分の課題に気付くこと ②ベンチマーク対象を選出する 能力に着目するのではなく、時間配分を真似する ③とりあえず真似てみる 素直に疑問を持たずに真似る
せい@seituka2025年8月25日また読み進めた。 心に残ったものを書く。 楽しんだほうが学べる 興味のないことを苦しんで進める人は、楽しむ人に勝てない。 内発的動機づけがある人が効果が出やすい 打席に立つことに専念する 成功の数は失敗も含めた打席の数に比例する。 失敗は忘れられるが、成功は名誉となる。 ベンチマーク=素直に真似るを実践するとよい 順序は ①課題認識を持つ 自分の課題に気付くこと ②ベンチマーク対象を選出する 能力に着目するのではなく、時間配分を真似する ③とりあえず真似てみる 素直に疑問を持たずに真似る
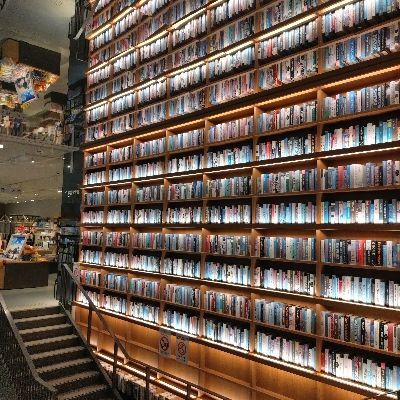 せい@seituka2025年8月20日読み始めた人生をマネジメントするための本 正直一度では、あまり頭に入ってこないが、まとめることで自分のものになりそうなので、まとめる。 一章パーパス 人生は時間資本を人的資本、社会資本、金融資本に変えるゲームである。 誰もが時間的資本を持っているが、それをどのタイミングでどう投資するかが重要。 時間資本⇒人的資本(スキル面や経験に投資する) 人的資本⇒社会資本(人的資本により、社会的に評価されるように) 社会資本⇒金融資本(より上質な仕事に就ける) 上記サイクルがウェルビーイングを生み出す ※人的資本は直接金融資本にならない(社会的資本(評価)がなければ稼げる仕事に就けない) 現在自分の時間的資本の投資は、通常の仕事、勉強(応用情報技術者試験)に向いている。 現在の仕事のスキル面いえば、主務では成長を感じない(下がいないので、最低限の仕事までやっている)。また残業も多い 勉強も主務には関わらないものの兼務で入っている仕事に役立つ上、部長、課長からの評価は上がるため、やっていて悪いものではない。 今無駄にしている時間は、 朝の通勤電車での睡眠 家に帰ってからのスマホ触る ここを人的資本の投資に繋がるよう意識していきたい。
せい@seituka2025年8月20日読み始めた人生をマネジメントするための本 正直一度では、あまり頭に入ってこないが、まとめることで自分のものになりそうなので、まとめる。 一章パーパス 人生は時間資本を人的資本、社会資本、金融資本に変えるゲームである。 誰もが時間的資本を持っているが、それをどのタイミングでどう投資するかが重要。 時間資本⇒人的資本(スキル面や経験に投資する) 人的資本⇒社会資本(人的資本により、社会的に評価されるように) 社会資本⇒金融資本(より上質な仕事に就ける) 上記サイクルがウェルビーイングを生み出す ※人的資本は直接金融資本にならない(社会的資本(評価)がなければ稼げる仕事に就けない) 現在自分の時間的資本の投資は、通常の仕事、勉強(応用情報技術者試験)に向いている。 現在の仕事のスキル面いえば、主務では成長を感じない(下がいないので、最低限の仕事までやっている)。また残業も多い 勉強も主務には関わらないものの兼務で入っている仕事に役立つ上、部長、課長からの評価は上がるため、やっていて悪いものではない。 今無駄にしている時間は、 朝の通勤電車での睡眠 家に帰ってからのスマホ触る ここを人的資本の投資に繋がるよう意識していきたい。 kei@k32452025年8月17日読み終わった山口周著「人生の経営戦略」読了。 2025/8 4冊目 ◎サマリ ・人生を春夏秋冬で考えてみる ・いろんなものの掛け合わせで自分らしさを築く ・頑張るは楽しいに勝てない ◎書評 毎度多くの示唆を提供してくれる山口さんの著作。 今回もハッとさせられる観点がたくさんあった。 人生を幸せで豊かなものにするためには必ず長期視点が必要だということ、そしてそれは戦略的に構築していけるというのが本書のメッセージ。 ①人生を春夏秋冬で考える 20代までは人生の春→多様な価値観を取り入れるべき時期 30代〜40代は人生の夏→人生で一番輝く時、20代で得た多様な価値観の中から自分がこれだと思うものに時間をかける 50代〜60代は人生の秋→夏に築いたものをどんどん拡げる 70代〜は人生の冬→これまで培ってきたものを人に教えてる、人と人とをつなぐ じゃあ自分は今どこにいるか。もう30代になってしまったが、まだ人生の春の延長戦をやるのもいいのかなと気づいた。 しかし、やるなるならやるで早めにならないと夏が短くなるわけで… このあたりをどういったバランスでやるべきかすごく考えるきっかけになった ②いろんなものの掛け合わせで自分らしさを築く 有名なブルーオーシャン戦略にも触れられているが、それは自分の過去を振り返ってユニークな組み合わせで作るべきとの示唆があった。 自分も転職何回も重ねてジョブホッパーと言われようが、それはそれで個性。 いろんなものの掛け合わせがしやすくなるので、何か良い視点が生まれるのではないかとずっと思っていた。 それをうまく山口さんが言語化してくれていてすごくすっきりした。 改めて自分の経験の掛け合わせをやってみたい。 ③頑張るは楽しいに勝てない これがほんと一番身に沁みた。 今の仕事に対してつらさしか感じていない自分はかち殴られたような感じがした。 楽しく長くやる。それが最高の戦略だと。 しかし、コンフォートゾーンに収まり続けてもいけない。長くても10年でステージを変えていく。 でも楽しくなること。それが一番。 もっとたくさん打席に立って自分の楽しいをもっと真剣に見出さなくてはならないのだと思う。 なんならこうやって本の感想を書いているのが一番楽しいかもしれない。 これもまた気づきだ。
kei@k32452025年8月17日読み終わった山口周著「人生の経営戦略」読了。 2025/8 4冊目 ◎サマリ ・人生を春夏秋冬で考えてみる ・いろんなものの掛け合わせで自分らしさを築く ・頑張るは楽しいに勝てない ◎書評 毎度多くの示唆を提供してくれる山口さんの著作。 今回もハッとさせられる観点がたくさんあった。 人生を幸せで豊かなものにするためには必ず長期視点が必要だということ、そしてそれは戦略的に構築していけるというのが本書のメッセージ。 ①人生を春夏秋冬で考える 20代までは人生の春→多様な価値観を取り入れるべき時期 30代〜40代は人生の夏→人生で一番輝く時、20代で得た多様な価値観の中から自分がこれだと思うものに時間をかける 50代〜60代は人生の秋→夏に築いたものをどんどん拡げる 70代〜は人生の冬→これまで培ってきたものを人に教えてる、人と人とをつなぐ じゃあ自分は今どこにいるか。もう30代になってしまったが、まだ人生の春の延長戦をやるのもいいのかなと気づいた。 しかし、やるなるならやるで早めにならないと夏が短くなるわけで… このあたりをどういったバランスでやるべきかすごく考えるきっかけになった ②いろんなものの掛け合わせで自分らしさを築く 有名なブルーオーシャン戦略にも触れられているが、それは自分の過去を振り返ってユニークな組み合わせで作るべきとの示唆があった。 自分も転職何回も重ねてジョブホッパーと言われようが、それはそれで個性。 いろんなものの掛け合わせがしやすくなるので、何か良い視点が生まれるのではないかとずっと思っていた。 それをうまく山口さんが言語化してくれていてすごくすっきりした。 改めて自分の経験の掛け合わせをやってみたい。 ③頑張るは楽しいに勝てない これがほんと一番身に沁みた。 今の仕事に対してつらさしか感じていない自分はかち殴られたような感じがした。 楽しく長くやる。それが最高の戦略だと。 しかし、コンフォートゾーンに収まり続けてもいけない。長くても10年でステージを変えていく。 でも楽しくなること。それが一番。 もっとたくさん打席に立って自分の楽しいをもっと真剣に見出さなくてはならないのだと思う。 なんならこうやって本の感想を書いているのが一番楽しいかもしれない。 これもまた気づきだ。
 chihhy@chi_hi_ro112025年7月8日読み終わった▪︎人生は時間資本を別の資本に変えるゲーム。 時間資本 → 人的資本: スキル、知識、経験 人的資本 → 社会資本: 信用・評判、ネットワーク、友人・家族関係 社会資本 → 金融資本: 現金、株式・債券、不動産等 ▪︎打席に立つ数を増やす 若ければ若いほどホームランが出るとリターンの期間が長くなる。失敗のコストは人生の後半になればなるほど高くなる。
chihhy@chi_hi_ro112025年7月8日読み終わった▪︎人生は時間資本を別の資本に変えるゲーム。 時間資本 → 人的資本: スキル、知識、経験 人的資本 → 社会資本: 信用・評判、ネットワーク、友人・家族関係 社会資本 → 金融資本: 現金、株式・債券、不動産等 ▪︎打席に立つ数を増やす 若ければ若いほどホームランが出るとリターンの期間が長くなる。失敗のコストは人生の後半になればなるほど高くなる。 ぜんこ@shirushiru2025年6月20日読み終わったテレビで著者が話しているのを見て、すぐ買った。 落としこむまで読みたい本。 持続的なウェルビーイングを目指すため、まずは時間資本の見直しから取りかかる。 もっと若いうちから読みたかったなー
ぜんこ@shirushiru2025年6月20日読み終わったテレビで著者が話しているのを見て、すぐ買った。 落としこむまで読みたい本。 持続的なウェルビーイングを目指すため、まずは時間資本の見直しから取りかかる。 もっと若いうちから読みたかったなー

 さくら@saku_kamo_ne2025年6月12日気になる山口周さんの新しめの本。YouTubeを見ていて読みたくなった。人生を長期的に捉えて設計するなんて、今まではつまらないなと思っていたし、なんか怖いなって感じていた。自分も変わってきたということなのかな。
さくら@saku_kamo_ne2025年6月12日気になる山口周さんの新しめの本。YouTubeを見ていて読みたくなった。人生を長期的に捉えて設計するなんて、今まではつまらないなと思っていたし、なんか怖いなって感じていた。自分も変わってきたということなのかな。

 耕太郎@Forester_7272025年6月5日感想山口さんの人生に対する想いの深さと、それに対する解決策の洞察に感動する。 自分に残された時間をどのように投資し、使っていくかの指針にしたい本となる。
耕太郎@Forester_7272025年6月5日感想山口さんの人生に対する想いの深さと、それに対する解決策の洞察に感動する。 自分に残された時間をどのように投資し、使っていくかの指針にしたい本となる。

 ぽぽ@wakio2025年4月7日読み終わった⸻ 『人生の経営戦略』山口周 読書記録 ⸻ キャリアの意思決定に、俯瞰の視点を 本書は、人生を「経営」するという視点から、自分らしい時間配分と意思決定をどのように行うかを問いかけてくる一冊だった。 きっかけは、妻からの勧めと、以前読んだ山口周の著作が好みに合っていたこと。読み進める中で、これまでぼんやりと考えていた「人生の時間の使い方」についての感覚が、より解像度高く整理された感覚を得た。 ⸻ 「いつ余命宣告されても、いい人生だった」と思えるように 本書の中で特に印象に残ったのは、著者が提唱するパーパス(目的)の定義だった。 「時間配分を適切に配分することで持続的なウェルビーイングの状態を築き上げ、いつ余命宣告をされても『自分らしい、いい人生だった』と思えるような人生を送る」 これは、働き方やキャリアの選び方を考えるうえで、日々の忙しさに追われがちな視点から一歩引いて、自分の人生全体を設計する視点を持たせてくれる言葉だった。 ⸻ アウトプットを起点に、思考を整理する 本書を読んだことで、「やはりアウトプット量は正義だ」という思いが強くなった。 実際に、なかなかできていなかったアウトプットとして、noteでの記述を開始した。テーマは主に、自己実現に向けた取り組みに関するChatGPTとの対話や、読書記録など。思考を外に出すことで、輪郭がはっきりしてくる実感がある。 ⸻ まとめ 『人生の経営戦略』は、キャリアを含めた人生全体の設計を考えるうえでの俯瞰的な視点を与えてくれる一冊だった。 すでに考えていたことに対し、理論的な裏付けや言語化の助けを与えてくれたことで、自分の方針に対する納得感が高まり、行動にもつながったと感じている。 ⸻ 今後も、noteでの発信を通じて思考を深めていきたい。 読書もアウトプットのきっかけとして続けていきたいと感じさせる読後だった。
ぽぽ@wakio2025年4月7日読み終わった⸻ 『人生の経営戦略』山口周 読書記録 ⸻ キャリアの意思決定に、俯瞰の視点を 本書は、人生を「経営」するという視点から、自分らしい時間配分と意思決定をどのように行うかを問いかけてくる一冊だった。 きっかけは、妻からの勧めと、以前読んだ山口周の著作が好みに合っていたこと。読み進める中で、これまでぼんやりと考えていた「人生の時間の使い方」についての感覚が、より解像度高く整理された感覚を得た。 ⸻ 「いつ余命宣告されても、いい人生だった」と思えるように 本書の中で特に印象に残ったのは、著者が提唱するパーパス(目的)の定義だった。 「時間配分を適切に配分することで持続的なウェルビーイングの状態を築き上げ、いつ余命宣告をされても『自分らしい、いい人生だった』と思えるような人生を送る」 これは、働き方やキャリアの選び方を考えるうえで、日々の忙しさに追われがちな視点から一歩引いて、自分の人生全体を設計する視点を持たせてくれる言葉だった。 ⸻ アウトプットを起点に、思考を整理する 本書を読んだことで、「やはりアウトプット量は正義だ」という思いが強くなった。 実際に、なかなかできていなかったアウトプットとして、noteでの記述を開始した。テーマは主に、自己実現に向けた取り組みに関するChatGPTとの対話や、読書記録など。思考を外に出すことで、輪郭がはっきりしてくる実感がある。 ⸻ まとめ 『人生の経営戦略』は、キャリアを含めた人生全体の設計を考えるうえでの俯瞰的な視点を与えてくれる一冊だった。 すでに考えていたことに対し、理論的な裏付けや言語化の助けを与えてくれたことで、自分の方針に対する納得感が高まり、行動にもつながったと感じている。 ⸻ 今後も、noteでの発信を通じて思考を深めていきたい。 読書もアウトプットのきっかけとして続けていきたいと感じさせる読後だった。
 コージー@koji15332025年3月17日読み終わったこの本に出会えてよかった。今年ナンバーワン本の候補。経営学を学んでいない一般人からすると難しい話も出てくるので、手元に置いておいて定期的に読み返そうと思う。雑な言い方だけど、ほんと全人類読んだほうがいい。
コージー@koji15332025年3月17日読み終わったこの本に出会えてよかった。今年ナンバーワン本の候補。経営学を学んでいない一般人からすると難しい話も出てくるので、手元に置いておいて定期的に読み返そうと思う。雑な言い方だけど、ほんと全人類読んだほうがいい。
- とあるサラリーマン部長@hakusant2025年3月8日子どもの教育視点で、この情報はとても役に立った。→創造性に関する研究によると、成功は「量」から生まれることが多い。歴史上の偉大なイノベーター(ダ・ヴィンチ、エジソンなど)を分析し、「多くを生み出したから成功した」と指摘。彼らの傑作は、膨大なアウトプットの中のごく一部であり、量を増やすことで質の高い成果が確率的に生まれる。バッハの残した1000以上の曲のうち、今日でもコンサートで演奏さ れているのは定番の30~50曲程度でしかありません。エジソンに至っては取得した1 000以上の特許のうち、実際のビジネスに繋がったものは10~20程度とのこと。重要なのは「打率」ではなく「打席数」で、多くの挑戦が成功への鍵、とのこと。

 yasunaga@y5ng1900年1月1日読了「発言と離脱」(アルバート•ハーシュマン) ↪︎組織や社会などのシステムを健全に機能させるためには重要 ↪︎「発言」とは「間違っていると思うことに対して声を上げる」こと、「離脱」とは「間違っていると思う場所や組織から離脱する」こと 『蛇のように賢く、鳩のように素直に』 人生の経営戦略=ライフ•マネジメント•ストラテジーの検討において、コントロールできる戦略変数は「時間資本」しかない 市場における価値は能力や知識の水準ではなく、需要と供給の関係によって決まる ↪︎流行の資格や学位は戦略的にスジの悪い戦略 RVB(リソース•ベースド•ビュー) ↔︎ポジショニング ↪︎企業の持続的な競争優位性が、その企業が持つ独自の資源や能力に依存する ↪︎条件①有用性(Valuable)②希少性(Rare)③模倣困難性(Inimitable)④代替不可能性(Non-substitutable) 成功と失敗の費用対効果は非対称 ゲーム理論 ↪︎相手に出方や環境の変化に応じて変動する自分の選択肢の正味リターンを分析する ↪︎相手がどう出てこようと、周辺環境がどう変わろうと、自分の持っている選択肢の中で一番リターンが大きくなる選択肢「絶対優位の戦略」 NPVの考え方 ↪︎「目の前の小さな利益」を「ずっと先の大きな利益」よりも過大評価する誤認識=現状バイアスがある ⇨示唆①「すぐに役に立つもの」ばかりに手を出すのは危険②「リターンの期間」が非常に重要③流行りのスキルや知識に時間資本を投下するのは「絶対劣位の戦略」 コンフォートゾーンを抜ける 流動性知能 ↪︎過去の経験や学習に依存せず、論理的に考えたり、パターンを見つけたりする知的能力 ↪︎20歳前後にピークに達し、40代以降は急速に低下 結晶性知能 ↪︎過去の経験や学習によって蓄積された知識やスキルを活用する知的能力 ↪︎蓄積依存のため、年を追うごとに向上し、50〜60代にピークを迎え、その後も高原状態
yasunaga@y5ng1900年1月1日読了「発言と離脱」(アルバート•ハーシュマン) ↪︎組織や社会などのシステムを健全に機能させるためには重要 ↪︎「発言」とは「間違っていると思うことに対して声を上げる」こと、「離脱」とは「間違っていると思う場所や組織から離脱する」こと 『蛇のように賢く、鳩のように素直に』 人生の経営戦略=ライフ•マネジメント•ストラテジーの検討において、コントロールできる戦略変数は「時間資本」しかない 市場における価値は能力や知識の水準ではなく、需要と供給の関係によって決まる ↪︎流行の資格や学位は戦略的にスジの悪い戦略 RVB(リソース•ベースド•ビュー) ↔︎ポジショニング ↪︎企業の持続的な競争優位性が、その企業が持つ独自の資源や能力に依存する ↪︎条件①有用性(Valuable)②希少性(Rare)③模倣困難性(Inimitable)④代替不可能性(Non-substitutable) 成功と失敗の費用対効果は非対称 ゲーム理論 ↪︎相手に出方や環境の変化に応じて変動する自分の選択肢の正味リターンを分析する ↪︎相手がどう出てこようと、周辺環境がどう変わろうと、自分の持っている選択肢の中で一番リターンが大きくなる選択肢「絶対優位の戦略」 NPVの考え方 ↪︎「目の前の小さな利益」を「ずっと先の大きな利益」よりも過大評価する誤認識=現状バイアスがある ⇨示唆①「すぐに役に立つもの」ばかりに手を出すのは危険②「リターンの期間」が非常に重要③流行りのスキルや知識に時間資本を投下するのは「絶対劣位の戦略」 コンフォートゾーンを抜ける 流動性知能 ↪︎過去の経験や学習に依存せず、論理的に考えたり、パターンを見つけたりする知的能力 ↪︎20歳前後にピークに達し、40代以降は急速に低下 結晶性知能 ↪︎過去の経験や学習によって蓄積された知識やスキルを活用する知的能力 ↪︎蓄積依存のため、年を追うごとに向上し、50〜60代にピークを迎え、その後も高原状態