
読書日和
@miou-books
- 2026年2月24日
 読み終わった余命宣告を受けてからの1年間、 「死に最も近い場所」から書かれた記録。 私たちは、生まれてきたこと自体が奇跡。 世界中に何十億もの人の中で、両親が出会い、愛し合い、その結果として今ここに自分がいる。 ほんの少しタイミングが違っただけで、 ここにいるのは別の誰かだったかもしれない。 そう考えると、生きているだけで幸せ、という言葉の重みが変わってくる。 読んでいて、頭では理解しているのに、実生活ではできていないことがたくさんあると痛感した。 もうこの世にいない著者からのアドバイスとして、 自分の中にもう一度落とし込みたいと思った。 特に心に残ったのは、 人はいつも誰かと自分を比べてしまうという話。 SNSには、誰かの人生の「いい部分」だけが並んでいる。 それを見て、自分の人生を小さく感じてしまう。 でも本当に大切なのは、 お金では買えないもの。 家族、愛情、成長、達成感、 そして何かに夢中になること。 印象的だった言葉がもう一つ。 「思考や感情は浮かんでは消えるもの。過去は記憶の中、未来は想像の中にしかない。」だからこそ、今に集中すること。 「定年になったらやろう」そう思っていることがあるなら、今やるべきなのだ。 旅に出よう。 新しいことを始めよう。 学ぼう。 誰かに会おう。 働きすぎないようにしよう。 今日という日を、ちゃんと生き、そして楽しみ続けよう。
読み終わった余命宣告を受けてからの1年間、 「死に最も近い場所」から書かれた記録。 私たちは、生まれてきたこと自体が奇跡。 世界中に何十億もの人の中で、両親が出会い、愛し合い、その結果として今ここに自分がいる。 ほんの少しタイミングが違っただけで、 ここにいるのは別の誰かだったかもしれない。 そう考えると、生きているだけで幸せ、という言葉の重みが変わってくる。 読んでいて、頭では理解しているのに、実生活ではできていないことがたくさんあると痛感した。 もうこの世にいない著者からのアドバイスとして、 自分の中にもう一度落とし込みたいと思った。 特に心に残ったのは、 人はいつも誰かと自分を比べてしまうという話。 SNSには、誰かの人生の「いい部分」だけが並んでいる。 それを見て、自分の人生を小さく感じてしまう。 でも本当に大切なのは、 お金では買えないもの。 家族、愛情、成長、達成感、 そして何かに夢中になること。 印象的だった言葉がもう一つ。 「思考や感情は浮かんでは消えるもの。過去は記憶の中、未来は想像の中にしかない。」だからこそ、今に集中すること。 「定年になったらやろう」そう思っていることがあるなら、今やるべきなのだ。 旅に出よう。 新しいことを始めよう。 学ぼう。 誰かに会おう。 働きすぎないようにしよう。 今日という日を、ちゃんと生き、そして楽しみ続けよう。 - 2026年2月23日
 台湾にひとりで1か月住んでみたおがたちえ読み終わった会社帰りに丸善に寄り道。 平台に積まれていたこの本を見て、 「そうだよーーー、私も1か月くらい台湾に住んでみたい…」 と、すがるような気持ちでタイトルだけ見て即決。 帰りの電車で読み始めてしまった。 50歳を迎え、ひとり息子も成人。 仕事・家事・育児で大忙しだった日々が少し落ち着いた頃、 著者がふと思い出した長年の夢。 台湾でひとり暮らしをする。 確かに、1か月単位なら不動産契約もいらないし、 気軽に戻れるし、私にもできるかも…… (いやいや、仕事どうするの?収入源は?とすぐ自分ツッコミ) いきなり1都市に絞るのではなく、 台北・高雄・台南・台中といくつかの都市で ホテル暮らし、学生寮(おお!と食いついたけれど想像と少し違った)、 友人宅に宿泊、民泊など、いろいろ試していて、コストの紹介もあり参考になる。 とはいえ、今の円安と物価高。 日本の物価が上がる以上に、ここ数年の台湾の物価上昇にはため息…。 できるかなぁ、憧れるけどなぁ、となかなか思いきれない自分もいる。 便利な台北にはやっぱり憧れるけれど、 不動産価格と物価の高さには涙目。 でも最近読んだ作品の影響で、台中暮らしもいいよなぁ、とか、 日差しに耐えられるか分からないけど高雄もいいよねぇ、とか。 夢だけはどんどん広がっていく。
台湾にひとりで1か月住んでみたおがたちえ読み終わった会社帰りに丸善に寄り道。 平台に積まれていたこの本を見て、 「そうだよーーー、私も1か月くらい台湾に住んでみたい…」 と、すがるような気持ちでタイトルだけ見て即決。 帰りの電車で読み始めてしまった。 50歳を迎え、ひとり息子も成人。 仕事・家事・育児で大忙しだった日々が少し落ち着いた頃、 著者がふと思い出した長年の夢。 台湾でひとり暮らしをする。 確かに、1か月単位なら不動産契約もいらないし、 気軽に戻れるし、私にもできるかも…… (いやいや、仕事どうするの?収入源は?とすぐ自分ツッコミ) いきなり1都市に絞るのではなく、 台北・高雄・台南・台中といくつかの都市で ホテル暮らし、学生寮(おお!と食いついたけれど想像と少し違った)、 友人宅に宿泊、民泊など、いろいろ試していて、コストの紹介もあり参考になる。 とはいえ、今の円安と物価高。 日本の物価が上がる以上に、ここ数年の台湾の物価上昇にはため息…。 できるかなぁ、憧れるけどなぁ、となかなか思いきれない自分もいる。 便利な台北にはやっぱり憧れるけれど、 不動産価格と物価の高さには涙目。 でも最近読んだ作品の影響で、台中暮らしもいいよなぁ、とか、 日差しに耐えられるか分からないけど高雄もいいよねぇ、とか。 夢だけはどんどん広がっていく。 - 2026年2月23日
 最悪の相棒伏尾美紀読み終わったお正月に実家へ帰ったとき、 実家の本棚から持ち帰ってきた一冊。 予備知識もなく、なんとなく選んだ本。 警察ミステリー。 かつて姉をストーカーに殺害された犯罪被害者家族の潮崎と、代々警察一家に育った広中。 広中の父は犯罪被害者支援室の担当として潮崎に寄り添っていたが、 その結果、自分は父を失った――そんな思いを抱えている。 その二人が、潮崎を中心とした新しい部署の立ち上げでバディを組むことになる。 設定だけ見ると、 「ちょっと無理があるのでは…?」と思いつつも、 読み始めるとすぐに物語になじんでしまった。 展開も早くて、気づけばあっという間に読み終わっていた。 やっぱり刑事ドラマが好きなんだな、と実感。 そして、疲れているときほどミステリーは癒しになる。
最悪の相棒伏尾美紀読み終わったお正月に実家へ帰ったとき、 実家の本棚から持ち帰ってきた一冊。 予備知識もなく、なんとなく選んだ本。 警察ミステリー。 かつて姉をストーカーに殺害された犯罪被害者家族の潮崎と、代々警察一家に育った広中。 広中の父は犯罪被害者支援室の担当として潮崎に寄り添っていたが、 その結果、自分は父を失った――そんな思いを抱えている。 その二人が、潮崎を中心とした新しい部署の立ち上げでバディを組むことになる。 設定だけ見ると、 「ちょっと無理があるのでは…?」と思いつつも、 読み始めるとすぐに物語になじんでしまった。 展開も早くて、気づけばあっという間に読み終わっていた。 やっぱり刑事ドラマが好きなんだな、と実感。 そして、疲れているときほどミステリーは癒しになる。 - 2026年2月20日
 ゆっくり、いそげ影山知明読み終わった働いても働いても幸せが遠のいていくように感じるのはなぜなのか。 金銭換算しにくい価値は失われるしかないのか。 「時間との戦い」は終わることがないのか。 この生きづらさの正体は何なのか。 読み終わって、この本10年以上前に書かれたんだ!と驚く。 いまでこそ「利益追求」「Take」だけじゃないんじゃないの?世の中。と思えるようになってきたけれど、 それを10年前から実践していたんだ、それもカフェで。 お金だけでない大事なものを大事にする仕組み。 漠然と老後の不安、お金の不安を抱えているけれど、こういう仕組みの中にいたら世の中の見方、考え方も変わってくるかも、と思った。
ゆっくり、いそげ影山知明読み終わった働いても働いても幸せが遠のいていくように感じるのはなぜなのか。 金銭換算しにくい価値は失われるしかないのか。 「時間との戦い」は終わることがないのか。 この生きづらさの正体は何なのか。 読み終わって、この本10年以上前に書かれたんだ!と驚く。 いまでこそ「利益追求」「Take」だけじゃないんじゃないの?世の中。と思えるようになってきたけれど、 それを10年前から実践していたんだ、それもカフェで。 お金だけでない大事なものを大事にする仕組み。 漠然と老後の不安、お金の不安を抱えているけれど、こういう仕組みの中にいたら世の中の見方、考え方も変わってくるかも、と思った。 - 2026年2月20日
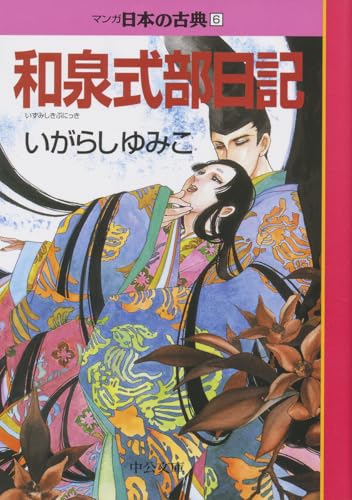 マンガ日本の古典(6)いがらしゆみこ読み終わった急に古典が読みたくなって。 でも時間もあまりなかったので、手っ取り早く漫画版に手を伸ばしました。 てっきり、和泉式部本人が書いた日記だと思っていたのですが、実は第三者が書いたという説もあるらしい。 読んでみると、男女の馴れ初めから、 亡くなった元恋人を思う気持ち、さらにその弟との恋愛、 そして宮中に召し上げられていくまで―― かなり赤裸々な恋愛の記録。 ここまでドラマチックだと、 むしろ「誰かが物語として書いた」と言われたほうがしっくりくる気もする。 そしてラスト。 私は御所に迎えられ、正妻である北の方は出ていった、ところで終わる。 わー、平安時代のマウンティング?略奪愛も激しいわね、、と読み終えたところです。
マンガ日本の古典(6)いがらしゆみこ読み終わった急に古典が読みたくなって。 でも時間もあまりなかったので、手っ取り早く漫画版に手を伸ばしました。 てっきり、和泉式部本人が書いた日記だと思っていたのですが、実は第三者が書いたという説もあるらしい。 読んでみると、男女の馴れ初めから、 亡くなった元恋人を思う気持ち、さらにその弟との恋愛、 そして宮中に召し上げられていくまで―― かなり赤裸々な恋愛の記録。 ここまでドラマチックだと、 むしろ「誰かが物語として書いた」と言われたほうがしっくりくる気もする。 そしてラスト。 私は御所に迎えられ、正妻である北の方は出ていった、ところで終わる。 わー、平安時代のマウンティング?略奪愛も激しいわね、、と読み終えたところです。 - 2026年2月17日
 花咲く街の少女たち青波杏読み終わった1936年、日本統治下の京城(ソウル)を舞台に出会った二人の少女、翠とハナの物語。 日本の私娼窟育ちの翠と、朝鮮人のお手伝いであるハナ。 立場も生い立ちも異なる二人は、惹かれ合いながらも、時代や差別、そして自分たちの置かれた環境によって素直になれず、もどかしい関係を続る。 物語は翠の父親の秘密へとつながり、二人の運命が静かに交差していく。最後は日本統治下の台湾へと舞台を移し、歴史の流れの中で懸命に生きる少女たちの姿が、前向きな気持ちにさせてくれる。 仲良くなりたいのに、なれない。心を開きたいのに、立場がそれを許さない。その繊細な心の揺れが胸に残りました。 読み終えた今、青波さんの他の作品も読みたい!気持ちです。
花咲く街の少女たち青波杏読み終わった1936年、日本統治下の京城(ソウル)を舞台に出会った二人の少女、翠とハナの物語。 日本の私娼窟育ちの翠と、朝鮮人のお手伝いであるハナ。 立場も生い立ちも異なる二人は、惹かれ合いながらも、時代や差別、そして自分たちの置かれた環境によって素直になれず、もどかしい関係を続る。 物語は翠の父親の秘密へとつながり、二人の運命が静かに交差していく。最後は日本統治下の台湾へと舞台を移し、歴史の流れの中で懸命に生きる少女たちの姿が、前向きな気持ちにさせてくれる。 仲良くなりたいのに、なれない。心を開きたいのに、立場がそれを許さない。その繊細な心の揺れが胸に残りました。 読み終えた今、青波さんの他の作品も読みたい!気持ちです。 - 2026年2月16日
 神秘列車甘耀明,白水紀子読み終わった三叉山事件を題材にした「真の人間になる」を読んで、すっかり甘耀明さんのファンになり、こちらも手に取った。 本書は短編集で、収録作の多くは 著者の故郷、台湾・苗栗県を舞台にしている。 表題作「神秘列車」は、 かつて政治犯として拘束された祖父が乗ったという “謎の列車”を探すため、少年が旅に出る物語。 国民党による白色テロによって引き裂かれた 祖父と祖母の秘められた過去、 政治の暴力が家族にもたらした分断の記憶を、 少年の視点からさかのぼっていく。 読んでいると、光景が自然と目に浮かび、 まるで映画の世界に入り込んだようだった。 二作目の「伯公、妾を娶る」は、 背景を理解するのに正直かなり苦戦した。 神様が妾を娶る? もともと祀られていた正妻の伯婆とは別の存在、 浮気性の伯公、大陸出身で言葉の通じない妾 (客家語、台湾語)。 はちゃめちゃで、最後まで完全には理解できていない。 この物語と「神秘列車」を近い時期に同じ作者が書いていることに、驚きを覚えた。 そして「葬儀でのお話」。 祖父母、母の死をきっかけによみがえる、郷土の村に生きた家族絆と、命のかがやき。 今回もまた、甘耀明さんの魅力に、 どっぷり浸かってしまった。
神秘列車甘耀明,白水紀子読み終わった三叉山事件を題材にした「真の人間になる」を読んで、すっかり甘耀明さんのファンになり、こちらも手に取った。 本書は短編集で、収録作の多くは 著者の故郷、台湾・苗栗県を舞台にしている。 表題作「神秘列車」は、 かつて政治犯として拘束された祖父が乗ったという “謎の列車”を探すため、少年が旅に出る物語。 国民党による白色テロによって引き裂かれた 祖父と祖母の秘められた過去、 政治の暴力が家族にもたらした分断の記憶を、 少年の視点からさかのぼっていく。 読んでいると、光景が自然と目に浮かび、 まるで映画の世界に入り込んだようだった。 二作目の「伯公、妾を娶る」は、 背景を理解するのに正直かなり苦戦した。 神様が妾を娶る? もともと祀られていた正妻の伯婆とは別の存在、 浮気性の伯公、大陸出身で言葉の通じない妾 (客家語、台湾語)。 はちゃめちゃで、最後まで完全には理解できていない。 この物語と「神秘列車」を近い時期に同じ作者が書いていることに、驚きを覚えた。 そして「葬儀でのお話」。 祖父母、母の死をきっかけによみがえる、郷土の村に生きた家族絆と、命のかがやき。 今回もまた、甘耀明さんの魅力に、 どっぷり浸かってしまった。 - 2026年2月10日
 高宮麻綾の引継書城戸川りょう読み終わった書店で何度も見かけるうちに、気になっていた高宮麻綾シリーズ。 これまた、内容をよく知らないまま手に取ってしまった。 表紙の帯には「ミステリー」の文字。 でも読み始めると、お仕事小説の色がかなり濃くて、 「どこからミステリーになるんだろう?」と思いながら読み進める。 それにしても、こんなふうに 仕事に情熱を傾けられる人たちが、ただただ眩しい。 私は主人公の友人と同じで、 仕事は生活費のため、と割り切っていて、 情熱の“じょ”の字もなく日々を過ごしているから。 だからこそ、登場人物たちの姿が、少し羨ましい。 若いころはこんなだったろうか・・!? それにしても麻綾さん、 異動、多すぎじゃない?
高宮麻綾の引継書城戸川りょう読み終わった書店で何度も見かけるうちに、気になっていた高宮麻綾シリーズ。 これまた、内容をよく知らないまま手に取ってしまった。 表紙の帯には「ミステリー」の文字。 でも読み始めると、お仕事小説の色がかなり濃くて、 「どこからミステリーになるんだろう?」と思いながら読み進める。 それにしても、こんなふうに 仕事に情熱を傾けられる人たちが、ただただ眩しい。 私は主人公の友人と同じで、 仕事は生活費のため、と割り切っていて、 情熱の“じょ”の字もなく日々を過ごしているから。 だからこそ、登場人物たちの姿が、少し羨ましい。 若いころはこんなだったろうか・・!? それにしても麻綾さん、 異動、多すぎじゃない? - 2026年2月10日
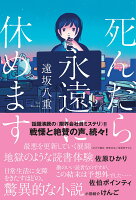 死んだら永遠に休めます遠坂八重読み終わったこちらも、図書館で長く順番待ちしていた一冊。 内容をよく知らずに予約したものの、届いたら面白くて、やっぱり一気読み。 「死んでほしい」と思っていたパワハラ上司が、死んだらしい。 容疑者は――部下、全員。 序盤は、お仕事小説かな、という入り。 そこから徐々にミステリー要素が強まり、早く、次へ次へ。 そして迎える、予想もしなかったラスト。 わー、ちょっと人間不信になりそう…と思いつつも、爽快感の残る結末だった。 先月からずっと仕事に疲れ切っていて、 この手の本を、通勤電車でむさぼるように読んでいる。
死んだら永遠に休めます遠坂八重読み終わったこちらも、図書館で長く順番待ちしていた一冊。 内容をよく知らずに予約したものの、届いたら面白くて、やっぱり一気読み。 「死んでほしい」と思っていたパワハラ上司が、死んだらしい。 容疑者は――部下、全員。 序盤は、お仕事小説かな、という入り。 そこから徐々にミステリー要素が強まり、早く、次へ次へ。 そして迎える、予想もしなかったラスト。 わー、ちょっと人間不信になりそう…と思いつつも、爽快感の残る結末だった。 先月からずっと仕事に疲れ切っていて、 この手の本を、通勤電車でむさぼるように読んでいる。 - 2026年2月6日
 爆弾犯の娘梶原阿貴読み終わったこちらも、図書館で長く順番待ちしていた一冊。 書店で平積みにされているのを何となく眺め、 内容もよく知らないまま予約していた。 タイトルから、てっきりミステリー小説だと思っていたら、 まさかのノンフィクション、自叙伝。 読み始めてすぐ、その事実に驚かされる。 実の父が爆弾犯。 しかも、生まれる前から指名手配中で、 小学校を卒業するまで自宅にかくまわれ、一緒に暮らしていたという。 そんな現実が、本当にあったのかと、何度もページをめくりながら思った。 爆弾犯である父との関係、母との生活、 芸者置屋の祖母。 語られるエピソードの一つひとつが濃く、 登場する人たちのキャラクターも強烈で、 ぐいぐいと引き込まれるように読んだ。 昭和の小学生の日常描写もあまりにリアルで、 重い題材でありながら、読みにくさはない。 むしろ、淡々とした語りが、現実の重さを際立たせている。 これは、ぜひ映画化されたら観てみたい一冊。
爆弾犯の娘梶原阿貴読み終わったこちらも、図書館で長く順番待ちしていた一冊。 書店で平積みにされているのを何となく眺め、 内容もよく知らないまま予約していた。 タイトルから、てっきりミステリー小説だと思っていたら、 まさかのノンフィクション、自叙伝。 読み始めてすぐ、その事実に驚かされる。 実の父が爆弾犯。 しかも、生まれる前から指名手配中で、 小学校を卒業するまで自宅にかくまわれ、一緒に暮らしていたという。 そんな現実が、本当にあったのかと、何度もページをめくりながら思った。 爆弾犯である父との関係、母との生活、 芸者置屋の祖母。 語られるエピソードの一つひとつが濃く、 登場する人たちのキャラクターも強烈で、 ぐいぐいと引き込まれるように読んだ。 昭和の小学生の日常描写もあまりにリアルで、 重い題材でありながら、読みにくさはない。 むしろ、淡々とした語りが、現実の重さを際立たせている。 これは、ぜひ映画化されたら観てみたい一冊。 - 2026年2月6日
 水車小屋のネネ津村記久子読み終わった18歳と8歳の姉妹がたどり着いた町で出会った、しゃべる鳥〈ネネ〉。 ネネに見守られながら、変転していくいくつもの人生。 助け合い、支え合う人々の40年を描いた長編小説。 図書館で長く長く順番待ちをして、 ようやく私のところに回ってきた一冊だった。 1981年から2021年までの40年間、 ある姉妹の人生が丹念に描かれている大作なのに、 通勤電車で1週間、夢中になって読んでしまった。 この本のテーマは「善意」だと思う。 悪い人は出てこない。 物語のはじめ、姉妹は周囲の大人の善意を受け取る側にいる。 でも、べたべたに甘えることはなく、 淡々と、自分たちにできること、やるべきことを必死にこなしていく。 各章は10年ごとに切り替わり、 姉妹が受け取った善意は、次の誰かへと静かに引き継がれていく。 派手な出来事はない。 けれど、物語の隅々まで、押しつけがましさのない善意が行き渡っていて、 読んでいるこちらの心まで、少しずつ整えられていく。 先月から仕事で、生活も心も荒れ荒れだったけれど、この本に、確かに救われた。 特に心に残った部分、2か所だけ厳選で記録。 「誰かに親切にしなきゃ、人生は長く退屈なものですよ」 「自分が元から持っているものはたぶん何もなくて、そうやって出会った人が分けてくれたいい部分で自分はたぶん生きてるって。だから誰かの役に立ちたいって思うことは、はじめから何でも持ってる人が持っている自由からしたら制約に見えたりするのかもしれない。けれどもそのことは自分に道みたいなものを示してくれたし、幸せなことだと思います」
水車小屋のネネ津村記久子読み終わった18歳と8歳の姉妹がたどり着いた町で出会った、しゃべる鳥〈ネネ〉。 ネネに見守られながら、変転していくいくつもの人生。 助け合い、支え合う人々の40年を描いた長編小説。 図書館で長く長く順番待ちをして、 ようやく私のところに回ってきた一冊だった。 1981年から2021年までの40年間、 ある姉妹の人生が丹念に描かれている大作なのに、 通勤電車で1週間、夢中になって読んでしまった。 この本のテーマは「善意」だと思う。 悪い人は出てこない。 物語のはじめ、姉妹は周囲の大人の善意を受け取る側にいる。 でも、べたべたに甘えることはなく、 淡々と、自分たちにできること、やるべきことを必死にこなしていく。 各章は10年ごとに切り替わり、 姉妹が受け取った善意は、次の誰かへと静かに引き継がれていく。 派手な出来事はない。 けれど、物語の隅々まで、押しつけがましさのない善意が行き渡っていて、 読んでいるこちらの心まで、少しずつ整えられていく。 先月から仕事で、生活も心も荒れ荒れだったけれど、この本に、確かに救われた。 特に心に残った部分、2か所だけ厳選で記録。 「誰かに親切にしなきゃ、人生は長く退屈なものですよ」 「自分が元から持っているものはたぶん何もなくて、そうやって出会った人が分けてくれたいい部分で自分はたぶん生きてるって。だから誰かの役に立ちたいって思うことは、はじめから何でも持ってる人が持っている自由からしたら制約に見えたりするのかもしれない。けれどもそのことは自分に道みたいなものを示してくれたし、幸せなことだと思います」 - 2026年2月2日
 本日は、お日柄もよく原田マハ読み終わった言葉の威力って、やっぱり強大だ。 伝説のスピーチライターと 彼女の言葉に魅せられた若者の物語。 スピーチライターという仕事を通して描かれる、言葉の力。 折しも衆院選を前にした今だからこそ、後半はいっそう心に響いた。 誰も嫌な人が出てこないのも、この物語の好きなところ。 二十代の熱さ、まっすぐさがまぶしかった。 後半の展開は、いい意味で予想を裏切られ、 朝の満員電車でスンスンしてしまって大変でした。 心に残った言葉。 「困難に向かい合ったとき、もうだめだ、と思ったとき、想像してみるといい。 三時間後の君、涙がとまっている。 二十四時間後の君、涙は乾いている。 二日後の君、顔を上げている。 三日後の君、歩き出している」
本日は、お日柄もよく原田マハ読み終わった言葉の威力って、やっぱり強大だ。 伝説のスピーチライターと 彼女の言葉に魅せられた若者の物語。 スピーチライターという仕事を通して描かれる、言葉の力。 折しも衆院選を前にした今だからこそ、後半はいっそう心に響いた。 誰も嫌な人が出てこないのも、この物語の好きなところ。 二十代の熱さ、まっすぐさがまぶしかった。 後半の展開は、いい意味で予想を裏切られ、 朝の満員電車でスンスンしてしまって大変でした。 心に残った言葉。 「困難に向かい合ったとき、もうだめだ、と思ったとき、想像してみるといい。 三時間後の君、涙がとまっている。 二十四時間後の君、涙は乾いている。 二日後の君、顔を上げている。 三日後の君、歩き出している」 - 2026年1月25日
 限りなくシンプルに、豊かに暮らす枡野俊明読み終わった建功寺住職、枡野俊明さんの言葉の数々。 もやもやしているとき、疲れているとき、枡野さんの言葉を読みたくなる。 物欲に振り回されず、執着しない。今の私の課題。 ・自然の中に身を置いてみる。 今咲いている花は去年と同じ花ではありません。 今日のあなたも、昨日と同じあなたではないのです。 →ハッとしました。山歩きをしていて、この葉は今年の葉だよな、と意識するようになったけれど、自分にも当てはまるのか、、 ・お金は自分の心を豊かにしてくれるものに使う ・まずは1つだけ手放す 小さな一歩が大きな変化を生むことがある ・「いつかやりたいこと」は今日始める ・他人を批判しない 自分への自信のなさが、他人に投影されているのかもしれません。 誰かを批判する前に、自分自身を愛しましょう。
限りなくシンプルに、豊かに暮らす枡野俊明読み終わった建功寺住職、枡野俊明さんの言葉の数々。 もやもやしているとき、疲れているとき、枡野さんの言葉を読みたくなる。 物欲に振り回されず、執着しない。今の私の課題。 ・自然の中に身を置いてみる。 今咲いている花は去年と同じ花ではありません。 今日のあなたも、昨日と同じあなたではないのです。 →ハッとしました。山歩きをしていて、この葉は今年の葉だよな、と意識するようになったけれど、自分にも当てはまるのか、、 ・お金は自分の心を豊かにしてくれるものに使う ・まずは1つだけ手放す 小さな一歩が大きな変化を生むことがある ・「いつかやりたいこと」は今日始める ・他人を批判しない 自分への自信のなさが、他人に投影されているのかもしれません。 誰かを批判する前に、自分自身を愛しましょう。 - 2026年1月25日
 韓国インスタントラーメンの世界チ・ヨンジュン,中川里沙読み終わった新聞の書評をきっかけに、図書館で借りた一冊。 インスタントラーメンの歴史から語り始める構成がまず面白い。 中国から伝わった「拉麺(ラーメン)」を、 台湾生まれの安藤百福が日本で世界初のインスタントラーメンに。 ※この辺はぜひカップヌードルミュージアムへ! 韓国のインスタントラーメン年間消費量は 1人あたり78個(2023年)で世界2位。 ただし1個あたりの内容量は、1位ベトナムの約1.5倍。 著者いわく、実質最多消費国は韓国。 そのラーメン愛が、とにかく熱い。 日本生まれのインスタントラーメンが 韓国でどう進化し、世界に広がっていったのかを丁寧に追う。 激辛の韓国、牛肉の台湾、エビとパクチーのベトナム、カレーのインド。 ローカライズが生んだ多彩な麺文化に。 個人的には「韓国ラーメン=辛ラーメン(農心)」と思っていたけれど、 実は三養食品が草分け。 創業者チョン・ヨンジュンと明星食品との出会い、協力、苦労、 なぜ韓国でラーメンを広めようとしたのか、読んでいて胸が熱くなる。 韓国で“辛いラーメン”が生まれた背景には、 当時の大統領・朴正煕が三養食品に 「スープに唐辛子粉を入れてはどうか」と提案した、というエピソードも。 2020年時点の世界シェア1位が康師傅だったのも衝撃。 巻末のラーメン評価&写真資料も圧巻で、眺めるだけでも楽しい。 記録用:スコヴィル値基準・最も辛いラーメン(2024年3月) 1位 パルド トゥムセラーメン 2位 クンビ 火魔王ラーメン 3位 パルド キングトゥッコン 4位 パルド トゥムセラーメン パルゲトッ、辛いキムチ 5位 農心 辛ラーメンザレッド
韓国インスタントラーメンの世界チ・ヨンジュン,中川里沙読み終わった新聞の書評をきっかけに、図書館で借りた一冊。 インスタントラーメンの歴史から語り始める構成がまず面白い。 中国から伝わった「拉麺(ラーメン)」を、 台湾生まれの安藤百福が日本で世界初のインスタントラーメンに。 ※この辺はぜひカップヌードルミュージアムへ! 韓国のインスタントラーメン年間消費量は 1人あたり78個(2023年)で世界2位。 ただし1個あたりの内容量は、1位ベトナムの約1.5倍。 著者いわく、実質最多消費国は韓国。 そのラーメン愛が、とにかく熱い。 日本生まれのインスタントラーメンが 韓国でどう進化し、世界に広がっていったのかを丁寧に追う。 激辛の韓国、牛肉の台湾、エビとパクチーのベトナム、カレーのインド。 ローカライズが生んだ多彩な麺文化に。 個人的には「韓国ラーメン=辛ラーメン(農心)」と思っていたけれど、 実は三養食品が草分け。 創業者チョン・ヨンジュンと明星食品との出会い、協力、苦労、 なぜ韓国でラーメンを広めようとしたのか、読んでいて胸が熱くなる。 韓国で“辛いラーメン”が生まれた背景には、 当時の大統領・朴正煕が三養食品に 「スープに唐辛子粉を入れてはどうか」と提案した、というエピソードも。 2020年時点の世界シェア1位が康師傅だったのも衝撃。 巻末のラーメン評価&写真資料も圧巻で、眺めるだけでも楽しい。 記録用:スコヴィル値基準・最も辛いラーメン(2024年3月) 1位 パルド トゥムセラーメン 2位 クンビ 火魔王ラーメン 3位 パルド キングトゥッコン 4位 パルド トゥムセラーメン パルゲトッ、辛いキムチ 5位 農心 辛ラーメンザレッド - 2026年1月25日
 世界100ヵ国の旅で出会った人たちが教えてくれた人生で大切なこと旅人KAD(かど)読み終わった旅先で偶然出会った人との、何気ない会話。 その一瞬のやり取りから生まれた言葉が心に残る。 読むほどに旅に出たくなるし、 同時に「これは自分のために残しておきたい」と思う言葉が増えていく。 ネタバレになるので、ひとつだけ。 誰かを許すのはその人のためじゃない。 許せない相手に自分の人生を支配させないためだ。 怒りを握ってると、それが人生の重りになるだけだ。 でも手を放せば、人生が軽くなる。 他にも素敵な言葉がたくさん。 私も旅先で誰かの言葉を聞きたいし、伝えたいと思った。 生き方の選択肢を増やそう!
世界100ヵ国の旅で出会った人たちが教えてくれた人生で大切なこと旅人KAD(かど)読み終わった旅先で偶然出会った人との、何気ない会話。 その一瞬のやり取りから生まれた言葉が心に残る。 読むほどに旅に出たくなるし、 同時に「これは自分のために残しておきたい」と思う言葉が増えていく。 ネタバレになるので、ひとつだけ。 誰かを許すのはその人のためじゃない。 許せない相手に自分の人生を支配させないためだ。 怒りを握ってると、それが人生の重りになるだけだ。 でも手を放せば、人生が軽くなる。 他にも素敵な言葉がたくさん。 私も旅先で誰かの言葉を聞きたいし、伝えたいと思った。 生き方の選択肢を増やそう! - 2026年1月25日
 NAMASTE とらわれない自分のつくり方エクトル・ガルシア,フランセスク・ミラージェス,杉田真読み終わった人生を「山」にたとえるメタファーが印象的。 人生の前半は、得ること・集めること・到達することに夢中になる。 でも後半は、下山のために背負ってきたものを手放し、身軽になる必要がある。 本当に必要なもの以外を、手放す。 人は皆、自分の「真実」のために戦っている。 でもそれは、数ある意見のひとつに過ぎないことを、私たちは忘れがちだ。 《人間関係にとらわれない》 私は私を生きる。あなたはあなたを生きる。 期待に応えるために生きているわけではない。 出会えたら素晴らしいし、出会えなくても、それはそれ。 《カルマの戒律(抜粋)》 ・蒔いた種は自分で刈り取る ・親切さと寛大さを実践する ・変化のために行動を改める ・カルマを育てる場所は「いまここ」だけ 過去にとらわれるのは、もうやめよう。 《インド式「とらわれない生き方」》 必要ないものを手放し、 マインドフルに、呼吸し、 「いまこの瞬間」を生きる。 執着を手放したい、と思って手にした本。これは練習だ、辛抱強く、この瞬間に意識を向け続ける練習をしていくのだ。
NAMASTE とらわれない自分のつくり方エクトル・ガルシア,フランセスク・ミラージェス,杉田真読み終わった人生を「山」にたとえるメタファーが印象的。 人生の前半は、得ること・集めること・到達することに夢中になる。 でも後半は、下山のために背負ってきたものを手放し、身軽になる必要がある。 本当に必要なもの以外を、手放す。 人は皆、自分の「真実」のために戦っている。 でもそれは、数ある意見のひとつに過ぎないことを、私たちは忘れがちだ。 《人間関係にとらわれない》 私は私を生きる。あなたはあなたを生きる。 期待に応えるために生きているわけではない。 出会えたら素晴らしいし、出会えなくても、それはそれ。 《カルマの戒律(抜粋)》 ・蒔いた種は自分で刈り取る ・親切さと寛大さを実践する ・変化のために行動を改める ・カルマを育てる場所は「いまここ」だけ 過去にとらわれるのは、もうやめよう。 《インド式「とらわれない生き方」》 必要ないものを手放し、 マインドフルに、呼吸し、 「いまこの瞬間」を生きる。 執着を手放したい、と思って手にした本。これは練習だ、辛抱強く、この瞬間に意識を向け続ける練習をしていくのだ。 - 2026年1月24日
- 2026年1月22日
 梧桐に眠る澤田瞳子読み終わった舞台は8世紀の寧楽(奈良)、そして大宰府・那の津。 主人公の袁晋卿は実在の人物で、唐から渡来し、漢字音や当時最先端の唐楽を日本にもたらした。 日本から請われ、手厚い待遇を受けた渡来人がいる一方で、 そうではない者たちは、言葉も文化も通じない異国で生き抜くしかなかった。 平城京で天然痘が猛威を振るう中、異なる背景をもつ人々の出会いと葛藤が描かれる。 奈良時代は、仏教が国家に取り込まれ、外来文化が一気に流れ込んだ激動の時代。 自然神を祀る世界観から仏教を国教とする転換は、 現代に起きたとしたら大きな混乱を生んだはず。 道教が日本に根づかなかった理由も、 この時代の政治と人の選択の積み重ねにあったのかもしれない、そんなことを考えさせられる一冊。
梧桐に眠る澤田瞳子読み終わった舞台は8世紀の寧楽(奈良)、そして大宰府・那の津。 主人公の袁晋卿は実在の人物で、唐から渡来し、漢字音や当時最先端の唐楽を日本にもたらした。 日本から請われ、手厚い待遇を受けた渡来人がいる一方で、 そうではない者たちは、言葉も文化も通じない異国で生き抜くしかなかった。 平城京で天然痘が猛威を振るう中、異なる背景をもつ人々の出会いと葛藤が描かれる。 奈良時代は、仏教が国家に取り込まれ、外来文化が一気に流れ込んだ激動の時代。 自然神を祀る世界観から仏教を国教とする転換は、 現代に起きたとしたら大きな混乱を生んだはず。 道教が日本に根づかなかった理由も、 この時代の政治と人の選択の積み重ねにあったのかもしれない、そんなことを考えさせられる一冊。 - 2026年1月20日
- 2026年1月20日
 読み終わった宇宙や科学の話なのに、どこか思想・哲学に触れる感覚があって、去年まで学んでいたヴァガバットギーターの世界観と重なった。 「私も世界も、大きな一つの流れの中にある」というワンネスのような感覚、小さなことでイライラしている自分が、恥ずかしくなる。 心に残った話をいくつか。 ・冥王星は2006年から惑星ではなく「準惑星」になったこと (昭和世代のみなさん、水金地火木土天海冥、って習いませんでした?!) ・地球の水の97%以上は海水で、私たちが使える淡水はわずか0.01%ほど。お風呂一杯を地球の水とすると、手にできるのは大さじ1杯くらいしかない。これを人間だけでなく生き物すべてで分け合うのだ。 ・誕生日星座は、太陽と一緒に昼間に昇ってしまうから、誕生日の夜には実は見えないこと(見たかったら、お誕生日の1個前の季節に探そう!) ・ニュージーランド・テカポで著者が感じた「自分は広い宇宙の中でほんの一瞬をもらって、いまここを眺めている」という感覚。私たちは目に映っているものがすべてと思いがちな生き物だけど、あなたや私が満点の星を見たとしても、それは宇宙の一部でしかない。 ・そして結局のところ、私たちはみんな星くず。人も動物も山も川も、何十億年も前は星だった ・宇宙の成分のうち、わかっているのはたった5%しかない 最後に、アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターがボイジャー号に託したメッセージが好きすぎるので残します。 「これは小さな遠い世界からの贈り物であり、私たちの音、科学、映像、音楽、思考、そして感情の象徴です。私たちは、私たちの時代を生き延び、あなたたちの時代に生き続けるために試みています。いつの日か、直面している問題を解決し、銀河文明のコミュニティに加わることを願っています。このレコードは私たちの希望、決意、そして広大で素晴らしい宇宙における善意を表しています。」
読み終わった宇宙や科学の話なのに、どこか思想・哲学に触れる感覚があって、去年まで学んでいたヴァガバットギーターの世界観と重なった。 「私も世界も、大きな一つの流れの中にある」というワンネスのような感覚、小さなことでイライラしている自分が、恥ずかしくなる。 心に残った話をいくつか。 ・冥王星は2006年から惑星ではなく「準惑星」になったこと (昭和世代のみなさん、水金地火木土天海冥、って習いませんでした?!) ・地球の水の97%以上は海水で、私たちが使える淡水はわずか0.01%ほど。お風呂一杯を地球の水とすると、手にできるのは大さじ1杯くらいしかない。これを人間だけでなく生き物すべてで分け合うのだ。 ・誕生日星座は、太陽と一緒に昼間に昇ってしまうから、誕生日の夜には実は見えないこと(見たかったら、お誕生日の1個前の季節に探そう!) ・ニュージーランド・テカポで著者が感じた「自分は広い宇宙の中でほんの一瞬をもらって、いまここを眺めている」という感覚。私たちは目に映っているものがすべてと思いがちな生き物だけど、あなたや私が満点の星を見たとしても、それは宇宙の一部でしかない。 ・そして結局のところ、私たちはみんな星くず。人も動物も山も川も、何十億年も前は星だった ・宇宙の成分のうち、わかっているのはたった5%しかない 最後に、アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターがボイジャー号に託したメッセージが好きすぎるので残します。 「これは小さな遠い世界からの贈り物であり、私たちの音、科学、映像、音楽、思考、そして感情の象徴です。私たちは、私たちの時代を生き延び、あなたたちの時代に生き続けるために試みています。いつの日か、直面している問題を解決し、銀河文明のコミュニティに加わることを願っています。このレコードは私たちの希望、決意、そして広大で素晴らしい宇宙における善意を表しています。」
読み込み中...

![AI時代の[お金を稼ぐ力]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3053/9784866633053_1_2.jpg?_ex=200x200)