春琴抄改版
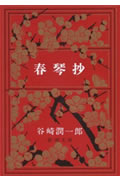
43件の記録
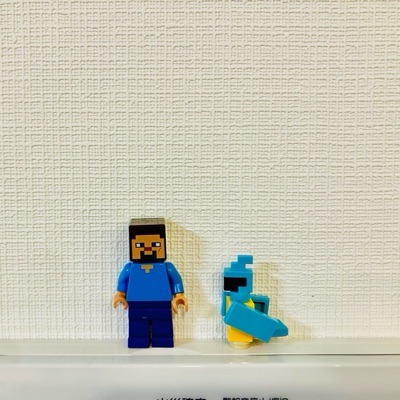 さおり@prn9909082025年8月2日読み終わった佐助、どうしようもなく「魅入られ」てしまったんだな…と思った.春琴は間違いなくヤバい女だけどそこに強烈に惹かれて、自分自身を犠牲にして、そしてそこに悦びを感じながら仕える佐助も確実にヤバく、「凄絶な師弟愛」というよりは「狂った信仰」のようなものを感じてしまった.とくに子どもまでつくっておきながら、春琴も佐助も体の関係を認めるのを拒否したり、2人がどうしても結婚に踏み切らなかった理由に佐助の春琴への禍々しいほどの「信仰」を見た.かなり歪ではあるけれど、2人の世界はそれで綺麗に完成していて、その歪さの描き方の引力がすごくて最後まで駆け抜けるように読んでしまった.
さおり@prn9909082025年8月2日読み終わった佐助、どうしようもなく「魅入られ」てしまったんだな…と思った.春琴は間違いなくヤバい女だけどそこに強烈に惹かれて、自分自身を犠牲にして、そしてそこに悦びを感じながら仕える佐助も確実にヤバく、「凄絶な師弟愛」というよりは「狂った信仰」のようなものを感じてしまった.とくに子どもまでつくっておきながら、春琴も佐助も体の関係を認めるのを拒否したり、2人がどうしても結婚に踏み切らなかった理由に佐助の春琴への禍々しいほどの「信仰」を見た.かなり歪ではあるけれど、2人の世界はそれで綺麗に完成していて、その歪さの描き方の引力がすごくて最後まで駆け抜けるように読んでしまった.


 アル子@yamanbalcohol2025年3月23日かつて読んだ多様性と叫ばれながらも幸せの形は出来上がっており、そこからはみ出ている・入ろうとしない人が逆に目立ってしまう今の時代にこそ読む意味があるのではと思った。 でもそんなことより淡々と語られるふたりの関係や出来事にじわじわと幸せにさせられる素晴らしい作品です。癖がはまる人にとっては。
アル子@yamanbalcohol2025年3月23日かつて読んだ多様性と叫ばれながらも幸せの形は出来上がっており、そこからはみ出ている・入ろうとしない人が逆に目立ってしまう今の時代にこそ読む意味があるのではと思った。 でもそんなことより淡々と語られるふたりの関係や出来事にじわじわと幸せにさせられる素晴らしい作品です。癖がはまる人にとっては。 izy@izy2025年3月22日かつて読んだ純愛物語というとどこか陳腐な感じがしてしまうのは、世代的には「セカチュー」や「冬ソナ」のせいかな。『春琴抄』も純愛物語には違いないけど、そういうブームと化した「純愛」に比べると、この作品の持つ独自性と新鮮さは今なお際立っていると思う。 描かれるのは、美貌で盲目の三味線師匠春琴と、丁稚から彼女の世話役となった佐助との「純愛」であるが、それはあくまでも、春琴が佐助をいじめたり罵ったりしながら身の回りの世話をさせ、佐助も喜んでそれに従うという、谷崎お得意のマゾヒズムである。 有名な作品なのでネタバレしてしまうが、生まれた子どもが春琴の意向で里子に出されるばかりか、美衣美食を恣にし、鶯や雲雀を何羽も飼い育てるなど贅沢の限りを尽くした挙句、何者かによって顔に大火傷を負わされた春琴の焼けただれた顔を見るまいと、佐助も自ら目を突いて盲目になり、死ぬまで春琴に仕えるというなかなかぶっ飛んだ話だ。 佐助が「誰しも眼が潰れることは不仕合はせだと思ふであらうが自分は盲目になつてからさう云ふ感情を味はつたことがない寧ろ反対に此の世が極楽浄土になつたやうに思はれお師匠様と唯二人で生きながら蓮の台の上に住んでゐるやうな心地がした」と述べているように、美の陶酔に殉じることで自らの運命を全うするという谷崎の思想が、句読点を極端に省いた流麗かつ簡素な文体を通じて遺憾なく発揮されている。 「セカチュー」に代表される、恋人の死という悲哀と、素朴な愛情の結晶化という結末が、洋の東西や時代を問わずごまんと語り尽くされて来た「純愛物語」の焼増しに過ぎないのなら、『春琴抄』において描き出されるのは、崇拝の対象への狂信的とも言える肉体的・精神的苦役である。その苦役が対象との一体化による快楽へと転化され、佐助みずから盲目となって春琴と同じ視覚世界への没入を図り、観念としての美貌の記憶と感覚世界の合一をもってその頂点を迎える過程は、「純愛物語」の極端にして過剰なひとつの到達点であるように思う。
izy@izy2025年3月22日かつて読んだ純愛物語というとどこか陳腐な感じがしてしまうのは、世代的には「セカチュー」や「冬ソナ」のせいかな。『春琴抄』も純愛物語には違いないけど、そういうブームと化した「純愛」に比べると、この作品の持つ独自性と新鮮さは今なお際立っていると思う。 描かれるのは、美貌で盲目の三味線師匠春琴と、丁稚から彼女の世話役となった佐助との「純愛」であるが、それはあくまでも、春琴が佐助をいじめたり罵ったりしながら身の回りの世話をさせ、佐助も喜んでそれに従うという、谷崎お得意のマゾヒズムである。 有名な作品なのでネタバレしてしまうが、生まれた子どもが春琴の意向で里子に出されるばかりか、美衣美食を恣にし、鶯や雲雀を何羽も飼い育てるなど贅沢の限りを尽くした挙句、何者かによって顔に大火傷を負わされた春琴の焼けただれた顔を見るまいと、佐助も自ら目を突いて盲目になり、死ぬまで春琴に仕えるというなかなかぶっ飛んだ話だ。 佐助が「誰しも眼が潰れることは不仕合はせだと思ふであらうが自分は盲目になつてからさう云ふ感情を味はつたことがない寧ろ反対に此の世が極楽浄土になつたやうに思はれお師匠様と唯二人で生きながら蓮の台の上に住んでゐるやうな心地がした」と述べているように、美の陶酔に殉じることで自らの運命を全うするという谷崎の思想が、句読点を極端に省いた流麗かつ簡素な文体を通じて遺憾なく発揮されている。 「セカチュー」に代表される、恋人の死という悲哀と、素朴な愛情の結晶化という結末が、洋の東西や時代を問わずごまんと語り尽くされて来た「純愛物語」の焼増しに過ぎないのなら、『春琴抄』において描き出されるのは、崇拝の対象への狂信的とも言える肉体的・精神的苦役である。その苦役が対象との一体化による快楽へと転化され、佐助みずから盲目となって春琴と同じ視覚世界への没入を図り、観念としての美貌の記憶と感覚世界の合一をもってその頂点を迎える過程は、「純愛物語」の極端にして過剰なひとつの到達点であるように思う。

 individual@individual2025年3月16日読み終わった『春琴抄』が発表された年は、1933年(昭和8年)です。僕は読む前に、1912年(明治45年、大正元年)前後の作品かと思っていました。しかし読み進んでいくうちに、谷崎の初期作品(『刺青』など)とは、違う「匂い」がしました。『春琴抄』は、段落下げがなく句読点も少ない作品です。おそらくこれらの仕掛けには意味があります。それは近代日本以前の古典、とくに平安時代の文章表記のオマージュです。以上の表記の場合、物語が連綿と綴られている印象を読者に与えます。僕は、巻物(作品)を引き伸ばしながら読んでいる印象を受けて、この表記が気に入りました。平安時代の代表的作品の『源氏物語』が、「いづれの御時にか」で始まるように、『春琴抄』も回想形式の作品です(ちなみに、『源氏物語』の原文には、段落下げと句読点がないそうです)。谷崎は、古典の「お約束」を踏襲しているのでしょう。『春琴抄』の後半で、春琴は顔を損なわれてしまいます。谷崎は“顔”を失うことを物語に取り入れることで、江戸時代の都会の習俗を表現しているのだと僕は思っています。この作品のおもな舞台の時代は、江戸幕末から明治19年(春琴が亡くなる年)までです。以下は推測ですが、このあたりの時代は、文字通りの“美”が人々の「位」を決めていたのではないか。たとえば歌舞伎では、とくに“顔”を飾ります。これはおそらく江戸時代の市井の方々の常識を抽出したのだと僕は思っています。また、明治19年は、言文一致体がこれから創られていく年であり、「心理」や「内面」はまだ創られていません。そうであるからこそ、この時代には文字通りの“美”が、大切にされたのではないか。このような時代を生きた春琴にとって、“顔”を損なうことは死ぬことに等しかったのではないでしょうか。
individual@individual2025年3月16日読み終わった『春琴抄』が発表された年は、1933年(昭和8年)です。僕は読む前に、1912年(明治45年、大正元年)前後の作品かと思っていました。しかし読み進んでいくうちに、谷崎の初期作品(『刺青』など)とは、違う「匂い」がしました。『春琴抄』は、段落下げがなく句読点も少ない作品です。おそらくこれらの仕掛けには意味があります。それは近代日本以前の古典、とくに平安時代の文章表記のオマージュです。以上の表記の場合、物語が連綿と綴られている印象を読者に与えます。僕は、巻物(作品)を引き伸ばしながら読んでいる印象を受けて、この表記が気に入りました。平安時代の代表的作品の『源氏物語』が、「いづれの御時にか」で始まるように、『春琴抄』も回想形式の作品です(ちなみに、『源氏物語』の原文には、段落下げと句読点がないそうです)。谷崎は、古典の「お約束」を踏襲しているのでしょう。『春琴抄』の後半で、春琴は顔を損なわれてしまいます。谷崎は“顔”を失うことを物語に取り入れることで、江戸時代の都会の習俗を表現しているのだと僕は思っています。この作品のおもな舞台の時代は、江戸幕末から明治19年(春琴が亡くなる年)までです。以下は推測ですが、このあたりの時代は、文字通りの“美”が人々の「位」を決めていたのではないか。たとえば歌舞伎では、とくに“顔”を飾ります。これはおそらく江戸時代の市井の方々の常識を抽出したのだと僕は思っています。また、明治19年は、言文一致体がこれから創られていく年であり、「心理」や「内面」はまだ創られていません。そうであるからこそ、この時代には文字通りの“美”が、大切にされたのではないか。このような時代を生きた春琴にとって、“顔”を損なうことは死ぬことに等しかったのではないでしょうか。



- ぷり子@Puricco2025年3月11日かつて読んだこんな小説を書ける筆力と感性が欲しいと思うことは何度もあるが、大谷崎先生の性癖と業が付属品として付いてくるのならばこのままでもいいやと思えるくらいに業が深い作品です。みんなある意味幸せ!
























