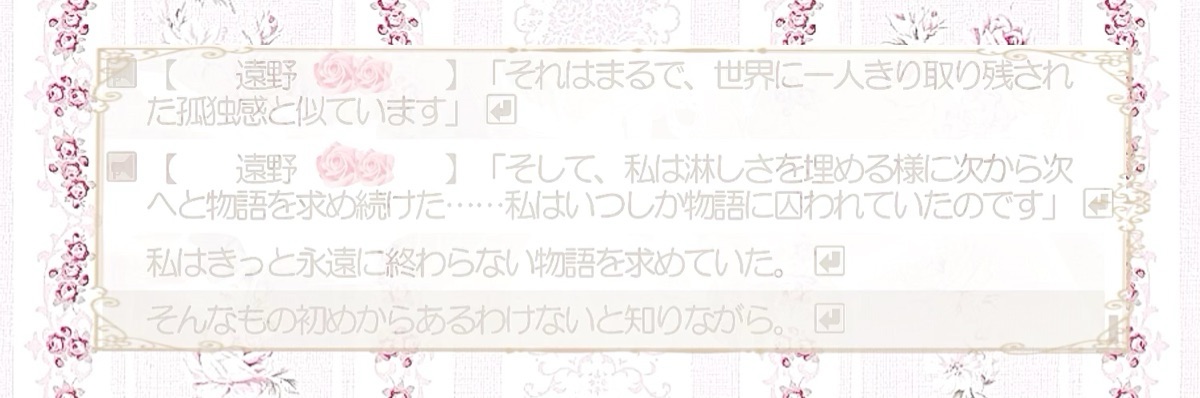

✟
@x_toyanya_x
𝐶𝑜𝑠'è 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑜𝑙𝑐𝑒 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒?
- 2026年2月11日
 作家と楽しむ古典 土左日記 堤中納言物語 枕草子 方丈記 徒然草中島京子,内田樹,堀江敏幸,酒井順子,高橋源一郎借りてきた読み終わった特に土佐日記の「おとこもすなる日記といふものを」について、日記が公務員の記録であり私的なものではなかった点などを踏まえ「おとこもし(男文字)」、「おんなもし(女文字)」、つまり男文字の日記を女文字で書く。という解釈が従来の女装的文脈から一線を画しており、面白かった。
作家と楽しむ古典 土左日記 堤中納言物語 枕草子 方丈記 徒然草中島京子,内田樹,堀江敏幸,酒井順子,高橋源一郎借りてきた読み終わった特に土佐日記の「おとこもすなる日記といふものを」について、日記が公務員の記録であり私的なものではなかった点などを踏まえ「おとこもし(男文字)」、「おんなもし(女文字)」、つまり男文字の日記を女文字で書く。という解釈が従来の女装的文脈から一線を画しており、面白かった。 - 2026年2月11日
 ガダラの豚 1中島らも読み終わった
ガダラの豚 1中島らも読み終わった - 2026年1月19日
 雨月物語円城塔読み終わった買った解説にもあったが、異形の恐ろしさや残虐性よりも呪いや怨念となった人間そのものの持つ強い執着心やその背景に焦点を当てて各話が描かれており、物語として楽しむことができた。 また、現代語訳が美麗でありながらわかりやすく、特に漢詩の部分に原文とひらがなの訳が併せて表記されているのが良かった。
雨月物語円城塔読み終わった買った解説にもあったが、異形の恐ろしさや残虐性よりも呪いや怨念となった人間そのものの持つ強い執着心やその背景に焦点を当てて各話が描かれており、物語として楽しむことができた。 また、現代語訳が美麗でありながらわかりやすく、特に漢詩の部分に原文とひらがなの訳が併せて表記されているのが良かった。 - 2026年1月14日
 雨月物語円城塔買ったまだ読んでる
雨月物語円城塔買ったまだ読んでる - 2026年1月5日
- 2025年12月28日
 時の束を披く-古典籍からうまれるアートと翻訳-国文学研究資料館借りてきた読み終わった
時の束を披く-古典籍からうまれるアートと翻訳-国文学研究資料館借りてきた読み終わった - 2025年12月22日
- 2025年12月19日
 卍谷崎潤一郎
卍谷崎潤一郎 - 2025年12月16日
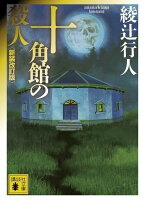 十角館の殺人 <新装改訂版>綾辻行人読み終わった買った
十角館の殺人 <新装改訂版>綾辻行人読み終わった買った - 2025年11月5日
- 2025年11月3日
 濹東綺譚永井荷風読み終わった買った
濹東綺譚永井荷風読み終わった買った - 2025年8月20日
 責任と物語戸谷洋志買ったまだ読んでる物語のテクスト論的な話かと思っていたが哲学的なアプローチから始まって面白い。難解な内容だけれどわかりやすく例えも用いられていて読みやすかった。 この本では社会的・法律面での責任ではなく道徳の面においての責任を取り扱うという前提の次に、では人間には責任を負うための自由意志があるのか? という決定論の解説が続き、自由意志が無ければ責任概念が成立しないという説明に展開されていく。 デカルトの思椎実体(精神や自由意志)と延長実態(物理空間に存在する事物)という二分において、他の動物が機械的な動きをする延長実体であり、人間は「言葉の使用と応用的な創造」をできることを根拠に思椎実体であるとするのなら生成AIはどうなるのだろう? と読んでいて疑問に思ったら、次のページでその点にも触れられていて面白かった。
責任と物語戸谷洋志買ったまだ読んでる物語のテクスト論的な話かと思っていたが哲学的なアプローチから始まって面白い。難解な内容だけれどわかりやすく例えも用いられていて読みやすかった。 この本では社会的・法律面での責任ではなく道徳の面においての責任を取り扱うという前提の次に、では人間には責任を負うための自由意志があるのか? という決定論の解説が続き、自由意志が無ければ責任概念が成立しないという説明に展開されていく。 デカルトの思椎実体(精神や自由意志)と延長実態(物理空間に存在する事物)という二分において、他の動物が機械的な動きをする延長実体であり、人間は「言葉の使用と応用的な創造」をできることを根拠に思椎実体であるとするのなら生成AIはどうなるのだろう? と読んでいて疑問に思ったら、次のページでその点にも触れられていて面白かった。 - 2025年8月8日
 巴里の憂鬱ボードレール,三好達治読み終わった買った言葉選びが美麗で素晴らしいと思ったけれど、調べるうち訳者によってかなり違うことがわかった。三好達治の訳もこの詩を引き立てているのかもしれない。 "私が讃美した人々の魂よ、私を強くせよ、私を援けて支えよ、この世の虚偽と腐敗気とを、私より遠ざからしめよ。" /「夜半の一時に」 "恐らく人は不幸である。されど、願望の虐む芸術家は幸いなるかな! 時あってたまたま私に現れ、且つ倏忽として私から逃れ去るところのもの、夜の中へとつれ去られる旅行者の、背後の方に残される、あの美しく名残惜しきものの如きを、私は描き写そうと激しく焦躁する。" /「描かんとする願望」
巴里の憂鬱ボードレール,三好達治読み終わった買った言葉選びが美麗で素晴らしいと思ったけれど、調べるうち訳者によってかなり違うことがわかった。三好達治の訳もこの詩を引き立てているのかもしれない。 "私が讃美した人々の魂よ、私を強くせよ、私を援けて支えよ、この世の虚偽と腐敗気とを、私より遠ざからしめよ。" /「夜半の一時に」 "恐らく人は不幸である。されど、願望の虐む芸術家は幸いなるかな! 時あってたまたま私に現れ、且つ倏忽として私から逃れ去るところのもの、夜の中へとつれ去られる旅行者の、背後の方に残される、あの美しく名残惜しきものの如きを、私は描き写そうと激しく焦躁する。" /「描かんとする願望」 - 2025年8月7日
 巴里の憂鬱ボードレール,三好達治買ったまだ読んでる詩を読んでいてこんなにはっとさせられたのは高村光太郎ぶり。実用書のように読んですぐに役に立つわけではないけれど、切実に、誠実に、そして激しく、美しく。選りすぐった言葉で世界を飾っている感覚。一気に読んでしまうのが勿体無いような気がしてきた。
巴里の憂鬱ボードレール,三好達治買ったまだ読んでる詩を読んでいてこんなにはっとさせられたのは高村光太郎ぶり。実用書のように読んですぐに役に立つわけではないけれど、切実に、誠実に、そして激しく、美しく。選りすぐった言葉で世界を飾っている感覚。一気に読んでしまうのが勿体無いような気がしてきた。 - 2025年8月6日
 巴里の憂鬱ボードレール,三好達治買ったまだ読んでる
巴里の憂鬱ボードレール,三好達治買ったまだ読んでる - 2025年8月6日
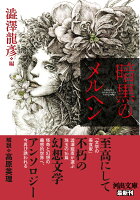 暗黒のメルヘン澁澤龍彦買ったまだ読んでる
暗黒のメルヘン澁澤龍彦買ったまだ読んでる - 2025年7月29日
 草枕夏目漱石読み終わった買ったそんなオチ?!と思ったけれど、芸術を表現する描き手である主人公と登場人物(被写体)の間に実際の情熱的な関係があるというよりはそこには一定の距離があって、あくまで第三者的な視点から表現するべきって考え方は序盤から統一されていた。余裕を持たない人生は詰まらない、というまさに「余裕派」の美学の話。
草枕夏目漱石読み終わった買ったそんなオチ?!と思ったけれど、芸術を表現する描き手である主人公と登場人物(被写体)の間に実際の情熱的な関係があるというよりはそこには一定の距離があって、あくまで第三者的な視点から表現するべきって考え方は序盤から統一されていた。余裕を持たない人生は詰まらない、というまさに「余裕派」の美学の話。 - 2025年7月27日
 決定版カフカ短編集フランツ・カフカ,頭木弘樹買ったまだ読んでる
決定版カフカ短編集フランツ・カフカ,頭木弘樹買ったまだ読んでる - 2025年7月26日
 若きウェルテルの悩みゲーテ読み終わった買ったまさに「青春の悲劇」だった。どこまでも純粋な恋と信仰と真念の行く末。「分別を知る前か、忘れ去ってしまった後」でしか幸せでいられないという一節が印象深い。 この下り、アルジャーノンにもあったけどキリスト教的価値観(知恵の実)なのかな
若きウェルテルの悩みゲーテ読み終わった買ったまさに「青春の悲劇」だった。どこまでも純粋な恋と信仰と真念の行く末。「分別を知る前か、忘れ去ってしまった後」でしか幸せでいられないという一節が印象深い。 この下り、アルジャーノンにもあったけどキリスト教的価値観(知恵の実)なのかな - 2025年7月24日
 若きウェルテルの悩みゲーテ買ったまだ読んでる
若きウェルテルの悩みゲーテ買ったまだ読んでる
読み込み中...

