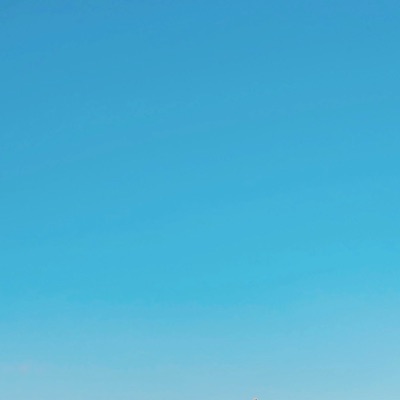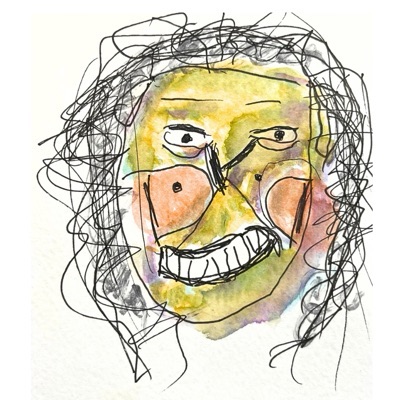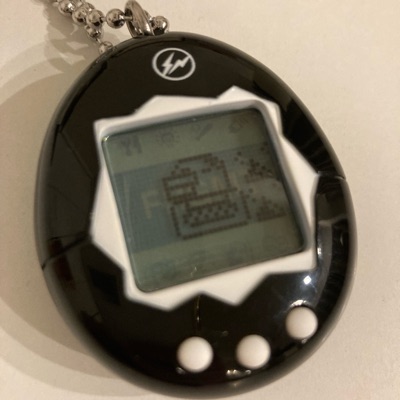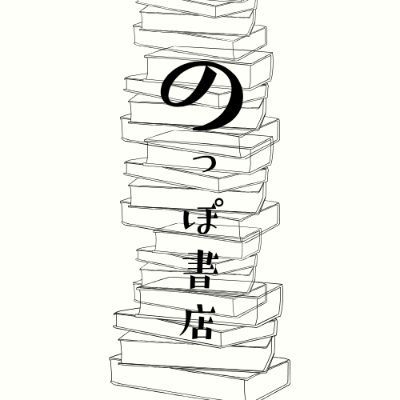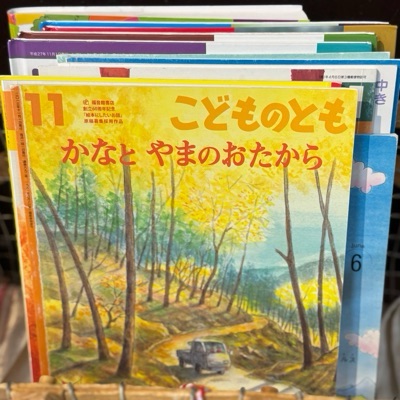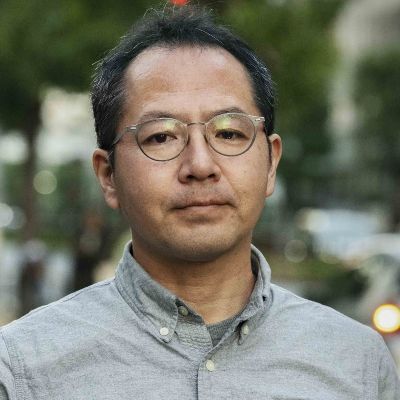疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた

56件の記録
 とろたく@takutsuna2025年10月11日読み終わった紙の本疲労が起きるメカニズムに迫る本。筆者のブルーバックス好きが溢れていて、きっと楽しみながら執筆されたのだろう。ということが想像できる本だった。 また、コロナ後遺症や様々な論文をもとに、疲労の仕組みを解説していて、そこにウイルスが影響していたり、ウイルスの人間の共存関係まで言及されていて、知的好奇心が刺激される面白い本だった。
とろたく@takutsuna2025年10月11日読み終わった紙の本疲労が起きるメカニズムに迫る本。筆者のブルーバックス好きが溢れていて、きっと楽しみながら執筆されたのだろう。ということが想像できる本だった。 また、コロナ後遺症や様々な論文をもとに、疲労の仕組みを解説していて、そこにウイルスが影響していたり、ウイルスの人間の共存関係まで言及されていて、知的好奇心が刺激される面白い本だった。
 あき@4rcoid2025年10月1日かつて読んだまとめ実家近くの書店にて目に留まり、「疲れたと思わなければ疲れないのでは?(謎)」と一時期思っていたことがあったので実際の疲労のメカニズムについて知りたいと思い購入。 著者は東京慈恵会医科大学ウイルス学講座教授であり中でもヘルペスウイルスを専門にしているとのこと。 ヘルペスウイルスの多くは子どもの頃に初感染し、発疹や発熱などを発症したあとは神経節等に潜伏することが知られています。 また疲労などで身体の免疫が弱ったときには再び再活性化して発症します。 このことに注目し、唾液中のヘルペスウイルス(特にHHV-6)の量を測定することで疲労の程度が分かるということでした。 このHHV-6の量は絶対値(ある量を超えたら疲労)ではなく相対値(平常時との比較)であることに注意が必要で、実際の疲労度合いを知るには何回か測定が必要とのことです。 疲労が起こる実際のメカニズムについても詳しく書かれており、疲れたな休みたいなと思う疲労感は炎症性サイトカイン(炎症により細胞から分泌されるタンパク質)が脳に伝わることで生じます。 ではその原因となる炎症性サイトカインはどこから生じるのか?というところで先ほどのHHV-6が出てきます。 HHV-6の再活性化を誘導する因子が炎症性サイトカインも産生するのではという仮説が立ち、実際に「eIF2αのリン酸化」がアポトーシス(細胞死)や炎症性サイトカインの産生を引き起こし疲労の原因となっているそうです。 eIF2αのリン酸化は肝臓、心臓、脳、筋肉などの様々な場所で起こり、特に肝臓で多く、次いで心臓での炎症性サイトカインの産生が多いようです。 ではこのリン酸化を防げば疲労しないのではということになりますが、残念ながら生体に使えるよい阻害剤は存在していないとのこと。 抗酸化剤(N-アセチルシステインなど)は肝臓でのリン酸化を抑制して疲労感の軽減に繋がるが他の部位では効かず、働き過ぎないことに注意が必要。 次善の策としてリン酸化したeIF2αからリン酸を取る脱リン酸化を促すことで疲労が回復する方法はないかとなりますが、これには軽い運動が有効とのことでした。 この辺りの話はウイルス学や細胞生物学、生化学、薬理学に親しんだ方ならとても楽しく読めると思います。 ここまでの話は生理的な疲労で、ここから更に病的な疲労である慢性疲労症候群やうつ病についてのメカニズム、原因の考察についても詳しく述べられております。 詳しく知りたい方はぜひ読まれてみることをおすすめします。 まだまだHHV-6やSITH-1(うつ病の因子)の検査は一般的ではないので、これからさらなる技術の発展でスマートウォッチなどで経皮的に正確な疲労度合いが分かるようになると活動の指標になっていいなと思いました。 他分野との共同研究等で休養や睡眠によってHHV-6の検出量が変わるのかやeIF2αの脱リン酸化が進むのかなどが分かってくるといいな。 https://youtu.be/kPoFiv9jD7I?si=Be-FEC_j4ILcffUS https://youtu.be/kwhzhwCIf-Q?si=1oKfIswgT5rFGqRW https://amzn.asia/d/097jnUX
あき@4rcoid2025年10月1日かつて読んだまとめ実家近くの書店にて目に留まり、「疲れたと思わなければ疲れないのでは?(謎)」と一時期思っていたことがあったので実際の疲労のメカニズムについて知りたいと思い購入。 著者は東京慈恵会医科大学ウイルス学講座教授であり中でもヘルペスウイルスを専門にしているとのこと。 ヘルペスウイルスの多くは子どもの頃に初感染し、発疹や発熱などを発症したあとは神経節等に潜伏することが知られています。 また疲労などで身体の免疫が弱ったときには再び再活性化して発症します。 このことに注目し、唾液中のヘルペスウイルス(特にHHV-6)の量を測定することで疲労の程度が分かるということでした。 このHHV-6の量は絶対値(ある量を超えたら疲労)ではなく相対値(平常時との比較)であることに注意が必要で、実際の疲労度合いを知るには何回か測定が必要とのことです。 疲労が起こる実際のメカニズムについても詳しく書かれており、疲れたな休みたいなと思う疲労感は炎症性サイトカイン(炎症により細胞から分泌されるタンパク質)が脳に伝わることで生じます。 ではその原因となる炎症性サイトカインはどこから生じるのか?というところで先ほどのHHV-6が出てきます。 HHV-6の再活性化を誘導する因子が炎症性サイトカインも産生するのではという仮説が立ち、実際に「eIF2αのリン酸化」がアポトーシス(細胞死)や炎症性サイトカインの産生を引き起こし疲労の原因となっているそうです。 eIF2αのリン酸化は肝臓、心臓、脳、筋肉などの様々な場所で起こり、特に肝臓で多く、次いで心臓での炎症性サイトカインの産生が多いようです。 ではこのリン酸化を防げば疲労しないのではということになりますが、残念ながら生体に使えるよい阻害剤は存在していないとのこと。 抗酸化剤(N-アセチルシステインなど)は肝臓でのリン酸化を抑制して疲労感の軽減に繋がるが他の部位では効かず、働き過ぎないことに注意が必要。 次善の策としてリン酸化したeIF2αからリン酸を取る脱リン酸化を促すことで疲労が回復する方法はないかとなりますが、これには軽い運動が有効とのことでした。 この辺りの話はウイルス学や細胞生物学、生化学、薬理学に親しんだ方ならとても楽しく読めると思います。 ここまでの話は生理的な疲労で、ここから更に病的な疲労である慢性疲労症候群やうつ病についてのメカニズム、原因の考察についても詳しく述べられております。 詳しく知りたい方はぜひ読まれてみることをおすすめします。 まだまだHHV-6やSITH-1(うつ病の因子)の検査は一般的ではないので、これからさらなる技術の発展でスマートウォッチなどで経皮的に正確な疲労度合いが分かるようになると活動の指標になっていいなと思いました。 他分野との共同研究等で休養や睡眠によってHHV-6の検出量が変わるのかやeIF2αの脱リン酸化が進むのかなどが分かってくるといいな。 https://youtu.be/kPoFiv9jD7I?si=Be-FEC_j4ILcffUS https://youtu.be/kwhzhwCIf-Q?si=1oKfIswgT5rFGqRW https://amzn.asia/d/097jnUX
 あき@4rcoid2025年9月27日かつて読んだ神経節などに潜伏感染し疲れた時などに再発症することで知られるヘルペスウイルス。 ウイルス学教授である著者が唾液中のヘルペスウイルスの量を測定すれば疲労の度合いが分かるのではという所から疲労が発生するメカニズムを解明していくまでの過程が詳しく書いてある。 生化学や細胞生物学、ウイルス学、薬理学などを学んだことのある方ならより楽しめると思います。 病的な疲労である慢性疲労症候群やうつ病についても学ぶことができる。
あき@4rcoid2025年9月27日かつて読んだ神経節などに潜伏感染し疲れた時などに再発症することで知られるヘルペスウイルス。 ウイルス学教授である著者が唾液中のヘルペスウイルスの量を測定すれば疲労の度合いが分かるのではという所から疲労が発生するメカニズムを解明していくまでの過程が詳しく書いてある。 生化学や細胞生物学、ウイルス学、薬理学などを学んだことのある方ならより楽しめると思います。 病的な疲労である慢性疲労症候群やうつ病についても学ぶことができる。
 空色栞@reads_2025032025年6月12日聴き終わったaudibleで再生済み。 コロナの後遺症が研究を推し進めるきっかけになったのが皮肉。疲労は怖いけど全く無くなるのもいいことではない。疲労した時はビタミンB1を摂るといい。玄米、小麦、豚肉。
空色栞@reads_2025032025年6月12日聴き終わったaudibleで再生済み。 コロナの後遺症が研究を推し進めるきっかけになったのが皮肉。疲労は怖いけど全く無くなるのもいいことではない。疲労した時はビタミンB1を摂るといい。玄米、小麦、豚肉。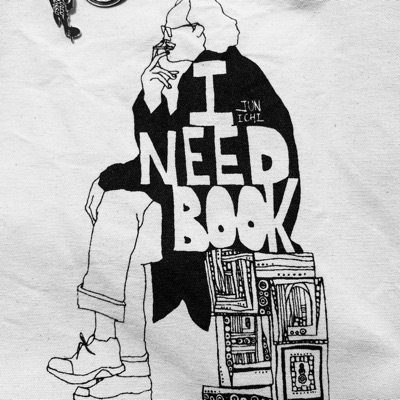 ゆかこ@crosscounter_ubk2025年3月26日読み終わった借りてきた図書館本疲れについて考えてみる。 なかなか難しい単語も多く完全に理解できなかったが、疲労とはなにかとその仕組みについては大枠を理解できた。
ゆかこ@crosscounter_ubk2025年3月26日読み終わった借りてきた図書館本疲れについて考えてみる。 なかなか難しい単語も多く完全に理解できなかったが、疲労とはなにかとその仕組みについては大枠を理解できた。
 kibita@kibita2025年3月11日読み終わった「疲労」という曖昧な概念が納得感を伴って明らかになっていく。その過程が実に快感だった。 本書では疲労と疲労感の違い、さらに生理的疲労と病的疲労の違いをわかりやすく解説している。ただの仕組みの説明ではなく、「どのようにしてそれが解明されてきたのか?」という科学史的な視点も加わっており、知識が組み上がっていく感覚が楽しい。 特に印象に残ったのはメタゲノム解析の考え方だ。遺伝率はヒトのDNAだけで決まるわけではなく、マイクロバイオーム(ヒトに棲む細菌)やバイローム(ヒトや細菌に感染しているウイルス)もまた、遺伝のように伝わるという。つまり、私たちの体の中で生きる微生物が遺伝の一部として機能しているのだ。この視点は新鮮だった。 マイクロバイオームの解析にはヒトゲノム解析の100倍、バイローム解析にはさらにその100倍のコストがかかるらしい。それをどう乗り越えていくのか? 研究の進め方という科学の面白さを感じさせてくれた。 ただ科学的な知識が十分でない自分にとっては、少しずつ明らかになる仕組みを把握しながら読むのが難しかった。先に基本的な概念を押さえてから読んだ方が混乱せずに楽しめたかもしれない。 けれど、その試行錯誤も含めて知識が腑に落ちる感覚が味わえる一冊だった。
kibita@kibita2025年3月11日読み終わった「疲労」という曖昧な概念が納得感を伴って明らかになっていく。その過程が実に快感だった。 本書では疲労と疲労感の違い、さらに生理的疲労と病的疲労の違いをわかりやすく解説している。ただの仕組みの説明ではなく、「どのようにしてそれが解明されてきたのか?」という科学史的な視点も加わっており、知識が組み上がっていく感覚が楽しい。 特に印象に残ったのはメタゲノム解析の考え方だ。遺伝率はヒトのDNAだけで決まるわけではなく、マイクロバイオーム(ヒトに棲む細菌)やバイローム(ヒトや細菌に感染しているウイルス)もまた、遺伝のように伝わるという。つまり、私たちの体の中で生きる微生物が遺伝の一部として機能しているのだ。この視点は新鮮だった。 マイクロバイオームの解析にはヒトゲノム解析の100倍、バイローム解析にはさらにその100倍のコストがかかるらしい。それをどう乗り越えていくのか? 研究の進め方という科学の面白さを感じさせてくれた。 ただ科学的な知識が十分でない自分にとっては、少しずつ明らかになる仕組みを把握しながら読むのが難しかった。先に基本的な概念を押さえてから読んだ方が混乱せずに楽しめたかもしれない。 けれど、その試行錯誤も含めて知識が腑に落ちる感覚が味わえる一冊だった。 とろたく@takutsuna2025年3月8日読んでる学び!紙の本ブルーバックスなんとなく疲れたなー。という気分が起こる体の仕組みを解説してくれる本。ブルーバックスが好きな著者が、ノリノリで解説してくれてるし、著者が研究者として行なった最新の知見にも触れられています。疲れが吹っ飛ぶような知的な刺激溢れる面白い本です。
とろたく@takutsuna2025年3月8日読んでる学び!紙の本ブルーバックスなんとなく疲れたなー。という気分が起こる体の仕組みを解説してくれる本。ブルーバックスが好きな著者が、ノリノリで解説してくれてるし、著者が研究者として行なった最新の知見にも触れられています。疲れが吹っ飛ぶような知的な刺激溢れる面白い本です。