自転車

32件の記録
 Kenichi Kawamura@ken1kwmr2025年6月25日読み終わった返却期限に追われて無理矢理読了。分厚い本を読み切ったのは久しぶりだが、思ったほど自分の中に残るものがなかった。『禅とオートバイ修理技術』の続きを読もうと思った。
Kenichi Kawamura@ken1kwmr2025年6月25日読み終わった返却期限に追われて無理矢理読了。分厚い本を読み切ったのは久しぶりだが、思ったほど自分の中に残るものがなかった。『禅とオートバイ修理技術』の続きを読もうと思った。 ゆらゆら@yuurayurari2025年6月24日読み終わった470頁に自転車の発明から200年の歴史での何度ものブームや馬車や自動車との軋轢や白眼視されたりの話、政治との結びつき(反権力)等盛り沢山で、最近ハマり始めた自転車への愛着と敬意が増した。タイヤの原料の天然ゴムが植民地搾取と無関係ではないこと、戦争での自転車部隊など兵器利用、アメリカ自動車連盟の人種差別など負の側面も書かれてるのも興味深かった。歴代国王が熱心なサイクリストのブータンのレースの話も気になるし、76年にアメリカ独立200周年記念で行われた6800kmの大陸横断ライド<バイクセンテニアル>の話も面白かった。 訳者あとがきでも触れられてる通り、タイヤの原料の天然ゴムが植民地での搾取と無関係ではないこと、戦争での自転車部隊などの兵器利用、アメリカの自動車連盟の人種差別、など負の側面も書かれてるのも興味深かった。あとは歴代国王が熱心なサイクリストのブータンでのレースの話も気になる。 あと、1976年にアメリカ独立200周年記念で行われた、6800kmの大陸横断ライド<バイクセンテニアル>の話も面白かった。ドキュメンタリーとかあったら観てみたい。にしても、そんなに読まないけど、ノンフィクションの本もいいな。 (25.6.14読了)
ゆらゆら@yuurayurari2025年6月24日読み終わった470頁に自転車の発明から200年の歴史での何度ものブームや馬車や自動車との軋轢や白眼視されたりの話、政治との結びつき(反権力)等盛り沢山で、最近ハマり始めた自転車への愛着と敬意が増した。タイヤの原料の天然ゴムが植民地搾取と無関係ではないこと、戦争での自転車部隊など兵器利用、アメリカ自動車連盟の人種差別など負の側面も書かれてるのも興味深かった。歴代国王が熱心なサイクリストのブータンのレースの話も気になるし、76年にアメリカ独立200周年記念で行われた6800kmの大陸横断ライド<バイクセンテニアル>の話も面白かった。 訳者あとがきでも触れられてる通り、タイヤの原料の天然ゴムが植民地での搾取と無関係ではないこと、戦争での自転車部隊などの兵器利用、アメリカの自動車連盟の人種差別、など負の側面も書かれてるのも興味深かった。あとは歴代国王が熱心なサイクリストのブータンでのレースの話も気になる。 あと、1976年にアメリカ独立200周年記念で行われた、6800kmの大陸横断ライド<バイクセンテニアル>の話も面白かった。ドキュメンタリーとかあったら観てみたい。にしても、そんなに読まないけど、ノンフィクションの本もいいな。 (25.6.14読了) 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月7日読み終わった3.11の直後に自転車で西日本に逃げた汽水空港のモリさんのことが急に思い出された。モリさんが自転車を買った自転車屋は本屋lighthouseのすぐそばにある。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月7日読み終わった3.11の直後に自転車で西日本に逃げた汽水空港のモリさんのことが急に思い出された。モリさんが自転車を買った自転車屋は本屋lighthouseのすぐそばにある。



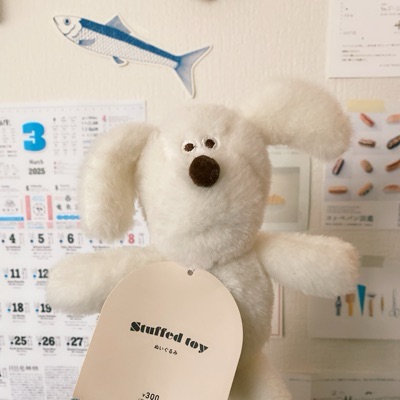





 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月6日読んでるまだ読んでるどうにか起床して少しだけ読む。第15章:大衆運動、つづき。自転車はコロナ禍、そしてBLM運動においても重要な役割を担った。そもそも移動の自由は大切な権利のひとつであり、しかしアメリカにおいては黒人などの非白人は自転車に乗っているだけで職質を受ける割合が高く、それを基本的に侵害されている。自転車に乗っているのは、あるいは乗らざるを得ないのは、ときに社会から周縁化された者=低所得になりがちな者でもある。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年3月6日読んでるまだ読んでるどうにか起床して少しだけ読む。第15章:大衆運動、つづき。自転車はコロナ禍、そしてBLM運動においても重要な役割を担った。そもそも移動の自由は大切な権利のひとつであり、しかしアメリカにおいては黒人などの非白人は自転車に乗っているだけで職質を受ける割合が高く、それを基本的に侵害されている。自転車に乗っているのは、あるいは乗らざるを得ないのは、ときに社会から周縁化された者=低所得になりがちな者でもある。









- numa@numa2025年3月6日読んでる祝・リリースにつき再開。 〈自転車の部品でもっとも重要なのはエンジン、つまり乗り手だ。(…)もっとも偉大な自転車詩人のひとりであるフラン・オブライエンはこのことを「人間と自転車の間で原子を交換した結果、本来の性格と自転車の性格が混ざりあっている……ほぼ半分人間、半分自転車となっている人びとがいる」と書いている。〉P105



 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月26日読んでるまだ読んでる第14章:墓場 自転車の廃棄について。運河や用水路の底には大量の自転車が存在している。悪ふざけと鬱憤晴らし、酔っ払い、事故、意図的な放棄、そして政治的な意思表示。2016年にはアメリカでトランスジェンダーの人が自転車とともに川に投身自殺した例があり、それはおそらくトランプとの影響も少なからずあることが推測され、となるといまも同様の事例が起きていることが推測され、トランプたちの悪ふざけにあらためて怒りを覚える。悪ふざけがしたいなら自分で買った自転車をホワイトハウスの噴水に投げ込みやがれ。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月26日読んでるまだ読んでる第14章:墓場 自転車の廃棄について。運河や用水路の底には大量の自転車が存在している。悪ふざけと鬱憤晴らし、酔っ払い、事故、意図的な放棄、そして政治的な意思表示。2016年にはアメリカでトランスジェンダーの人が自転車とともに川に投身自殺した例があり、それはおそらくトランプとの影響も少なからずあることが推測され、となるといまも同様の事例が起きていることが推測され、トランプたちの悪ふざけにあらためて怒りを覚える。悪ふざけがしたいなら自分で買った自転車をホワイトハウスの噴水に投げ込みやがれ。



 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月23日読んでるまだ読んでる第13章:ぼくの自転車遍歴 おわり これで本そのものも終わりにしてもよいのでは?と思うくらい締めかたが綺麗だったが、あと2章残っている。90代でまだ自転車に乗って生計を立てている人の話が出てきて、祖母を思い出した。怪我をするまで、80代でもまだ自転車に乗っていた。怪我したときもたしか歩きだったはずで、自転車に乗っていれば怪我しなかったかもしれない。それくらい優雅に漕ぎたおしていた。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月23日読んでるまだ読んでる第13章:ぼくの自転車遍歴 おわり これで本そのものも終わりにしてもよいのでは?と思うくらい締めかたが綺麗だったが、あと2章残っている。90代でまだ自転車に乗って生計を立てている人の話が出てきて、祖母を思い出した。怪我をするまで、80代でもまだ自転車に乗っていた。怪我したときもたしか歩きだったはずで、自転車に乗っていれば怪我しなかったかもしれない。それくらい優雅に漕ぎたおしていた。




 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月22日読んでるまだ読んでる第13章:ぼくの自転車遍歴 途中まで 前章から章ごとのボリュームが増えていて、一度で読みきれなくなっている。本章の始まりは遍歴という題のとおり幼少期の記憶を辿ることで、自転車に乗れるようになったその瞬間の記憶(がぼんやりとあること)について綴られている。「スポークに薄汚れたテニスボールを挟んでいるのがお決まりだった」(p.369)とあり、あれは世界共通のテニスボールだということを知る。著者は学生時代にありきたりのミュージシャンになりたい熱にも浮かされていて、バイクメッセンジャーのバイトをしながら曲作りをしていた頃の描写がよい。「「ロマンスに恋して」は、ぼくのデビュー・アルバムの四曲目になるはずだった。通好みの隠れた名曲、知られざる傑作」(p.379)。私にもデビューアルバムになるはずのアルバムがあり、どうやら4曲目のタイトルは「UOU-SAOU」らしい。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月22日読んでるまだ読んでる第13章:ぼくの自転車遍歴 途中まで 前章から章ごとのボリュームが増えていて、一度で読みきれなくなっている。本章の始まりは遍歴という題のとおり幼少期の記憶を辿ることで、自転車に乗れるようになったその瞬間の記憶(がぼんやりとあること)について綴られている。「スポークに薄汚れたテニスボールを挟んでいるのがお決まりだった」(p.369)とあり、あれは世界共通のテニスボールだということを知る。著者は学生時代にありきたりのミュージシャンになりたい熱にも浮かされていて、バイクメッセンジャーのバイトをしながら曲作りをしていた頃の描写がよい。「「ロマンスに恋して」は、ぼくのデビュー・アルバムの四曲目になるはずだった。通好みの隠れた名曲、知られざる傑作」(p.379)。私にもデビューアルバムになるはずのアルバムがあり、どうやら4曲目のタイトルは「UOU-SAOU」らしい。 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月18日読んでるまだ読んでる第12章:荷を負う動物たち おわり 過酷な現実を描写する後半。ダッカの街のルポとしても意義深い章だった。先進国へ向けて輸出されるものをつくり、先進国で廃棄されたものが行き着く場所でもある。そのどちらもがダッカを汚染する。荷を負う、というのは人力車だけの話ではないということか。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月18日読んでるまだ読んでる第12章:荷を負う動物たち おわり 過酷な現実を描写する後半。ダッカの街のルポとしても意義深い章だった。先進国へ向けて輸出されるものをつくり、先進国で廃棄されたものが行き着く場所でもある。そのどちらもがダッカを汚染する。荷を負う、というのは人力車だけの話ではないということか。

 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月17日読んでるまだ読んでる第12章:荷を負う動物 つづき 自転車=荷を負う動物として、人力車関連の話になる。冒頭の調子とは一転して、シリアスな雰囲気が強くなる。少しテーマはずれるが、スナウラ・テイラー『荷を引く獣たち 動物の解放と障害者の解放』(洛北出版)を次に読むべきな気がしてきた。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月17日読んでるまだ読んでる第12章:荷を負う動物 つづき 自転車=荷を負う動物として、人力車関連の話になる。冒頭の調子とは一転して、シリアスな雰囲気が強くなる。少しテーマはずれるが、スナウラ・テイラー『荷を引く獣たち 動物の解放と障害者の解放』(洛北出版)を次に読むべきな気がしてきた。
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月15日読んでるまだ読んでる第12章:荷を負う動物 このバングラデシュの首都でしばらく時間を過ごすと、人は「交通(ルビ:トラフィック)」という言葉に新しい意味を感じるようになり、自分が抱いていた定義を再考しはじめる。(p.318) ダッカのとてつもない渋滞への言及によって幕をあける章だが、私はタイのバンコクを思い出さずにはいられない。はじめてタイの車に乗せられたときはぬらぬらと隙間を縫うドライビングに死への恐怖を感じたが、慣れるとむしろ居心地がよかった。車線という概念を無視して連なる車たちと、日本の運転に慣れている者には隙間とは思えないそのスペースへ入り込んでいくバイクたち。その混沌≒交通ルールの無視が渋滞を悪化させていると我々は言いたくなるが、かれらはもはやそれを前提としてある種の「抜け穴」のようなものを適切に見つけ適切に活用しているのかもしれず、つまりかれらにとってこの渋滞は通常運行であり不快なものではないのかもしれない。というのは正確には少し言い過ぎで、イライラしてる人は時折発見された。とか考えてたら一段落目で読書がとまってしまった。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月15日読んでるまだ読んでる第12章:荷を負う動物 このバングラデシュの首都でしばらく時間を過ごすと、人は「交通(ルビ:トラフィック)」という言葉に新しい意味を感じるようになり、自分が抱いていた定義を再考しはじめる。(p.318) ダッカのとてつもない渋滞への言及によって幕をあける章だが、私はタイのバンコクを思い出さずにはいられない。はじめてタイの車に乗せられたときはぬらぬらと隙間を縫うドライビングに死への恐怖を感じたが、慣れるとむしろ居心地がよかった。車線という概念を無視して連なる車たちと、日本の運転に慣れている者には隙間とは思えないそのスペースへ入り込んでいくバイクたち。その混沌≒交通ルールの無視が渋滞を悪化させていると我々は言いたくなるが、かれらはもはやそれを前提としてある種の「抜け穴」のようなものを適切に見つけ適切に活用しているのかもしれず、つまりかれらにとってこの渋滞は通常運行であり不快なものではないのかもしれない。というのは正確には少し言い過ぎで、イライラしてる人は時折発見された。とか考えてたら一段落目で読書がとまってしまった。
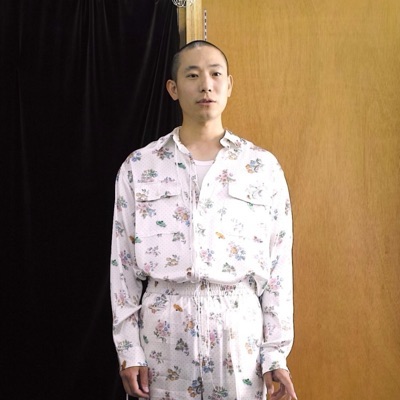

 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月12日読んでるまだ読んでる第11章:アメリカの海から海まで 1970年代に開催したアメリカ横断の自転車ツアーと、そのツアーがきっかけで結婚したふたりのライフヒストリー。2018年に結婚40周年でもう一度横断ツアーをしたときに、トランプの看板がたくさんあって辟易したことが綴られている。このふたりがそういう感覚を持っていること、つまり自分と同じ景色を見ていることに安心した。2025年、再度、そしてさらに厳しい状況を突きつけられている。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月12日読んでるまだ読んでる第11章:アメリカの海から海まで 1970年代に開催したアメリカ横断の自転車ツアーと、そのツアーがきっかけで結婚したふたりのライフヒストリー。2018年に結婚40周年でもう一度横断ツアーをしたときに、トランプの看板がたくさんあって辟易したことが綴られている。このふたりがそういう感覚を持っていること、つまり自分と同じ景色を見ていることに安心した。2025年、再度、そしてさらに厳しい状況を突きつけられている。



 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月9日読んでるまだ読んでる第10章:停まったまま全速力で エクササイズ用の自転車の話。タイタニック号にの客室にも設置されていたらしい。いまは海の中。暗闇のなかでエクササイズをする、ちょっと前に流行ってたやつにも触れられていて、その運動部屋には「決意を吸い、希望を吐く」「汗と車輪の回転にハイになる」などと貼り紙がされているらしい。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月9日読んでるまだ読んでる第10章:停まったまま全速力で エクササイズ用の自転車の話。タイタニック号にの客室にも設置されていたらしい。いまは海の中。暗闇のなかでエクササイズをする、ちょっと前に流行ってたやつにも触れられていて、その運動部屋には「決意を吸い、希望を吐く」「汗と車輪の回転にハイになる」などと貼り紙がされているらしい。
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月8日読んでるまだ読んでる第9章:山間の王国 ブータンでの自転車の話。ブータンは幸福の国としてのイメージが強いが、20世紀半ばまで農奴制があったし、幸福の国としての「アピール」をする前にはネパール系の民族を追放したり殺害したりして、いわゆる民族浄化をした。という自転車とは繋がりつつも別の観点にページが割かれていて、それがよかった。しかしどこにいっても奴隷制はあるし、ナショナリズムは跋扈する。そしてそれを隠蔽、カモフラージュする。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月8日読んでるまだ読んでる第9章:山間の王国 ブータンでの自転車の話。ブータンは幸福の国としてのイメージが強いが、20世紀半ばまで農奴制があったし、幸福の国としての「アピール」をする前にはネパール系の民族を追放したり殺害したりして、いわゆる民族浄化をした。という自転車とは繋がりつつも別の観点にページが割かれていて、それがよかった。しかしどこにいっても奴隷制はあるし、ナショナリズムは跋扈する。そしてそれを隠蔽、カモフラージュする。
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月7日読んでるまだ読んでる第8章:凍てつく大地 極寒の地とか山とか凍ってる川の上とかを自転車で走る者たちの話。びっくりするくらいたくさんの誤字脱字があり、校正どころか編集のチェックもし忘れた章なのだろうことが予測される。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月7日読んでるまだ読んでる第8章:凍てつく大地 極寒の地とか山とか凍ってる川の上とかを自転車で走る者たちの話。びっくりするくらいたくさんの誤字脱字があり、校正どころか編集のチェックもし忘れた章なのだろうことが予測される。
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月6日読んでるまだ読んでる第7章:脚のあいだの悦楽 自転車が登場し普及しはじめた19世紀末、主に女性の堕落を批判する意味合いで自転車と性的快楽を結びつける言説が増える(クソな家父長制だ)。もちろんそれに抵抗するフェミニズム的言説も現れる。現在はクィア的文脈にも波及している。引用されているバタイユの『眼球譚』、ヴィ・キ・ナオ『亡命中の魚』を読んでみたくなる。後者は未邦訳っぽい。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年2月6日読んでるまだ読んでる第7章:脚のあいだの悦楽 自転車が登場し普及しはじめた19世紀末、主に女性の堕落を批判する意味合いで自転車と性的快楽を結びつける言説が増える(クソな家父長制だ)。もちろんそれに抵抗するフェミニズム的言説も現れる。現在はクィア的文脈にも波及している。引用されているバタイユの『眼球譚』、ヴィ・キ・ナオ『亡命中の魚』を読んでみたくなる。後者は未邦訳っぽい。








