
ゆらゆら
@yuurayurari
6/24からおそるおそる使い始め。直近読んだ本をひとまずいろいろ登録してみよう…(すみません、まだフォローとかのこととかわかってなくて、手探りです。。)
- 2026年2月15日
 タタール人の砂漠ブッツァーティ,ディーノ・ブッツァーティ,脇功読み終わった敵襲の到来が一筋の希望という、ある砦の任務についた若き将校の単調な日々。気がついたら《時の遁走》にのみこまれている人生で、もう若くなく、最後に残った希望が《死の想念》というのは、この年齢で読んだからか、何となくわかる気がした。ブッツァーティの原風景とも言えそうなドロミテ・アルプス、いつか見てみたいな。
タタール人の砂漠ブッツァーティ,ディーノ・ブッツァーティ,脇功読み終わった敵襲の到来が一筋の希望という、ある砦の任務についた若き将校の単調な日々。気がついたら《時の遁走》にのみこまれている人生で、もう若くなく、最後に残った希望が《死の想念》というのは、この年齢で読んだからか、何となくわかる気がした。ブッツァーティの原風景とも言えそうなドロミテ・アルプス、いつか見てみたいな。 - 2026年2月7日
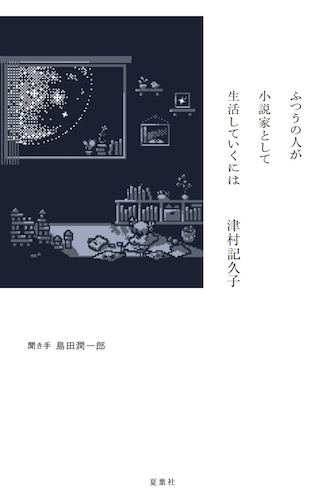 ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった小説も大好きな津村さんへの4日間にわたるロングインタビューということで、もったいなくて、毎週末に1日分ずつだけ読んできたけど、とうとう読み終えてしまった。なんというか、正気を保てる本、という思いが一番。 “いい人間にはなれなくても、いい行動はできるでしょということを書きたい”とか、“お金を出して誰かの人生をコントロールするより(←作られた幻想)、自分の人生をコントロールするために動いた人は大丈夫”とか、“精神的なギャンブルと感情的にケチなこと”とか、“自律性と時間は残る”とか、心に残る話もたくさん。あと、ティモシー・スナイダーの『暴政』読みたいな。
ふつうの人が小説家として生活していくには津村記久子読み終わった小説も大好きな津村さんへの4日間にわたるロングインタビューということで、もったいなくて、毎週末に1日分ずつだけ読んできたけど、とうとう読み終えてしまった。なんというか、正気を保てる本、という思いが一番。 “いい人間にはなれなくても、いい行動はできるでしょということを書きたい”とか、“お金を出して誰かの人生をコントロールするより(←作られた幻想)、自分の人生をコントロールするために動いた人は大丈夫”とか、“精神的なギャンブルと感情的にケチなこと”とか、“自律性と時間は残る”とか、心に残る話もたくさん。あと、ティモシー・スナイダーの『暴政』読みたいな。 - 2026年1月4日
 アワヨンベは大丈夫伊藤亜和読み終わった気になってた伊藤亜和さん、別冊太陽の呪物特集のイベントを視聴して面白かったので、読むなら今だと手にとる。セネガル人の父と日本人の母の間に生まれた著者の、20代の日々と子どもの頃の思い出を行き来するエッセイで、とにかく文章が面白くて、性別も年齢も境遇も全然違うのに、彼女の人生に思いを寄せながら読んだ。父と娘、母と娘、弟、祖父母と葛藤の少なくない家族の話としてもある普遍性があって読ませたし、一番感じたのは、人は“正しさ”だけで生きているのではなく、その間に人の生があるんだなということ。まとまらないけど、そんなことを思った。
アワヨンベは大丈夫伊藤亜和読み終わった気になってた伊藤亜和さん、別冊太陽の呪物特集のイベントを視聴して面白かったので、読むなら今だと手にとる。セネガル人の父と日本人の母の間に生まれた著者の、20代の日々と子どもの頃の思い出を行き来するエッセイで、とにかく文章が面白くて、性別も年齢も境遇も全然違うのに、彼女の人生に思いを寄せながら読んだ。父と娘、母と娘、弟、祖父母と葛藤の少なくない家族の話としてもある普遍性があって読ませたし、一番感じたのは、人は“正しさ”だけで生きているのではなく、その間に人の生があるんだなということ。まとまらないけど、そんなことを思った。 - 2025年12月31日
 ほんのささやかなことクレア・キーガン,鴻巣友季子読み終わった気になってたこの本もアイルランド文学で、中篇で読みやすく一気読み。舞台は1985年のクリスマス時季。96年まで実在したカトリック教会運営の母子収容施設とマグダレン洗濯所をモデルにした話で、主人公が一歩を踏み出せたのは、今が安定しているからだけど、それは運が良かったというのが、読み手の自分にもなんだか迫ってくるな。
ほんのささやかなことクレア・キーガン,鴻巣友季子読み終わった気になってたこの本もアイルランド文学で、中篇で読みやすく一気読み。舞台は1985年のクリスマス時季。96年まで実在したカトリック教会運営の母子収容施設とマグダレン洗濯所をモデルにした話で、主人公が一歩を踏み出せたのは、今が安定しているからだけど、それは運が良かったというのが、読み手の自分にもなんだか迫ってくるな。 - 2025年12月31日
 MONKEY vol. 36 特集 オーイン・マクナミーという謎オーイン・マクナミー,柴田元幸読み終わった北アイルランド生まれの作家オーイン・マクナミーの短篇11本、エッセイ、インタビュー、訳者の柴田先生×アンドルー・フィッツサイモンズ×デイヴィッド・ピース鼎談など。 悪天候の海辺の町、厳しい労働、移民、国境、暴力の気配、消える女性…などとにかく不穏な話が、詩のような透徹した描写で積み重なる。それでも手放さない感じが良かった。鼎談では、国境地帯を描いたアメリカのコーマック・マッカーシーとの比較もあって興味深くよむ。
MONKEY vol. 36 特集 オーイン・マクナミーという謎オーイン・マクナミー,柴田元幸読み終わった北アイルランド生まれの作家オーイン・マクナミーの短篇11本、エッセイ、インタビュー、訳者の柴田先生×アンドルー・フィッツサイモンズ×デイヴィッド・ピース鼎談など。 悪天候の海辺の町、厳しい労働、移民、国境、暴力の気配、消える女性…などとにかく不穏な話が、詩のような透徹した描写で積み重なる。それでも手放さない感じが良かった。鼎談では、国境地帯を描いたアメリカのコーマック・マッカーシーとの比較もあって興味深くよむ。 - 2025年12月29日
 アイルランド紀行栩木伸明読み終わったNEECAPを観てアイルランドのことを知りたくなって読んだ。歴史・地理・文化を自由に渡り歩く寄り道的エピソードに溢れた30章で、少しずつアイルランドが身近なものになっていく楽しい読書体験だった。 まず、ぼんやりアイルランドとしかイメージできてなかったのが、ダブリンのある東部レンスター、西部コナハト、南部マンスター、北部アルスター、そして北アイルランドと地理的なことが見えてきた。 そしてスウィフト、ワイルド、ジョイス、ベケット、イェイツ、ヒーニーと偉大な作家達(!)の話も興味深く、映画もザ・コミットメンツとかブッチャー・ボーイとか色々観たくなった。
アイルランド紀行栩木伸明読み終わったNEECAPを観てアイルランドのことを知りたくなって読んだ。歴史・地理・文化を自由に渡り歩く寄り道的エピソードに溢れた30章で、少しずつアイルランドが身近なものになっていく楽しい読書体験だった。 まず、ぼんやりアイルランドとしかイメージできてなかったのが、ダブリンのある東部レンスター、西部コナハト、南部マンスター、北部アルスター、そして北アイルランドと地理的なことが見えてきた。 そしてスウィフト、ワイルド、ジョイス、ベケット、イェイツ、ヒーニーと偉大な作家達(!)の話も興味深く、映画もザ・コミットメンツとかブッチャー・ボーイとか色々観たくなった。 - 2025年12月14日
 ブランコブリッタ・テッケントラップ,梨木香歩読み終わった大学の同級生が編集担当したというのでおすすめしてもらった本。鳥がたくさん印象的な感じで出てきて、梨木さんの翻訳というのも合ってて良かった。本のことを言うのにあまり上手な言い方ではないと思いつつ、かつていろんな人がいろんな場面で拠り所としていたことが定点観測で表現されてて、そこに時間の厚みを感じ、映画みたいだなあと思った。最後の展開も、ノンフィクションのような感じもして、絵空事でないリアリティも感じられて良かった。
ブランコブリッタ・テッケントラップ,梨木香歩読み終わった大学の同級生が編集担当したというのでおすすめしてもらった本。鳥がたくさん印象的な感じで出てきて、梨木さんの翻訳というのも合ってて良かった。本のことを言うのにあまり上手な言い方ではないと思いつつ、かつていろんな人がいろんな場面で拠り所としていたことが定点観測で表現されてて、そこに時間の厚みを感じ、映画みたいだなあと思った。最後の展開も、ノンフィクションのような感じもして、絵空事でないリアリティも感じられて良かった。 - 2025年12月13日
 小僧の神様・城の崎にて志賀直哉読み終わった大正6(1917)〜15(1926)年発表の作家・第二期の18篇を収めた短篇集。読書会で「小僧の神様」を読んだのを機に初めて志賀直哉をまとめて読む。 「小僧〜」は、読書会で読んだからか、余計に“善/偽善”とは、と考えさせられたし、最後の段落は、小説って自由だなと。 時代物の「赤西蠣太」は菓子好きの“醜男”で将棋好きという人物造形も良くて、シンプルに面白かった。お伽話風の「転生」は落語になりそう。 「焚火」「城の崎にて」は文章も良いし、暗く静かな感じが好ましかった。これが志賀直哉の大きな魅力の一つなんだなと。 「佐々木の場合」「好人物の夫婦」や山科四部作など、男女や夫婦の話では、褒められたものではないはずの、男の正直なのか開き直りなのか、内面告白が清々しさすらあるくらい。 いつか『暗夜行路』と『和解』も読みたいな。
小僧の神様・城の崎にて志賀直哉読み終わった大正6(1917)〜15(1926)年発表の作家・第二期の18篇を収めた短篇集。読書会で「小僧の神様」を読んだのを機に初めて志賀直哉をまとめて読む。 「小僧〜」は、読書会で読んだからか、余計に“善/偽善”とは、と考えさせられたし、最後の段落は、小説って自由だなと。 時代物の「赤西蠣太」は菓子好きの“醜男”で将棋好きという人物造形も良くて、シンプルに面白かった。お伽話風の「転生」は落語になりそう。 「焚火」「城の崎にて」は文章も良いし、暗く静かな感じが好ましかった。これが志賀直哉の大きな魅力の一つなんだなと。 「佐々木の場合」「好人物の夫婦」や山科四部作など、男女や夫婦の話では、褒められたものではないはずの、男の正直なのか開き直りなのか、内面告白が清々しさすらあるくらい。 いつか『暗夜行路』と『和解』も読みたいな。 - 2025年10月12日
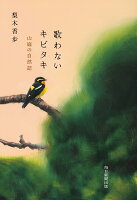 歌わないキビタキ梨木香歩読み終わったサンデー毎日連載時に時々読んでいたけど、今まとめて読むと、特にコロナの時代の人の心のありようが思い出されて、そういう意味でも貴重なドキュメントと思った。東京の自宅、八ヶ岳の山小屋、そしてお母様の介護のために通う南九州、と場所を行ったり来たりしながらも、常に野鳥や草花やキノコなど自然に思いを傾け、かと思うと具体的な事件や時事的な社会のことなどの考察にも筆は及び、概して社会的動物である人類という種への理解を深めようとする試みの集積と思った。著者のようには生きられないけど、その思考の一片を共有できる本というもののありがたさを思ったり。
歌わないキビタキ梨木香歩読み終わったサンデー毎日連載時に時々読んでいたけど、今まとめて読むと、特にコロナの時代の人の心のありようが思い出されて、そういう意味でも貴重なドキュメントと思った。東京の自宅、八ヶ岳の山小屋、そしてお母様の介護のために通う南九州、と場所を行ったり来たりしながらも、常に野鳥や草花やキノコなど自然に思いを傾け、かと思うと具体的な事件や時事的な社会のことなどの考察にも筆は及び、概して社会的動物である人類という種への理解を深めようとする試みの集積と思った。著者のようには生きられないけど、その思考の一片を共有できる本というもののありがたさを思ったり。 - 2025年9月23日
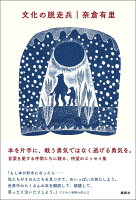 文化の脱走兵奈倉有里読み終わった@ 国営昭和記念公園大きな公園で秋風に吹かれてチェアリングしながら読み終える。 前作『夕暮れに〜』が、(ほんとはそんなことないはずだけど)無邪気とも言えるくらい、ひたすら文学への愛に満たされてたのと比べ、2022〜24年に連載された本書はどうしたってロシアとウクライナの戦争のことが随所に現れる。いや、だからこそ、かえって文学(文化)の力を強く感じた。 加えて、子ども時代の話がたくさん入ってくるのも、(割と同世代で住んでた場所もそう遠くないから実感としてわかることも多く)懐かしさと少しの寂しさとを共感できて良かった。 秋を数える話(人生の時間の捉え方が良い方に広がった)や源氏物語の話(やはり角田源氏を読まねば)、巣穴の会話(津村さんの小説みたい)、猫背の鯨(誤植の詩!)…などが特に好き。柏崎の狸の話も、最近家のことをよく考えるようになってたからとても印象深い。雪の新潟に行ってみたいな。
文化の脱走兵奈倉有里読み終わった@ 国営昭和記念公園大きな公園で秋風に吹かれてチェアリングしながら読み終える。 前作『夕暮れに〜』が、(ほんとはそんなことないはずだけど)無邪気とも言えるくらい、ひたすら文学への愛に満たされてたのと比べ、2022〜24年に連載された本書はどうしたってロシアとウクライナの戦争のことが随所に現れる。いや、だからこそ、かえって文学(文化)の力を強く感じた。 加えて、子ども時代の話がたくさん入ってくるのも、(割と同世代で住んでた場所もそう遠くないから実感としてわかることも多く)懐かしさと少しの寂しさとを共感できて良かった。 秋を数える話(人生の時間の捉え方が良い方に広がった)や源氏物語の話(やはり角田源氏を読まねば)、巣穴の会話(津村さんの小説みたい)、猫背の鯨(誤植の詩!)…などが特に好き。柏崎の狸の話も、最近家のことをよく考えるようになってたからとても印象深い。雪の新潟に行ってみたいな。 - 2025年9月16日
 推し、燃ゆ宇佐見りん聴き終わった長距離バス移動で、初めてオーディオブックで本を読んだ(聴いた?)。意外と、というか、全然苦もなく集中して聴了できた。作品は、最初はアイドルを推すということ自体が、あんまり自分にはわからないし、そんなに興味を持てないかも…と思ってたけど、主人公の生きづらさがやっぱり切実な感じがして、それを追体験していくことはある種のカタルシスがあったと思う。あと、最近芥川を読んだから、この人生の生きづらさを書くというのは、文学の世界では連綿と続いてきたんだなあ、さすが芥川賞受賞作と思ったり。
推し、燃ゆ宇佐見りん聴き終わった長距離バス移動で、初めてオーディオブックで本を読んだ(聴いた?)。意外と、というか、全然苦もなく集中して聴了できた。作品は、最初はアイドルを推すということ自体が、あんまり自分にはわからないし、そんなに興味を持てないかも…と思ってたけど、主人公の生きづらさがやっぱり切実な感じがして、それを追体験していくことはある種のカタルシスがあったと思う。あと、最近芥川を読んだから、この人生の生きづらさを書くというのは、文学の世界では連綿と続いてきたんだなあ、さすが芥川賞受賞作と思ったり。 - 2025年9月13日
 読んでる明日からの上高地旅行に向けて、手に取る。 ひとまず読んだのは… 浦松佐美太郎「穂高・徳沢・梓川」 串田孫一「初夏の神河内」 田中澄江「花の百名山」 北杜夫「アルプス讃歌」 芥川龍之介「槍ヶ嶽紀行」 山崎安治「芥川龍之介の槍ヶ岳登山」 大森久雄「解説(上高地・神河内・上荻河内)」 編者でもある大森久雄さんの解説が、上高地自体の全体的な紹介になってて、かつ収録作を概観でき、そして、かつては“神河内”とも表記されたことや今どう表記すべきかの話もあり、良かった。 浦松さん(1907-1981)のエッセイは、梓川の流れにきらめく光や夕陽に照らされる穂高の岩壁などの描写が美しくて、期待が高まる。牛番や岩魚釣など人も出てくる(牧場があるんだと知る)。 串田さん(1915-2005)は、自分でも名前は知ってる山のことを書いた人。大正池は、大正時代(1915年)の焼岳の噴火でできた池だと知る。観光化されていく上高地を残念に思いながら、昔の上高地での思い出を愛おしんだりしてる。 田中さん(1908-2000)のが、一番良かった。からだの弱い息子さんのことを考えたり、一緒に来れたことを喜んだり、上高地のことが田中さんの人生の歩みとともに語られてるのが、心に染みた。 北杜夫(1927-2011)は、槍ヶ岳登山のことを書いたというデビュー長編『幽霊』を読んでみたくなった。 芥川は、こないだ「河童」を読んだから、興味を持って読む。この本に収められているのも小説だけど、山崎さん(1919-1985)のも併せて読むと、実際に高校時代に友人と上高地に来た時のことが、結構そのまま作品になってるのがわかって面白かった。カモシカに会いたいな。 また上高地に本を持ってって、他のも読もう。 (25.9.12)
読んでる明日からの上高地旅行に向けて、手に取る。 ひとまず読んだのは… 浦松佐美太郎「穂高・徳沢・梓川」 串田孫一「初夏の神河内」 田中澄江「花の百名山」 北杜夫「アルプス讃歌」 芥川龍之介「槍ヶ嶽紀行」 山崎安治「芥川龍之介の槍ヶ岳登山」 大森久雄「解説(上高地・神河内・上荻河内)」 編者でもある大森久雄さんの解説が、上高地自体の全体的な紹介になってて、かつ収録作を概観でき、そして、かつては“神河内”とも表記されたことや今どう表記すべきかの話もあり、良かった。 浦松さん(1907-1981)のエッセイは、梓川の流れにきらめく光や夕陽に照らされる穂高の岩壁などの描写が美しくて、期待が高まる。牛番や岩魚釣など人も出てくる(牧場があるんだと知る)。 串田さん(1915-2005)は、自分でも名前は知ってる山のことを書いた人。大正池は、大正時代(1915年)の焼岳の噴火でできた池だと知る。観光化されていく上高地を残念に思いながら、昔の上高地での思い出を愛おしんだりしてる。 田中さん(1908-2000)のが、一番良かった。からだの弱い息子さんのことを考えたり、一緒に来れたことを喜んだり、上高地のことが田中さんの人生の歩みとともに語られてるのが、心に染みた。 北杜夫(1927-2011)は、槍ヶ岳登山のことを書いたというデビュー長編『幽霊』を読んでみたくなった。 芥川は、こないだ「河童」を読んだから、興味を持って読む。この本に収められているのも小説だけど、山崎さん(1919-1985)のも併せて読むと、実際に高校時代に友人と上高地に来た時のことが、結構そのまま作品になってるのがわかって面白かった。カモシカに会いたいな。 また上高地に本を持ってって、他のも読もう。 (25.9.12) - 2025年9月10日
 河童/或阿呆の一生改版芥川龍之介読んでる週末の上高地旅行に備えて、収録されている短編「河童」を読む。冒頭こそ上高地が出てくるものの、その後は河童の国に行ってしまって、当時の社会に対する皮肉や批評がありそうな寓話めいてくるんだけど、あんまりわかんないから少し退屈かもと思ってるうちに、雄を追いかける雌河童の話やら“自殺”をめぐる話やら、どんどん気が滅入る話になっていく。でも、なにかそこから突き抜けていく、人生について考え抜こうという凄みを感じた。1927年発表の芥川最晩年の作(同年7月没)。
河童/或阿呆の一生改版芥川龍之介読んでる週末の上高地旅行に備えて、収録されている短編「河童」を読む。冒頭こそ上高地が出てくるものの、その後は河童の国に行ってしまって、当時の社会に対する皮肉や批評がありそうな寓話めいてくるんだけど、あんまりわかんないから少し退屈かもと思ってるうちに、雄を追いかける雌河童の話やら“自殺”をめぐる話やら、どんどん気が滅入る話になっていく。でも、なにかそこから突き抜けていく、人生について考え抜こうという凄みを感じた。1927年発表の芥川最晩年の作(同年7月没)。 - 2025年9月4日
 焼跡のイエス・善財石川淳,立石伯読み終わった初めて読んだ石川淳の短編集。モラルも秩序もリセットされた戦後の空白を舞台に、基本的に男と女の話が多いんだけど、息の長い文章で、あてもなく歩くシーンが多くて、結構好きかも。幻想に振れる「山桜」や、結婚を巡る駆引きが妙に緊張感がある「処女懐胎」も良かった。 「焼跡のイエス」は、三鷹のUNITEさんの読書会で読んで、みんなで精読するから、一人で初読の時には気がつかない細部の発見(最後の砂漠のとことか)もたくさんあって、楽しかった。 あとは、内容もさることながら、やっぱり文章それ自体が良くて、何となく最初に堀江敏幸を読んだ時のことを思い出した。時代はもちろん逆だけど、フランス文学者の書くものの系譜みたいなのがあるのかな。
焼跡のイエス・善財石川淳,立石伯読み終わった初めて読んだ石川淳の短編集。モラルも秩序もリセットされた戦後の空白を舞台に、基本的に男と女の話が多いんだけど、息の長い文章で、あてもなく歩くシーンが多くて、結構好きかも。幻想に振れる「山桜」や、結婚を巡る駆引きが妙に緊張感がある「処女懐胎」も良かった。 「焼跡のイエス」は、三鷹のUNITEさんの読書会で読んで、みんなで精読するから、一人で初読の時には気がつかない細部の発見(最後の砂漠のとことか)もたくさんあって、楽しかった。 あとは、内容もさることながら、やっぱり文章それ自体が良くて、何となく最初に堀江敏幸を読んだ時のことを思い出した。時代はもちろん逆だけど、フランス文学者の書くものの系譜みたいなのがあるのかな。 - 2025年9月3日
 木かげの家の小人たちいぬいとみこ,吉井忠読み終わった数年前に読んだのを、今回、読書会のために再読。冒頭の「ぼく」視点語りのプロローグ的な文章の存在をすっかり忘れてたけど、「だれにも行けない土地」の話は、抜き出しても名エッセイで良かった。 物語としても、単に戦時中のことを稀有な自由主義の両親のもとで育った少女のお話をベースに、英国ファンタジー×日本の土着の想像上の存在(アマネジャキ)も加えて描いたという試みを超えて、面白く読んだ。それは細部の豊かさと作家の読ませる技量なのかとひとまずは思った。 斎藤真理子さんの『本の栞にぶら下がる』の「いぬいとみこさんのこと」の章を合わせて読むと、この物語を1959年に書いたいぬいさんという人間のことをより意識することになり、本って一冊では完結しないんだなと思った。
木かげの家の小人たちいぬいとみこ,吉井忠読み終わった数年前に読んだのを、今回、読書会のために再読。冒頭の「ぼく」視点語りのプロローグ的な文章の存在をすっかり忘れてたけど、「だれにも行けない土地」の話は、抜き出しても名エッセイで良かった。 物語としても、単に戦時中のことを稀有な自由主義の両親のもとで育った少女のお話をベースに、英国ファンタジー×日本の土着の想像上の存在(アマネジャキ)も加えて描いたという試みを超えて、面白く読んだ。それは細部の豊かさと作家の読ませる技量なのかとひとまずは思った。 斎藤真理子さんの『本の栞にぶら下がる』の「いぬいとみこさんのこと」の章を合わせて読むと、この物語を1959年に書いたいぬいさんという人間のことをより意識することになり、本って一冊では完結しないんだなと思った。 - 2025年8月17日
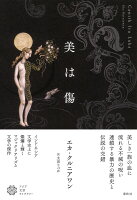 美は傷エカ・クルニアワン,太田りべか読み終わったジャワ島東部の架空の街ハリムンダを舞台に、オランダ植民地時代末期から日本占領下、独立、独裁下の弾圧と、インドネシア100年の暴力にまみれた歴史を、ある女性とその一族の物語を軸に描いてて、500頁超えの長編ながら、死者や幽霊も出てくるお話の面白さでぐいぐい引き込まれた。 こないだ観た「ルック・オブ・サイレンス」と前作「アクト・オブ・キリング」で描かれた1965年の「9月30日事件」(クーデターとその後の“共産主義者”弾圧)のことも、ある意味、寓話的に描かれていて、小説の凄みを感じた。最終的には、どこか、歴史で犠牲になった人々への鎮魂歌のようにも思った。 春秋社さんのアジア文芸ライブラリー。チベットの『花と夢』に続いて、読むの2冊目。他のも読んでいきたいな。
美は傷エカ・クルニアワン,太田りべか読み終わったジャワ島東部の架空の街ハリムンダを舞台に、オランダ植民地時代末期から日本占領下、独立、独裁下の弾圧と、インドネシア100年の暴力にまみれた歴史を、ある女性とその一族の物語を軸に描いてて、500頁超えの長編ながら、死者や幽霊も出てくるお話の面白さでぐいぐい引き込まれた。 こないだ観た「ルック・オブ・サイレンス」と前作「アクト・オブ・キリング」で描かれた1965年の「9月30日事件」(クーデターとその後の“共産主義者”弾圧)のことも、ある意味、寓話的に描かれていて、小説の凄みを感じた。最終的には、どこか、歴史で犠牲になった人々への鎮魂歌のようにも思った。 春秋社さんのアジア文芸ライブラリー。チベットの『花と夢』に続いて、読むの2冊目。他のも読んでいきたいな。 - 2025年8月3日
 向田邦子の恋文向田和子読み終わった同僚から借りっぱなしの本を整理しがてら読む。トットてれびで美村里江さんが演じてたので気になり、4年前に行った没後40周年展もすごく良かった向田邦子(彼女自身のドラマはまだ観れてない)。その彼女の“秘め事”を、彼女の手紙とN氏の日記も収め、9つ下の妹が綴る。向田邦子という人は、圧倒的にケアの人で、かつ自分の仕事と人生も楽しみ謳歌する人だったんだなあと感じた。妹の和子さんが、その秘められた封筒を開けるのに、20年もかかったというのに、それだけ家族という物語の大きさ・重さを感じた。良い本だった。
向田邦子の恋文向田和子読み終わった同僚から借りっぱなしの本を整理しがてら読む。トットてれびで美村里江さんが演じてたので気になり、4年前に行った没後40周年展もすごく良かった向田邦子(彼女自身のドラマはまだ観れてない)。その彼女の“秘め事”を、彼女の手紙とN氏の日記も収め、9つ下の妹が綴る。向田邦子という人は、圧倒的にケアの人で、かつ自分の仕事と人生も楽しみ謳歌する人だったんだなあと感じた。妹の和子さんが、その秘められた封筒を開けるのに、20年もかかったというのに、それだけ家族という物語の大きさ・重さを感じた。良い本だった。 - 2025年8月3日
 ババヤガの夜王谷晶読み終わった積ん読だったのを、ダガー賞受賞の話題で読むなら今だ!と読み始めたら、想像していたよりリーダビリティの高いエンタメで、一気に読んだ。「アウトレイジ」的世界にシスターフッドが乗り込んだ(或いは引きずり込まれた)ような物語で、終盤の捻り方にはおおっとなった(物語の時代設定も、途中で、あっそうだったのかとなった)。ラストに広がる風景は、『ピエタとトランジ』を思い出してた。装画も格好よい。映画化されるといいな。
ババヤガの夜王谷晶読み終わった積ん読だったのを、ダガー賞受賞の話題で読むなら今だ!と読み始めたら、想像していたよりリーダビリティの高いエンタメで、一気に読んだ。「アウトレイジ」的世界にシスターフッドが乗り込んだ(或いは引きずり込まれた)ような物語で、終盤の捻り方にはおおっとなった(物語の時代設定も、途中で、あっそうだったのかとなった)。ラストに広がる風景は、『ピエタとトランジ』を思い出してた。装画も格好よい。映画化されるといいな。 - 2025年8月2日
 夕暮れに夜明けの歌を奈倉有里読み終わったなんでもっと早く読まなかったのかと思うくらい、良い本だった。こんなにも文学を魅力的に書いて、その力を肯定する言葉たちに出会えて良かったし、特にラストにかけてのアントーノフ先生のことなど、一冊の本としても凄みがあった。学生時代、こんな同級生がいたら、もっと文学の話をしたかったなと思ったけど、気づかなかっただけで本当はいたのかもなあと思ったり。 ユーリャやマーシャなど登場する同級生たちも、それぞれの個性が魅力的に書かれてたし、反対に、自分が創作科の学生たちの小説に書かれるところでは、現実とフィクションの一筋縄で行かない関係についても考察が深められてて、読み応えがあった。 『巨匠とマルガリータ』とか、登場するロシア文学作品も読みたくなったし、詩の朗読CDを聴きながら散歩するところでは、日本にも詩の朗読CDとかないのなかなあと調べた(昔の「新潮」の特集の付録が気になる)。
夕暮れに夜明けの歌を奈倉有里読み終わったなんでもっと早く読まなかったのかと思うくらい、良い本だった。こんなにも文学を魅力的に書いて、その力を肯定する言葉たちに出会えて良かったし、特にラストにかけてのアントーノフ先生のことなど、一冊の本としても凄みがあった。学生時代、こんな同級生がいたら、もっと文学の話をしたかったなと思ったけど、気づかなかっただけで本当はいたのかもなあと思ったり。 ユーリャやマーシャなど登場する同級生たちも、それぞれの個性が魅力的に書かれてたし、反対に、自分が創作科の学生たちの小説に書かれるところでは、現実とフィクションの一筋縄で行かない関係についても考察が深められてて、読み応えがあった。 『巨匠とマルガリータ』とか、登場するロシア文学作品も読みたくなったし、詩の朗読CDを聴きながら散歩するところでは、日本にも詩の朗読CDとかないのなかなあと調べた(昔の「新潮」の特集の付録が気になる)。 - 2025年7月23日
 霧が晴れた時 自選恐怖小説集小松左京読み終わった名前は知ってたけど、初めて読んだ小松左京。全部が最高に面白かったかはわからないけど、戦争の災禍を土着的な呪いと掛け合わせた「くだんのはは」、戦争の忌まわしい記憶をSF的想像力で再現する「召集令状」、完全に振り切れた「秘密」、さすがの作品だった。 特に、平穏で平凡な日常の見事な描写からの、狂気や恐怖にスイッチが入るときのギャップがすごく面白かった。どんな風に小松左京が小説を書いていったのかに、俄然興味がわいた。和田忠彦さんがカルヴィーノイベントで京大でイタリア文学を学んだと話題にしてたのも思い出したり。
霧が晴れた時 自選恐怖小説集小松左京読み終わった名前は知ってたけど、初めて読んだ小松左京。全部が最高に面白かったかはわからないけど、戦争の災禍を土着的な呪いと掛け合わせた「くだんのはは」、戦争の忌まわしい記憶をSF的想像力で再現する「召集令状」、完全に振り切れた「秘密」、さすがの作品だった。 特に、平穏で平凡な日常の見事な描写からの、狂気や恐怖にスイッチが入るときのギャップがすごく面白かった。どんな風に小松左京が小説を書いていったのかに、俄然興味がわいた。和田忠彦さんがカルヴィーノイベントで京大でイタリア文学を学んだと話題にしてたのも思い出したり。
読み込み中...