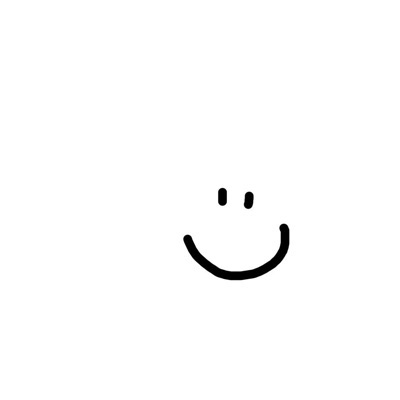差し出し方の教室

16件の記録
 トマト1号@tomato_12025年11月20日読み終わった感想@ 自宅差し出すお仕事の方にオススメ。 私的には第II部に入って急におもしろくなった。 読了したいけど、まだしばらく手元に置いておきたい本なので、ちょっとペースダウンする。 --25.11.16. 第二部『城崎裁判』 p.216 このまちが儲かるまちでいなければ、まちの人も居続けてくれませんし、まちを出て行った跡取りたちも戻ってこない 共栄共存を大事にしています(略)街並みをつくるのは一軒一軒の商店であり旅館なので、数がないことには継続できません p.224(サイトシーイングとツーリズム)未知なる場所と偶然にも深く結びついてしまう一個人をどうつくっていくのか p.226 場所としての引力をつくろうと思ったら、そのヒントは自分たちが踏みしめている地べたにある --25.11.20.読了 最後まで興味深く読んだ。今後の仕事でたびたびレファレンスしていきたい。 各章末尾の「参考文献」も今後のターゲットになりそうな本が色々あった。
トマト1号@tomato_12025年11月20日読み終わった感想@ 自宅差し出すお仕事の方にオススメ。 私的には第II部に入って急におもしろくなった。 読了したいけど、まだしばらく手元に置いておきたい本なので、ちょっとペースダウンする。 --25.11.16. 第二部『城崎裁判』 p.216 このまちが儲かるまちでいなければ、まちの人も居続けてくれませんし、まちを出て行った跡取りたちも戻ってこない 共栄共存を大事にしています(略)街並みをつくるのは一軒一軒の商店であり旅館なので、数がないことには継続できません p.224(サイトシーイングとツーリズム)未知なる場所と偶然にも深く結びついてしまう一個人をどうつくっていくのか p.226 場所としての引力をつくろうと思ったら、そのヒントは自分たちが踏みしめている地べたにある --25.11.20.読了 最後まで興味深く読んだ。今後の仕事でたびたびレファレンスしていきたい。 各章末尾の「参考文献」も今後のターゲットになりそうな本が色々あった。

 高卒派遣社員@hidari_s2025年4月4日読み終わった著者はブックディレクターとして自ら執筆するだけでなく、図書館・病院・公共施設の書棚の選書や本にまつわる空間プロデュースを手がける人物。可処分時間の争奪戦となっている現代において、本を「読め、読め」と圧力をかけるのではなく「気がついたら手に取っていた」という状況を作ることが理想的だと説く。そのためには読者になり得る人々への「本の差し出し方」が重要だという考えに基づき、本書には様々な業界の「差し出し手」や、実際に著者と一緒に「本の差し出し方」を考えた人々へのインタビューが収録されている。 前半では、博物館・動物園・デジタルコミュニケーション・ワインバーで差し出すことを極めた人々が登場する。取材に答えているそれぞれが活躍しているのは全く違うジャンルではあるが、「差し出す側」の意図と、「差し出された側」の心地よさが交わるポイントを狙うために、試行錯誤することが大切なのだと伝わってくる。押し付けがましくなく、かつ意図はあっても過度に作為的にはならずに心地よさを演出するのは至難の業である。 後半では、著者と一緒に新しい本の差し出し方を考えた温泉地・病院・保育園の担当者が登場する。特に城崎温泉でしか買えない、いわば地産地消の自費出版本を町おこしに繋げていった実例は、本というモノと温泉旅行というコトがうまく噛み合った素晴らしい実例だと思う。もちろんそこに至るまでには紆余曲折があり、核となるNPO法人がうまく地元の人々を巻き込んでいったからこそ成し得た結果である。このやり方が万能薬とはならないかもしれないが、何をどのように差し出すかを考える上で参考になった。 「差し出し方」とじっくり向き合う著者の思考は、本にまつわる流通・小売業界だけではなくメディア論や教育論にも応用できるものだと感じた。 本書を読んだ後は、ひとまず「感想の差し出し方」から考えてみようと思った。
高卒派遣社員@hidari_s2025年4月4日読み終わった著者はブックディレクターとして自ら執筆するだけでなく、図書館・病院・公共施設の書棚の選書や本にまつわる空間プロデュースを手がける人物。可処分時間の争奪戦となっている現代において、本を「読め、読め」と圧力をかけるのではなく「気がついたら手に取っていた」という状況を作ることが理想的だと説く。そのためには読者になり得る人々への「本の差し出し方」が重要だという考えに基づき、本書には様々な業界の「差し出し手」や、実際に著者と一緒に「本の差し出し方」を考えた人々へのインタビューが収録されている。 前半では、博物館・動物園・デジタルコミュニケーション・ワインバーで差し出すことを極めた人々が登場する。取材に答えているそれぞれが活躍しているのは全く違うジャンルではあるが、「差し出す側」の意図と、「差し出された側」の心地よさが交わるポイントを狙うために、試行錯誤することが大切なのだと伝わってくる。押し付けがましくなく、かつ意図はあっても過度に作為的にはならずに心地よさを演出するのは至難の業である。 後半では、著者と一緒に新しい本の差し出し方を考えた温泉地・病院・保育園の担当者が登場する。特に城崎温泉でしか買えない、いわば地産地消の自費出版本を町おこしに繋げていった実例は、本というモノと温泉旅行というコトがうまく噛み合った素晴らしい実例だと思う。もちろんそこに至るまでには紆余曲折があり、核となるNPO法人がうまく地元の人々を巻き込んでいったからこそ成し得た結果である。このやり方が万能薬とはならないかもしれないが、何をどのように差し出すかを考える上で参考になった。 「差し出し方」とじっくり向き合う著者の思考は、本にまつわる流通・小売業界だけではなくメディア論や教育論にも応用できるものだと感じた。 本書を読んだ後は、ひとまず「感想の差し出し方」から考えてみようと思った。