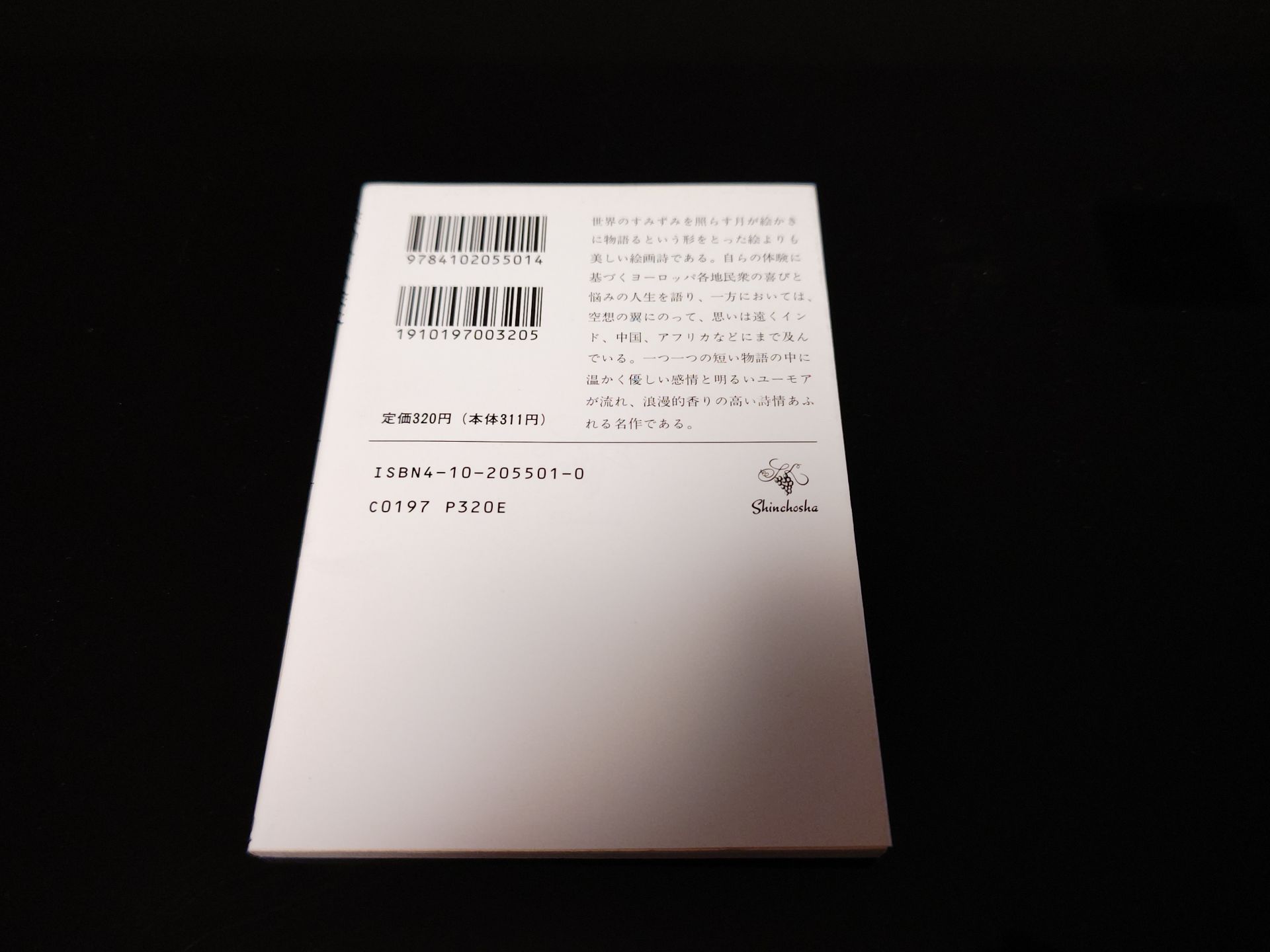絵のない絵本

絵のない絵本
アンデルセン
ハンス・クリスチャン・アンデルセン
Hans Christian Andersen
矢崎源九郎
新潮社
1983年10月1日
17件の記録
 松本真波@_mm1771772025年7月19日読み終わった読書日記@ 自宅いいなあ。きっと翻訳者によって多少文章の雰囲気は変わるのであろうけど、アンデルセンの人間世界に対する温かな眼差しを感じる一冊だった。 月から世界を見下ろした時、人間の行いには儚く美しい一面もあれば、醜く愚かな一面もあるだろう。だがそれでも「世界」は美しいのである。そして今日まで続く生命の営みの中で、我々人間たちも一生懸命に生きている。その事実を、月を通じてアンデルセンは愛を持って語ってくれている。 一つ一つのお話を、もっと深く味わって読み返したいと思う。初見でさらっと流し読みしてしまったお話にも必ずアンデルセンの込めた思いがあるはずだから。
松本真波@_mm1771772025年7月19日読み終わった読書日記@ 自宅いいなあ。きっと翻訳者によって多少文章の雰囲気は変わるのであろうけど、アンデルセンの人間世界に対する温かな眼差しを感じる一冊だった。 月から世界を見下ろした時、人間の行いには儚く美しい一面もあれば、醜く愚かな一面もあるだろう。だがそれでも「世界」は美しいのである。そして今日まで続く生命の営みの中で、我々人間たちも一生懸命に生きている。その事実を、月を通じてアンデルセンは愛を持って語ってくれている。 一つ一つのお話を、もっと深く味わって読み返したいと思う。初見でさらっと流し読みしてしまったお話にも必ずアンデルセンの込めた思いがあるはずだから。
 松本真波@_mm1771772025年7月6日読書メモ朗読某ワークショップ3日目。 今日扱ったのは「第十六夜」、プルチネッラ(道化師)のお話。今回もこれまで同様、作品のイメージをいくつか絵に描いてから臨んだのだが、求められたのは演出的な視点。 喜劇も、悲劇も、登場人物達は必死に生きている。だから観客は感動する。今回のプルチネッラは悲劇のお話。それをどのように演出するかの考え方を教わった。 そして最後、この作品で忘れてはならないのは「月が貧乏な絵描きに話を語っている」という点。ただ読むのではなく、この事実をそのように聴き手に伝えなくてはならない。それをどう表現するかが非常に難しかった。でも、段階的に自身の読みが変化していくのはとても面白かった。 そしてなにより、今まで自分が習ってきた朗読の先生と言っている事とあまり違わなかったのが良かった。むしろ、その考えを深める事ができた。その結果、アンデルセンの作品に深く感動する事ができたし、『絵のない絵本』が大好きになった。 この3日間のWSで得られたのは朗読の技術云々ではなく、【テキストに感動する心】かもしれない。改めて、アンデルセンの作品は優れたものであると実感した。 (余談。WSの指導者曰く、演出家の蜷川幸雄さんはきちんと作品解釈が出来ていない役者に対して「この不感症!!!!(心が動いていない)」と激怒していたそうです)
松本真波@_mm1771772025年7月6日読書メモ朗読某ワークショップ3日目。 今日扱ったのは「第十六夜」、プルチネッラ(道化師)のお話。今回もこれまで同様、作品のイメージをいくつか絵に描いてから臨んだのだが、求められたのは演出的な視点。 喜劇も、悲劇も、登場人物達は必死に生きている。だから観客は感動する。今回のプルチネッラは悲劇のお話。それをどのように演出するかの考え方を教わった。 そして最後、この作品で忘れてはならないのは「月が貧乏な絵描きに話を語っている」という点。ただ読むのではなく、この事実をそのように聴き手に伝えなくてはならない。それをどう表現するかが非常に難しかった。でも、段階的に自身の読みが変化していくのはとても面白かった。 そしてなにより、今まで自分が習ってきた朗読の先生と言っている事とあまり違わなかったのが良かった。むしろ、その考えを深める事ができた。その結果、アンデルセンの作品に深く感動する事ができたし、『絵のない絵本』が大好きになった。 この3日間のWSで得られたのは朗読の技術云々ではなく、【テキストに感動する心】かもしれない。改めて、アンデルセンの作品は優れたものであると実感した。 (余談。WSの指導者曰く、演出家の蜷川幸雄さんはきちんと作品解釈が出来ていない役者に対して「この不感症!!!!(心が動いていない)」と激怒していたそうです) RIYO BOOKS@riyo_books2025年7月5日読み終わったヒバリが歌いながら野から舞いあがって、棺の上のほうで朝の歌をさえずりました。それから、棺の上にとまって、くちばしでむしろをつつきました。そのようすは、まるでさなぎを裂きやぶろうとでもしているようでした。それからヒバリは、ふたたび歌いながら、大空に舞い上がりました。そしてわたしは赤い朝雲のうしろに引きさがったのです
RIYO BOOKS@riyo_books2025年7月5日読み終わったヒバリが歌いながら野から舞いあがって、棺の上のほうで朝の歌をさえずりました。それから、棺の上にとまって、くちばしでむしろをつつきました。そのようすは、まるでさなぎを裂きやぶろうとでもしているようでした。それからヒバリは、ふたたび歌いながら、大空に舞い上がりました。そしてわたしは赤い朝雲のうしろに引きさがったのです
 松本真波@_mm1771772025年7月3日読書メモ朗読某ワークショップ2日目。 今日は「第二十八夜」を扱った。非常に有名なお話で、この短いお話だけで一曲書いたクラシック作曲家もいるのだとか。(後で調べて探そう) 今回は事前に絵コンテを書いて臨んだ。だが、最初のひと段落の意味については全く考えていなかった。一見すると本題とはまったく関係のないような情景描写なのだが、どうしてアンデルセンはこれを描いたのか。改めて考察するとアンデルセンが世界を、尊い命の営みを愛していることがうかがえる。 普段は「文章を如何に聴き手に伝えるか」ばかり考えてしまうのだが、まずはこうして物語の世界に、作者の愛する世界に自身が入り込んでいく事の重要性をすごく感じた。 さらに、自分の声を全く聞かずに、作品の映像(イメージ)を想像するのに集中して、自身の心の動きを頼りにして読む練習は今までに無い体験だった。これは特に今後も続けて取り組みたい練習だった。
松本真波@_mm1771772025年7月3日読書メモ朗読某ワークショップ2日目。 今日は「第二十八夜」を扱った。非常に有名なお話で、この短いお話だけで一曲書いたクラシック作曲家もいるのだとか。(後で調べて探そう) 今回は事前に絵コンテを書いて臨んだ。だが、最初のひと段落の意味については全く考えていなかった。一見すると本題とはまったく関係のないような情景描写なのだが、どうしてアンデルセンはこれを描いたのか。改めて考察するとアンデルセンが世界を、尊い命の営みを愛していることがうかがえる。 普段は「文章を如何に聴き手に伝えるか」ばかり考えてしまうのだが、まずはこうして物語の世界に、作者の愛する世界に自身が入り込んでいく事の重要性をすごく感じた。 さらに、自分の声を全く聞かずに、作品の映像(イメージ)を想像するのに集中して、自身の心の動きを頼りにして読む練習は今までに無い体験だった。これは特に今後も続けて取り組みたい練習だった。 松本真波@_mm1771772025年7月2日読書メモ朗読某ワークショップ1日目。 今回は「第二十六夜」を扱った。日本では『絵のない絵本』だが、英語では『Moon Saw』(=月は見た)らしい。月が貧しい絵描きに毎晩短いお話を語るという作品。 恥ずかしながら、私はこの作品を知らなかった。だが一読しただけで心を奪われた。文章だけで月の語る情景が見ててくる、まさしく絵のない絵本であった。そして何より、文章から作者アンデルセンの優しさが溢れているのを感じた。 WSでは、自分で絵コンテを書いてカメラマンのように作品の映像を脳内で組み立てていった。カットやアングルを変化させると、こうも音色が変わるものかと驚いた。
松本真波@_mm1771772025年7月2日読書メモ朗読某ワークショップ1日目。 今回は「第二十六夜」を扱った。日本では『絵のない絵本』だが、英語では『Moon Saw』(=月は見た)らしい。月が貧しい絵描きに毎晩短いお話を語るという作品。 恥ずかしながら、私はこの作品を知らなかった。だが一読しただけで心を奪われた。文章だけで月の語る情景が見ててくる、まさしく絵のない絵本であった。そして何より、文章から作者アンデルセンの優しさが溢れているのを感じた。 WSでは、自分で絵コンテを書いてカメラマンのように作品の映像を脳内で組み立てていった。カットやアングルを変化させると、こうも音色が変わるものかと驚いた。 しまりす@alice_soror2025年6月11日読み終わった貧しい絵かきが孤独に所在なく絵を描きあぐねていたところ、いつもと変わらず空にある月があらわれ、雲がはいりこんでこない限り、毎晩絵かきに話をしてくれると言う。 話したことを絵にかけば良いと。「千一夜物語」を絵であらわすことができるかもしれない。 その月が語る美しい絵画のような物語を三十一夜分並べた短編集。 月が空に輝く間、見守ってきた人々の生活や人生。月が気にかける人間は「わたしの娘」、「わたしの老嬢」と愛おしげに語る。そして親愛のキスをする。 月の光は空気の澄んでいる度合いや物理的な距離にもよるが、いつも同じように控えめに見守るように優しい光で地上を照らす。 嬉しくても悲しくても寂しくても同じようにそこにある月の視点で夜の帷の中の人間の有り様を優しく見守り慈しむ物語は、短くともそれぞれが誰かを癒し清める力を持っていると思える。 月という、時代を超え夜を上から見渡せる超越する存在によって、整合性は保った上で時間的空間的制約がなくなり、あらゆる立場の人間の他の誰にも目撃されず掬い取り得ないエピソードを愛でるよう紡ぐ。 それは、自分の掴み得ぬほど遠くにいるかもしれない、世界のどこか誰かの小さな物語だ。そういうものを想像する視点を持つことで、狭い世界で近視眼的になった独善性に溺れず心を思いやりで満たす尊さを、今も尚我々に優しく説き続けている。
しまりす@alice_soror2025年6月11日読み終わった貧しい絵かきが孤独に所在なく絵を描きあぐねていたところ、いつもと変わらず空にある月があらわれ、雲がはいりこんでこない限り、毎晩絵かきに話をしてくれると言う。 話したことを絵にかけば良いと。「千一夜物語」を絵であらわすことができるかもしれない。 その月が語る美しい絵画のような物語を三十一夜分並べた短編集。 月が空に輝く間、見守ってきた人々の生活や人生。月が気にかける人間は「わたしの娘」、「わたしの老嬢」と愛おしげに語る。そして親愛のキスをする。 月の光は空気の澄んでいる度合いや物理的な距離にもよるが、いつも同じように控えめに見守るように優しい光で地上を照らす。 嬉しくても悲しくても寂しくても同じようにそこにある月の視点で夜の帷の中の人間の有り様を優しく見守り慈しむ物語は、短くともそれぞれが誰かを癒し清める力を持っていると思える。 月という、時代を超え夜を上から見渡せる超越する存在によって、整合性は保った上で時間的空間的制約がなくなり、あらゆる立場の人間の他の誰にも目撃されず掬い取り得ないエピソードを愛でるよう紡ぐ。 それは、自分の掴み得ぬほど遠くにいるかもしれない、世界のどこか誰かの小さな物語だ。そういうものを想像する視点を持つことで、狭い世界で近視眼的になった独善性に溺れず心を思いやりで満たす尊さを、今も尚我々に優しく説き続けている。