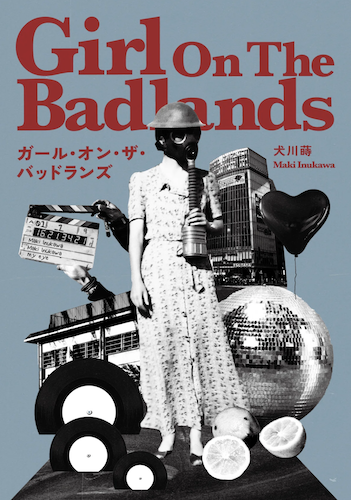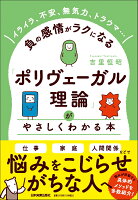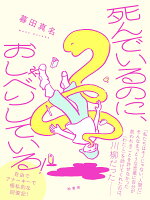ふじこ
@245pro
のろのろ読書
- 2026年2月24日
- 2026年2月19日
 ぼくらのSEX橋本治読み終わった橋本治さんによるまじめな性教育の本。初めてセックスをしてから20年以上経ってしまったが、初めてこんなにセックスとは何か、ということにとことん向き合った気がする。他人と関わった時点でセックスはすでに始まっている。誰かとセックスをしたいと思うのは自然なことだけど、信頼できる人なのかどうか自分で判断すること。私たちがつい忘れてしまいがちなことを、橋本さんはいちから丁寧に説明してくれる。二村ヒトシさんのあとがきも含めて、特に10代の若者に読んでもらいたい名著。
ぼくらのSEX橋本治読み終わった橋本治さんによるまじめな性教育の本。初めてセックスをしてから20年以上経ってしまったが、初めてこんなにセックスとは何か、ということにとことん向き合った気がする。他人と関わった時点でセックスはすでに始まっている。誰かとセックスをしたいと思うのは自然なことだけど、信頼できる人なのかどうか自分で判断すること。私たちがつい忘れてしまいがちなことを、橋本さんはいちから丁寧に説明してくれる。二村ヒトシさんのあとがきも含めて、特に10代の若者に読んでもらいたい名著。 - 2026年2月10日
 西村賢太殺人事件小林麻衣子読み終わった「自分の人生に責任、持てよ」故・西村賢太の元恋人である著者が書いた芥川賞作家との日々。不器用で、潔癖で、破滅型の私小説を書き続けた西村賢太という人に初めてちゃんと会えたような気がした。恰幅がよく、タバコを吸い、同じ作風の文章を延々と書き続ける無頼派というイメージだったが、実際はもっとお茶目で気の小さい人だったんだなあと感じた。恋人同士の微笑ましい話から一転、本書は10章で急に奇書へと変貌する。これまでにない、唯一無二の読書体験だった。
西村賢太殺人事件小林麻衣子読み終わった「自分の人生に責任、持てよ」故・西村賢太の元恋人である著者が書いた芥川賞作家との日々。不器用で、潔癖で、破滅型の私小説を書き続けた西村賢太という人に初めてちゃんと会えたような気がした。恰幅がよく、タバコを吸い、同じ作風の文章を延々と書き続ける無頼派というイメージだったが、実際はもっとお茶目で気の小さい人だったんだなあと感じた。恋人同士の微笑ましい話から一転、本書は10章で急に奇書へと変貌する。これまでにない、唯一無二の読書体験だった。 - 2026年1月29日
 女と男の品格。伊集院静読み終わった今更ながら伊集院さんのお悩み相談を読んでみたら、めちゃくちゃ面白かった。同時に、伊集院さんが女性にモテる理由がわかった気がした。男性には厳しく、女性には少し優しい。ダンディでチャーミング。女性に対して常に尊敬の気持ちがある人が、女性にモテるのだ。多少時代遅れな回答もいくつかあるけれど、それでも時を超えて通じる伊集院イズムが確かにある。読み終えたあと、しゃんと背筋が伸びた感じがした。伊集院さんが言ういい女に、私もなりたい。
女と男の品格。伊集院静読み終わった今更ながら伊集院さんのお悩み相談を読んでみたら、めちゃくちゃ面白かった。同時に、伊集院さんが女性にモテる理由がわかった気がした。男性には厳しく、女性には少し優しい。ダンディでチャーミング。女性に対して常に尊敬の気持ちがある人が、女性にモテるのだ。多少時代遅れな回答もいくつかあるけれど、それでも時を超えて通じる伊集院イズムが確かにある。読み終えたあと、しゃんと背筋が伸びた感じがした。伊集院さんが言ういい女に、私もなりたい。 - 2026年1月26日
- 2026年1月22日
 月 (角川文庫)辺見庸読み終わった実際にあった障害者施設殺傷事件をモデルに書かれた小説。寝たきりのきーちゃんと、施設職員のさとくん。自分以外の誰かの思考がそのまま頭になだれ込んでくるような構成に、吐き気を催しながら読み終えた。私はきーちゃん?私はさとくん?自他境界線が曖昧になっていき、さとくんのすることがだんだんと正しいことのように思えてくる。「あなた、こころ、ありますか?」こころのない生き物は人間ではないのだろうか。さとくんの問いが私にも突き刺さってくる。私も、結局綺麗事を並べたいだけの化け物なのかもしれない。
月 (角川文庫)辺見庸読み終わった実際にあった障害者施設殺傷事件をモデルに書かれた小説。寝たきりのきーちゃんと、施設職員のさとくん。自分以外の誰かの思考がそのまま頭になだれ込んでくるような構成に、吐き気を催しながら読み終えた。私はきーちゃん?私はさとくん?自他境界線が曖昧になっていき、さとくんのすることがだんだんと正しいことのように思えてくる。「あなた、こころ、ありますか?」こころのない生き物は人間ではないのだろうか。さとくんの問いが私にも突き刺さってくる。私も、結局綺麗事を並べたいだけの化け物なのかもしれない。 - 2026年1月21日
- 2026年1月20日
 迷ったら笑っといてください濱田祐太郎読み終わった面白かった!!盲目のR-1王者・濱田祐太郎くんのエッセイ集。濵田くんのワードセンスに今更ながら一目惚れしてしまい、あっという間に読み終えた。目が見えている人よりも本質が見えている彼の言葉はひとつひとつが綺麗に磨がれたナイフのように鋭い。小学生のときに目が完全に見えなくなり、音と記憶と親御さんの音読のみでポケモンやドラクエモンスターズをプレイしていた適応性の化け物。濱田くんがもっともっとメディアに出ることで、障がい者のイメージが大きく変わる予感がした。次回は下ネタマシマシでお願いします!
迷ったら笑っといてください濱田祐太郎読み終わった面白かった!!盲目のR-1王者・濱田祐太郎くんのエッセイ集。濵田くんのワードセンスに今更ながら一目惚れしてしまい、あっという間に読み終えた。目が見えている人よりも本質が見えている彼の言葉はひとつひとつが綺麗に磨がれたナイフのように鋭い。小学生のときに目が完全に見えなくなり、音と記憶と親御さんの音読のみでポケモンやドラクエモンスターズをプレイしていた適応性の化け物。濱田くんがもっともっとメディアに出ることで、障がい者のイメージが大きく変わる予感がした。次回は下ネタマシマシでお願いします! - 2026年1月16日
- 2026年1月13日
- 2025年12月26日
 今日も演じてます月と文社読み終わった市井の人たち8人にインタビューした演じている日常の話。人は多かれ少なかれ「演じる」ことで生活を回している。全ての人に素を曝け出すのは危険だし、摩擦を生むから演じてそれを回避する。ただ、演じることで生じる悩みや苦しみもある。演じることとありのままでいることの板挟みになりながら、私たちは今日も生きる。いずれも極めて個人的な話でありながら、そこには演じてきた人がみんな持つ感覚が共有されている。ほんとうの私を出したり隠したりしながら、私は今日も生きている。
今日も演じてます月と文社読み終わった市井の人たち8人にインタビューした演じている日常の話。人は多かれ少なかれ「演じる」ことで生活を回している。全ての人に素を曝け出すのは危険だし、摩擦を生むから演じてそれを回避する。ただ、演じることで生じる悩みや苦しみもある。演じることとありのままでいることの板挟みになりながら、私たちは今日も生きる。いずれも極めて個人的な話でありながら、そこには演じてきた人がみんな持つ感覚が共有されている。ほんとうの私を出したり隠したりしながら、私は今日も生きている。 - 2025年12月17日
 あのときマカロンさえ買わなければカツセマサヒコ,カツセ・マサヒコ読み終わった書き留めておかないと日々に流されて消えてしまうような、感情の断片たち。タイトルの切実さとそこまで気にしていない周囲との温度差がなんだか可笑しい。他の人は忘れてしまっても、カツセさんだけは覚えていてくれる。その安心感があるから彼の周りには人が集まるんだろう。マカロンに始まりマカロンで終わる。カツセさんともっとおしゃべりしたい余韻を残して読み終えた。不器用な人は、かわいくてやさしい。そんな人とのおしゃべりは、とても楽しい。
あのときマカロンさえ買わなければカツセマサヒコ,カツセ・マサヒコ読み終わった書き留めておかないと日々に流されて消えてしまうような、感情の断片たち。タイトルの切実さとそこまで気にしていない周囲との温度差がなんだか可笑しい。他の人は忘れてしまっても、カツセさんだけは覚えていてくれる。その安心感があるから彼の周りには人が集まるんだろう。マカロンに始まりマカロンで終わる。カツセさんともっとおしゃべりしたい余韻を残して読み終えた。不器用な人は、かわいくてやさしい。そんな人とのおしゃべりは、とても楽しい。 - 2025年11月8日
 虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった虚弱による虚弱のための虚弱のエッセイ。身体にさまざまな不調がある、体力がない、活動時間が短い。それらを包括して「虚弱」と表現し、対談及びエッセイがバズった終電さんの言葉はどれもこれもビシビシと突き刺さってくる。私が好きなことをできるのも全ては健康の上に成り立っている。ここまで慢性的に身体のどこかに不調があると「幸せって、健康のことだったんだ」という境地にたどり着くのもむべなるかなと感じる。他者と比較するのではなく、自分の身体と向き合って生きていくことの大切さを再確認できた一冊だった。
虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わった虚弱による虚弱のための虚弱のエッセイ。身体にさまざまな不調がある、体力がない、活動時間が短い。それらを包括して「虚弱」と表現し、対談及びエッセイがバズった終電さんの言葉はどれもこれもビシビシと突き刺さってくる。私が好きなことをできるのも全ては健康の上に成り立っている。ここまで慢性的に身体のどこかに不調があると「幸せって、健康のことだったんだ」という境地にたどり着くのもむべなるかなと感じる。他者と比較するのではなく、自分の身体と向き合って生きていくことの大切さを再確認できた一冊だった。 - 2025年11月5日
 〆切は破り方が9割カレー沢薫読み終わった〈本書に載っている原稿の9割は催促を受けて書き始めた。〉私の場合〆切に追われると大抵微妙なものしか生まれないのだが、メシアは今作もキレキレ。漫画家としての終わりを思わぬ形で告げられたメールCC誤爆事件、さくらももこに憧れて奇行に走った話、エーミールニキみたいにリスペクトできる担当がいないことへの憂いなど、担当さんは寧ろいい原稿を書けるようにわざとギリギリにしか催促しないのではないかと思えてくる。私もカレー沢さんを見習って、会社員の才能がない、今すぐに5億円が欲しいと堂々とアピールしていきたい。
〆切は破り方が9割カレー沢薫読み終わった〈本書に載っている原稿の9割は催促を受けて書き始めた。〉私の場合〆切に追われると大抵微妙なものしか生まれないのだが、メシアは今作もキレキレ。漫画家としての終わりを思わぬ形で告げられたメールCC誤爆事件、さくらももこに憧れて奇行に走った話、エーミールニキみたいにリスペクトできる担当がいないことへの憂いなど、担当さんは寧ろいい原稿を書けるようにわざとギリギリにしか催促しないのではないかと思えてくる。私もカレー沢さんを見習って、会社員の才能がない、今すぐに5億円が欲しいと堂々とアピールしていきたい。 - 2025年10月28日
 生きる言葉(新潮新書)俵万智読み終わった『サラダ記念日』がベストセラーになったのが38年前。とにかく俵万智の凄さが1000円ちょっとの新書にギュッと凝縮されている。特に息子さんとのやり取りが可愛くて微笑ましい。子どもってポロッと芯を食ったことを言ってくるから、話していて飽きることがない。文章の間に挟まる短歌がピリリと山椒のようにあとからじわじわと効いてくる。私たちは、言葉で自由にも不自由にもなれる。言葉で全てを伝え切ることはできないけれど、だからこそ言葉を諦めたくない。言葉とともに生きていきたい、と改めて思えた読書体験だった。
生きる言葉(新潮新書)俵万智読み終わった『サラダ記念日』がベストセラーになったのが38年前。とにかく俵万智の凄さが1000円ちょっとの新書にギュッと凝縮されている。特に息子さんとのやり取りが可愛くて微笑ましい。子どもってポロッと芯を食ったことを言ってくるから、話していて飽きることがない。文章の間に挟まる短歌がピリリと山椒のようにあとからじわじわと効いてくる。私たちは、言葉で自由にも不自由にもなれる。言葉で全てを伝え切ることはできないけれど、だからこそ言葉を諦めたくない。言葉とともに生きていきたい、と改めて思えた読書体験だった。 - 2025年10月25日
 きみは赤ちゃん (文春文庫)川上未映子読み終わったエコー写真の点から、赤ちゃんが産まれて一歳になるまで。お母さんって、本当にすごい。人ってこうやってお母さんになっていくんだ、という軌跡をひとつずつ丁寧に読んだ。我が子が愛しくて可愛くて、この子とあと50年くらいしか一緒にいられないと実感して泣いたりする。赤ちゃんを産んだ女の人の思考って、こんなにぐるぐるしてんねや。そして親が何を考えているかなんて我関せず、子どもはすくすくと成長していく。親子3人仲良うやってや、と心から思わせてくれるエッセイだった。
きみは赤ちゃん (文春文庫)川上未映子読み終わったエコー写真の点から、赤ちゃんが産まれて一歳になるまで。お母さんって、本当にすごい。人ってこうやってお母さんになっていくんだ、という軌跡をひとつずつ丁寧に読んだ。我が子が愛しくて可愛くて、この子とあと50年くらいしか一緒にいられないと実感して泣いたりする。赤ちゃんを産んだ女の人の思考って、こんなにぐるぐるしてんねや。そして親が何を考えているかなんて我関せず、子どもはすくすくと成長していく。親子3人仲良うやってや、と心から思わせてくれるエッセイだった。 - 2025年10月9日
- 2025年10月7日
 女王様の電話番渡辺優読み終わったとある理由から不動産会社を退職した主人公は、メンズマッサージ店・ファムファタルで電話番の仕事を始める。推しの女王様・美織さんと食事の約束をするがドタキャンされ、彼女はそのまま行方不明になってしまう。めちゃくちゃに面白くて一気読み。愛とは?セックスとは?美織さんを探すという行為そのものが、アセクシャルである自分自身との対話になっていく。何気ない会話の一つひとつが本質をぐさぐさと突いてきて、問いがぐるぐると回り続ける。私もスーパーセックスワールドを思い切り謳歌して生きていきたい。
女王様の電話番渡辺優読み終わったとある理由から不動産会社を退職した主人公は、メンズマッサージ店・ファムファタルで電話番の仕事を始める。推しの女王様・美織さんと食事の約束をするがドタキャンされ、彼女はそのまま行方不明になってしまう。めちゃくちゃに面白くて一気読み。愛とは?セックスとは?美織さんを探すという行為そのものが、アセクシャルである自分自身との対話になっていく。何気ない会話の一つひとつが本質をぐさぐさと突いてきて、問いがぐるぐると回り続ける。私もスーパーセックスワールドを思い切り謳歌して生きていきたい。 - 2025年9月25日
- 2025年9月25日
 アフターブルー朝宮夕読み終わった損傷の激しい遺体を専門に扱う納棺師たち。「だってみんな、自分の最期があんな姿になるなんて思ってないでしょ?」綺麗な状態で棺に収まるのは、決して当たり前ではない。自分の心の喪失と向き合いながら、ご遺体を修復していく。触った頬が冷たい描写に、心がざわざわと落ち着かなくなる。大切な人との別れは、ある日突然訪れるかもしれない。ならばせめて、お別れを言えるように心を尽くす。これからも生きていかなければならない人たちに寄り添い、そっと手を差し伸べる。悲しくてやさしい余韻に、心がぎゅっと掴まれる。
アフターブルー朝宮夕読み終わった損傷の激しい遺体を専門に扱う納棺師たち。「だってみんな、自分の最期があんな姿になるなんて思ってないでしょ?」綺麗な状態で棺に収まるのは、決して当たり前ではない。自分の心の喪失と向き合いながら、ご遺体を修復していく。触った頬が冷たい描写に、心がざわざわと落ち着かなくなる。大切な人との別れは、ある日突然訪れるかもしれない。ならばせめて、お別れを言えるように心を尽くす。これからも生きていかなければならない人たちに寄り添い、そっと手を差し伸べる。悲しくてやさしい余韻に、心がぎゅっと掴まれる。
読み込み中...