

べりん
@ngske94
月3冊を目標に読んでいます。
- 2026年2月22日
- 2026年2月8日
- 2026年2月8日
 フキサチーフ松下洸平読み終わったエバーフレッシュの話が1番印象的。 植物を当たり前のように生き物として扱う彼に、持ち前の優しさを感じた。 また舞台の座組で空気感を大切にしてるのも彼の印象通りでほっこりした。
フキサチーフ松下洸平読み終わったエバーフレッシュの話が1番印象的。 植物を当たり前のように生き物として扱う彼に、持ち前の優しさを感じた。 また舞台の座組で空気感を大切にしてるのも彼の印象通りでほっこりした。 - 2025年12月10日
 しばらくあかちゃんになりますのでヨシタケ・シンスケ読み終わった衝撃の絵本でした。建前の解放が生み出す混沌とシュール。 親子で読むとケラケラ笑いながら読めるかもしれません。 でも…でも… どうしても私には、パパの場面はメタファーにしか感じられませんでした。笑 心が薄汚れてしまっていますね。
しばらくあかちゃんになりますのでヨシタケ・シンスケ読み終わった衝撃の絵本でした。建前の解放が生み出す混沌とシュール。 親子で読むとケラケラ笑いながら読めるかもしれません。 でも…でも… どうしても私には、パパの場面はメタファーにしか感じられませんでした。笑 心が薄汚れてしまっていますね。 - 2025年12月1日
 エロってなんだろう?山本直樹読み終わった漫画家・山本直樹さんがエロについて考えている本です。 本書の中で、エロが文化として残るために教育や対話などコミュニケーションの重要性が何度も指摘されています。私もそれに賛同しますし、紛れもない事実だと思っています。 そんな本のラストが蛙亭・イワクラさんとの対談というまさに"コミュニケーション"で締められているのは、誠実な構成だなあと思いました。 私も私なりのエロが何なのか、考えてみます。
エロってなんだろう?山本直樹読み終わった漫画家・山本直樹さんがエロについて考えている本です。 本書の中で、エロが文化として残るために教育や対話などコミュニケーションの重要性が何度も指摘されています。私もそれに賛同しますし、紛れもない事実だと思っています。 そんな本のラストが蛙亭・イワクラさんとの対談というまさに"コミュニケーション"で締められているのは、誠実な構成だなあと思いました。 私も私なりのエロが何なのか、考えてみます。 - 2025年11月27日
 ええかげん論中島岳志,土井善晴読み終わったこの本で言うええかげんとは、「ちょうどよい」ことです。 決して「手を抜く」などといった意味ではありません。 私はこの本で、保守の考え方を改めました。 元々は「革新的な考え方を否定し、古来の考え方を絶対視すること」というイメージを持っていました。 しかしそうではなく、「基本的で普遍的な考え方を尊重しつつ、その時々で臨機応変にアップデートすること」と理解しました。 だから、何事も基本を押さえることは大切です。 その基本に、自分の経験則からアレンジを加えることがオリジナルであり、クリエイティブなのだと思います。 ハイキューの影山の成長、他にはファッションでおしゃれになることにも通ずる考え方だなと思いました。
ええかげん論中島岳志,土井善晴読み終わったこの本で言うええかげんとは、「ちょうどよい」ことです。 決して「手を抜く」などといった意味ではありません。 私はこの本で、保守の考え方を改めました。 元々は「革新的な考え方を否定し、古来の考え方を絶対視すること」というイメージを持っていました。 しかしそうではなく、「基本的で普遍的な考え方を尊重しつつ、その時々で臨機応変にアップデートすること」と理解しました。 だから、何事も基本を押さえることは大切です。 その基本に、自分の経験則からアレンジを加えることがオリジナルであり、クリエイティブなのだと思います。 ハイキューの影山の成長、他にはファッションでおしゃれになることにも通ずる考え方だなと思いました。 - 2025年11月27日
- 2025年10月4日
- 2025年9月20日
 君のクイズ小川哲読み終わった久々に手に取った小説でした。 生放送のクイズ大会決勝で対戦相手がまさかの問題文読み上げ直前に解答、それが正解で優勝を攫われる… なぜそんなことができたのかを突き止めていく物語です。 自分は1人の視聴者としてクイズ番組を見ているので、クイズプレイヤーがどんな思考で臨んでいるのかをほんの少しでも体験できた気分になりました。 (まさか問題文の読み手の口の形までヒントにしてるなんて…苦笑) そしてオチはまさかの展開。 頭の良い人に大いに手のひらで転がされた気持ちです!!笑 最近の読書ではビジネス書や啓発書を読むことが多かったです。 久しぶりの小説は、作中の世界に吸い込まれることで自分のものとは違う人生を疑似体験できて面白かったです!
君のクイズ小川哲読み終わった久々に手に取った小説でした。 生放送のクイズ大会決勝で対戦相手がまさかの問題文読み上げ直前に解答、それが正解で優勝を攫われる… なぜそんなことができたのかを突き止めていく物語です。 自分は1人の視聴者としてクイズ番組を見ているので、クイズプレイヤーがどんな思考で臨んでいるのかをほんの少しでも体験できた気分になりました。 (まさか問題文の読み手の口の形までヒントにしてるなんて…苦笑) そしてオチはまさかの展開。 頭の良い人に大いに手のひらで転がされた気持ちです!!笑 最近の読書ではビジネス書や啓発書を読むことが多かったです。 久しぶりの小説は、作中の世界に吸い込まれることで自分のものとは違う人生を疑似体験できて面白かったです! - 2025年9月16日
 葉桜の季節に君を想うということ歌野晶午気になる
葉桜の季節に君を想うということ歌野晶午気になる - 2025年9月14日
 世界は行動経済学でできている橋本之克気になる
世界は行動経済学でできている橋本之克気になる - 2025年9月14日
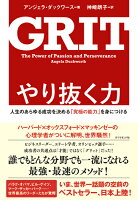 やり抜く力アンジェラ・ダックワース,神崎朗子読み終わったハイキューのメッセージそのもののような1冊です。 日向、及川、北、佐久早を思い出しながら読みました。 才能より重要なものがあるということを、証拠と共に示されていることは希望であり、同時に厳しさでもあると思いました。 努力して成長する。 当たり前のことですが、それが何かを成し遂げるための道筋なんです。
やり抜く力アンジェラ・ダックワース,神崎朗子読み終わったハイキューのメッセージそのもののような1冊です。 日向、及川、北、佐久早を思い出しながら読みました。 才能より重要なものがあるということを、証拠と共に示されていることは希望であり、同時に厳しさでもあると思いました。 努力して成長する。 当たり前のことですが、それが何かを成し遂げるための道筋なんです。 - 2025年9月11日
- 2025年8月26日
- 2025年8月26日
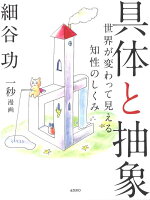 具体と抽象細谷功読みたい
具体と抽象細谷功読みたい - 2025年8月26日
 忍者の技術 解剖図鑑習志野青龍窟気になる
忍者の技術 解剖図鑑習志野青龍窟気になる - 2025年8月26日
 正欲朝井リョウ気になる
正欲朝井リョウ気になる - 2025年8月25日
 青木世界観 (文春e-book)尾崎世界観,青木宣親買った
青木世界観 (文春e-book)尾崎世界観,青木宣親買った - 2025年8月25日
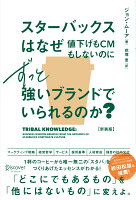 読み終わった読書習慣をつけたい!と思い、まずは自分にとって敷居が低い「好きなスタバがテーマの本を」と手に取りました。 商品、お客様、従業員それぞれに愚直なまでに熱心に向き合い、現状維持に抗いながら挑戦してきたことこそがスタバのブランドとして受け入れられたのだと学びました。 ビジネス書でありながら、私自身が日常生活でも使えそうな考え方も多く記されていたのがとても興味深いです。 特に従業員育成については、「従業員が働きたいと思える組織であれ」というベースのもと、待遇から育成まで充実しているとありました。 「上司は部下に奉仕し、惜しみないフォローをせよ」という理念は、昨今の高校野球の暴力問題もこの精神が根付いているときっと起こり得なかったのではないかなと思います。 結果を出すのは当然大切でありながら、その結果を出すには従業員にとって働きやすい環境でなければならないという考え方は、今後私が会社で立場が上がるときにも忘れずにいたいです。
読み終わった読書習慣をつけたい!と思い、まずは自分にとって敷居が低い「好きなスタバがテーマの本を」と手に取りました。 商品、お客様、従業員それぞれに愚直なまでに熱心に向き合い、現状維持に抗いながら挑戦してきたことこそがスタバのブランドとして受け入れられたのだと学びました。 ビジネス書でありながら、私自身が日常生活でも使えそうな考え方も多く記されていたのがとても興味深いです。 特に従業員育成については、「従業員が働きたいと思える組織であれ」というベースのもと、待遇から育成まで充実しているとありました。 「上司は部下に奉仕し、惜しみないフォローをせよ」という理念は、昨今の高校野球の暴力問題もこの精神が根付いているときっと起こり得なかったのではないかなと思います。 結果を出すのは当然大切でありながら、その結果を出すには従業員にとって働きやすい環境でなければならないという考え方は、今後私が会社で立場が上がるときにも忘れずにいたいです。 - 2025年8月25日
 文化系のための野球入門中野慧読み終わったもともと野球観戦が好き(競技経験はありません)、そして昨今の高校野球の暴力問題もある中、このタイトルの本には高校野球に根付く問題の整理がされているのではと期待し手に取りました。 特に印象的だったのは「学生野球のプロフェッショナル化」と「スポーツの意義」についてです。 「学生野球のプロフェッショナル化」は、野球部に所属する生徒が野球だけに特化して学生生活を送る状態です。その場合の多くは勝利・実力至上主義の世界観に支配されています。 スポーツなんだから勝ちを目指すのは自然なことではあるのですが、学生野球はあくまでアマチュアです。 アマチュアとは「競技の他に本分がある身分」のこと。 学生野球であれば学業、社会人野球であれば社業が本分です。アマチュアの選手は本分の傍ら、野球をプレーしているのです。 ところが、(特に強豪私学の)野球部ではアマチュアリズムが置き去りになり、有望な中学生を特待生や推薦で入学させ、学業成績や進学を優遇しながら、野球部の主力選手とする動きがよく見られます。 この本は、学生生活からアマチュアリズムがなくなり、プロフェッショナル化することに思いを巡らせるきっかけになりました。 「スポーツの意義」は、スポーツはそもそも健康のための体育をしながらゲーム性を楽しむものでないかという提言です。 この本によると野球はそもそも、明治時代の学生の運動不足解消のために広まったものとのことです。(それがなぜ国民的スポーツになったかの背景や歴史は、実際に読んでみてください) 現代では、健康のために運動が必要であることは様々な科学的知見から明らかです。 健康な身体つくりのために筋トレやストレッチをすることは良いのですが、そればかりだと運動が単調になりがちです。 そこで運動にゲーム性を持たせた、「スポーツ」を楽しもうという考えが、この本ではなされています。 先に書いた通り、野球部はプロフェッショナル化が強くなっている一方で、スポーツとしての野球はもっと気楽で敷居の低いものであっていいと提言されています。 これについては私も同意していて、何か高校野球を見ていて知らないうちに野球をプレーする敷居が高く感じていました。 ところが草野球でも壁当てでも、野球を楽しむことに何も敷居はないと思います。 野球の歴史を教養として知ることができ、また野球のあり方について考えを巡らせるきっかけとなる本でした。
文化系のための野球入門中野慧読み終わったもともと野球観戦が好き(競技経験はありません)、そして昨今の高校野球の暴力問題もある中、このタイトルの本には高校野球に根付く問題の整理がされているのではと期待し手に取りました。 特に印象的だったのは「学生野球のプロフェッショナル化」と「スポーツの意義」についてです。 「学生野球のプロフェッショナル化」は、野球部に所属する生徒が野球だけに特化して学生生活を送る状態です。その場合の多くは勝利・実力至上主義の世界観に支配されています。 スポーツなんだから勝ちを目指すのは自然なことではあるのですが、学生野球はあくまでアマチュアです。 アマチュアとは「競技の他に本分がある身分」のこと。 学生野球であれば学業、社会人野球であれば社業が本分です。アマチュアの選手は本分の傍ら、野球をプレーしているのです。 ところが、(特に強豪私学の)野球部ではアマチュアリズムが置き去りになり、有望な中学生を特待生や推薦で入学させ、学業成績や進学を優遇しながら、野球部の主力選手とする動きがよく見られます。 この本は、学生生活からアマチュアリズムがなくなり、プロフェッショナル化することに思いを巡らせるきっかけになりました。 「スポーツの意義」は、スポーツはそもそも健康のための体育をしながらゲーム性を楽しむものでないかという提言です。 この本によると野球はそもそも、明治時代の学生の運動不足解消のために広まったものとのことです。(それがなぜ国民的スポーツになったかの背景や歴史は、実際に読んでみてください) 現代では、健康のために運動が必要であることは様々な科学的知見から明らかです。 健康な身体つくりのために筋トレやストレッチをすることは良いのですが、そればかりだと運動が単調になりがちです。 そこで運動にゲーム性を持たせた、「スポーツ」を楽しもうという考えが、この本ではなされています。 先に書いた通り、野球部はプロフェッショナル化が強くなっている一方で、スポーツとしての野球はもっと気楽で敷居の低いものであっていいと提言されています。 これについては私も同意していて、何か高校野球を見ていて知らないうちに野球をプレーする敷居が高く感じていました。 ところが草野球でも壁当てでも、野球を楽しむことに何も敷居はないと思います。 野球の歴史を教養として知ることができ、また野球のあり方について考えを巡らせるきっかけとなる本でした。
読み込み中...





