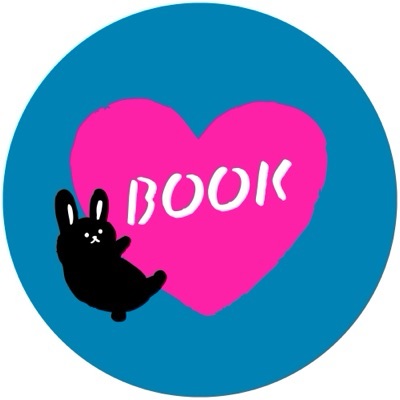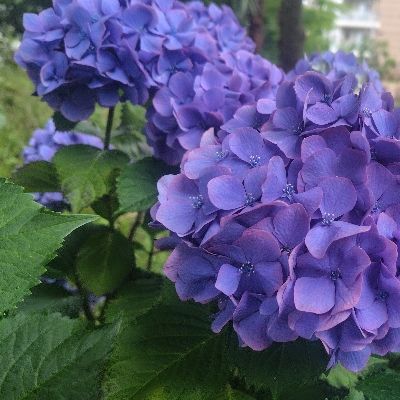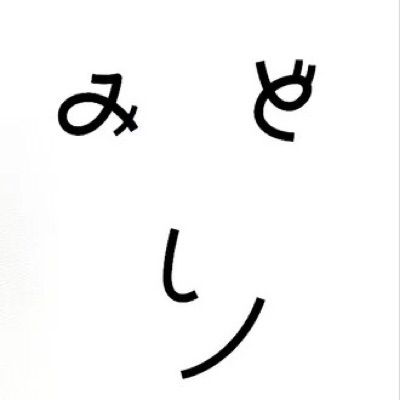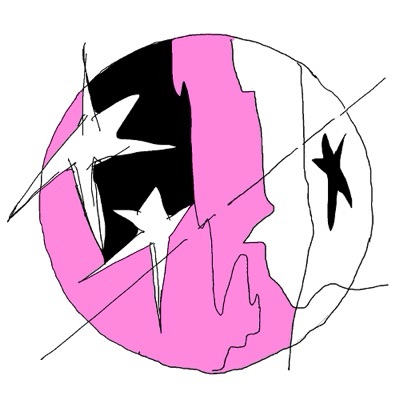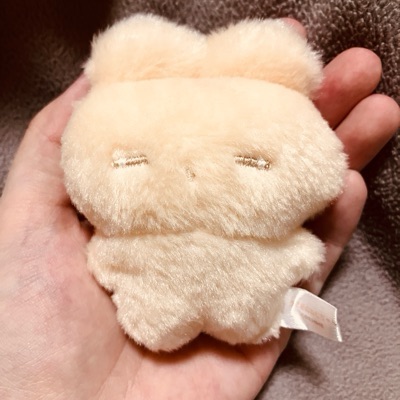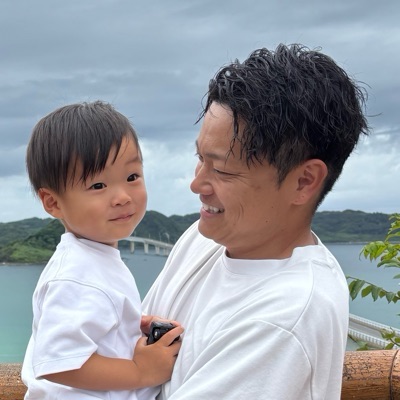自分のあたりまえを切り崩す文化人類学入門

139件の記録
- こうすけ@reads_kosuke2026年1月10日読み終わった2026年第二週 1/5 - 1/11 文化人類学入門 読みました。 少し難しい話でしたが、各章のとっかかりとまとめは分かりやすい言葉が使われていて理解できました。前提を問い直すきっかけをくれました。

 みみみ@kmkdnrd2026年1月3日読み終わった自分の当たり前は万人の当たり前ではないということを他者から学ぶというの、わかるんだけど難しいよなあ。この本を高校生のとき読んでいたら、なんとなく学部を選ぶのではなく、文化人類学は違う、という確固たる結論のもと、進路選択する上での選択肢を一つ減らせたと思う。結局わたしはフィールドワークで周りを見た事でしった「日本について」の部分にしか興味がないから日本史選んだんだろーなってしみじみしたよな。 しかしこれも「文化人類学とは?」を知ったからこそわかったことで、知ることは大切ですね、という話か。 民俗学、文化人類学と本を続けて読んだけど、圧倒的に民俗学が自分好みでした。これは本が面白いとか面白いとかではなく。
みみみ@kmkdnrd2026年1月3日読み終わった自分の当たり前は万人の当たり前ではないということを他者から学ぶというの、わかるんだけど難しいよなあ。この本を高校生のとき読んでいたら、なんとなく学部を選ぶのではなく、文化人類学は違う、という確固たる結論のもと、進路選択する上での選択肢を一つ減らせたと思う。結局わたしはフィールドワークで周りを見た事でしった「日本について」の部分にしか興味がないから日本史選んだんだろーなってしみじみしたよな。 しかしこれも「文化人類学とは?」を知ったからこそわかったことで、知ることは大切ですね、という話か。 民俗学、文化人類学と本を続けて読んだけど、圧倒的に民俗学が自分好みでした。これは本が面白いとか面白いとかではなく。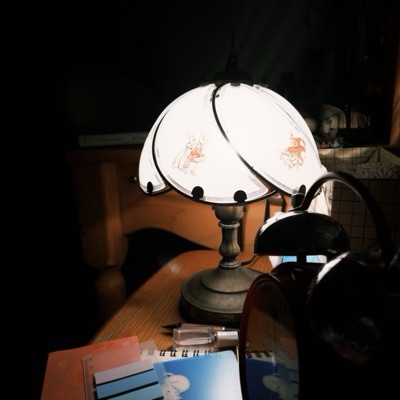
 かげ@Kage_03132025年12月31日読み終わったまた読みたい今年最後はこれ、あまりにも面白かったのでゆっくりじっくり読んだ本。文化人類学というものを今年知れて(世論の流れ的にも)ちょうど良かったなと思う。これからも大切な本になりそうな一冊。
かげ@Kage_03132025年12月31日読み終わったまた読みたい今年最後はこれ、あまりにも面白かったのでゆっくりじっくり読んだ本。文化人類学というものを今年知れて(世論の流れ的にも)ちょうど良かったなと思う。これからも大切な本になりそうな一冊。 もなか@monak2025年12月27日読み終わった各地域の文化や慣習をたくさん紹介してくれていて面白かった。 身近な文化と異なるものを"面白い、変"と片付けるのではなく、どういった背景でこうした文化ができたのかまで踏み込んで理解し比較することで、多様性を受け入れる度量が醸成されるのだと思う。 「民族の境界線は、…流動的で可変的」という文が印象に残った。
もなか@monak2025年12月27日読み終わった各地域の文化や慣習をたくさん紹介してくれていて面白かった。 身近な文化と異なるものを"面白い、変"と片付けるのではなく、どういった背景でこうした文化ができたのかまで踏み込んで理解し比較することで、多様性を受け入れる度量が醸成されるのだと思う。 「民族の境界線は、…流動的で可変的」という文が印象に残った。 ジア@sheletmego2025年12月23日読み終わった2025年に読んだ本のベスト候補かもしれない。文化人類学のことをあまりよく知らなかったのだが、大変面白かった。読みやすく知識がどんどんついていく感じがとても気持ちがいい。暮らしの中で生じる身近な問いがどういった背景からくるものなのかが詳しく書かれてあった。世の中にこんな面白い学問があるのだなと思っていたら、自分の好きな作家の上橋菜穂子さんが文化人類学を専攻していたことを知って驚きつつも納得した。
ジア@sheletmego2025年12月23日読み終わった2025年に読んだ本のベスト候補かもしれない。文化人類学のことをあまりよく知らなかったのだが、大変面白かった。読みやすく知識がどんどんついていく感じがとても気持ちがいい。暮らしの中で生じる身近な問いがどういった背景からくるものなのかが詳しく書かれてあった。世の中にこんな面白い学問があるのだなと思っていたら、自分の好きな作家の上橋菜穂子さんが文化人類学を専攻していたことを知って驚きつつも納得した。


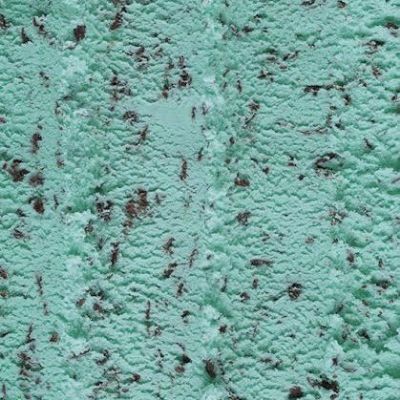 どこかの風車@drifloon_4252025年12月22日読み終わった身近な例を挙げた問い→実際の民族における事例→最初の問いへの回答 という一連の流れで章が構成されている。 読みやすく、文化人類学とは何かを理解するにはいい本だが、個人的読み物としての面白さはいまひとつ。
どこかの風車@drifloon_4252025年12月22日読み終わった身近な例を挙げた問い→実際の民族における事例→最初の問いへの回答 という一連の流れで章が構成されている。 読みやすく、文化人類学とは何かを理解するにはいい本だが、個人的読み物としての面白さはいまひとつ。 シロップ@sirop2025年9月15日買った読み終わった『ヤンキーと地元』からの流れで積読の中から手に取った本。『ヤンキーと地元』を読んでて文化人類学と手法が似てるけど、何が違うだろうと思ったのでちょうどよかった。 大元は講義だったらしく、とても読みやすい。むずかしいことが出てくるわけでない。気軽に人におすすめできる本だと思う。おもしろいから。 文化人類学があたりまえを切り崩してしまい、それに巻き込まれる、という表現がとても印象に残った。疑うではなく、切り崩す。その主語はわたしたちではないということ。 ブックガイドを眺めて、とりあえず『うしろめたさの人類学』読みたいなと思った。
シロップ@sirop2025年9月15日買った読み終わった『ヤンキーと地元』からの流れで積読の中から手に取った本。『ヤンキーと地元』を読んでて文化人類学と手法が似てるけど、何が違うだろうと思ったのでちょうどよかった。 大元は講義だったらしく、とても読みやすい。むずかしいことが出てくるわけでない。気軽に人におすすめできる本だと思う。おもしろいから。 文化人類学があたりまえを切り崩してしまい、それに巻き込まれる、という表現がとても印象に残った。疑うではなく、切り崩す。その主語はわたしたちではないということ。 ブックガイドを眺めて、とりあえず『うしろめたさの人類学』読みたいなと思った。
 べりん@ngske942025年8月25日読み終わったとても面白く読み進められました! 私自身が持つ「当たり前の考え方」を問う事例をもとに内容が進み、最後にそれらを踏まえて文化人類学とはどういう学問かを明らかにしてくれます。 読み進めて興味深かったのは、文化人類学は成果を出すのに非常に時間と労力を要する点です。 現代社会は情報化が進み、インターネットやテクノロジーも発達したことで、我々は欲しい答えに簡単にアクセスできるようになりました。 私自身も、調べ物はすぐにスマホで検索し、手っ取り早く知識を得ることがよくあります。 一方で文化人類学の研究は、多様な考え方を理解するために研究者自身が実際に異文化の地域に身を置き(現地の言語を学習し、原住民と共に生活する)、そこで気付きを得ることが成果となります。 それは文字通り、一朝一夕では得られないものです。 凄く効率悪いじゃん!と思ってしまいますが、自分に確立された常識や考え方と異なるものに触れ、新たな考え方を見つけるとともに、自分自身が意識していなかった考え方を自覚出来ることが文化人類学の魅力なのだと思います。 この本を読んでいるだけでも、読者自身の考え方が当たり前ではないと気付く場面がたくさんあると思いますよ。 例えば私は、葬式を2度行う地域があることに驚きました。 私(日本人)とは異なる世界観を持っていることに起因するのですが、それは実際にこの本を読んでみてください。 世の中、簡単に得られる情報ばかりじゃないよなと改めて思いました。 文化人類学のように世界の異文化を対象にしなくても、身近な人(たとえば気の合わない上司とか)を慮れるようになるきっかけの1冊になりました。
べりん@ngske942025年8月25日読み終わったとても面白く読み進められました! 私自身が持つ「当たり前の考え方」を問う事例をもとに内容が進み、最後にそれらを踏まえて文化人類学とはどういう学問かを明らかにしてくれます。 読み進めて興味深かったのは、文化人類学は成果を出すのに非常に時間と労力を要する点です。 現代社会は情報化が進み、インターネットやテクノロジーも発達したことで、我々は欲しい答えに簡単にアクセスできるようになりました。 私自身も、調べ物はすぐにスマホで検索し、手っ取り早く知識を得ることがよくあります。 一方で文化人類学の研究は、多様な考え方を理解するために研究者自身が実際に異文化の地域に身を置き(現地の言語を学習し、原住民と共に生活する)、そこで気付きを得ることが成果となります。 それは文字通り、一朝一夕では得られないものです。 凄く効率悪いじゃん!と思ってしまいますが、自分に確立された常識や考え方と異なるものに触れ、新たな考え方を見つけるとともに、自分自身が意識していなかった考え方を自覚出来ることが文化人類学の魅力なのだと思います。 この本を読んでいるだけでも、読者自身の考え方が当たり前ではないと気付く場面がたくさんあると思いますよ。 例えば私は、葬式を2度行う地域があることに驚きました。 私(日本人)とは異なる世界観を持っていることに起因するのですが、それは実際にこの本を読んでみてください。 世の中、簡単に得られる情報ばかりじゃないよなと改めて思いました。 文化人類学のように世界の異文化を対象にしなくても、身近な人(たとえば気の合わない上司とか)を慮れるようになるきっかけの1冊になりました。

 S@zukkiziburi2025年5月6日読み終わった民族境界論の民族の境界を作るから文化の違いが強調される。同じ文化を共有するもの同士が同じ民族なわけではない。 民族っていうのはとても人工的なもので、 地続きな大陸をイメージすれば分かるように、全てをカテゴリーに収めることはできない。 人が作った物なのに新しい発見であるかのように興味深く感じる私も、なんだかおもしろい
S@zukkiziburi2025年5月6日読み終わった民族境界論の民族の境界を作るから文化の違いが強調される。同じ文化を共有するもの同士が同じ民族なわけではない。 民族っていうのはとても人工的なもので、 地続きな大陸をイメージすれば分かるように、全てをカテゴリーに収めることはできない。 人が作った物なのに新しい発見であるかのように興味深く感じる私も、なんだかおもしろい