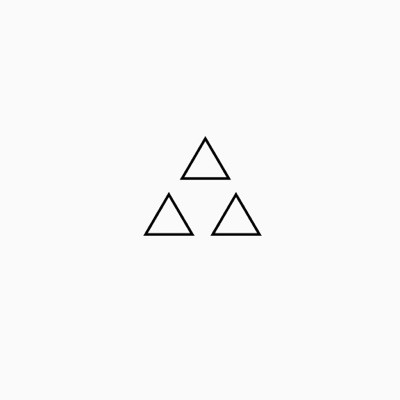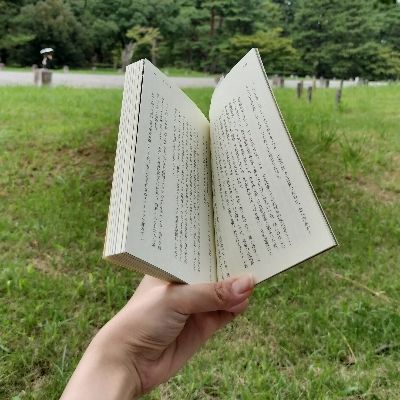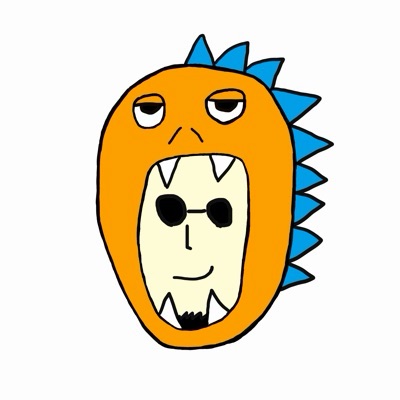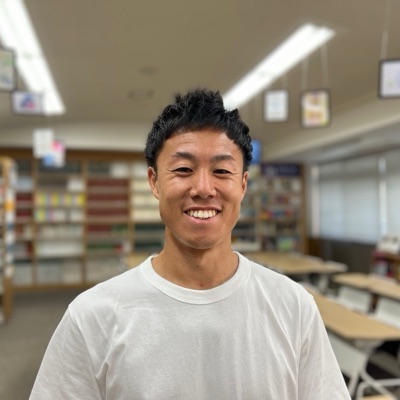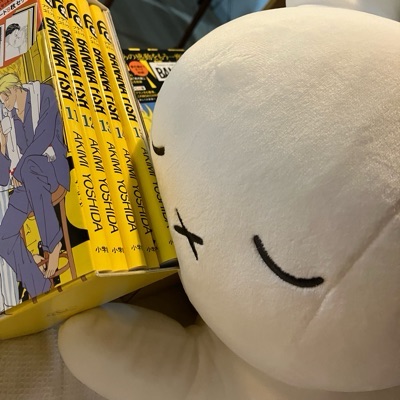とびこえる教室

54件の記録
 kirakira30@kirakira302026年1月1日読み終わった学び!フェミニズムとジェンダーのこと、もっともっと学びたいと思う。「正しさ」をふりかざすのではない、自分の当たり前と思い込みを見つけて、様々な人が少しでも生きやすい社会にしていく一員であるために。 こちらも大切にしていきたい1冊。
kirakira30@kirakira302026年1月1日読み終わった学び!フェミニズムとジェンダーのこと、もっともっと学びたいと思う。「正しさ」をふりかざすのではない、自分の当たり前と思い込みを見つけて、様々な人が少しでも生きやすい社会にしていく一員であるために。 こちらも大切にしていきたい1冊。
 くりこ@kurikomone2025年11月22日読み終わった以前から子供にこそフェミニズムが必要だと考えていたので、こういう先生がいらっしゃって本当に嬉しい。シスジェンダー、ヘテロセクシャルが普通であり、社会から押し付けられたジェンダー規範を身に着けることで私たちはどれだけ自由を奪われているだろうか 星野さんが虐待を受けた傷つきに信田さよ子さんの本やフェミニズムを通して言葉を紡いでいこうとする姿勢が、私と同じででぐいぐい引き込まれながら読む。 一番印象に残ったことは、暴力的な男子生徒に対して強い言葉で制するのではなく「大丈夫?」と声をかけることで彼らが自分の怒りや悲しみを語りだすと書かれていたこと。DVをしている男性は自分の被害体験を全部語ることで加害性に気づくと信田さよ子さんの本で読んだことがあるが、傷つきが積もり積もって他者への暴力になるという事は、子供はもちろんのこと、昨今排外主義に流れていってしまう人にも当てはまり、本当は彼らはケアを求めているのではないかと感じる(もちろん被害者救済が一番大事なのだが) 機能不全家族を描いた宇佐美りんの『くるまの娘』では、主人公かん子は家族から中々離れられない理由を「家族にすがられたから」「家族全体を救ってほしい」からだと吐露する。星野さんの父親に対するまなざしを見ると同じような空気を感じる(という私もそうだ)。 今の社会に決定的にかけているものは、「他者の苦悩へのまなざし」である。このまなざしを育むためには星野さんのように自分の深い傷つきに向き合い、もう一度生きなおしをする事がスタート地点なのではないだろうか。自分の弱さと向かい合えてこそ他人の弱さを見るようになるものであり、それが自分や他者の自由へと繋がる。それがケアに満ちた社会を作る回路となるのではないだろうか。
くりこ@kurikomone2025年11月22日読み終わった以前から子供にこそフェミニズムが必要だと考えていたので、こういう先生がいらっしゃって本当に嬉しい。シスジェンダー、ヘテロセクシャルが普通であり、社会から押し付けられたジェンダー規範を身に着けることで私たちはどれだけ自由を奪われているだろうか 星野さんが虐待を受けた傷つきに信田さよ子さんの本やフェミニズムを通して言葉を紡いでいこうとする姿勢が、私と同じででぐいぐい引き込まれながら読む。 一番印象に残ったことは、暴力的な男子生徒に対して強い言葉で制するのではなく「大丈夫?」と声をかけることで彼らが自分の怒りや悲しみを語りだすと書かれていたこと。DVをしている男性は自分の被害体験を全部語ることで加害性に気づくと信田さよ子さんの本で読んだことがあるが、傷つきが積もり積もって他者への暴力になるという事は、子供はもちろんのこと、昨今排外主義に流れていってしまう人にも当てはまり、本当は彼らはケアを求めているのではないかと感じる(もちろん被害者救済が一番大事なのだが) 機能不全家族を描いた宇佐美りんの『くるまの娘』では、主人公かん子は家族から中々離れられない理由を「家族にすがられたから」「家族全体を救ってほしい」からだと吐露する。星野さんの父親に対するまなざしを見ると同じような空気を感じる(という私もそうだ)。 今の社会に決定的にかけているものは、「他者の苦悩へのまなざし」である。このまなざしを育むためには星野さんのように自分の深い傷つきに向き合い、もう一度生きなおしをする事がスタート地点なのではないだろうか。自分の弱さと向かい合えてこそ他人の弱さを見るようになるものであり、それが自分や他者の自由へと繋がる。それがケアに満ちた社会を作る回路となるのではないだろうか。




 くりこ@kurikomone2025年11月18日読んでるこういう自分の経験を内省して何を掴んでいったか書かれてる本が好き。 星野さんが、父親から虐待を受けながら育ち、高校の時は自己責任論者になった下りは私も似たような境遇だったので既視感がある。 自己責任論者になったことは、信田さよ子さんが「虐待の本質は暴力とかネグレクトではない。今起こってること全部お前の責任なんだと罪悪感を植え付けることなのだ」と言っていたことと関係してるだろう この最悪感を植え付けられることに加えて、私の場合、「困っている時も誰も助けてくれない。だから自分でどうにかしなきゃ」という思いを他者にも投影して自己責任論者になったのだな。 星野さんが、信田さよ子さんの本を読んで自分のされたことが虐待だと気づいたことも一緒!信田さんはフェミニズムの視点を持ちながら虐待、DVについて語ってくれるのが特にいい。 まだ序盤だけど読むのが楽しみ!
くりこ@kurikomone2025年11月18日読んでるこういう自分の経験を内省して何を掴んでいったか書かれてる本が好き。 星野さんが、父親から虐待を受けながら育ち、高校の時は自己責任論者になった下りは私も似たような境遇だったので既視感がある。 自己責任論者になったことは、信田さよ子さんが「虐待の本質は暴力とかネグレクトではない。今起こってること全部お前の責任なんだと罪悪感を植え付けることなのだ」と言っていたことと関係してるだろう この最悪感を植え付けられることに加えて、私の場合、「困っている時も誰も助けてくれない。だから自分でどうにかしなきゃ」という思いを他者にも投影して自己責任論者になったのだな。 星野さんが、信田さよ子さんの本を読んで自分のされたことが虐待だと気づいたことも一緒!信田さんはフェミニズムの視点を持ちながら虐待、DVについて語ってくれるのが特にいい。 まだ序盤だけど読むのが楽しみ!




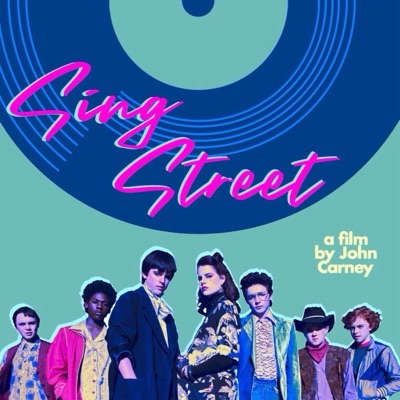



 yuki@yk_books2025年11月18日読み終わった自身の小学生時代を振り返ると、裕福だったわけでもない地方の公立小学校だったが、男女の社会規範にとらわれずに学びを楽しむことを尊重する学校だったように思う。 その中にも色々な、当時のわたしに見えていなかったことはあるはず。 言語化できないモヤモヤをご自身の経験も踏まえて丁寧に書いてくださっていて、たとえばパートナーに伝えたいのにうまく話せないときに読み返したいと思った。
yuki@yk_books2025年11月18日読み終わった自身の小学生時代を振り返ると、裕福だったわけでもない地方の公立小学校だったが、男女の社会規範にとらわれずに学びを楽しむことを尊重する学校だったように思う。 その中にも色々な、当時のわたしに見えていなかったことはあるはず。 言語化できないモヤモヤをご自身の経験も踏まえて丁寧に書いてくださっていて、たとえばパートナーに伝えたいのにうまく話せないときに読み返したいと思った。


 Matilde@i_griega_20252025年9月29日読み終わった男性の生きづらさを男性自身が語るのは本当に難しい社会だと思う。抑圧され鬱屈した思いがDVや虐待やパワハラ・モラハラ・セクハラ等のハラスメントという形で表れてくるんじゃないかなということは直感的に思ってはいたけれど、構造的にもやっぱりそうなんだろうな。 改善される、もしくは救われるかどうかは別として、女性の方が生きづらさを口にしやすいし連帯もしやすい。でも男性は女性と同じ意味での連帯は難しいのかも。マッチョなホモソーシャルの結びつきなら想像できるけれど。 それにしても、フェミニズムを経由しないと語れないことのなんと多いことか…
Matilde@i_griega_20252025年9月29日読み終わった男性の生きづらさを男性自身が語るのは本当に難しい社会だと思う。抑圧され鬱屈した思いがDVや虐待やパワハラ・モラハラ・セクハラ等のハラスメントという形で表れてくるんじゃないかなということは直感的に思ってはいたけれど、構造的にもやっぱりそうなんだろうな。 改善される、もしくは救われるかどうかは別として、女性の方が生きづらさを口にしやすいし連帯もしやすい。でも男性は女性と同じ意味での連帯は難しいのかも。マッチョなホモソーシャルの結びつきなら想像できるけれど。 それにしても、フェミニズムを経由しないと語れないことのなんと多いことか…


 はな@hana-hitsuji052025年9月20日読み終わった図書館本図書館で借りた一言で言えばめちゃ良い本だった。132 思いも葛藤も後悔も共感しきり。 p80 「何も手立てを講じなければ、その怨念に自分自身が蝕まれ、そのうち『もののけ姫』に出てくる「タタリ神」のように自分がなってしまうかもしれないという予感がありました。」 自分の家族でさえ裸眼で物事を見ている場所を1人だけメガネをかけて見えてしまったものから目が離せなくなっている気持ち。 誰かと分かち合いたいのに近くにはいない。 p128 著者は自分の過去や傷だけでなく、取り返しのつかない過ちや間違いも記している。 p181 柔らかい声をエンパワーすること。 トーンポリシング、マンスプレイニング p140 ケア労働は「女性的」 社会的承認を求めたかったのではなく、ただ「ケアされたい」と願っていた 教養とは。ここでも鬼滅っぽい「生殺与奪の権」「女の子の翼を折らない、男の子に呪いをかけない」 「性別vs性別の話ではなく、暴力は構造から立ち現れる」とはいえ、「性別にとらわれないこと」と「あえてとらわれること」ここが1番良かった。どっちか1つを選びそれを常に指針としていくのではなくて、この場合は何を大切にするのか。そこがごちゃごちゃになりがち。
はな@hana-hitsuji052025年9月20日読み終わった図書館本図書館で借りた一言で言えばめちゃ良い本だった。132 思いも葛藤も後悔も共感しきり。 p80 「何も手立てを講じなければ、その怨念に自分自身が蝕まれ、そのうち『もののけ姫』に出てくる「タタリ神」のように自分がなってしまうかもしれないという予感がありました。」 自分の家族でさえ裸眼で物事を見ている場所を1人だけメガネをかけて見えてしまったものから目が離せなくなっている気持ち。 誰かと分かち合いたいのに近くにはいない。 p128 著者は自分の過去や傷だけでなく、取り返しのつかない過ちや間違いも記している。 p181 柔らかい声をエンパワーすること。 トーンポリシング、マンスプレイニング p140 ケア労働は「女性的」 社会的承認を求めたかったのではなく、ただ「ケアされたい」と願っていた 教養とは。ここでも鬼滅っぽい「生殺与奪の権」「女の子の翼を折らない、男の子に呪いをかけない」 「性別vs性別の話ではなく、暴力は構造から立ち現れる」とはいえ、「性別にとらわれないこと」と「あえてとらわれること」ここが1番良かった。どっちか1つを選びそれを常に指針としていくのではなくて、この場合は何を大切にするのか。そこがごちゃごちゃになりがち。









 はな@hana-hitsuji052025年9月19日読み始めた図書館本図書館で借りたこれまで読んだ本や漫画といとも簡単にリンクする部分が出てきて家父長制の影響やそこから派生する暴力がそこらじゅうにあることに軽く驚いてる。 著者はこういう人生のスタートを切って、悪しき価値観が染み付いてないわけないと今の時点では思ってる。 ここからどうその鎖を振りほどいていくのか。出来るものなのか? いや、まだどんなお話なのかはわからない。
はな@hana-hitsuji052025年9月19日読み始めた図書館本図書館で借りたこれまで読んだ本や漫画といとも簡単にリンクする部分が出てきて家父長制の影響やそこから派生する暴力がそこらじゅうにあることに軽く驚いてる。 著者はこういう人生のスタートを切って、悪しき価値観が染み付いてないわけないと今の時点では思ってる。 ここからどうその鎖を振りほどいていくのか。出来るものなのか? いや、まだどんなお話なのかはわからない。









 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月21日読み終わった@ 自宅頭が回復してきたのでリハビリがてら最後まで読む。 ラスト二つのコラムがコンパクトながら良かった(「秩序とは何か」、「『性別にとらわれない』と『あえて性別にこだわる』の間で」)。 〈子どもを信じるとは、権力の非対称性を見抜いたうえで、それでもなお、対話の可能性を手放さないという誓いでもあるのかもしれません。〉(203頁) 終章(第7章)に出てきた以下の一節は、改めて胸に刻みたい。 〈必要なのは「私も考えたい」「共にやりたい」という言葉です。〉(231頁) また、「私」の物語を勇気をもって書いた著者に敬意を表したい。 〈つまり、そのような生きづらさは「教師自身の経験」ではなく、「特別に招かれた誰かの話」として扱われます。教師は、あくまで「場を整える側」にとどまり、自分の内側にある苦しみを子どもたちに語ることは望まれていません。ですから、語らないと言う選択は、一見すると個人の判断に見えますが、実際には学校という制度のあり方によって強いられた沈黙でもあります。〉(238頁) 学校の外に出た著者の今後の発信も楽しみ。 「おわりに」の父の写真と母のタペストリーの話を噛み締めながら、読了。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月21日読み終わった@ 自宅頭が回復してきたのでリハビリがてら最後まで読む。 ラスト二つのコラムがコンパクトながら良かった(「秩序とは何か」、「『性別にとらわれない』と『あえて性別にこだわる』の間で」)。 〈子どもを信じるとは、権力の非対称性を見抜いたうえで、それでもなお、対話の可能性を手放さないという誓いでもあるのかもしれません。〉(203頁) 終章(第7章)に出てきた以下の一節は、改めて胸に刻みたい。 〈必要なのは「私も考えたい」「共にやりたい」という言葉です。〉(231頁) また、「私」の物語を勇気をもって書いた著者に敬意を表したい。 〈つまり、そのような生きづらさは「教師自身の経験」ではなく、「特別に招かれた誰かの話」として扱われます。教師は、あくまで「場を整える側」にとどまり、自分の内側にある苦しみを子どもたちに語ることは望まれていません。ですから、語らないと言う選択は、一見すると個人の判断に見えますが、実際には学校という制度のあり方によって強いられた沈黙でもあります。〉(238頁) 学校の外に出た著者の今後の発信も楽しみ。 「おわりに」の父の写真と母のタペストリーの話を噛み締めながら、読了。

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月20日まだ読んでる就寝前読書@ 自宅暑さで頭も痛いし開票速報で頭も心も落ち着かないけど第5章を読む。「柔らかい声をエンパワーすること」の節、子どもたちのアイデアにハッとさせられた。負かし方も大事だよね...
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月20日まだ読んでる就寝前読書@ 自宅暑さで頭も痛いし開票速報で頭も心も落ち着かないけど第5章を読む。「柔らかい声をエンパワーすること」の節、子どもたちのアイデアにハッとさせられた。負かし方も大事だよね...



 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月19日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第4章の途中まで読む(〜121頁)。 著者が初めて試みた「生と性の授業」の具体的な実践内容や生徒たちの変化だけでなく、それが成立するまでのプロセスが書かれているのが良いなと思った。特に、保護者への事前説明をどう行ない、どういう反応があったかが書いてあるのは、ディテールとして大切。 現実問題、教育実践は生徒と教師のいる教室だけに閉じていないはずで、だからこそサポーティブな同僚、上司、保護者、地域の人々がいることが追い風になるというか、その足場を支えているはずで。今後、性教育、特に「包括的性教育」への風当たりは強くなるかもしれないから、そうなったときに学校側が(教師たちが)挫けないために周囲の支えがかなり大事になってくるのではないか、と思う。 このあたりは「日本の性教育実践と実践者の歴史」を研究している堀川修平さんの著書も参照されたい(第4章の註には堀川さんの博論本があげられているが、『「日本に性教育はなかった」と言う前に』の終章「ブームとバッシングのあいだで考える」もあわせて読むとよさそう)。 以下は余談だけど、さらっとしか描かれていないこの部分。 〈ある日、私はある男性の同僚に「学校で教師として働くことが苦しいです」とメールで弱音を吐きました。すると、彼から次のような返事がありました。/「しんどいね。だからこそ、多様で異質な他者との付き合い方を子どもたちに体験的に教えていかねばならない。自分たちがとらわれている認識をひっくり返すような授業をしたいね」〉(97頁) この男性の応答に勇気づけられた著者は、〈彼と一緒に学年を組み、ジェンダーやセクシュアリティに踏み込んだ性教育に取り組むことを決意〉する。 この男性についてこれ以上の情報は書かれていないからわからないけど、シズジェンダーの異性愛者だったと仮定すると、どうしてこの時このような応答をしたのですか?と個人的に聞いてみたくなった。というのは最近よく、(意地悪ではなく素朴な疑問として)当事者じゃないのに(「ノンケなのに」)どうしてクィアな本を作ってるの?と聞かれるから。そのたびにモニョモニョしてしまうから。 だからこそ、この男性のふるまいはとても気になるし、このような男性が増えることが大事だと思うから、話してみたいと思った。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月19日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第4章の途中まで読む(〜121頁)。 著者が初めて試みた「生と性の授業」の具体的な実践内容や生徒たちの変化だけでなく、それが成立するまでのプロセスが書かれているのが良いなと思った。特に、保護者への事前説明をどう行ない、どういう反応があったかが書いてあるのは、ディテールとして大切。 現実問題、教育実践は生徒と教師のいる教室だけに閉じていないはずで、だからこそサポーティブな同僚、上司、保護者、地域の人々がいることが追い風になるというか、その足場を支えているはずで。今後、性教育、特に「包括的性教育」への風当たりは強くなるかもしれないから、そうなったときに学校側が(教師たちが)挫けないために周囲の支えがかなり大事になってくるのではないか、と思う。 このあたりは「日本の性教育実践と実践者の歴史」を研究している堀川修平さんの著書も参照されたい(第4章の註には堀川さんの博論本があげられているが、『「日本に性教育はなかった」と言う前に』の終章「ブームとバッシングのあいだで考える」もあわせて読むとよさそう)。 以下は余談だけど、さらっとしか描かれていないこの部分。 〈ある日、私はある男性の同僚に「学校で教師として働くことが苦しいです」とメールで弱音を吐きました。すると、彼から次のような返事がありました。/「しんどいね。だからこそ、多様で異質な他者との付き合い方を子どもたちに体験的に教えていかねばならない。自分たちがとらわれている認識をひっくり返すような授業をしたいね」〉(97頁) この男性の応答に勇気づけられた著者は、〈彼と一緒に学年を組み、ジェンダーやセクシュアリティに踏み込んだ性教育に取り組むことを決意〉する。 この男性についてこれ以上の情報は書かれていないからわからないけど、シズジェンダーの異性愛者だったと仮定すると、どうしてこの時このような応答をしたのですか?と個人的に聞いてみたくなった。というのは最近よく、(意地悪ではなく素朴な疑問として)当事者じゃないのに(「ノンケなのに」)どうしてクィアな本を作ってるの?と聞かれるから。そのたびにモニョモニョしてしまうから。 だからこそ、この男性のふるまいはとても気になるし、このような男性が増えることが大事だと思うから、話してみたいと思った。


 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月19日まだ読んでる就寝前読書@ 自宅第4章読み終わる。さっき投稿したのと関連するくだり、ちゃんと「ケアの不在と報われなさのゆくえ」という節に書いてあった。 〈本来、公教育とは、学校が一方的にサービスを提供するものでも、家庭が教育を委託する場でもありません。子どもの学びと育ちを中心に、家庭・学校・地域が対話的に築いていく営みであるはずです。〉(138頁) 〈この尊くて、実存を賭するに値する仕事を、想いをもって選んだ教師たちが報われなさの中で続けられなくなってしまうこと。それが、何よりも悔しいのです。どれほど心をこめて働いても、労われることは少なく、制度的なケアも整っていない。そんな環境の中で、精神的なやりがいだけを支えに働き続けるには、この仕事はあまりにも過酷です。〉(142頁) 第1章に登場する毛利先生(素敵)が登場するダイアローグ❶もやっぱり素敵だった。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月19日まだ読んでる就寝前読書@ 自宅第4章読み終わる。さっき投稿したのと関連するくだり、ちゃんと「ケアの不在と報われなさのゆくえ」という節に書いてあった。 〈本来、公教育とは、学校が一方的にサービスを提供するものでも、家庭が教育を委託する場でもありません。子どもの学びと育ちを中心に、家庭・学校・地域が対話的に築いていく営みであるはずです。〉(138頁) 〈この尊くて、実存を賭するに値する仕事を、想いをもって選んだ教師たちが報われなさの中で続けられなくなってしまうこと。それが、何よりも悔しいのです。どれほど心をこめて働いても、労われることは少なく、制度的なケアも整っていない。そんな環境の中で、精神的なやりがいだけを支えに働き続けるには、この仕事はあまりにも過酷です。〉(142頁) 第1章に登場する毛利先生(素敵)が登場するダイアローグ❶もやっぱり素敵だった。

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月12日買った@ マルジナリア書店byよはく舎『「日本に性教育はなかった」と言う前に』でお世話になった堀川修平さんとのトークイベントにて。とても良さそう。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月12日買った@ マルジナリア書店byよはく舎『「日本に性教育はなかった」と言う前に』でお世話になった堀川修平さんとのトークイベントにて。とても良さそう。