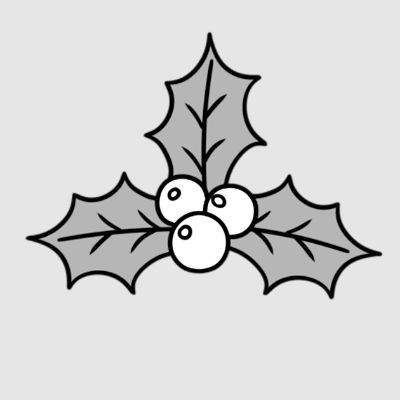「これくらいできないと困るのはきみだよ」?

67件の記録
 kirakira30@kirakira302025年12月28日読み終わったまた読みたい学び!ジャッジすること、評価することがあまりにも当たり前になりすぎている世界にいる自分への自戒をこめて、教育に携わる人は必読だと思う。
kirakira30@kirakira302025年12月28日読み終わったまた読みたい学び!ジャッジすること、評価することがあまりにも当たり前になりすぎている世界にいる自分への自戒をこめて、教育に携わる人は必読だと思う。 五月@gogatsu2025年10月22日4章まできた。特別支援学級より通常級のほうが、「これくらいできないと困る」と言われやすい話。小学校に向けて、年長の夏に「これとこれとこれとこれと(中略)これはできるようにしておいてください」と言われたけどすでにここから「これくらいできないと困るのはきみだよ」が始まってるんだな…
五月@gogatsu2025年10月22日4章まできた。特別支援学級より通常級のほうが、「これくらいできないと困る」と言われやすい話。小学校に向けて、年長の夏に「これとこれとこれとこれと(中略)これはできるようにしておいてください」と言われたけどすでにここから「これくらいできないと困るのはきみだよ」が始まってるんだな…

 毎分毎秒@maimmais2025年7月5日マイノリティ組織開発教育p.74 みな凸凹していて、いろんな状況、ままならなさを抱えていて、強気な場面もあれば、弱気なときだってある。声高に主張できたと思えば、聞き流されてしまうときもある。そういった現実的ながちゃがちゃとした揺らぎを前に、互いに持ちつ持たれつ、協働していくってことなんでしょうね。
毎分毎秒@maimmais2025年7月5日マイノリティ組織開発教育p.74 みな凸凹していて、いろんな状況、ままならなさを抱えていて、強気な場面もあれば、弱気なときだってある。声高に主張できたと思えば、聞き流されてしまうときもある。そういった現実的ながちゃがちゃとした揺らぎを前に、互いに持ちつ持たれつ、協働していくってことなんでしょうね。
 つばめ@swallow32025年6月29日読み終わった教育の話だと思ってたけど、能力主義って結局社会にも繋がってるからあるあると思うことがいくつもあった。 東洋哲学についての本読んだ後だからか、移り変わるものをある基準に合わせようとしたり、固定してみようとしたりすることでのしんどさが要因になってること多いんだろうなと思った。 みんなで思いの違いを共有し合って、うまくいくようにするのは大事だなと思うけど、「自分は頑張って乗り越えてきたのに今はこんなに良くしてもらえるのは不平等だ」っていう勢力と戦う感じになるだろうなと思う… ・ダメ出しではなくポジ出しをする。ここが良かったとフィードバックする。 ・"パターン認識をすることのほうが一見すると楽そうなんだけど、実は何もわからなくなるのよね。" ・"体制側が求めるものを、素早くわかりやすく差し出すことを「主体性」と呼ぶ" ・"説明できるはずだという前提で、説明できないことは主張すべきでないというのも暗に感じるじゃないですか。" ・"自分はこんな頑張ってるのに、あの人がこれぐらいもできひんのは許されへん。"
つばめ@swallow32025年6月29日読み終わった教育の話だと思ってたけど、能力主義って結局社会にも繋がってるからあるあると思うことがいくつもあった。 東洋哲学についての本読んだ後だからか、移り変わるものをある基準に合わせようとしたり、固定してみようとしたりすることでのしんどさが要因になってること多いんだろうなと思った。 みんなで思いの違いを共有し合って、うまくいくようにするのは大事だなと思うけど、「自分は頑張って乗り越えてきたのに今はこんなに良くしてもらえるのは不平等だ」っていう勢力と戦う感じになるだろうなと思う… ・ダメ出しではなくポジ出しをする。ここが良かったとフィードバックする。 ・"パターン認識をすることのほうが一見すると楽そうなんだけど、実は何もわからなくなるのよね。" ・"体制側が求めるものを、素早くわかりやすく差し出すことを「主体性」と呼ぶ" ・"説明できるはずだという前提で、説明できないことは主張すべきでないというのも暗に感じるじゃないですか。" ・"自分はこんな頑張ってるのに、あの人がこれぐらいもできひんのは許されへん。"



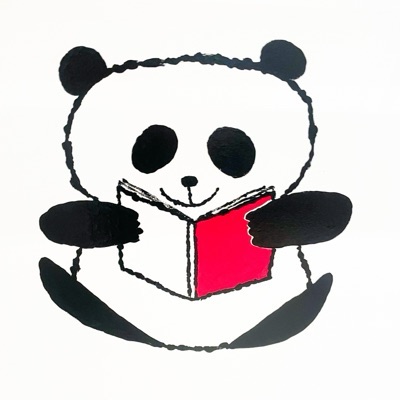





 あんこちゃん@anko2025年6月1日読み終わった借りてきた自身の行動言動を振り返って耳が痛くなることが多々あった。そんな理想を…とも思いつつ、でも変えた方がいいこといっぱいあるよな、思っていてもただ周りの空気について行くのってそれは変えたくない人に加担しているのと同じ。 『「こちらがやらせたいことを自ら進んでやってほしい」というのを「主体性」と呼んでいることがあるような。』まさにそう!
あんこちゃん@anko2025年6月1日読み終わった借りてきた自身の行動言動を振り返って耳が痛くなることが多々あった。そんな理想を…とも思いつつ、でも変えた方がいいこといっぱいあるよな、思っていてもただ周りの空気について行くのってそれは変えたくない人に加担しているのと同じ。 『「こちらがやらせたいことを自ら進んでやってほしい」というのを「主体性」と呼んでいることがあるような。』まさにそう!



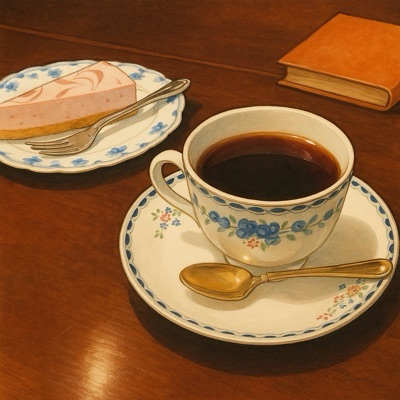
 いとま@itoma2025年6月1日読み終わった教育という括りではあるものの、社会に問うタイトル「このくらいできないと困るのはきみだよ」? 識者のお話を横で聴くことしかできない私ですが、それでも社会の一員。まず一歩として相手の話を聞くことを始めたいと思いました。
いとま@itoma2025年6月1日読み終わった教育という括りではあるものの、社会に問うタイトル「このくらいできないと困るのはきみだよ」? 識者のお話を横で聴くことしかできない私ですが、それでも社会の一員。まず一歩として相手の話を聞くことを始めたいと思いました。


 いっちー@icchii3172025年5月2日借りてきたちらっと読んだおもに教育業界に携わる人たちと作者との対談集。 自分たち(教師)が変わっても、彼らを待ち受ける能力主義社会は変わらないんじゃないか…という悩みに対して「それは囚人のジレンマに他ならない」とバッサリいくところから始まる。そもそも「これくらいできないと困るのは君だよ」、の「これくらい」が規定する社会は本当に実在するのか?と。 能力主義社会を、つまり「これくらい」で規定する社会を、自分たちでつくりだしてしまっているのではないか? 「これくらい」で相手を評価するとは、つまり 「変わるべきは自分ではなく、あくまで(できの悪い)相手である」(p365)というメッセージを伝えていることに他ならない。 「身分制に変わる配分原理としては、能力性に代わる名案はなかったかもしれない。でもだからと言って、それをこの先も続けていくべきかは、大いに再考の余地がある」p369 むしろ学校という場所から、変えていくことができるのでは、という希望の書。 最後の言葉もぶっささる。 先生が腐心すべきことは、 「子どもたちをそろえ、まとめ、整えることに長けた、有能かつ心に余裕がありながらも高い指導力を誇る教師 ではない」いうこと。
いっちー@icchii3172025年5月2日借りてきたちらっと読んだおもに教育業界に携わる人たちと作者との対談集。 自分たち(教師)が変わっても、彼らを待ち受ける能力主義社会は変わらないんじゃないか…という悩みに対して「それは囚人のジレンマに他ならない」とバッサリいくところから始まる。そもそも「これくらいできないと困るのは君だよ」、の「これくらい」が規定する社会は本当に実在するのか?と。 能力主義社会を、つまり「これくらい」で規定する社会を、自分たちでつくりだしてしまっているのではないか? 「これくらい」で相手を評価するとは、つまり 「変わるべきは自分ではなく、あくまで(できの悪い)相手である」(p365)というメッセージを伝えていることに他ならない。 「身分制に変わる配分原理としては、能力性に代わる名案はなかったかもしれない。でもだからと言って、それをこの先も続けていくべきかは、大いに再考の余地がある」p369 むしろ学校という場所から、変えていくことができるのでは、という希望の書。 最後の言葉もぶっささる。 先生が腐心すべきことは、 「子どもたちをそろえ、まとめ、整えることに長けた、有能かつ心に余裕がありながらも高い指導力を誇る教師 ではない」いうこと。
 ゆう@suisuiu2025年4月2日読み終わったこの言葉通りではないにしろこのような言葉を浴びせられてきた記憶がある人はあちこちにいるのでないか、と思うけれどもわたしもそうで、この本の内容自体はタイトルに対する批評的な姿勢、だけれど今思うと読み進めるのにいちいち時間がかかってしまったのはこの文字列のせいかもしれない。いちいち手に取るのに数秒躊躇する、本そのものには無関係な自分の余計なことを思い出すものだったのかもしれない。
ゆう@suisuiu2025年4月2日読み終わったこの言葉通りではないにしろこのような言葉を浴びせられてきた記憶がある人はあちこちにいるのでないか、と思うけれどもわたしもそうで、この本の内容自体はタイトルに対する批評的な姿勢、だけれど今思うと読み進めるのにいちいち時間がかかってしまったのはこの文字列のせいかもしれない。いちいち手に取るのに数秒躊躇する、本そのものには無関係な自分の余計なことを思い出すものだったのかもしれない。









 いま@mayonakayom222025年3月27日読み終わった教育関係の仕事ではないけれど、一保護者として学校というものに十数年関わっていく身として読んでよかった。 「対話の経験も非認知能力も、獲得機会が階層的に恵まれた子たちに偏在している」はまさにそうで。 社会が規定する能力や評価に辟易している自分と、どうしようもなくその評価を内包してしまっている自分にモヤモヤするけれど、じゃあどうする?を著者と一緒に考えながら読んでいけるような本。
いま@mayonakayom222025年3月27日読み終わった教育関係の仕事ではないけれど、一保護者として学校というものに十数年関わっていく身として読んでよかった。 「対話の経験も非認知能力も、獲得機会が階層的に恵まれた子たちに偏在している」はまさにそうで。 社会が規定する能力や評価に辟易している自分と、どうしようもなくその評価を内包してしまっている自分にモヤモヤするけれど、じゃあどうする?を著者と一緒に考えながら読んでいけるような本。
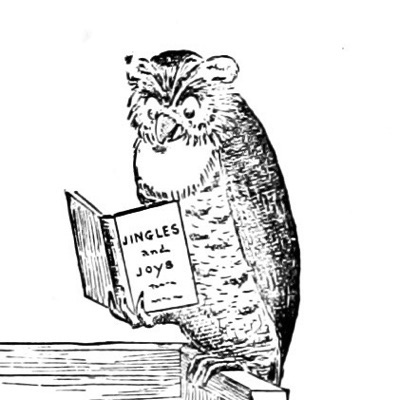



 萌生@moet-17152025年3月15日読みたいあ、何か耳が痛いかも!言っているかも、考えているかもしれない「これくらいできないと…」。不登校児の問題にも触れられてるみたいだけど、引きこもりの人たちが社会と繋がるときにも通じるのでは。障害福祉の支援職としても知っておきたいことですね。読みます、はい。
萌生@moet-17152025年3月15日読みたいあ、何か耳が痛いかも!言っているかも、考えているかもしれない「これくらいできないと…」。不登校児の問題にも触れられてるみたいだけど、引きこもりの人たちが社会と繋がるときにも通じるのでは。障害福祉の支援職としても知っておきたいことですね。読みます、はい。


 山田志穗@yamadashiho_2025年3月15日買った@ スーパーカボスプラスゲオ 二の宮本店ガツンとくるタイトルと表紙。SNSで何度か見かけているうちに気になってきて、書店でめくったらいい感じだったので買った。楽しみ。
山田志穗@yamadashiho_2025年3月15日買った@ スーパーカボスプラスゲオ 二の宮本店ガツンとくるタイトルと表紙。SNSで何度か見かけているうちに気になってきて、書店でめくったらいい感じだったので買った。楽しみ。


 yui@yui2025年3月5日読み始めた今年いろんな人にすすめている本。 自分は、ある側面ではマイノリティで、またある側面ではマジョリティで、多面的。マイノリティが変わるのではなく、マジョリティがマジョリティを変えていくためにどうしたらいいか考える。
yui@yui2025年3月5日読み始めた今年いろんな人にすすめている本。 自分は、ある側面ではマイノリティで、またある側面ではマジョリティで、多面的。マイノリティが変わるのではなく、マジョリティがマジョリティを変えていくためにどうしたらいいか考える。