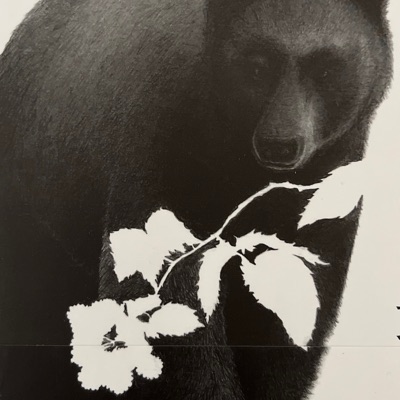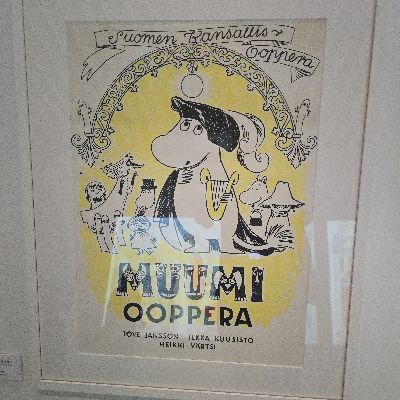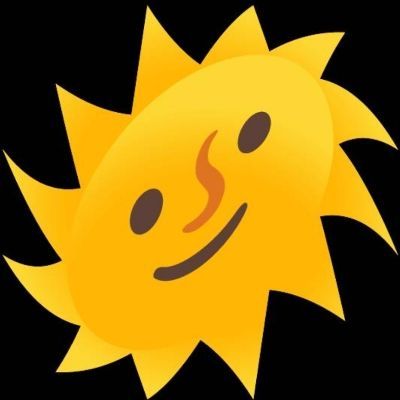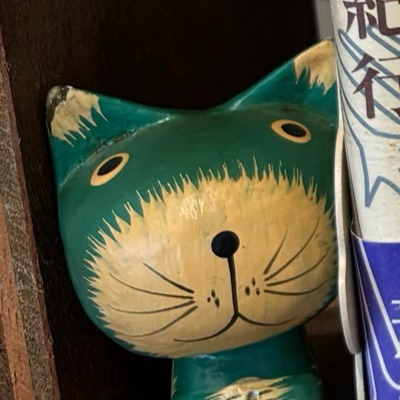アイヌがまなざす
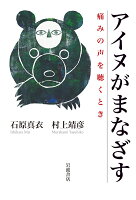
27件の記録
 あずき(小豆書房)@azukishobo2025年6月25日まだ読んでる第2部まで完。 第4章は、なるほど、そういうことか……と。分かってなかった、そういうことなんだな、と。 そして第5章は、なるほど、そうだな、と思う部分と、うーん、そうなのかなぁ?な部分、両方あった。 考え続けること。
あずき(小豆書房)@azukishobo2025年6月25日まだ読んでる第2部まで完。 第4章は、なるほど、そういうことか……と。分かってなかった、そういうことなんだな、と。 そして第5章は、なるほど、そうだな、と思う部分と、うーん、そうなのかなぁ?な部分、両方あった。 考え続けること。

 あずき(小豆書房)@azukishobo2025年4月28日読んでる第一部まで完。 「平等幻想」にハッとさせられる。置かれた立場や状況を完全に排除することはできない。 沈黙と言葉の過剰の振り子構造。癒しが必要。 多和田葉子さんの『地球にちりばめられて』(フィクションではあるが)を思い出す。 言語化されることで傷つくことがある。 言語化することで癒されることがある。 語る言葉をもつことはとても大事。 自分の癒しのために安易に言語化することは避けたい。
あずき(小豆書房)@azukishobo2025年4月28日読んでる第一部まで完。 「平等幻想」にハッとさせられる。置かれた立場や状況を完全に排除することはできない。 沈黙と言葉の過剰の振り子構造。癒しが必要。 多和田葉子さんの『地球にちりばめられて』(フィクションではあるが)を思い出す。 言語化されることで傷つくことがある。 言語化することで癒されることがある。 語る言葉をもつことはとても大事。 自分の癒しのために安易に言語化することは避けたい。




 あずき(小豆書房)@azukishobo2025年4月17日読み始めたひとまず序章完。 ここでは少しだけ触れられていた1903年の「人類館事件」だが、恥ずかしながらまったく知らなかったので少し調べてみた。かなり衝撃的な内容だった。しかし日本もまた西洋から対比されまなざされてきたという背景もあるのだろう。差別構造の連鎖が悲しい。
あずき(小豆書房)@azukishobo2025年4月17日読み始めたひとまず序章完。 ここでは少しだけ触れられていた1903年の「人類館事件」だが、恥ずかしながらまったく知らなかったので少し調べてみた。かなり衝撃的な内容だった。しかし日本もまた西洋から対比されまなざされてきたという背景もあるのだろう。差別構造の連鎖が悲しい。

 ユウキ@sonidori7772025年4月3日読み終わった借りてきた多重構造になってる差別/植民地主義の招いたアイデンティティの消失と現状まで続く差別、今生きているアイヌへのイメージ消費と無自覚で押し付ける偏見、に自覚がまったくない私たち…読めて良かった本だった。買おう。 内容メモ: 「「アイヌ文化」なるもの自体、和人が研究や観光という植民地主義的なまなざしのもとで規定したものである。」「まなざすことは人を人でないモノへと押し込める。」 入植者による強制移住、差別と暴力が文化、アイデンティティのつながりを阻んだゆえにアイヌ文化に愛着を持てないが、国家や法律が規定する文化がその限定的イメージをつくる/ アイデンティティや文化を持たないが、出自がアイヌ「民族」であることがゆえにヘイトクライムの対象になる/アイヌイメージからはみ出る人々を阻害する/ (例:金カム)コスメティックな消費は見せかけのインクルージョンを生み出し、根本的な課題を不可視化する/ マジョリティ女性は同じ女性としてマイノリティ女性を包括してしまい、マイノリティ女性の阻害を深め、レイシズムの暴力と共犯をしてしまってもいた/アイヌに寄り添っているつもりの知識人や支援者がイメージに押し込め、思想的消費を行使している
ユウキ@sonidori7772025年4月3日読み終わった借りてきた多重構造になってる差別/植民地主義の招いたアイデンティティの消失と現状まで続く差別、今生きているアイヌへのイメージ消費と無自覚で押し付ける偏見、に自覚がまったくない私たち…読めて良かった本だった。買おう。 内容メモ: 「「アイヌ文化」なるもの自体、和人が研究や観光という植民地主義的なまなざしのもとで規定したものである。」「まなざすことは人を人でないモノへと押し込める。」 入植者による強制移住、差別と暴力が文化、アイデンティティのつながりを阻んだゆえにアイヌ文化に愛着を持てないが、国家や法律が規定する文化がその限定的イメージをつくる/ アイデンティティや文化を持たないが、出自がアイヌ「民族」であることがゆえにヘイトクライムの対象になる/アイヌイメージからはみ出る人々を阻害する/ (例:金カム)コスメティックな消費は見せかけのインクルージョンを生み出し、根本的な課題を不可視化する/ マジョリティ女性は同じ女性としてマイノリティ女性を包括してしまい、マイノリティ女性の阻害を深め、レイシズムの暴力と共犯をしてしまってもいた/アイヌに寄り添っているつもりの知識人や支援者がイメージに押し込め、思想的消費を行使している