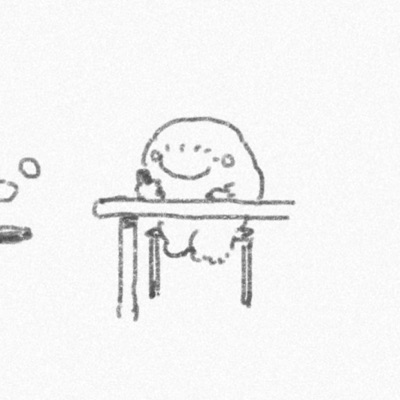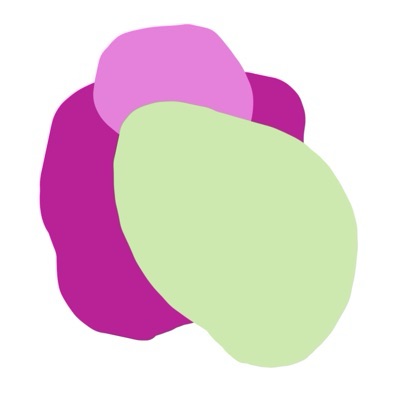増補 害虫の誕生

38件の記録
 なにわ@shidunowodamaki_322025年12月29日読み終わった環境史を専門とする筆者が、日本における「害虫と人間の関係の歴史」について論じている。 「害虫」という概念は近代の産物である。もちろん近代以前も、人々は農作物を害する虫に悩まされていた。だが、「害虫」という言葉はなく、それらはたたりなど、人間の力を超えるものと考えられていた。その例として「虫送り」や、「駆虫札」がある。 しかし明治維新が起こり西洋科学が流入すると、そのような儀式は無知蒙昧なものとされ、政府は警官を動員し、農民に強制的に害虫防除や様々な農業技術を実行させた。さらには農民の自然観を変えるため、「害虫駆除唱歌」を作ったり、賞金付きの「害虫取り競争」を行ったりした。 また、植民地獲得や近代都市化でマラリアやチフスが流行すると、それらの病気を媒介する虫も「衛生害虫」として排除の対象になった。さらに、戦争のために開発された毒ガスが殺虫剤に応用され、その逆の動きも起こった。 現代では当然の概念も、近代化によって作り上げられたものなのかもしれない、と身の回りの生活を見直すきっかけになった。また、自然が改変され、監視される現代において、「自然と人間の関係」はどうあるべきか、考えさせられた。
なにわ@shidunowodamaki_322025年12月29日読み終わった環境史を専門とする筆者が、日本における「害虫と人間の関係の歴史」について論じている。 「害虫」という概念は近代の産物である。もちろん近代以前も、人々は農作物を害する虫に悩まされていた。だが、「害虫」という言葉はなく、それらはたたりなど、人間の力を超えるものと考えられていた。その例として「虫送り」や、「駆虫札」がある。 しかし明治維新が起こり西洋科学が流入すると、そのような儀式は無知蒙昧なものとされ、政府は警官を動員し、農民に強制的に害虫防除や様々な農業技術を実行させた。さらには農民の自然観を変えるため、「害虫駆除唱歌」を作ったり、賞金付きの「害虫取り競争」を行ったりした。 また、植民地獲得や近代都市化でマラリアやチフスが流行すると、それらの病気を媒介する虫も「衛生害虫」として排除の対象になった。さらに、戦争のために開発された毒ガスが殺虫剤に応用され、その逆の動きも起こった。 現代では当然の概念も、近代化によって作り上げられたものなのかもしれない、と身の回りの生活を見直すきっかけになった。また、自然が改変され、監視される現代において、「自然と人間の関係」はどうあるべきか、考えさせられた。 ジクロロ@jirowcrew2025年10月10日ちょっと開いた「あらゆる空間はつねに監視され、すべての生物がモニタリングされている。とりわけかつて害虫とされてきた虫たちは注意深く監視され、一定以上の被害をもたらす前に予防される。これらの虫たちは、もはやヒトがつくった環境に生きる共生生物のひとつになる。そのときヒトが排除してきた〈害虫〉という存在は消滅するのである。」
ジクロロ@jirowcrew2025年10月10日ちょっと開いた「あらゆる空間はつねに監視され、すべての生物がモニタリングされている。とりわけかつて害虫とされてきた虫たちは注意深く監視され、一定以上の被害をもたらす前に予防される。これらの虫たちは、もはやヒトがつくった環境に生きる共生生物のひとつになる。そのときヒトが排除してきた〈害虫〉という存在は消滅するのである。」 JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月2日読み終わった@ 電車第四章3読む。 太平洋戦争の開戦、マラリア媒介蚊の駆除、アメリカにおける新しい殺虫剤DDTの大量生産、日本における「衛星昆虫学」という新しい分野の研究者集団の成立。さらには、駆除・根絶とは逆に、〈害虫〉を増やすという発想も。 〈〈害虫〉を根絶して人間を救うか。〈害虫〉を増殖して人間を殺すか。昆虫学者たちの目標は、太平洋の両岸でまったく反対であった。けれども〈害虫〉をコントロールし、人間との関係をつくりかえようとした点では、両者が目指したところは同じである。〉(197頁) エピローグも読む。安易な二分法に嵌まらないこと大事。 〈「エコロジーか自然破壊か」という二分法で歴史を描くことは、現在の目線で過去を評価し、断罪してしまうことになってしまう。/最近の環境史研究[...]では、「自然と人間の関係」がそれぞれの時代の社会的な状況のなかから、どのように形成されたかを明らかにすることが求められている。〉(204頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年8月2日読み終わった@ 電車第四章3読む。 太平洋戦争の開戦、マラリア媒介蚊の駆除、アメリカにおける新しい殺虫剤DDTの大量生産、日本における「衛星昆虫学」という新しい分野の研究者集団の成立。さらには、駆除・根絶とは逆に、〈害虫〉を増やすという発想も。 〈〈害虫〉を根絶して人間を救うか。〈害虫〉を増殖して人間を殺すか。昆虫学者たちの目標は、太平洋の両岸でまったく反対であった。けれども〈害虫〉をコントロールし、人間との関係をつくりかえようとした点では、両者が目指したところは同じである。〉(197頁) エピローグも読む。安易な二分法に嵌まらないこと大事。 〈「エコロジーか自然破壊か」という二分法で歴史を描くことは、現在の目線で過去を評価し、断罪してしまうことになってしまう。/最近の環境史研究[...]では、「自然と人間の関係」がそれぞれの時代の社会的な状況のなかから、どのように形成されたかを明らかにすることが求められている。〉(204頁)



 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月31日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第四章2まで読む。 近代日本では〈害虫〉を排除する「技術」がどのように発展し、また戦争によってどのような影響を受けてきたのか。天敵導入、誘蛾灯、毒ガスと殺虫剤の事例。 〈むしろ歴史から学ぶことは、戦争がいかに科学技術のあり方を変え、さらには「自然と人間との関係」を変えてきたのかということである。近代国家にとって戦争とは、国民すべてを動員する総力戦である。[...]科学技術を総動員して大規模に敵を倒す軍事テクノロジーと、科学の力で自然を制御するテクノロジーのあいだには共通性がある。両者[昆虫学者と化学者]のあいだで研究成果を利用しあい、科学的な知識を行き来させるのは、近代国家にとっては自然なことであった。〉(177頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月31日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅第四章2まで読む。 近代日本では〈害虫〉を排除する「技術」がどのように発展し、また戦争によってどのような影響を受けてきたのか。天敵導入、誘蛾灯、毒ガスと殺虫剤の事例。 〈むしろ歴史から学ぶことは、戦争がいかに科学技術のあり方を変え、さらには「自然と人間との関係」を変えてきたのかということである。近代国家にとって戦争とは、国民すべてを動員する総力戦である。[...]科学技術を総動員して大規模に敵を倒す軍事テクノロジーと、科学の力で自然を制御するテクノロジーのあいだには共通性がある。両者[昆虫学者と化学者]のあいだで研究成果を利用しあい、科学的な知識を行き来させるのは、近代国家にとっては自然なことであった。〉(177頁)
 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月30日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第三章3読む。 身近な虫にすぎなかったハエが〈衛生害虫〉として排除の対象となっていく過程について。言い換えれば、なぜ都市市民たちはハエを徹底的に排除することを受け入れていったのか。コレラとの結びつき、「不潔」な「スラム」に注がれた排除のまなざしの延長線上に位置する「蠅取りデー」、そして「清潔」で「美しい」都市を目指すことへのコミット。 〈「害虫と人間の関係」は、科学的な発見によって突然変わるものではなく、科学研究と社会的な文脈の両方が絡まり合いながらゆっくり変容していく〉(139頁)というのが面白い。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月30日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第三章3読む。 身近な虫にすぎなかったハエが〈衛生害虫〉として排除の対象となっていく過程について。言い換えれば、なぜ都市市民たちはハエを徹底的に排除することを受け入れていったのか。コレラとの結びつき、「不潔」な「スラム」に注がれた排除のまなざしの延長線上に位置する「蠅取りデー」、そして「清潔」で「美しい」都市を目指すことへのコミット。 〈「害虫と人間の関係」は、科学的な発見によって突然変わるものではなく、科学研究と社会的な文脈の両方が絡まり合いながらゆっくり変容していく〉(139頁)というのが面白い。


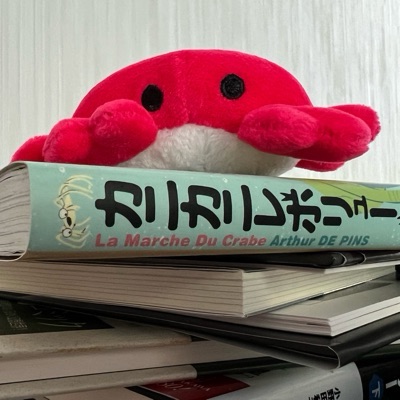


 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月29日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第三章2まで。〈衛生害虫〉の誕生過程、蚊の根絶(対蚊法)と病原体の駆逐(対原虫法)とのあいだでしばしば見られた対立、日本の植民地統治。読みたかった章に突入。 〈こうして日本におけるマラリア研究は、北海道と台湾という帝国の両端ではじまった。これは決して偶然ではない。北海道は新たに開拓された内国植民地であり、台湾は文字通り植民地である。そこに入植したのは、マラリアに免疫力のない本土の人々である。その上、森を切り開くと、日当たりのよい水たまりのような、マラリア媒介蚊が発生しやすい環境がつくられてしまう。このように入植者のあいだで流行する熱帯病は多くの場合、自然環境の改造によって引き起こされる「開発原病」であった。〉(116-117頁) 〈かつて日本で〈農業害虫〉の駆除が強制されたように、植民地台湾においても、啓蒙運動と警察権力の両方でもって〈衛生害虫〉の根絶が目指されたのである。〉(124頁)
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月29日まだ読んでるお風呂読書@ 自宅第三章2まで。〈衛生害虫〉の誕生過程、蚊の根絶(対蚊法)と病原体の駆逐(対原虫法)とのあいだでしばしば見られた対立、日本の植民地統治。読みたかった章に突入。 〈こうして日本におけるマラリア研究は、北海道と台湾という帝国の両端ではじまった。これは決して偶然ではない。北海道は新たに開拓された内国植民地であり、台湾は文字通り植民地である。そこに入植したのは、マラリアに免疫力のない本土の人々である。その上、森を切り開くと、日当たりのよい水たまりのような、マラリア媒介蚊が発生しやすい環境がつくられてしまう。このように入植者のあいだで流行する熱帯病は多くの場合、自然環境の改造によって引き起こされる「開発原病」であった。〉(116-117頁) 〈かつて日本で〈農業害虫〉の駆除が強制されたように、植民地台湾においても、啓蒙運動と警察権力の両方でもって〈衛生害虫〉の根絶が目指されたのである。〉(124頁)


 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月29日まだ読んでる@ 電車第二章4読む。民間昆虫学者・名和靖の生涯と「昆虫思想」。様々なメディアやアクターを利用しての啓蒙と教育の話、面白かった。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月29日まだ読んでる@ 電車第二章4読む。民間昆虫学者・名和靖の生涯と「昆虫思想」。様々なメディアやアクターを利用しての啓蒙と教育の話、面白かった。
 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月28日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅『農事月報』というメディアが果たした役割、国家が求める自然とのつきあい方vs.農民たちの自然観(明治末期)、その先例としての「筑後稲株騒動」、等々。第二章3まで読む。面白いな〜
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月28日まだ読んでる就寝前読書お風呂読書@ 自宅『農事月報』というメディアが果たした役割、国家が求める自然とのつきあい方vs.農民たちの自然観(明治末期)、その先例としての「筑後稲株騒動」、等々。第二章3まで読む。面白いな〜

 JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月27日読み始めた就寝前読書お風呂読書@ 自宅先日試聴した『生き物の死なせ方』合評会が面白かったので、関連書(関連しそうな本?)としてこちらも読む。不真面目な読者なので補章、プロローグの順で第一章まで。
JUMPEI AMANO@Amanong22025年7月27日読み始めた就寝前読書お風呂読書@ 自宅先日試聴した『生き物の死なせ方』合評会が面白かったので、関連書(関連しそうな本?)としてこちらも読む。不真面目な読者なので補章、プロローグの順で第一章まで。
 こんめ@conconcocon2025年6月29日読んでる江戸時代のところまで読了。 元々民俗をかじっているので、虫送りの行事はとても身近で、様々な虫送りのやり方、人形、などなど見てきたけれど、こちらを読んでその背景の解像度が上がった。 言われてみれば確かに、その辺にいる虫がどのように生まれて成長して成虫になっているのか、自身の目で見て確かめることができた例は少ない。(ユスリカやコバエ、ガガンボなどなど…普通に生活してて、その成長過程を追えるかというと、なかなか難しい…) となると、虫は自然に発生する、とした昔の人々の考え方は納得ができる。し、それを天災と捉えて、信仰に頼った駆除方法を行ったのも、さもありなん… 興味深いのは、田んぼに油を注ぐという、かなり(今で言う)科学的な駆除方法と、上記の虫送りが同時に、並行的に行われていたことである。 江戸の人々にとっては、どちらも、実用的な方法だったのだろうなぁと当時の生活に思いを馳せてみた。
こんめ@conconcocon2025年6月29日読んでる江戸時代のところまで読了。 元々民俗をかじっているので、虫送りの行事はとても身近で、様々な虫送りのやり方、人形、などなど見てきたけれど、こちらを読んでその背景の解像度が上がった。 言われてみれば確かに、その辺にいる虫がどのように生まれて成長して成虫になっているのか、自身の目で見て確かめることができた例は少ない。(ユスリカやコバエ、ガガンボなどなど…普通に生活してて、その成長過程を追えるかというと、なかなか難しい…) となると、虫は自然に発生する、とした昔の人々の考え方は納得ができる。し、それを天災と捉えて、信仰に頼った駆除方法を行ったのも、さもありなん… 興味深いのは、田んぼに油を注ぐという、かなり(今で言う)科学的な駆除方法と、上記の虫送りが同時に、並行的に行われていたことである。 江戸の人々にとっては、どちらも、実用的な方法だったのだろうなぁと当時の生活に思いを馳せてみた。