独自性のつくり方
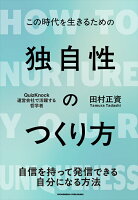
25件の記録
 俐央@rio-icns2025年11月20日買った読み終わった青山ブックセンターで平積みされていて、なんとなく手に取ったのだけど、良かった。 著者自身の経験や哲学研究から編まれているのだけど、語り口が読みやすい。
俐央@rio-icns2025年11月20日買った読み終わった青山ブックセンターで平積みされていて、なんとなく手に取ったのだけど、良かった。 著者自身の経験や哲学研究から編まれているのだけど、語り口が読みやすい。
 毎分毎秒@maimmais2025年10月19日p.20 他の人たちに喜ばれるような価値を提供するためには、「誰か」の一例としての自分が喜びを持てる場所を見つける必要があります。まずは自分のために、自分自身の自己満足を見つけること。
毎分毎秒@maimmais2025年10月19日p.20 他の人たちに喜ばれるような価値を提供するためには、「誰か」の一例としての自分が喜びを持てる場所を見つける必要があります。まずは自分のために、自分自身の自己満足を見つけること。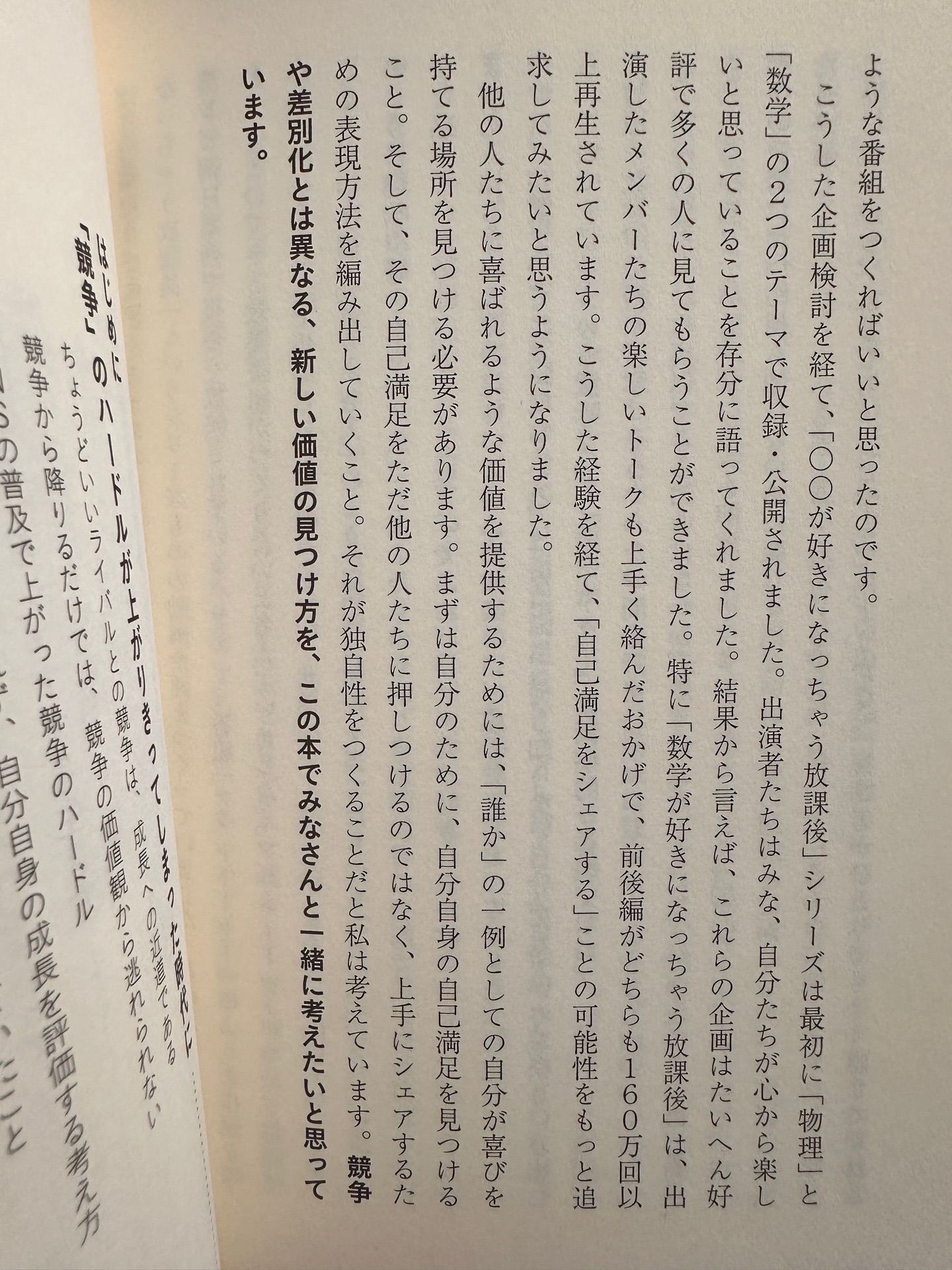
 毎分毎秒@maimmais2025年10月19日p.10 夜寝るときに、明日も頑張らなければならないと、自分はどれくらい頑張ればこの先も生き残れるのだろうかと、こなさなければいけないタスクをずっと気にしながら、心配事を抱えて生きていくのは御免被りたい。
毎分毎秒@maimmais2025年10月19日p.10 夜寝るときに、明日も頑張らなければならないと、自分はどれくらい頑張ればこの先も生き残れるのだろうかと、こなさなければいけないタスクをずっと気にしながら、心配事を抱えて生きていくのは御免被りたい。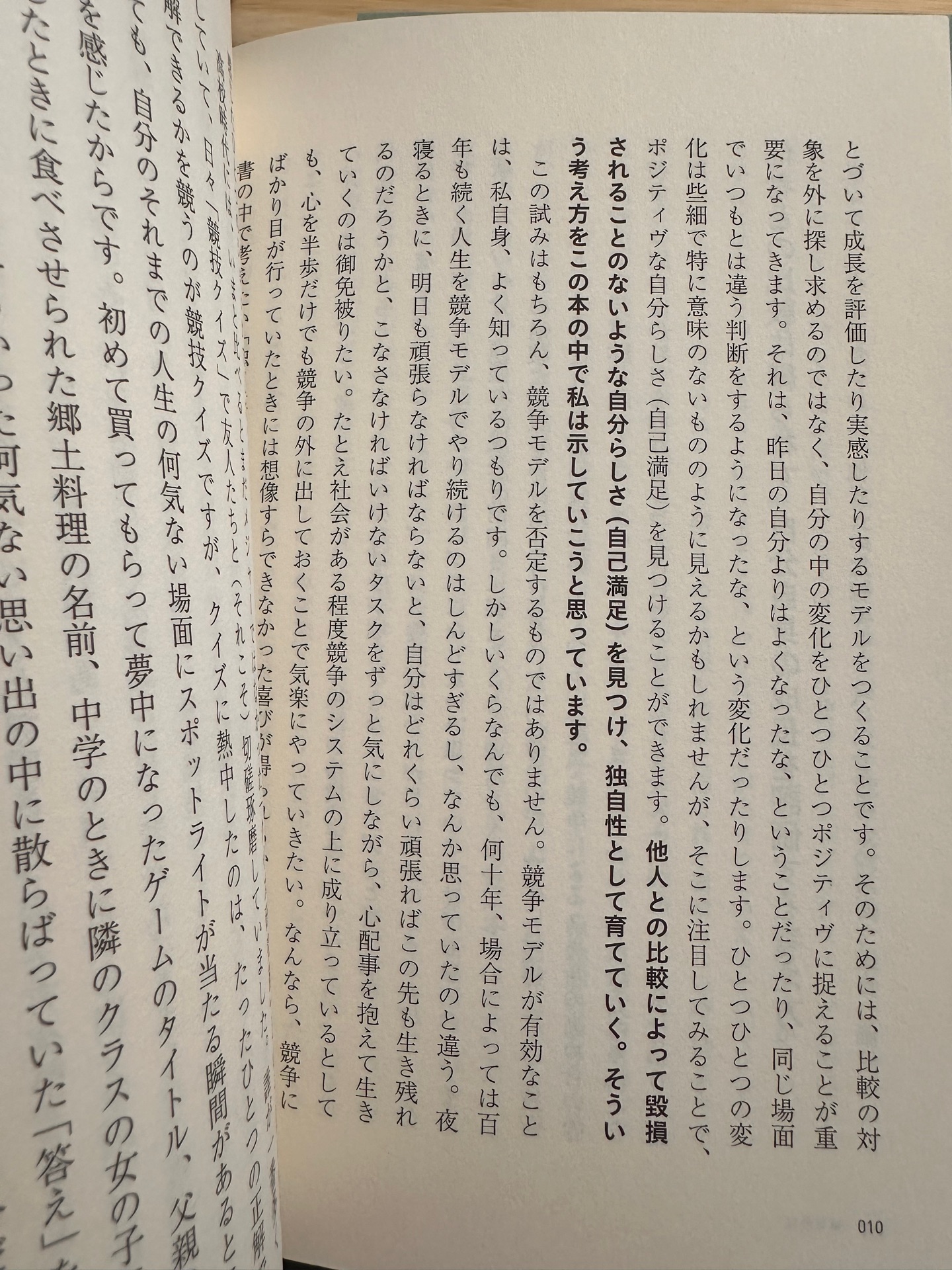
- mm7785mm@pkflddvbwldzplln2122025年9月14日最近ちゃんみなのオーディション番組を観ている。気になったのがちゃんみな何回「自分に自信を持って」って言うんやろってこと。みんな十分に歌って踊れてすごく頑張ってるのに。それぐらい今のSNS当たり前で育った世代の子たちは人と比べすぎているんだと思う。 というわけで今の気分にぴったりすぎるし田村さんのトークイベントも面白かったので読むのが楽しみ。


 オケタニ@oketani2025年9月2日読んでる競走から降りて自己満足の時間を取り戻せ ・クイズと哲学に傾倒した著者が会社員になって感じた成長比較ゲームのもたなさ。競走からは降りることを前提とする。そのなかで、リセットや転生ができない人生において過去から現在を独自性として受け止めることを探る趣旨になる? 「誰かを出し抜くことを考えるのではなく、自分の世界に居座ったまま外側にある社会とのつながりを思い出していくこと」 ・思い出していく、がフックになりそう。目次を見るに"自己満足の解像度を高める"本か? ・1章。独自性の種は自己満足。世界と自分の"あいだ"をメタ的に見て表現することで自分を面白がれる、余裕が生まれる。 <はちくちダブルヒガシのこれ好きやねんのコーナーの独自の視点を要求するくだり>じゃん。 ・2章。メルロ=ポンティを参考にした「経験」までの道筋。「環境」「技能・関心」「行動目標」(街に住んでて、甘いものが好きで、近所のケーキ屋が気になる→ケーキ屋に行く) ・図と地の話は割愛。おそらくこの本自体が地を意識させるための図を狙っている。 ・3章。違和感を感じる瞬間「異文化」「自分の持たない技能を持つ人との会話」「自分の変化(ポジティブもネガティブも)」 本の真ん中にTips集が来るの面白い。違和感を感じてみよう、それを記録しよう、は確かにビジネス本ぽい。メモ魔的なやつもでてくる。 ・4章。自分の視点を養ううえで、連続性(MCU予習ルート)だけでなく共通性(別ジャンルのものを強制的に括る何かを考える)ことの面白がり方。これはビジネスマンも面白いかも。批評的視点の導入。宇野常寛も参考文献に出てくる。 ・自己満足を自覚して表現することで「共通言語」を作りうる可能性があることの説明。鉤括弧の活用の有用性は初めて見た気がする。 ・クイズの出題者になれ。出題者に必要なホスピタリティ(自己満足をベースにした地の共有)。良き回答者を目指すことと競争社会から降りれないことは似ている。 (・そしてそれはテレビ文化によって醸成されてない?正解は90秒後システム。予測できる範囲が多いという勘違いによるレスバ。) ・最終章のまとめでは、自己満足の概念をクイズ的と批評的の二つの角度からまとめる。 ↑ひとまず読書中メモ ***
オケタニ@oketani2025年9月2日読んでる競走から降りて自己満足の時間を取り戻せ ・クイズと哲学に傾倒した著者が会社員になって感じた成長比較ゲームのもたなさ。競走からは降りることを前提とする。そのなかで、リセットや転生ができない人生において過去から現在を独自性として受け止めることを探る趣旨になる? 「誰かを出し抜くことを考えるのではなく、自分の世界に居座ったまま外側にある社会とのつながりを思い出していくこと」 ・思い出していく、がフックになりそう。目次を見るに"自己満足の解像度を高める"本か? ・1章。独自性の種は自己満足。世界と自分の"あいだ"をメタ的に見て表現することで自分を面白がれる、余裕が生まれる。 <はちくちダブルヒガシのこれ好きやねんのコーナーの独自の視点を要求するくだり>じゃん。 ・2章。メルロ=ポンティを参考にした「経験」までの道筋。「環境」「技能・関心」「行動目標」(街に住んでて、甘いものが好きで、近所のケーキ屋が気になる→ケーキ屋に行く) ・図と地の話は割愛。おそらくこの本自体が地を意識させるための図を狙っている。 ・3章。違和感を感じる瞬間「異文化」「自分の持たない技能を持つ人との会話」「自分の変化(ポジティブもネガティブも)」 本の真ん中にTips集が来るの面白い。違和感を感じてみよう、それを記録しよう、は確かにビジネス本ぽい。メモ魔的なやつもでてくる。 ・4章。自分の視点を養ううえで、連続性(MCU予習ルート)だけでなく共通性(別ジャンルのものを強制的に括る何かを考える)ことの面白がり方。これはビジネスマンも面白いかも。批評的視点の導入。宇野常寛も参考文献に出てくる。 ・自己満足を自覚して表現することで「共通言語」を作りうる可能性があることの説明。鉤括弧の活用の有用性は初めて見た気がする。 ・クイズの出題者になれ。出題者に必要なホスピタリティ(自己満足をベースにした地の共有)。良き回答者を目指すことと競争社会から降りれないことは似ている。 (・そしてそれはテレビ文化によって醸成されてない?正解は90秒後システム。予測できる範囲が多いという勘違いによるレスバ。) ・最終章のまとめでは、自己満足の概念をクイズ的と批評的の二つの角度からまとめる。 ↑ひとまず読書中メモ ***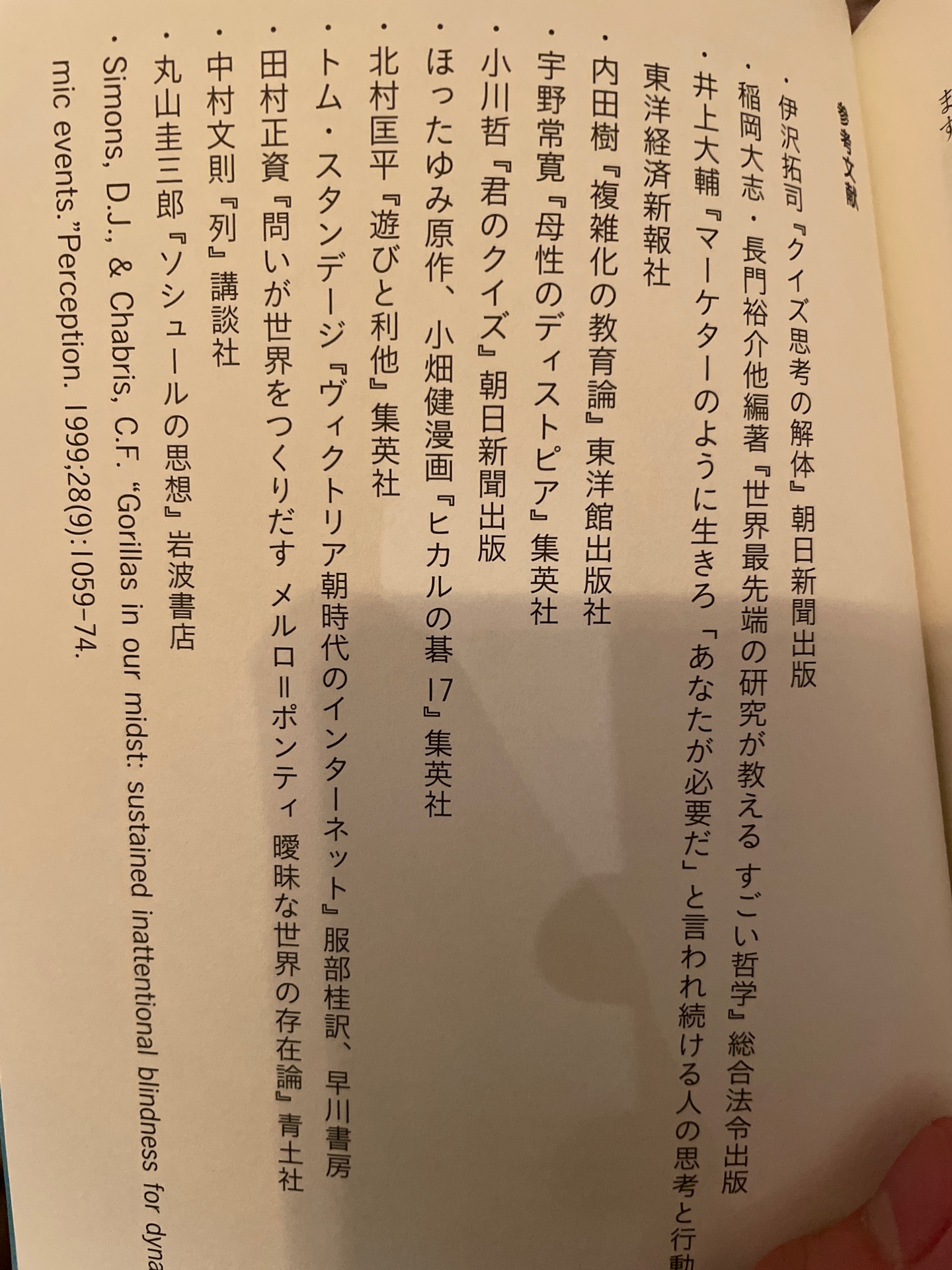


 いっちー@icchii3172025年8月21日気になる知り合いに教えてもらった。なんでも三宅夏帆さんが「初めて自分より文章が上手いと思った」的なことを話していたらしい(伝聞なので良くないです)。 興味あったけど感想を読んでるとそこまですぐに読まなくてもいいか、というテンションになってきた。勝手に、千葉雅也さん『センスの哲学』に近いのではないかと思ってる。坂口恭平さん『生きのびるための事務』にも近いのかな?と。使ってる論理はそれぞれ別だけど、言わんとすることは似ていそう。こういう話で重要なのは、結局実践ありきなのだよなー。その実践に、何か風穴を開けれる衝撃がありそうだったら買うかも。図書館にまだなかったから今度本屋で立ち読みしてみようっと。
いっちー@icchii3172025年8月21日気になる知り合いに教えてもらった。なんでも三宅夏帆さんが「初めて自分より文章が上手いと思った」的なことを話していたらしい(伝聞なので良くないです)。 興味あったけど感想を読んでるとそこまですぐに読まなくてもいいか、というテンションになってきた。勝手に、千葉雅也さん『センスの哲学』に近いのではないかと思ってる。坂口恭平さん『生きのびるための事務』にも近いのかな?と。使ってる論理はそれぞれ別だけど、言わんとすることは似ていそう。こういう話で重要なのは、結局実践ありきなのだよなー。その実践に、何か風穴を開けれる衝撃がありそうだったら買うかも。図書館にまだなかったから今度本屋で立ち読みしてみようっと。
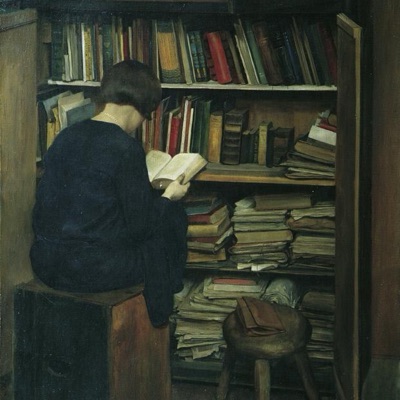 うども@udo_momo2025年8月20日読み終わっためちゃくちゃ良かった… 色々な評価が見知らぬ人によってジャッジされる現代でどのような事に自分は興味を持っているか、なぜこのことに違和感を感じるかを深く考えて言語化する事が自分の人生を少しでも軽くする方法だと確信した
うども@udo_momo2025年8月20日読み終わっためちゃくちゃ良かった… 色々な評価が見知らぬ人によってジャッジされる現代でどのような事に自分は興味を持っているか、なぜこのことに違和感を感じるかを深く考えて言語化する事が自分の人生を少しでも軽くする方法だと確信した
 Eukalyptus@euka_inrevarld2025年8月1日読み終わったこれを読んでハッとしたのは、私は本書のほとんどを「当たり前に」行ってきているという点だ。 読めば読むほど、「やっぱりそうだよね」「これいつもの私じゃん」と思う内容ばかり。 なので、私からしてみれば、薄めの本だし、内容は薄くはないのはわかっているが、目新しさがなかった。 そこで思うのは、もしかしたら一般的にはこういった考え方が不足しているのか、ということ。故に書籍化されているのか、と。 私は田村正資さんが書いた本だから読んだだけで、その『独自性』を欲して買う人の方が大半なのかもしれないと。 私ら世代の人たちは特にであるが、昨今の人間は「ライフステージ」というものショートカットしようと躍起になっているのだよ。 コストパフォーマンスや効率化、そんなワードがネットワークでは飛び交っている。 それほど、何かから逃げたいのか、スキップしたいのか…待てない人間が増えてきているかもしれない。 そんな時にこの本は「待った」をかけてくれる。私はデフォルトでできているので、再構築でもしないと伝えることが難しいが、何故そう感じたか、や何故そう思うか、といういわゆる「内省」にフォーカスすると本書の内容のような『独自性』を見出せるかもしれない。 そうそう、根本的に「内省的でない人」だったり、物事の奥行きを考えられず、「平面的にしか捉えられない考え方」の人は、この本を読んでも体得は難しいと思う。元々、あるものに対して多角的(立体的でも可)に捉えるタイプの人には理解がしやすいと思う。そういう文体だからだ。 *とてもざっくりと言うならば、MBTIでいう「N」と人には読みやすく、「S」の人には読みづらいかもしれない。
Eukalyptus@euka_inrevarld2025年8月1日読み終わったこれを読んでハッとしたのは、私は本書のほとんどを「当たり前に」行ってきているという点だ。 読めば読むほど、「やっぱりそうだよね」「これいつもの私じゃん」と思う内容ばかり。 なので、私からしてみれば、薄めの本だし、内容は薄くはないのはわかっているが、目新しさがなかった。 そこで思うのは、もしかしたら一般的にはこういった考え方が不足しているのか、ということ。故に書籍化されているのか、と。 私は田村正資さんが書いた本だから読んだだけで、その『独自性』を欲して買う人の方が大半なのかもしれないと。 私ら世代の人たちは特にであるが、昨今の人間は「ライフステージ」というものショートカットしようと躍起になっているのだよ。 コストパフォーマンスや効率化、そんなワードがネットワークでは飛び交っている。 それほど、何かから逃げたいのか、スキップしたいのか…待てない人間が増えてきているかもしれない。 そんな時にこの本は「待った」をかけてくれる。私はデフォルトでできているので、再構築でもしないと伝えることが難しいが、何故そう感じたか、や何故そう思うか、といういわゆる「内省」にフォーカスすると本書の内容のような『独自性』を見出せるかもしれない。 そうそう、根本的に「内省的でない人」だったり、物事の奥行きを考えられず、「平面的にしか捉えられない考え方」の人は、この本を読んでも体得は難しいと思う。元々、あるものに対して多角的(立体的でも可)に捉えるタイプの人には理解がしやすいと思う。そういう文体だからだ。 *とてもざっくりと言うならば、MBTIでいう「N」と人には読みやすく、「S」の人には読みづらいかもしれない。
















