
オケタニ
@oketani887
🆕
- 2025年9月2日
- 2025年9月2日
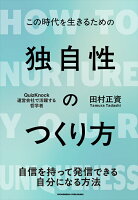 独自性のつくり方田村正資読んでる競走から降りて自己満足の時間を取り戻せ ・クイズと哲学に傾倒した著者が会社員になって感じた成長比較ゲームのもたなさ。競走からは降りることを前提とする。そのなかで、リセットや転生ができない人生において過去から現在を独自性として受け止めることを探る趣旨になる? 「誰かを出し抜くことを考えるのではなく、自分の世界に居座ったまま外側にある社会とのつながりを思い出していくこと」 ・思い出していく、がフックになりそう。目次を見るに"自己満足の解像度を高める"本か? ・1章。独自性の種は自己満足。世界と自分の"あいだ"をメタ的に見て表現することで自分を面白がれる、余裕が生まれる。 <はちくちダブルヒガシのこれ好きやねんのコーナーの独自の視点を要求するくだり>じゃん。 ・2章。メルロ=ポンティを参考にした「経験」までの道筋。「環境」「技能・関心」「行動目標」(街に住んでて、甘いものが好きで、近所のケーキ屋が気になる→ケーキ屋に行く) ・図と地の話は割愛。おそらくこの本自体が地を意識させるための図を狙っている。 ・3章。違和感を感じる瞬間「異文化」「自分の持たない技能を持つ人との会話」「自分の変化(ポジティブもネガティブも)」 本の真ん中にTips集が来るの面白い。違和感を感じてみよう、それを記録しよう、は確かにビジネス本ぽい。メモ魔的なやつもでてくる。 ・4章。自分の視点を養ううえで、連続性(MCU予習ルート)だけでなく共通性(別ジャンルのものを強制的に括る何かを考える)ことの面白がり方。これはビジネスマンも面白いかも。批評的視点の導入。宇野常寛も参考文献に出てくる。 ・自己満足を自覚して表現することで「共通言語」を作りうる可能性があることの説明。鉤括弧の活用の有用性は初めて見た気がする。 ・クイズの出題者になれ。出題者に必要なホスピタリティ(自己満足をベースにした地の共有)。良き回答者を目指すことと競争社会から降りれないことは似ている。 (・そしてそれはテレビ文化によって醸成されてない?正解は90秒後システム。予測できる範囲が多いという勘違いによるレスバ。) ・最終章のまとめでは、自己満足の概念をクイズ的と批評的の二つの角度からまとめる。 ↑ひとまず読書中メモ ***
独自性のつくり方田村正資読んでる競走から降りて自己満足の時間を取り戻せ ・クイズと哲学に傾倒した著者が会社員になって感じた成長比較ゲームのもたなさ。競走からは降りることを前提とする。そのなかで、リセットや転生ができない人生において過去から現在を独自性として受け止めることを探る趣旨になる? 「誰かを出し抜くことを考えるのではなく、自分の世界に居座ったまま外側にある社会とのつながりを思い出していくこと」 ・思い出していく、がフックになりそう。目次を見るに"自己満足の解像度を高める"本か? ・1章。独自性の種は自己満足。世界と自分の"あいだ"をメタ的に見て表現することで自分を面白がれる、余裕が生まれる。 <はちくちダブルヒガシのこれ好きやねんのコーナーの独自の視点を要求するくだり>じゃん。 ・2章。メルロ=ポンティを参考にした「経験」までの道筋。「環境」「技能・関心」「行動目標」(街に住んでて、甘いものが好きで、近所のケーキ屋が気になる→ケーキ屋に行く) ・図と地の話は割愛。おそらくこの本自体が地を意識させるための図を狙っている。 ・3章。違和感を感じる瞬間「異文化」「自分の持たない技能を持つ人との会話」「自分の変化(ポジティブもネガティブも)」 本の真ん中にTips集が来るの面白い。違和感を感じてみよう、それを記録しよう、は確かにビジネス本ぽい。メモ魔的なやつもでてくる。 ・4章。自分の視点を養ううえで、連続性(MCU予習ルート)だけでなく共通性(別ジャンルのものを強制的に括る何かを考える)ことの面白がり方。これはビジネスマンも面白いかも。批評的視点の導入。宇野常寛も参考文献に出てくる。 ・自己満足を自覚して表現することで「共通言語」を作りうる可能性があることの説明。鉤括弧の活用の有用性は初めて見た気がする。 ・クイズの出題者になれ。出題者に必要なホスピタリティ(自己満足をベースにした地の共有)。良き回答者を目指すことと競争社会から降りれないことは似ている。 (・そしてそれはテレビ文化によって醸成されてない?正解は90秒後システム。予測できる範囲が多いという勘違いによるレスバ。) ・最終章のまとめでは、自己満足の概念をクイズ的と批評的の二つの角度からまとめる。 ↑ひとまず読書中メモ ***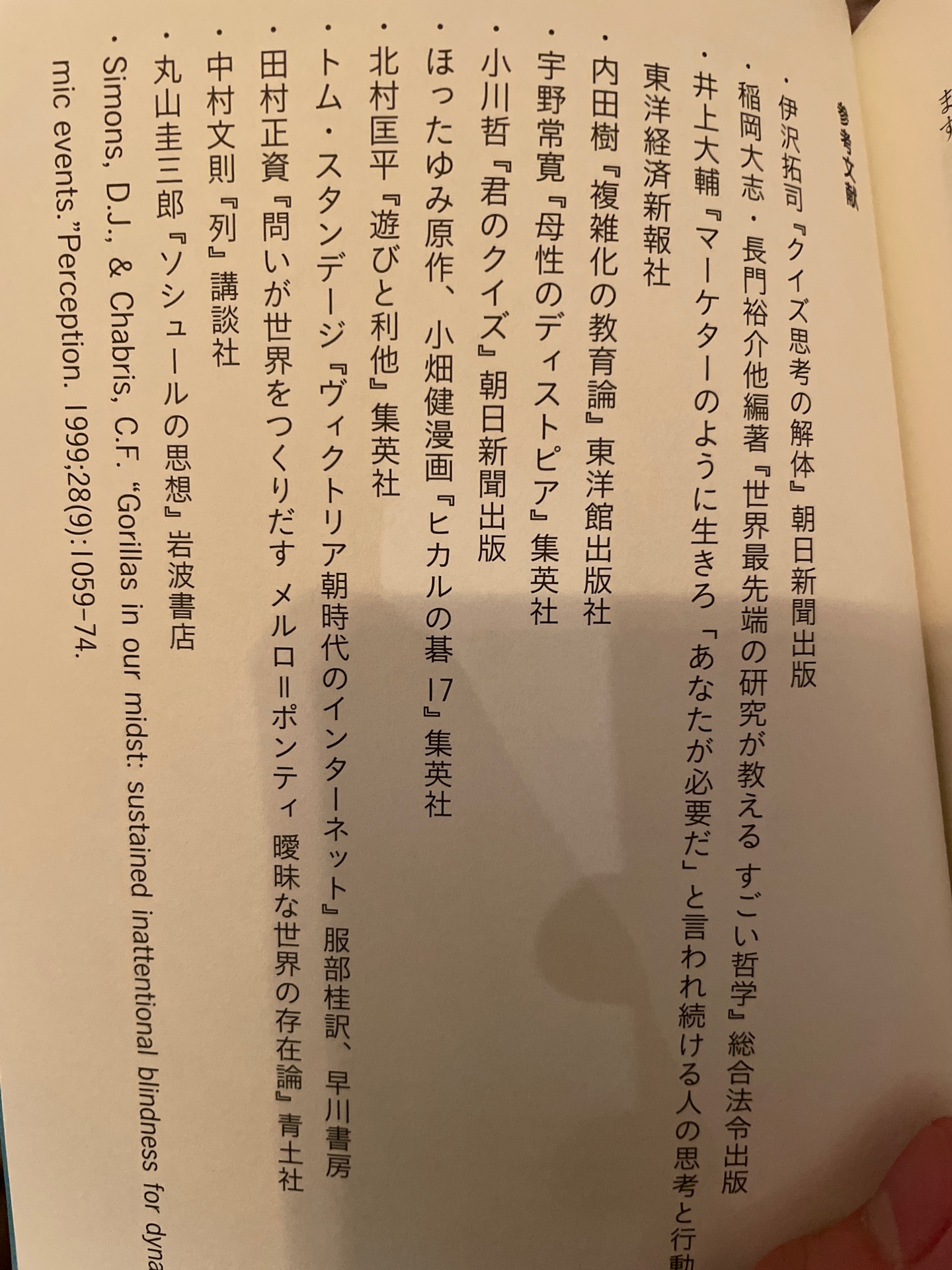
- 2025年5月21日
- 2025年5月21日
 性格診断ブームを問う小塩真司読み終わった・MBTIは商標登録されており、世に流通しているものは本書でMBTI?と表記されている。 ・タグ付けされることへの危機感を「やっぱり」の膨張から問う。機会損失、差別、へつながると。 ・パーソナリティ(性格)という語を読む中で、ラジオのパーソナリティってどこから来た言葉?となった。 ・欧米は早かったらしいが、日本で最初は1967年初代オールナイトニッポンのDJを務めた糸居五郎。アナウンサーなのだが、番組の"個性"を個人がつくるムードで前面に出す役割、という意味でのパーソナリティ。
性格診断ブームを問う小塩真司読み終わった・MBTIは商標登録されており、世に流通しているものは本書でMBTI?と表記されている。 ・タグ付けされることへの危機感を「やっぱり」の膨張から問う。機会損失、差別、へつながると。 ・パーソナリティ(性格)という語を読む中で、ラジオのパーソナリティってどこから来た言葉?となった。 ・欧米は早かったらしいが、日本で最初は1967年初代オールナイトニッポンのDJを務めた糸居五郎。アナウンサーなのだが、番組の"個性"を個人がつくるムードで前面に出す役割、という意味でのパーソナリティ。 - 2025年5月5日
 YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み終わった・「藪の中」を下敷きに、ある文芸界の女性搾取問題に迫る。告発されるのは老舗文芸誌の元編集長で、そいつの現役時代に作家志望で学生だった自分は搾取されたという告発が起こる。時間が経ってからの告発なので、それが成されるまで、成される以前に情熱を失った文芸人の土台は描かれ甲斐がある。 ・加えて、現行の若手編集者の女性問題も表出する。マチアプを使う自分も社会の乗りこなし甲斐のなさも冷静に見ていつつも、周囲の影響の反動もあってじわじわ皮が剥がれる。皮が剥がれるというか、醸造される熱量があり、それがやはり女への行動で表出してしまう。 ・掻き回すのは孤独になっても世界と戦う売れっ子作家であり、彼女自身も関係の冷えた夫、長く連れそうパートナー、娘、と問題に溢れる。作家ゆえに主観と客観の切り替えは自然に備わっているが、具体的な事件を機にそのバランスが崩れる。 ・シャンタルアケルマンの映画にも感じたが、淡々としたルーティンに見えても、それはバランスが取れていた訳でなく、徐々にある瞬間に向かっていってしまう、蟻地獄のような生活。作品が読者に見せる"1日目"はその人にとっては別に1日目ではない。 ・ビビッドなことはいろいろあるが、それは折り目をつけたから本を確認する。 ・この本が描いた世界を自分に引き付けるうえでは意外と、鮮烈な場面、些細な思考のよぎり、立場による理屈、ではなく、告発文が出来上がり受容されるまでの運動。 ・告発した女は、まず作家に相談した。その上で、文章の添削をお願いした。作家はたくさん赤字を入れたが、半分も採用せず女はそれを世に出す。かつて作家を志したこともあり「自分の復帰第1作となる」という言葉も入れている。それを作家は、中途半端なものだと冷めた目で見る。一つの短編小説にもなるのに、中途半端だと。そして、告発された編集者は、当然自身の言い分もあるが言い返すことはなく、その文章の中にかつて担当した作家の匂いに気づく。作家はもともと告発された編集者が担当していた。そして、そもそも女が告発する動機には、自分がとれなかった文芸誌の新人賞をとってデビューした同級生がついにヒット作を出したことへの嫉妬があった。 文章、創作をめぐる目線という補助線がしっかりとあることに、この作品世界の現実味を何よりも感じた。 ・この本は心にくるから一週間かけて読んだ。その間、アケルマンの映画と、その前日に「想像の犠牲」を見た。いぜれも3時間越えで腰が逝った。太×3の一週間として、記憶している。
YABUNONAKA-ヤブノナカー金原ひとみ読み終わった・「藪の中」を下敷きに、ある文芸界の女性搾取問題に迫る。告発されるのは老舗文芸誌の元編集長で、そいつの現役時代に作家志望で学生だった自分は搾取されたという告発が起こる。時間が経ってからの告発なので、それが成されるまで、成される以前に情熱を失った文芸人の土台は描かれ甲斐がある。 ・加えて、現行の若手編集者の女性問題も表出する。マチアプを使う自分も社会の乗りこなし甲斐のなさも冷静に見ていつつも、周囲の影響の反動もあってじわじわ皮が剥がれる。皮が剥がれるというか、醸造される熱量があり、それがやはり女への行動で表出してしまう。 ・掻き回すのは孤独になっても世界と戦う売れっ子作家であり、彼女自身も関係の冷えた夫、長く連れそうパートナー、娘、と問題に溢れる。作家ゆえに主観と客観の切り替えは自然に備わっているが、具体的な事件を機にそのバランスが崩れる。 ・シャンタルアケルマンの映画にも感じたが、淡々としたルーティンに見えても、それはバランスが取れていた訳でなく、徐々にある瞬間に向かっていってしまう、蟻地獄のような生活。作品が読者に見せる"1日目"はその人にとっては別に1日目ではない。 ・ビビッドなことはいろいろあるが、それは折り目をつけたから本を確認する。 ・この本が描いた世界を自分に引き付けるうえでは意外と、鮮烈な場面、些細な思考のよぎり、立場による理屈、ではなく、告発文が出来上がり受容されるまでの運動。 ・告発した女は、まず作家に相談した。その上で、文章の添削をお願いした。作家はたくさん赤字を入れたが、半分も採用せず女はそれを世に出す。かつて作家を志したこともあり「自分の復帰第1作となる」という言葉も入れている。それを作家は、中途半端なものだと冷めた目で見る。一つの短編小説にもなるのに、中途半端だと。そして、告発された編集者は、当然自身の言い分もあるが言い返すことはなく、その文章の中にかつて担当した作家の匂いに気づく。作家はもともと告発された編集者が担当していた。そして、そもそも女が告発する動機には、自分がとれなかった文芸誌の新人賞をとってデビューした同級生がついにヒット作を出したことへの嫉妬があった。 文章、創作をめぐる目線という補助線がしっかりとあることに、この作品世界の現実味を何よりも感じた。 ・この本は心にくるから一週間かけて読んだ。その間、アケルマンの映画と、その前日に「想像の犠牲」を見た。いぜれも3時間越えで腰が逝った。太×3の一週間として、記憶している。
- 2025年4月28日
 ワールドアトラスいとうせいこう読んでるもう日記に近いけど。 ・漢字辞書を小さい机いっぱいに広げて、片手でこの本、もう片方で不二世の水割り、スマホのchatGPTの返信待ちを過ごしていた。 ・帰りの電車で5分前に投稿された令和ロマンのYouTubeで久しぶりに姿形を見る芸人があり、彼が吉本を退所したことの衝撃をどの視点で考えるかを考えながら、回覧板を読んで、消費者はどうあるべきというか、どこに幸せを感じるのかに考えがスライドしていた。 ・ラジオが更新されたからそれを聴き、自分は人の姿形と声に感化される情動のデカさに勝るものがあるのかと考える。推しが分からないできたけど、人1人が放てる情報の中毒性はヤバい(その点だけで松ちゃんねるを歓迎する人の気持ちはわかる) ・翻って、文章って糖分の無い世界じゃん、と言われたらその常識に何を返せるのか怖くなる。 ・密教と風狂と絡めて聴いているGPTは返信を返しているだろうか。密教時代の風通しの有無を考えてる。 ・ワールドアトラスが世界地図を作ろうとした時代を、もはや牧歌的とすら思ってしまうんだが!!!!!
ワールドアトラスいとうせいこう読んでるもう日記に近いけど。 ・漢字辞書を小さい机いっぱいに広げて、片手でこの本、もう片方で不二世の水割り、スマホのchatGPTの返信待ちを過ごしていた。 ・帰りの電車で5分前に投稿された令和ロマンのYouTubeで久しぶりに姿形を見る芸人があり、彼が吉本を退所したことの衝撃をどの視点で考えるかを考えながら、回覧板を読んで、消費者はどうあるべきというか、どこに幸せを感じるのかに考えがスライドしていた。 ・ラジオが更新されたからそれを聴き、自分は人の姿形と声に感化される情動のデカさに勝るものがあるのかと考える。推しが分からないできたけど、人1人が放てる情報の中毒性はヤバい(その点だけで松ちゃんねるを歓迎する人の気持ちはわかる) ・翻って、文章って糖分の無い世界じゃん、と言われたらその常識に何を返せるのか怖くなる。 ・密教と風狂と絡めて聴いているGPTは返信を返しているだろうか。密教時代の風通しの有無を考えてる。 ・ワールドアトラスが世界地図を作ろうとした時代を、もはや牧歌的とすら思ってしまうんだが!!!!! - 2025年4月27日
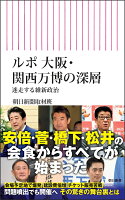 ルポ 大阪・関西万博の深層朝日新聞取材班読んでる・大阪に行くに際して買ったけど、行くまでに手に取れなかった。向こうのお昼ワイドテレビはどこも万博ロケを流していたけど、東京はどうなんだろう、知り合いと話しているなかでは全く話題に上がっていない。 ・今日、海外の万博大好きおじさんの酷評レビューの翻訳ツイートが回ってきた。延べ来場者が100万人突破したが関係者もカウントしているとか、揚げ足なのか本質なのかわからないけど開催以来万博のイメージがひっくり返っていないまま、ミャクミャクだけが目に留まる。 ・本書の話。まだ二章までしか読めてないけど、あまりに新聞の文体すぎる。以前、新聞記者が書いた新書(なんだっけ)の前書きに、本が書けると思っているが、本として読まれるに足る文章が書けない職業としてまず新聞記者がいる、みたいなことを思い出した。 ・もちろん成立はしているけれど、情報の置き石とはいえ情感を期待してしまうのが本。
ルポ 大阪・関西万博の深層朝日新聞取材班読んでる・大阪に行くに際して買ったけど、行くまでに手に取れなかった。向こうのお昼ワイドテレビはどこも万博ロケを流していたけど、東京はどうなんだろう、知り合いと話しているなかでは全く話題に上がっていない。 ・今日、海外の万博大好きおじさんの酷評レビューの翻訳ツイートが回ってきた。延べ来場者が100万人突破したが関係者もカウントしているとか、揚げ足なのか本質なのかわからないけど開催以来万博のイメージがひっくり返っていないまま、ミャクミャクだけが目に留まる。 ・本書の話。まだ二章までしか読めてないけど、あまりに新聞の文体すぎる。以前、新聞記者が書いた新書(なんだっけ)の前書きに、本が書けると思っているが、本として読まれるに足る文章が書けない職業としてまず新聞記者がいる、みたいなことを思い出した。 ・もちろん成立はしているけれど、情報の置き石とはいえ情感を期待してしまうのが本。 - 2025年4月27日
 読んでる・夜に食べたインド×イタリア料理の店が本当に美味しくて、色々食べたけど野菜とスパイスのおひたしに感動した。根菜は強い(ピクルスもおひたしの仲間という理解で良いのか) ・溜めたチラシで水位が上がったポストからはみ出たAmazonの封筒に入っていた本。手触りもサイズも色も想定も良くて、積まずに読み始めた。 ・世界に表明する自分という決まりがあって、世界も自分も言葉を通してくるくる回るから、言葉を連ねている人のように思う。 ・対峙する他者から向けられた言葉が起点となるものが多く、半拍遅れて対応した後悔の種や、決め打ちしたフレーズを用意する自分を振り返る文章は、誰かの半拍を埋めるかもしれないし、引き出しを暖めるかもしれない。 その矜持が持つ力を理解した上で書かれてている。 ・人を人と思ったら崩壊する満員電車社会が他者への無関心性を高め、柳のように受け流す心得みたいなものがインストールされた平成があったとして、 何がインストールされているか判別がつかない他者が溢れるいま、体をヌルヌルさせて毒針を喰らわないようにする心構えは一つの解だと思う。プラスのイメージで星野源のアメーバ論を思い出す。 ・友達の話すこともわからないのに日本語で文章を書いたって、と泣く友達がいたとして、自分には言葉でウジウジゆうことしできないよなあ。
読んでる・夜に食べたインド×イタリア料理の店が本当に美味しくて、色々食べたけど野菜とスパイスのおひたしに感動した。根菜は強い(ピクルスもおひたしの仲間という理解で良いのか) ・溜めたチラシで水位が上がったポストからはみ出たAmazonの封筒に入っていた本。手触りもサイズも色も想定も良くて、積まずに読み始めた。 ・世界に表明する自分という決まりがあって、世界も自分も言葉を通してくるくる回るから、言葉を連ねている人のように思う。 ・対峙する他者から向けられた言葉が起点となるものが多く、半拍遅れて対応した後悔の種や、決め打ちしたフレーズを用意する自分を振り返る文章は、誰かの半拍を埋めるかもしれないし、引き出しを暖めるかもしれない。 その矜持が持つ力を理解した上で書かれてている。 ・人を人と思ったら崩壊する満員電車社会が他者への無関心性を高め、柳のように受け流す心得みたいなものがインストールされた平成があったとして、 何がインストールされているか判別がつかない他者が溢れるいま、体をヌルヌルさせて毒針を喰らわないようにする心構えは一つの解だと思う。プラスのイメージで星野源のアメーバ論を思い出す。 ・友達の話すこともわからないのに日本語で文章を書いたって、と泣く友達がいたとして、自分には言葉でウジウジゆうことしできないよなあ。 - 2025年3月29日
- 2025年3月29日
 広告 Vol.418 特集:領域侵犯合法化。山口綱士,『広告』編集部読んでる・これまでの広告と比べると見栄えは普通の雑誌より。昨今の越境的なノリを「領域侵犯」から感じる。 ・九段理江に95%AIで小説を書かせる企画は良い。同情塔が現代アート化してると振り返る本人が、今作制作の意義を(プロンプトも公開することで)自分も小説を書けるかもと思ってもらう、という副産物を目標にしてるのもいい。 きっと小説よりプロンプトの方が面白いのでは。後にwebで全部公開するらしい。 ・半分まで読んだ。若林恵のインタビューが圧倒的。 ・雑誌は情報発信媒体ではなく、情報調達の受信機能そのものを公開するという視点。 ・であるから、編集部という情報収集と人的ネットワークに長けた運動体の蓄積こそ大事。 ・コンテンツの面白さは生まれる過程ではどこがどう面白いか説明できない。 ・整理するとパワポ1枚で済む話、結論自体微妙でも、最初に設定した項目と項目の間の話が大事だったりするし、右往左往するプロセス、複数のトピックスの絡み合いが面白い。 ・もう面白いのはプロセスだけ。雑誌は情報を手繰り寄せるプロセスを記述して、読者が追体験するもの。
広告 Vol.418 特集:領域侵犯合法化。山口綱士,『広告』編集部読んでる・これまでの広告と比べると見栄えは普通の雑誌より。昨今の越境的なノリを「領域侵犯」から感じる。 ・九段理江に95%AIで小説を書かせる企画は良い。同情塔が現代アート化してると振り返る本人が、今作制作の意義を(プロンプトも公開することで)自分も小説を書けるかもと思ってもらう、という副産物を目標にしてるのもいい。 きっと小説よりプロンプトの方が面白いのでは。後にwebで全部公開するらしい。 ・半分まで読んだ。若林恵のインタビューが圧倒的。 ・雑誌は情報発信媒体ではなく、情報調達の受信機能そのものを公開するという視点。 ・であるから、編集部という情報収集と人的ネットワークに長けた運動体の蓄積こそ大事。 ・コンテンツの面白さは生まれる過程ではどこがどう面白いか説明できない。 ・整理するとパワポ1枚で済む話、結論自体微妙でも、最初に設定した項目と項目の間の話が大事だったりするし、右往左往するプロセス、複数のトピックスの絡み合いが面白い。 ・もう面白いのはプロセスだけ。雑誌は情報を手繰り寄せるプロセスを記述して、読者が追体験するもの。
- 2025年3月29日
 読み終わった読んでる・伊藤亜紗氏がちゃぶ台で連載している会議の研究が面白くて、言語化だのハラスメント対策だの流行している言葉の運用に関して論を形成する会議論みたいなものがずっと頭にあった。 ・先に誰かやらないで欲しいと思いつつ、本書を知っておっかなびっくり読み始めたわけだが、 これは労働者の会議というよりは、依存症の人たちのオープンダイアローグが導入にあった。 ・オープンダイアローグはケア的な文脈で近年よく目にするし、文芸誌でアルコール依存症をテーマにした創作もあった。とはいえ本書は会議×ネガティブケイパビリティのよう。 ・3章「悪を生む会議と人を成長させるミーティング」に入り、興味の鮮度が落ちる。 ・腐敗した現代の会議を炙り出す意気込みはあれど、宝塚イジメやビックモーターなど企業不祥事は議事録があるわけではないので、隠蔽体質はしっかりした会議をしていないから、という無理を感じる。 戦時中の作戦会議は資料があるが、これは遡りすぎ。 生成AIは会議の質を変えられるか、という項目もくるが、まずAIが学んでおくべきなのは正義と良心、そして倫理人権でしょう、とざっくりした推測を出ない。 ・ネガティブケイパビリティを経由して、 会議は、論争(ディベート)の側面ばかり注視してはいけない、というまとめ。 言いっぱなし聞きっぱなしのオープンダイアローグ的なものとの対比関係はよくわかるが ・求めていた「労働者の会議」ではなかった。 何かしらの同意形成という目的があり、出席している時点である種の"説得力カード"を配られた人たちが会話するミーティングについて、引き続き考える。
読み終わった読んでる・伊藤亜紗氏がちゃぶ台で連載している会議の研究が面白くて、言語化だのハラスメント対策だの流行している言葉の運用に関して論を形成する会議論みたいなものがずっと頭にあった。 ・先に誰かやらないで欲しいと思いつつ、本書を知っておっかなびっくり読み始めたわけだが、 これは労働者の会議というよりは、依存症の人たちのオープンダイアローグが導入にあった。 ・オープンダイアローグはケア的な文脈で近年よく目にするし、文芸誌でアルコール依存症をテーマにした創作もあった。とはいえ本書は会議×ネガティブケイパビリティのよう。 ・3章「悪を生む会議と人を成長させるミーティング」に入り、興味の鮮度が落ちる。 ・腐敗した現代の会議を炙り出す意気込みはあれど、宝塚イジメやビックモーターなど企業不祥事は議事録があるわけではないので、隠蔽体質はしっかりした会議をしていないから、という無理を感じる。 戦時中の作戦会議は資料があるが、これは遡りすぎ。 生成AIは会議の質を変えられるか、という項目もくるが、まずAIが学んでおくべきなのは正義と良心、そして倫理人権でしょう、とざっくりした推測を出ない。 ・ネガティブケイパビリティを経由して、 会議は、論争(ディベート)の側面ばかり注視してはいけない、というまとめ。 言いっぱなし聞きっぱなしのオープンダイアローグ的なものとの対比関係はよくわかるが ・求めていた「労働者の会議」ではなかった。 何かしらの同意形成という目的があり、出席している時点である種の"説得力カード"を配られた人たちが会話するミーティングについて、引き続き考える。 - 2025年3月23日
 いい音がする文章高橋久美子読んでる・名著の予想がぶんぶんする。文章論の切り口で"いい音"というのも良い。目的じゃなく効果の面で、しかも五感絡みだとハードルも低く感じる。 ・切り口もだが文章も良い。一章終わりのコラムで「こころ」の一文をひいた感想の中に、「開きそうで開かないカーテンのよう」とあって、痺れてしまった。「高校生にも理解できる言葉で、手の届かない深い場所を握られる感じ」の後にくるカーテン。画を想像してもぴったりだし、単に喩えとしても素晴らしい。 ・よく引用を用いて論を展開するテクストがあるが、引用部分を飛ばして読む人も多いと思う。だけどこのコラムはつい読んでしまう。それは引用される目的が情報共有じゃなくリスニングパーティだからだ。し、最後吉本ばななを引いて「地の文が美しいと、たとえ抜粋だとしても、色褪せることがないんだなと思った」とある。この定義付け、ここまで読ませた読者の心を拓く誠実さ、何よりあなたの文章からいい音がしている。 と、たったの一章で感動してしまっている。 ・第二章。絵本や小唄を例に言葉とリズムが原初的なものだとみせる。オノマトペや繰り返し、文字の調子からして、確かに子供の頃最初に言葉と肩を組んでいたのはリズムだ。 ・福音館書店の松井さん「絵本とは何か」にも惹かれる。一方的に話しかける動画が果たしていいリズムかというと決してそうではない、という理屈が一番しっくりきたのはこの本かもしれない。リズムが大事なんだ、というのはアンパンマンがまず幼児が発音しやすい六文字だと示す本において決定力がデカい。 ・日本特有のビートとして7・5調の考察に移る。早く読みたい続きを。
いい音がする文章高橋久美子読んでる・名著の予想がぶんぶんする。文章論の切り口で"いい音"というのも良い。目的じゃなく効果の面で、しかも五感絡みだとハードルも低く感じる。 ・切り口もだが文章も良い。一章終わりのコラムで「こころ」の一文をひいた感想の中に、「開きそうで開かないカーテンのよう」とあって、痺れてしまった。「高校生にも理解できる言葉で、手の届かない深い場所を握られる感じ」の後にくるカーテン。画を想像してもぴったりだし、単に喩えとしても素晴らしい。 ・よく引用を用いて論を展開するテクストがあるが、引用部分を飛ばして読む人も多いと思う。だけどこのコラムはつい読んでしまう。それは引用される目的が情報共有じゃなくリスニングパーティだからだ。し、最後吉本ばななを引いて「地の文が美しいと、たとえ抜粋だとしても、色褪せることがないんだなと思った」とある。この定義付け、ここまで読ませた読者の心を拓く誠実さ、何よりあなたの文章からいい音がしている。 と、たったの一章で感動してしまっている。 ・第二章。絵本や小唄を例に言葉とリズムが原初的なものだとみせる。オノマトペや繰り返し、文字の調子からして、確かに子供の頃最初に言葉と肩を組んでいたのはリズムだ。 ・福音館書店の松井さん「絵本とは何か」にも惹かれる。一方的に話しかける動画が果たしていいリズムかというと決してそうではない、という理屈が一番しっくりきたのはこの本かもしれない。リズムが大事なんだ、というのはアンパンマンがまず幼児が発音しやすい六文字だと示す本において決定力がデカい。 ・日本特有のビートとして7・5調の考察に移る。早く読みたい続きを。 - 2025年3月23日
 きみのお金は誰のため田内学読み終わった・20万部の帯があったから読んでみた。射程に小中学生があると変わってくるのか。学校図書館的な言葉も帯にあった。 ・物語性と漫才師起用インフォマみたいなやり取りで「お金の向こう研究所」ボスが生き別れの娘と街の学生にお金について伝える。 ・小学生の学習用歴史漫画を思い出した。あのノリ。この内容とトピックスの数だと、テキストとマンガどっちの方が頁数かからないんだろう。 知らないだけでメディアミックスされてる?ビジネス書にすることで棚を取れるのだろうか。売れていることの良さ以外は分からなかった。 ・が、子供向けのありきたりなストーリーとやり取りと切ってしまったらそれまでで、例えば大人が令和の虎の成田悠輔回を見てるのと相似関係にあると考えることもできるか? ・タイトルが良い。幅広く売れるのはやっぱタイトル。
きみのお金は誰のため田内学読み終わった・20万部の帯があったから読んでみた。射程に小中学生があると変わってくるのか。学校図書館的な言葉も帯にあった。 ・物語性と漫才師起用インフォマみたいなやり取りで「お金の向こう研究所」ボスが生き別れの娘と街の学生にお金について伝える。 ・小学生の学習用歴史漫画を思い出した。あのノリ。この内容とトピックスの数だと、テキストとマンガどっちの方が頁数かからないんだろう。 知らないだけでメディアミックスされてる?ビジネス書にすることで棚を取れるのだろうか。売れていることの良さ以外は分からなかった。 ・が、子供向けのありきたりなストーリーとやり取りと切ってしまったらそれまでで、例えば大人が令和の虎の成田悠輔回を見てるのと相似関係にあると考えることもできるか? ・タイトルが良い。幅広く売れるのはやっぱタイトル。 - 2025年3月19日
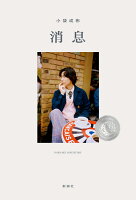 消息小袋成彬読んでる・イギリスに飛んだときの実感が一番でかいんだと思う。タイトルがいい ・価値観、社会人といったようなざっくりした言葉(デカい主語、みたいなものに対する違和感はずっとある)の説得力って、個人の原体験からじゃないと眺められないのか?とは思う。が、それを青さというのは簡単で、だけど軽やかさより軽さの印象が強いのは初出媒体の背景もあるのか。 ・いや、それもこれも25年にこれを読んでるという越権の気もする。 ・音楽家はどうも背中で見せていく美学的なノリがある気もするが、著者は思考したことを誠実に書いているように思う。書いていること、その過程自体をも受け入れてもらえるという過信も感じる。 ・的はでかい。2か月に一遍だから大上段に構えてる感じもする。が、見せかけのユーモアを使わない。ハナにつかないだけで信頼に足るこの世の方が弱ってる。
消息小袋成彬読んでる・イギリスに飛んだときの実感が一番でかいんだと思う。タイトルがいい ・価値観、社会人といったようなざっくりした言葉(デカい主語、みたいなものに対する違和感はずっとある)の説得力って、個人の原体験からじゃないと眺められないのか?とは思う。が、それを青さというのは簡単で、だけど軽やかさより軽さの印象が強いのは初出媒体の背景もあるのか。 ・いや、それもこれも25年にこれを読んでるという越権の気もする。 ・音楽家はどうも背中で見せていく美学的なノリがある気もするが、著者は思考したことを誠実に書いているように思う。書いていること、その過程自体をも受け入れてもらえるという過信も感じる。 ・的はでかい。2か月に一遍だから大上段に構えてる感じもする。が、見せかけのユーモアを使わない。ハナにつかないだけで信頼に足るこの世の方が弱ってる。 - 2025年3月17日
 AIに書けない文章を書く前田安正読んでる・5W1Hから欠落したWhyについて。いつ、どこで、だれが、何を、どうした(do)、は4W1Dに過ぎない。 ・「昨日僕は動物園でライオンを見た。楽しかった。なぜなら、友達と行ったからだし、天気が良くて他の動物もいたから」 Whyをこう使うと、楽しかった、の理由を列挙するだけの形になる。 なぜ昨日、なぜ動物園、なぜライオンというふうに Wnyをそれまでの5wに掛けることで文章が広がる。 ・ここまでで3/7章。 ・一昨日から令和の虎を見ている。出演者やビジネスプランは置いておいて、結局WhyWhyWhyを詰められる。就職面接もそうだな。
AIに書けない文章を書く前田安正読んでる・5W1Hから欠落したWhyについて。いつ、どこで、だれが、何を、どうした(do)、は4W1Dに過ぎない。 ・「昨日僕は動物園でライオンを見た。楽しかった。なぜなら、友達と行ったからだし、天気が良くて他の動物もいたから」 Whyをこう使うと、楽しかった、の理由を列挙するだけの形になる。 なぜ昨日、なぜ動物園、なぜライオンというふうに Wnyをそれまでの5wに掛けることで文章が広がる。 ・ここまでで3/7章。 ・一昨日から令和の虎を見ている。出演者やビジネスプランは置いておいて、結局WhyWhyWhyを詰められる。就職面接もそうだな。 - 2025年3月13日
 読んでる・「誰でも思いつくじゃん」でもお前はやらなかったよねこのタイミングで、ってものは往々にしてある。 ・俺でも思いつくわってみんなに思わせるものって浸透しやすい。一発ギャグ(ゲッツとかそんなの関係ねぇ)は結構そうだと思う。今年の漢字とか流行語みたいなのは違う。金って言われてもへえ、みたいな。 ・漢字ってそうで、一度知るとそれ以降しっくり来るんだけど、でも知らなかった、みたいなのはすごいと思う改めて。「礼賛」「王墓」とか。漢字を使う意味合い、デザイン的な風格すら感じる。 ・王道の中でアングラをやる小粋さの原点っぽいな。今じゃそういう立ち位置のものってハックというパフォーマンス性までをも期待される感じがするが、そこまでの過激さも求められてない、そうじゃなく風格は風格で楽しむ気概と余裕があった気もする。 ・インタビューはノーと言わせてからが面白い、というのは面白い。なんで?とかから始まる。あとは知らないとか好きじゃないも同様。 ・NYのファッションショーで蛍光色のスーツを見て、それがNYぽくて、それ以来NYに行くと文房具屋で蛍光色のペンとか紙とか買うようになった、ってエピソードいいなあ。
読んでる・「誰でも思いつくじゃん」でもお前はやらなかったよねこのタイミングで、ってものは往々にしてある。 ・俺でも思いつくわってみんなに思わせるものって浸透しやすい。一発ギャグ(ゲッツとかそんなの関係ねぇ)は結構そうだと思う。今年の漢字とか流行語みたいなのは違う。金って言われてもへえ、みたいな。 ・漢字ってそうで、一度知るとそれ以降しっくり来るんだけど、でも知らなかった、みたいなのはすごいと思う改めて。「礼賛」「王墓」とか。漢字を使う意味合い、デザイン的な風格すら感じる。 ・王道の中でアングラをやる小粋さの原点っぽいな。今じゃそういう立ち位置のものってハックというパフォーマンス性までをも期待される感じがするが、そこまでの過激さも求められてない、そうじゃなく風格は風格で楽しむ気概と余裕があった気もする。 ・インタビューはノーと言わせてからが面白い、というのは面白い。なんで?とかから始まる。あとは知らないとか好きじゃないも同様。 ・NYのファッションショーで蛍光色のスーツを見て、それがNYぽくて、それ以来NYに行くと文房具屋で蛍光色のペンとか紙とか買うようになった、ってエピソードいいなあ。 - 2025年3月13日
 生成AI時代の言語論大澤真幸気になる
生成AI時代の言語論大澤真幸気になる - 2025年3月12日
 読んでる・ナイキの回の後半で、店舗/オンライン/受注生産とかの販売チャネルの話になっているのが面白い。当時のスニーカーが持つ磁場ってやっぱりここか。 ・藤原ヒロシがNike By Youにハマってるのも分かる。カミナリが発掘できなかっまVHSの本体カラーリングでスニーカーを作るというあの閉め方が見事だったと思い出す。 ・結局、自分がいいと思ったものを選ぶ、ということの良さを大切にしないといけない。だけど、それには原体験が必要で、例えば推し活が原体験だと、人と同じだから良い、がハナから備わることになるのか? ・限定商品の告知義務はメーカー側にないというのはよく分かる。 ・新商品開発のときに、あの定番商品の幻の別バージョンという物語をつけた話は面白い。生き別れた兄弟が後半に出てくるみたいなラインの引き方か?
読んでる・ナイキの回の後半で、店舗/オンライン/受注生産とかの販売チャネルの話になっているのが面白い。当時のスニーカーが持つ磁場ってやっぱりここか。 ・藤原ヒロシがNike By Youにハマってるのも分かる。カミナリが発掘できなかっまVHSの本体カラーリングでスニーカーを作るというあの閉め方が見事だったと思い出す。 ・結局、自分がいいと思ったものを選ぶ、ということの良さを大切にしないといけない。だけど、それには原体験が必要で、例えば推し活が原体験だと、人と同じだから良い、がハナから備わることになるのか? ・限定商品の告知義務はメーカー側にないというのはよく分かる。 ・新商品開発のときに、あの定番商品の幻の別バージョンという物語をつけた話は面白い。生き別れた兄弟が後半に出てくるみたいなラインの引き方か? - 2025年3月11日
- 2025年3月11日
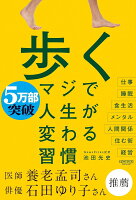 歩く マジで人生が変わる習慣池田光史買った・NewsPicksで昨年ハネた特集。AI時代における「人間の幸せは動物として快調かどうかにかかってる」はブームじゃ済まない。 ・脳盗のIGNITE企画くらいに見た本で、一度見送ったがやっぱり買った。良い装丁だと思う。 ・上出さんのMPCと同色で、連想するものも少しかぶるか? ・「呪術廻戦」もスペースの話だ、という伏見瞬の指摘を見てから「領域」のことを考えていて、例えば踏破/踏襲/足跡/掘る、とかぼやぼや浮かべるなかで、歩く、はそれらの起点になる概念としてありか? でもそういう本とはまた違いそうだけど。
歩く マジで人生が変わる習慣池田光史買った・NewsPicksで昨年ハネた特集。AI時代における「人間の幸せは動物として快調かどうかにかかってる」はブームじゃ済まない。 ・脳盗のIGNITE企画くらいに見た本で、一度見送ったがやっぱり買った。良い装丁だと思う。 ・上出さんのMPCと同色で、連想するものも少しかぶるか? ・「呪術廻戦」もスペースの話だ、という伏見瞬の指摘を見てから「領域」のことを考えていて、例えば踏破/踏襲/足跡/掘る、とかぼやぼや浮かべるなかで、歩く、はそれらの起点になる概念としてありか? でもそういう本とはまた違いそうだけど。
読み込み中...


