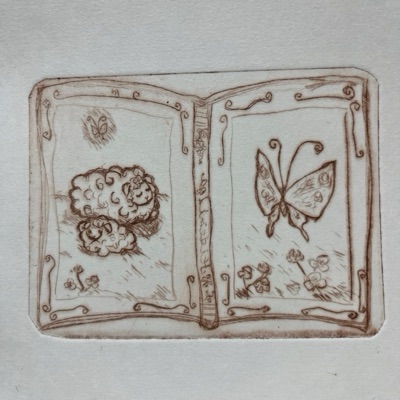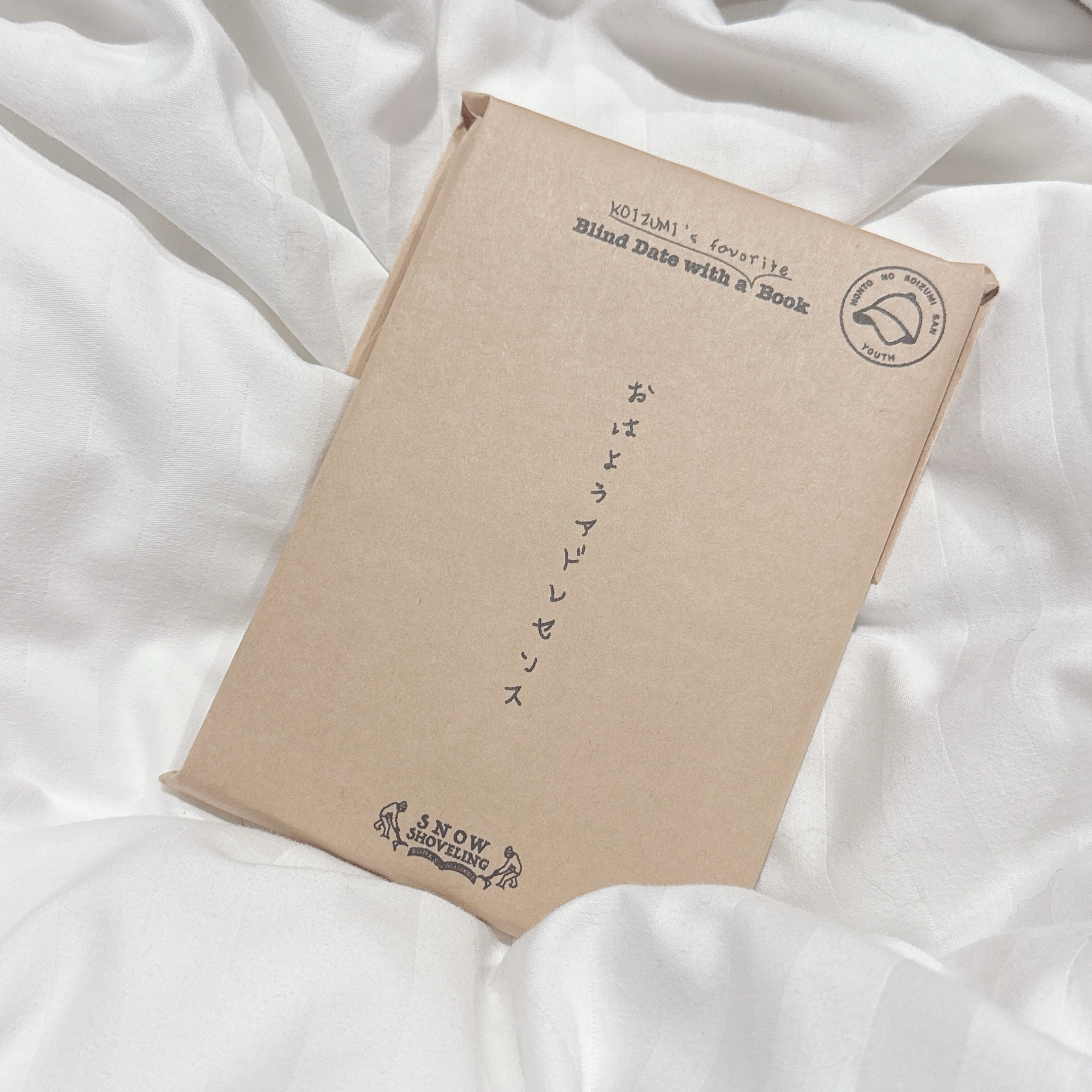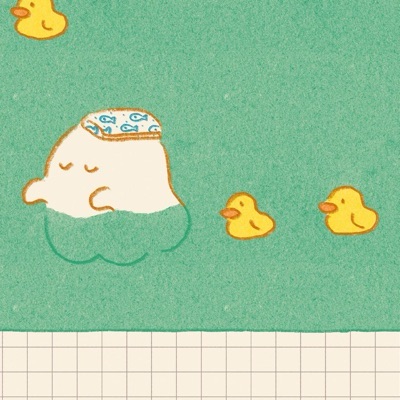女生徒

41件の記録
 ぽっぽ@risu_pocchi2025年12月26日読み終わった女の好ききらいなんて、ずいぶんいい加減なものだと思う。 燈籠、葉桜と魔笛、皮膚と心、きりぎりすが面白かった 特にきりぎりすが好き 女性視点の書き方が上手いと思った 太宰治の小説を初めてちゃんと読んだけど思っていたより楽しめた
ぽっぽ@risu_pocchi2025年12月26日読み終わった女の好ききらいなんて、ずいぶんいい加減なものだと思う。 燈籠、葉桜と魔笛、皮膚と心、きりぎりすが面白かった 特にきりぎりすが好き 女性視点の書き方が上手いと思った 太宰治の小説を初めてちゃんと読んだけど思っていたより楽しめた

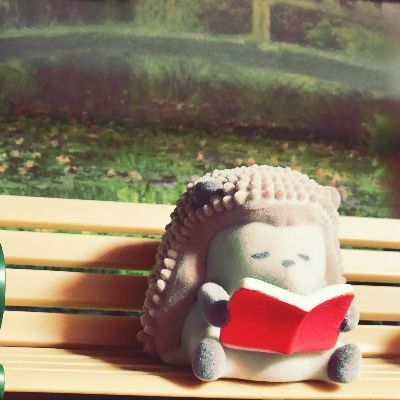 みちほ@full1moon5blue2025年9月27日読み終わった太宰治ってすごいなと思わざるを得ない。読み進めていくにつれ、どんどん面白く、どんどん楽しくなる。私、この子の気持ちすごくわかる!と思わずにはいられない。女の生きる中での窮屈さがさりげなく盛り込まれていてすごく興味深かった。これだけ女心をわかっているなんて、太宰がモテる理由がなんとなくわかった気がした。個人的には「誰も知らぬ」と「葉桜と魔笛」が好きだった。
みちほ@full1moon5blue2025年9月27日読み終わった太宰治ってすごいなと思わざるを得ない。読み進めていくにつれ、どんどん面白く、どんどん楽しくなる。私、この子の気持ちすごくわかる!と思わずにはいられない。女の生きる中での窮屈さがさりげなく盛り込まれていてすごく興味深かった。これだけ女心をわかっているなんて、太宰がモテる理由がなんとなくわかった気がした。個人的には「誰も知らぬ」と「葉桜と魔笛」が好きだった。
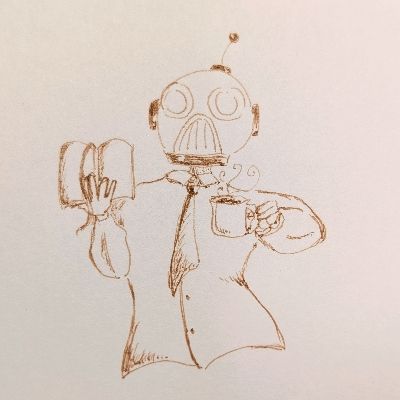
 しゃの@katnez2025年7月9日かつて読んだ『待つ』、この最も印象的な小品。日常のルーティンの一コマを「儀式」とし、外部を召喚する能動的な受動性の構えとなる。何を待っているのかは当人さえ不明、想像可能なものにはことごとく否定がふされ、その彼方に待ち受けられる名指しえないもの。重要なのは、その「何か」を待つために主人公はそのようにしはじめるのではないということ。そうした目的性さえ先の想像可能性の範疇に入るものだから。むしろ、ある日常における、ある規則的な反復を通して、自覚し得ぬうちに「儀式」が構成され、結果「待つ」ことになった、と言ってみたくなる。
しゃの@katnez2025年7月9日かつて読んだ『待つ』、この最も印象的な小品。日常のルーティンの一コマを「儀式」とし、外部を召喚する能動的な受動性の構えとなる。何を待っているのかは当人さえ不明、想像可能なものにはことごとく否定がふされ、その彼方に待ち受けられる名指しえないもの。重要なのは、その「何か」を待つために主人公はそのようにしはじめるのではないということ。そうした目的性さえ先の想像可能性の範疇に入るものだから。むしろ、ある日常における、ある規則的な反復を通して、自覚し得ぬうちに「儀式」が構成され、結果「待つ」ことになった、と言ってみたくなる。

 nogi@mitsu_read2025年7月9日読み終わった太宰治作品を今まで読んだことは(教科書以外で)なくて、なんとなく苦手意識もあったというのに、本当に面白かった。面白いと言うべきなのかわからないけど、このひとは女性なのかと思うくらい、どの短編の女の独白(告白)も生々しい手ざわりがして、薄暗くて、すごくよかった。 特に「きりぎりす」と「貨幣」と「おさん」が好きだった。 解説読んでてなるほどなと思ったのは、太宰が女性的で、けれどもそれは母性ではなく乙女的潔癖症でもって、理想主義的、というところだった。 「貨幣」 p207-208 〝あのころは、もう日本も、やぶれかぶれになっていた時期でしょうね。私がどんな人の手から、どんな人の手に、何の目的で、そうしてどんなむごい会話でもって手渡されていたか、それはもう皆さんも、十二分にご存知の筈で、聞き飽き見飽きていらっしゃることでしょうから、くわしくは申し上げませんが、けだものみたいになっていたのは、軍閥とやらいうものだけではなかったように私には思われました。〟 〝この世の中にひとりでも不幸な人のいる限り、自分も幸福にはなれないと思う事こそ、本当の人間らしい感情でしょうに、自分だけ、或いは自分の家だけの束の間の安楽を得るために、隣人を罵り、あざむき、押し倒し、(いいえ、あなただって、いちどはそれをなさいました。無意識でなさって、ご自身それに気づかないなんてのは、さらに恐るべき事です。恥じて下さい。人間ならば恥じて下さい。恥じるというのは人間だけにある感情ですから。)まるでもう地獄の亡者がつかみ合いの喧嘩をしているような滑稽で悲惨な図ばかり見せつけられてまいりました。〟
nogi@mitsu_read2025年7月9日読み終わった太宰治作品を今まで読んだことは(教科書以外で)なくて、なんとなく苦手意識もあったというのに、本当に面白かった。面白いと言うべきなのかわからないけど、このひとは女性なのかと思うくらい、どの短編の女の独白(告白)も生々しい手ざわりがして、薄暗くて、すごくよかった。 特に「きりぎりす」と「貨幣」と「おさん」が好きだった。 解説読んでてなるほどなと思ったのは、太宰が女性的で、けれどもそれは母性ではなく乙女的潔癖症でもって、理想主義的、というところだった。 「貨幣」 p207-208 〝あのころは、もう日本も、やぶれかぶれになっていた時期でしょうね。私がどんな人の手から、どんな人の手に、何の目的で、そうしてどんなむごい会話でもって手渡されていたか、それはもう皆さんも、十二分にご存知の筈で、聞き飽き見飽きていらっしゃることでしょうから、くわしくは申し上げませんが、けだものみたいになっていたのは、軍閥とやらいうものだけではなかったように私には思われました。〟 〝この世の中にひとりでも不幸な人のいる限り、自分も幸福にはなれないと思う事こそ、本当の人間らしい感情でしょうに、自分だけ、或いは自分の家だけの束の間の安楽を得るために、隣人を罵り、あざむき、押し倒し、(いいえ、あなただって、いちどはそれをなさいました。無意識でなさって、ご自身それに気づかないなんてのは、さらに恐るべき事です。恥じて下さい。人間ならば恥じて下さい。恥じるというのは人間だけにある感情ですから。)まるでもう地獄の亡者がつかみ合いの喧嘩をしているような滑稽で悲惨な図ばかり見せつけられてまいりました。〟



 nogi@mitsu_read2025年7月2日読んでるp67 〝現在こんな烈しい腹痛を起しているのに、その腹痛に対しては、見て見ぬふりをして、ただ、さあさあ、もう少しのがまんだ、あの山の頂上まで行けば、しめたものだ、とただ、そのことばかり教えている。きっと、誰かが間違っている。わるいのは、あなただ。〟
nogi@mitsu_read2025年7月2日読んでるp67 〝現在こんな烈しい腹痛を起しているのに、その腹痛に対しては、見て見ぬふりをして、ただ、さあさあ、もう少しのがまんだ、あの山の頂上まで行けば、しめたものだ、とただ、そのことばかり教えている。きっと、誰かが間違っている。わるいのは、あなただ。〟


 歩@takeastroll2025年5月23日読み終わった自意識とか痛々しさが、刺さる。 これ時代に関わらず共通なんですか? 女生徒、思春期少女のインサイドヘッドで好き。なんで太宰治はこの年頃の次々湧いては移る思考回路とか、影響を多方面から受けすぎて何者だかわからない様子を書けるんだ。 戦争と交えてる話のあたりから男性の見栄、女性の甲斐甲斐しさ、それに違和感を覚えても従うほかないって描写が強調して書かれていて、あまり読んでて気持ちよくない。当たり前だったんだろうけど。 この本読んで、文学の教養が増えた私ですよと背筋伸ばしてますから、私も大概。
歩@takeastroll2025年5月23日読み終わった自意識とか痛々しさが、刺さる。 これ時代に関わらず共通なんですか? 女生徒、思春期少女のインサイドヘッドで好き。なんで太宰治はこの年頃の次々湧いては移る思考回路とか、影響を多方面から受けすぎて何者だかわからない様子を書けるんだ。 戦争と交えてる話のあたりから男性の見栄、女性の甲斐甲斐しさ、それに違和感を覚えても従うほかないって描写が強調して書かれていて、あまり読んでて気持ちよくない。当たり前だったんだろうけど。 この本読んで、文学の教養が増えた私ですよと背筋伸ばしてますから、私も大概。

 ⛄️@mnan1900年1月1日かつて読んだ蔵書持ち歩いてるよく読み返す表紙が好きで、収録された作品もよくて、持ち歩き用と、いざというときのために本棚に予備を置いて、ぜんぶで2冊もっています。 いまのところ、事情があって2冊もっているとかではなく、目的をもって2冊もっているのは、たしかこの本だけ。
⛄️@mnan1900年1月1日かつて読んだ蔵書持ち歩いてるよく読み返す表紙が好きで、収録された作品もよくて、持ち歩き用と、いざというときのために本棚に予備を置いて、ぜんぶで2冊もっています。 いまのところ、事情があって2冊もっているとかではなく、目的をもって2冊もっているのは、たしかこの本だけ。