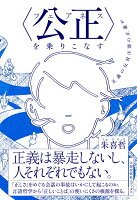Aruiwa
@atodeyomu
背を眺めるだけで80点
- 2025年6月11日
 ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のことアンジェラ・チェン,羽生有希読んでるとりあえず2章まで。経験論的に書かれているのでアセクシュアルの正確な定義を追究する本ではなく、しかしそこが重要である(そして読みやすい)。 アセクシュアルは性行為をしない/嫌悪するのではなく、「性的惹かれ」のない人のことを指す、とあっていままでの自分の雑な理解がころっと覆された。性的惹かれ、恋愛的惹かれ、美的惹かれは同じではないということ。 「はい、復唱してくださいね。性的惹かれは性欲動ではありません。これら二つの現象はしばしば取り替え可能なものとして扱われているけれど、それらが別物だと理解することで、エースの経験を説明しやすくなるのだ」p.52 「セクシュアリティは性的指向以上のものであり、惹かれは性的惹かれ以上のものだが、人間はあたかも、性的関心が唯一の理由であるかのように振る舞う。私たち自身が他者に心揺さぶられると感じる理由はそれだけだというように」p.68
ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のことアンジェラ・チェン,羽生有希読んでるとりあえず2章まで。経験論的に書かれているのでアセクシュアルの正確な定義を追究する本ではなく、しかしそこが重要である(そして読みやすい)。 アセクシュアルは性行為をしない/嫌悪するのではなく、「性的惹かれ」のない人のことを指す、とあっていままでの自分の雑な理解がころっと覆された。性的惹かれ、恋愛的惹かれ、美的惹かれは同じではないということ。 「はい、復唱してくださいね。性的惹かれは性欲動ではありません。これら二つの現象はしばしば取り替え可能なものとして扱われているけれど、それらが別物だと理解することで、エースの経験を説明しやすくなるのだ」p.52 「セクシュアリティは性的指向以上のものであり、惹かれは性的惹かれ以上のものだが、人間はあたかも、性的関心が唯一の理由であるかのように振る舞う。私たち自身が他者に心揺さぶられると感じる理由はそれだけだというように」p.68 - 2025年6月6日
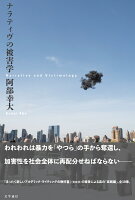 ナラティヴの被害学阿部幸大読んでる「わたしはここで、良心が問題を解決するはずだと主張したいのではない。みずからが無関係だと思ってきた問題に、じつは生まれながらにして間接的に関わってきたのだと知り驚くことが、その問題にコミットしよういうモチベーションを発生させうるということだ。とにかく責任を負えと要求するのではなく、個々人の内側から芽生える、それぞれの応答可能性――その実現を促すには、おそらくその個々人の歴史を知り、そのうちに応答可能性へと発展しうる固有の種子を見出すような努力が必要になるだろう」 第3章「ノラ・オッジャ・ケラー『慰安婦』におけるコリアン・アメリカン二世の応答可能性」
ナラティヴの被害学阿部幸大読んでる「わたしはここで、良心が問題を解決するはずだと主張したいのではない。みずからが無関係だと思ってきた問題に、じつは生まれながらにして間接的に関わってきたのだと知り驚くことが、その問題にコミットしよういうモチベーションを発生させうるということだ。とにかく責任を負えと要求するのではなく、個々人の内側から芽生える、それぞれの応答可能性――その実現を促すには、おそらくその個々人の歴史を知り、そのうちに応答可能性へと発展しうる固有の種子を見出すような努力が必要になるだろう」 第3章「ノラ・オッジャ・ケラー『慰安婦』におけるコリアン・アメリカン二世の応答可能性」 - 2025年6月2日
 修理する権利アーロン・パーザナウスキー,西村伸泰読んでる特許や商標といった知的財産または著作権法が、対他企業を牽制すること以上にユーザー(=まさに消費者!)のアクセスを防いで修理できなくしているという指摘は重要。 デバイスに使用する原材料を採掘するために引き起こされている環境破壊や労働力の搾取についても詳しく書いてある。 (2章まで)
修理する権利アーロン・パーザナウスキー,西村伸泰読んでる特許や商標といった知的財産または著作権法が、対他企業を牽制すること以上にユーザー(=まさに消費者!)のアクセスを防いで修理できなくしているという指摘は重要。 デバイスに使用する原材料を採掘するために引き起こされている環境破壊や労働力の搾取についても詳しく書いてある。 (2章まで) - 2025年5月28日
 恋する少年十字軍早助よう子再読中特に表題の作品には読んでいてヒリリとする一文やユーモアがそこかしこに散りばめられている。楽しいのにずっと不穏。名作。 「だから今日も瞬点は、声明案を練るために、テーブルにノートを広げている。まだノートは自紙。なにも書かれていないページを見つめていると、どこからかため息が聞こえてくる。行列を作って並ぶのはいつも貧乏人ばかり。金持ちはいつでも先頭に割り込めるか、そもそも並ばなくてもいいようになっている。ノートの野線が憎い。罫線に字を並ばせようとするのは誰だ?」 (恋する少年十字軍 p.45)
恋する少年十字軍早助よう子再読中特に表題の作品には読んでいてヒリリとする一文やユーモアがそこかしこに散りばめられている。楽しいのにずっと不穏。名作。 「だから今日も瞬点は、声明案を練るために、テーブルにノートを広げている。まだノートは自紙。なにも書かれていないページを見つめていると、どこからかため息が聞こえてくる。行列を作って並ぶのはいつも貧乏人ばかり。金持ちはいつでも先頭に割り込めるか、そもそも並ばなくてもいいようになっている。ノートの野線が憎い。罫線に字を並ばせようとするのは誰だ?」 (恋する少年十字軍 p.45) - 2025年5月28日
 すべてのことばが起こりますように柿木優,江藤健太郎,郡司ペギオ幸夫読んでる「あ、また光った。どう考えてもどう感じてももう一秒も続けられないことをそれでも続けることそうやってただ今この瞬間を生き繋いでいくことそしてそのことに真剣でありながら同時に全てを笑いとばすこと」 (すべてのことばが起こりますように p.114)
すべてのことばが起こりますように柿木優,江藤健太郎,郡司ペギオ幸夫読んでる「あ、また光った。どう考えてもどう感じてももう一秒も続けられないことをそれでも続けることそうやってただ今この瞬間を生き繋いでいくことそしてそのことに真剣でありながら同時に全てを笑いとばすこと」 (すべてのことばが起こりますように p.114) - 2025年5月18日
 長距離走者の孤独A.シリトー再読中「それに奴らはきまって、《わたし》とか《おれ》とか言うかわりに、《われわれが》《われわれは》とくる――たった一人の相手に対して、こっちには味方がたくさんいるんだぞという気がして、元気と正義感がわいてくるしくみだろう」 p.41-42
長距離走者の孤独A.シリトー再読中「それに奴らはきまって、《わたし》とか《おれ》とか言うかわりに、《われわれが》《われわれは》とくる――たった一人の相手に対して、こっちには味方がたくさんいるんだぞという気がして、元気と正義感がわいてくるしくみだろう」 p.41-42 - 2025年5月8日
 ユリイカ(2025 3(第57巻第4号))小林銅蟲,有元葉子,稲田俊輔,高山なおみ読んでるひとまず読んだのは、 藤田周「現代料理の人類学者の自炊でない自炊」 久保明教「おかわりパスタと虚無レシピ」 この2つの論考が隣り合ったのは偶然だろうか、その落差にクラクラした。高度な実践としての自炊と、インスタントな救いのある自炊(それは保守的な社会状況を温存または強化する側面がある)の、そのあいだについて。
ユリイカ(2025 3(第57巻第4号))小林銅蟲,有元葉子,稲田俊輔,高山なおみ読んでるひとまず読んだのは、 藤田周「現代料理の人類学者の自炊でない自炊」 久保明教「おかわりパスタと虚無レシピ」 この2つの論考が隣り合ったのは偶然だろうか、その落差にクラクラした。高度な実践としての自炊と、インスタントな救いのある自炊(それは保守的な社会状況を温存または強化する側面がある)の、そのあいだについて。 - 2025年5月8日
 そろそろ左派は〈経済〉を語ろうブレイディみかこ,北田暁大,松尾匡まだ読んでる新自由主義(ネオリベ)という用語の使われ方が気になって読み始めたら、おもしろくてしっかりめに読み進めてしまった。経済についてちゃんと勉強しないといけない……資本主義が嫌いな人のための経済入門的な本あったよね…… あと、リベラルということばの分裂(ヨーロッパ的な経済における自由主義という意味か、アメリカ的な社会・政治ないしは文化における自由主義か)については良い再認識になった。常に立ち返りたい。人によってリベラルの意味にズレが生じるので、ひとまず自分の基本方針として(松尾匡的な意味での)左翼または左派(レフト)を選びたい。 ※この本を公共的な場にアップするのであれば、以前告発があった北田暁大さんのハラスメント疑惑についても認識しておきたいが、公開されている事実関係があまりにすれ違っておりまだうまく掴めていません
そろそろ左派は〈経済〉を語ろうブレイディみかこ,北田暁大,松尾匡まだ読んでる新自由主義(ネオリベ)という用語の使われ方が気になって読み始めたら、おもしろくてしっかりめに読み進めてしまった。経済についてちゃんと勉強しないといけない……資本主義が嫌いな人のための経済入門的な本あったよね…… あと、リベラルということばの分裂(ヨーロッパ的な経済における自由主義という意味か、アメリカ的な社会・政治ないしは文化における自由主義か)については良い再認識になった。常に立ち返りたい。人によってリベラルの意味にズレが生じるので、ひとまず自分の基本方針として(松尾匡的な意味での)左翼または左派(レフト)を選びたい。 ※この本を公共的な場にアップするのであれば、以前告発があった北田暁大さんのハラスメント疑惑についても認識しておきたいが、公開されている事実関係があまりにすれ違っておりまだうまく掴めていません - 2025年5月6日
 百年と一日柴崎友香まだ読んでる各篇に付けられた内容を圧縮したタイトルが、このように語らなければ本来は短く要約してはいはいと終わってしまうような取るに足らない物語未満であることを、ユーモアをもってドライに示唆しているところがいい。それでも語るということ。
百年と一日柴崎友香まだ読んでる各篇に付けられた内容を圧縮したタイトルが、このように語らなければ本来は短く要約してはいはいと終わってしまうような取るに足らない物語未満であることを、ユーモアをもってドライに示唆しているところがいい。それでも語るということ。 - 2025年5月6日
 大不況には本を読む橋本治再読中「大資本の登場によって、その地域は一時的に活性化して「発展」の色を見せますが、その発展を持続させるためには、外からやって来た大資本の力に依存し、大資本の存在する「遠くの経済圏の一員」になるしかないのです。それが「侵略」ですが、この「侵略」は、いたって日常的な形で起こります。つまり、「就職」です」
大不況には本を読む橋本治再読中「大資本の登場によって、その地域は一時的に活性化して「発展」の色を見せますが、その発展を持続させるためには、外からやって来た大資本の力に依存し、大資本の存在する「遠くの経済圏の一員」になるしかないのです。それが「侵略」ですが、この「侵略」は、いたって日常的な形で起こります。つまり、「就職」です」 - 2025年4月20日
 幸せな日々多賀盛剛読んだ世界も宇宙も人間もこれまでずっとそうであったことが詩を読むことで創造されていく、と言いたくなるような壮大な矛盾が文字を通して生身の体にストンと落ちる。本書に通底する「順接」の力が大きく作用していそう。 「幸せな日々」というタイトルに、ちょっとおそろしさを感じる。
幸せな日々多賀盛剛読んだ世界も宇宙も人間もこれまでずっとそうであったことが詩を読むことで創造されていく、と言いたくなるような壮大な矛盾が文字を通して生身の体にストンと落ちる。本書に通底する「順接」の力が大きく作用していそう。 「幸せな日々」というタイトルに、ちょっとおそろしさを感じる。 - 2025年4月19日
- 2025年4月19日
- 2025年4月18日
- 2025年4月18日
 龍子 RYUKO(1巻)エルド吉水読み終わった
龍子 RYUKO(1巻)エルド吉水読み終わった - 2025年4月15日
- 2025年4月8日
 わたしの天気予報 (1973年)白石かずこたまにパラパラと矢吹伸彦の装幀に惹かれて購入。 深沢七郎や北園克衛との個人的なエピソードもあり。まだパラパラとしか読んでいないけど、なんとなく信頼できるような印象を受ける。
わたしの天気予報 (1973年)白石かずこたまにパラパラと矢吹伸彦の装幀に惹かれて購入。 深沢七郎や北園克衛との個人的なエピソードもあり。まだパラパラとしか読んでいないけど、なんとなく信頼できるような印象を受ける。 - 2025年4月7日
- 2025年4月2日
- 2025年4月2日
読み込み中...