ACE アセクシュアルから見たセックスと社会のこと

48件の記録
 Eukalyptus@euka_inrevarld2026年2月3日読み終わった『私自身が性的惹かれを経験することはないものの、他者には私に対する欲望を持って欲しかったのだ。』 『ACEアセクシュアルから見たセックスと社会のこと』315p.3 アセクシュアルの中にもスペクトラムがあって、性的惹かれを経験しない、しにくいとしても人との関わりが要らないわけではないし、誰かを好きになる事だってある。 そんな多様な在り方について、さまざまな視点から書かれたルポ。アセクシュアルの本はなかなか濃い内容のものが無い。入門書や浅い本であって専門書は無いから、こういう本が実は元祖だったりする。 類書がこれから増えると良いな、本当に、新書とかじゃなくて単行本で。
Eukalyptus@euka_inrevarld2026年2月3日読み終わった『私自身が性的惹かれを経験することはないものの、他者には私に対する欲望を持って欲しかったのだ。』 『ACEアセクシュアルから見たセックスと社会のこと』315p.3 アセクシュアルの中にもスペクトラムがあって、性的惹かれを経験しない、しにくいとしても人との関わりが要らないわけではないし、誰かを好きになる事だってある。 そんな多様な在り方について、さまざまな視点から書かれたルポ。アセクシュアルの本はなかなか濃い内容のものが無い。入門書や浅い本であって専門書は無いから、こういう本が実は元祖だったりする。 類書がこれから増えると良いな、本当に、新書とかじゃなくて単行本で。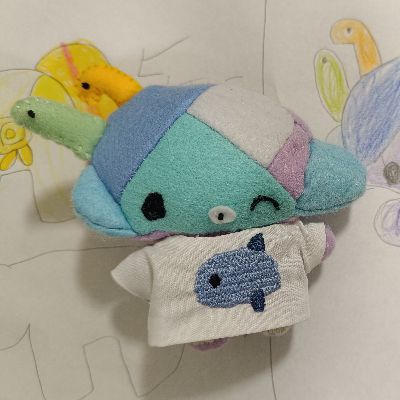 ゆのか@marsgarden2026年1月19日読み終わった川野芽生さんの著作を読むための下準備として読んだもの。 目の前で面白くて頭のいい人にいろんな話を聞かせてもらっているかのようなとっつきやすい本でした。 アセクシャルについて、自分にはあまりわからない、馴染みのないものなのではないか、という気持ちはなくなって、あれ? これは思い当たる節がある、わかるような気がする、ここまでいくと違う気がする、と、ちょっと引き寄せてみて、自分がそのことについて考えたことがなかったのはなぜなのか今のこの国の社会のありようについて考えながら読み終えました。 エースの一つならざる世界はまったくの異国ではなかったです。
ゆのか@marsgarden2026年1月19日読み終わった川野芽生さんの著作を読むための下準備として読んだもの。 目の前で面白くて頭のいい人にいろんな話を聞かせてもらっているかのようなとっつきやすい本でした。 アセクシャルについて、自分にはあまりわからない、馴染みのないものなのではないか、という気持ちはなくなって、あれ? これは思い当たる節がある、わかるような気がする、ここまでいくと違う気がする、と、ちょっと引き寄せてみて、自分がそのことについて考えたことがなかったのはなぜなのか今のこの国の社会のありようについて考えながら読み終えました。 エースの一つならざる世界はまったくの異国ではなかったです。
 犬山俊之@inuyamanihongo2026年1月2日読み終わった多くの当事者の方へのインタビューをもとにした、性と社会についてのルポエッセイ。 自分にとっては「言葉」についての本でもありました。 「アセクシャル」という語を知らなければ、「恋愛とは性行為を前提とした関係性である」という「常識」の外に出ることはできませんでした。しかし、同時に「アセクシャル」その他、様々な用語を知っても、それで一人一人の性的指向や恋愛感情を正確に表現できるわけではないのだとも思い知らされます。言葉の力と言葉の限界。 そして「アセクシャル」という語の意味を説明しようとする時、どうしても「欠如」という形で語ることになってしまうという陥穽。「他人に性的に惹かれない人」。この「〜ない人」という語りは、それが前提としている暗黙の基準を、そして、その特権性を隠蔽します。「歩けない人」「聞こえない人」「日本語が話せない人」。「〜ない人」はいちいち言語化される一方「ある人」はどんどん見えなくなってしまうのです。 そういうわけで、「第7章 恋愛再考」は特に付箋まみれになるほど、読み応えがありました。人は異性に(或いは同性に)性的に惹かれるのが「普通」だと漠然と思っていた「こちら側」の意識が揺さぶられます。正直、自分(犬山)は今まで一度も自分自身の性的な欲望とか、恋愛感情とかをきちんと考えたことがありませんでした。とにかく、その「考えたことがなかった」事に自分で驚きました。それでいて、他人に対して「彼女/彼氏はいないの?」とか「結婚しないのか?」といった言葉を発していたのです。その攻撃性に無自覚に。(メモ: この章に『最小の結婚』(エリザベス・ブレイク)への言及あり) 各章、様々な当事者の声を丁寧に拾っていて、そこにかぶさる著者の言葉が途方もなく深い。テレビドラマや漫画、また時事的なことへの言及を絡めながら、平易な口調で読者に語りかけるような文体はすごく読みやすいのですが、内容はすごく骨太です。練られているし、考え抜かれていると感じました。そこが本書で一番感心した点でもあります。 また、こうした文章を日本語を丁寧に日本語に翻訳した翻訳者の方の実力にも脱帽。アメリカ及び日本におけるこの分野へのの深い理解と同時に、様々なコンテンツ、時事問題についての広い知識なしにはできないお仕事。ありがとうございました。 ジェンダーやセクシュアリティ問題を考える上で非常に勉強になる一冊。 自分に関して言えば、ホントに「人生を変えた」一冊と言えます▼
犬山俊之@inuyamanihongo2026年1月2日読み終わった多くの当事者の方へのインタビューをもとにした、性と社会についてのルポエッセイ。 自分にとっては「言葉」についての本でもありました。 「アセクシャル」という語を知らなければ、「恋愛とは性行為を前提とした関係性である」という「常識」の外に出ることはできませんでした。しかし、同時に「アセクシャル」その他、様々な用語を知っても、それで一人一人の性的指向や恋愛感情を正確に表現できるわけではないのだとも思い知らされます。言葉の力と言葉の限界。 そして「アセクシャル」という語の意味を説明しようとする時、どうしても「欠如」という形で語ることになってしまうという陥穽。「他人に性的に惹かれない人」。この「〜ない人」という語りは、それが前提としている暗黙の基準を、そして、その特権性を隠蔽します。「歩けない人」「聞こえない人」「日本語が話せない人」。「〜ない人」はいちいち言語化される一方「ある人」はどんどん見えなくなってしまうのです。 そういうわけで、「第7章 恋愛再考」は特に付箋まみれになるほど、読み応えがありました。人は異性に(或いは同性に)性的に惹かれるのが「普通」だと漠然と思っていた「こちら側」の意識が揺さぶられます。正直、自分(犬山)は今まで一度も自分自身の性的な欲望とか、恋愛感情とかをきちんと考えたことがありませんでした。とにかく、その「考えたことがなかった」事に自分で驚きました。それでいて、他人に対して「彼女/彼氏はいないの?」とか「結婚しないのか?」といった言葉を発していたのです。その攻撃性に無自覚に。(メモ: この章に『最小の結婚』(エリザベス・ブレイク)への言及あり) 各章、様々な当事者の声を丁寧に拾っていて、そこにかぶさる著者の言葉が途方もなく深い。テレビドラマや漫画、また時事的なことへの言及を絡めながら、平易な口調で読者に語りかけるような文体はすごく読みやすいのですが、内容はすごく骨太です。練られているし、考え抜かれていると感じました。そこが本書で一番感心した点でもあります。 また、こうした文章を日本語を丁寧に日本語に翻訳した翻訳者の方の実力にも脱帽。アメリカ及び日本におけるこの分野へのの深い理解と同時に、様々なコンテンツ、時事問題についての広い知識なしにはできないお仕事。ありがとうございました。 ジェンダーやセクシュアリティ問題を考える上で非常に勉強になる一冊。 自分に関して言えば、ホントに「人生を変えた」一冊と言えます▼






 河野@kono_a162025年12月24日読み終わった相当集中して読んだがかなり時間がかかった、ジェンダー学と海外の差別については一般レベルで知っていないと難しいと思う。多分1周だと理解できてないと思うが、今回の感想。 自認クエスチョン寄りのアセクシャル、だったんだがそれのせいで少し前から他人と喧嘩することが増えた。常に被害妄想に囚われていて自分は普通ではないと悩み続けている。 途中で出てきた「アセクではなくゲイだったら疎外感を感じなくて済む」という言葉が残っている。誰かと関係が持てる人間の方が正しいと思っている。 大好きな幼馴染がいた。一生一緒にいると思ったが彼氏ができて遠い地域に住み始めた。私は幼馴染と同居できると15年間思っていた。 「その人が私の人生にとって重要であるように私もその人の人生で重要なのだという、ある種の確証が欲しかったのかな」 友愛に関する章で出てきた言葉で大泣きした。私は幼馴染に必要とされているから1人の人として生きていたのにそれを失ってしまった。それ以降は前より一層 現実の人間に関わらずに生きている。他者に依存したらまた失ってしまう。 普通だったらよかったと悩む人間がたくさん出てきて、少しだけ自分の考え方にも自信が持てた。まだまだ苦しむことがあると思うけど、他人に嫉妬せずに自分を保ちながら1人で生きていく。もう誰も傷つけたくない。
河野@kono_a162025年12月24日読み終わった相当集中して読んだがかなり時間がかかった、ジェンダー学と海外の差別については一般レベルで知っていないと難しいと思う。多分1周だと理解できてないと思うが、今回の感想。 自認クエスチョン寄りのアセクシャル、だったんだがそれのせいで少し前から他人と喧嘩することが増えた。常に被害妄想に囚われていて自分は普通ではないと悩み続けている。 途中で出てきた「アセクではなくゲイだったら疎外感を感じなくて済む」という言葉が残っている。誰かと関係が持てる人間の方が正しいと思っている。 大好きな幼馴染がいた。一生一緒にいると思ったが彼氏ができて遠い地域に住み始めた。私は幼馴染と同居できると15年間思っていた。 「その人が私の人生にとって重要であるように私もその人の人生で重要なのだという、ある種の確証が欲しかったのかな」 友愛に関する章で出てきた言葉で大泣きした。私は幼馴染に必要とされているから1人の人として生きていたのにそれを失ってしまった。それ以降は前より一層 現実の人間に関わらずに生きている。他者に依存したらまた失ってしまう。 普通だったらよかったと悩む人間がたくさん出てきて、少しだけ自分の考え方にも自信が持てた。まだまだ苦しむことがあると思うけど、他人に嫉妬せずに自分を保ちながら1人で生きていく。もう誰も傷つけたくない。 みと@ss86l2025年12月18日読み終わったアセクシュアル本としては2冊目以降に読むのがおすすめ。エッセイということもあってか、アセクシュアルの説明に留まらず社会問題にまで言及していてとても読み応えがあった
みと@ss86l2025年12月18日読み終わったアセクシュアル本としては2冊目以降に読むのがおすすめ。エッセイということもあってか、アセクシュアルの説明に留まらず社会問題にまで言及していてとても読み応えがあった
 ひろき@bayleaf2025年8月13日読んでる借りてきた1,2章 ・性的惹かれを経験しない人(アセクシャル)≠セックスが嫌いな人 ・性的惹かれと性行動、(性欲動と同義?)は同じとではない ・セクシュアリティと性的惹かれについて十分綿密に考える人が少ないという事実のまずさ(エースの範囲は広い) 具体例:エースの編集者であるサラが、マスターバージョンするのは「シモのところのチリチリ」を感じる時だが、ある人や行為を見ることで、自身の身体に物理的な変化が掻き立てられたり、自分の心中に欲望がかき立てられたりといった事はわからないことだった(p.52) ・性欲動の強いエースもいれば、性欲動の少ないストレートもいるわけやな ・セクシュアリティは人々が自身を性的に表現する方法というのが曖昧な説明らしい。性的指向よりももっといろんなもの(性自認、性的行動、性的欲求、価値観、関係性等?)を含む。 ・『ネイキッド・アトラクション』おもしろそう。確かに性器のみをあらゆる文脈から切り離して見ても興奮はしなさそうである ・これら3つ(美的惹かれと恋愛的惹かれと性的惹かれ)の主な惹かれのタイプに加え、エースはまた接触の惹かれ、もしくは感情的惹かれ、感情的および知的惹かれなどについても議論している。←このように欲望が細分化される感じが自分にも引きつけて考えられて読んでて楽しい 4章 セックスは常に政治的。フェミニストにもセックスポジティブとセックスネガティブがあるが、どちらも家父長制や抑圧からの解放を求める態度としては同じ 特権サークルの話も面白い。プログレッシブが偉いわけでもバニラが劣ってるわけでもない。3章ででてきた強制的異性愛による刷り込みの関係も しかしこの章をまとめるのは難しい… 9章くらいまで読んで返却 登場人物が多く、物語っぽいのが後半読みづらくなってきた…
ひろき@bayleaf2025年8月13日読んでる借りてきた1,2章 ・性的惹かれを経験しない人(アセクシャル)≠セックスが嫌いな人 ・性的惹かれと性行動、(性欲動と同義?)は同じとではない ・セクシュアリティと性的惹かれについて十分綿密に考える人が少ないという事実のまずさ(エースの範囲は広い) 具体例:エースの編集者であるサラが、マスターバージョンするのは「シモのところのチリチリ」を感じる時だが、ある人や行為を見ることで、自身の身体に物理的な変化が掻き立てられたり、自分の心中に欲望がかき立てられたりといった事はわからないことだった(p.52) ・性欲動の強いエースもいれば、性欲動の少ないストレートもいるわけやな ・セクシュアリティは人々が自身を性的に表現する方法というのが曖昧な説明らしい。性的指向よりももっといろんなもの(性自認、性的行動、性的欲求、価値観、関係性等?)を含む。 ・『ネイキッド・アトラクション』おもしろそう。確かに性器のみをあらゆる文脈から切り離して見ても興奮はしなさそうである ・これら3つ(美的惹かれと恋愛的惹かれと性的惹かれ)の主な惹かれのタイプに加え、エースはまた接触の惹かれ、もしくは感情的惹かれ、感情的および知的惹かれなどについても議論している。←このように欲望が細分化される感じが自分にも引きつけて考えられて読んでて楽しい 4章 セックスは常に政治的。フェミニストにもセックスポジティブとセックスネガティブがあるが、どちらも家父長制や抑圧からの解放を求める態度としては同じ 特権サークルの話も面白い。プログレッシブが偉いわけでもバニラが劣ってるわけでもない。3章ででてきた強制的異性愛による刷り込みの関係も しかしこの章をまとめるのは難しい… 9章くらいまで読んで返却 登場人物が多く、物語っぽいのが後半読みづらくなってきた…
 socotsu@shelf_soya2025年7月9日読み終わった訳者あとがきにもあるように、とても砕けた口調と学術的な知識、かための文体と比喩表現が織り混ざった文章なので、翻訳は大変だっただろうなと想像されるし、読むのに立ち止まる箇所がゼロではないんだけど、個人的にはこのようなリズムの文章で書かれたクィア・スタディーズに関する本ってとてもいいなと思う。
socotsu@shelf_soya2025年7月9日読み終わった訳者あとがきにもあるように、とても砕けた口調と学術的な知識、かための文体と比喩表現が織り混ざった文章なので、翻訳は大変だっただろうなと想像されるし、読むのに立ち止まる箇所がゼロではないんだけど、個人的にはこのようなリズムの文章で書かれたクィア・スタディーズに関する本ってとてもいいなと思う。

 socotsu@shelf_soya2025年7月7日まだ読んでる強制的性愛社会という視点で自分が生きる社会について考える。自分の属性のステレオタイプとセクシュアリティの関係性を考えてしまい、それが自分の「本当」か判断をつけることが非常にむずかしくなる、という「第5章 ホワイトウォッシュされて」のインターセクショナリティに関する記述の細やかさは、当人にとって○○人(「人種」以外の適当な表現を探している)、ジェンダー、セクシュアリティはいずれも重要なものだが、個別に抜き出すものではなく、その人を構成する全体の一要素であり、それぞれの要素は限定的な仕方で交差しているわけではない、という事実を理解するために非常に助けになった。それは理解のための「事例」ではなく同じ世界に生きている人の現実として提示されていることを忘れてはならないのだが。
socotsu@shelf_soya2025年7月7日まだ読んでる強制的性愛社会という視点で自分が生きる社会について考える。自分の属性のステレオタイプとセクシュアリティの関係性を考えてしまい、それが自分の「本当」か判断をつけることが非常にむずかしくなる、という「第5章 ホワイトウォッシュされて」のインターセクショナリティに関する記述の細やかさは、当人にとって○○人(「人種」以外の適当な表現を探している)、ジェンダー、セクシュアリティはいずれも重要なものだが、個別に抜き出すものではなく、その人を構成する全体の一要素であり、それぞれの要素は限定的な仕方で交差しているわけではない、という事実を理解するために非常に助けになった。それは理解のための「事例」ではなく同じ世界に生きている人の現実として提示されていることを忘れてはならないのだが。


 Aruiwa@atodeyomu2025年6月11日読んでるとりあえず2章まで。経験論的に書かれているのでアセクシュアルの正確な定義を追究する本ではなく、しかしそこが重要である(そして読みやすい)。 アセクシュアルは性行為をしない/嫌悪するのではなく、「性的惹かれ」のない人のことを指す、とあっていままでの自分の雑な理解がころっと覆された。性的惹かれ、恋愛的惹かれ、美的惹かれは同じではないということ。 「はい、復唱してくださいね。性的惹かれは性欲動ではありません。これら二つの現象はしばしば取り替え可能なものとして扱われているけれど、それらが別物だと理解することで、エースの経験を説明しやすくなるのだ」p.52 「セクシュアリティは性的指向以上のものであり、惹かれは性的惹かれ以上のものだが、人間はあたかも、性的関心が唯一の理由であるかのように振る舞う。私たち自身が他者に心揺さぶられると感じる理由はそれだけだというように」p.68
Aruiwa@atodeyomu2025年6月11日読んでるとりあえず2章まで。経験論的に書かれているのでアセクシュアルの正確な定義を追究する本ではなく、しかしそこが重要である(そして読みやすい)。 アセクシュアルは性行為をしない/嫌悪するのではなく、「性的惹かれ」のない人のことを指す、とあっていままでの自分の雑な理解がころっと覆された。性的惹かれ、恋愛的惹かれ、美的惹かれは同じではないということ。 「はい、復唱してくださいね。性的惹かれは性欲動ではありません。これら二つの現象はしばしば取り替え可能なものとして扱われているけれど、それらが別物だと理解することで、エースの経験を説明しやすくなるのだ」p.52 「セクシュアリティは性的指向以上のものであり、惹かれは性的惹かれ以上のものだが、人間はあたかも、性的関心が唯一の理由であるかのように振る舞う。私たち自身が他者に心揺さぶられると感じる理由はそれだけだというように」p.68







 そらばら@kufuku182025年4月8日読み終わった借りてきた松浦優「アセクシュアル アロマンティック入門」集英社(2025)と同時並行で読んだ。ルポエッセイではあるが、多くの言葉や概念を丁寧に説明されてて読み進めやすかった。
そらばら@kufuku182025年4月8日読み終わった借りてきた松浦優「アセクシュアル アロマンティック入門」集英社(2025)と同時並行で読んだ。ルポエッセイではあるが、多くの言葉や概念を丁寧に説明されてて読み進めやすかった。



 萌生@moet-17152025年3月12日読みたいこういう本は自分の考えてきたことに疑問を投げかけてくれる。 「それって、そうなのかな?」 私自身はアセクシャルではないけど、読んで性にまつわることへの自分なりの答えが出せればいいな。
萌生@moet-17152025年3月12日読みたいこういう本は自分の考えてきたことに疑問を投げかけてくれる。 「それって、そうなのかな?」 私自身はアセクシャルではないけど、読んで性にまつわることへの自分なりの答えが出せればいいな。
 amy@note_15812025年3月10日かつて読んだ感想当事者である著者が「他者に性的に惹かれない」という視点から、セックスや社会の常識を問い直すルポエッセイ。 交際・結婚におけるセックスの当たり前とされる役割や、「男らしさ」へのプレッシャー、恋愛と友情の境界、同性同士の恋愛におけるセックスの中心性、フェミニストに対する性的なステレオタイプなど、多岐にわたるテーマを扱っている 人種にも性的なステレオタイプというものがあり、とりわけアジア人女性は性を無化されがちだという。口調がやわらかくて人に仕えたがりで服従的だという。また東アジア人は行儀が良く、”手本となるべきマイノリティ”と考えられていて、極右白人至上主義の人たちはアジア人女性とデートなどの関係を結びたがるという。本邦の環境のせいか、アジア人が白人至上主義の人たちからどういう偏見をされているかというのを知る機会があまりなかったのである意味では新鮮だった。同時に偏見というものには何の根拠もないことがわかり、やはり偏見や何となくのイメージというものは自分のなかに育てていくべきではないとも思った ・言葉は私たちを裏切る。性的な惹かれを達成や興奮それ自体の類義語にすることによって。 これはめちゃめちゃ思い当たりがある。特にフィクションコンテンツ を楽しむオタクで、クィアリーディングに基づく二次創作を愛好するようなファンダムでは特に男性キャラ同士がお互いの信念がぶつかって拳を交えたり、争ったり、勝負事に持ち込んだりするようなイベントが作中で起こる。そういったものに対して”実質セックス”というような言葉を見かける。一度や二度ではなくある程度観測できるものだと思われる 私は二次創作で同性同士の恋愛もの性愛ものの作品を愛好したり創作したりするが、この作中で二者間の感情が激しく行き交うような出来事が”実質セックス”とは思ったことがないのだ 私はデミセクシュアルだと思っているのだが、もしかしてそれが関係しているのだろうか?と思ってみたりもした ただサンプル数が私だけなのでそのへんの検証がよくわからない。もしAスペクトラムの人で自分はこう、というものを聞かせてくれる人がいたら聞かせてほしいです…切実に… ・欲望がラベルに合わないなら、調整されたり捨てられたりすべきはしばしばラベルなのであって、欲望ではない 内実が社会に用意されたものにあわないのであれば、当然のことながらその内実に即した名前なり入れ物なりが必要になる もちろんそのなかにはさらに細かい区分けやグラデーションが発生する可能性もあるが、そういうときはまた内実に即したものに変更していけばよいのだと思う。それがなされないと社会から透明化されて存在を消されるからだ。もっとACEの概念が広く知られる必要がある またこの本で初めて知ったのだが恋愛的な愛が不当に崇め立てられ中心化されることを恋愛伴侶規範と呼ぶらしい。 そして恋愛伴侶規範のせいで独身の人々の調査が不足しているというのだ このことも私は知らなかった。基本的にみんなが他者と性的な関係を持ちたいということを前提に社会科学などの分野が研究されたりしてきたということらしい。これは本書での指摘を読むまで考えもしなかった。そうなるとあらゆる調査でACEの人が取りこぼされているということになる そしてそこに気づいていない研究者は今もACEを取りこぼしたまま研究をしているということになる。ラベルの話のでもそうだが、やはり名前がつくことによって存在が認知される、ということは大きい 本書のなかではエースでありながらアローと交際する人たちや実際に性的な行為をしているエースもいることが書かれていた 現実的にそういった営みをしているエースのこともエースとして捉えることやエースであってもパートナーやセックスへの関わりは多種多様で大切なことはあらゆるエースのかたちを受け入れることであるということは章の至るところで書かれている またフェミニズムでは女性の性の解放がとりわけセックスにアクティブであることと結び付けられいてるがそれに関する批判も本書内ではなされている エースを解放することがあらゆる人を解放する、そういう力強いメッセージが込められている
amy@note_15812025年3月10日かつて読んだ感想当事者である著者が「他者に性的に惹かれない」という視点から、セックスや社会の常識を問い直すルポエッセイ。 交際・結婚におけるセックスの当たり前とされる役割や、「男らしさ」へのプレッシャー、恋愛と友情の境界、同性同士の恋愛におけるセックスの中心性、フェミニストに対する性的なステレオタイプなど、多岐にわたるテーマを扱っている 人種にも性的なステレオタイプというものがあり、とりわけアジア人女性は性を無化されがちだという。口調がやわらかくて人に仕えたがりで服従的だという。また東アジア人は行儀が良く、”手本となるべきマイノリティ”と考えられていて、極右白人至上主義の人たちはアジア人女性とデートなどの関係を結びたがるという。本邦の環境のせいか、アジア人が白人至上主義の人たちからどういう偏見をされているかというのを知る機会があまりなかったのである意味では新鮮だった。同時に偏見というものには何の根拠もないことがわかり、やはり偏見や何となくのイメージというものは自分のなかに育てていくべきではないとも思った ・言葉は私たちを裏切る。性的な惹かれを達成や興奮それ自体の類義語にすることによって。 これはめちゃめちゃ思い当たりがある。特にフィクションコンテンツ を楽しむオタクで、クィアリーディングに基づく二次創作を愛好するようなファンダムでは特に男性キャラ同士がお互いの信念がぶつかって拳を交えたり、争ったり、勝負事に持ち込んだりするようなイベントが作中で起こる。そういったものに対して”実質セックス”というような言葉を見かける。一度や二度ではなくある程度観測できるものだと思われる 私は二次創作で同性同士の恋愛もの性愛ものの作品を愛好したり創作したりするが、この作中で二者間の感情が激しく行き交うような出来事が”実質セックス”とは思ったことがないのだ 私はデミセクシュアルだと思っているのだが、もしかしてそれが関係しているのだろうか?と思ってみたりもした ただサンプル数が私だけなのでそのへんの検証がよくわからない。もしAスペクトラムの人で自分はこう、というものを聞かせてくれる人がいたら聞かせてほしいです…切実に… ・欲望がラベルに合わないなら、調整されたり捨てられたりすべきはしばしばラベルなのであって、欲望ではない 内実が社会に用意されたものにあわないのであれば、当然のことながらその内実に即した名前なり入れ物なりが必要になる もちろんそのなかにはさらに細かい区分けやグラデーションが発生する可能性もあるが、そういうときはまた内実に即したものに変更していけばよいのだと思う。それがなされないと社会から透明化されて存在を消されるからだ。もっとACEの概念が広く知られる必要がある またこの本で初めて知ったのだが恋愛的な愛が不当に崇め立てられ中心化されることを恋愛伴侶規範と呼ぶらしい。 そして恋愛伴侶規範のせいで独身の人々の調査が不足しているというのだ このことも私は知らなかった。基本的にみんなが他者と性的な関係を持ちたいということを前提に社会科学などの分野が研究されたりしてきたということらしい。これは本書での指摘を読むまで考えもしなかった。そうなるとあらゆる調査でACEの人が取りこぼされているということになる そしてそこに気づいていない研究者は今もACEを取りこぼしたまま研究をしているということになる。ラベルの話のでもそうだが、やはり名前がつくことによって存在が認知される、ということは大きい 本書のなかではエースでありながらアローと交際する人たちや実際に性的な行為をしているエースもいることが書かれていた 現実的にそういった営みをしているエースのこともエースとして捉えることやエースであってもパートナーやセックスへの関わりは多種多様で大切なことはあらゆるエースのかたちを受け入れることであるということは章の至るところで書かれている またフェミニズムでは女性の性の解放がとりわけセックスにアクティブであることと結び付けられいてるがそれに関する批判も本書内ではなされている エースを解放することがあらゆる人を解放する、そういう力強いメッセージが込められている






 台湾犬@Masa_SMZ2023年11月3日かつて読んだ人生の多くのことが恋愛、そして結婚、が中心になっている。そこに性のことが絡みつく。でもそれは制度が後付けしていったもの。人と人との付き合い方の本質を知ることができた。
台湾犬@Masa_SMZ2023年11月3日かつて読んだ人生の多くのことが恋愛、そして結婚、が中心になっている。そこに性のことが絡みつく。でもそれは制度が後付けしていったもの。人と人との付き合い方の本質を知ることができた。
 さかな@sakana13162023年6月1日読んだ2年前 アセクシャルの啓発週間の時に読んだような エッセイぽくて読みやすかったし、ちゃんと自分の中の知が刷新されるような学びも沢山あって良かった。 セックスについて何かしら疑問や歪みを感じたことある人にはもちろんオススメしたいけど、逆にセックスになにも疑問抱いたことないや、ってひとにも(もしいれば)オススメしたい本かも セックスと恋愛ってセットなのかな といった疑問がある人にもオススメかもしれない
さかな@sakana13162023年6月1日読んだ2年前 アセクシャルの啓発週間の時に読んだような エッセイぽくて読みやすかったし、ちゃんと自分の中の知が刷新されるような学びも沢山あって良かった。 セックスについて何かしら疑問や歪みを感じたことある人にはもちろんオススメしたいけど、逆にセックスになにも疑問抱いたことないや、ってひとにも(もしいれば)オススメしたい本かも セックスと恋愛ってセットなのかな といった疑問がある人にもオススメかもしれない



























