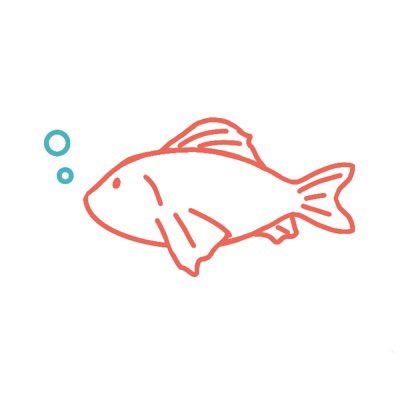
潮満希
@chosekido_m
趣味で文章を書いている人間。ここには、これからも大切に読み続けたい本の簡潔な読書録を綴っています。
- 2025年12月26日
 何度でも読みたい古本屋で出逢った本結城信一が初めて出した小品集。 「アルプ」で掲載されていた文章を中心に集められた作品集であり、まるで小説とエッセーを行き来するかのような、日常の中に潜む幻想の世界へと飛翔してゆく様に、自らの心までもが引き摺られてゆくように感じられる。 個人的には『湖尻の芒』が大変に慕わしく、野添教授とゆふ子さんの物語の続きが気になって気になって仕方がない。あまりにも気になり過ぎて、恐らく続きはないとわかりつつも、ついには全集にまで手を出してしまった。また、桃源台の方にあるロープウェイのゴンドラを“赤い金魚”と表現しており、その表現力にも個人的には舌を巻いている。 古本屋で偶然見つけた作家であったが、辻邦生以来の衝撃を受けており、これまた生涯の付き合いになりそうである。
何度でも読みたい古本屋で出逢った本結城信一が初めて出した小品集。 「アルプ」で掲載されていた文章を中心に集められた作品集であり、まるで小説とエッセーを行き来するかのような、日常の中に潜む幻想の世界へと飛翔してゆく様に、自らの心までもが引き摺られてゆくように感じられる。 個人的には『湖尻の芒』が大変に慕わしく、野添教授とゆふ子さんの物語の続きが気になって気になって仕方がない。あまりにも気になり過ぎて、恐らく続きはないとわかりつつも、ついには全集にまで手を出してしまった。また、桃源台の方にあるロープウェイのゴンドラを“赤い金魚”と表現しており、その表現力にも個人的には舌を巻いている。 古本屋で偶然見つけた作家であったが、辻邦生以来の衝撃を受けており、これまた生涯の付き合いになりそうである。 - 2025年8月12日
 もうひとつの夜へ辻邦生何度でも読みたい古本屋で出逢った本純文学を描いてきた辻邦生作品としては珍しいコズミック・ホラーの雰囲気を濃く漂わせる意欲的な中編小説。 自宅の食卓に横たわり、全裸の状態でショック死していた立花朋二を巡り、友人たちと“なぜそんなことになったのか”と話をしていた小説家の「私」は、立花朋二と仲の良かった砧と別れた後、自宅のポストに一冊の大学ノートが送りつけられていることに気がつく。 そこには、今や死者となった立花朋二の名前が送り主として記されており、それを一読した「私」は、孤独に苛まれた者たちへの警告として、世間にこの大学ノートを公表することを選択する——というのが本作品のあらすじである。 この物語の主人公である立花朋二は、ある時から自らの腹の下で何かが這いずり回っていることに気がつき、その正体を知るために自分自身で腹を捌いて白く柔らかで繭のような姿をした奇妙なその生命体をこの世に生み出してしまう。 繭のような生き物は、騒音、爆速、光を養分に、どんどんと鳥のような姿へと成長していくのだが、作中の冒頭にもカラオケスナックの名として「火の鳥」という言葉が出ていることを思うと、不死鳥をモチーフにした存在のようにも思われる。ただし、それはあくまでも姿形の話であり、その本質は人々の心に巣食う“孤独”が実体を伴って肥大化した姿なのではないかと個人的には思うところである。騒音、爆速に身を置く時、立花朋二は楽しそうであり、それらの行為は、実際、孤独を誤魔化す——あくまでも、“癒す”ものではないというところが重要である——作用があるようにも感じられる。 立花朋二は、繭のような生き物と出逢ったことで、それを守ること、生かすことへと心血を注ぐようになり、この生き物を育てるため、“その他には何もいらない”と考えるようになっていくのだが、そのために彼はそれ以外の繋がりを最終的に自ら絶ってしまい、「私」が冒頭で嘆いた孤独の悲劇に向かって進んでゆくのである。 物語中、“こいつ”や“そいつ”と呼ばれる繭のような生命体の正体が明らかになることは決してなく、また、その存在が実在したかどうかさえ定かではない。 “終わりに消化不良感がある”とはパートナーの言葉であるが、だからこそ、考察が捗る一面もあり、この生命体の正体や様々な事由に思いを馳せて、誰かに語りたくなるようにも思われる。 もし興味がある方がいるならば、是非是非一読してほしい。
もうひとつの夜へ辻邦生何度でも読みたい古本屋で出逢った本純文学を描いてきた辻邦生作品としては珍しいコズミック・ホラーの雰囲気を濃く漂わせる意欲的な中編小説。 自宅の食卓に横たわり、全裸の状態でショック死していた立花朋二を巡り、友人たちと“なぜそんなことになったのか”と話をしていた小説家の「私」は、立花朋二と仲の良かった砧と別れた後、自宅のポストに一冊の大学ノートが送りつけられていることに気がつく。 そこには、今や死者となった立花朋二の名前が送り主として記されており、それを一読した「私」は、孤独に苛まれた者たちへの警告として、世間にこの大学ノートを公表することを選択する——というのが本作品のあらすじである。 この物語の主人公である立花朋二は、ある時から自らの腹の下で何かが這いずり回っていることに気がつき、その正体を知るために自分自身で腹を捌いて白く柔らかで繭のような姿をした奇妙なその生命体をこの世に生み出してしまう。 繭のような生き物は、騒音、爆速、光を養分に、どんどんと鳥のような姿へと成長していくのだが、作中の冒頭にもカラオケスナックの名として「火の鳥」という言葉が出ていることを思うと、不死鳥をモチーフにした存在のようにも思われる。ただし、それはあくまでも姿形の話であり、その本質は人々の心に巣食う“孤独”が実体を伴って肥大化した姿なのではないかと個人的には思うところである。騒音、爆速に身を置く時、立花朋二は楽しそうであり、それらの行為は、実際、孤独を誤魔化す——あくまでも、“癒す”ものではないというところが重要である——作用があるようにも感じられる。 立花朋二は、繭のような生き物と出逢ったことで、それを守ること、生かすことへと心血を注ぐようになり、この生き物を育てるため、“その他には何もいらない”と考えるようになっていくのだが、そのために彼はそれ以外の繋がりを最終的に自ら絶ってしまい、「私」が冒頭で嘆いた孤独の悲劇に向かって進んでゆくのである。 物語中、“こいつ”や“そいつ”と呼ばれる繭のような生命体の正体が明らかになることは決してなく、また、その存在が実在したかどうかさえ定かではない。 “終わりに消化不良感がある”とはパートナーの言葉であるが、だからこそ、考察が捗る一面もあり、この生命体の正体や様々な事由に思いを馳せて、誰かに語りたくなるようにも思われる。 もし興味がある方がいるならば、是非是非一読してほしい。 - 2025年6月11日
 猫町萩原朔太郎何度でも読みたい古本屋で出逢った本詩人として有名な萩原朔太郎の小説作品。 冒頭には、哲学者であるショーペンハウアーの蠅の現象と“物そのもの”に対する言葉がエピグラフとして引用されており、この『猫町』という作品の理解を助けてくれる。 主人公である“私”——おそらくは、萩原朔太郎本人——は、もともと旅に浪漫を抱いていたが、それが「同一空間における同一事物の移動」であると思うようになって以来、旅をすることへの興味とロマンスを失くしてしまう。しかし、“私”にはその本心として旅をしたい欲求があるらしく、過去にはモルヒネなどを使用した幻覚世界の“旅行”にも勤しんでいた。ただ、それらが身体を蝕むものであったことから、“私”はそういった“旅行”を止めざるを得なくなり、運動のための散歩をするようになるのだが、その中で、方向感覚を失った際、世界の様相が反転する現象——“曰く、「磁石を反対に裏返した、宇宙の逆空間」”——に出逢い、“私”はこれに楽しみを見出すようになる。 この物語は、そうした“旅”の中で出逢ったとある“猫の町”についての話であり、幻想的な雰囲気を孕むと共に、一種の悍ましさを見るものへと意識させる。 長崎出版から出ている『猫町』には、金井田英津子さんの絵がふんだんに用いられており、個人的にはその絶妙な作風が萩原朔太郎の持つ幻想的な世界観をより増幅させている印象を受け、大変に慕わしい。 短なお話であり、青空文庫にも置かれているため、興味がある方には是非ともおすすめしたい。
猫町萩原朔太郎何度でも読みたい古本屋で出逢った本詩人として有名な萩原朔太郎の小説作品。 冒頭には、哲学者であるショーペンハウアーの蠅の現象と“物そのもの”に対する言葉がエピグラフとして引用されており、この『猫町』という作品の理解を助けてくれる。 主人公である“私”——おそらくは、萩原朔太郎本人——は、もともと旅に浪漫を抱いていたが、それが「同一空間における同一事物の移動」であると思うようになって以来、旅をすることへの興味とロマンスを失くしてしまう。しかし、“私”にはその本心として旅をしたい欲求があるらしく、過去にはモルヒネなどを使用した幻覚世界の“旅行”にも勤しんでいた。ただ、それらが身体を蝕むものであったことから、“私”はそういった“旅行”を止めざるを得なくなり、運動のための散歩をするようになるのだが、その中で、方向感覚を失った際、世界の様相が反転する現象——“曰く、「磁石を反対に裏返した、宇宙の逆空間」”——に出逢い、“私”はこれに楽しみを見出すようになる。 この物語は、そうした“旅”の中で出逢ったとある“猫の町”についての話であり、幻想的な雰囲気を孕むと共に、一種の悍ましさを見るものへと意識させる。 長崎出版から出ている『猫町』には、金井田英津子さんの絵がふんだんに用いられており、個人的にはその絶妙な作風が萩原朔太郎の持つ幻想的な世界観をより増幅させている印象を受け、大変に慕わしい。 短なお話であり、青空文庫にも置かれているため、興味がある方には是非ともおすすめしたい。 - 2025年3月10日
 衣巻省三作品集 街のスタイル山本善行,衣巻省三何度でも読みたい本屋で出逢った本街の本屋で見かけて、カバーに納められた表紙の美しさと気取らない詩の慕わしさに魅入られて購入した本。 江戸川乱歩と同時代——大正時代の作家、衣巻省三の作品集。 帯にも書かれている通り、ここに収録された詩は、どれも普段着を身に纏ったような詩である。ラフなスタイルというのは、一見すれば確かにシンプルなようにも思えるかもしれないが、それ故の美しさが、この作品には内包されている。 “作品集”と書かれている通り、詩だけでなく、小説もまた収録されている。 大正時代に書かれたとは思えないほどの新しさが詰まった作風だけに、その作家の思考にも触れたいと願うが——衣巻省三のエッセイなどが気軽に読める環境ではないことだけが悔やまれる。
衣巻省三作品集 街のスタイル山本善行,衣巻省三何度でも読みたい本屋で出逢った本街の本屋で見かけて、カバーに納められた表紙の美しさと気取らない詩の慕わしさに魅入られて購入した本。 江戸川乱歩と同時代——大正時代の作家、衣巻省三の作品集。 帯にも書かれている通り、ここに収録された詩は、どれも普段着を身に纏ったような詩である。ラフなスタイルというのは、一見すれば確かにシンプルなようにも思えるかもしれないが、それ故の美しさが、この作品には内包されている。 “作品集”と書かれている通り、詩だけでなく、小説もまた収録されている。 大正時代に書かれたとは思えないほどの新しさが詰まった作風だけに、その作家の思考にも触れたいと願うが——衣巻省三のエッセイなどが気軽に読める環境ではないことだけが悔やまれる。 - 2025年3月10日
 ともだちは海のにおい工藤直子,長新太Readsで出逢った本何度でも読みたいReadsで初めてこの本の存在を知り、絶対に購入したいと思った本。 静か過ぎて寂しい夜の海で出逢った、いるかとくじらの物語。 活発できりりとした口を持ついるかと穏やかでやさしい目をしたくじらが互いの違いを良さとして受け入れながら、友達となるのが慕わしい。 本の形式としても、ところどころで詩や手紙、メモなどが挟まり、読んでいて飽きが来ない。 恋をして、生涯の伴侶を見つけた上で、いるかにとっても、くじらにとっても、相手が心に棲まうほどに大切な存在であるということが、ただただ“友情”という枠へとくくるのにはもったいないほどの、大きくて深い愛の形を感じさせるものだった。
ともだちは海のにおい工藤直子,長新太Readsで出逢った本何度でも読みたいReadsで初めてこの本の存在を知り、絶対に購入したいと思った本。 静か過ぎて寂しい夜の海で出逢った、いるかとくじらの物語。 活発できりりとした口を持ついるかと穏やかでやさしい目をしたくじらが互いの違いを良さとして受け入れながら、友達となるのが慕わしい。 本の形式としても、ところどころで詩や手紙、メモなどが挟まり、読んでいて飽きが来ない。 恋をして、生涯の伴侶を見つけた上で、いるかにとっても、くじらにとっても、相手が心に棲まうほどに大切な存在であるということが、ただただ“友情”という枠へとくくるのにはもったいないほどの、大きくて深い愛の形を感じさせるものだった。 - 2025年3月9日
 何度でも読みたい古本屋で出逢った本実際に手元にあるのは、文庫版ではなく、単行本版の全八巻。 物語はプロローグやエピローグを含めて百篇の話から構成されており、これらは勿論、短編である以上、それぞれの話単体として楽しむこともできるが、実質的には連作短編にあたる。 物語は赤、橙、黄、緑、青、藍、菫という七つの色に分けられており、それぞれの場所にⅠからⅩⅣまでの数字が振られている。これは、色を数字通りに追いかけていけば、ある年代、及び、ある世代の「私」の物語として成立し、同じ数字の物語を色ごとに追いかけていけば、ある登場人物や事物を関連づけて読み解くことができる仕組みとなっている。 個人としては、赤と橙の主人公である「私」の物語が好きであり、特に橙色の物語は青春ならではの色鮮やかさ、交流、苦しみなどが丁寧に描かれ、その世界へとのめり込む形で浸ってしまう。橙色の物語に登場する秋山という登場人物が、これまた憎めない先輩であり、慕わしい。 是非とも、これからも大切に読み続けていきたい物語。
何度でも読みたい古本屋で出逢った本実際に手元にあるのは、文庫版ではなく、単行本版の全八巻。 物語はプロローグやエピローグを含めて百篇の話から構成されており、これらは勿論、短編である以上、それぞれの話単体として楽しむこともできるが、実質的には連作短編にあたる。 物語は赤、橙、黄、緑、青、藍、菫という七つの色に分けられており、それぞれの場所にⅠからⅩⅣまでの数字が振られている。これは、色を数字通りに追いかけていけば、ある年代、及び、ある世代の「私」の物語として成立し、同じ数字の物語を色ごとに追いかけていけば、ある登場人物や事物を関連づけて読み解くことができる仕組みとなっている。 個人としては、赤と橙の主人公である「私」の物語が好きであり、特に橙色の物語は青春ならではの色鮮やかさ、交流、苦しみなどが丁寧に描かれ、その世界へとのめり込む形で浸ってしまう。橙色の物語に登場する秋山という登場人物が、これまた憎めない先輩であり、慕わしい。 是非とも、これからも大切に読み続けていきたい物語。 - 2025年3月9日
 ここにないもの植田真,野矢茂樹古本屋で出逢った本ほとんど読んだ初めて哲学へと触れる人にお勧めしたい一冊。 本書は、永井均さんの『翔太と猫のインサイトの夏休み』と同様に、対話篇と呼ばれる物語に近い形式で綴られていく。 主だった登場人物は、人ではなく、不思議な存在であるエプシロンとミューであり、彼らの日常は、和やかでいつでもほのぼのとしている。 しっかり者のエプシロンは、ぽやぽやとしたミューからの疑問に“常識”を以て答えていくが、あらゆるものを不思議に思うミューは、人々の考える“普通の答え”には、なかなか満足をしない——そうしたミューの考えに、エプシロンもまた考えを深化させ、新たな答えを導き出していく。 本書は、あくまでも野矢茂樹さんの考えが示された本であるため、読者の中にはその結論に納得のいかないものもいるかもしれない。しかし、哲学とは、考えることであり、その方法はまさに、本書が示す通り、対話することの中にある。 ミューの出す疑問を前に、読者自身がその答えを考え、自分なりの回答を導き出すこと——それもまた、一つの読み方となるのではないだろうか。
ここにないもの植田真,野矢茂樹古本屋で出逢った本ほとんど読んだ初めて哲学へと触れる人にお勧めしたい一冊。 本書は、永井均さんの『翔太と猫のインサイトの夏休み』と同様に、対話篇と呼ばれる物語に近い形式で綴られていく。 主だった登場人物は、人ではなく、不思議な存在であるエプシロンとミューであり、彼らの日常は、和やかでいつでもほのぼのとしている。 しっかり者のエプシロンは、ぽやぽやとしたミューからの疑問に“常識”を以て答えていくが、あらゆるものを不思議に思うミューは、人々の考える“普通の答え”には、なかなか満足をしない——そうしたミューの考えに、エプシロンもまた考えを深化させ、新たな答えを導き出していく。 本書は、あくまでも野矢茂樹さんの考えが示された本であるため、読者の中にはその結論に納得のいかないものもいるかもしれない。しかし、哲学とは、考えることであり、その方法はまさに、本書が示す通り、対話することの中にある。 ミューの出す疑問を前に、読者自身がその答えを考え、自分なりの回答を導き出すこと——それもまた、一つの読み方となるのではないだろうか。 - 2025年3月8日
 美しい街尾形亀之助,松本竣介何度でも読みたい図書館で出逢った本尾形亀之助の詩が纏められた本。 纏められた詩を読んでみると、「明るい夜」のように温もりを伴った柔らかな夜を描く詩というのは意外に少なく、引き延ばされる夜の時間に耐えながら、朝を待ち望む詩というものが多いように思われる。 日常を愛でる詩も多く、時としては間の抜けた表現に笑みの溢れてしまうものもあるが、その作風の根底には——勿論、亀之助の生きた時代を思えば、戦時との関わりもあるのかもしれないが——なにか言いしれぬ無常感のようなものが漂っているようにも感じる。
美しい街尾形亀之助,松本竣介何度でも読みたい図書館で出逢った本尾形亀之助の詩が纏められた本。 纏められた詩を読んでみると、「明るい夜」のように温もりを伴った柔らかな夜を描く詩というのは意外に少なく、引き延ばされる夜の時間に耐えながら、朝を待ち望む詩というものが多いように思われる。 日常を愛でる詩も多く、時としては間の抜けた表現に笑みの溢れてしまうものもあるが、その作風の根底には——勿論、亀之助の生きた時代を思えば、戦時との関わりもあるのかもしれないが——なにか言いしれぬ無常感のようなものが漂っているようにも感じる。 - 2025年3月8日
 なんだか眠いのです西尾勝彦何度でも読みたい本屋で出逢った本詩文集というものに憧れを抱くに至ったきっかけの本。 最近も詩集が刊行されたばかりである西尾勝彦さんの詩だけではない文章までもが詰め込まれた作品集であり、その眼差しは、のんびりとした朗らかな優しさと見つめるものへの愛に満ち満ちている。 慕わしい作品に出逢う時、その人の思考を覗きたくなる人間としては、あまりにも有難い一冊。 尾形亀之助についての論考も収録されているため、尾形亀之助に関心がある方にも、是非ご一読いただきたい。
なんだか眠いのです西尾勝彦何度でも読みたい本屋で出逢った本詩文集というものに憧れを抱くに至ったきっかけの本。 最近も詩集が刊行されたばかりである西尾勝彦さんの詩だけではない文章までもが詰め込まれた作品集であり、その眼差しは、のんびりとした朗らかな優しさと見つめるものへの愛に満ち満ちている。 慕わしい作品に出逢う時、その人の思考を覗きたくなる人間としては、あまりにも有難い一冊。 尾形亀之助についての論考も収録されているため、尾形亀之助に関心がある方にも、是非ご一読いただきたい。 - 2025年3月8日
 わたしを空腹にしないほうがいい 改訂版くどうれいん何度でも読みたい古本屋で出逢った本大学生時代のくどうれいんさんが垣間見えるエッセイ集。 日付の記載がある通り、これはほぼ日記であり、それぞれのエッセイにはタイトルとして俳句が詠まれている。 美味しいもの、綴られる感情、人々との交流や懐かしさ——その全てが青い瑞々しさに満ち溢れ、彼女の出会ってきた一つ一つのものを、こちらも愛おしい気持ちで追い掛けたくなる。 普段、俳句にはあまり触れないが、タイトルの俳句もまた、個人としては美しく感じる
わたしを空腹にしないほうがいい 改訂版くどうれいん何度でも読みたい古本屋で出逢った本大学生時代のくどうれいんさんが垣間見えるエッセイ集。 日付の記載がある通り、これはほぼ日記であり、それぞれのエッセイにはタイトルとして俳句が詠まれている。 美味しいもの、綴られる感情、人々との交流や懐かしさ——その全てが青い瑞々しさに満ち溢れ、彼女の出会ってきた一つ一つのものを、こちらも愛おしい気持ちで追い掛けたくなる。 普段、俳句にはあまり触れないが、タイトルの俳句もまた、個人としては美しく感じる - 2025年3月8日
 詩と散策ハン・ジョンウォン,橋本智保何度でも読みたい本屋で出逢った本去年から読み始め、大事に読み進めている本。 詩を愛し、詩人になりたいと願い、過去の出来事から失語症にもなったハン・ジョンウォンさんが綴る、まさに“詩と散策”のエッセイ。 一編一編が、まるで暖炉の前にそっと腰掛け、ココアを飲みながら、彼女の話へと耳を澄ませているような気さえする文章となっており、その言葉を、一つ一つじっくりと噛み締めて読みたくなる。 ハン・ジョンウォンさんの詩は現状、日本語には訳されていないとのことだが、その表現は実に繊細で心奥に広がるような含蓄を持つ。是非とも、詩集も拝読したいところ
詩と散策ハン・ジョンウォン,橋本智保何度でも読みたい本屋で出逢った本去年から読み始め、大事に読み進めている本。 詩を愛し、詩人になりたいと願い、過去の出来事から失語症にもなったハン・ジョンウォンさんが綴る、まさに“詩と散策”のエッセイ。 一編一編が、まるで暖炉の前にそっと腰掛け、ココアを飲みながら、彼女の話へと耳を澄ませているような気さえする文章となっており、その言葉を、一つ一つじっくりと噛み締めて読みたくなる。 ハン・ジョンウォンさんの詩は現状、日本語には訳されていないとのことだが、その表現は実に繊細で心奥に広がるような含蓄を持つ。是非とも、詩集も拝読したいところ - 2025年3月8日
 編棒を火の色に替えてから冬野虹,四ッ谷龍本屋で出逢った本ほとんど読んだ五十九歳の若さでこの世を去ってしまった冬野虹の詩文集。 集成・文芸誌からの抜粋と未収録の作品から構成された本書は、自由自在かつ繊細なポエジーで見るものを空想の世界へと誘い、その心を浮かび上がらせる。 冬野虹の集成は全三巻——素晴らしい文章作品であるだけに、そちらもまた、気になるところ。
編棒を火の色に替えてから冬野虹,四ッ谷龍本屋で出逢った本ほとんど読んだ五十九歳の若さでこの世を去ってしまった冬野虹の詩文集。 集成・文芸誌からの抜粋と未収録の作品から構成された本書は、自由自在かつ繊細なポエジーで見るものを空想の世界へと誘い、その心を浮かび上がらせる。 冬野虹の集成は全三巻——素晴らしい文章作品であるだけに、そちらもまた、気になるところ。 - 2025年3月8日
- 2025年3月8日
 京都で考えた吉田篤弘かつて読んだ古本屋で出逢った本クラフト・エヴィング商會でも有名な吉田篤弘さんのエッセイ。 京都を散策する中で考えたことやそこでの思い出などが綴られており、吉田さんの表現により、読者はそこに描かれた思考や情景の世界へと引き込まれる。 神戸のことを書いた『神様のいる街』も大変良く、こちらもおすすめ。
京都で考えた吉田篤弘かつて読んだ古本屋で出逢った本クラフト・エヴィング商會でも有名な吉田篤弘さんのエッセイ。 京都を散策する中で考えたことやそこでの思い出などが綴られており、吉田さんの表現により、読者はそこに描かれた思考や情景の世界へと引き込まれる。 神戸のことを書いた『神様のいる街』も大変良く、こちらもおすすめ。
読み込み中...

