
07
@cocoa007
朝活で読書したい
どこかに報告したら続くんじゃないかという実験
- 2026年2月21日
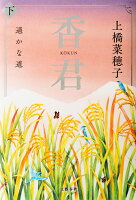 香君 下 遥かな道上橋菜穂子読み終わった植物がある種の化学物質を出して他の植物や虫とコミニュケーションをとっているという話は、なにかの本で読んで知っていたが、上橋さんが仕立てるとこんな物語になるのか。綿密かつ壮大な大型ファンタジーだった。 アイシャは戦わないナウシカ、といった風情だ。人間以外の生物の声が聞こえるところとか、その聖性、カリスマ性とか。でもナウシカは王蟲と心を通わせられるけど、アイシャは一方的に植物の香りを聞くだけだから、より孤独である。 アイシャは自分を神格化したくないと思っているけど、それはやっぱり難しいんじゃないかなあ。生い立ちすべてが神話的過ぎる。あまりにも博愛精神に満ちていて、一切個人の幸せを追求しないし。主人公でありながら、ここまで周囲の人物と親密にならないキャラって珍しいんじゃないだろうか? 唯一、オリエとはシスターフッド的な絆で結ばれるが、彼女にはちゃんと別に心を預ける人がいる。最後のシーンは、なんとも言えない切なさがあった。 それしても、オアレ稲の恐ろしさよ。あれは自然の循環の中に入れてはいけないんじゃないか?あんな物が本当に自然に出現するものなのか? 神郷の謎はほとんど解明されていない。オアレ稲は人工的に生み出された植物なんじゃないか?神郷ってオーバーテクノロジーな世界なのでは?とか、色々妄想が捗ってしまう。
香君 下 遥かな道上橋菜穂子読み終わった植物がある種の化学物質を出して他の植物や虫とコミニュケーションをとっているという話は、なにかの本で読んで知っていたが、上橋さんが仕立てるとこんな物語になるのか。綿密かつ壮大な大型ファンタジーだった。 アイシャは戦わないナウシカ、といった風情だ。人間以外の生物の声が聞こえるところとか、その聖性、カリスマ性とか。でもナウシカは王蟲と心を通わせられるけど、アイシャは一方的に植物の香りを聞くだけだから、より孤独である。 アイシャは自分を神格化したくないと思っているけど、それはやっぱり難しいんじゃないかなあ。生い立ちすべてが神話的過ぎる。あまりにも博愛精神に満ちていて、一切個人の幸せを追求しないし。主人公でありながら、ここまで周囲の人物と親密にならないキャラって珍しいんじゃないだろうか? 唯一、オリエとはシスターフッド的な絆で結ばれるが、彼女にはちゃんと別に心を預ける人がいる。最後のシーンは、なんとも言えない切なさがあった。 それしても、オアレ稲の恐ろしさよ。あれは自然の循環の中に入れてはいけないんじゃないか?あんな物が本当に自然に出現するものなのか? 神郷の謎はほとんど解明されていない。オアレ稲は人工的に生み出された植物なんじゃないか?神郷ってオーバーテクノロジーな世界なのでは?とか、色々妄想が捗ってしまう。 - 2026年2月18日
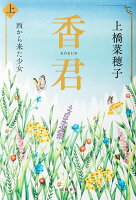 香君 上 西から来た少女上橋菜穂子読み終わった
香君 上 西から来た少女上橋菜穂子読み終わった - 2026年2月16日
- 2026年2月14日
 小説野崎まど読み終わったあらすじをまったく知らずに読み始めたので、途中どこに連れて行かれるのか見当もつかず、最終的にファンタジーとSFの世界になってひっくり返った。 でも、素晴らしい小説というのは、どこか美しい別の世界からなにかすごい真理を運んできた…という感触はある、確かに。
小説野崎まど読み終わったあらすじをまったく知らずに読み始めたので、途中どこに連れて行かれるのか見当もつかず、最終的にファンタジーとSFの世界になってひっくり返った。 でも、素晴らしい小説というのは、どこか美しい別の世界からなにかすごい真理を運んできた…という感触はある、確かに。 - 2026年2月10日
 君のクイズ小川哲読み終わった今一番勢いのある作家の一人だと思う。でも、ちょっと自分には合わなかった。冒頭が秀逸で「ゼロ文字解答なんて本当にできるのか?」という好奇心でグイグイ読み進めたが、そこが興奮の頂点だったというか…。謎解きが陳腐だったとか、そういうことでもないんだけど。 最後にもっと驚かせてくれるんじゃないか?と思っちゃったのかな。
君のクイズ小川哲読み終わった今一番勢いのある作家の一人だと思う。でも、ちょっと自分には合わなかった。冒頭が秀逸で「ゼロ文字解答なんて本当にできるのか?」という好奇心でグイグイ読み進めたが、そこが興奮の頂点だったというか…。謎解きが陳腐だったとか、そういうことでもないんだけど。 最後にもっと驚かせてくれるんじゃないか?と思っちゃったのかな。 - 2026年2月9日
 コンビニ人間村田沙耶香「普通」の集団に馴染めない、自分のことを「人間」とすら思えない主人公でも、こんなにも所属への渇望は凄まじい。彼女は、コンビニの部品になっているときだけは安心して生きていられる。 「普通」の人々の、繁殖の話題になったときの熱狂や、逆に主人公からさーっと引いていく感じ、その瞬間に「人間」という仮面がズレ落ちて剥き出しの本能が晒される感じが、すごく不気味だった。 軽快にどんどん読めてしまったのだが、とにかく不気味な後味だけが残るという、なかなか他にない面白い読書体験だった。
コンビニ人間村田沙耶香「普通」の集団に馴染めない、自分のことを「人間」とすら思えない主人公でも、こんなにも所属への渇望は凄まじい。彼女は、コンビニの部品になっているときだけは安心して生きていられる。 「普通」の人々の、繁殖の話題になったときの熱狂や、逆に主人公からさーっと引いていく感じ、その瞬間に「人間」という仮面がズレ落ちて剥き出しの本能が晒される感じが、すごく不気味だった。 軽快にどんどん読めてしまったのだが、とにかく不気味な後味だけが残るという、なかなか他にない面白い読書体験だった。 - 2026年2月5日
 神の蝶、舞う果て上橋菜穂子,白浜鴎読み終わった素晴らしかった。上橋奈緒子さんらしい目に浮かぶような情景描写のおかげで、読んでいる間この世界に住むことができた。 クライマックスのシーンは、曼荼羅図が思い浮かんだ。俯瞰しなければ捉えることができない全体像、それが世界の真理であり設計図なのだ…という作者のメッセージを強く感じた。人間が自分だけの視点で眺めていては、決して知ることができないものがあるのだ。 葦の舟云々のところは、そのままヒルコだろう。生まれた途端に無用とされた悲しい存在への愛情も強く感じた。 守り人シリーズを読み返したくなっちゃったな。ファンタジー小説の達人である。
神の蝶、舞う果て上橋菜穂子,白浜鴎読み終わった素晴らしかった。上橋奈緒子さんらしい目に浮かぶような情景描写のおかげで、読んでいる間この世界に住むことができた。 クライマックスのシーンは、曼荼羅図が思い浮かんだ。俯瞰しなければ捉えることができない全体像、それが世界の真理であり設計図なのだ…という作者のメッセージを強く感じた。人間が自分だけの視点で眺めていては、決して知ることができないものがあるのだ。 葦の舟云々のところは、そのままヒルコだろう。生まれた途端に無用とされた悲しい存在への愛情も強く感じた。 守り人シリーズを読み返したくなっちゃったな。ファンタジー小説の達人である。 - 2026年1月28日
 魚が存在しない理由 世界一空恐ろしい生物分類の話ルル・ミラー読み終わった一人の分類学者の生涯を追う話かと思いきや、中盤から予想だにしない方向へ進んでびっくり。一体どこに着地するのか、はらはらしながら読んだ。 軽い読み口だが、人間の本質のかなり深い部分を抉ってるなあと思った。 なんでも分類して名前を付けたがるのは、どうしようもない脳の性質な気がする。けれどそれが、区別から差別へシームレスに繋がっている感じがして怖い。
魚が存在しない理由 世界一空恐ろしい生物分類の話ルル・ミラー読み終わった一人の分類学者の生涯を追う話かと思いきや、中盤から予想だにしない方向へ進んでびっくり。一体どこに着地するのか、はらはらしながら読んだ。 軽い読み口だが、人間の本質のかなり深い部分を抉ってるなあと思った。 なんでも分類して名前を付けたがるのは、どうしようもない脳の性質な気がする。けれどそれが、区別から差別へシームレスに繋がっている感じがして怖い。 - 2026年1月19日
- 2026年1月13日
 熊になったわたし 人類学者、シベリアで世界の狭間に生きるナスターシャ・マルタン,大石侑香,高野優熊に襲われて生き残った人間は半分人間、半分熊になる…エヴェン族の言い伝えを図らずも身をもって体験した人類学者の話。 この作者は、熊に襲われる以前から現代の西洋文明に違和感を感じていた節がある。そこに現代西洋文明とは真逆のシベリアの少数民族の思想が流れこんでくる。 熊に襲われる前に作者は繰り返し熊の夢を見ている。また、エヴェン人から「あなたは熊と引き寄せあっている」というようなことを言われる。 事前にこの予言めいた出来事がなければ、熊に襲われる体験は恐怖だけで塗り潰されていただろう。作者はエヴェン族の思想のおかげで、この恐ろしい体験を別の意味付けで捉え直すことができた。 しかしそれは同時に、現代文明からの逸脱を意味する。今の社会では、人間と自然、自己と他者に明確な線引きをすることが正気の証明で、熊と一体化してしまった作者は狂人のカテゴリになってしまうのだ。 彼女の居場所は現代社会にはなく、かと言って熊の住む自然の森に同化することもできない。 彼女は二つの世界の中間に立ち、別世界の存在を我々に教えることを仕事とする決意をした。 そうしてできたのが、この本だ。 狩猟民族の狩人は、獲物を捕らえる前夜に自分が獲物になる夢を見るという。また、矢を放つ瞬間に獲物の目から自分を見る狩人もいるという。殺す者、殺される者の同化が、そこにはある。 現代でこの狩人と類似した心理状態を、理屈による理解ではなく、体感的に再現した人間いたことに驚いた。 現代ではともすれば狂気とされてしまうこの感覚は、人間の中にまだある。科学文明に押しやられて、奥深くで眠っているだけなのだ。そう思わずにいられない内容だった。
熊になったわたし 人類学者、シベリアで世界の狭間に生きるナスターシャ・マルタン,大石侑香,高野優熊に襲われて生き残った人間は半分人間、半分熊になる…エヴェン族の言い伝えを図らずも身をもって体験した人類学者の話。 この作者は、熊に襲われる以前から現代の西洋文明に違和感を感じていた節がある。そこに現代西洋文明とは真逆のシベリアの少数民族の思想が流れこんでくる。 熊に襲われる前に作者は繰り返し熊の夢を見ている。また、エヴェン人から「あなたは熊と引き寄せあっている」というようなことを言われる。 事前にこの予言めいた出来事がなければ、熊に襲われる体験は恐怖だけで塗り潰されていただろう。作者はエヴェン族の思想のおかげで、この恐ろしい体験を別の意味付けで捉え直すことができた。 しかしそれは同時に、現代文明からの逸脱を意味する。今の社会では、人間と自然、自己と他者に明確な線引きをすることが正気の証明で、熊と一体化してしまった作者は狂人のカテゴリになってしまうのだ。 彼女の居場所は現代社会にはなく、かと言って熊の住む自然の森に同化することもできない。 彼女は二つの世界の中間に立ち、別世界の存在を我々に教えることを仕事とする決意をした。 そうしてできたのが、この本だ。 狩猟民族の狩人は、獲物を捕らえる前夜に自分が獲物になる夢を見るという。また、矢を放つ瞬間に獲物の目から自分を見る狩人もいるという。殺す者、殺される者の同化が、そこにはある。 現代でこの狩人と類似した心理状態を、理屈による理解ではなく、体感的に再現した人間いたことに驚いた。 現代ではともすれば狂気とされてしまうこの感覚は、人間の中にまだある。科学文明に押しやられて、奥深くで眠っているだけなのだ。そう思わずにいられない内容だった。 - 2026年1月6日
 言語化するための小説思考小川哲読み終わった
言語化するための小説思考小川哲読み終わった - 2025年12月15日
 アーサー王伝説の起源 新装版リンダ・A・マルカー,C・スコット・リトルトン,吉田瑞穂,辺見葉子読み終わったアーサー王伝説の起源は、スキタイの遊牧民族の神話だった説。 興味深い切り口だった。アーサー王とランスロットは同一人物説はかなりの説得力を感じた。
アーサー王伝説の起源 新装版リンダ・A・マルカー,C・スコット・リトルトン,吉田瑞穂,辺見葉子読み終わったアーサー王伝説の起源は、スキタイの遊牧民族の神話だった説。 興味深い切り口だった。アーサー王とランスロットは同一人物説はかなりの説得力を感じた。 - 2025年12月15日
 ゲーテはすべてを言った鈴木結生読み終わったこの小説全体に流れる雰囲気が、郷愁を駆り立ててやまない。大学のゼミの先生の話って全般こんな感じだった。私は引用される言葉のほとんどがわからず、なんとなく頷いているだけの生徒でした。 あのころからもっとちゃんと本を読み続けていれば、ゲーテの知識もついていたかもしれない…。 アカデミックで友愛に満ちた安心できる家庭。ここがもはや理想郷。 終盤からのミステリーの回収も見事で、なんか難しいテーマってだけじゃなく、何重にも読者を惹きつける魅力のある本だと思った。
ゲーテはすべてを言った鈴木結生読み終わったこの小説全体に流れる雰囲気が、郷愁を駆り立ててやまない。大学のゼミの先生の話って全般こんな感じだった。私は引用される言葉のほとんどがわからず、なんとなく頷いているだけの生徒でした。 あのころからもっとちゃんと本を読み続けていれば、ゲーテの知識もついていたかもしれない…。 アカデミックで友愛に満ちた安心できる家庭。ここがもはや理想郷。 終盤からのミステリーの回収も見事で、なんか難しいテーマってだけじゃなく、何重にも読者を惹きつける魅力のある本だと思った。 - 2025年12月9日
 虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わったずっと読みたいと思っていた本が今日やっと届いた。一気読みした。 まず冒頭で「私も虚弱気味だから同じだね」などと思っていたことを謝りたくなった。人生が壮絶過ぎる。 ここまで色々な不調があるのに、病名がつかない。病名がないから専門的な対策もわからず、ひたすら健康に良いと言われる習慣を積み重ねていくしかできない。しかも、そんな血の滲むような努力をしていても、それでも虚弱なのだ。 わかる、と言っては烏滸がましいのかもしれないけど、わかる部分が多々あった。健康法のおかげで少し体調が良くなり、自分で自分の体をコントロールできたと実感できたシーンは泣きそうになった。 この方は自己の客観視の達人で、もはや普通に生きている人たちへの羨望がない。今より健康になることが、自分の一番の幸せなのだと知っている。 ある意味、悟りの境地である。
虚弱に生きる絶対に終電を逃さない女読み終わったずっと読みたいと思っていた本が今日やっと届いた。一気読みした。 まず冒頭で「私も虚弱気味だから同じだね」などと思っていたことを謝りたくなった。人生が壮絶過ぎる。 ここまで色々な不調があるのに、病名がつかない。病名がないから専門的な対策もわからず、ひたすら健康に良いと言われる習慣を積み重ねていくしかできない。しかも、そんな血の滲むような努力をしていても、それでも虚弱なのだ。 わかる、と言っては烏滸がましいのかもしれないけど、わかる部分が多々あった。健康法のおかげで少し体調が良くなり、自分で自分の体をコントロールできたと実感できたシーンは泣きそうになった。 この方は自己の客観視の達人で、もはや普通に生きている人たちへの羨望がない。今より健康になることが、自分の一番の幸せなのだと知っている。 ある意味、悟りの境地である。 - 2025年12月7日
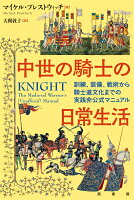 中世の騎士の日常生活マイケル・プレストウィッチ,大槻敦子読み終わった十五世紀に執筆されたことを装った騎士になりたい若者向けの非公式マニュアル。非公式マニュアルだけあって、かなり赤裸々に騎士の実情を描いている。 騎士道精神は…ほとんど、ない。 農民に対して悪逆非道過ぎ。貴族の女性にメロメロになって、片目で戦争に行って勝ってくるとかいうバカな誓いを立てる。 なかなか人間味のある騎士の生活を垣間見ることができた。
中世の騎士の日常生活マイケル・プレストウィッチ,大槻敦子読み終わった十五世紀に執筆されたことを装った騎士になりたい若者向けの非公式マニュアル。非公式マニュアルだけあって、かなり赤裸々に騎士の実情を描いている。 騎士道精神は…ほとんど、ない。 農民に対して悪逆非道過ぎ。貴族の女性にメロメロになって、片目で戦争に行って勝ってくるとかいうバカな誓いを立てる。 なかなか人間味のある騎士の生活を垣間見ることができた。 - 2025年12月6日
 増補改訂 アースダイバー中沢新一,大森克己読み終わった本当は増補版じゃなくて最初に出た版を借りたのだが、検索に上がってこなかった。 中沢新一、いつかは読まなくてはと思っていた。幻想的でわくわくするような都市論。なんとなく梅原猛氏のことを思い出した。過去を幻視しているようなシャーマン的な雰囲気を感じる。 他の本もこんな感じなのか、この本だけなのか。何冊か中沢さんの本を追っていきたい。
増補改訂 アースダイバー中沢新一,大森克己読み終わった本当は増補版じゃなくて最初に出た版を借りたのだが、検索に上がってこなかった。 中沢新一、いつかは読まなくてはと思っていた。幻想的でわくわくするような都市論。なんとなく梅原猛氏のことを思い出した。過去を幻視しているようなシャーマン的な雰囲気を感じる。 他の本もこんな感じなのか、この本だけなのか。何冊か中沢さんの本を追っていきたい。 - 2025年11月30日
 金をつなぐ 北鎌倉七福堂ゆいあい,山本瑤読み終わった
金をつなぐ 北鎌倉七福堂ゆいあい,山本瑤読み終わった - 2025年11月30日
 白い盾の少年騎士 下トンケ・ドラフト,西村由美読み終わった読了! めちゃくちゃ面白かったー!誤解を恐れずに言うなら、これは王道の児童文学でありながらキャラ小説でもある。出てくる人物が全員魅力的で、それが一番の駆動力になっていると思う。 今回は主人公ティウリと同じくらい盾持ちのピアックが目立っていた。ティウリは使命を果たす過程で精神的に大人になり、読者である子どもたちと同じ目線に立つ者はピアックだけになったからだろう。 ずっとこの世界にいたいけど、このあたりで幕引きがちょうどいい。次の話があったとしても、きっと、ピアックも大人になってしまっている。
白い盾の少年騎士 下トンケ・ドラフト,西村由美読み終わった読了! めちゃくちゃ面白かったー!誤解を恐れずに言うなら、これは王道の児童文学でありながらキャラ小説でもある。出てくる人物が全員魅力的で、それが一番の駆動力になっていると思う。 今回は主人公ティウリと同じくらい盾持ちのピアックが目立っていた。ティウリは使命を果たす過程で精神的に大人になり、読者である子どもたちと同じ目線に立つ者はピアックだけになったからだろう。 ずっとこの世界にいたいけど、このあたりで幕引きがちょうどいい。次の話があったとしても、きっと、ピアックも大人になってしまっている。 - 2025年11月29日
- 2025年11月27日
 わたしたちが光の速さで進めないならユン・ジヨン,カン・バンファ,キム・チョヨプ読み終わった
わたしたちが光の速さで進めないならユン・ジヨン,カン・バンファ,キム・チョヨプ読み終わった
読み込み中...


