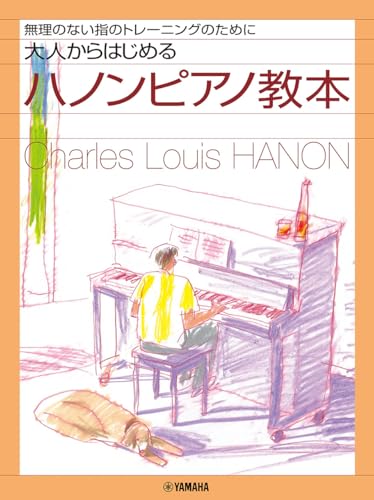石坂わたる
@ishizakawataru
- 2026年2月24日
 若きウェルテルの悩みゲーテ,酒寄進一「ぼくらが平等ではなく、そもそも平等になることなど不可能なのはわかっている。 それでも、威厳を保つために庶民から距離を置くことが必要だと考える奴はろくでなしだ。負けるのが怖くて敵から逃げる臆病者と同じじゃないか。」 「それなりの身分の者は庶民に冷たい態度をとって距離を置く。近しくなるのは身のためにならないとでも言うように。その一方で、へりくだってみせることで、かえって貧しい人たちに尊大な奴だと思われてしまうこともある。」 「喜んで白状するけど、だれよりも幸せなのは、子どものようにその日その日を生きていける連中だ。人形を連れ歩いて着せ替えをしたり、母親がいつも菓子パンをしまっておく引出しのあたりを虎視眈々と歩きまわって、望みのものを手に入れたらすかさず頬張り、「もっとちょうだい」と声を上げたりする。こういうのが幸せな人種さ!くだらないことや夢中になっていることに、たいそうなタイトルをつけて、これぞ人類安寧のための大事業なりと嘘く連中もおめでたい奴らだ。そんなことが言える御仁は幸いなり!だけど、謙虚になって、こんなことがいったいなんになるんだと考えてしまう人もいるだろう。そういう人なら、自分のささやかな庭を夢の楽園にしようと勤しみ、運に見放されても不平を言わずに重荷を担いで自分の道を歩く幸いなる市民がいて、一様に少しでも長くお天道様を拝もうと汲々としていることに気づくはずだ。そうだろう!そういう人は黙って自分だけの世界を作りあげる。これまた幸せなことだ。それこそ人間なのだから。」 「ほかの人から見て、ぼくにどういう魅力があるのかわからないけど、たくさんの人が気に入ってくれて、親しくしてくれる。だけど道を同じくできるのはごく短いあいだだけだ。じつに残念でならないよ。そう言うと、そこに暮らすのはどんな人たちなんだい、ときみは気にするかもしれないね。どこも同じと言うほかないさ!人間なんて所詮同じ。 たいていの人は生きるために汲々としている。残された自由時間なんてほとんどない。 それでも時間を持て余して、あらゆる手を使って浪費しようとする。これは人間の性 だな!」 「この世でぼくの心に最も近しい存在は子どもだ。子どもを見ていると、小さな存在に美徳の芽や、いずれ必要になるさまざまな能力の芽があり、それが開花するのがわかる。わがままな性格には、将来身につけるだろう不屈の精神が見てとれるし、奔放さには、この世のあらゆる危険をかいくぐるユーモア感覚と身軽さの片鱗がある。なににも毒されていない、ありのままの姿じゃないか! 毎度、人類の師が宣った金言が脳裏を過ぎる。 『子どものようにならなければ』 ところで、ぼくらと同等であり、むしろぼくらが模範とすべき子どもたちを、大人は下に見る傾向がある。子どもに意志などあるはずがないだって?一大人にだってないじゃないか。大人が特権を得られるいわれはどこにあるんだ?一大人の方が歳をとっていて、賢いからかい?一 『天にまします主よ、この世にいるのは歳をとった子どもと年若い子どもだけ。それ以外はいません。どちらがあなたにとって喜ばしいか、あなたの子イエスが答えをだしています』 ところが、みんな、イエスの存在は倍じても、その言葉には耳を貸そうとしない。 昔からそうと相場が決まっている。そして子どもたちを自分と同じように育てる一」 「『自分を律することなんてできるものでしょうかね。自分の感情を意のままにするな んてむりでしょう』……牧師も話に加わろうとして熱心に聞き耳を立てていることに気づいた。 ぼくは彼にもわかるように声を張りあげた。 『人間のさまざまな悪癖をいましめるお説教はありますが、不機嫌を礼す説教はいまだかつて聞いたことがありませんね』」 「『人はよく、よい日はすくなく、いやな日が多すぎると嘆きますね』ぼくはそう言って、口火を切った。『しかし、たいていは正しくないと思うんです。神が毎日授けてくれるよいことを素直に享受するなら、災いが起きても、充分に耐えられるはずです』 『けれども、気持ちというのは思うようにならないものですよ』牧師夫人が応じた。 『体調にも左右されますしね!具合がよくないと、なにをやっても満足できないものです』 ぼくはその意見にうなずいて言った。 『それなら病気と見たらどうでしょう。そして治す薬はないかと考えてみるんです!』 『一理ありますね』ロッテが言った。『気の持ちようってあると思うんです。』」 「すごいことやありえないことをする非凡な人間は、えてして自分に酔っているとか、正気をなくしていると昔から言われているからね。 だけど、自由で気高く、予想を覆す行動に出た者を自分に酔っている愚か者だと陰口を叩くのは、普段の生活でも聞くに耐えないことだ。きみたち理性のある者は恥を知るべきだ。きみたち賢者は恥を知るべきなんだよ」 「しかしい。美しどんな事情があるか、どのくらい調べてみたんだい?それがなぜ起 ったか、その原因をきちんと説明できるのかい? そうするなら、そんな性急に判断を下したりしないはずだ」「きみも認めることだろうが、ある種の行為は、動機の如何にかかわらず、罪悪たり うるものだよ」 ぼくは肩をすくめて、同意しつつこうつづけた。 「けれども、そこにも例外はある。たしかに盗みは罪悪だ。しかし自分と家族を餓死から救うために盗みをはたらいた人間には同情すべきだと思うが、やはり罰するのかい?不実な妻と不届きな間男に当然の怒りをぶつけて死に追いやった夫に、だれ が石を投げるかな?歓喜に満ちたひと時に、愛の喜びを抑えきれずに我を忘れた娘がいるとして、それを責められるだろうか?法律という冷酷な代物だって、心を動かされて、罰することを控えるだろう』 『それは別の話だ。激情に駆ら』れた人間は自制心を失ってしまう。自分に酔っていたり、正気をなくしたりした者と同じだ」 『分別のある人間はこれだからな!』ぼくは微笑みながら叫んだ。」 「作家が自分の物語を改訂すると、文学としての出来映えはよくなるかもしれないが、どうしても作品を損ねてしまうってことをね。 第一印象は好意的に受けとめられるものだ。」 「『ネーデルラント連邦共和国がちゃんとおれに報酬を払ってくれりゃあ、こんなに落ちぶれちゃいない!すごい時代だったよ。俺は羽振りがよかった。だけど、いまはこの体たらくだ。俺はもう』 涙をこえて天を仰ぐまなざしがすべてを物語っていた。」 「見ろよ、おまえはこの家にとってどういう存在か。ここに住む友人たちに敬愛される存在だ!ふたりの喜びの源であり、おまえ自身もふたりなしにはいられない。だけどーもしおまえがいなくなったら、どうだ?この友だちの輪から出ていったら、どうなるだろう?おまえを失うことで、自分たちの運命にぽっかり開いたうつろな気分を、ふたりはいつまで感じるだろう?いったいいつまで?1ああ、人間は儚い存在だ。この世に存在したという生きた証を、愛する者たちの思い出や魂にはっきり刻みつけたとしても、消えてなくなるほかない。しかも時間をかけずに!」
若きウェルテルの悩みゲーテ,酒寄進一「ぼくらが平等ではなく、そもそも平等になることなど不可能なのはわかっている。 それでも、威厳を保つために庶民から距離を置くことが必要だと考える奴はろくでなしだ。負けるのが怖くて敵から逃げる臆病者と同じじゃないか。」 「それなりの身分の者は庶民に冷たい態度をとって距離を置く。近しくなるのは身のためにならないとでも言うように。その一方で、へりくだってみせることで、かえって貧しい人たちに尊大な奴だと思われてしまうこともある。」 「喜んで白状するけど、だれよりも幸せなのは、子どものようにその日その日を生きていける連中だ。人形を連れ歩いて着せ替えをしたり、母親がいつも菓子パンをしまっておく引出しのあたりを虎視眈々と歩きまわって、望みのものを手に入れたらすかさず頬張り、「もっとちょうだい」と声を上げたりする。こういうのが幸せな人種さ!くだらないことや夢中になっていることに、たいそうなタイトルをつけて、これぞ人類安寧のための大事業なりと嘘く連中もおめでたい奴らだ。そんなことが言える御仁は幸いなり!だけど、謙虚になって、こんなことがいったいなんになるんだと考えてしまう人もいるだろう。そういう人なら、自分のささやかな庭を夢の楽園にしようと勤しみ、運に見放されても不平を言わずに重荷を担いで自分の道を歩く幸いなる市民がいて、一様に少しでも長くお天道様を拝もうと汲々としていることに気づくはずだ。そうだろう!そういう人は黙って自分だけの世界を作りあげる。これまた幸せなことだ。それこそ人間なのだから。」 「ほかの人から見て、ぼくにどういう魅力があるのかわからないけど、たくさんの人が気に入ってくれて、親しくしてくれる。だけど道を同じくできるのはごく短いあいだだけだ。じつに残念でならないよ。そう言うと、そこに暮らすのはどんな人たちなんだい、ときみは気にするかもしれないね。どこも同じと言うほかないさ!人間なんて所詮同じ。 たいていの人は生きるために汲々としている。残された自由時間なんてほとんどない。 それでも時間を持て余して、あらゆる手を使って浪費しようとする。これは人間の性 だな!」 「この世でぼくの心に最も近しい存在は子どもだ。子どもを見ていると、小さな存在に美徳の芽や、いずれ必要になるさまざまな能力の芽があり、それが開花するのがわかる。わがままな性格には、将来身につけるだろう不屈の精神が見てとれるし、奔放さには、この世のあらゆる危険をかいくぐるユーモア感覚と身軽さの片鱗がある。なににも毒されていない、ありのままの姿じゃないか! 毎度、人類の師が宣った金言が脳裏を過ぎる。 『子どものようにならなければ』 ところで、ぼくらと同等であり、むしろぼくらが模範とすべき子どもたちを、大人は下に見る傾向がある。子どもに意志などあるはずがないだって?一大人にだってないじゃないか。大人が特権を得られるいわれはどこにあるんだ?一大人の方が歳をとっていて、賢いからかい?一 『天にまします主よ、この世にいるのは歳をとった子どもと年若い子どもだけ。それ以外はいません。どちらがあなたにとって喜ばしいか、あなたの子イエスが答えをだしています』 ところが、みんな、イエスの存在は倍じても、その言葉には耳を貸そうとしない。 昔からそうと相場が決まっている。そして子どもたちを自分と同じように育てる一」 「『自分を律することなんてできるものでしょうかね。自分の感情を意のままにするな んてむりでしょう』……牧師も話に加わろうとして熱心に聞き耳を立てていることに気づいた。 ぼくは彼にもわかるように声を張りあげた。 『人間のさまざまな悪癖をいましめるお説教はありますが、不機嫌を礼す説教はいまだかつて聞いたことがありませんね』」 「『人はよく、よい日はすくなく、いやな日が多すぎると嘆きますね』ぼくはそう言って、口火を切った。『しかし、たいていは正しくないと思うんです。神が毎日授けてくれるよいことを素直に享受するなら、災いが起きても、充分に耐えられるはずです』 『けれども、気持ちというのは思うようにならないものですよ』牧師夫人が応じた。 『体調にも左右されますしね!具合がよくないと、なにをやっても満足できないものです』 ぼくはその意見にうなずいて言った。 『それなら病気と見たらどうでしょう。そして治す薬はないかと考えてみるんです!』 『一理ありますね』ロッテが言った。『気の持ちようってあると思うんです。』」 「すごいことやありえないことをする非凡な人間は、えてして自分に酔っているとか、正気をなくしていると昔から言われているからね。 だけど、自由で気高く、予想を覆す行動に出た者を自分に酔っている愚か者だと陰口を叩くのは、普段の生活でも聞くに耐えないことだ。きみたち理性のある者は恥を知るべきだ。きみたち賢者は恥を知るべきなんだよ」 「しかしい。美しどんな事情があるか、どのくらい調べてみたんだい?それがなぜ起 ったか、その原因をきちんと説明できるのかい? そうするなら、そんな性急に判断を下したりしないはずだ」「きみも認めることだろうが、ある種の行為は、動機の如何にかかわらず、罪悪たり うるものだよ」 ぼくは肩をすくめて、同意しつつこうつづけた。 「けれども、そこにも例外はある。たしかに盗みは罪悪だ。しかし自分と家族を餓死から救うために盗みをはたらいた人間には同情すべきだと思うが、やはり罰するのかい?不実な妻と不届きな間男に当然の怒りをぶつけて死に追いやった夫に、だれ が石を投げるかな?歓喜に満ちたひと時に、愛の喜びを抑えきれずに我を忘れた娘がいるとして、それを責められるだろうか?法律という冷酷な代物だって、心を動かされて、罰することを控えるだろう』 『それは別の話だ。激情に駆ら』れた人間は自制心を失ってしまう。自分に酔っていたり、正気をなくしたりした者と同じだ」 『分別のある人間はこれだからな!』ぼくは微笑みながら叫んだ。」 「作家が自分の物語を改訂すると、文学としての出来映えはよくなるかもしれないが、どうしても作品を損ねてしまうってことをね。 第一印象は好意的に受けとめられるものだ。」 「『ネーデルラント連邦共和国がちゃんとおれに報酬を払ってくれりゃあ、こんなに落ちぶれちゃいない!すごい時代だったよ。俺は羽振りがよかった。だけど、いまはこの体たらくだ。俺はもう』 涙をこえて天を仰ぐまなざしがすべてを物語っていた。」 「見ろよ、おまえはこの家にとってどういう存在か。ここに住む友人たちに敬愛される存在だ!ふたりの喜びの源であり、おまえ自身もふたりなしにはいられない。だけどーもしおまえがいなくなったら、どうだ?この友だちの輪から出ていったら、どうなるだろう?おまえを失うことで、自分たちの運命にぽっかり開いたうつろな気分を、ふたりはいつまで感じるだろう?いったいいつまで?1ああ、人間は儚い存在だ。この世に存在したという生きた証を、愛する者たちの思い出や魂にはっきり刻みつけたとしても、消えてなくなるほかない。しかも時間をかけずに!」 - 2026年2月10日
 ラグビー 荒ぶる魂大西鉄之祐「一つのチームがちゃんと均衡がとれたものであったときには、その役割一つひとつがちょっとぐらい弱くても、チームは強くなるというチームワークの原理を、新人のときから教えられた。身をもって僕はそれを知った。だから僕が、チームのなかでスタープレーヤーがいなくても勝てると言ったり、みんなちゃんと自分のポジション、自分の役割をしっかり果せば負けることはない、ということを若い選手たちに教えていくのは、自分自身が経た体験から話しているのです。」 「ノーサイドになると、敵味方の区別なく、ポジションの区別なく語りあい、またの機会の奮闘を誓いあう。そういう、ラガーマンならではの世界が、地球上のさまざまな場所にあるということを感じる。それがラグビーの偉大さではないか、そういうことをいまつくづく感じています。何となく始めてしまったラグビーとのつきあいが、もう五〇年以上になりますが、ラ グビーの持っている魅力に引きこまれるまま、僕は歩んできたように思います」 「ラグビーの戦法としてゆさぶりというものをやるのならば、なぜゆさぶりを早稲田はやるのだということをもっと部員全部に徹底して教えるべきではなかったか。早稲田はゆさぶりをやるのだ、それで勝ってきたのだということはみんな知っているけれども、部員全部が、ゆさぶりというのはどういう理論に基づいて、どういうふうにやるのかということは、慣習的にサーッと練習のなかで覚えているだけで、しっかりした理論をまだもってなかった。それがあの年に、技術も練習も非常に積んだけれども、負けた一つの原因ではないか。もっと部全体に、あるいは選手全員に、ゆさぶり理論を徹底していけば、勝てたのではないかという感じがする。 だから、僕が監督になってからはその点を大変考えた。ラグビー部のように伝統が長いと、伝統という一つのベルトコンベヤーが流れているのと同じだから、その上でずっとやっているとやることが似てくる。そしてマンネリに陥ってしまう。それで勝っていると、そのやり方をやっていれば隣てるじゃないかということになり、なぜこれをやるのかということを忘れてしまう。 よくこのごろ日本の強いチームが試合をやり、ある程度勝ち続けると、何だかこうやっていれば勝てるのだということになれてしまって、あとは研究しないで、そしてマンネリに陥って負けていくケースがあるが、早稲田もあの当時そうなっていたのではないかという気がします。チームがマンネリに陥るということは、一人ひとりのプレーヤーが考えてプレーしなくなることと裏腹なのです。」 「収集した情報と研究の組織化による理論的戦法の成立は、次いで具体的戦法の開発に向けられます。具体的戦法の開発は、そのチームまたはプレーヤーに最も適した合理的な攻防の理論を、多数ある理論的戦法の中から選択して適用することなのです。もちろん具体的戦法を勝率の最も高いものにするためには、プレーヤーが持つ技術をその戦法に適応した最高のものにしなければなりません。 しかし技術を科学的に研究するだけではスポーツでは勝てないことは、少しゲームをやればわかるでしょう。科学的研究は客観的操作の可能なものごとの認識と、その認識にもとづくものごとの支配については偉大なる業績をあげてきました。しかしスポーツという一種の闘争(英知による闘争のゲーム化)という特殊な情況の中において、プレーヤー自身が客観化できないことがらに対しては、個人の意志や感情はもちろん、時に思考や判断さえ力とはなりえない。こうした事態における自己コントロールは、そうした事態を何回となく体験して、その経験の累積の中で体得する以外に方法はない。幸いにしてこれらの事態は、ゲームの中に満ちあふれています。 ゲームにおけるピンチとチャンスは最大の緊急事態です。勝敗の岐路はこれに対し、いかに適切な処置ができるかどうかにかかっているからです。…同時に、スポーツは闘争です。そして闘争には恐怖が伴う。旺盛な闘志と勇気をもって、この恐怖をのり越えなければゲームには勝てない。大試合における闘争の倫理の葛藤ほど対処のむずかしいものはない。汚ないプレーをしても勝負に勝ちたいという誘惑にかられることも、ないとはいえません。こうした善悪二律背反の間での修行とフェアーな行動こそ、ゲームにおける最も重要なものなのです。 スポーツの勝負におけるいろいろな情緒的行動ほど、コントロールのむずかしいものはありません。ここにスポーツを通じてのもう一つの教育的価値があると思うのです。愛動する社会の闘争、あるいは競争の渦中にあって自らの情緒的行動をいかに平和にコントロールするか。こうした修行の過程が、ゲームの中に存在すると考えるからです。」
ラグビー 荒ぶる魂大西鉄之祐「一つのチームがちゃんと均衡がとれたものであったときには、その役割一つひとつがちょっとぐらい弱くても、チームは強くなるというチームワークの原理を、新人のときから教えられた。身をもって僕はそれを知った。だから僕が、チームのなかでスタープレーヤーがいなくても勝てると言ったり、みんなちゃんと自分のポジション、自分の役割をしっかり果せば負けることはない、ということを若い選手たちに教えていくのは、自分自身が経た体験から話しているのです。」 「ノーサイドになると、敵味方の区別なく、ポジションの区別なく語りあい、またの機会の奮闘を誓いあう。そういう、ラガーマンならではの世界が、地球上のさまざまな場所にあるということを感じる。それがラグビーの偉大さではないか、そういうことをいまつくづく感じています。何となく始めてしまったラグビーとのつきあいが、もう五〇年以上になりますが、ラ グビーの持っている魅力に引きこまれるまま、僕は歩んできたように思います」 「ラグビーの戦法としてゆさぶりというものをやるのならば、なぜゆさぶりを早稲田はやるのだということをもっと部員全部に徹底して教えるべきではなかったか。早稲田はゆさぶりをやるのだ、それで勝ってきたのだということはみんな知っているけれども、部員全部が、ゆさぶりというのはどういう理論に基づいて、どういうふうにやるのかということは、慣習的にサーッと練習のなかで覚えているだけで、しっかりした理論をまだもってなかった。それがあの年に、技術も練習も非常に積んだけれども、負けた一つの原因ではないか。もっと部全体に、あるいは選手全員に、ゆさぶり理論を徹底していけば、勝てたのではないかという感じがする。 だから、僕が監督になってからはその点を大変考えた。ラグビー部のように伝統が長いと、伝統という一つのベルトコンベヤーが流れているのと同じだから、その上でずっとやっているとやることが似てくる。そしてマンネリに陥ってしまう。それで勝っていると、そのやり方をやっていれば隣てるじゃないかということになり、なぜこれをやるのかということを忘れてしまう。 よくこのごろ日本の強いチームが試合をやり、ある程度勝ち続けると、何だかこうやっていれば勝てるのだということになれてしまって、あとは研究しないで、そしてマンネリに陥って負けていくケースがあるが、早稲田もあの当時そうなっていたのではないかという気がします。チームがマンネリに陥るということは、一人ひとりのプレーヤーが考えてプレーしなくなることと裏腹なのです。」 「収集した情報と研究の組織化による理論的戦法の成立は、次いで具体的戦法の開発に向けられます。具体的戦法の開発は、そのチームまたはプレーヤーに最も適した合理的な攻防の理論を、多数ある理論的戦法の中から選択して適用することなのです。もちろん具体的戦法を勝率の最も高いものにするためには、プレーヤーが持つ技術をその戦法に適応した最高のものにしなければなりません。 しかし技術を科学的に研究するだけではスポーツでは勝てないことは、少しゲームをやればわかるでしょう。科学的研究は客観的操作の可能なものごとの認識と、その認識にもとづくものごとの支配については偉大なる業績をあげてきました。しかしスポーツという一種の闘争(英知による闘争のゲーム化)という特殊な情況の中において、プレーヤー自身が客観化できないことがらに対しては、個人の意志や感情はもちろん、時に思考や判断さえ力とはなりえない。こうした事態における自己コントロールは、そうした事態を何回となく体験して、その経験の累積の中で体得する以外に方法はない。幸いにしてこれらの事態は、ゲームの中に満ちあふれています。 ゲームにおけるピンチとチャンスは最大の緊急事態です。勝敗の岐路はこれに対し、いかに適切な処置ができるかどうかにかかっているからです。…同時に、スポーツは闘争です。そして闘争には恐怖が伴う。旺盛な闘志と勇気をもって、この恐怖をのり越えなければゲームには勝てない。大試合における闘争の倫理の葛藤ほど対処のむずかしいものはない。汚ないプレーをしても勝負に勝ちたいという誘惑にかられることも、ないとはいえません。こうした善悪二律背反の間での修行とフェアーな行動こそ、ゲームにおける最も重要なものなのです。 スポーツの勝負におけるいろいろな情緒的行動ほど、コントロールのむずかしいものはありません。ここにスポーツを通じてのもう一つの教育的価値があると思うのです。愛動する社会の闘争、あるいは競争の渦中にあって自らの情緒的行動をいかに平和にコントロールするか。こうした修行の過程が、ゲームの中に存在すると考えるからです。」 - 2025年12月26日
 「三島はK子を、強制的異性愛イデオロギーとロマンチック・ラブ・イデオロギーの規範でしか見られなかったのである。愛している以上性愛に至らざるをえず、そして結婚へと向かうのが当然だという規範に不可能を感じ、離れざるをえなかったのだ。……同性愛を描いた「仮面の告白』『禁色』は、今世紀になってみれば、性の多様性という題材によってむしろ高く評価される。異性愛を「正常」とする作品の規範性に時代的な限界はあるものの、日本の近代文学が男性同性愛文学の傑作を持ったことは、誇れることである。」 「『憂国』(「小説中央公論」一九六一年一月号)の前に、三島は『愛の処刑』を書いている。男性同性愛のアドニス会の機関誌『ADONIS』の別冊『APOLLO』五号(一九六〇年十月)に、『楠山保』の筆名で発表した短編小説である。愛する教え子を死なせてしまった体操教師が、別の教え子からその過失を責められ切腹する話である。血まみれの切腹の最中に交わされる教え子との愛のことばと苦痛の描写が、この小説を特異なものとしている。『愛の処刑』の存在は話では聞いていたが、変名を使っていること、原稿に複数の人の手が入っているらしいこと、発表誌が稀書であることから扱いが難しかった。『決定版 三島由紀夫全集』の編集過程で、ノートに書かれた三島のオリジナル原稿が出てきたのだが、その意義は小さくない。作品の存在自体もさることながら、切腹という行為に、三島の前意味論的欲動が具体化していることがはっきりしたからである。 『憂国』で想像されたことが補われた形である。」 「『身を挺する』『悲劇的なもの』という前意味論的欲動の全的な解放にほかならない。 三島は新潮文庫『花ざかりの森・憂国』の自作解説で、『もし、忙しい人が、三島の小説の中から一編だけ、三島のよいところ悪いところすべてを凝縮したエキスのやうな小説を読みたいと求めたら、『憂国』の一編を読んでもらへばよい』と述べた。」 「『サド侯爵夫人』…三島由紀夫は、澁澤龍彦の『サド侯爵の生涯』(桃源社、一九六四年)に触発されてこの戯曲を書いた。サド侯爵夫人は獄中の夫に終始尽くしながら、サドが釈放されると別れてしまうが、『その謎の論理的解明を試みた』というのである(「祓(「サド侯爵夫人」)」)。」 「『わが友ヒットラー』は『朱雀家の滅亡』に比べれば、政治というずっと卑近な意味を持っている。『さうです、政治は中道を行かなければなりません』というのがヒットラーの幕切れの台詞だが、独裁者となるためにはまずは民衆の支持を得ておく必要がある。そのマキャベリズムに巻き込まれる人物が、ヒットラーを「わが友」と呼ぶエルンスト・レーム※である。三百万人の非正規軍を率いる突撃隊の隊長であるレームは、いまやヒットラーが政権を掌握するための最も厄介な邪魔者になっていることを知ろうともしないし、処刑される運命にも気づかない。『人間の信頼だよ。友愛、同志愛、戦友愛、それらもろもろの気高い男らしい神々の特質だ』。それが自分とヒットラーとを結びつけている絆だと肩じている。 レームと突撃隊は、明らかに三島と楯の会を表している。楯の会など政治の権謀術数から見れば、子ども騙しの集団でしかないことを作者は知っている。しかし同時に三島は、レームの単純な盲信が『神々の特質』であることも知り、この戯曲であっさりと粛正される『三度の飯よりも兵隊ごつこが好き』なレームを、戯画化した上で憧れているのである。このような複眼のどこに作者の力点が置かれているかを見なければならない。」(※ ナチス政権下では男性同性愛が弾圧され、約10万人が逮捕、多くが強制収容所で殺害された。SAリーダーのエルンスト・レームも同性愛者であった。レームはヒトラーの数少ない腹心であり、ヒトラーは当初レームが同性愛者であることを黙認していた。しかし、レームの権力拡大を恐れ、1934年の「長いナイフの夜」で彼を粛清する際、レームの同性愛を「不道徳」として糾弾、これを口実とした。) 「ナショナリズムに落とし込む愚は避けたのかもしれないが、アメリカへの屈折した感情を介在せずに戦後のナショナリズムを披瀝する三島の表現は、大塚英志『サブカルチャー文学論』も指摘しているとおり独特な言説である。『英霊の声』は、批判の目を外に向けずに内なる日本に向けたことで、人間天皇と大衆との結びつきが経済成長を用意し、戦前戦中の記憶を歪めていると指弾することにもなったのである。』 「戦時中『現人神』と言われた天皇は、一九四六(昭和二十一)年にいわゆる『人間宣言』を発して『人間』となった。この単純な神から人間への変化という通念に、三島は与しなかった。 『英霊の声』では『陛下は人間であらせられた』『それはよい』と霊たちは言い、次のように続ける。 だが、昭和の歴史においてただ二度だけ、陛下は神であらせられるべきだった。何と云はうか、人間としての義務において、神であらせられるべきだつた。この二度だけは、陛下は人間であらせられるその深度のきはみにおいて、正に、神であらせられるべきだった。 それを二度とも陛下は逸したまうた。もつとも神であらせられるべき時に、人間にましましたのだ。二・二六事件の際の天皇の人間的な怒り、特攻隊の死から遠くない年の『人間宣言』、それは許せないというのだが、天皇が人間であるのは認めているのである。天皇を人間と認めかつまた神であるべきだとする考えは、人間である天皇個人と天皇制とを分離して見る見方である。 それは、天皇個人が天皇制そのものであると一体化して見ていた昭和の戦中戦後期の多くの国民の天皇観と比較すると、柔軟で実質的でもあった。 白井聡は『永続敗戦論!戦後日本の核心』で『「平和と繁栄」に酔い痴れる高度成長下の戦後日本社会の精神的退魔(それは本書が「永続敗戦」と呼ぶものだ)の元図をそこ(天皇ー引用者注)に求めた三島由紀夫は、まさに意識であった』と述べる。『英霊の声』の霊たちが』平和と繁栄』の浮薄をあげつらい、それと天皇の『人間宣言』とを結びつけて糾弾したのは、その背後におけるアメリカの介入とそれを進んで受け入れた天皇 ーしかしそのじつそれは、日本の大来にほかならなかったー の覚醒を呼びかけた「声」であったということになろう。そしてそれは、二・二六事件に際しての天皇の生な感情の表出に繋っており、その感情には親英米の思考が働いていた点で、戦後日本のアメリカ従属下における『平和と繁栄』をもたらしたと白井聡の思考を敷衍することもできる。」 「三島はまず「国民文化の三特質」として、伝統との連続性である「再帰性」、あらゆる文化の「まるごとの容認」である「全体性」、文化の成果のための関与である「主体性」を挙げる。 このうち最も重要なのは「全体性」である。それは言論の自由を基盤として、「文化の無差別包括性」を持つということだ。「雑多な、広汎な、包括的な文化の全体性」ともあり、「空間的連続性は時には政治的無秩序をさへ容認する」ともある。……このような文化の「全体性」が保障される社会は、歓迎すべき社会である。」
「三島はK子を、強制的異性愛イデオロギーとロマンチック・ラブ・イデオロギーの規範でしか見られなかったのである。愛している以上性愛に至らざるをえず、そして結婚へと向かうのが当然だという規範に不可能を感じ、離れざるをえなかったのだ。……同性愛を描いた「仮面の告白』『禁色』は、今世紀になってみれば、性の多様性という題材によってむしろ高く評価される。異性愛を「正常」とする作品の規範性に時代的な限界はあるものの、日本の近代文学が男性同性愛文学の傑作を持ったことは、誇れることである。」 「『憂国』(「小説中央公論」一九六一年一月号)の前に、三島は『愛の処刑』を書いている。男性同性愛のアドニス会の機関誌『ADONIS』の別冊『APOLLO』五号(一九六〇年十月)に、『楠山保』の筆名で発表した短編小説である。愛する教え子を死なせてしまった体操教師が、別の教え子からその過失を責められ切腹する話である。血まみれの切腹の最中に交わされる教え子との愛のことばと苦痛の描写が、この小説を特異なものとしている。『愛の処刑』の存在は話では聞いていたが、変名を使っていること、原稿に複数の人の手が入っているらしいこと、発表誌が稀書であることから扱いが難しかった。『決定版 三島由紀夫全集』の編集過程で、ノートに書かれた三島のオリジナル原稿が出てきたのだが、その意義は小さくない。作品の存在自体もさることながら、切腹という行為に、三島の前意味論的欲動が具体化していることがはっきりしたからである。 『憂国』で想像されたことが補われた形である。」 「『身を挺する』『悲劇的なもの』という前意味論的欲動の全的な解放にほかならない。 三島は新潮文庫『花ざかりの森・憂国』の自作解説で、『もし、忙しい人が、三島の小説の中から一編だけ、三島のよいところ悪いところすべてを凝縮したエキスのやうな小説を読みたいと求めたら、『憂国』の一編を読んでもらへばよい』と述べた。」 「『サド侯爵夫人』…三島由紀夫は、澁澤龍彦の『サド侯爵の生涯』(桃源社、一九六四年)に触発されてこの戯曲を書いた。サド侯爵夫人は獄中の夫に終始尽くしながら、サドが釈放されると別れてしまうが、『その謎の論理的解明を試みた』というのである(「祓(「サド侯爵夫人」)」)。」 「『わが友ヒットラー』は『朱雀家の滅亡』に比べれば、政治というずっと卑近な意味を持っている。『さうです、政治は中道を行かなければなりません』というのがヒットラーの幕切れの台詞だが、独裁者となるためにはまずは民衆の支持を得ておく必要がある。そのマキャベリズムに巻き込まれる人物が、ヒットラーを「わが友」と呼ぶエルンスト・レーム※である。三百万人の非正規軍を率いる突撃隊の隊長であるレームは、いまやヒットラーが政権を掌握するための最も厄介な邪魔者になっていることを知ろうともしないし、処刑される運命にも気づかない。『人間の信頼だよ。友愛、同志愛、戦友愛、それらもろもろの気高い男らしい神々の特質だ』。それが自分とヒットラーとを結びつけている絆だと肩じている。 レームと突撃隊は、明らかに三島と楯の会を表している。楯の会など政治の権謀術数から見れば、子ども騙しの集団でしかないことを作者は知っている。しかし同時に三島は、レームの単純な盲信が『神々の特質』であることも知り、この戯曲であっさりと粛正される『三度の飯よりも兵隊ごつこが好き』なレームを、戯画化した上で憧れているのである。このような複眼のどこに作者の力点が置かれているかを見なければならない。」(※ ナチス政権下では男性同性愛が弾圧され、約10万人が逮捕、多くが強制収容所で殺害された。SAリーダーのエルンスト・レームも同性愛者であった。レームはヒトラーの数少ない腹心であり、ヒトラーは当初レームが同性愛者であることを黙認していた。しかし、レームの権力拡大を恐れ、1934年の「長いナイフの夜」で彼を粛清する際、レームの同性愛を「不道徳」として糾弾、これを口実とした。) 「ナショナリズムに落とし込む愚は避けたのかもしれないが、アメリカへの屈折した感情を介在せずに戦後のナショナリズムを披瀝する三島の表現は、大塚英志『サブカルチャー文学論』も指摘しているとおり独特な言説である。『英霊の声』は、批判の目を外に向けずに内なる日本に向けたことで、人間天皇と大衆との結びつきが経済成長を用意し、戦前戦中の記憶を歪めていると指弾することにもなったのである。』 「戦時中『現人神』と言われた天皇は、一九四六(昭和二十一)年にいわゆる『人間宣言』を発して『人間』となった。この単純な神から人間への変化という通念に、三島は与しなかった。 『英霊の声』では『陛下は人間であらせられた』『それはよい』と霊たちは言い、次のように続ける。 だが、昭和の歴史においてただ二度だけ、陛下は神であらせられるべきだった。何と云はうか、人間としての義務において、神であらせられるべきだつた。この二度だけは、陛下は人間であらせられるその深度のきはみにおいて、正に、神であらせられるべきだった。 それを二度とも陛下は逸したまうた。もつとも神であらせられるべき時に、人間にましましたのだ。二・二六事件の際の天皇の人間的な怒り、特攻隊の死から遠くない年の『人間宣言』、それは許せないというのだが、天皇が人間であるのは認めているのである。天皇を人間と認めかつまた神であるべきだとする考えは、人間である天皇個人と天皇制とを分離して見る見方である。 それは、天皇個人が天皇制そのものであると一体化して見ていた昭和の戦中戦後期の多くの国民の天皇観と比較すると、柔軟で実質的でもあった。 白井聡は『永続敗戦論!戦後日本の核心』で『「平和と繁栄」に酔い痴れる高度成長下の戦後日本社会の精神的退魔(それは本書が「永続敗戦」と呼ぶものだ)の元図をそこ(天皇ー引用者注)に求めた三島由紀夫は、まさに意識であった』と述べる。『英霊の声』の霊たちが』平和と繁栄』の浮薄をあげつらい、それと天皇の『人間宣言』とを結びつけて糾弾したのは、その背後におけるアメリカの介入とそれを進んで受け入れた天皇 ーしかしそのじつそれは、日本の大来にほかならなかったー の覚醒を呼びかけた「声」であったということになろう。そしてそれは、二・二六事件に際しての天皇の生な感情の表出に繋っており、その感情には親英米の思考が働いていた点で、戦後日本のアメリカ従属下における『平和と繁栄』をもたらしたと白井聡の思考を敷衍することもできる。」 「三島はまず「国民文化の三特質」として、伝統との連続性である「再帰性」、あらゆる文化の「まるごとの容認」である「全体性」、文化の成果のための関与である「主体性」を挙げる。 このうち最も重要なのは「全体性」である。それは言論の自由を基盤として、「文化の無差別包括性」を持つということだ。「雑多な、広汎な、包括的な文化の全体性」ともあり、「空間的連続性は時には政治的無秩序をさへ容認する」ともある。……このような文化の「全体性」が保障される社会は、歓迎すべき社会である。」 - 2025年12月17日
 プレップ経済倫理学柘植尚則「経済における倫理的な問題について考察する場合でも、そこで求められているのは、経済を相対化する視点です。ここに、『倫理学』としての経済論理学の大きな意義があります。」 「消費には、それ以上の『意味』があります。では、その意味とはどのようなものでしょうか。 たとえば、アメリカのヴェブレンによると、消費は、個人の社会的な『成功』や『地位』を示すものでもあります。そこで、人びとは、しばしば、みずからの効用を実現することよりもむしろ、自分の成功や地位を他人に示すことを目的として、清費を行うようになります。その動機は、必要よりもむしろ、見栄や競争心であり、そうした動機にもとづいて、人びとは必要以上のものを浪費するようになります。ヴェブレンは、そのような消費を『顕示的消費』と呼んでいます。 ヴェブレン自身は、おもに、当時の上流階級の費を問題にしていました。ですが、それと似たような費は、中流・下流階級にも見られます。また、現代でも、多くの人は、自分の成功や地位を示すために、たとえば、いわゆる『ブランド』の商品を買ったりしています。現在は、このような清はすべて、顕示的消費と呼ばれています。 ただ、ブラント商品を買うのは、自分の成功や地位を示すためだけではありません。たとえば、自分らしさや他人との違いを示すために、つまり、個性を提示するために、ブランド商品を買うこともあります。さらに言うと、ブランド商品に限らず、ほとんどすべての商品を買うさいにも、人びとは、その商品がもつ「イメージ」を考慮します。そして、そのイメージを、自分の『個性』『感情』『気分』などを示すものとして利用します。その場合、人びとは、商品よりもむしろ、商品がもつイメージを買っているのです。 では、なぜそうするのでしょうか。それは、主として、特定のイメージをもった商品を費することで、自分の個性、感情、気分などを、他人に伝えるためです。言い換えると、他人とのコミュニケーションのために、商品が示すイメージを買っているのです。このように、消費には、コミュニケーションという役割があります。 消費は、言語によらないコミュニケーションの一種です。言語の場合、言葉という『記号』を介して、コミュニケーションが行われます。それと同様に、消費の場合、商品という『記号』を介して、コミュニケーションが行われます。それゆえ、消費は、欲求の充足や効用の実現のためだけでなく、他人とのコミュニケーションのためにも行われるのです。言い換えると、消費するとは、商品という記号を消費することでもあるのです。このような考え方は、一般に、『記号消費論』と呼ばれています。それをいち早く唱えたのは、7ランスのボードリヤールです。 以上に見たように、消費は、社会的な成功や地位、自分の個性、感情、気分などを示すものでもあります。これらが消費のもつ意味とされています。」
プレップ経済倫理学柘植尚則「経済における倫理的な問題について考察する場合でも、そこで求められているのは、経済を相対化する視点です。ここに、『倫理学』としての経済論理学の大きな意義があります。」 「消費には、それ以上の『意味』があります。では、その意味とはどのようなものでしょうか。 たとえば、アメリカのヴェブレンによると、消費は、個人の社会的な『成功』や『地位』を示すものでもあります。そこで、人びとは、しばしば、みずからの効用を実現することよりもむしろ、自分の成功や地位を他人に示すことを目的として、清費を行うようになります。その動機は、必要よりもむしろ、見栄や競争心であり、そうした動機にもとづいて、人びとは必要以上のものを浪費するようになります。ヴェブレンは、そのような消費を『顕示的消費』と呼んでいます。 ヴェブレン自身は、おもに、当時の上流階級の費を問題にしていました。ですが、それと似たような費は、中流・下流階級にも見られます。また、現代でも、多くの人は、自分の成功や地位を示すために、たとえば、いわゆる『ブランド』の商品を買ったりしています。現在は、このような清はすべて、顕示的消費と呼ばれています。 ただ、ブラント商品を買うのは、自分の成功や地位を示すためだけではありません。たとえば、自分らしさや他人との違いを示すために、つまり、個性を提示するために、ブランド商品を買うこともあります。さらに言うと、ブランド商品に限らず、ほとんどすべての商品を買うさいにも、人びとは、その商品がもつ「イメージ」を考慮します。そして、そのイメージを、自分の『個性』『感情』『気分』などを示すものとして利用します。その場合、人びとは、商品よりもむしろ、商品がもつイメージを買っているのです。 では、なぜそうするのでしょうか。それは、主として、特定のイメージをもった商品を費することで、自分の個性、感情、気分などを、他人に伝えるためです。言い換えると、他人とのコミュニケーションのために、商品が示すイメージを買っているのです。このように、消費には、コミュニケーションという役割があります。 消費は、言語によらないコミュニケーションの一種です。言語の場合、言葉という『記号』を介して、コミュニケーションが行われます。それと同様に、消費の場合、商品という『記号』を介して、コミュニケーションが行われます。それゆえ、消費は、欲求の充足や効用の実現のためだけでなく、他人とのコミュニケーションのためにも行われるのです。言い換えると、消費するとは、商品という記号を消費することでもあるのです。このような考え方は、一般に、『記号消費論』と呼ばれています。それをいち早く唱えたのは、7ランスのボードリヤールです。 以上に見たように、消費は、社会的な成功や地位、自分の個性、感情、気分などを示すものでもあります。これらが消費のもつ意味とされています。」 - 2025年11月24日
 幸福の増税論-財政はだれのために井手英策「二〇〇一年以降、歴史的な、いや世界史的ともいうべき金融緩和をつづけてきたが、物価の上昇もかつてのような経済成長も実現されなかった。そもそも、四%、五%というかつての経済成長率は、二〇〇〇年代以降、ほとんどの主要先進国で実現できていない数字だ。 これが現実の姿である。いくら借金してもよいのだ、将来の成長が借金をなかったことにしてくれる、そうした主張は『願望』としては理解できるが、『現実』としては受けいれられない。財政支出がまだ足りないからいけないのだ、という主張は、市場の自由化が足りないから経済が成長しないのだと繰りかえした市場原理主義者のロジックとなんらかわらない。」 「日本経済が復活するとすれば、それは劇的なイノベーションをきっかけに、活発な資金循環がおきることを期待するしかない。しかし、日本銀行が大量の国債買入れをおこなうからこそ、経済の血液ともいうべき金融システムが機能不全化した。 現在の国債価格の安定は日銀の買入れによるところが大きい。その結果、長期金利がゼロ近くにべったりとはりつき、金利の変動こそが収益の源であるのに、市場の金利メカニズムが機能しなくなってしまっている。国債増発派がその拠りどころとするのは、日銀のさらなる買入れ、そして引受けだ。だが、国債発行を可能にするその条件こそが、成長力を弱める重要なファクターなのだ。」 「事業への貸付けは、イノベーションのためには不可欠なはずである。ところが、ここまで金利がさがってしまえば、リスクの大きな事業にも低い金利で資金を貸し付けなくてはならなくなる。金融機関はそのアンバランスさにおびえ、融資を踏みとどまっている。 皮肉な話だが、国債価格が暴落しない、財政危機はやってこない、だからこそ、日本経済も復活しない、こうした悪循環にいまの僕たちはおちいっているのだ。」 「だれがムダづかいをし、どの予算から削るかという犯人さがしと袋だたきの政治が横行し、政府や政治、そして他者にたいする不感は強く、平等、自由、愛国心、人権といった普遍的な価値を共有できない分断された社会の姿も浮き彫りになった。」 「税が一九%になるといわれるとおどろく人が多いだろう。だが、これほどの大増税をしても、OECD加盟三五か国の平均に届くか、届かないかくらいの国民負担率でしかない。日本はそれだけ税が安い国、反対にいえば、自己責任でやってきた国だということである。 今後高齢化が進展し、社会保障費が伸びるといわれているが、その可能性を想定してもなお、税をあげる余裕は十分にある。第一章でも論じたようにOECDには多数の新興国がくわわった。もし、そのなかの平均ではなく、主要先進国の平均をめざしていくのであれば、たんなる無償化をこえ、サービスの質的拡充に足を踏みだすことも可能になる。 そうすれば、たとえば教育であれば、就学前教育や大学教育の無償化、義務教育の完全無償化だけではなく、職業教育や職業訓練の拡充、基礎研究の充実、教育の質の向上へとさらにあゆみをすすめていくことができることとなる。あるいは、人びとの命やくらしをささえるための雇用、のちに述べるソーシャル・ワーカーの拡充も可能になるだろう。」 「税の負担をめぐってはしばしば、低所得層の負担が問題とされる。だが、この図が示すのは、給付面を適切におこなえば、所得格差は小さくできるということだ。」 「たしかに僕たちは取られる。だが、自分が必要なときにはだれかがはらってくれる。 さらには、手元にのこったお金は、貯蓄ではなく、遠慮なく消費にまわしてよい。『貯蓄ゼロでも不安ゼロ』が頼りあえる社会のめざす究極の姿である。」 「貯蓄をすれば、資産が増えることは事実である。ただし、それが将来へのそなえであり、いま使うことのできない資産である以上、税を取られるのと同じように消費は抑えられている。」 「生活不安におびえ、権力者や他の納税者をじられず、社会のメンバーと価値を共有できない、そのような人たちが税の負担を受けいれるはずがない。」 「僕たちは、相税負担率があがれば、人びとの消費が減り、労働の意欲が減退すると肩じてきた。だが、むしろ頑健な「保障の場」があるとき、人びとは自由な発想のもとで思いきったチャレンジができるようになるのではないだろうか。」 「財政の将来の持続可能性を高めるためには、増税はさけられない。だが、それに立ちはだかるのは、痛続感による種税抵抗だ。税の痛みを緩和しないかぎり、増税の実現はむつかしい。 だからこそ、受益感にとみ、将来不安の軽減につながる増税案を示すことが不可々なのだ。 税が生活の安心につながるという成功体験が土台にあってようやく「増税の一部を財政健全化にクから可能性もひらけてくる。」 「ここで読者にいっておきたいことがある。 頼りあえる社会とは、自分はもちろんのこと、同じ社会を生きる仲間たちが苦境に立たされているいまだからこそ、税という痛みを引き取ってでも、みんなでみんなのくらしをささえあう社会を作ろうという考えかた、あえていえば社会観が根底にある。 まずしい人や腹がいのある人もあくめてだれも置き去りにしない、嫉妬や憎悪で語る政治をおわりにする、ちかいてはなく共通点に思いをはせる、分断をくいとめ、連帯の社会を次の世代の子どもたちに残していく、そういう提案だ。」 「経済が成長し、所得がふえなければみなが幸せになれない社会は、経済の停滞とともに、深刻な社会状況を過去にも、現在にももたらした。僕たちはその反省のうえにたち、あるべき社会の姿、未来を構想すべきなのである。」 「家政=オイコノミアは、経済ルエコノミーの語源だが、一家の生活にかかわるすべてのことがらを処理し、治めることを意味している。アリストテレスは、家とは、財産の望ましい状態よりも人間の望ましい状態を維持するための存在だと説いたのである。」「一部のだれかを救済するのではない、可能なかぎり多くの人たちを家族のようにささえるということだ。」 「はげしい将来不安に直面するとき、人びとは痛みを分かちあい、連帯する道をえらぶ。」 「頼りあえる社会とは、税による痛みの分かちあいで財源を獲得し、ふたつの「生の保障」、つまりベーシック・サービスによる「尊厳ある生活保障」と、生活扶助と住手当による「品位ある命の保障」を徹底しておこなう枠組みだ。勤労国家という自己責任モデルを終わらせ、「保障の場」を鋳直そうという提案である。」
幸福の増税論-財政はだれのために井手英策「二〇〇一年以降、歴史的な、いや世界史的ともいうべき金融緩和をつづけてきたが、物価の上昇もかつてのような経済成長も実現されなかった。そもそも、四%、五%というかつての経済成長率は、二〇〇〇年代以降、ほとんどの主要先進国で実現できていない数字だ。 これが現実の姿である。いくら借金してもよいのだ、将来の成長が借金をなかったことにしてくれる、そうした主張は『願望』としては理解できるが、『現実』としては受けいれられない。財政支出がまだ足りないからいけないのだ、という主張は、市場の自由化が足りないから経済が成長しないのだと繰りかえした市場原理主義者のロジックとなんらかわらない。」 「日本経済が復活するとすれば、それは劇的なイノベーションをきっかけに、活発な資金循環がおきることを期待するしかない。しかし、日本銀行が大量の国債買入れをおこなうからこそ、経済の血液ともいうべき金融システムが機能不全化した。 現在の国債価格の安定は日銀の買入れによるところが大きい。その結果、長期金利がゼロ近くにべったりとはりつき、金利の変動こそが収益の源であるのに、市場の金利メカニズムが機能しなくなってしまっている。国債増発派がその拠りどころとするのは、日銀のさらなる買入れ、そして引受けだ。だが、国債発行を可能にするその条件こそが、成長力を弱める重要なファクターなのだ。」 「事業への貸付けは、イノベーションのためには不可欠なはずである。ところが、ここまで金利がさがってしまえば、リスクの大きな事業にも低い金利で資金を貸し付けなくてはならなくなる。金融機関はそのアンバランスさにおびえ、融資を踏みとどまっている。 皮肉な話だが、国債価格が暴落しない、財政危機はやってこない、だからこそ、日本経済も復活しない、こうした悪循環にいまの僕たちはおちいっているのだ。」 「だれがムダづかいをし、どの予算から削るかという犯人さがしと袋だたきの政治が横行し、政府や政治、そして他者にたいする不感は強く、平等、自由、愛国心、人権といった普遍的な価値を共有できない分断された社会の姿も浮き彫りになった。」 「税が一九%になるといわれるとおどろく人が多いだろう。だが、これほどの大増税をしても、OECD加盟三五か国の平均に届くか、届かないかくらいの国民負担率でしかない。日本はそれだけ税が安い国、反対にいえば、自己責任でやってきた国だということである。 今後高齢化が進展し、社会保障費が伸びるといわれているが、その可能性を想定してもなお、税をあげる余裕は十分にある。第一章でも論じたようにOECDには多数の新興国がくわわった。もし、そのなかの平均ではなく、主要先進国の平均をめざしていくのであれば、たんなる無償化をこえ、サービスの質的拡充に足を踏みだすことも可能になる。 そうすれば、たとえば教育であれば、就学前教育や大学教育の無償化、義務教育の完全無償化だけではなく、職業教育や職業訓練の拡充、基礎研究の充実、教育の質の向上へとさらにあゆみをすすめていくことができることとなる。あるいは、人びとの命やくらしをささえるための雇用、のちに述べるソーシャル・ワーカーの拡充も可能になるだろう。」 「税の負担をめぐってはしばしば、低所得層の負担が問題とされる。だが、この図が示すのは、給付面を適切におこなえば、所得格差は小さくできるということだ。」 「たしかに僕たちは取られる。だが、自分が必要なときにはだれかがはらってくれる。 さらには、手元にのこったお金は、貯蓄ではなく、遠慮なく消費にまわしてよい。『貯蓄ゼロでも不安ゼロ』が頼りあえる社会のめざす究極の姿である。」 「貯蓄をすれば、資産が増えることは事実である。ただし、それが将来へのそなえであり、いま使うことのできない資産である以上、税を取られるのと同じように消費は抑えられている。」 「生活不安におびえ、権力者や他の納税者をじられず、社会のメンバーと価値を共有できない、そのような人たちが税の負担を受けいれるはずがない。」 「僕たちは、相税負担率があがれば、人びとの消費が減り、労働の意欲が減退すると肩じてきた。だが、むしろ頑健な「保障の場」があるとき、人びとは自由な発想のもとで思いきったチャレンジができるようになるのではないだろうか。」 「財政の将来の持続可能性を高めるためには、増税はさけられない。だが、それに立ちはだかるのは、痛続感による種税抵抗だ。税の痛みを緩和しないかぎり、増税の実現はむつかしい。 だからこそ、受益感にとみ、将来不安の軽減につながる増税案を示すことが不可々なのだ。 税が生活の安心につながるという成功体験が土台にあってようやく「増税の一部を財政健全化にクから可能性もひらけてくる。」 「ここで読者にいっておきたいことがある。 頼りあえる社会とは、自分はもちろんのこと、同じ社会を生きる仲間たちが苦境に立たされているいまだからこそ、税という痛みを引き取ってでも、みんなでみんなのくらしをささえあう社会を作ろうという考えかた、あえていえば社会観が根底にある。 まずしい人や腹がいのある人もあくめてだれも置き去りにしない、嫉妬や憎悪で語る政治をおわりにする、ちかいてはなく共通点に思いをはせる、分断をくいとめ、連帯の社会を次の世代の子どもたちに残していく、そういう提案だ。」 「経済が成長し、所得がふえなければみなが幸せになれない社会は、経済の停滞とともに、深刻な社会状況を過去にも、現在にももたらした。僕たちはその反省のうえにたち、あるべき社会の姿、未来を構想すべきなのである。」 「家政=オイコノミアは、経済ルエコノミーの語源だが、一家の生活にかかわるすべてのことがらを処理し、治めることを意味している。アリストテレスは、家とは、財産の望ましい状態よりも人間の望ましい状態を維持するための存在だと説いたのである。」「一部のだれかを救済するのではない、可能なかぎり多くの人たちを家族のようにささえるということだ。」 「はげしい将来不安に直面するとき、人びとは痛みを分かちあい、連帯する道をえらぶ。」 「頼りあえる社会とは、税による痛みの分かちあいで財源を獲得し、ふたつの「生の保障」、つまりベーシック・サービスによる「尊厳ある生活保障」と、生活扶助と住手当による「品位ある命の保障」を徹底しておこなう枠組みだ。勤労国家という自己責任モデルを終わらせ、「保障の場」を鋳直そうという提案である。」 - 2025年11月8日
 万葉集の〈われ〉佐佐木幸綱「共感と言ってもいいが、もうすこしふみこんだ読みを考えた方がよさそうである。作者と読者はいわば共犯関係をむすぶのだ。そこでカギを握るのが多分<われ>の問題なのである。 啄木という作者<われ>に読者は自分を代入する。…… 一人称でありつつ、一方で『作者未詳』『詠み人知らず』でありうるのが短歌の本質なのである。融通無碍な<われ>である。開かれた<われ>である。おそらくこれは、日本人の<われ>観の機影をなすものであり、長い時代をかけて醸成してきた日本文化の特質をなすものなのだろう。……歌が個人的なものではなく、社会に共用されていた時代の名残である。……作者がだれなのかは問題ではない。歌は共有・共用のもの。作中の<われ>は発声するその人の意味であった。……作者よりもうたう人、発声する人が主役なのである。カラオケと同じで、作者は問題にされない。」 「7世紀から8世紀にかけて……その背景には中央集権国家の成立があり、都市社会の出現があった。従来の村落共同体と個人との関係とは異なった個人と社会の関係がうまれつつあった。我を知る人が誰もいない都市社会を生きる。全く知る者がいない遠い国へ国司として赴任する。…そこではだれも<われ>を知らない。<われ>のアイデンティティは、役職とか立場だけである。 「一方、近代もまた<われ>が意識化された時代だった。……藩のため家のために生きる<われ>ではない、<われ>は<われ>自身のために生きるのだ。大正時代早期になると私小説が興隆する。」 「私たち現代人は、行き過ぎた<われ>へのこだわりにとらえられているようだ。自我や個性にとらわれ、こだわって、不自由になっている。万葉集の<われ>を書きつづけつつ、いつもそのことを思っていた。
万葉集の〈われ〉佐佐木幸綱「共感と言ってもいいが、もうすこしふみこんだ読みを考えた方がよさそうである。作者と読者はいわば共犯関係をむすぶのだ。そこでカギを握るのが多分<われ>の問題なのである。 啄木という作者<われ>に読者は自分を代入する。…… 一人称でありつつ、一方で『作者未詳』『詠み人知らず』でありうるのが短歌の本質なのである。融通無碍な<われ>である。開かれた<われ>である。おそらくこれは、日本人の<われ>観の機影をなすものであり、長い時代をかけて醸成してきた日本文化の特質をなすものなのだろう。……歌が個人的なものではなく、社会に共用されていた時代の名残である。……作者がだれなのかは問題ではない。歌は共有・共用のもの。作中の<われ>は発声するその人の意味であった。……作者よりもうたう人、発声する人が主役なのである。カラオケと同じで、作者は問題にされない。」 「7世紀から8世紀にかけて……その背景には中央集権国家の成立があり、都市社会の出現があった。従来の村落共同体と個人との関係とは異なった個人と社会の関係がうまれつつあった。我を知る人が誰もいない都市社会を生きる。全く知る者がいない遠い国へ国司として赴任する。…そこではだれも<われ>を知らない。<われ>のアイデンティティは、役職とか立場だけである。 「一方、近代もまた<われ>が意識化された時代だった。……藩のため家のために生きる<われ>ではない、<われ>は<われ>自身のために生きるのだ。大正時代早期になると私小説が興隆する。」 「私たち現代人は、行き過ぎた<われ>へのこだわりにとらえられているようだ。自我や個性にとらわれ、こだわって、不自由になっている。万葉集の<われ>を書きつづけつつ、いつもそのことを思っていた。 - 2025年11月7日
 「いずれの場合でも、そこに人間の行為があって、行為の力がピラミッドをかたちづくる力とあらがいながら問題を噴出させ、『場』を『現場』に変える。」 「『現場』には、『他者』があまたいるゆえに、よほどしっかりと自分を持ちつづけていないと、それこそ『他者』にのみ込まれてしまうということがある。自主、自決がそこで要求されるのは当然のことだが、もうひとつ、『現場』には、さきに触れたことだが、人がそこにいっしょに何人いようと、「『現場』の壁にひとりでむきあっているようなところがある。」 「『現場』は大きく現在、過去、未来に時間的にも空間的にも開かれていると言うのだが、そうしたことのありようはふつう『場』には見られないことだ。」 「この『場』で、人は自分の存在のなかに閉じ込もることができる。たとえば、家庭の主婦は『主婦の座』に、会社員は『わが社の立』、日本人は『日本人の立場』に閉じ込もり、たてこもって、他者をすべて異分子として斥けることができる。『場』にいるのは自分ひとりだけで、たとえ、他者が万が一そこにいたとしても、それは異質の動きを示すものとしてあるのではないゆえに、『場』の一部だ。 『主婦の座』にたてこもる家庭の主婦にとって、彼女の子供は彼女の一部であって、独立した人格をそなえた他者ではない。『わが社の立場』、『日本人の立場』から見れば、わが社の人間、日本人だけがこの世界に生きる人間だろう。」 「私が日本語の『われわれ』ということばをガンチクのあることばだと思うのは、これほど個々におたがいが独立しながら、しかも結びついている『共生』のあるべき人間関係をみごとに言いあらわしていることばはないと考えるからだ。『われら」ということばが言いあらわす世界は閉じていて、自分たち以外の『他者』をきびしく咬別している感じだが、この『われ=われ』の関係のなかでは『他者』は『他者』でありつづけながら自分と結びついていて、『われ=われ」の世界は外にむかって大きく開かれた世界であるにちがいない。『われわれ」はそれを「われ=われ」ととらえるとき、そこで『われ=われ=われ=われ・・・・・・』というふうにつづいて行く連環のなかで考えて行くことができる。さっきからの例で言えば、黒人A、黒人B、黒人C・・・・・がそれぞれ自分の行為によって『われの現場』を持つことで、『われA"われB"われC"・・・・・」の連環をかたちづくれば、彼らに腕をさしのべる白人D、白人E、白人F.…・・・・&またそれぞれに『われの現場』を形成して、『われ"われの現場』の連環は『われAわれ BわれC"われD"われE"われF…・・・・』にまで拡大される。」
「いずれの場合でも、そこに人間の行為があって、行為の力がピラミッドをかたちづくる力とあらがいながら問題を噴出させ、『場』を『現場』に変える。」 「『現場』には、『他者』があまたいるゆえに、よほどしっかりと自分を持ちつづけていないと、それこそ『他者』にのみ込まれてしまうということがある。自主、自決がそこで要求されるのは当然のことだが、もうひとつ、『現場』には、さきに触れたことだが、人がそこにいっしょに何人いようと、「『現場』の壁にひとりでむきあっているようなところがある。」 「『現場』は大きく現在、過去、未来に時間的にも空間的にも開かれていると言うのだが、そうしたことのありようはふつう『場』には見られないことだ。」 「この『場』で、人は自分の存在のなかに閉じ込もることができる。たとえば、家庭の主婦は『主婦の座』に、会社員は『わが社の立』、日本人は『日本人の立場』に閉じ込もり、たてこもって、他者をすべて異分子として斥けることができる。『場』にいるのは自分ひとりだけで、たとえ、他者が万が一そこにいたとしても、それは異質の動きを示すものとしてあるのではないゆえに、『場』の一部だ。 『主婦の座』にたてこもる家庭の主婦にとって、彼女の子供は彼女の一部であって、独立した人格をそなえた他者ではない。『わが社の立場』、『日本人の立場』から見れば、わが社の人間、日本人だけがこの世界に生きる人間だろう。」 「私が日本語の『われわれ』ということばをガンチクのあることばだと思うのは、これほど個々におたがいが独立しながら、しかも結びついている『共生』のあるべき人間関係をみごとに言いあらわしていることばはないと考えるからだ。『われら」ということばが言いあらわす世界は閉じていて、自分たち以外の『他者』をきびしく咬別している感じだが、この『われ=われ』の関係のなかでは『他者』は『他者』でありつづけながら自分と結びついていて、『われ=われ」の世界は外にむかって大きく開かれた世界であるにちがいない。『われわれ」はそれを「われ=われ」ととらえるとき、そこで『われ=われ=われ=われ・・・・・・』というふうにつづいて行く連環のなかで考えて行くことができる。さっきからの例で言えば、黒人A、黒人B、黒人C・・・・・がそれぞれ自分の行為によって『われの現場』を持つことで、『われA"われB"われC"・・・・・」の連環をかたちづくれば、彼らに腕をさしのべる白人D、白人E、白人F.…・・・・&またそれぞれに『われの現場』を形成して、『われ"われの現場』の連環は『われAわれ BわれC"われD"われE"われF…・・・・』にまで拡大される。」 - 2025年11月6日
 物理学はいかに創られたか 上インフェルト,アインシュタイン,石原純「習慣によれば甘いものは甘く、苦いものは苦く、熱いものは熱く、冷たいものは冷たく、色づいたものは色づいています。しかし本当は原子と空虚とがあるだけです。すなわち感覚の対象を実在であると考えて、習慣的にそう認めてはいるが、真実ではそうではないので、ただ原子と空虚とが実在なのであります。」……「空間そのものが電磁波を伝える物理的性質をもっているということを事実として許すより外にはないので、しかもこの言葉の意味がどういうものであるかについて余り執拗に拘泥しないがよいということになるのです。」 …… 「科学的研究の結果はしばしば科学自体の局限された領域を遥かに超えて、問題の哲学的見解をも変えさせるようになることがあります。」……「哲学的に一旦完成されて広く受け容れられてしまうと、これが種々の可能な進歩の方向の中の一つを指定してしまうので、科学的思想のその後の発展にまで影響を及ぼすことになります。この認容されていた見解に対して反抗が成功すると、いつも予期しない、かつまるで異なった発展を起し、それがまた新しい哲学的見解の源となってゆきます。」……「新しい証拠、新しい事実及び理論のおかげでこれを放棄するのやむなきに至り、今度はそれらが科学の新しい背景を形づくるようになりました。」……「一見複雑な自然現象を、ある簡単な根本的な思想と関係とに帰着させようとする企てはギリシャ哲学から近代の物理学に至る科学の全歴史の上で絶えず続いて来ました。」……「過去の世紀の物理学者たちによって受け容れられたかような見解が、その後は廃れるようになったのですが、」…… 「たとえて言えば、新しい理論をつくるのは、古い納屋を取りこわして、その跡に摩天楼を建てるというのとは違います。それよりもむしろ、山に登ってゆくと、だんだんに新しい広々とした展望が開けて来て、最初の出発点からはまるで思いもよらなかった周囲のたくさんの眺めを見つけ出すというのと、よく似ています。」 …… 「場の実在性」(追記:物理学における「場」とは、空間の各点に物理量(値)が定まっている状態のことで、相互作用を記述するために使われます。例えば、磁石の周りの「磁場」や、電気量を持つ粒子の周りの「電場」は、空間全体にわたって「磁気的な力」や「電気的な力」が及んでいることを表しています。)
物理学はいかに創られたか 上インフェルト,アインシュタイン,石原純「習慣によれば甘いものは甘く、苦いものは苦く、熱いものは熱く、冷たいものは冷たく、色づいたものは色づいています。しかし本当は原子と空虚とがあるだけです。すなわち感覚の対象を実在であると考えて、習慣的にそう認めてはいるが、真実ではそうではないので、ただ原子と空虚とが実在なのであります。」……「空間そのものが電磁波を伝える物理的性質をもっているということを事実として許すより外にはないので、しかもこの言葉の意味がどういうものであるかについて余り執拗に拘泥しないがよいということになるのです。」 …… 「科学的研究の結果はしばしば科学自体の局限された領域を遥かに超えて、問題の哲学的見解をも変えさせるようになることがあります。」……「哲学的に一旦完成されて広く受け容れられてしまうと、これが種々の可能な進歩の方向の中の一つを指定してしまうので、科学的思想のその後の発展にまで影響を及ぼすことになります。この認容されていた見解に対して反抗が成功すると、いつも予期しない、かつまるで異なった発展を起し、それがまた新しい哲学的見解の源となってゆきます。」……「新しい証拠、新しい事実及び理論のおかげでこれを放棄するのやむなきに至り、今度はそれらが科学の新しい背景を形づくるようになりました。」……「一見複雑な自然現象を、ある簡単な根本的な思想と関係とに帰着させようとする企てはギリシャ哲学から近代の物理学に至る科学の全歴史の上で絶えず続いて来ました。」……「過去の世紀の物理学者たちによって受け容れられたかような見解が、その後は廃れるようになったのですが、」…… 「たとえて言えば、新しい理論をつくるのは、古い納屋を取りこわして、その跡に摩天楼を建てるというのとは違います。それよりもむしろ、山に登ってゆくと、だんだんに新しい広々とした展望が開けて来て、最初の出発点からはまるで思いもよらなかった周囲のたくさんの眺めを見つけ出すというのと、よく似ています。」 …… 「場の実在性」(追記:物理学における「場」とは、空間の各点に物理量(値)が定まっている状態のことで、相互作用を記述するために使われます。例えば、磁石の周りの「磁場」や、電気量を持つ粒子の周りの「電場」は、空間全体にわたって「磁気的な力」や「電気的な力」が及んでいることを表しています。) - 2025年10月19日
- 2025年10月1日
 古典力齋藤孝(教育学)「震災はこれからもまだ起こるだろう。低成長時代も続くことが予想される。しかし、この状況は、人類の歴史の中でそれほど絶望的なものではない。運命の理不尽さに対して、なんとか生き抜いてきた人類の精神のプロセスが、古典には詰まっている。 古典は全部読まなくても、一部をパラッとめくるだけでも、気持ちと視野を大きくしてくれる。 私たちの社会や人間性も歴史的な達成であり、まだ途上だということを教えてくれる。死を意識しつつも、暗くならず、前を向いて生きていく力を古典は与えてくれる。」
古典力齋藤孝(教育学)「震災はこれからもまだ起こるだろう。低成長時代も続くことが予想される。しかし、この状況は、人類の歴史の中でそれほど絶望的なものではない。運命の理不尽さに対して、なんとか生き抜いてきた人類の精神のプロセスが、古典には詰まっている。 古典は全部読まなくても、一部をパラッとめくるだけでも、気持ちと視野を大きくしてくれる。 私たちの社会や人間性も歴史的な達成であり、まだ途上だということを教えてくれる。死を意識しつつも、暗くならず、前を向いて生きていく力を古典は与えてくれる。」 - 2025年9月28日
- 2025年9月15日
 都市計画: 利権の構図を超えて五十嵐敬喜,小川明雄「(中野区吉田事件 東京地方裁判所 1978.9.21)『近隣住民の意思を考慮することなく建築行政を行うことはもはや不可能であり、建築確認制度のみでは対処できないこれらの問題を事実に即して妥当な解決をすることが建築行政上関係地方公共団体に強く求められ、かつ重要な機能を果している』」 「世田谷区の『住宅条例』は、まず区は『すべての区民が、地域の個性を生かした魅力的なまちづくりを進めつつ、良好な住生活を主体的に営むことができる権利を有することを確認し、その充実を図ることを、住宅及び住環境の維持及び向上についての基本理念とする』とうたい、区民が良好な住宅を持つことは権利だと述べている。」 「裁判においても、市町村の行政指導よりも、議会の議決、つまり全住民の意志によって決められる条例の方が、『正当性』をより強くもっている。」 「ひるがえって考えてみれば、都市の問題に限ってもこれだけ多数の要綱と条例ができていることは、もはや『国家高権論』による全国画一の都市法の体系が限界をこえていることを証明している。」 「共同案によれば、土地所有権は、はじめから『絶対的』なものとしてあるのではなく、その利用方法をマスタープランづくりなどを通じて、住民がみんなで決めていくのだということになる。そのプロセスのなかで、新しい所有権が生まれる。これは『絶対的』にたいしては、『相対的』ということになる。もっといえば、住民みんなで利用方法を決めてはじめて、その土地を利用できる、つまりその段階で土地所有権が生まれるといえる。つまり、欧米なみの『計画なければ開発なし』という『建築不自由』を原則とした所有権に変わるわけである。 本来の都市計画を無視してきた日本では、建築不自由の原則といえば、『損するのではないか』という誤解をあたえるおそれがある。しかし、これまで述べてきたように、建築の自由、言葉をかえれば、緩い規制を緩めに緩めて何を建ててもいいという原則をとってきたために、住宅地に中高層ビルが建ち、地価の高騰を繰り返し、住民は追い出されるという構造ができてしまった。」
都市計画: 利権の構図を超えて五十嵐敬喜,小川明雄「(中野区吉田事件 東京地方裁判所 1978.9.21)『近隣住民の意思を考慮することなく建築行政を行うことはもはや不可能であり、建築確認制度のみでは対処できないこれらの問題を事実に即して妥当な解決をすることが建築行政上関係地方公共団体に強く求められ、かつ重要な機能を果している』」 「世田谷区の『住宅条例』は、まず区は『すべての区民が、地域の個性を生かした魅力的なまちづくりを進めつつ、良好な住生活を主体的に営むことができる権利を有することを確認し、その充実を図ることを、住宅及び住環境の維持及び向上についての基本理念とする』とうたい、区民が良好な住宅を持つことは権利だと述べている。」 「裁判においても、市町村の行政指導よりも、議会の議決、つまり全住民の意志によって決められる条例の方が、『正当性』をより強くもっている。」 「ひるがえって考えてみれば、都市の問題に限ってもこれだけ多数の要綱と条例ができていることは、もはや『国家高権論』による全国画一の都市法の体系が限界をこえていることを証明している。」 「共同案によれば、土地所有権は、はじめから『絶対的』なものとしてあるのではなく、その利用方法をマスタープランづくりなどを通じて、住民がみんなで決めていくのだということになる。そのプロセスのなかで、新しい所有権が生まれる。これは『絶対的』にたいしては、『相対的』ということになる。もっといえば、住民みんなで利用方法を決めてはじめて、その土地を利用できる、つまりその段階で土地所有権が生まれるといえる。つまり、欧米なみの『計画なければ開発なし』という『建築不自由』を原則とした所有権に変わるわけである。 本来の都市計画を無視してきた日本では、建築不自由の原則といえば、『損するのではないか』という誤解をあたえるおそれがある。しかし、これまで述べてきたように、建築の自由、言葉をかえれば、緩い規制を緩めに緩めて何を建ててもいいという原則をとってきたために、住宅地に中高層ビルが建ち、地価の高騰を繰り返し、住民は追い出されるという構造ができてしまった。」 - 2025年9月15日
 「私たちの研究室にあるサイトカインの遺伝子破壊マウスに脳梗塞を実験的に起こさせたところ、ある種のサイトカインがないと脳梗塞がひどくならないことがわかりました。それがIL-1B、IL-23とIL-17でした。」 「脳梗塞という脳組織の損傷という外科的な現象にも、それが悪化したり収束したりする過程で自然免疫と獲得免疫が重要な役割を演じていることが明らかになってきました。しかも、脳という非常に特殊な環境のせいかもしれませんが、脳梗塞やアルツハイマー病など脳内で起きる病気で使われる免疫細胞や免疫分子にはほかの臓器とは異なる特殊性があることもわかります。 脳の免疫にはまだまだ知られざる大きな可能性が秘められています。」
「私たちの研究室にあるサイトカインの遺伝子破壊マウスに脳梗塞を実験的に起こさせたところ、ある種のサイトカインがないと脳梗塞がひどくならないことがわかりました。それがIL-1B、IL-23とIL-17でした。」 「脳梗塞という脳組織の損傷という外科的な現象にも、それが悪化したり収束したりする過程で自然免疫と獲得免疫が重要な役割を演じていることが明らかになってきました。しかも、脳という非常に特殊な環境のせいかもしれませんが、脳梗塞やアルツハイマー病など脳内で起きる病気で使われる免疫細胞や免疫分子にはほかの臓器とは異なる特殊性があることもわかります。 脳の免疫にはまだまだ知られざる大きな可能性が秘められています。」 - 2025年9月15日
 国際人権入門申惠丰「法改正により、女性だけでなく、男性が強制性交の被害者になる場合もカバーされた」 (学費に関して、奨学金利用者の平均では)「大学卒業生の平均借り入れ額は324.3万円にもなる」 (社会権規約委員会)「締約国が、権利の実現にとって、交代的な措置を取るとすればそれは社会権規約の趣旨に反することになる」
国際人権入門申惠丰「法改正により、女性だけでなく、男性が強制性交の被害者になる場合もカバーされた」 (学費に関して、奨学金利用者の平均では)「大学卒業生の平均借り入れ額は324.3万円にもなる」 (社会権規約委員会)「締約国が、権利の実現にとって、交代的な措置を取るとすればそれは社会権規約の趣旨に反することになる」 - 2025年8月25日
 平静の祈りあきた・のぶこ,やすたか・としまさ,Elizabeth Sifton「何年かのちに、その頃まだ出来て十年にもならない小さな団体だったアルコホーリクス・アノニマス(AA〕も、わたしの父から許可を得て、その小さい祈りを定例会で使い始めた。 AAがいつどのようにして本文を簡略化したかをわたしは知らない。もしかすると最初から、ああだったのかもしれない。その版では、祈りは一人称単数、そして頭の部分が略されている。霊的には正しくても簡単ではない、変えられないことを平静に受け入れる恵み[grace to accept with serenity that which we camnot change ]を求めて祈る(praying for)という思想を省き、そのかわり変えられないことを受け入れる平静さ(serenity to accept what camnot bechanged)を得る[obtaining ]というもと単純な思想に焦点が絞られている。表現が変わったときに、わたしの父は好きにさせ、とやかく言わなかったが、気にはしていた。最終的にふたつの文章の間には大きな違いが数か所ある。 より重大なのはもうひとつの変更だ。二節目の変えるべきことを変える勇気 [courage to change what should be changed]がAAの表現では、単に変えられることを変える夢気[courage to change what can be changed ]となっている。 これには呆れる。何かを変えられるということが、それを変えるべきだ、に直結しはしない。そしてこの表現では、責務とする範囲が狭まる点がさらに重大である。変えられることを変える(to change what we can change)のでわたしたちがある時点でなんとか変えられそうだと思ったことしか指さない。しかし、変えるための力がわたしたちに足りないとしても、変えるべき(should be changed )状況は存在し、そういうときにこそ、この祈りが最も必要とされるのである。本文のこの変更は、難しいが強い思想を、陳腐で弱いものに引き下げている。こう薄めたことがこの祈りの一般受けにつながったのではないかと、わたしは思っている。 オリジナルの三部分からなる祈りに対してAAが付け加えた文節が、どこから来たのかはまったくわからないが、ともかくその内容と調子とはまったくニーバー的でない。しかし、わたしの父は自分の祈りに著作権をとるようなことを一度もしなかったから -ー祈りで儲けるなど彼には考えられなかったーー 不正確な引用や、著作者の誤認や、潤色があっても彼には対処できなかった。今までに本当に数え切れない人が、お父さんはこの件でしくじりましたねと、わたしにからかい半分、何の悪気もなく忠告してくれた。いかにもアメリカ人らしい、恥ずべきでない考えなのだろう。人が何らかの価値ある行為をしたら、それでお金を儲けるべきで、もしそうできたにもかかわらずやり損なったときは、膝を叩いて大笑いするのである。金の子牛を拝むことは疑う余地なき規範なのだ。
平静の祈りあきた・のぶこ,やすたか・としまさ,Elizabeth Sifton「何年かのちに、その頃まだ出来て十年にもならない小さな団体だったアルコホーリクス・アノニマス(AA〕も、わたしの父から許可を得て、その小さい祈りを定例会で使い始めた。 AAがいつどのようにして本文を簡略化したかをわたしは知らない。もしかすると最初から、ああだったのかもしれない。その版では、祈りは一人称単数、そして頭の部分が略されている。霊的には正しくても簡単ではない、変えられないことを平静に受け入れる恵み[grace to accept with serenity that which we camnot change ]を求めて祈る(praying for)という思想を省き、そのかわり変えられないことを受け入れる平静さ(serenity to accept what camnot bechanged)を得る[obtaining ]というもと単純な思想に焦点が絞られている。表現が変わったときに、わたしの父は好きにさせ、とやかく言わなかったが、気にはしていた。最終的にふたつの文章の間には大きな違いが数か所ある。 より重大なのはもうひとつの変更だ。二節目の変えるべきことを変える勇気 [courage to change what should be changed]がAAの表現では、単に変えられることを変える夢気[courage to change what can be changed ]となっている。 これには呆れる。何かを変えられるということが、それを変えるべきだ、に直結しはしない。そしてこの表現では、責務とする範囲が狭まる点がさらに重大である。変えられることを変える(to change what we can change)のでわたしたちがある時点でなんとか変えられそうだと思ったことしか指さない。しかし、変えるための力がわたしたちに足りないとしても、変えるべき(should be changed )状況は存在し、そういうときにこそ、この祈りが最も必要とされるのである。本文のこの変更は、難しいが強い思想を、陳腐で弱いものに引き下げている。こう薄めたことがこの祈りの一般受けにつながったのではないかと、わたしは思っている。 オリジナルの三部分からなる祈りに対してAAが付け加えた文節が、どこから来たのかはまったくわからないが、ともかくその内容と調子とはまったくニーバー的でない。しかし、わたしの父は自分の祈りに著作権をとるようなことを一度もしなかったから -ー祈りで儲けるなど彼には考えられなかったーー 不正確な引用や、著作者の誤認や、潤色があっても彼には対処できなかった。今までに本当に数え切れない人が、お父さんはこの件でしくじりましたねと、わたしにからかい半分、何の悪気もなく忠告してくれた。いかにもアメリカ人らしい、恥ずべきでない考えなのだろう。人が何らかの価値ある行為をしたら、それでお金を儲けるべきで、もしそうできたにもかかわらずやり損なったときは、膝を叩いて大笑いするのである。金の子牛を拝むことは疑う余地なき規範なのだ。 - 2025年8月25日
 @ 中野区「謝罪の時期は、たいてい捜査段階である。早期に謝罪をしておかなければ家族の仕事への影響も長期化することから、捜査が進行するまで沈黙は許されず、無罪推定の原則は無視されている。 親の責任とは何なのか。少年事件の保護者は、事件によって損害賠償責任を負うケースもあるが、法的責任を負う相手は被害者やその家族など損害を与えた人々に限定され、支払いの完了によって終了する。保護者が悩むのは、親としての『道義的責任』であり、少年の更生に対する責任は被害者のみならず迷惑をかけた社会に対しても負いうると考える傾向がある。 事件が起きた原因が家庭にあったとして、具体的に家庭の何が問題だったのかは事件を丁寧に見ていかなければ導くことはできず、捜査段階ですぐに判明するわけではなく家族との長期的な関わりが必要となる。 加害者家族は、曖昧な存在である『世間』からの終わりの見えない制裁に怯え悩まされている。支援者は、当該事件の加害者家族が背負いうる責任について、誰に対していつまでにどのような責任を負うのか、事件の進捗状況を見ながら明確にしていく必要がある。」 「日本では子がいつくになろうと親の責任が免責されることはない。親の責任を突き詰めた結果、世間が我が子を憎むならば、手にかけなければならないという発想が生まれている。しかし、子どもは親の所有物ではなく、親に子どもを殺す権利などないのである。 親であれば、永遠に子どもの行動に責任を持たなければならないという考えは、子どもの権利が確立していないことの証でもある」 「保護者には『原因として家族』と『抑止要因・更生の場としての家族』の2つの側面……に加えて『被害者としての家族』という側面もある。………保護者が罪を犯したわけではなく、決して子どもを犯罪者として育てたわけでもない。事件によって加害者家族もついており、重要なことはその傷を癒すことである。」 「たとえ非行少年を虐待してきた親であったとしても、その親自身が虐待などの手ひどい扱いを受けてきた被害者であったことは稀というよりも、むしろ一般的と言えることが明らかになっている現在では、上で挙げたような、非行少年の非行の責任は親にあるという単純な見方を採ることは妥当ではない。むしろ、非行少年の保護者も、非行少年ともども支援を必要としている者と位置づけられるべきように思われる。」 「少年B(17歳)は、13歳以下の男児への強制わいせつにより少年院送致となった。……筆者はBの両親と面談を重ね、今後のBの将来設計はBに任せ、可能な限り応援してほしい旨を広えた。医師や弁護士も合めてBの更生に関わった地域の人々がセクシュアリティに関して誤った認識を持っており、Bを追いつめていた事実に衝撃を受けた。こうした地域の人々の偏見もまた事件の要因となっている側面は否めなかった。 このような環境下でBを更生させることは非常に困難である。」 「家族会への参加を重ね、『語り』を繰り返すうちに家族たちは落ち着き、日常を取り戻して行く。それは何よりも自分自身を取り戻しているかのようである。冗談を言えるようにもなるし、希望を含んだ話をする人もいる。もちろん時間の経過とともに事件当初のショック状態から脱しているという事情もある。こうして地域や職場といった『理解してもらえなかったコミュニティ』から隔離し、安心して『話すこと』と『泣くこと』に『仕切られた』コミュニティに身を置くことによって、参加者はまた現実の日常に戻ることができている。」 「加害者家族に優しい「世間」に変わる日を信じたい。」
@ 中野区「謝罪の時期は、たいてい捜査段階である。早期に謝罪をしておかなければ家族の仕事への影響も長期化することから、捜査が進行するまで沈黙は許されず、無罪推定の原則は無視されている。 親の責任とは何なのか。少年事件の保護者は、事件によって損害賠償責任を負うケースもあるが、法的責任を負う相手は被害者やその家族など損害を与えた人々に限定され、支払いの完了によって終了する。保護者が悩むのは、親としての『道義的責任』であり、少年の更生に対する責任は被害者のみならず迷惑をかけた社会に対しても負いうると考える傾向がある。 事件が起きた原因が家庭にあったとして、具体的に家庭の何が問題だったのかは事件を丁寧に見ていかなければ導くことはできず、捜査段階ですぐに判明するわけではなく家族との長期的な関わりが必要となる。 加害者家族は、曖昧な存在である『世間』からの終わりの見えない制裁に怯え悩まされている。支援者は、当該事件の加害者家族が背負いうる責任について、誰に対していつまでにどのような責任を負うのか、事件の進捗状況を見ながら明確にしていく必要がある。」 「日本では子がいつくになろうと親の責任が免責されることはない。親の責任を突き詰めた結果、世間が我が子を憎むならば、手にかけなければならないという発想が生まれている。しかし、子どもは親の所有物ではなく、親に子どもを殺す権利などないのである。 親であれば、永遠に子どもの行動に責任を持たなければならないという考えは、子どもの権利が確立していないことの証でもある」 「保護者には『原因として家族』と『抑止要因・更生の場としての家族』の2つの側面……に加えて『被害者としての家族』という側面もある。………保護者が罪を犯したわけではなく、決して子どもを犯罪者として育てたわけでもない。事件によって加害者家族もついており、重要なことはその傷を癒すことである。」 「たとえ非行少年を虐待してきた親であったとしても、その親自身が虐待などの手ひどい扱いを受けてきた被害者であったことは稀というよりも、むしろ一般的と言えることが明らかになっている現在では、上で挙げたような、非行少年の非行の責任は親にあるという単純な見方を採ることは妥当ではない。むしろ、非行少年の保護者も、非行少年ともども支援を必要としている者と位置づけられるべきように思われる。」 「少年B(17歳)は、13歳以下の男児への強制わいせつにより少年院送致となった。……筆者はBの両親と面談を重ね、今後のBの将来設計はBに任せ、可能な限り応援してほしい旨を広えた。医師や弁護士も合めてBの更生に関わった地域の人々がセクシュアリティに関して誤った認識を持っており、Bを追いつめていた事実に衝撃を受けた。こうした地域の人々の偏見もまた事件の要因となっている側面は否めなかった。 このような環境下でBを更生させることは非常に困難である。」 「家族会への参加を重ね、『語り』を繰り返すうちに家族たちは落ち着き、日常を取り戻して行く。それは何よりも自分自身を取り戻しているかのようである。冗談を言えるようにもなるし、希望を含んだ話をする人もいる。もちろん時間の経過とともに事件当初のショック状態から脱しているという事情もある。こうして地域や職場といった『理解してもらえなかったコミュニティ』から隔離し、安心して『話すこと』と『泣くこと』に『仕切られた』コミュニティに身を置くことによって、参加者はまた現実の日常に戻ることができている。」 「加害者家族に優しい「世間」に変わる日を信じたい。」 - 2025年8月23日
 学問と世間阿部謹也「十八世紀以降産業化が進められ、経営と家計が分離されると、」 「教養というものが『いかに生きるか』という問いに対する自らの答えであったとすると、文字などはそのひとつの手段ではあっても、すべてではないことが明らかとなる。」 「教養とは自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のために何ができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状態であると。このように教養のある人を定義すると、これまでの教養概念のように知識人だけでなく、農民や漁民、手工業者たちも含まれることになる。これまでは教養のある人というと、学歴の高い人、ブルーカラーでない人、書物などに通じている人といったイメージがあり、時には人格高潔といった言葉さえ出かねない。しかし先ほどのような定義をすれば、さまざまな人が対象になる。農民や漁民、手工業者その他の職業の人には立派な方が数多くおられ、それらの人を除外した従来の教養概念は極めて偏狭なものといわねばならない。」 「西欧ですでに個人との関係が確立されていたから、個人の意志が結集されれば社会を変えることができるという道筋は示されていた。しかし『世間』については、そのような道筋は全く示されたことがなく、『世間』は天から与えられたもののごとく個人の意志ではどうにもならないものと受けとめられていた。」 「大きな騒ぎになっている。排斥運動をしている人々は、人権という言葉や法律という言葉にも反感を示す場合がある。 論理ではなく、感情の次元での反発となっている場合が見られる。そこに働いているのは『世間』の感情なのである。」 「最近の政局のきしみに見られるものも『世間』の動きである。わが国の政治は『世間』の動きを見なければ理解できない。派閥の動静などは『世間』の典型というべきものである。」
学問と世間阿部謹也「十八世紀以降産業化が進められ、経営と家計が分離されると、」 「教養というものが『いかに生きるか』という問いに対する自らの答えであったとすると、文字などはそのひとつの手段ではあっても、すべてではないことが明らかとなる。」 「教養とは自分が社会の中でどのような位置にあり、社会のために何ができるかを知っている状態、あるいはそれを知ろうと努力している状態であると。このように教養のある人を定義すると、これまでの教養概念のように知識人だけでなく、農民や漁民、手工業者たちも含まれることになる。これまでは教養のある人というと、学歴の高い人、ブルーカラーでない人、書物などに通じている人といったイメージがあり、時には人格高潔といった言葉さえ出かねない。しかし先ほどのような定義をすれば、さまざまな人が対象になる。農民や漁民、手工業者その他の職業の人には立派な方が数多くおられ、それらの人を除外した従来の教養概念は極めて偏狭なものといわねばならない。」 「西欧ですでに個人との関係が確立されていたから、個人の意志が結集されれば社会を変えることができるという道筋は示されていた。しかし『世間』については、そのような道筋は全く示されたことがなく、『世間』は天から与えられたもののごとく個人の意志ではどうにもならないものと受けとめられていた。」 「大きな騒ぎになっている。排斥運動をしている人々は、人権という言葉や法律という言葉にも反感を示す場合がある。 論理ではなく、感情の次元での反発となっている場合が見られる。そこに働いているのは『世間』の感情なのである。」 「最近の政局のきしみに見られるものも『世間』の動きである。わが国の政治は『世間』の動きを見なければ理解できない。派閥の動静などは『世間』の典型というべきものである。」 - 2025年8月22日
 人生論・愛について武者小路実篤※この本はまだ読めていませんが、内容的に近い「人生読本(現代教養文庫101 , 1953年, 武者小路実篤著)」を読んだ。以下は全て「人生読本」についてである。 「我らの一番尊敬する人間は、我等に得さしてくれる人間ではなく、損さしても我等の内の人類的本能を生かしてくれた人である」 「人類の生長しようとする意志に反した言行は全て悪であり、人類の成長しようとする意志にすなほな言行は善になるのだと思ふ。……善は、意識された行動で、無心の行動には美と云う方が自然のやうに思ふ。」 「金の害はすべての人間の欲望を無際限に大きくする力をもつてゐるから、同時にその欲望の満たされない不満、不服、不平の感じを人に起こさせやすい。」 「東京の大地震の時でもかう云う時でなければ人は切れないと云って、日本人を切った日本人もあつたことを聞いた。…猛獣などと戦ふ時、殺伐な本能が人間に与えられてゐなければならないのは事実である。人間の本能は完全なものではなく病的に発展し得べき性質を持ってゐる」 「色欲は人間に大事なものにかかわらず、罪悪視されやすい。…人間を愛するものは色欲は尊敬せねばならない。しかし……制裁されないではどんなことになるかわからないほど、自然は我らに子供をつくる以上すぎる程に多量の色欲を与えている。……色を好むが如く徳を愛する者がいたらいいと思ふ孔子は、又色欲の強さを知ってゐたと言える」
人生論・愛について武者小路実篤※この本はまだ読めていませんが、内容的に近い「人生読本(現代教養文庫101 , 1953年, 武者小路実篤著)」を読んだ。以下は全て「人生読本」についてである。 「我らの一番尊敬する人間は、我等に得さしてくれる人間ではなく、損さしても我等の内の人類的本能を生かしてくれた人である」 「人類の生長しようとする意志に反した言行は全て悪であり、人類の成長しようとする意志にすなほな言行は善になるのだと思ふ。……善は、意識された行動で、無心の行動には美と云う方が自然のやうに思ふ。」 「金の害はすべての人間の欲望を無際限に大きくする力をもつてゐるから、同時にその欲望の満たされない不満、不服、不平の感じを人に起こさせやすい。」 「東京の大地震の時でもかう云う時でなければ人は切れないと云って、日本人を切った日本人もあつたことを聞いた。…猛獣などと戦ふ時、殺伐な本能が人間に与えられてゐなければならないのは事実である。人間の本能は完全なものではなく病的に発展し得べき性質を持ってゐる」 「色欲は人間に大事なものにかかわらず、罪悪視されやすい。…人間を愛するものは色欲は尊敬せねばならない。しかし……制裁されないではどんなことになるかわからないほど、自然は我らに子供をつくる以上すぎる程に多量の色欲を与えている。……色を好むが如く徳を愛する者がいたらいいと思ふ孔子は、又色欲の強さを知ってゐたと言える」 - 2025年8月21日
 道教思想10講神塚淑子「一には、不忠不孝、不仁不信であってはいけない。君親に尽くし、万物に対して誠を尽くすべきである。 二には、人の婦女を姪犯せず。 三には、義に非ざるの財を盗み取らず。 四には、敷きて善悪論(善悪正反対の議論)せず。 五には、酔わず、常に浄行を思う。 六には、宗親和睦し、親(親族)を非ること有る無し。 七には、人の善事を見れば、心に助して(自分も同じように)歓喜す。 八には、人の憂い有るを見れば、助けて為に福を伴す。 九には、彼来たりて我に加うるも(相手の方から私に危害を加えても)、志は報いざるに在り。 十には、一切未だ道を得ざれば、我は望みを有せず。(十戒)」 「民であっても、内に修めた徳が、家族から始まって次第にその及ぼす範囲を広げて多くの人々を感化する。まして、天子が……」 「小国宴民」 「天下統治の仕事は完成し、大きな事業は成し遂げられて、しかも人民たちは皆、私はひとりでにこうなったと言う、そんな統治こそが最高の統治であるというのが、『老子』の考え方である。」
道教思想10講神塚淑子「一には、不忠不孝、不仁不信であってはいけない。君親に尽くし、万物に対して誠を尽くすべきである。 二には、人の婦女を姪犯せず。 三には、義に非ざるの財を盗み取らず。 四には、敷きて善悪論(善悪正反対の議論)せず。 五には、酔わず、常に浄行を思う。 六には、宗親和睦し、親(親族)を非ること有る無し。 七には、人の善事を見れば、心に助して(自分も同じように)歓喜す。 八には、人の憂い有るを見れば、助けて為に福を伴す。 九には、彼来たりて我に加うるも(相手の方から私に危害を加えても)、志は報いざるに在り。 十には、一切未だ道を得ざれば、我は望みを有せず。(十戒)」 「民であっても、内に修めた徳が、家族から始まって次第にその及ぼす範囲を広げて多くの人々を感化する。まして、天子が……」 「小国宴民」 「天下統治の仕事は完成し、大きな事業は成し遂げられて、しかも人民たちは皆、私はひとりでにこうなったと言う、そんな統治こそが最高の統治であるというのが、『老子』の考え方である。」 - 2025年8月11日
 民俗学入門 (岩波新書)菊地暁「『生き物の時間』と『資本の時間』、2つの時間の分裂に、ヒトは『中途半端に賢い生き物』として、迷い続けるほかない。これが、私たちの現在を取り巻く根本問題なのだ。」 「伝統と、近代が拮抗する様子を描いた。『北白川こども風土記』(山口書店、1959)という作品がある。これは、1946年生まれの戦後の子たちが、小学校の課外学習で地域を調べあげたもので、世間の耳目を集めた映画化までされている。この作品を改めて見直すと、混住によりハイブリッド化する地域にあって、ネイティブとニューカマー(の師弟)が協力しあって、地域コミュニティーを再発見しようとする試みだった、ということができる。そしてそれは程度の差こそ、あれ、近代化するムラ/マチの多くが直面する課題でもあった。」
民俗学入門 (岩波新書)菊地暁「『生き物の時間』と『資本の時間』、2つの時間の分裂に、ヒトは『中途半端に賢い生き物』として、迷い続けるほかない。これが、私たちの現在を取り巻く根本問題なのだ。」 「伝統と、近代が拮抗する様子を描いた。『北白川こども風土記』(山口書店、1959)という作品がある。これは、1946年生まれの戦後の子たちが、小学校の課外学習で地域を調べあげたもので、世間の耳目を集めた映画化までされている。この作品を改めて見直すと、混住によりハイブリッド化する地域にあって、ネイティブとニューカマー(の師弟)が協力しあって、地域コミュニティーを再発見しようとする試みだった、ということができる。そしてそれは程度の差こそ、あれ、近代化するムラ/マチの多くが直面する課題でもあった。」
読み込み中...