にょろぞう
@kofun_nameko55
書庫を求めて三千里
- 2025年10月9日
 日本の絶滅危惧知識吉川さやか気になる
日本の絶滅危惧知識吉川さやか気になる - 2025年10月9日
 銀座「四宝堂」文房具店上田健次気になる
銀座「四宝堂」文房具店上田健次気になる - 2025年10月9日
- 2025年7月19日
 変な絵雨穴借りてきたかつて読んだ絵は精神を表すという冒頭に始まり、どこか不気味な絵にまつわるオムニバス小説。 前作に思うところがあったので期待半分で読んだが、記事部分の気持ち悪ささそのままに面白かった。この方の真骨頂は人怖だと思う。 個人的には最後のアゲはなくても良かった。 あと巷に流れる栗原最強説。
変な絵雨穴借りてきたかつて読んだ絵は精神を表すという冒頭に始まり、どこか不気味な絵にまつわるオムニバス小説。 前作に思うところがあったので期待半分で読んだが、記事部分の気持ち悪ささそのままに面白かった。この方の真骨頂は人怖だと思う。 個人的には最後のアゲはなくても良かった。 あと巷に流れる栗原最強説。 - 2025年7月11日
- 2025年7月11日
 水俣病原田正純借りてきたかつて読んだ前回読んだ『日本のアジール〜』を受けて手に取った本。教科書でしか知らない事柄の行間を知りたくなった。 数奇な巡り合わせから水俣病の全てを見届けることになった医者の本。 終始感じられる加害者への怒りには納得の一言。 それとは別に被害者の方を含む登場人物たちの行動には考えさせられるものがあった。 ずっと共に在ったものを突然高名なだけの人に否定された時、果たして自分は簡単にそれを捨てられるだろうか。
水俣病原田正純借りてきたかつて読んだ前回読んだ『日本のアジール〜』を受けて手に取った本。教科書でしか知らない事柄の行間を知りたくなった。 数奇な巡り合わせから水俣病の全てを見届けることになった医者の本。 終始感じられる加害者への怒りには納得の一言。 それとは別に被害者の方を含む登場人物たちの行動には考えさせられるものがあった。 ずっと共に在ったものを突然高名なだけの人に否定された時、果たして自分は簡単にそれを捨てられるだろうか。 - 2025年7月11日
- 2025年7月6日
- 2025年7月6日
- 2025年7月6日
- 2025年5月30日
 一次元の挿し木松下龍之介買ったかつて読んだXで大絶賛されているのを見かけて買った。 タイトルと序章部分でオチが読めたせいか、私には刺さらなかった。 読んでて目が滑るようなことはなくて良かった。 個人的には主人公が全てを兼ね備えすぎてて感情移入が難しかったなと思った。 上記の理由があるからかもしれないが、ミステリーというよりはホラーの心持ちで読みたかった。
一次元の挿し木松下龍之介買ったかつて読んだXで大絶賛されているのを見かけて買った。 タイトルと序章部分でオチが読めたせいか、私には刺さらなかった。 読んでて目が滑るようなことはなくて良かった。 個人的には主人公が全てを兼ね備えすぎてて感情移入が難しかったなと思った。 上記の理由があるからかもしれないが、ミステリーというよりはホラーの心持ちで読みたかった。 - 2025年1月28日
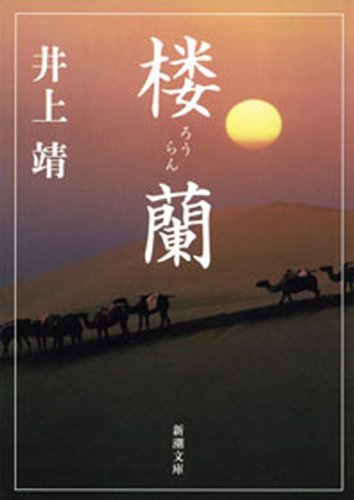 楼蘭井上靖借りてきたかつて読んだ補陀落渡海のことを知りたくなり、紙の書籍を借りた。友人ありがとう 触れれば崩れそうなほどの歴史を感じさせる見た目だった。1968年出版ならそりゃそう。 表題含めた全12話の短編集。 補陀落渡海もさることながら、どの話も人ひとり(或いは一般国民)ではどうすることもできないような運命のようなものに翻弄され、飲み込まれていく無常感は言葉に出来ない。読了後は必ず上の方を向いて目を瞑ってうめいてた。 確か昔の小説を読む抵抗感を薄れさせてくれた作品。読んで良かった。 借りるギリギリまであの教科書に載ってた井上ひさしと勘違いしていたのは秘密。
楼蘭井上靖借りてきたかつて読んだ補陀落渡海のことを知りたくなり、紙の書籍を借りた。友人ありがとう 触れれば崩れそうなほどの歴史を感じさせる見た目だった。1968年出版ならそりゃそう。 表題含めた全12話の短編集。 補陀落渡海もさることながら、どの話も人ひとり(或いは一般国民)ではどうすることもできないような運命のようなものに翻弄され、飲み込まれていく無常感は言葉に出来ない。読了後は必ず上の方を向いて目を瞑ってうめいてた。 確か昔の小説を読む抵抗感を薄れさせてくれた作品。読んで良かった。 借りるギリギリまであの教科書に載ってた井上ひさしと勘違いしていたのは秘密。 - 2025年1月18日
 みんなの民俗学(960;960)島村恭則借りてきたかつて読んだ元々興味のあった民俗学に加えてアマビエを取り上げていると聞いて借りてみた。 人の営みの隣にはいつでも民俗学がいるのだとわかるとても良い本だった。 中盤は空腹の時には読まない方がいいと思う。 調査ジャンルごとにいくつかの章に分かれているのだけれど、 大勢の人が一度なら触れたことがあるのでは?みたいなジャンルを丁寧に取り上げているから、この本を読んで民俗学を身近に感じない人はいないんじゃないかと思える本だった。 数多ある学問への誘い本の中でもトップクラスにやさしい本。
みんなの民俗学(960;960)島村恭則借りてきたかつて読んだ元々興味のあった民俗学に加えてアマビエを取り上げていると聞いて借りてみた。 人の営みの隣にはいつでも民俗学がいるのだとわかるとても良い本だった。 中盤は空腹の時には読まない方がいいと思う。 調査ジャンルごとにいくつかの章に分かれているのだけれど、 大勢の人が一度なら触れたことがあるのでは?みたいなジャンルを丁寧に取り上げているから、この本を読んで民俗学を身近に感じない人はいないんじゃないかと思える本だった。 数多ある学問への誘い本の中でもトップクラスにやさしい本。 - 2025年1月13日
- 1900年1月1日
 罪と罰 上ドストエフスキー,F.M.,江川卓気になる
罪と罰 上ドストエフスキー,F.M.,江川卓気になる - 1900年1月1日
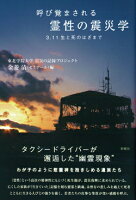 呼び覚まされる霊性の震災学東北学院大学,金菱清かつて読んだ今こそかなと 東北学院大学のゼミ生が震災死にまつわる出来事を各々調査、報告したレポートが一冊にまとまった本。 様々な側面で難しい題材に対して、若さもありつつ真摯に向き合っていたレポートが多かったと記憶している。 葬儀は実は生者のためにある、生者側の未練を断ち切るための儀だと聞いたことがあるが、そのことが何度も頭を過ぎるような一冊だった。
呼び覚まされる霊性の震災学東北学院大学,金菱清かつて読んだ今こそかなと 東北学院大学のゼミ生が震災死にまつわる出来事を各々調査、報告したレポートが一冊にまとまった本。 様々な側面で難しい題材に対して、若さもありつつ真摯に向き合っていたレポートが多かったと記憶している。 葬儀は実は生者のためにある、生者側の未練を断ち切るための儀だと聞いたことがあるが、そのことが何度も頭を過ぎるような一冊だった。 - 1900年1月1日
- 1900年1月1日
 青木世界観尾崎世界観,青木宣親気になる
青木世界観尾崎世界観,青木宣親気になる
読み込み中...








