

もくず
@mokuzuuu
本を読むことを頑張る💪
癒し系の小説と乙女向けラノベとゴリゴリの歴史書が好き
- 2025年4月11日
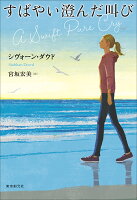 すばやい澄んだ叫びシヴォーン・ダウド,宮坂宏美読み終わったアイルランドの小さな村に住む少女、シェルの物語。詩的で温かみを感じる文体が特徴的。また、1984年のアイルランドが舞台なので、カトリックの世界観を(肯定的に)理解しておくと、読解にかなり有効かもしれない。 母が死んでから貧困かつネグレクトに陥った家庭で育ち、そのせいで教育が受けられていないシェルは友達デクランの思春期特有の激しい性的好奇心と性欲の芽生えに直面して妊娠してしまう。友達以上恋人未満という言葉があるけれど、まさにそれの最悪なパターン。 しかも貧困状態で学校も通わないシェルを見かねたローズ神父(シェルが唯一信用する大人である)は、彼女を救おうとするが、その奔走がシェルに対する性虐待を疑われる羽目に。 真綿で首を絞められる地獄とはこのこと。どんどん膨らむお腹にシェルはどうするのか。そして未婚の母(聖母マリアを思わせる)シェルは閉鎖的な田舎社会でどうなるのか……是非とも見届けてほしい。
すばやい澄んだ叫びシヴォーン・ダウド,宮坂宏美読み終わったアイルランドの小さな村に住む少女、シェルの物語。詩的で温かみを感じる文体が特徴的。また、1984年のアイルランドが舞台なので、カトリックの世界観を(肯定的に)理解しておくと、読解にかなり有効かもしれない。 母が死んでから貧困かつネグレクトに陥った家庭で育ち、そのせいで教育が受けられていないシェルは友達デクランの思春期特有の激しい性的好奇心と性欲の芽生えに直面して妊娠してしまう。友達以上恋人未満という言葉があるけれど、まさにそれの最悪なパターン。 しかも貧困状態で学校も通わないシェルを見かねたローズ神父(シェルが唯一信用する大人である)は、彼女を救おうとするが、その奔走がシェルに対する性虐待を疑われる羽目に。 真綿で首を絞められる地獄とはこのこと。どんどん膨らむお腹にシェルはどうするのか。そして未婚の母(聖母マリアを思わせる)シェルは閉鎖的な田舎社会でどうなるのか……是非とも見届けてほしい。 - 2025年4月4日
 北条泰時上横手雅敬かつて読んだ日本史の最も優れた政治家のひとりをあげなさいと言われたら、この人が上がるのだろうけど、大河ドラマにはならないよね! 彼のやっている事は、非常に地道で、物語には決してならない。ちまちま、ちまちま、法律を作り、御家人を調停し、朝廷と交渉している。その手案は巧みだ。だが、例えば祖父の北条時政や父親の北条義時のように、悪辣な手段を用いて、権力を握ったと言うわけでもなく、伯母の北条政子のように優れたキャラクター性を持っていたわけではない。 本書も、泰時の生まれ育ちまでは非常に面白く、北条義時って、ほんとに適当なんだななどと少し怒りが湧いてきたものだが、北条泰時が大人になってから、そして政治の実権を握ってから、ほんとにつまらない。彼は、日常の業務を粛々とこなし御成敗式目を制定している。そこに物語やドラマはなく必要だからやっている。おかげで、武士は無駄な闘争を起こさずに裁判と言う手段を学ぶことができた。 ここから考えられるのは、素晴らしい政治家ってたぶん、ドラマ性のない地に足のついたことを地道にやる政治家なんだと思う。
北条泰時上横手雅敬かつて読んだ日本史の最も優れた政治家のひとりをあげなさいと言われたら、この人が上がるのだろうけど、大河ドラマにはならないよね! 彼のやっている事は、非常に地道で、物語には決してならない。ちまちま、ちまちま、法律を作り、御家人を調停し、朝廷と交渉している。その手案は巧みだ。だが、例えば祖父の北条時政や父親の北条義時のように、悪辣な手段を用いて、権力を握ったと言うわけでもなく、伯母の北条政子のように優れたキャラクター性を持っていたわけではない。 本書も、泰時の生まれ育ちまでは非常に面白く、北条義時って、ほんとに適当なんだななどと少し怒りが湧いてきたものだが、北条泰時が大人になってから、そして政治の実権を握ってから、ほんとにつまらない。彼は、日常の業務を粛々とこなし御成敗式目を制定している。そこに物語やドラマはなく必要だからやっている。おかげで、武士は無駄な闘争を起こさずに裁判と言う手段を学ぶことができた。 ここから考えられるのは、素晴らしい政治家ってたぶん、ドラマ性のない地に足のついたことを地道にやる政治家なんだと思う。 - 2025年3月29日
 チューリップ・バブル: 人間を狂わせた花の物語 (文春文庫 タ 11-1)マイク・ダッシュ,Mike Dash,明石三世読み終わった天山山脈で生まれたチューリップの小さな野生種。この可愛らしい花が、オスマン帝国にわたり、オランダにわたり、オランダで人を狂わす花になるとは思っても見ないことだった——。 オランダと言えば、チューリップの国。だけれども、そのチューリップにかける情熱と言うのは17世紀から始まる。チューリップによってバブルが生まれ、球根が豪邸よりも高いなんて言うことが起きたと言う。 読んだ歴史書の中で、実は結構好きな部類の歴史書だ。こういう歴史書が増えてくれればいいのにだなんて思うのは結構わがままだと思うし、探せばいいんだけどね。
チューリップ・バブル: 人間を狂わせた花の物語 (文春文庫 タ 11-1)マイク・ダッシュ,Mike Dash,明石三世読み終わった天山山脈で生まれたチューリップの小さな野生種。この可愛らしい花が、オスマン帝国にわたり、オランダにわたり、オランダで人を狂わす花になるとは思っても見ないことだった——。 オランダと言えば、チューリップの国。だけれども、そのチューリップにかける情熱と言うのは17世紀から始まる。チューリップによってバブルが生まれ、球根が豪邸よりも高いなんて言うことが起きたと言う。 読んだ歴史書の中で、実は結構好きな部類の歴史書だ。こういう歴史書が増えてくれればいいのにだなんて思うのは結構わがままだと思うし、探せばいいんだけどね。 - 2025年3月29日
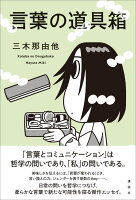 言葉の道具箱三木那由他読み終わった癒しのエッセイだよと言われて、ホイホイ買ってしまった。読んでみたら、中身は言語哲学の話で、言語哲学を敬遠していた私は騙されたと思ってしまったのであった。 とは言え、非常に身近な事柄から、言語哲学について語ってくれている。本当に頭が良い人は難しい事柄はわかりやすく語れるのかもしれない。そういうふうに思って読んでいたら、確かに癒しのエッセイだった。生きる力というか、考える力をくれたようだ。 著者は、性的マイノリティーで、そこからの視点は非常に私の視座を広げたような気がする。気がするだけで、本当に広げられているかはわからない。特に「生き延びましょう」という言葉は、津久井やまゆり園の事件でSNSの反応から「ぁあ、死ぬなぁ、ガチで」と感じた私のことも思い出した。 人間は、言葉をほとんどの人がある程度自由に使えるために粗雑に扱いがちだが、同時に言葉で人を殺すこともできる。言葉と言うものの深淵を気づけば考えてしまっていた。
言葉の道具箱三木那由他読み終わった癒しのエッセイだよと言われて、ホイホイ買ってしまった。読んでみたら、中身は言語哲学の話で、言語哲学を敬遠していた私は騙されたと思ってしまったのであった。 とは言え、非常に身近な事柄から、言語哲学について語ってくれている。本当に頭が良い人は難しい事柄はわかりやすく語れるのかもしれない。そういうふうに思って読んでいたら、確かに癒しのエッセイだった。生きる力というか、考える力をくれたようだ。 著者は、性的マイノリティーで、そこからの視点は非常に私の視座を広げたような気がする。気がするだけで、本当に広げられているかはわからない。特に「生き延びましょう」という言葉は、津久井やまゆり園の事件でSNSの反応から「ぁあ、死ぬなぁ、ガチで」と感じた私のことも思い出した。 人間は、言葉をほとんどの人がある程度自由に使えるために粗雑に扱いがちだが、同時に言葉で人を殺すこともできる。言葉と言うものの深淵を気づけば考えてしまっていた。 - 2025年3月28日
 狭き門ジッドかつて読んだ愛読書いとこのアリサは僕にとって最愛の人だった。皆がアリサを僕と結婚させようと動く。だけれども、アリサはそれに抵抗して、神への信仰を貫いて死んでいく。アリサは日記を残しており、僕を愛していたとわかる。 本当に大好きな悲恋物語で、様々な読み方をしているのだけれど、この今の私の読み方は、優秀であり、非の打ち所のない「僕」が強者すぎるのではないか、ということ。アリサの視点に立ってみると、息が詰まるほどの苦しい完璧さで「僕」が、頼んでもいないのに勝手に君は僕が守ると言う論理を振りかざして迫ってくる。勝手にアリサを判断して勝手に期待したり、失望したりする。これではアリサは生きていくのが苦しい。神に逃げるしかない。もちろんアリサはジェロームが好きだけど、好きだからこそ完璧すぎる「僕」がきつい。…と言うふうに読めるのだけど、もうしばらくしたら、また別の読み方をしているだろう。その時はまたメモしに来る。
狭き門ジッドかつて読んだ愛読書いとこのアリサは僕にとって最愛の人だった。皆がアリサを僕と結婚させようと動く。だけれども、アリサはそれに抵抗して、神への信仰を貫いて死んでいく。アリサは日記を残しており、僕を愛していたとわかる。 本当に大好きな悲恋物語で、様々な読み方をしているのだけれど、この今の私の読み方は、優秀であり、非の打ち所のない「僕」が強者すぎるのではないか、ということ。アリサの視点に立ってみると、息が詰まるほどの苦しい完璧さで「僕」が、頼んでもいないのに勝手に君は僕が守ると言う論理を振りかざして迫ってくる。勝手にアリサを判断して勝手に期待したり、失望したりする。これではアリサは生きていくのが苦しい。神に逃げるしかない。もちろんアリサはジェロームが好きだけど、好きだからこそ完璧すぎる「僕」がきつい。…と言うふうに読めるのだけど、もうしばらくしたら、また別の読み方をしているだろう。その時はまたメモしに来る。 - 2025年3月28日
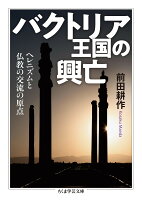 バクトリア王国の興亡前田耕作読み終わった大昔、今からすると中央アジアと考えられているヒンドゥークシュ山脈とアムダリアの間にはアレクサンダー大王率いる遠征軍が到着し、ギリシア人の国家が建てられた。これをグレコバクトリア王国と言う。そのバクトリア王国の歴史を語る話である。最初はアケメネス朝に支配された彼らがアレキサンダー大王の支配下に入る。アレキサンダー大王の妻はバクトリア人だったと言う。そこでアケメネス朝とギリシャの混融が始まる。アレキサンダー大王の後継者たちの流れを継ぐグレコバクトリア王国はギリシャ文化を保持しつつもインド文化に吸収されていき、最後、遊牧民に滅ぼされてしまう。 宗教も様々で、ゾロアスター教からギリシャ神話の神々へ、そして仏教へとつながっていく。そんな中で生まれたガンダーラ美術の美しさは、本当に目を見張るものがある。 ただ、実はかなり本書は難しい。グレコバクトリア王国のことを知りたくて、本書を開いたのだが、グレコバクトリア王国の記述はあまり多くなく、アレクサンダー大王やアケメネス朝のことについてかなりページを割かれているため、正直言ってどこの国の話をしているのかよくわからなかった。 とはいえ一読の価値はある。
バクトリア王国の興亡前田耕作読み終わった大昔、今からすると中央アジアと考えられているヒンドゥークシュ山脈とアムダリアの間にはアレクサンダー大王率いる遠征軍が到着し、ギリシア人の国家が建てられた。これをグレコバクトリア王国と言う。そのバクトリア王国の歴史を語る話である。最初はアケメネス朝に支配された彼らがアレキサンダー大王の支配下に入る。アレキサンダー大王の妻はバクトリア人だったと言う。そこでアケメネス朝とギリシャの混融が始まる。アレキサンダー大王の後継者たちの流れを継ぐグレコバクトリア王国はギリシャ文化を保持しつつもインド文化に吸収されていき、最後、遊牧民に滅ぼされてしまう。 宗教も様々で、ゾロアスター教からギリシャ神話の神々へ、そして仏教へとつながっていく。そんな中で生まれたガンダーラ美術の美しさは、本当に目を見張るものがある。 ただ、実はかなり本書は難しい。グレコバクトリア王国のことを知りたくて、本書を開いたのだが、グレコバクトリア王国の記述はあまり多くなく、アレクサンダー大王やアケメネス朝のことについてかなりページを割かれているため、正直言ってどこの国の話をしているのかよくわからなかった。 とはいえ一読の価値はある。 - 2025年3月22日
 読み終わった妹に全てを奪われた主人公がタイムリープして、人生をやり直す話、下巻。 主人公だけでなく、相手役もタイムリープしており、お互いすれ違っていたのが思いを通じさせるあたりはかなり良かった。でもちょっと悪役の前で惚けすぎだと思う。まぁそこは気にしないでいいとして。 悪役は結構きれいに退場。父親と娘の話であったけれども、父親が第1巻では、不倫相手の愛人だった妻とその間にできた妹を可愛がっているのかと思いきや、それも偽物の愛情で、誰も愛せないタイプであったと言うことに衝撃を受けた。 少し戸惑ったのが主人公が1人で旅をしてしまうところ、確かに主人公は小さい頃の目標で旅をしたいと思っていたけれども、いきなり登場人物や場面が変わってしまって、混乱してしまった。そこは相手役と旅をするって言う形の方が良かったんじゃないかなぁと思った。 でも、全体的に楽しめてよかった!
読み終わった妹に全てを奪われた主人公がタイムリープして、人生をやり直す話、下巻。 主人公だけでなく、相手役もタイムリープしており、お互いすれ違っていたのが思いを通じさせるあたりはかなり良かった。でもちょっと悪役の前で惚けすぎだと思う。まぁそこは気にしないでいいとして。 悪役は結構きれいに退場。父親と娘の話であったけれども、父親が第1巻では、不倫相手の愛人だった妻とその間にできた妹を可愛がっているのかと思いきや、それも偽物の愛情で、誰も愛せないタイプであったと言うことに衝撃を受けた。 少し戸惑ったのが主人公が1人で旅をしてしまうところ、確かに主人公は小さい頃の目標で旅をしたいと思っていたけれども、いきなり登場人物や場面が変わってしまって、混乱してしまった。そこは相手役と旅をするって言う形の方が良かったんじゃないかなぁと思った。 でも、全体的に楽しめてよかった! - 2025年3月21日
 物語 チベットの歴史石濱裕美子読み終わった苦難の歴史を歩むチベットの通史。古代から現在のダライ・ラマの時代の事まで知れる。 ガチの仏教国らしく、仏教のかなりの部分まで知らないといけないのかなあと身構えたけれども、著者の文章がうまいので、結構のことがわかってくる。 前半は神話に彩られた面白い話が多かったが、後半は大国にもてあそばれ、それでも独立を保とうとした国のありようを感じて、ただひたすら圧倒されるしかなかった。後半は泣きながら読んでいた。 そして何より筆者の熱量が尋常ではない。今まで中公新書の物語シリーズはいくつか読んだが、ここまで涙が出てくる名著は見当たらない。 帯にあるチベット僧が唱える菩薩の祈りをメモしておく。 世界が存在する限り 命あるものが存在する限り 私も輪廻の中にとどまって 有情の苦しみを滅することが できますように
物語 チベットの歴史石濱裕美子読み終わった苦難の歴史を歩むチベットの通史。古代から現在のダライ・ラマの時代の事まで知れる。 ガチの仏教国らしく、仏教のかなりの部分まで知らないといけないのかなあと身構えたけれども、著者の文章がうまいので、結構のことがわかってくる。 前半は神話に彩られた面白い話が多かったが、後半は大国にもてあそばれ、それでも独立を保とうとした国のありようを感じて、ただひたすら圧倒されるしかなかった。後半は泣きながら読んでいた。 そして何より筆者の熱量が尋常ではない。今まで中公新書の物語シリーズはいくつか読んだが、ここまで涙が出てくる名著は見当たらない。 帯にあるチベット僧が唱える菩薩の祈りをメモしておく。 世界が存在する限り 命あるものが存在する限り 私も輪廻の中にとどまって 有情の苦しみを滅することが できますように - 2025年3月15日
 悲劇のアルメニア藤野幸雄読み終わったかつて読んだまた読みたい故郷を大国に奪われ、世界を放浪し、それでも故郷を再建し、また大国に奪われ、ついには虐殺をされてしまったアルメニア人。彼らの独特な文化や美しい修道院に興味惹かれて読んだ本だけれども、書かれていたのは、予想の何倍も天を見上げる辛い現実であった。それでも民族として生きると言う事。それでも国として存続すると言う事。国とは何か。民族とは何か。滅びるとはどういうことか。それを訴えかけてくる本だった。 ソ連が崩壊してアルメニアは再建されたし、何とかコーカサス三国の中にある。けれども、まだ完全に彼らの傷がいえているわけではない。しかし、一度滅びの淵に立った存在は、したたかだ。
悲劇のアルメニア藤野幸雄読み終わったかつて読んだまた読みたい故郷を大国に奪われ、世界を放浪し、それでも故郷を再建し、また大国に奪われ、ついには虐殺をされてしまったアルメニア人。彼らの独特な文化や美しい修道院に興味惹かれて読んだ本だけれども、書かれていたのは、予想の何倍も天を見上げる辛い現実であった。それでも民族として生きると言う事。それでも国として存続すると言う事。国とは何か。民族とは何か。滅びるとはどういうことか。それを訴えかけてくる本だった。 ソ連が崩壊してアルメニアは再建されたし、何とかコーカサス三国の中にある。けれども、まだ完全に彼らの傷がいえているわけではない。しかし、一度滅びの淵に立った存在は、したたかだ。 - 2025年3月15日
- 2025年3月9日
 名君の碑中村彰彦読み終わった稀代の名君と呼ばれる、保科正之の生涯の物語です。事情があって、実の父親である徳川秀忠の手によって徳川家ではなく、現在の長野県あたりに領土を持つ大名の家に育ちますが、まっすぐ育っていく彼がよかったです。そして何よりゾクゾクしたのが自分を捨てた実の父親との心理的な対立と、自分を見出してくれた兄の徳川家光への愛情です。ここにもう少しページを割いて欲しかったのですが、作風上そうではなかったので少し残念でした。 そして、君主になるのですが、彼も失敗することがいっぱいあったり、心が病んでしまいそうなほどの非情な決断を下したりすることがあったりして。君主と言うものも、最初から有能なわけではないと言うふうに思いました。失敗から学んで、会津藩へと移る彼ですが、そこからの快進撃がかなり面白い。 歴史書レベルの淡々とした筆致なため、少し主人公に感情しにくいところもありましたが、そこはまぁ仕方がないとして。数少ない保科正之の本格的な歴史小説として貴重な1冊です。
名君の碑中村彰彦読み終わった稀代の名君と呼ばれる、保科正之の生涯の物語です。事情があって、実の父親である徳川秀忠の手によって徳川家ではなく、現在の長野県あたりに領土を持つ大名の家に育ちますが、まっすぐ育っていく彼がよかったです。そして何よりゾクゾクしたのが自分を捨てた実の父親との心理的な対立と、自分を見出してくれた兄の徳川家光への愛情です。ここにもう少しページを割いて欲しかったのですが、作風上そうではなかったので少し残念でした。 そして、君主になるのですが、彼も失敗することがいっぱいあったり、心が病んでしまいそうなほどの非情な決断を下したりすることがあったりして。君主と言うものも、最初から有能なわけではないと言うふうに思いました。失敗から学んで、会津藩へと移る彼ですが、そこからの快進撃がかなり面白い。 歴史書レベルの淡々とした筆致なため、少し主人公に感情しにくいところもありましたが、そこはまぁ仕方がないとして。数少ない保科正之の本格的な歴史小説として貴重な1冊です。 - 2025年3月9日
 ヴェネツィアの宿須賀敦子読み終わったじゅうぶん読んだまた読みたい愛読書最高に何度も読んでしまう本。作者の人に対する温かい眼差しや、過去に対する柔らかい眼差しが心を暖かくさせる。こういう柔らかく、しなやかなものの見方をしてみたいと言うふうに私は思ってしまう。
ヴェネツィアの宿須賀敦子読み終わったじゅうぶん読んだまた読みたい愛読書最高に何度も読んでしまう本。作者の人に対する温かい眼差しや、過去に対する柔らかい眼差しが心を暖かくさせる。こういう柔らかく、しなやかなものの見方をしてみたいと言うふうに私は思ってしまう。 - 2025年3月9日
- 2025年3月9日
- 2025年3月9日
- 2025年3月9日
 音楽家の食卓野田浩資かつて読んだじゅうぶん読んだまた読みたいバッハやモーツァルト、ショパンは何を食べていたのだろうかと言う本。もうどれもこれもが美味しそうでたまらない。そして作者の音楽家への暖かい愛を感じる。
音楽家の食卓野田浩資かつて読んだじゅうぶん読んだまた読みたいバッハやモーツァルト、ショパンは何を食べていたのだろうかと言う本。もうどれもこれもが美味しそうでたまらない。そして作者の音楽家への暖かい愛を感じる。 - 2025年3月9日
 ミラノ霧の風景須賀敦子かつて読んだじゅうぶん読んだまた読みたいとっても良い本だから、みんなにお勧めしたい。 作者は夫をなくして、その夫を始めとした様々な人の記憶の間で暮らしている。そんな作者が書くことによって、彼らとの記憶を消化しているような気がして、とても素敵だった。
ミラノ霧の風景須賀敦子かつて読んだじゅうぶん読んだまた読みたいとっても良い本だから、みんなにお勧めしたい。 作者は夫をなくして、その夫を始めとした様々な人の記憶の間で暮らしている。そんな作者が書くことによって、彼らとの記憶を消化しているような気がして、とても素敵だった。 - 2025年3月9日
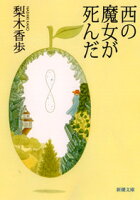 西の魔女が死んだ梨木香歩読み終わった北欧暮らしの道具店と言うサイトで紹介されていたので買った。最高に良かった。多分今年1番買ってよかった本だと思う。電車の中で最後ボロ泣きしてしまって不審者になってしまった。多分何度でも読み返す。今はボロ泣きしてしまうので読み返せないけど、1年後とか半年後とかにまた読み返すだろう。
西の魔女が死んだ梨木香歩読み終わった北欧暮らしの道具店と言うサイトで紹介されていたので買った。最高に良かった。多分今年1番買ってよかった本だと思う。電車の中で最後ボロ泣きしてしまって不審者になってしまった。多分何度でも読み返す。今はボロ泣きしてしまうので読み返せないけど、1年後とか半年後とかにまた読み返すだろう。 - 2025年3月9日
- 2025年3月9日
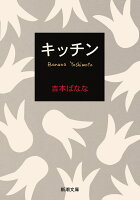 キッチン吉本ばなな読み終わったお勧めされた本。よしもとばななは敬遠していたけど、まあ読んでみるかと思った。 とてもよかった…と言う言い方は月並みだけれども、とても良かった。 このあと吉本ばななの著作が、AIでぱくられたと知って複雑な気分になってしまった
キッチン吉本ばなな読み終わったお勧めされた本。よしもとばななは敬遠していたけど、まあ読んでみるかと思った。 とてもよかった…と言う言い方は月並みだけれども、とても良かった。 このあと吉本ばななの著作が、AIでぱくられたと知って複雑な気分になってしまった
読み込み中...




