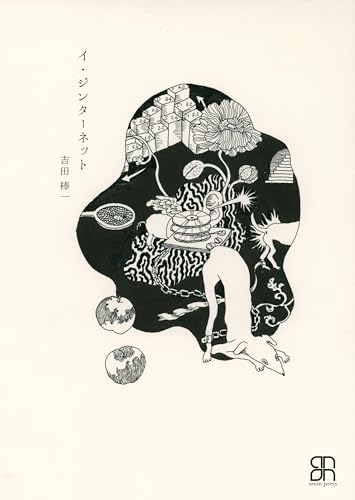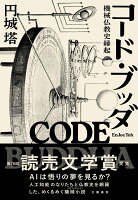najiok
@najiok
- 2025年9月29日
 やまんばの12にんのむすめ塩野米松,小沢さかえ読み終わった
やまんばの12にんのむすめ塩野米松,小沢さかえ読み終わった - 2025年9月8日
- 2025年9月6日
- 2025年8月24日
 火の鳥(3(ヤマト編・宇宙編))手塚治虫読み終わった
火の鳥(3(ヤマト編・宇宙編))手塚治虫読み終わった - 2025年8月24日
 火の鳥(2(未来編))手塚治虫読み終わった
火の鳥(2(未来編))手塚治虫読み終わった - 2025年8月20日
 ブラック・カルチャー中村隆之読み終わった
ブラック・カルチャー中村隆之読み終わった - 2025年7月16日
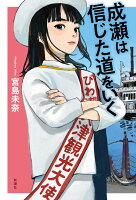 成瀬は信じた道をいく宮島未奈読み終わった
成瀬は信じた道をいく宮島未奈読み終わった - 2025年6月16日
- 2025年6月14日
- 2025年6月11日
- 2025年6月5日
- 2025年6月1日
 パリンプセスト草野理恵子読み終わった
パリンプセスト草野理恵子読み終わった - 2025年6月1日
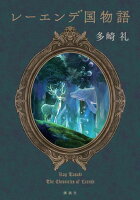 レーエンデ国物語多崎礼読み終わった
レーエンデ国物語多崎礼読み終わった - 2025年5月17日
 センス・オブ・ワンダーレイチェル・カーソン,上遠恵子読み終わった
センス・オブ・ワンダーレイチェル・カーソン,上遠恵子読み終わった - 2025年4月29日
 コロナ禍と出会い直す磯野真穂読み終わった
コロナ禍と出会い直す磯野真穂読み終わった - 2025年4月26日
 ナヌークの贈りもの星野道夫読み終わった
ナヌークの贈りもの星野道夫読み終わった - 2025年3月22日
- 2025年3月16日
- 2025年3月15日
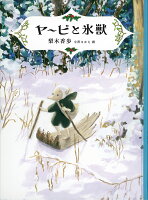 ヤービと氷獣小沢さかえ,梨木香歩読み終わった
ヤービと氷獣小沢さかえ,梨木香歩読み終わった - 2025年3月8日
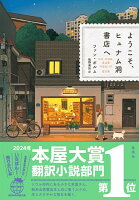 ようこそ、ヒュナム洞書店へファン・ボルム,牧野美加読み終わった
ようこそ、ヒュナム洞書店へファン・ボルム,牧野美加読み終わった
読み込み中...