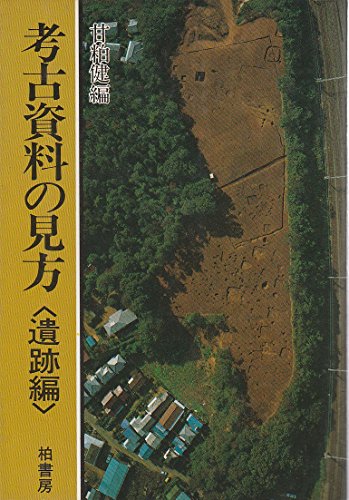りおかんぽす
@riocampos
りおかんぽすです。本は何かしら毎日読んでます。マンガもかなり読んでますが登録しないかなあ。
ここでは意図的に「読む」いわゆる物語がある本に限らず、図鑑や辞書など、何か調べるときに触れた本も記録しています。
また「読みたい」本はどこで知ったか、なぜ読みたいのかを、「読んでる」本は進行状況などメモ書きなどを入れています。単にタグ付けるだけでも良いのですが、意図的に一言だけでも書くように「実験」しています(タグ付けのみで済むのがReadsの良い点だと認識していますが、それに反したことをやってるのは自分への「実験」です)。←2025/6以降は実験がうまくいってないですorz→2026年は記録重視にしようかと思っています。
- 2026年2月24日
 古地図で見る京都金田章裕借りてきた
古地図で見る京都金田章裕借りてきた - 2026年2月24日
 禅の高僧大森曹玄もらった
禅の高僧大森曹玄もらった - 2026年2月24日
- 2026年2月24日
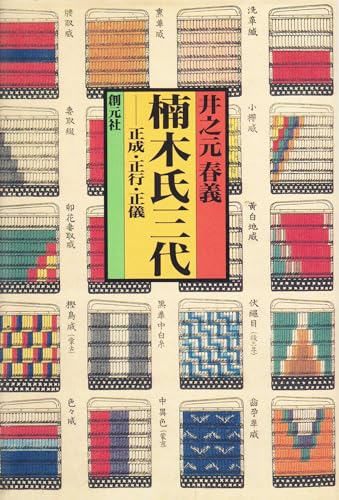 楠木氏三代: 正成・正行・正儀井之元春義もらった
楠木氏三代: 正成・正行・正儀井之元春義もらった - 2026年2月24日
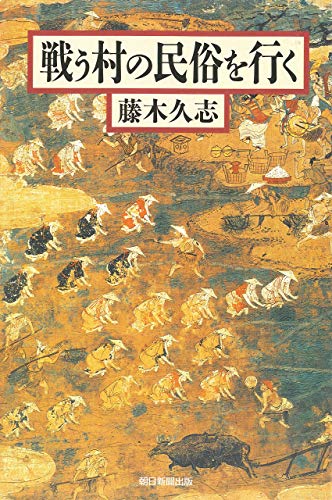 戦う村の民俗を行く 戦国を行く藤木久志もらった
戦う村の民俗を行く 戦国を行く藤木久志もらった - 2026年2月17日
 関西のあんこ 100名品京阪神エルマガジン社買った
関西のあんこ 100名品京阪神エルマガジン社買った - 2026年2月14日
- 2026年2月14日
 何歳からでも 丸まった背中が2ヵ月で伸びる!中山恭秀,安保雅博借りてきた
何歳からでも 丸まった背中が2ヵ月で伸びる!中山恭秀,安保雅博借りてきた - 2026年2月11日
- 2026年2月11日
 特薦いいビル 千日前味園ビルBMC,夜長堂,岩田雅希,川原由美子,西岡潔,阪口大介,高岡伸一,髙岡伸一借りてきた
特薦いいビル 千日前味園ビルBMC,夜長堂,岩田雅希,川原由美子,西岡潔,阪口大介,高岡伸一,髙岡伸一借りてきた - 2026年2月11日
 琵琶湖はいつできた里口保文借りてきた
琵琶湖はいつできた里口保文借りてきた - 2026年2月11日
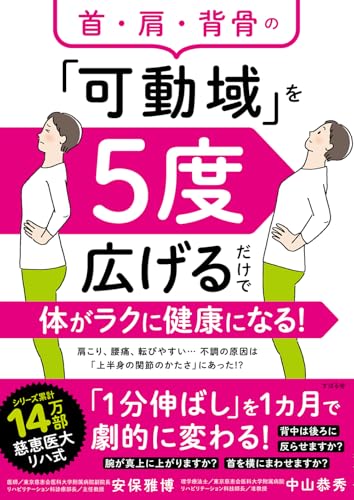 首・肩・背骨の「可動域」を5度広げるだけで体がラクに健康になる!中山恭秀,安保雅博借りてきた
首・肩・背骨の「可動域」を5度広げるだけで体がラクに健康になる!中山恭秀,安保雅博借りてきた - 2026年2月11日
 「橋のない川」を読む住井すゑ,福田雅子借りてきた
「橋のない川」を読む住井すゑ,福田雅子借りてきた - 2026年2月11日
- 2026年2月10日
 読み終わった導入の第1部としてベストセラー「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」をなぜ持ってきたのか、とも思った。しかしこの本は「この時代に本を売るにはどうすればいいのか」つまりは読者側の読書量を云々するのではなく、本の販売数、読者の購入冊数を増やすには、なので「似て非なる本」だと主張するために第1部が置かれたのだと最終的に理解した。(ただしベストセラーをどうこうするつもりはないと言いつつもディスってる感じなのはどうなのだろうか。なお私はこのベストセラーも著者も好かない。) タイトルの「本」に惹かれて読んだのだけど、上にも書いたように、この本は読者側向けではなく販売側向けであり、そして内容はマーケティング戦略の紹介である。個人的にマーケティングの書籍は読んだことが無かったので、その面で読後感は良い。 日本の書店は書籍と雑誌を共に販売している特殊な形態だとも知った。つまり海外だと書籍だけで本屋は勝負してる。 雑誌の売れ行きが落ち込んで書店や出版社が悩んでるのだけど、雑誌の「送客」「宣伝」「育成」の役割をWebに担わせることで書籍を売ることは可能、その成功例がマンガだと。 私は出版業界の人間ではないのだけど、マーケティングのこと(特にバイロン・シャープ)を知れて良かったと感じる。 なお章ごとに「まとめ」があり、更に終章には「本のまとめ」があるので、結論だけ知りたい場合にはそこを読めば済む。だけどそこだけで了解して理解できるほど私は頭がよくないので一通り読んで良かったと思う。 まとまり無い文になったな。 実はこの本のマーケティング戦略解説のところを読んで、先日(ついこないだの日曜日だ)の衆院選の結果を解釈・分析できるなあと思った。その意味でもいま読めて良かった。
読み終わった導入の第1部としてベストセラー「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」をなぜ持ってきたのか、とも思った。しかしこの本は「この時代に本を売るにはどうすればいいのか」つまりは読者側の読書量を云々するのではなく、本の販売数、読者の購入冊数を増やすには、なので「似て非なる本」だと主張するために第1部が置かれたのだと最終的に理解した。(ただしベストセラーをどうこうするつもりはないと言いつつもディスってる感じなのはどうなのだろうか。なお私はこのベストセラーも著者も好かない。) タイトルの「本」に惹かれて読んだのだけど、上にも書いたように、この本は読者側向けではなく販売側向けであり、そして内容はマーケティング戦略の紹介である。個人的にマーケティングの書籍は読んだことが無かったので、その面で読後感は良い。 日本の書店は書籍と雑誌を共に販売している特殊な形態だとも知った。つまり海外だと書籍だけで本屋は勝負してる。 雑誌の売れ行きが落ち込んで書店や出版社が悩んでるのだけど、雑誌の「送客」「宣伝」「育成」の役割をWebに担わせることで書籍を売ることは可能、その成功例がマンガだと。 私は出版業界の人間ではないのだけど、マーケティングのこと(特にバイロン・シャープ)を知れて良かったと感じる。 なお章ごとに「まとめ」があり、更に終章には「本のまとめ」があるので、結論だけ知りたい場合にはそこを読めば済む。だけどそこだけで了解して理解できるほど私は頭がよくないので一通り読んで良かったと思う。 まとまり無い文になったな。 実はこの本のマーケティング戦略解説のところを読んで、先日(ついこないだの日曜日だ)の衆院選の結果を解釈・分析できるなあと思った。その意味でもいま読めて良かった。 - 2026年2月3日
- 2026年2月3日
- 2026年2月3日
- 2026年1月27日
- 2026年1月26日
 歴史小説のウソ佐藤賢一読み終わった「はじめに」 歴史小説と歴史学の違いを挙げた。歴史小説の対象は人間で「どの時代でも変わらない」、歴史学の対象は時代で「今とはこう違う」。とはいえ実際はどちらも意図的に混じる/混ぜると。 「第一章 歴史は物語なのか」 歴史の記述というか文書の特性を挙げる。当然ながら一次文献であっても主観が入り、誇張やウソが紛れ込む。また近世以前では歴史と物語とが分けられていない。ここで歴史学の創始者ランケが実証主義を持ち込み、歴史を「歴史学」に変えたことを紹介。つまり文学との境界が曖昧だった歴史を科学としての歴史学へと変えた。とはいえ歴史学となると歴史のワクワクが減ってしまったとも言え、それに応えるのが歴史小説、とも言えると。 「第二章 歴史小説のウソ」 歴史学には会話文が無い。会話文は歴史小説の専売特許。人物の心の動きについても歴史小説なら書けるが歴史学では書けない。「本能寺の変」の歴史小説は多いが、歴史学での研究意義が見出しにくい。やるとすれば政治構造分析か。「なぜ明智光秀は謀反を起こしたのか」は歴史学では答えられない。 なお歴史小説を書く上で調べる文献は二次文献が大半。一次文献だけではその文献の読み方さえ分からないし誤読する。先学の調べたことを利用するのは当然。史料(=一次文献)として例えばナレーション史料。ただし文学的要素も多くてウソだらけ、また「勝者の歴史」でもある。法律、裁判記録、行政文書(戸籍・出納簿・議事録)などはウソが少なめ。手紙は美化する必要がないのでウソが少ないが、しかし公開前提や途中で読まれること前提の手紙の取扱は注意を要する。 歴史小説の読者は現代人なので、現代人の共感を生むよう書く必要がある。しかし歴史小説の時代と現代では価値観が異なることも多い。特に人権。そこで宗教や信仰を使って現代人の価値観に近い視点を生み出すようにしていると。 「第三章 歴史小説と史観」 先に結論を書くと「自分なりの史観を持てば「歴史小説のウソ」に惑わされない」。 史観/歴史観は広辞苑によると「歴史的世界の構造やその発展についての一つの体系的な見方」。時代区分の「古代・中世・近代」も一種の史観で「悪い中世」と「良い古代・良い近代」。 歴史学以前の歴史には文学的要素が混じり、またイデオロギーの要素が含まれている。先にイデオロギーありきで歴史を描くことも多い。ただし科学的であるとの前提に立つ歴史学でもイデオロギーが含まれることがある。そしてこのイデオロギーが史観を打ち出すことがある。良い悪いの基準が先にあり、それを時代に当てはめる、これでは物語であり伝説であり、聖典にもなる。 近代でも「唯物史観」「皇国史観」などイデオロギーが先にある史観が力を持った。しかしイデオロギーは論に過ぎず、それを支えるために歴史の力を借りた。皇国史観の大元は水戸藩の尊皇イデオロギー。そのために水戸光圀は「大日本史」編纂に力を注いだ。敗戦により皇国史観が打ちのめされ、しかし日本は前に進む活力となる史観を求めた。ここで出てきたのが、歴史小説であり司馬遼太郎であり「司馬史観」であると。しかし歴史小説にはウソが含まれる。そのウソにより読者を信じさせることができてしまう。(もしもイデオロギーによるウソが…。) さて史観は歴史学が出すべきものなのか。判断を伴うので科学的ではない。よって史観を打ち出すことができるのは(前近代的)歴史家ではないか。歴史小説家でも歴史学者でも、史観を持つときは歴史家だと。もちろん読者も歴史家。史観は他人から与えられるものではなく、自分の頭で考えて、自分なりのものを作り上げていくことが大事。 第三章の史観の話は、一読しただけではうまく腑に落ちなかった(というか理解出来なかった)ので、私の理解を含めて書きながら腹にすえてみた。納得できた。 書名「歴史小説のウソ」よりも大きい内容の本でした。なお「おわりに」はぜひご一読頂きたいので、ここでは取り上げません。
歴史小説のウソ佐藤賢一読み終わった「はじめに」 歴史小説と歴史学の違いを挙げた。歴史小説の対象は人間で「どの時代でも変わらない」、歴史学の対象は時代で「今とはこう違う」。とはいえ実際はどちらも意図的に混じる/混ぜると。 「第一章 歴史は物語なのか」 歴史の記述というか文書の特性を挙げる。当然ながら一次文献であっても主観が入り、誇張やウソが紛れ込む。また近世以前では歴史と物語とが分けられていない。ここで歴史学の創始者ランケが実証主義を持ち込み、歴史を「歴史学」に変えたことを紹介。つまり文学との境界が曖昧だった歴史を科学としての歴史学へと変えた。とはいえ歴史学となると歴史のワクワクが減ってしまったとも言え、それに応えるのが歴史小説、とも言えると。 「第二章 歴史小説のウソ」 歴史学には会話文が無い。会話文は歴史小説の専売特許。人物の心の動きについても歴史小説なら書けるが歴史学では書けない。「本能寺の変」の歴史小説は多いが、歴史学での研究意義が見出しにくい。やるとすれば政治構造分析か。「なぜ明智光秀は謀反を起こしたのか」は歴史学では答えられない。 なお歴史小説を書く上で調べる文献は二次文献が大半。一次文献だけではその文献の読み方さえ分からないし誤読する。先学の調べたことを利用するのは当然。史料(=一次文献)として例えばナレーション史料。ただし文学的要素も多くてウソだらけ、また「勝者の歴史」でもある。法律、裁判記録、行政文書(戸籍・出納簿・議事録)などはウソが少なめ。手紙は美化する必要がないのでウソが少ないが、しかし公開前提や途中で読まれること前提の手紙の取扱は注意を要する。 歴史小説の読者は現代人なので、現代人の共感を生むよう書く必要がある。しかし歴史小説の時代と現代では価値観が異なることも多い。特に人権。そこで宗教や信仰を使って現代人の価値観に近い視点を生み出すようにしていると。 「第三章 歴史小説と史観」 先に結論を書くと「自分なりの史観を持てば「歴史小説のウソ」に惑わされない」。 史観/歴史観は広辞苑によると「歴史的世界の構造やその発展についての一つの体系的な見方」。時代区分の「古代・中世・近代」も一種の史観で「悪い中世」と「良い古代・良い近代」。 歴史学以前の歴史には文学的要素が混じり、またイデオロギーの要素が含まれている。先にイデオロギーありきで歴史を描くことも多い。ただし科学的であるとの前提に立つ歴史学でもイデオロギーが含まれることがある。そしてこのイデオロギーが史観を打ち出すことがある。良い悪いの基準が先にあり、それを時代に当てはめる、これでは物語であり伝説であり、聖典にもなる。 近代でも「唯物史観」「皇国史観」などイデオロギーが先にある史観が力を持った。しかしイデオロギーは論に過ぎず、それを支えるために歴史の力を借りた。皇国史観の大元は水戸藩の尊皇イデオロギー。そのために水戸光圀は「大日本史」編纂に力を注いだ。敗戦により皇国史観が打ちのめされ、しかし日本は前に進む活力となる史観を求めた。ここで出てきたのが、歴史小説であり司馬遼太郎であり「司馬史観」であると。しかし歴史小説にはウソが含まれる。そのウソにより読者を信じさせることができてしまう。(もしもイデオロギーによるウソが…。) さて史観は歴史学が出すべきものなのか。判断を伴うので科学的ではない。よって史観を打ち出すことができるのは(前近代的)歴史家ではないか。歴史小説家でも歴史学者でも、史観を持つときは歴史家だと。もちろん読者も歴史家。史観は他人から与えられるものではなく、自分の頭で考えて、自分なりのものを作り上げていくことが大事。 第三章の史観の話は、一読しただけではうまく腑に落ちなかった(というか理解出来なかった)ので、私の理解を含めて書きながら腹にすえてみた。納得できた。 書名「歴史小説のウソ」よりも大きい内容の本でした。なお「おわりに」はぜひご一読頂きたいので、ここでは取り上げません。
読み込み中...