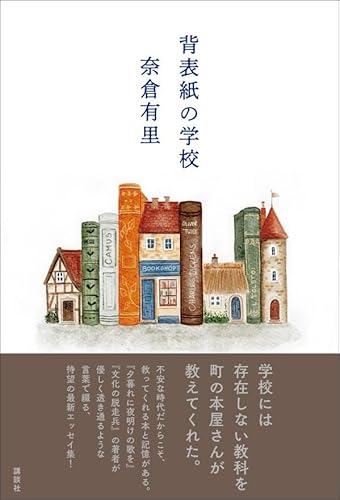yo_yohei
@yo_yohei
シンガポールでドラムを叩いています。シンガポールに来ることがあったら、気軽に声かけてください。
今ボクはゲーム作りにハマっているので、プレイしてコメントくれたら泣いて喜びます。以下URLからプレイできます。
- 2026年2月24日
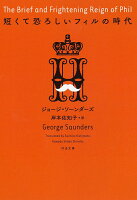 短くて恐ろしいフィルの時代ジョージ・ソーンダーズ,岸本佐知子読み終わった@ シンガポール一見、カオスな世界観だけど、驚くほどに“今”を描いている。でも、この原著が発表されたのは2005年らしいから更に驚き。さすがソーンダーズ先生だ。 はっきり言って、今、日本は大ピンチだと思ってるんですが、この本を読んで、「これって今の日本のこと描いてるんじゃない?」と思う人が1人でも多く増えたらいいなと思います。 ここからはネタバレの感想ですが、 とても面白く読んだ一方、フィルの時代を終わらせたのが内側からの自浄作用ではなく、外側からの圧力だったことが暗澹たる気持ちにもなりました。現在、大ピンチな日本、そして世界を変えるには、自分たちの力だけではなし得ないのだろうか。そうじゃないと思いたい。
短くて恐ろしいフィルの時代ジョージ・ソーンダーズ,岸本佐知子読み終わった@ シンガポール一見、カオスな世界観だけど、驚くほどに“今”を描いている。でも、この原著が発表されたのは2005年らしいから更に驚き。さすがソーンダーズ先生だ。 はっきり言って、今、日本は大ピンチだと思ってるんですが、この本を読んで、「これって今の日本のこと描いてるんじゃない?」と思う人が1人でも多く増えたらいいなと思います。 ここからはネタバレの感想ですが、 とても面白く読んだ一方、フィルの時代を終わらせたのが内側からの自浄作用ではなく、外側からの圧力だったことが暗澹たる気持ちにもなりました。現在、大ピンチな日本、そして世界を変えるには、自分たちの力だけではなし得ないのだろうか。そうじゃないと思いたい。 - 2026年2月24日
 ソーンダーズ先生の小説教室 ロシア文学に学ぶ書くこと、読むこと、生きることジョージ・ソーンダーズ,柳田麻里,秋草俊一郎紹介今、『ソーンダーズ先生の小説教室』がKindleで半額になっています。ボクの「棺桶に入れてほしい本」の一冊です。これがあれば、あの世でもずっと何かを作っていられる気がする。
ソーンダーズ先生の小説教室 ロシア文学に学ぶ書くこと、読むこと、生きることジョージ・ソーンダーズ,柳田麻里,秋草俊一郎紹介今、『ソーンダーズ先生の小説教室』がKindleで半額になっています。ボクの「棺桶に入れてほしい本」の一冊です。これがあれば、あの世でもずっと何かを作っていられる気がする。 - 2026年2月20日
 刑務所で当事者研究をやってみた向谷地生良,村上靖彦気になる「シリーズ ケアを開く」だし、以下の紹介文からも気になっている。 「「シャバより刑務所のほうがマシ」と彼らは言った。他者に頼ることを知らないその人たちを「犯罪者」として裁き、…」
刑務所で当事者研究をやってみた向谷地生良,村上靖彦気になる「シリーズ ケアを開く」だし、以下の紹介文からも気になっている。 「「シャバより刑務所のほうがマシ」と彼らは言った。他者に頼ることを知らないその人たちを「犯罪者」として裁き、…」 - 2026年2月17日
- 2026年2月8日
- 2026年2月5日
 ソーンダーズ先生の小説教室 ロシア文学に学ぶ書くこと、読むこと、生きることジョージ・ソーンダーズ,柳田麻里,秋草俊一郎まだ読んでる@ シンガポール第二講(?)を読了。 ツルゲーネフの『のど自慢』を題材に選んでいるのだが、なぜこのような冗長な小説を題材に選んだのか、読んでいてずっと疑問だった。 だが、ソーンダーズ先生(この本を読むとソーンダーズ先生と呼びたくなる)の講義部分を読んで、鳥肌が立った。 「自分が夢みた作家傷とはほど遠い作家になるかもしれない。けっきょくのところ、書き手はよくも悪くも、本当の自分に書けるものしか書けない。」という部分に深く、とても深く共感する。 芸術家は自分がどのような芸術家に成長するか、自分で取捨選択することはできないのだ。 いつかソーンダーズ先生に会うことができたら、ガッツリ握手したい。
ソーンダーズ先生の小説教室 ロシア文学に学ぶ書くこと、読むこと、生きることジョージ・ソーンダーズ,柳田麻里,秋草俊一郎まだ読んでる@ シンガポール第二講(?)を読了。 ツルゲーネフの『のど自慢』を題材に選んでいるのだが、なぜこのような冗長な小説を題材に選んだのか、読んでいてずっと疑問だった。 だが、ソーンダーズ先生(この本を読むとソーンダーズ先生と呼びたくなる)の講義部分を読んで、鳥肌が立った。 「自分が夢みた作家傷とはほど遠い作家になるかもしれない。けっきょくのところ、書き手はよくも悪くも、本当の自分に書けるものしか書けない。」という部分に深く、とても深く共感する。 芸術家は自分がどのような芸術家に成長するか、自分で取捨選択することはできないのだ。 いつかソーンダーズ先生に会うことができたら、ガッツリ握手したい。 - 2026年1月31日
 読み終わった@ シンガポール以前読んだ『やっと言えた』を通じて、カウンセリングという場で「こんなにも怖いことが起こりうるのか」と衝撃を受けた。いったいカウンセリングとは何なのだろうという疑問から本書を手に取った。 本書は感動を覚えるような類いの本ではないかもしれない。だが読み進めるうちに、自分でも驚くほど深く感動していた。ここまで心を動かされたのは、『やっと言えた』を先に読んでいたからでもあると思う。そして読み終えたあと、私は『やっと言えた』にも改めて深い感動を覚えた。本書『カウンセリングとは何か』と『やっと言えた』は、互いを補い合う関係にあると感じている。 本書は、さまざまな各論が点在しているカウンセリングの世界において、それらを比較しながら整理し、全体像を描き出した一冊である。(こうした本は、これまであまりなかったのではないだろうか。) この本を読んだことで、なぜ心理士があの心理士を批判していたのか、その理由がなんとなくわかったし、また、自分自身に対しても、ある程度のセルフカウンセリングができるようになった気がする。(あくまで「ある程度」ではあるが。)
読み終わった@ シンガポール以前読んだ『やっと言えた』を通じて、カウンセリングという場で「こんなにも怖いことが起こりうるのか」と衝撃を受けた。いったいカウンセリングとは何なのだろうという疑問から本書を手に取った。 本書は感動を覚えるような類いの本ではないかもしれない。だが読み進めるうちに、自分でも驚くほど深く感動していた。ここまで心を動かされたのは、『やっと言えた』を先に読んでいたからでもあると思う。そして読み終えたあと、私は『やっと言えた』にも改めて深い感動を覚えた。本書『カウンセリングとは何か』と『やっと言えた』は、互いを補い合う関係にあると感じている。 本書は、さまざまな各論が点在しているカウンセリングの世界において、それらを比較しながら整理し、全体像を描き出した一冊である。(こうした本は、これまであまりなかったのではないだろうか。) この本を読んだことで、なぜ心理士があの心理士を批判していたのか、その理由がなんとなくわかったし、また、自分自身に対しても、ある程度のセルフカウンセリングができるようになった気がする。(あくまで「ある程度」ではあるが。) - 2026年1月23日
- 2026年1月23日
 フェミニスト経済学ハンドブックエブル・コンガー,グンセリ・ベリック,日本フェミニスト経済学会気になる読みたい
フェミニスト経済学ハンドブックエブル・コンガー,グンセリ・ベリック,日本フェミニスト経済学会気になる読みたい - 2026年1月18日
- 2026年1月13日
 その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのかアグラヤ・ヴェテラニー,松永美穂読み終わった@ シンガポール常に不穏な空気が流れている、通常の散文と詩の中間のような文体だった。ハン・ガンの小説にも詩的な要素が感じられるが、本書はそれ以上に抽象度が高く、より濃密な詩的成分を含んでいるように思う。物語はさまざまな場所へと飛躍しながら進み、その全体を通して暴力と死の匂いが漂っている。文章は切迫しているようでもあり、同時にどこか俯瞰して語られているようにも感じられる。 読んでいるあいだ、終始、不安で不穏な気持ちになっていた。しかし一方で、私はそうした感情を味わいたくて、小説を読んでいる部分もある。
その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのかアグラヤ・ヴェテラニー,松永美穂読み終わった@ シンガポール常に不穏な空気が流れている、通常の散文と詩の中間のような文体だった。ハン・ガンの小説にも詩的な要素が感じられるが、本書はそれ以上に抽象度が高く、より濃密な詩的成分を含んでいるように思う。物語はさまざまな場所へと飛躍しながら進み、その全体を通して暴力と死の匂いが漂っている。文章は切迫しているようでもあり、同時にどこか俯瞰して語られているようにも感じられる。 読んでいるあいだ、終始、不安で不穏な気持ちになっていた。しかし一方で、私はそうした感情を味わいたくて、小説を読んでいる部分もある。 - 2026年1月11日
 読み終わった@ シンガポール本書は、自閉症の当事者である著者が自身の経験について綴った一冊である。個人的な体験に基づく貴重な証言であると同時に、文章そのものがとても面白い。 私は正式な診断は受けていないものの、心療内科医から「ASD/ADHDの特性があると思う」と言われたことがあり、自分自身でもその自覚がある。その立場から読むと、著者が語る困難には身に覚えのある部分が多かった。もちろん、著者が直面してきた苦労・今も直面している苦労は、私の比ではないが。 また、著者はいわゆる“重度”の自閉症を持つとされているが、一括りに“重度”と言っても、その症状や困難のあり方は個々人によって違う。“自閉症”というラベルではなく、その人自身と向き合うことの大切さを本書は伝えてくれるものだった。
読み終わった@ シンガポール本書は、自閉症の当事者である著者が自身の経験について綴った一冊である。個人的な体験に基づく貴重な証言であると同時に、文章そのものがとても面白い。 私は正式な診断は受けていないものの、心療内科医から「ASD/ADHDの特性があると思う」と言われたことがあり、自分自身でもその自覚がある。その立場から読むと、著者が語る困難には身に覚えのある部分が多かった。もちろん、著者が直面してきた苦労・今も直面している苦労は、私の比ではないが。 また、著者はいわゆる“重度”の自閉症を持つとされているが、一括りに“重度”と言っても、その症状や困難のあり方は個々人によって違う。“自閉症”というラベルではなく、その人自身と向き合うことの大切さを本書は伝えてくれるものだった。 - 2026年1月7日
 読み終わった@ 横浜市シンガポールで暮らすなかで、日々実感しているのは、「自分は“日本人”というアイデンティティを捨てることができない」という事実だ。それはつまり、日本人としての責任と向き合うことでもある。加害の歴史を背負う側に属する日本人として、朝鮮半島の現代史を知ることは一つの責務だと感じ、本書を手に取った。 7年にも及ぶ執筆活動の成果に納得させられる内容だった。「韓国の民主主義の最大値は分断体制が規定する」という指摘が示す通り、「分断」を口実に韓国の民主主義が幾度も脅かされてきた過程が、具体的に描かれている。 本書によって、韓国現代史を理解するための基盤が自分の中にできたように思う。今後、韓国に関する文献や小説を読む際にも、これまでより一段深い理解が可能になるはずだ。
読み終わった@ 横浜市シンガポールで暮らすなかで、日々実感しているのは、「自分は“日本人”というアイデンティティを捨てることができない」という事実だ。それはつまり、日本人としての責任と向き合うことでもある。加害の歴史を背負う側に属する日本人として、朝鮮半島の現代史を知ることは一つの責務だと感じ、本書を手に取った。 7年にも及ぶ執筆活動の成果に納得させられる内容だった。「韓国の民主主義の最大値は分断体制が規定する」という指摘が示す通り、「分断」を口実に韓国の民主主義が幾度も脅かされてきた過程が、具体的に描かれている。 本書によって、韓国現代史を理解するための基盤が自分の中にできたように思う。今後、韓国に関する文献や小説を読む際にも、これまでより一段深い理解が可能になるはずだ。 - 2026年1月3日
 読み終わった@ ソウルアメリカが突然戦争を始めて言葉を失っている。今ある戦争をやめさせることができないばかりか、新たな戦争が始まってしまったことに虚無感を覚える。 ——— 本書は、『純粋理性批判』『精神現象学』『存在と時間』といった難解な哲学書について、「そこに何が書かれているのか」を概観できる入門書である。同時に、現代社会が抱える「真実(陰謀論)」「共同体(排外主義)」「不安」といった問題を、これらの哲学を手がかりに捉え直そうとする試みでもある。 まず、哲学書の概要解説としては非常に優れていると感じた。カント、ヘーゲル、ハイデガーという、通常であれば専門書を何冊も読まなければ全体像がつかめない思想について、「それぞれが何を問題にしていたのか」が明確に整理されている。本書を通じて、これらの哲学書に「何が書いてあるのか、少なくとも輪郭は理解できた」と感じられたのは大きい。これほど平易にまとめられているのは、著者の膨大な知識と読解の蓄積によるものだろう。 一方で、現代社会の問題を「どのように捉え直すか」という点については、やや物足りなさも残った。たとえば陰謀論について考えると、それを強く信じている人々は、カントが想定した「誰もが共有する理性」をすでに放棄している存在なのではないか、あるいはカントが警戒した擬似科学を積極的に支持している人々なのではないか、という疑問が浮かぶ。もしそうであるなら、著者が提唱するように「議論や対話を通じて真実の追求を目指す」という構図は、必ずしも容易には成り立たないのではないか。 排外主義についても同様である。ヘーゲルの言う相互承認が成立していないからこそ、現在の排外主義的状況があるのだとすれば、「相互承認が欠けているのだから、相互承認を回復しよう」という説明は、やや循環的に感じられる。また、排外主義を「不安からの逃避」として説明することも、一つの側面ではあっても、それだけでは捉えきれない複雑さがあるように思う。 総じて、本書は難解な哲学を理解するための導入としては非常に有用である一方、現代社会の問題の「本質」に迫るためには、陰謀論、排外主義、不安といったテーマごとに、より踏み込んだ個別の検討が必要なのではないか、という印象を持った。
読み終わった@ ソウルアメリカが突然戦争を始めて言葉を失っている。今ある戦争をやめさせることができないばかりか、新たな戦争が始まってしまったことに虚無感を覚える。 ——— 本書は、『純粋理性批判』『精神現象学』『存在と時間』といった難解な哲学書について、「そこに何が書かれているのか」を概観できる入門書である。同時に、現代社会が抱える「真実(陰謀論)」「共同体(排外主義)」「不安」といった問題を、これらの哲学を手がかりに捉え直そうとする試みでもある。 まず、哲学書の概要解説としては非常に優れていると感じた。カント、ヘーゲル、ハイデガーという、通常であれば専門書を何冊も読まなければ全体像がつかめない思想について、「それぞれが何を問題にしていたのか」が明確に整理されている。本書を通じて、これらの哲学書に「何が書いてあるのか、少なくとも輪郭は理解できた」と感じられたのは大きい。これほど平易にまとめられているのは、著者の膨大な知識と読解の蓄積によるものだろう。 一方で、現代社会の問題を「どのように捉え直すか」という点については、やや物足りなさも残った。たとえば陰謀論について考えると、それを強く信じている人々は、カントが想定した「誰もが共有する理性」をすでに放棄している存在なのではないか、あるいはカントが警戒した擬似科学を積極的に支持している人々なのではないか、という疑問が浮かぶ。もしそうであるなら、著者が提唱するように「議論や対話を通じて真実の追求を目指す」という構図は、必ずしも容易には成り立たないのではないか。 排外主義についても同様である。ヘーゲルの言う相互承認が成立していないからこそ、現在の排外主義的状況があるのだとすれば、「相互承認が欠けているのだから、相互承認を回復しよう」という説明は、やや循環的に感じられる。また、排外主義を「不安からの逃避」として説明することも、一つの側面ではあっても、それだけでは捉えきれない複雑さがあるように思う。 総じて、本書は難解な哲学を理解するための導入としては非常に有用である一方、現代社会の問題の「本質」に迫るためには、陰謀論、排外主義、不安といったテーマごとに、より踏み込んだ個別の検討が必要なのではないか、という印象を持った。 - 2026年1月1日
 読み終わった@ シンガポール本書はまず世界を席巻している、人生や人格を「物語化」することの危険性について説いている。「物語化」することで、必ずこぼれ落ちるものが出てくるからだ。 そして、「物語化すること」の代わりになるものとして、「ゲーム」、「パズル」、「ギャンブル」、「おもちゃ遊び」を挙げ、それぞれのメリット、デメリット、それぞれの関係性を挙げる。世界をどのように見るか。物語的にみるか、ゲーム的に見るか、パズル的に見るか。もしくはギャンブル的、おもちゃ遊び的に世界のあり方を壊すか。 確か、村上春樹と河合隼雄の対談で「人間は物事を物語を通してしか見ることができない」と言っていたことを思い出した。だが、この文言は本書と矛盾しないと思っている。村上春樹と河合隼雄は”物語”というものを広義の意味で使用しているのに対し、本書では”物語”を狭義の意味で使っていると思う。村上春樹たちが使っていた”物語”を細分化すると、”物語”、”ゲーム”、”パズル”、”ギャンブル”、”おもちゃ遊び”になるのではないだろうか。 日々、漠然と考えていたことを言語化してくれたような読書体験だった。
読み終わった@ シンガポール本書はまず世界を席巻している、人生や人格を「物語化」することの危険性について説いている。「物語化」することで、必ずこぼれ落ちるものが出てくるからだ。 そして、「物語化すること」の代わりになるものとして、「ゲーム」、「パズル」、「ギャンブル」、「おもちゃ遊び」を挙げ、それぞれのメリット、デメリット、それぞれの関係性を挙げる。世界をどのように見るか。物語的にみるか、ゲーム的に見るか、パズル的に見るか。もしくはギャンブル的、おもちゃ遊び的に世界のあり方を壊すか。 確か、村上春樹と河合隼雄の対談で「人間は物事を物語を通してしか見ることができない」と言っていたことを思い出した。だが、この文言は本書と矛盾しないと思っている。村上春樹と河合隼雄は”物語”というものを広義の意味で使用しているのに対し、本書では”物語”を狭義の意味で使っていると思う。村上春樹たちが使っていた”物語”を細分化すると、”物語”、”ゲーム”、”パズル”、”ギャンブル”、”おもちゃ遊び”になるのではないだろうか。 日々、漠然と考えていたことを言語化してくれたような読書体験だった。 - 2025年12月29日
 スラムに水は流れないヴァルシャ・バジャージ,村上利佳読み終わった@ シンガポール本作は、第1回「10代が選ぶ海外文学大賞」第一次投票のノミネート作品であり、中学生の夏休み読書感想文の課題図書にもなっているらしい。 中学生向けの小説ということもあり、スラムでの生活描写は過度に生々しいものではなく、物語は最終的に大団円で終わる。そこについてはあえて口を出すべきところではないだろう。 だが、気になった点が二つある。 一つ目は、主人公の父が持つ信条についてだ。父は「悪いものは見ない、悪いことは聞かない、言わないのが良い」という後ろ向きな考えを信じており、それを破ると災いを招くと本気で思っている。実際、主人公の兄はこの信条を破ったことでトラブルに巻き込まれ、一家は大きな危機に陥る。こうした展開を読むと、読者は「やはり余計なことには首を突っ込まない方がいいのだ」という印象を抱かざるを得ないだろう。物語の終盤でもこの信条は再び言及されるが、それを明確に打ち破るような出来事は描かれない。もし私が作者だったら、主人公か兄がもう一度あえて「悪いこと」に関わり、その行動によって事態が好転するエピソードを入れたと思う。 二つ目に気になったのは、父親がまったく家事をしない点と、それに対する問題提起が一切ないことだ。さまざまなトラブルの結果、主人公は勉強を続けながら働きに出ることになるが、水汲みという重要で重労働な家事まで、なぜか主人公一人が担うことになる。そこに父の姿はない。もともと母親が担っていた家事だからという理由で、娘である主人公が当然のように引き継ぐのだが、この家父長制を強く感じさせる場面に対して、批判的な描写や言葉が全くない。家事労働に関して、小説内では父親はまるで透明人間のように扱われている。 もっとも、こうした点を含めて批判的に読むことができる作品であるという意味では、読書感想文の題材としては適しているのかもしれない。
スラムに水は流れないヴァルシャ・バジャージ,村上利佳読み終わった@ シンガポール本作は、第1回「10代が選ぶ海外文学大賞」第一次投票のノミネート作品であり、中学生の夏休み読書感想文の課題図書にもなっているらしい。 中学生向けの小説ということもあり、スラムでの生活描写は過度に生々しいものではなく、物語は最終的に大団円で終わる。そこについてはあえて口を出すべきところではないだろう。 だが、気になった点が二つある。 一つ目は、主人公の父が持つ信条についてだ。父は「悪いものは見ない、悪いことは聞かない、言わないのが良い」という後ろ向きな考えを信じており、それを破ると災いを招くと本気で思っている。実際、主人公の兄はこの信条を破ったことでトラブルに巻き込まれ、一家は大きな危機に陥る。こうした展開を読むと、読者は「やはり余計なことには首を突っ込まない方がいいのだ」という印象を抱かざるを得ないだろう。物語の終盤でもこの信条は再び言及されるが、それを明確に打ち破るような出来事は描かれない。もし私が作者だったら、主人公か兄がもう一度あえて「悪いこと」に関わり、その行動によって事態が好転するエピソードを入れたと思う。 二つ目に気になったのは、父親がまったく家事をしない点と、それに対する問題提起が一切ないことだ。さまざまなトラブルの結果、主人公は勉強を続けながら働きに出ることになるが、水汲みという重要で重労働な家事まで、なぜか主人公一人が担うことになる。そこに父の姿はない。もともと母親が担っていた家事だからという理由で、娘である主人公が当然のように引き継ぐのだが、この家父長制を強く感じさせる場面に対して、批判的な描写や言葉が全くない。家事労働に関して、小説内では父親はまるで透明人間のように扱われている。 もっとも、こうした点を含めて批判的に読むことができる作品であるという意味では、読書感想文の題材としては適しているのかもしれない。 - 2025年12月29日
 名著でひらく男性学 <男>のこれからを考える天野諭,川口遼,杉田俊介,西井開読み終わった@ シンガポール「男性学」と聞くと、どこかインセル的な響きを感じてしまうのですが(ボクだけ?)、実際には、社会構造や歴史の捉え方など、多くの点でフェミニズムと重なり合う領域だと思います。 本書では、おすすめ書籍の紹介や対話を通じて、男性や男性性が抱える問題や課題が丁寧に掘り下げられています。 例えば、男性の身体や人格が軽視されがちな問題、「男性」と一括りにしてしまうことでマジョリティ性の交差性が見えにくくなる問題、ジェンダー平等を掲げながらも結果的に既存の差別構造を温存してしまう「リベラル・エリート男性」の問題など、フェミニズムだけでは十分に届かなかった論点が数多く提示されています。
名著でひらく男性学 <男>のこれからを考える天野諭,川口遼,杉田俊介,西井開読み終わった@ シンガポール「男性学」と聞くと、どこかインセル的な響きを感じてしまうのですが(ボクだけ?)、実際には、社会構造や歴史の捉え方など、多くの点でフェミニズムと重なり合う領域だと思います。 本書では、おすすめ書籍の紹介や対話を通じて、男性や男性性が抱える問題や課題が丁寧に掘り下げられています。 例えば、男性の身体や人格が軽視されがちな問題、「男性」と一括りにしてしまうことでマジョリティ性の交差性が見えにくくなる問題、ジェンダー平等を掲げながらも結果的に既存の差別構造を温存してしまう「リベラル・エリート男性」の問題など、フェミニズムだけでは十分に届かなかった論点が数多く提示されています。 - 2025年12月23日
- 2025年12月23日
- 2025年12月22日
 集団的自衛権はなぜ違憲なのか國分功一郎,木村草太読み終わった@ シンガポール当時、「限定された」集団的自衛権であると繰り返し言われていた真意が、この本を通じてやっとわかった。安保法制は曖昧な条項が多く、恣意的な運用がされそうな懸念があるものの、集団的自衛権が行使できるようにした違憲なものではなく、個別的自衛権としても認められるような事態の場合には、個別的自衛権、集団的自衛権のどちらを選択してもいいですよということらしい。 問題なのは、安倍さんや高市さんが、閣議や法律で制定した事項の解釈を(おそらく意図的に)歪め、存立危機事態の拡大、集団的自衛権の行使が行えるようにしようとしているところだ。たとえ台湾有事が起こっても、日本が攻撃されていない以上、軍事行為をすることは違憲であるし、現在の安保法制の規定をも破るものであるということだ。
集団的自衛権はなぜ違憲なのか國分功一郎,木村草太読み終わった@ シンガポール当時、「限定された」集団的自衛権であると繰り返し言われていた真意が、この本を通じてやっとわかった。安保法制は曖昧な条項が多く、恣意的な運用がされそうな懸念があるものの、集団的自衛権が行使できるようにした違憲なものではなく、個別的自衛権としても認められるような事態の場合には、個別的自衛権、集団的自衛権のどちらを選択してもいいですよということらしい。 問題なのは、安倍さんや高市さんが、閣議や法律で制定した事項の解釈を(おそらく意図的に)歪め、存立危機事態の拡大、集団的自衛権の行使が行えるようにしようとしているところだ。たとえ台湾有事が起こっても、日本が攻撃されていない以上、軍事行為をすることは違憲であるし、現在の安保法制の規定をも破るものであるということだ。
読み込み中...