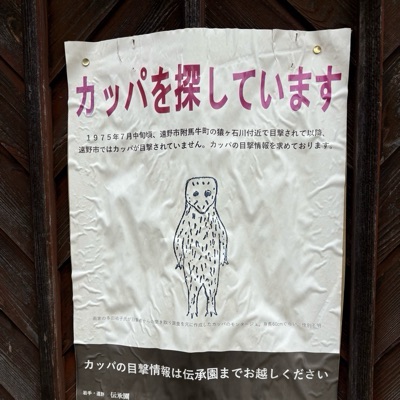ジョゼフ・コーネル 箱の中のユートピア

27件の記録
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月1日読み終わった晩年になってようやく名声やら評価やらを手に入れ始めたコーネルだが、それゆえかどんどん人との関わりを減らしていく。しかし学生を筆頭にした若者や子どもに対しては、むしろ積極的に関わっていく。もちろん、女性に対する偏執的で歪みのある愛情、あるいは性的欲求も変わらない。 ほとんど毎日、台所のテーブルで本を読んだり書きものをしたり、時折かかってくる電話に答えたりして、落ち着いた暮らしを送っていた。青いタオル地のバスローブを着たまま、ことさら何かに駆り立てられるかのように自分の見た夢を日記にしるした。弟や母の夢を見た。ジョイス・ハンターと一緒にストランド・フードショップでジュークボックスに耳を傾けている夢を見た。彼が日記をつけているのか、日記が彼を支えているのか、わからなくなっていた。(p.438)
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年6月1日読み終わった晩年になってようやく名声やら評価やらを手に入れ始めたコーネルだが、それゆえかどんどん人との関わりを減らしていく。しかし学生を筆頭にした若者や子どもに対しては、むしろ積極的に関わっていく。もちろん、女性に対する偏執的で歪みのある愛情、あるいは性的欲求も変わらない。 ほとんど毎日、台所のテーブルで本を読んだり書きものをしたり、時折かかってくる電話に答えたりして、落ち着いた暮らしを送っていた。青いタオル地のバスローブを着たまま、ことさら何かに駆り立てられるかのように自分の見た夢を日記にしるした。弟や母の夢を見た。ジョイス・ハンターと一緒にストランド・フードショップでジュークボックスに耳を傾けている夢を見た。彼が日記をつけているのか、日記が彼を支えているのか、わからなくなっていた。(p.438)







 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月31日まだ読んでる私たちが偉大な芸術家の伝記を読む理由のひとつは、彼らが周囲の人々の人生を壊していくのに魅了されるからである。「芸術は救いとなる」というが、芸術は人を傷つけることもある。ピカソ以降の近代芸術家たちの人生譚にはよく裏切られた妻や恋人、母親や子どもたちの涙を誘う物語がある。 コーネルはそれと正反対だった。驚くほどに自己中心的でなく、あきれるほど無私無欲なのだ。そして従順でおとなしく、無気力なまでに母親の計略に黙従するのである。(中略)。ウエストハンプトンから届く、情熱的でいびつな告白付きのコーネル夫人の手紙を読むと、彼女が息子にどれほど固執していたか、なぜ彼の女性関係が妄想のなかに閉じ込められていたのかが理解できよう。(p.412) 結局、芸術を生み出すには自分か他者かその両方を傷つけないとならないのか、と暗澹とした気持ちになってしまう。コーネルの母親もまた、なにか歪な構造のなかに強制的に身を置かれていたことを感じさせる。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月31日まだ読んでる私たちが偉大な芸術家の伝記を読む理由のひとつは、彼らが周囲の人々の人生を壊していくのに魅了されるからである。「芸術は救いとなる」というが、芸術は人を傷つけることもある。ピカソ以降の近代芸術家たちの人生譚にはよく裏切られた妻や恋人、母親や子どもたちの涙を誘う物語がある。 コーネルはそれと正反対だった。驚くほどに自己中心的でなく、あきれるほど無私無欲なのだ。そして従順でおとなしく、無気力なまでに母親の計略に黙従するのである。(中略)。ウエストハンプトンから届く、情熱的でいびつな告白付きのコーネル夫人の手紙を読むと、彼女が息子にどれほど固執していたか、なぜ彼の女性関係が妄想のなかに閉じ込められていたのかが理解できよう。(p.412) 結局、芸術を生み出すには自分か他者かその両方を傷つけないとならないのか、と暗澹とした気持ちになってしまう。コーネルの母親もまた、なにか歪な構造のなかに強制的に身を置かれていたことを感じさせる。







 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月29日まだ読んでるコーネルのアダルトチルドレン的な生育環境、つまりほぼ生涯を通じた母と弟へのケアを伴った生活は、結果として自身への極端な禁欲主義となり、さらに翻って他者への偏執的な感情と行為に転化された。被害と加害は切り離して考えるべきではない、少なくともそのようなパターンもある、ということを何度も考えさせられる終盤。残り3章ほど。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月29日まだ読んでるコーネルのアダルトチルドレン的な生育環境、つまりほぼ生涯を通じた母と弟へのケアを伴った生活は、結果として自身への極端な禁欲主義となり、さらに翻って他者への偏執的な感情と行為に転化された。被害と加害は切り離して考えるべきではない、少なくともそのようなパターンもある、ということを何度も考えさせられる終盤。残り3章ほど。









 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月21日読んでるまだ読んでるコーネルはそれまでシュルレアリスムと抽象表現主義というふたつの前衛運動のさなかで生き延びてきた。ひとつの運動の終焉はしばしば芸術家の衰退を運命づけ、そのキャリアの終焉を予兆する。しかし、どんな運動にも加わることのなかったコーネルは、いかなる運動が終わりを告げても破滅しなかった。(p.341) さみしさと勇気づけられが同居するなんとも言えない感情を抱かされる。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月21日読んでるまだ読んでるコーネルはそれまでシュルレアリスムと抽象表現主義というふたつの前衛運動のさなかで生き延びてきた。ひとつの運動の終焉はしばしば芸術家の衰退を運命づけ、そのキャリアの終焉を予兆する。しかし、どんな運動にも加わることのなかったコーネルは、いかなる運動が終わりを告げても破滅しなかった。(p.341) さみしさと勇気づけられが同居するなんとも言えない感情を抱かされる。




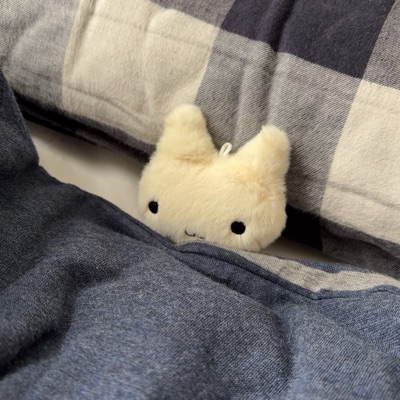
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月15日読んでるまだ読んでる今日もコーネルは展示のチャンスをダメにしている。ドロシー・ミラーという学芸員からの依頼に対し、 だがこれまで同様、コーネルは自分を「急がせる」ことはできないと主張して、彼女の仕事を台無しにしてしまう。彼はいかなる締切にも向き合えなかったのだ。そしてその展覧会を放棄した。(p.309) また、別の展示も断っている。しかし「自分の作品は「とてもゆっくりと熟す」というのが断りの理由であり、時期尚早だ」(p.309)というエピソードからは、なにか大事なことを言われている気もする。「とてもゆっくりと熟す」。これを信じ続けることは現代社会ではなおさら難しいが、だからこそそう信じることに意味があるかもしれない。とてもゆっくりと熟すものに対する辛抱強さ。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月15日読んでるまだ読んでる今日もコーネルは展示のチャンスをダメにしている。ドロシー・ミラーという学芸員からの依頼に対し、 だがこれまで同様、コーネルは自分を「急がせる」ことはできないと主張して、彼女の仕事を台無しにしてしまう。彼はいかなる締切にも向き合えなかったのだ。そしてその展覧会を放棄した。(p.309) また、別の展示も断っている。しかし「自分の作品は「とてもゆっくりと熟す」というのが断りの理由であり、時期尚早だ」(p.309)というエピソードからは、なにか大事なことを言われている気もする。「とてもゆっくりと熟す」。これを信じ続けることは現代社会ではなおさら難しいが、だからこそそう信じることに意味があるかもしれない。とてもゆっくりと熟すものに対する辛抱強さ。







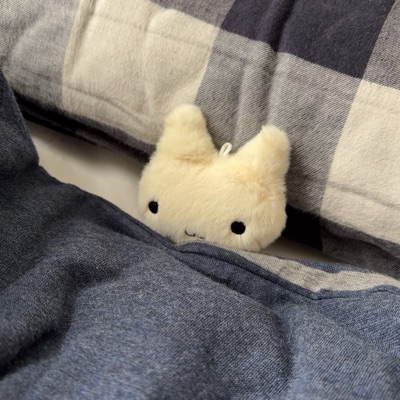
 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月10日読んでるまだ読んでる図書館の児童書室で企画しているおとぎ話の展覧会を手伝うことを安請け合いしたコーネルだが、 結局このプロジェクトは彼の怠け癖の犠牲になってしまう。司書が後に年報に記したように「彼は、周囲の壁面を大きな絵のようなもので飾り、部屋をおとぎの国に変えたいと提案してきました。しかしながら、コーネル氏はある日、児童書室にやってきて(展覧会が始まる直前のことです)、絵はまだできていない、締切を守ることを考えるだけで描けなくなってしまうと口にしたのです。私たちは、急いで頭のなかで計算しました」。ずっと仕事をしていなかったのを弁明するのに「締切」という言葉を使うのを、彼女はそれまで他の誰からも聞いたことはなかっただろう。(p.263-264) と、今日もディスられるコーネル。しかしこれはコーネルが悪い。とはいえかわいさも感じてしまう。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月10日読んでるまだ読んでる図書館の児童書室で企画しているおとぎ話の展覧会を手伝うことを安請け合いしたコーネルだが、 結局このプロジェクトは彼の怠け癖の犠牲になってしまう。司書が後に年報に記したように「彼は、周囲の壁面を大きな絵のようなもので飾り、部屋をおとぎの国に変えたいと提案してきました。しかしながら、コーネル氏はある日、児童書室にやってきて(展覧会が始まる直前のことです)、絵はまだできていない、締切を守ることを考えるだけで描けなくなってしまうと口にしたのです。私たちは、急いで頭のなかで計算しました」。ずっと仕事をしていなかったのを弁明するのに「締切」という言葉を使うのを、彼女はそれまで他の誰からも聞いたことはなかっただろう。(p.263-264) と、今日もディスられるコーネル。しかしこれはコーネルが悪い。とはいえかわいさも感じてしまう。










 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月9日読んでるまだ読んでるコーネルが〈鳥小屋〉シリーズという新機軸を打ち立てたことを賛美とまではいかないがそれなりにアゲアゲのテンションで書き記しているなかに、突如としてあらわれるディスり。「普段はぐずぐずしがちなコーネルも、状況に応じてさっさと仕事を済ませることができたらしい」(p.247)。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月9日読んでるまだ読んでるコーネルが〈鳥小屋〉シリーズという新機軸を打ち立てたことを賛美とまではいかないがそれなりにアゲアゲのテンションで書き記しているなかに、突如としてあらわれるディスり。「普段はぐずぐずしがちなコーネルも、状況に応じてさっさと仕事を済ませることができたらしい」(p.247)。





 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月7日読んでるまだ読んでるコーネルのアンに対する振る舞いには、恋をしたいという欲望と、かつそうした欲望をこそこそした形でしか満たすことができなかったという事実とがともども集約されている。女性と関係をもつなどということは及びもつかなかったが、性的な事柄にはずっと強い興味を抱いていたようだ。この興味を満たすにあたって彼は、「視覚的な所有」とでも呼べそうな行為をもって対処した。女性をじっと見つめ、そのイメージを自分の内側にある美術館に収めるのである。そうすればいくらでも眺め、あれこれ操作することができ、かつ何か危険な結果になるのを恐れる必要もなかった。コーネルは自分が生身の女性を所有できるなどとは考えていなかった。(p.200) 選択的夫婦別姓に強い拒否感を抱くような男性は、おそらく女性を所有したい=支配したいという欲求に突き動かされている。あるいはそれは、自分の魅力のなさや、そのことで離れられてしまうことへの不安感を解消するために、強制的な所有のシステムを必要とする、ということなのかもしれない。このあたり、コーネルは自身の欲求が加害になりうる可能性を知っていたのか、結果として適切な(と思われる)距離感を維持する方法を芸術制作に見出している。しかしなんとも言えない気持ちの悪さは残っていて、それがこの本の書き手による描写がそうさせるのか、そもそも「まなざす」という行為に本質的に備わっている危険性なのか、そのあたりははっきりしない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月7日読んでるまだ読んでるコーネルのアンに対する振る舞いには、恋をしたいという欲望と、かつそうした欲望をこそこそした形でしか満たすことができなかったという事実とがともども集約されている。女性と関係をもつなどということは及びもつかなかったが、性的な事柄にはずっと強い興味を抱いていたようだ。この興味を満たすにあたって彼は、「視覚的な所有」とでも呼べそうな行為をもって対処した。女性をじっと見つめ、そのイメージを自分の内側にある美術館に収めるのである。そうすればいくらでも眺め、あれこれ操作することができ、かつ何か危険な結果になるのを恐れる必要もなかった。コーネルは自分が生身の女性を所有できるなどとは考えていなかった。(p.200) 選択的夫婦別姓に強い拒否感を抱くような男性は、おそらく女性を所有したい=支配したいという欲求に突き動かされている。あるいはそれは、自分の魅力のなさや、そのことで離れられてしまうことへの不安感を解消するために、強制的な所有のシステムを必要とする、ということなのかもしれない。このあたり、コーネルは自身の欲求が加害になりうる可能性を知っていたのか、結果として適切な(と思われる)距離感を維持する方法を芸術制作に見出している。しかしなんとも言えない気持ちの悪さは残っていて、それがこの本の書き手による描写がそうさせるのか、そもそも「まなざす」という行為に本質的に備わっている危険性なのか、そのあたりははっきりしない。









 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月5日読んでるまだ読んでる一九四二年ほどアメリカ美術が活況を呈した年も稀だった。ひとつには、立役者たちがアメリカ人ではなかったという事情がある。主役だったのはむしろ、このころニューヨークにたどりついたヨーロッパ人たちだった。フランスの敗北後、芸術家や知識人たちが大挙して祖国を逃れてきていた。(p.171) 国外に逃げられるだけの地位や財産などがあるということ、そしてアメリカもまた戦争当事国であるにもかかわらず逃げ場にできたということ、そして戦争中でも芸術界が賑わっていたということ、などなどにあらためて日本の状況との差を感じる。「三巨頭――ピカソ、ミロ、マティス――はヨーロッパにとどまり、名声に守られて安全に暮らしていた」(同)という事実もまた、安全が確保される者とそうではない者の隔絶を突きつけられる。偉くなれば生き残りやすくなるこの世界のシステムは明確に倫理的ではないが、それを転覆させる方法がわからない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月5日読んでるまだ読んでる一九四二年ほどアメリカ美術が活況を呈した年も稀だった。ひとつには、立役者たちがアメリカ人ではなかったという事情がある。主役だったのはむしろ、このころニューヨークにたどりついたヨーロッパ人たちだった。フランスの敗北後、芸術家や知識人たちが大挙して祖国を逃れてきていた。(p.171) 国外に逃げられるだけの地位や財産などがあるということ、そしてアメリカもまた戦争当事国であるにもかかわらず逃げ場にできたということ、そして戦争中でも芸術界が賑わっていたということ、などなどにあらためて日本の状況との差を感じる。「三巨頭――ピカソ、ミロ、マティス――はヨーロッパにとどまり、名声に守られて安全に暮らしていた」(同)という事実もまた、安全が確保される者とそうではない者の隔絶を突きつけられる。偉くなれば生き残りやすくなるこの世界のシステムは明確に倫理的ではないが、それを転覆させる方法がわからない。






 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月2日読んでるまだ読んでるコーネルの女性に対するある種偏執的な関わり方は、どこかプルーストの「私」を思わせる。実際になにか行動を起こすわけではなく、基本的には自己完結する営みではあるものの、加害性すら伴うmale gazeであることも確かであり、手放しで賛美することはできないものである。憧れのバレエダンサーに初めて会った際に「現実の生きたバレリーナと初めて出会ってびっくりしたコーネルは、ぎこちなく「五歩も後ずさりした」とトゥマノワは後年回想している」(p.157)と書かれるほどには、実際の対象=女性とは距離を置きたがるコーネルを見ていると、成育環境、特にコーネルに関しては母親との関係性が強く影響を与えているらしく、抱え持ってしまう加害性を当人だけの責任とするのもやはり非情すぎるな、と朝から真剣に考えてしまう。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年5月2日読んでるまだ読んでるコーネルの女性に対するある種偏執的な関わり方は、どこかプルーストの「私」を思わせる。実際になにか行動を起こすわけではなく、基本的には自己完結する営みではあるものの、加害性すら伴うmale gazeであることも確かであり、手放しで賛美することはできないものである。憧れのバレエダンサーに初めて会った際に「現実の生きたバレリーナと初めて出会ってびっくりしたコーネルは、ぎこちなく「五歩も後ずさりした」とトゥマノワは後年回想している」(p.157)と書かれるほどには、実際の対象=女性とは距離を置きたがるコーネルを見ていると、成育環境、特にコーネルに関しては母親との関係性が強く影響を与えているらしく、抱え持ってしまう加害性を当人だけの責任とするのもやはり非情すぎるな、と朝から真剣に考えてしまう。




 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月30日読んでるまだ読んでる久しぶりのコーネル。ダリに酷いことを言われてるのを見てから2週間も経っていた。コーネルは複写写真という、いわばコピーのコピーを使って作品を制作していた。それは実際には倹約のためだったのだけど、のちに「オリジナルの意味について重要な問題提起を行なっていた」(p.142)として、美術史的にモダニズムの先駆けなのではないかと考えられるようになった、というのがおもしろい。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月30日読んでるまだ読んでる久しぶりのコーネル。ダリに酷いことを言われてるのを見てから2週間も経っていた。コーネルは複写写真という、いわばコピーのコピーを使って作品を制作していた。それは実際には倹約のためだったのだけど、のちに「オリジナルの意味について重要な問題提起を行なっていた」(p.142)として、美術史的にモダニズムの先駆けなのではないかと考えられるようになった、というのがおもしろい。








 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月16日読んでるまだ読んでるコーネルのアーティスト仲間のなかにはリー・ミラーもいるとのことで驚いた。リー・ミラーのことをよく知っているかのような書きぶりだが、近々公開される伝記映画の予告を見てその存在を知ったばかりだから驚いているだけである。 なお、コーネルは自作映画をダリに「このアイデアはおれがやろうとしてたことだ!盗まれた!」と激昂され落ち込んでいる。ダリ、ひどいやつだ。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月16日読んでるまだ読んでるコーネルのアーティスト仲間のなかにはリー・ミラーもいるとのことで驚いた。リー・ミラーのことをよく知っているかのような書きぶりだが、近々公開される伝記映画の予告を見てその存在を知ったばかりだから驚いているだけである。 なお、コーネルは自作映画をダリに「このアイデアはおれがやろうとしてたことだ!盗まれた!」と激昂され落ち込んでいる。ダリ、ひどいやつだ。





 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月14日読んでるまだ読んでる第4章。コーネルが初の展覧会に参加するも、主催者の紹介文が本質を見誤った陳腐なもので、長年その印象がつきまとってしまったことなどが書かれている。これもまたナラティヴ。そして本屋としても、適切におそれなくてはならないエピソードだ。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月14日読んでるまだ読んでる第4章。コーネルが初の展覧会に参加するも、主催者の紹介文が本質を見誤った陳腐なもので、長年その印象がつきまとってしまったことなどが書かれている。これもまたナラティヴ。そして本屋としても、適切におそれなくてはならないエピソードだ。






 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月13日第2章はコーネルが13歳になり、寄宿制私立学校に通わされることになる場面から始まる。父親が死に、その雇い主だったクンハートという男が「男らしい目標や助言を与えるという意味で有益である、同じ年頃の活発な少年たちに囲まれることはジョゼフが悲嘆から抜け出すにもきっと役に立つ」(p.36)と考え、そうするように金まで出したらしい。1917年といえば第一次大戦のさなかであり、ヨーロッパではこの戦争によって「男らしさ」を競い合ってきた男たちの多くがシェル・ショック状態となり帰国した。コーネルのいたアメリカも同様だったはずだし、その反省もなしにベトナム戦争によるPTSDまで突き進むのだから、人類、なにがよろしくないのかわかってないとしか思えない(そしてPTSDという概念および症状は「ベトナム戦争においてアメリカは被害者なのだ」というナラティヴを構築することにも役立ってしまった、ということが『ナラティヴの被害学』では書かれていた)。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月13日第2章はコーネルが13歳になり、寄宿制私立学校に通わされることになる場面から始まる。父親が死に、その雇い主だったクンハートという男が「男らしい目標や助言を与えるという意味で有益である、同じ年頃の活発な少年たちに囲まれることはジョゼフが悲嘆から抜け出すにもきっと役に立つ」(p.36)と考え、そうするように金まで出したらしい。1917年といえば第一次大戦のさなかであり、ヨーロッパではこの戦争によって「男らしさ」を競い合ってきた男たちの多くがシェル・ショック状態となり帰国した。コーネルのいたアメリカも同様だったはずだし、その反省もなしにベトナム戦争によるPTSDまで突き進むのだから、人類、なにがよろしくないのかわかってないとしか思えない(そしてPTSDという概念および症状は「ベトナム戦争においてアメリカは被害者なのだ」というナラティヴを構築することにも役立ってしまった、ということが『ナラティヴの被害学』では書かれていた)。








 本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月12日読み始めたDIC川村記念美術館に行ったときに勢いで買ったのを、なんとなく勢いで読み始める。このジョゼフ・コーネルというアーティストのことはほとんど知らず、ただただユートピアという文字に引きつけられただけではあるが、そういうものこそおもしろい事態を生じさせたりもする。 昔から伝記の使命は、芸術と人生の間につながりを見出し、どのようにして日常的な出来事が芸術家の作品に形を与えるかを論証することであった。けれど、たとえ「実生活」が芸術家の作品に影響を与えているとしても、それによって作品を完全に説明することはできない。実のところ、芸術とその中に潜在する夢想が人生に形を与えることも、その逆もありうるのだ。 デボラ・ソロモン『ジョゼフ・コーネル 箱の中のユートピア』(白水社)p.34 オスカー・ワイルドの言う「芸術が人生を模倣するのではなく、人生が芸術を模倣する」的なものに通ずる箇所だった。学生時代にはほとんどわからなかったワイルドの話が、いまはもう少しわかるかもしれない。
本屋lighthouse@books-lighthouse2025年4月12日読み始めたDIC川村記念美術館に行ったときに勢いで買ったのを、なんとなく勢いで読み始める。このジョゼフ・コーネルというアーティストのことはほとんど知らず、ただただユートピアという文字に引きつけられただけではあるが、そういうものこそおもしろい事態を生じさせたりもする。 昔から伝記の使命は、芸術と人生の間につながりを見出し、どのようにして日常的な出来事が芸術家の作品に形を与えるかを論証することであった。けれど、たとえ「実生活」が芸術家の作品に影響を与えているとしても、それによって作品を完全に説明することはできない。実のところ、芸術とその中に潜在する夢想が人生に形を与えることも、その逆もありうるのだ。 デボラ・ソロモン『ジョゼフ・コーネル 箱の中のユートピア』(白水社)p.34 オスカー・ワイルドの言う「芸術が人生を模倣するのではなく、人生が芸術を模倣する」的なものに通ずる箇所だった。学生時代にはほとんどわからなかったワイルドの話が、いまはもう少しわかるかもしれない。