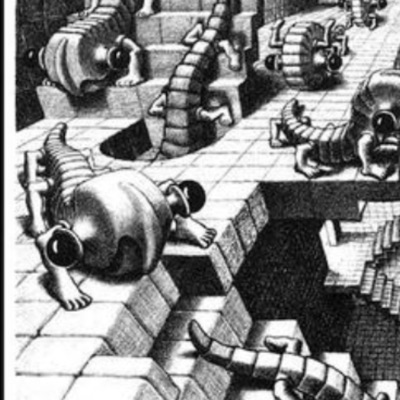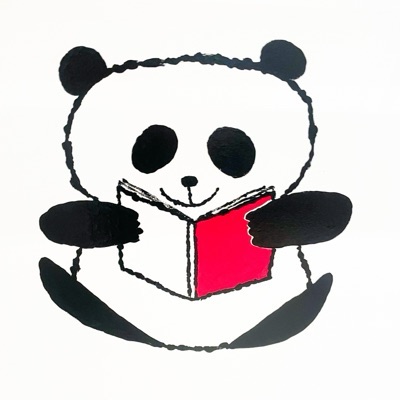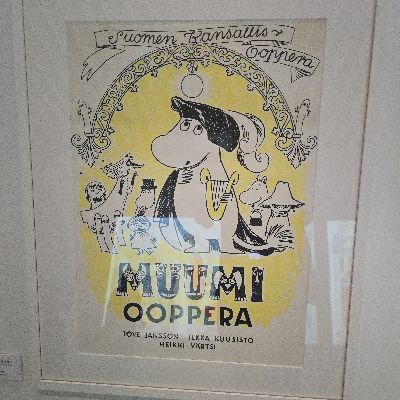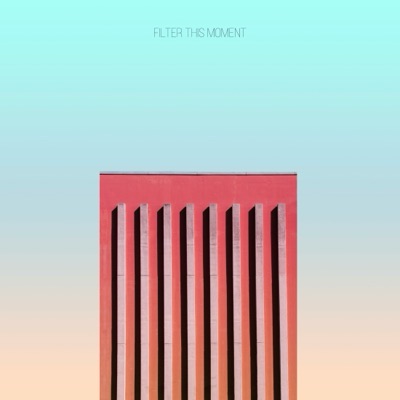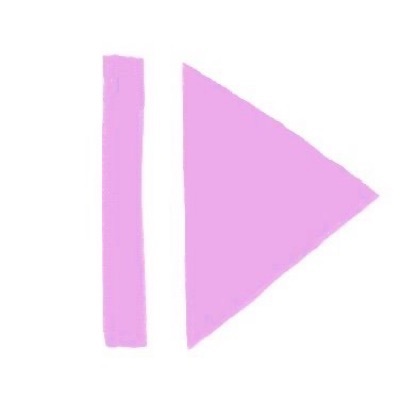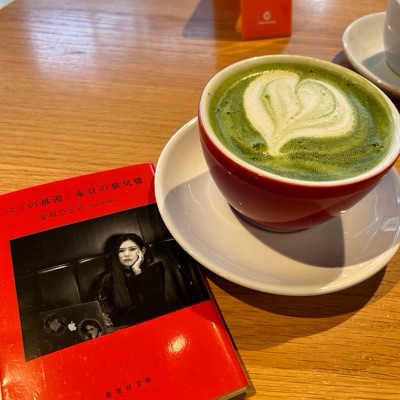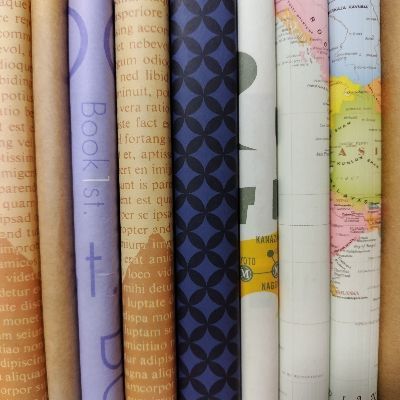エビデンスを嫌う人たち

84件の記録
 Moonflower@Moonflower02262026年2月21日読み終わった第4章 気候変動を否定する人たち 〜 第8章 新型コロナウイルスと私たちのこれから 【感想】 科学哲学者による、科学否定論者との対話を理論と行動から綴った体験的ノンフィクションにして、他者との真摯な関係構築を提案する警世の書。 第2,3章が理論編で、残りが実践編と大まかに言える。後者はところにより語り口も軽妙で楽しく読めた。(ただし、科学哲学を知らないと読みにくく思えるであろう箇所はいくつもあるので、著者の旧著を読んでおくといいかもしれない) フラットアース(地球平面説)、気候変動否定、反GMO(遺伝子組換え作物)、反ワクチン、またそれらに共通する陰謀論といった科学否定論が語られるが、それらを珍奇なトンデモ言説として斥けるのではなく、なぜそのようなものを信じる(信じるに至った)のか、またどうしたらその考えを変えることができるのか、著者は対話を通じて真摯に探っていく。 執筆時期が第一期トランプ政権と重なっているため、アメリカが被った大きな転換期のドキュメントともなっている。 科学否定論者の五つの類型(①証拠のチェリーピッキング、②陰謀論への傾倒、③偽物の専門家への依存、④非論理的な推論、⑤科学への現実離れした期待)や、信念形成におけるアイデンティティの中心的役割、確信を変えるのは情報ではなく信頼であることなど、理論編から学ぶことは多々あった。 ただ、本書の素晴らしさは実践編にある。真摯な対話を重ね、様々な推測と思索を巡らせる著者の姿に感銘を受けた。 もっとも、著者が対峙したのは知的な人がほとんどで、言うなればもっと「考えが凝り固まった」人たちはほぼ(冒頭のフラットアーサー以外は)出てこない。なので、本書は哲学者による電波系陰謀論者ぶった斬り武勇伝みたいなものではない。むしろ、そうした信念を抱くに至った経緯に関心を示すことで、他者に心を開いてもらうことからすべては始まるのだと本書は語っている。 その実践は誰にとっても困難だろうが、それでも理論編で得た知識や実践編での悪戦苦闘ぶりは参考になるはず。SNS全盛/AI興隆の現代にあって、本書が愚直に示す「真摯さ」は眩しくも儚い(かもしれない)が、だからこそ重要なのだと思えてならない。
Moonflower@Moonflower02262026年2月21日読み終わった第4章 気候変動を否定する人たち 〜 第8章 新型コロナウイルスと私たちのこれから 【感想】 科学哲学者による、科学否定論者との対話を理論と行動から綴った体験的ノンフィクションにして、他者との真摯な関係構築を提案する警世の書。 第2,3章が理論編で、残りが実践編と大まかに言える。後者はところにより語り口も軽妙で楽しく読めた。(ただし、科学哲学を知らないと読みにくく思えるであろう箇所はいくつもあるので、著者の旧著を読んでおくといいかもしれない) フラットアース(地球平面説)、気候変動否定、反GMO(遺伝子組換え作物)、反ワクチン、またそれらに共通する陰謀論といった科学否定論が語られるが、それらを珍奇なトンデモ言説として斥けるのではなく、なぜそのようなものを信じる(信じるに至った)のか、またどうしたらその考えを変えることができるのか、著者は対話を通じて真摯に探っていく。 執筆時期が第一期トランプ政権と重なっているため、アメリカが被った大きな転換期のドキュメントともなっている。 科学否定論者の五つの類型(①証拠のチェリーピッキング、②陰謀論への傾倒、③偽物の専門家への依存、④非論理的な推論、⑤科学への現実離れした期待)や、信念形成におけるアイデンティティの中心的役割、確信を変えるのは情報ではなく信頼であることなど、理論編から学ぶことは多々あった。 ただ、本書の素晴らしさは実践編にある。真摯な対話を重ね、様々な推測と思索を巡らせる著者の姿に感銘を受けた。 もっとも、著者が対峙したのは知的な人がほとんどで、言うなればもっと「考えが凝り固まった」人たちはほぼ(冒頭のフラットアーサー以外は)出てこない。なので、本書は哲学者による電波系陰謀論者ぶった斬り武勇伝みたいなものではない。むしろ、そうした信念を抱くに至った経緯に関心を示すことで、他者に心を開いてもらうことからすべては始まるのだと本書は語っている。 その実践は誰にとっても困難だろうが、それでも理論編で得た知識や実践編での悪戦苦闘ぶりは参考になるはず。SNS全盛/AI興隆の現代にあって、本書が愚直に示す「真摯さ」は眩しくも儚い(かもしれない)が、だからこそ重要なのだと思えてならない。 トラ@Toreads12342026年2月8日フラットアーサー、反気候変動説、反コロナ、反GMO(遺伝子組み換え作物)など、科学否定論者の人達とどう向き合うかという話。 それぞれの人の内部に、どこまで入り込んでいるかによって対処が変わる。知識のみの人には、明確なデータを。アイデンティティにまで食い込んでいる人には信頼のある対話を。 自分も見失いそうになってしまうが、科学とは絶対ではなく、現在のデータから導かれる暫定的な結論であるということを忘れると、そこから反〇〇の思想は入り込んできてしまう。曖昧なものをとりあえず受け入れて、主流の考え(データが支持する考え)を取り入れる。主流の説に鮮やかな反論が一つあったからといって、その反論を支持するのは危うい。その反論に科学的なフォローが積み重なっていったときに再考するのがいいと思う。科学的とはどういうことかを考えるきっかけになった。 アメリカの事例だからピンとこない部分も多い。「アル・ゴア」という名前を出されてもその立ち位置が一瞬でわからないように、著者の常識と自分の常識には大きな隔たりがあり、読みやすくはなかった。個人の思考の癖として「〇〇否定論者は、△△を否定しない。」のように、否定の否定みたいな文章が多くて、それが思いの外、読む時の負荷になった。
トラ@Toreads12342026年2月8日フラットアーサー、反気候変動説、反コロナ、反GMO(遺伝子組み換え作物)など、科学否定論者の人達とどう向き合うかという話。 それぞれの人の内部に、どこまで入り込んでいるかによって対処が変わる。知識のみの人には、明確なデータを。アイデンティティにまで食い込んでいる人には信頼のある対話を。 自分も見失いそうになってしまうが、科学とは絶対ではなく、現在のデータから導かれる暫定的な結論であるということを忘れると、そこから反〇〇の思想は入り込んできてしまう。曖昧なものをとりあえず受け入れて、主流の考え(データが支持する考え)を取り入れる。主流の説に鮮やかな反論が一つあったからといって、その反論を支持するのは危うい。その反論に科学的なフォローが積み重なっていったときに再考するのがいいと思う。科学的とはどういうことかを考えるきっかけになった。 アメリカの事例だからピンとこない部分も多い。「アル・ゴア」という名前を出されてもその立ち位置が一瞬でわからないように、著者の常識と自分の常識には大きな隔たりがあり、読みやすくはなかった。個人の思考の癖として「〇〇否定論者は、△△を否定しない。」のように、否定の否定みたいな文章が多くて、それが思いの外、読む時の負荷になった。
 Nada_Reads@Nada_Masa2025年11月19日読み終わったコロナ禍以降陰謀論を声高に叫ぶ人について興味が出てきたので購入。 極論を言う人に対しては対話して信頼を得るところからスタートしよう、というわりと普通の結論でした。結局この作者も対話で陰謀論から脱却させることも出来てないので、この本の構成は経験や思考の置き場であって実用性を求めるものではないのかもしれない。 フラットアース国際会議潜入の章は面白かったのですが、中盤での炭鉱で働く人たちを会う前からトランプ主義者だと決めつけてかかっていたり、モルディブの現地民への振る舞いなど、この作者も結構偏ってるな〜と感じるところもしばしば。 否定論者の5つの特徴は勉強になりました。科学に無知だからこそ科学に完全性を求めるのは陰謀論界隈でよく見かけますね。
Nada_Reads@Nada_Masa2025年11月19日読み終わったコロナ禍以降陰謀論を声高に叫ぶ人について興味が出てきたので購入。 極論を言う人に対しては対話して信頼を得るところからスタートしよう、というわりと普通の結論でした。結局この作者も対話で陰謀論から脱却させることも出来てないので、この本の構成は経験や思考の置き場であって実用性を求めるものではないのかもしれない。 フラットアース国際会議潜入の章は面白かったのですが、中盤での炭鉱で働く人たちを会う前からトランプ主義者だと決めつけてかかっていたり、モルディブの現地民への振る舞いなど、この作者も結構偏ってるな〜と感じるところもしばしば。 否定論者の5つの特徴は勉強になりました。科学に無知だからこそ科学に完全性を求めるのは陰謀論界隈でよく見かけますね。
 キシハル@kishihal192025年11月11日かつて読んだ陰謀論について興味津々な人間にはめちゃくちゃ面白かった。 図書館の返却期限に迫られていたので慌てており、もっと考えて読みたい部分もあった。 ちょっと難しく感じたところもあったから調べたかったかも。 こういうのがあると本買った方がいいなと思う。 対話が大事!!
キシハル@kishihal192025年11月11日かつて読んだ陰謀論について興味津々な人間にはめちゃくちゃ面白かった。 図書館の返却期限に迫られていたので慌てており、もっと考えて読みたい部分もあった。 ちょっと難しく感じたところもあったから調べたかったかも。 こういうのがあると本買った方がいいなと思う。 対話が大事!! 白玉庵@shfttg2025年11月10日読み終わった長い付き合いの人たちのなかで、コロナを契機として陰謀論的な考え方が明らかになり付き合わなくなった人がいる。 また、最近の差別を公然と口にする風潮のなかで、いい人なのに、根拠のない外国人への反感を普段の会話で出してくる人がいる。 そういう人たちへの対処として、私は、特に困る訳でもないので、こちらからは誘わずフェードアウトするという方法を取っていた。この本を読んで虚を突かれたのは、GMO農作物に対する自分の態度が、ワクチン反対派と同じふるまいであったこと。それで慌ててGMO農作物について考え直す必要がでてきた。 この、自分に引き寄せて別な視点で見直しをする機会を提供するという考えがあれば、意見に賛同できない友人からフェードアウトせずに対話を続けることができるのかもしれない。 放置しておけば、巡り巡って、おかしな人が当選する原動力になったりして結局自分の生活に影響があるのだ。
白玉庵@shfttg2025年11月10日読み終わった長い付き合いの人たちのなかで、コロナを契機として陰謀論的な考え方が明らかになり付き合わなくなった人がいる。 また、最近の差別を公然と口にする風潮のなかで、いい人なのに、根拠のない外国人への反感を普段の会話で出してくる人がいる。 そういう人たちへの対処として、私は、特に困る訳でもないので、こちらからは誘わずフェードアウトするという方法を取っていた。この本を読んで虚を突かれたのは、GMO農作物に対する自分の態度が、ワクチン反対派と同じふるまいであったこと。それで慌ててGMO農作物について考え直す必要がでてきた。 この、自分に引き寄せて別な視点で見直しをする機会を提供するという考えがあれば、意見に賛同できない友人からフェードアウトせずに対話を続けることができるのかもしれない。 放置しておけば、巡り巡って、おかしな人が当選する原動力になったりして結局自分の生活に影響があるのだ。






 橋本吉央@yoshichiha2025年10月18日読み終わった『知ってるつもりーー無知の科学』でもあったが、反科学的な態度をとる人=科学的な知識が足りていない人、とみなしてその知識の欠乏を埋めれば良いという「欠乏モデル」はうまくいかないということが全体を通して明確に書かれている。 対抗するためには、反科学的な言説の内容だけでなく、その言説が依拠している誤ったアプローチ自体を批判するのが有効であること、ただし攻撃的にではなく、リスペクトと信頼を示しながらの態度が重要である、と。 本当に、反科学的な姿勢だけでなく、自分に理解が及ばないものについて「おかしい、馬鹿だ」と捉えてポジションを決めて振る舞うことの危うさも、誰もが内省する必要があるだろうなと思う。
橋本吉央@yoshichiha2025年10月18日読み終わった『知ってるつもりーー無知の科学』でもあったが、反科学的な態度をとる人=科学的な知識が足りていない人、とみなしてその知識の欠乏を埋めれば良いという「欠乏モデル」はうまくいかないということが全体を通して明確に書かれている。 対抗するためには、反科学的な言説の内容だけでなく、その言説が依拠している誤ったアプローチ自体を批判するのが有効であること、ただし攻撃的にではなく、リスペクトと信頼を示しながらの態度が重要である、と。 本当に、反科学的な姿勢だけでなく、自分に理解が及ばないものについて「おかしい、馬鹿だ」と捉えてポジションを決めて振る舞うことの危うさも、誰もが内省する必要があるだろうなと思う。


 橋本吉央@yoshichiha2025年10月18日まだ読んでるフラットアースの話から始まるが、改めてアメリカって宗教大国だなあと思う。神によるインテリジェント・デザインの話が進化論と拮抗しうるというあたりとか特に。一神教は大変だ。 単に科学否定論者を論評するのではなく、対話と説得を試みようとするというプロセスが新しい。そういう実践を経ているからこそ、お互いのリスペクトと対話が大事だ、という言葉に納得感が出る。
橋本吉央@yoshichiha2025年10月18日まだ読んでるフラットアースの話から始まるが、改めてアメリカって宗教大国だなあと思う。神によるインテリジェント・デザインの話が進化論と拮抗しうるというあたりとか特に。一神教は大変だ。 単に科学否定論者を論評するのではなく、対話と説得を試みようとするというプロセスが新しい。そういう実践を経ているからこそ、お互いのリスペクトと対話が大事だ、という言葉に納得感が出る。

 semi@hirakegoma2025年7月12日読み終わったちびちび読み進め、わりと時間がかかった… 洋書の翻訳は文体なのか構成なのか、本の雰囲気が自分にハマらないとうまく乗ってこない感じがある。 新型コロナが流行していたころから、科学コミュニケーションと陰謀論(という現象)に興味があった。本書のタイトルにそそられて購入。 フラットアースに始まり、色んな人と関わっていくノンフィクション。通読した後だと、原題の"How to Talk to a Science Denier"がしっくりくる。解説にもあるが、まさに現象を外から見ようとするものではなく、積極的に会話する、関わっていくための本だ。 まずは、繰り返し出てくる5つの類型については、その公式に当てはめるだけで現象が整理され、非常にわかりやすく、なるほど!という感じ。これを知っているだけで世の中の科学否定がとらえやすくなった。 また、科学否定の問題というよりはアイデンティティの問題だと理解すること。これも非常に重要だと思うし、何となく理解できる。アイデンティティの問題だとすれば、自分にもすぐ身近に科学否定はある、ということを実感する。 私自身は、この本を読んでから、科学否定に対して距離が縮まった気がする。
semi@hirakegoma2025年7月12日読み終わったちびちび読み進め、わりと時間がかかった… 洋書の翻訳は文体なのか構成なのか、本の雰囲気が自分にハマらないとうまく乗ってこない感じがある。 新型コロナが流行していたころから、科学コミュニケーションと陰謀論(という現象)に興味があった。本書のタイトルにそそられて購入。 フラットアースに始まり、色んな人と関わっていくノンフィクション。通読した後だと、原題の"How to Talk to a Science Denier"がしっくりくる。解説にもあるが、まさに現象を外から見ようとするものではなく、積極的に会話する、関わっていくための本だ。 まずは、繰り返し出てくる5つの類型については、その公式に当てはめるだけで現象が整理され、非常にわかりやすく、なるほど!という感じ。これを知っているだけで世の中の科学否定がとらえやすくなった。 また、科学否定の問題というよりはアイデンティティの問題だと理解すること。これも非常に重要だと思うし、何となく理解できる。アイデンティティの問題だとすれば、自分にもすぐ身近に科学否定はある、ということを実感する。 私自身は、この本を読んでから、科学否定に対して距離が縮まった気がする。




 amy@note_15812025年6月29日読み終わった感想読んだ。いや~~~~~~~よかった。読んでよかった。これは保守的な人たちや右派に腹立ててるリベラル左派の人こそ読むべき 陰謀論や科学否定論者に対して正しさは通じない。彼らにとって支持している陰謀論や科学を否定する言説はその人自身のアイデンティティと密接に結びついてるという。今まで生きてきた環境、生育歴、受けてきた教育、人間関係、職場の状況などなど。その人の人生と生活に根ざしたアイデンティティに関わる部分であるから、"正しさ”で説得しようとしても意味がなく、むしろ態度を硬化させてしまうという。こういった人たちにはどういう手立てを講じるべきかというと、何よりも大事なのは信頼関係である。その人の考えや言葉に敬意を払うこと、抱いた感情を尊重すること、そうして対面で会話を重ねて、信頼関係を築くことでしか、その人の主張や信じている説を変えられない 知識がないなんて馬鹿にするのは持ってのほかだという。本書からの引用だが"信念を理由に相手を侮辱したり、恥をかかせたりするのは、あきらかな間違いだ。"と書かれているのだ 都知事選のころなどから一部の左派リベラルの人たちが自分たちとは異なる主義主張の人を揶揄する様子を見てきた 私個人としても人間には感情があり、正しさだけで世の中の差別や偏見が解決できるなら、とっくに世の中は穏やかなものになっているだろと思う そして陰謀論や科学否定に走るのは保守派や右派だけではないともこの本には書かれている。この本を読んでいて気分が悪くなったり、耳に痛いと思うリベラル左派もいるだろうけど、まさにそういうリアクションを催し、自分の支持しない説を差し出されると突っぱねるのは左右や保守やリベラルは関係ない ちょうど先日某SNSで正しい情報だけでは相手の主義主張に変化を起こせない、態度が大切であるという研究結果を見たリベラル左派の人は『こういうファクトベースの話ではなく~』などと言っていたので、まさに『エビデンスを嫌う人たち』だなあと私は思ったんであった
amy@note_15812025年6月29日読み終わった感想読んだ。いや~~~~~~~よかった。読んでよかった。これは保守的な人たちや右派に腹立ててるリベラル左派の人こそ読むべき 陰謀論や科学否定論者に対して正しさは通じない。彼らにとって支持している陰謀論や科学を否定する言説はその人自身のアイデンティティと密接に結びついてるという。今まで生きてきた環境、生育歴、受けてきた教育、人間関係、職場の状況などなど。その人の人生と生活に根ざしたアイデンティティに関わる部分であるから、"正しさ”で説得しようとしても意味がなく、むしろ態度を硬化させてしまうという。こういった人たちにはどういう手立てを講じるべきかというと、何よりも大事なのは信頼関係である。その人の考えや言葉に敬意を払うこと、抱いた感情を尊重すること、そうして対面で会話を重ねて、信頼関係を築くことでしか、その人の主張や信じている説を変えられない 知識がないなんて馬鹿にするのは持ってのほかだという。本書からの引用だが"信念を理由に相手を侮辱したり、恥をかかせたりするのは、あきらかな間違いだ。"と書かれているのだ 都知事選のころなどから一部の左派リベラルの人たちが自分たちとは異なる主義主張の人を揶揄する様子を見てきた 私個人としても人間には感情があり、正しさだけで世の中の差別や偏見が解決できるなら、とっくに世の中は穏やかなものになっているだろと思う そして陰謀論や科学否定に走るのは保守派や右派だけではないともこの本には書かれている。この本を読んでいて気分が悪くなったり、耳に痛いと思うリベラル左派もいるだろうけど、まさにそういうリアクションを催し、自分の支持しない説を差し出されると突っぱねるのは左右や保守やリベラルは関係ない ちょうど先日某SNSで正しい情報だけでは相手の主義主張に変化を起こせない、態度が大切であるという研究結果を見たリベラル左派の人は『こういうファクトベースの話ではなく~』などと言っていたので、まさに『エビデンスを嫌う人たち』だなあと私は思ったんであった






 りんご食べたい@k-masahiro92025年4月24日読み始めた対話をしながら諦めないで信頼関係を築くことで、ようやく一歩進めるかどうか。それくらい人々は違う次元に生きている。別世界とのコミュニケーションはとてつもない労力がかかるんだ。
りんご食べたい@k-masahiro92025年4月24日読み始めた対話をしながら諦めないで信頼関係を築くことで、ようやく一歩進めるかどうか。それくらい人々は違う次元に生きている。別世界とのコミュニケーションはとてつもない労力がかかるんだ。 高橋|青山ブックセンター本店@frog_goes_home2025年3月31日読み始めたサイエンス系の人文書かと思ったら、人間模様を描いたノンフィクションでした。地球平面説を支持するグループの集会に潜入するところからスタートして、のっけからもう面白い。荒唐無稽な論理を信じる人々を決してバカにせず、あくまで自分と地続きの存在として対面する著者の姿勢に敬服。ちびちび読み進めるぞ。
高橋|青山ブックセンター本店@frog_goes_home2025年3月31日読み始めたサイエンス系の人文書かと思ったら、人間模様を描いたノンフィクションでした。地球平面説を支持するグループの集会に潜入するところからスタートして、のっけからもう面白い。荒唐無稽な論理を信じる人々を決してバカにせず、あくまで自分と地続きの存在として対面する著者の姿勢に敬服。ちびちび読み進めるぞ。







 たなぱんだ@tanapanda2025年2月19日読み終わった感想表紙のインパクトに反して、著者自身が地球平面説支持者の集会に潜入するなど想像以上に人間臭くて泥臭いエピソードが描かれている。書き味もエモくて、サイエンス本というより上質なノンフィクション。いい意味で裏切られた。 著者が掲げるのは「対立ではなく対話」。単に科学的・論理的な正論をぶつけるのではなく、相手が何を信じ、なぜその考えに至ったのかを理解しようとする。そして、そこから信頼関係を築き、対話を重ねていくことの重要性を説いている。 象徴的なのは、原著のタイトルが 『How to Talk to a Science Denier』(科学否定論者と話す方法) であり、『How to Talk to Science Deniers』(科学否定論者たちと話す方法) ではないこと。著者が意識しているのは、「集団」としての科学否定論者ではなく、目の前にいる「一人ひとり」と向き合うこと。レッテルを貼るのではなく、一個人として対話することが何よりも大事だと教えてくれる。 特に第7章で描かれる、遺伝子組み換え作物(GMO)をめぐる論争が圧巻だった。相手は著者の長年の友人であり、科学者でありながらGMOに否定的な立場をとる人物だ。信頼関係があるからこそ、真正面からぶつかり合い、互いの立場を理解しようとする姿が描かれている。これこそが、科学否定論に対処するための本質なのかもしれない。 また、この本自体は「科学的思考の大切さ」を説く本だが、その裏側で「文学の重要性」が浮き彫りになっているとも感じた。著者も指摘するように、人は動揺をもたらすような大事件に直面し、心理的に不安定になると、何かすがる「物語」を求めてしまう。その「物語」が陰謀論やカルト宗教の教義になってしまうことが、科学否定論の根底にある問題だ。もし、そうした「乾き切ったスポンジ」のような心に、より良い物語を提供することができたなら、それは科学否定論に対する予防策になり得る。それこそが、文学が社会にとって必要な理由なのだろう。そんなことに考えを巡らせる余白の大きさも持ち合わせた一冊だった。 単なる理屈やデータだけで陰謀論に対抗するのではなく、信頼と対話を通じて相手の心を動かす。読後、暖かな余韻が残った。
たなぱんだ@tanapanda2025年2月19日読み終わった感想表紙のインパクトに反して、著者自身が地球平面説支持者の集会に潜入するなど想像以上に人間臭くて泥臭いエピソードが描かれている。書き味もエモくて、サイエンス本というより上質なノンフィクション。いい意味で裏切られた。 著者が掲げるのは「対立ではなく対話」。単に科学的・論理的な正論をぶつけるのではなく、相手が何を信じ、なぜその考えに至ったのかを理解しようとする。そして、そこから信頼関係を築き、対話を重ねていくことの重要性を説いている。 象徴的なのは、原著のタイトルが 『How to Talk to a Science Denier』(科学否定論者と話す方法) であり、『How to Talk to Science Deniers』(科学否定論者たちと話す方法) ではないこと。著者が意識しているのは、「集団」としての科学否定論者ではなく、目の前にいる「一人ひとり」と向き合うこと。レッテルを貼るのではなく、一個人として対話することが何よりも大事だと教えてくれる。 特に第7章で描かれる、遺伝子組み換え作物(GMO)をめぐる論争が圧巻だった。相手は著者の長年の友人であり、科学者でありながらGMOに否定的な立場をとる人物だ。信頼関係があるからこそ、真正面からぶつかり合い、互いの立場を理解しようとする姿が描かれている。これこそが、科学否定論に対処するための本質なのかもしれない。 また、この本自体は「科学的思考の大切さ」を説く本だが、その裏側で「文学の重要性」が浮き彫りになっているとも感じた。著者も指摘するように、人は動揺をもたらすような大事件に直面し、心理的に不安定になると、何かすがる「物語」を求めてしまう。その「物語」が陰謀論やカルト宗教の教義になってしまうことが、科学否定論の根底にある問題だ。もし、そうした「乾き切ったスポンジ」のような心に、より良い物語を提供することができたなら、それは科学否定論に対する予防策になり得る。それこそが、文学が社会にとって必要な理由なのだろう。そんなことに考えを巡らせる余白の大きさも持ち合わせた一冊だった。 単なる理屈やデータだけで陰謀論に対抗するのではなく、信頼と対話を通じて相手の心を動かす。読後、暖かな余韻が残った。