

amy
@note_1581
悲しみなら忘れられるけど 愛はなかなか消えやしないよ
2025.03.05〜
- 2026年2月23日
 マチズモを削り取れ武田砂鉄マチズモフェミニズム読み終わった感想良い本だとは思うのだが、私にはちょっとタイミングが遅かったかなと思う 武田氏の担当編集者が疑問や怒りを投げかけるかたちで章がたてられ、世に蔓延るマチズモについて述べていく1冊 たぶんフェミニズムやマチズモ批判の入口の人にはよい本だと思う。やっぱりこれっておかしいよな?なんでこんなことがまかり通っているんだ?という社会への溜飲を下げるような本ではあるのだが、いかんせんこのマチズモを主導している人たち(主に男性)へのアプローチがほぼ書かれていないため、こっからどうすればいいんだよとなるので、基本的なフェミニズムやマチズモ批判の考えや知識をすでに持っている人には物足りないかもしれん 入門や入口としてはわかりやすく、おもしろく読めていい。北大路魯山人が女が一人で寿司を食べるなぞよろしくないと言っていたことがわかり、こんにゃろー!うるせー!一人で寿司ぐらいくったるわ!となった
マチズモを削り取れ武田砂鉄マチズモフェミニズム読み終わった感想良い本だとは思うのだが、私にはちょっとタイミングが遅かったかなと思う 武田氏の担当編集者が疑問や怒りを投げかけるかたちで章がたてられ、世に蔓延るマチズモについて述べていく1冊 たぶんフェミニズムやマチズモ批判の入口の人にはよい本だと思う。やっぱりこれっておかしいよな?なんでこんなことがまかり通っているんだ?という社会への溜飲を下げるような本ではあるのだが、いかんせんこのマチズモを主導している人たち(主に男性)へのアプローチがほぼ書かれていないため、こっからどうすればいいんだよとなるので、基本的なフェミニズムやマチズモ批判の考えや知識をすでに持っている人には物足りないかもしれん 入門や入口としてはわかりやすく、おもしろく読めていい。北大路魯山人が女が一人で寿司を食べるなぞよろしくないと言っていたことがわかり、こんにゃろー!うるせー!一人で寿司ぐらいくったるわ!となった - 2026年2月22日
 新訳 ドリアン・グレイの肖像オスカー・ワイルド,河合祥一郎エイジズムルッキズム読み終わったLGBTQ感想現代に響く「美」と「秘匿」の呪い オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』を読み終えた。まず心に残ったのは主人公ドリアンが世間の規範を脱ぎ捨て、自らの美学と快楽に忠実に生きる姿に見出した「清々しさ」だった。他者の視線や道徳に縛られず、己の欲求を最優先するその生き方はある種の解放感に満ちている。しかし、その清々しさの裏側には、ヘンリー卿という甘美な言葉を操る大人によってかけられた「若さと美への執着」という重い呪いが横たわっていた。 ドリアンが堕落の道を突き進めたのは自分の罪をすべて引き受けてくれる「肖像画」という身代わりがいたからに他ならない。もし肖像画がなければ彼はここまで大胆にはなれなかっただろう。しかし同時に、たとえ肖像画がなくても、老いや醜さを恐れる彼は今の社会でも見られるような「自暴自棄な生き方」を選んでいたかもしれないとも感じる。 現代を生きる私たちもまた、ドリアンと地続きの場所にいる。彼が恐れたのは「自己の劣化」そのものだったけれども現代社会においては「他者と比較だ。もしくは「他者から見て若いか、美しいか」という方向に呪いの形が変わっただけではないだろうか。 エイジズムやルッキズムという言葉で語られる今の社会の閉塞感は、ドリアンを狂わせた呪いと本質的な強さにおいて何ら変わりはないように思える。 また、ドリアンが肖像画を屋根裏に隠してまで必死に秘匿しようとしたその異様なまでの執着は、当時の同性愛者たちが置かれていた”クローゼット”として生きることの過酷さを物語っている。彼にとっての肖像画は社会から決して許されない「真の自己」の象徴でもある。自分の快楽を優先したいという個人的な欲望と、それが社会的に「罪」とされてしまう構造。その板挟みのなかで罪悪感に削られながら証拠(肖像画)を消し去ろうとした彼の最期は単なる自業自得ではなく、時代が生んだ悲劇としての側面も持っている。 ドリアンほどの度胸も肖像画という魔法の鏡も持たない私ではあるが、自分の中にある快楽への渇望や、老いへの微かな恐怖を突きつけられた気がする。この物語は19世紀末の退廃的な幻想譚でありながら、今なお「美」という呪いに揺さぶられる私たちへの鋭い鏡として存在し続けている。
新訳 ドリアン・グレイの肖像オスカー・ワイルド,河合祥一郎エイジズムルッキズム読み終わったLGBTQ感想現代に響く「美」と「秘匿」の呪い オスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』を読み終えた。まず心に残ったのは主人公ドリアンが世間の規範を脱ぎ捨て、自らの美学と快楽に忠実に生きる姿に見出した「清々しさ」だった。他者の視線や道徳に縛られず、己の欲求を最優先するその生き方はある種の解放感に満ちている。しかし、その清々しさの裏側には、ヘンリー卿という甘美な言葉を操る大人によってかけられた「若さと美への執着」という重い呪いが横たわっていた。 ドリアンが堕落の道を突き進めたのは自分の罪をすべて引き受けてくれる「肖像画」という身代わりがいたからに他ならない。もし肖像画がなければ彼はここまで大胆にはなれなかっただろう。しかし同時に、たとえ肖像画がなくても、老いや醜さを恐れる彼は今の社会でも見られるような「自暴自棄な生き方」を選んでいたかもしれないとも感じる。 現代を生きる私たちもまた、ドリアンと地続きの場所にいる。彼が恐れたのは「自己の劣化」そのものだったけれども現代社会においては「他者と比較だ。もしくは「他者から見て若いか、美しいか」という方向に呪いの形が変わっただけではないだろうか。 エイジズムやルッキズムという言葉で語られる今の社会の閉塞感は、ドリアンを狂わせた呪いと本質的な強さにおいて何ら変わりはないように思える。 また、ドリアンが肖像画を屋根裏に隠してまで必死に秘匿しようとしたその異様なまでの執着は、当時の同性愛者たちが置かれていた”クローゼット”として生きることの過酷さを物語っている。彼にとっての肖像画は社会から決して許されない「真の自己」の象徴でもある。自分の快楽を優先したいという個人的な欲望と、それが社会的に「罪」とされてしまう構造。その板挟みのなかで罪悪感に削られながら証拠(肖像画)を消し去ろうとした彼の最期は単なる自業自得ではなく、時代が生んだ悲劇としての側面も持っている。 ドリアンほどの度胸も肖像画という魔法の鏡も持たない私ではあるが、自分の中にある快楽への渇望や、老いへの微かな恐怖を突きつけられた気がする。この物語は19世紀末の退廃的な幻想譚でありながら、今なお「美」という呪いに揺さぶられる私たちへの鋭い鏡として存在し続けている。 - 2026年2月14日
 ばくうどの悪夢(8)澤村伊智読み終わった感想澤村伊智再読期間はまだ続く。 読んでいる最中に新潮社と契約やめたニュースが流れてきてびびる。 澤村伊智は本当にネットの冷笑露悪に染まり、その場所から動いたり他者のことを考えないオタクが嫌いだし、安易に地方=因習と結びつけるような同業者のこともすごい嫌いなんだな⋯!と思う 作中でも明確に批判対象として描いているし。やはりホラー作家としてそのあたりに安心できるかは大きい 澤村伊智の作品のなかではめずらしくスプラッタっぽい業者もあるけど、これもまた澤村伊智はスプラッタが書けないと言われたからだそうな⋯。 だとしても相変わらずのおもしろさだし、作中の強キャラが負傷したときのあの不安感と小説だからこそできるしかけがとてもおもしろかった。この人の作品いつもおもしろいな⋯
ばくうどの悪夢(8)澤村伊智読み終わった感想澤村伊智再読期間はまだ続く。 読んでいる最中に新潮社と契約やめたニュースが流れてきてびびる。 澤村伊智は本当にネットの冷笑露悪に染まり、その場所から動いたり他者のことを考えないオタクが嫌いだし、安易に地方=因習と結びつけるような同業者のこともすごい嫌いなんだな⋯!と思う 作中でも明確に批判対象として描いているし。やはりホラー作家としてそのあたりに安心できるかは大きい 澤村伊智の作品のなかではめずらしくスプラッタっぽい業者もあるけど、これもまた澤村伊智はスプラッタが書けないと言われたからだそうな⋯。 だとしても相変わらずのおもしろさだし、作中の強キャラが負傷したときのあの不安感と小説だからこそできるしかけがとてもおもしろかった。この人の作品いつもおもしろいな⋯ - 2026年2月14日
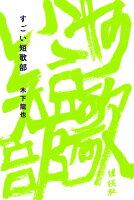 すごい短歌部木下龍也読み終わった感想短歌短歌を知りたくて短歌の本を読む 木下龍也が投稿された短歌を詠みながら、自分もそのお題にそって短歌を作り、その作る過程を解説するという本 お題の解釈が木下さんも含め投稿者でいろいろでおもしろかったし、自分にはない景色や趣を見出す作品はかなり痛くて気持ちいい感覚
すごい短歌部木下龍也読み終わった感想短歌短歌を知りたくて短歌の本を読む 木下龍也が投稿された短歌を詠みながら、自分もそのお題にそって短歌を作り、その作る過程を解説するという本 お題の解釈が木下さんも含め投稿者でいろいろでおもしろかったし、自分にはない景色や趣を見出す作品はかなり痛くて気持ちいい感覚 - 2026年2月11日
 読み終わった感想ずっと読みたいな~と頭の片隅で考えていたけど読めてなかったやつ 芥川賞受賞。いや、もうどんどん怖くなってきて、読むのが止まらなかった。怖くて怖くて、早く読み切ってしまいたい!みたいな感じだった。初めての感覚である。 一人称の小説って書き方ひとつでこんなにも読み手の感情をあちらこちらに揺さぶることができるのすごいよなあ。いや今村さんの手腕によるのが一番大きいんですけど。 最初の数ページはこんなに特定の人間のことをじろじろ観察して、見下しながらもそれを続けているの性格悪いなーと思ったんだけど、いや、そんな性格悪いとかじゃない。そんなんじゃない。 小説のジャンルとしてはホラーではないと思う。ホラーではないのだけど、怖い。 人間の視野や語りがどれだけ信用ならないのか、事実を覆い隠してしまうのかという点において非常に恐ろしい作品だった。 ミスドでロイヤルミルクティーをおかわりしながらゆっくり読むかーと思ったら全然そんな余裕なかった。本の世界感に引きずり込まれる。引力がすごい。 小野不由美の『残穢』が家にあることは何も怖くないけど、今村夏子の『むらさきのスカートの女』が家にあるのは怖いです!!!!
読み終わった感想ずっと読みたいな~と頭の片隅で考えていたけど読めてなかったやつ 芥川賞受賞。いや、もうどんどん怖くなってきて、読むのが止まらなかった。怖くて怖くて、早く読み切ってしまいたい!みたいな感じだった。初めての感覚である。 一人称の小説って書き方ひとつでこんなにも読み手の感情をあちらこちらに揺さぶることができるのすごいよなあ。いや今村さんの手腕によるのが一番大きいんですけど。 最初の数ページはこんなに特定の人間のことをじろじろ観察して、見下しながらもそれを続けているの性格悪いなーと思ったんだけど、いや、そんな性格悪いとかじゃない。そんなんじゃない。 小説のジャンルとしてはホラーではないと思う。ホラーではないのだけど、怖い。 人間の視野や語りがどれだけ信用ならないのか、事実を覆い隠してしまうのかという点において非常に恐ろしい作品だった。 ミスドでロイヤルミルクティーをおかわりしながらゆっくり読むかーと思ったら全然そんな余裕なかった。本の世界感に引きずり込まれる。引力がすごい。 小野不由美の『残穢』が家にあることは何も怖くないけど、今村夏子の『むらさきのスカートの女』が家にあるのは怖いです!!!! - 2026年2月11日
 恋愛ってなんだろう?大森美佐ジェンダーフェミニズム読み終わった感想通っている図書館の企画選書にあったから読んでみた 中学生の質問箱シリーズというものでほかにもいろんなテーマがあるけど、架空の中学生の疑問に答えるかたちで離婚研究をしている著者がそもそも恋愛とは、結婚とはを紐解く本 同性婚ができないことやポリアモリーのこと、婚姻制度やアセクシャル、アロマンティックのことなども平易な言葉で解説しているので、興味があるけど何から読めばいいのかという人やそれこそ中高生にもおすすめできる本
恋愛ってなんだろう?大森美佐ジェンダーフェミニズム読み終わった感想通っている図書館の企画選書にあったから読んでみた 中学生の質問箱シリーズというものでほかにもいろんなテーマがあるけど、架空の中学生の疑問に答えるかたちで離婚研究をしている著者がそもそも恋愛とは、結婚とはを紐解く本 同性婚ができないことやポリアモリーのこと、婚姻制度やアセクシャル、アロマンティックのことなども平易な言葉で解説しているので、興味があるけど何から読めばいいのかという人やそれこそ中高生にもおすすめできる本 - 2026年2月8日
 読み終わった感想閃光のハサウェイ読んだ いや~~~、なんというか大人世代の因果というかそれに巻き込まれる若い世代というのがいて、そこからさらに諍いは続いてしまうというのがあり、被害者が加害者になってしまい連鎖してしまうということはこと戦争においてはよくある そしてまあ富野由悠季だからというのもあるんだけど、人間の心理や行動原理が矛盾していたりしてその危なっかしさがまさに人間だよなあと思うし、そんな人間が作るシステムなんぞ不全で当然でだからこそコミュニケーションというか対話をしていかねば、コンフリクトが大きくなったときに極端な行動をする人たちが出てきて、さらに災禍が起こってしまうというのは、あるよなあ⋯ とりあえずキルケーの魔女観に行く
読み終わった感想閃光のハサウェイ読んだ いや~~~、なんというか大人世代の因果というかそれに巻き込まれる若い世代というのがいて、そこからさらに諍いは続いてしまうというのがあり、被害者が加害者になってしまい連鎖してしまうということはこと戦争においてはよくある そしてまあ富野由悠季だからというのもあるんだけど、人間の心理や行動原理が矛盾していたりしてその危なっかしさがまさに人間だよなあと思うし、そんな人間が作るシステムなんぞ不全で当然でだからこそコミュニケーションというか対話をしていかねば、コンフリクトが大きくなったときに極端な行動をする人たちが出てきて、さらに災禍が起こってしまうというのは、あるよなあ⋯ とりあえずキルケーの魔女観に行く - 2026年2月8日
 閃光のハサウェイ(中) 機動戦士ガンダム富野由悠季,美樹本晴彦読み終わった
閃光のハサウェイ(中) 機動戦士ガンダム富野由悠季,美樹本晴彦読み終わった - 2026年2月8日
 閃光のハサウェイ(上) 機動戦士ガンダム富野由悠季読み終わった
閃光のハサウェイ(上) 機動戦士ガンダム富野由悠季読み終わった - 2026年2月8日
 フェミニズム読み終わった感想うおー、おもしろかった 田嶋陽子先生の著書を読んだのは初めて。ヒロインが殺される映画を取り上げて、そのヒロインが作中でどんな存在だったのか。そしてなぜ死なねばならなかったのか、その死はどんな意味があるのかを論じている本 こういうフィクションのなかに横たわる社会や構造を読み解く本は大大大好物なので楽しく読めたし、こういうかたちで女(ヒロイン)ってめっちゃ殺されとる!なんか役割を負わされて男のために殺されとる!と履修中の機動戦士ガンダム「逆襲のシャア」と「閃光のハサウェイ」が頭の中をビュンビュンよぎった(笑) 男と男の友情のために殺されたり、自己犠牲を強いられたり、家父長制に取り込まれたなかで母と娘がいがみあったり。今でも全然よく見る流れだ。 本の巻末にはそんな田嶋陽子先生が進めてくれる映画が一覧でまとめられている。新装版ということでかなり最近の作品も羅列されていて見たい作品が増えた。 ひとつだけ気がかりだったのは取り上げた時代が1980年代のものなどが多かったせいもあるだろうけど、女性も仕事を持つべしという論調が終始強くてポストフェミニズムやリーン・イン・フェミニズムぽさが強かった 対象となる作品をここ20年ほどのものにしてまた書いてほしい
フェミニズム読み終わった感想うおー、おもしろかった 田嶋陽子先生の著書を読んだのは初めて。ヒロインが殺される映画を取り上げて、そのヒロインが作中でどんな存在だったのか。そしてなぜ死なねばならなかったのか、その死はどんな意味があるのかを論じている本 こういうフィクションのなかに横たわる社会や構造を読み解く本は大大大好物なので楽しく読めたし、こういうかたちで女(ヒロイン)ってめっちゃ殺されとる!なんか役割を負わされて男のために殺されとる!と履修中の機動戦士ガンダム「逆襲のシャア」と「閃光のハサウェイ」が頭の中をビュンビュンよぎった(笑) 男と男の友情のために殺されたり、自己犠牲を強いられたり、家父長制に取り込まれたなかで母と娘がいがみあったり。今でも全然よく見る流れだ。 本の巻末にはそんな田嶋陽子先生が進めてくれる映画が一覧でまとめられている。新装版ということでかなり最近の作品も羅列されていて見たい作品が増えた。 ひとつだけ気がかりだったのは取り上げた時代が1980年代のものなどが多かったせいもあるだろうけど、女性も仕事を持つべしという論調が終始強くてポストフェミニズムやリーン・イン・フェミニズムぽさが強かった 対象となる作品をここ20年ほどのものにしてまた書いてほしい - 2026年2月8日
 アボカドの種俵万智読み終わった感想短歌上坂あゆ美さんの影響で短歌の本を読みたくなったので短歌といえば!の俵万智⋯ 「チョコレート革命」しか読んだことがなくだいぶ久しぶり この人は日常のふとした光景を切り取るのがうますぎる。こう考えると短歌は昔でいうとSNSやメールだったというのがすごいわかるな⋯ このちょっとしたことを共有したいと思えるときのツールだったんだなあ 俵万智という王道かつ大メジャーなところを読んだのでほかの歌人の本も読みたい
アボカドの種俵万智読み終わった感想短歌上坂あゆ美さんの影響で短歌の本を読みたくなったので短歌といえば!の俵万智⋯ 「チョコレート革命」しか読んだことがなくだいぶ久しぶり この人は日常のふとした光景を切り取るのがうますぎる。こう考えると短歌は昔でいうとSNSやメールだったというのがすごいわかるな⋯ このちょっとしたことを共有したいと思えるときのツールだったんだなあ 俵万智という王道かつ大メジャーなところを読んだのでほかの歌人の本も読みたい - 2026年2月8日
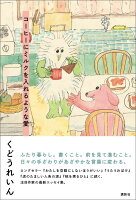 コーヒーにミルクを入れるような愛くどうれいんエッセイ読み終わった感想くどうれいんさんのエッセイ れいんさんのエッセイ、タイトルがおいしそうなので読みたくなってしまう(食いしんぼう) れいんさんのエッセイってオノマトペとかも使われているんだけど、かといってやわらかすぎるとかポップすぎるということもなくて 生活の悲喜こもごもだったりをほろ苦く書いてたりして、ケーキのオペラみたいなんだよな 甘さもあるけどコーヒーのシロップがじわっと舌にのっかるみたいな そんでもって感情とそのときの光景へのピントの合わせ方が鮮やかでそんな角度から!?と驚くことも多くて読んでて本当に楽しい ここまで書いててれいんさんのエッセイを1冊積んでるのを思い出した。はよ読まなければ⋯
コーヒーにミルクを入れるような愛くどうれいんエッセイ読み終わった感想くどうれいんさんのエッセイ れいんさんのエッセイ、タイトルがおいしそうなので読みたくなってしまう(食いしんぼう) れいんさんのエッセイってオノマトペとかも使われているんだけど、かといってやわらかすぎるとかポップすぎるということもなくて 生活の悲喜こもごもだったりをほろ苦く書いてたりして、ケーキのオペラみたいなんだよな 甘さもあるけどコーヒーのシロップがじわっと舌にのっかるみたいな そんでもって感情とそのときの光景へのピントの合わせ方が鮮やかでそんな角度から!?と驚くことも多くて読んでて本当に楽しい ここまで書いててれいんさんのエッセイを1冊積んでるのを思い出した。はよ読まなければ⋯ - 2026年2月8日
 BLマンガの表現史西原麻里フェミニズムBL読み終わった感想BLマンガをその表現の歴史から振り返り、数量的な分析をしていく本 おもしろかったし、自分の知らない時代の様子を知ることができてよかった いわゆる少年愛と呼ばれる、BLの先駆け的なものが起こったときは少女マンガで表現できることが限定的だったからこそ、少女マンガの紙面で展開できるような内容かつ、少女マンガでは見られなかった展開やキャラメイクができるようになったということ、少女マンガでは激情的な内容はあまり歓迎されない時代に恋による激情を描くために少年たちが用いられたというのは知らなかったし、目からうろこだった 性描写のシーンの変遷、キャラクターの外見やルーツの変遷などもまとめられておりとても興味深かった
BLマンガの表現史西原麻里フェミニズムBL読み終わった感想BLマンガをその表現の歴史から振り返り、数量的な分析をしていく本 おもしろかったし、自分の知らない時代の様子を知ることができてよかった いわゆる少年愛と呼ばれる、BLの先駆け的なものが起こったときは少女マンガで表現できることが限定的だったからこそ、少女マンガの紙面で展開できるような内容かつ、少女マンガでは見られなかった展開やキャラメイクができるようになったということ、少女マンガでは激情的な内容はあまり歓迎されない時代に恋による激情を描くために少年たちが用いられたというのは知らなかったし、目からうろこだった 性描写のシーンの変遷、キャラクターの外見やルーツの変遷などもまとめられておりとても興味深かった - 2026年1月18日
 老人ホームで死ぬほどモテたい上坂あゆ美読み終わった感想短歌上坂あゆ美さんの”上坂あゆ美の「私より先に丁寧に暮らすな」”というPodcastが好きなのだが、肝心の短歌の本をまだ読んだことがなかった 上坂さんを知ったのは『ロイヤルホストで朝まで語りたい』のエッセイだったので、だいぶ特殊なルートからたどりついた感じである 上坂さんの短歌、日常に頻出する単語を使いながら、ちょっと爪でひっかかれたような心地がしてクセになる 私も短歌詠めるようになりたいな、どこからどう始めればいいのかわからんが 特に好きなのはこのあたり ・にせものの光こわいよ道徳の教科書笑顔Windowsの壁紙 ・手を握らないで人間にしないでここが地獄だと気づいてしまう ・お好み焼きの大きい方をくれたこと地球ではこえrを愛とか言うよ
老人ホームで死ぬほどモテたい上坂あゆ美読み終わった感想短歌上坂あゆ美さんの”上坂あゆ美の「私より先に丁寧に暮らすな」”というPodcastが好きなのだが、肝心の短歌の本をまだ読んだことがなかった 上坂さんを知ったのは『ロイヤルホストで朝まで語りたい』のエッセイだったので、だいぶ特殊なルートからたどりついた感じである 上坂さんの短歌、日常に頻出する単語を使いながら、ちょっと爪でひっかかれたような心地がしてクセになる 私も短歌詠めるようになりたいな、どこからどう始めればいいのかわからんが 特に好きなのはこのあたり ・にせものの光こわいよ道徳の教科書笑顔Windowsの壁紙 ・手を握らないで人間にしないでここが地獄だと気づいてしまう ・お好み焼きの大きい方をくれたこと地球ではこえrを愛とか言うよ - 2026年1月18日
 エロってなんだろう?山本直樹読み終わった感想山本直樹の『エロってなんだろう?』を読んだ。 発売された当初から気になっていたのだが、この世にはおもしろそうな本やそのほかコンテンツがたくさんあるため、やや後回し気味になっていた。 内容は山本直樹のエッセイに近いが、表現規制の歴史や、それが起こった時代の空気が押さえられていて、そのへんについてはぼんやりとしか理解していなかったので自分でも整理できてよかった 途中までは、ほほお、なるほどなあ。いや、このへんは全然知らなかったわーと思っていたのだが、第四章【隠すことにもルールがいる?】のラストのほうに”社会的な約束事をちゃんと理解していないと作品は作れないんですよね。エロはとくに。そこをちゃんと理解していないと、作り手としてダメだと思うんですよね。”と言い切ったあたりから、第五章【現実とフィクション】に入り、様子が少し変わってくる。 第五章で山本直樹はずっと現実と他者のことを書いている。もっと言うと他者を人間として扱うこと、現実こそが他者=人間であることをずっとずっと書いている。 過去に描いた作品のことからもあれこれは言えないけれども、と前置きをしながらも”相手を道具扱いしていまう諸悪の根源が「現実とフィクションの混同」なんだと思います。これが一番性質が悪い。”と言っている。 それを皮切りに現実の事象と照らし合わせながら、現実を生きている人間を道具扱いすることの最たるものは国家が行う戦争であり、あれは人の命よりも国体の護持が大事なのだと若者を特攻させた、現実とフィクションを現実しているのがロシアのプーチンであり、彼のなかのフィクションの邪魔をするからという理由でプーチンはウクライナへ侵攻した、などである。 この本のレーベルであるちくまプリマー新書は公式サイトの紹介文を見る限り、若い年齢だと思う。 そんな読者層を想定してか、山本直樹は話がおおごとになってきているかもしれないが、こういうことを話し出すとこんなことまでいかざるをえないのだと誠実な言葉も記している。 また新自由主義も批判していた。新自由主義はつまるところお金原理主義であり、人の命よりもお金が大事だと本気で思っている人たちがやっていることで、そもそも人の命よりも大事なものがあるというのは、全部「原理主義」なのだと。 人の命という現実よりも、お金や国家や会社なんかのフィクションが大事であるというのは山本直樹に言わせれば現実とフィクションの混同だ。 現実の相手よりも、自分の中にある言葉ですべてをコントロールしたくなる。現実とフィクションの混同=マチズモと言ってもいいと思います。p109 刊行時に公開されていた目次では知っていたのだが、エロからどう持っていくんだ?と予想していなかった項目がある。 それが『日本国憲法』だった。 山本直樹本人も”さっきから話がどんどんエロから離れまくっていますが”と前置きしたうえで彼が考える日本国憲法について書いていた。 日本国憲法もただの言葉ではありますけれど、「人が生きて暮らして死ぬのがいちばん大事だよ。それより大事なものはないよ」と伝えている言葉です。p112 つまり日本国憲法という人が生きて、暮らして、死ぬことが何より大事だという言葉はフィクションではない。日本国憲法に書かれている言葉はフィクションではなく現実である。 でも言葉がフィクションであるときもある。 世界の古今東西はそれはもう残虐な歴史があって、人より言葉(フィクション)が大事だった場面のほうが圧倒的に多く、だからこそ、今はそれが間違っていたと言わなければならない。イデオロギーよりもお金よりも何よりも人が大事なのだと言葉にしていかなければならない。 山本直樹はそれが日本国憲法だと言っている。 日本国憲法の説明として明快で、こういう明快さを打ち出せるのは漫画家らしいなと思ったんであった。 「人権」というと「なんかむずかしい」とか「左翼っぽい」とか「あんまり言いすぎるとややこしくなるよね。堅苦しくなるよね。」とか言う人も最近多いようですが、「言葉やお金や国より、人のほうが大事だよね」という普通のことだと思うんだけど。p113 この本はエロからスタートし、エロを解体していくことで、他者とは、人間とはを説いている。もちろんそれは山本直樹の思う、という枕詞がつくのだけれど、なかなかエロを解体している人やその延長で他者や人間のことを語っている人は少ない。 それはエロというコンテンツが受け手にとって都合の良いものであるからだろう。 そこに描かれている人間を道具化していけばいくほど、受け手は楽にそれを消費できる。エロと消費はセパレートすることが難しい。 だからこそ、エロを楽しみながらも真面目に考え、自分の消費しているものは何かを考え続けていかなければならない。エロ楽しむなら本気でやれ、手を抜くなということなのだ。 そして、人間は反復不可能だし、再生不可能なんです。 ~略~ 今この本を読んでいるあなたを作ることもできない。p137
エロってなんだろう?山本直樹読み終わった感想山本直樹の『エロってなんだろう?』を読んだ。 発売された当初から気になっていたのだが、この世にはおもしろそうな本やそのほかコンテンツがたくさんあるため、やや後回し気味になっていた。 内容は山本直樹のエッセイに近いが、表現規制の歴史や、それが起こった時代の空気が押さえられていて、そのへんについてはぼんやりとしか理解していなかったので自分でも整理できてよかった 途中までは、ほほお、なるほどなあ。いや、このへんは全然知らなかったわーと思っていたのだが、第四章【隠すことにもルールがいる?】のラストのほうに”社会的な約束事をちゃんと理解していないと作品は作れないんですよね。エロはとくに。そこをちゃんと理解していないと、作り手としてダメだと思うんですよね。”と言い切ったあたりから、第五章【現実とフィクション】に入り、様子が少し変わってくる。 第五章で山本直樹はずっと現実と他者のことを書いている。もっと言うと他者を人間として扱うこと、現実こそが他者=人間であることをずっとずっと書いている。 過去に描いた作品のことからもあれこれは言えないけれども、と前置きをしながらも”相手を道具扱いしていまう諸悪の根源が「現実とフィクションの混同」なんだと思います。これが一番性質が悪い。”と言っている。 それを皮切りに現実の事象と照らし合わせながら、現実を生きている人間を道具扱いすることの最たるものは国家が行う戦争であり、あれは人の命よりも国体の護持が大事なのだと若者を特攻させた、現実とフィクションを現実しているのがロシアのプーチンであり、彼のなかのフィクションの邪魔をするからという理由でプーチンはウクライナへ侵攻した、などである。 この本のレーベルであるちくまプリマー新書は公式サイトの紹介文を見る限り、若い年齢だと思う。 そんな読者層を想定してか、山本直樹は話がおおごとになってきているかもしれないが、こういうことを話し出すとこんなことまでいかざるをえないのだと誠実な言葉も記している。 また新自由主義も批判していた。新自由主義はつまるところお金原理主義であり、人の命よりもお金が大事だと本気で思っている人たちがやっていることで、そもそも人の命よりも大事なものがあるというのは、全部「原理主義」なのだと。 人の命という現実よりも、お金や国家や会社なんかのフィクションが大事であるというのは山本直樹に言わせれば現実とフィクションの混同だ。 現実の相手よりも、自分の中にある言葉ですべてをコントロールしたくなる。現実とフィクションの混同=マチズモと言ってもいいと思います。p109 刊行時に公開されていた目次では知っていたのだが、エロからどう持っていくんだ?と予想していなかった項目がある。 それが『日本国憲法』だった。 山本直樹本人も”さっきから話がどんどんエロから離れまくっていますが”と前置きしたうえで彼が考える日本国憲法について書いていた。 日本国憲法もただの言葉ではありますけれど、「人が生きて暮らして死ぬのがいちばん大事だよ。それより大事なものはないよ」と伝えている言葉です。p112 つまり日本国憲法という人が生きて、暮らして、死ぬことが何より大事だという言葉はフィクションではない。日本国憲法に書かれている言葉はフィクションではなく現実である。 でも言葉がフィクションであるときもある。 世界の古今東西はそれはもう残虐な歴史があって、人より言葉(フィクション)が大事だった場面のほうが圧倒的に多く、だからこそ、今はそれが間違っていたと言わなければならない。イデオロギーよりもお金よりも何よりも人が大事なのだと言葉にしていかなければならない。 山本直樹はそれが日本国憲法だと言っている。 日本国憲法の説明として明快で、こういう明快さを打ち出せるのは漫画家らしいなと思ったんであった。 「人権」というと「なんかむずかしい」とか「左翼っぽい」とか「あんまり言いすぎるとややこしくなるよね。堅苦しくなるよね。」とか言う人も最近多いようですが、「言葉やお金や国より、人のほうが大事だよね」という普通のことだと思うんだけど。p113 この本はエロからスタートし、エロを解体していくことで、他者とは、人間とはを説いている。もちろんそれは山本直樹の思う、という枕詞がつくのだけれど、なかなかエロを解体している人やその延長で他者や人間のことを語っている人は少ない。 それはエロというコンテンツが受け手にとって都合の良いものであるからだろう。 そこに描かれている人間を道具化していけばいくほど、受け手は楽にそれを消費できる。エロと消費はセパレートすることが難しい。 だからこそ、エロを楽しみながらも真面目に考え、自分の消費しているものは何かを考え続けていかなければならない。エロ楽しむなら本気でやれ、手を抜くなということなのだ。 そして、人間は反復不可能だし、再生不可能なんです。 ~略~ 今この本を読んでいるあなたを作ることもできない。p137 - 2026年1月18日
 などらきの首(3)澤村伊智読み終わった感想再読澤村伊智再読月間 比嘉姉妹シリーズ短編集の「などらきの首」 久しぶりに読んでもおもしろすぎ~。やっぱりホラーは澤村伊智なんだよな。 嫌なホラーオタクとかおっさんとかの描写がうますぎるだろ。 一番好きなのは『居酒屋脳髄談義』なんだけど、嫌なやつの着地点がそこ!?ってなるのが鮮やかすぎて何度読んでも、おもしろすぎる。この大回転をホラーで書けるのすごいな~、え~、澤村伊智って天才? ここまできたら比嘉姉妹シリーズは全部再読するか
などらきの首(3)澤村伊智読み終わった感想再読澤村伊智再読月間 比嘉姉妹シリーズ短編集の「などらきの首」 久しぶりに読んでもおもしろすぎ~。やっぱりホラーは澤村伊智なんだよな。 嫌なホラーオタクとかおっさんとかの描写がうますぎるだろ。 一番好きなのは『居酒屋脳髄談義』なんだけど、嫌なやつの着地点がそこ!?ってなるのが鮮やかすぎて何度読んでも、おもしろすぎる。この大回転をホラーで書けるのすごいな~、え~、澤村伊智って天才? ここまできたら比嘉姉妹シリーズは全部再読するか - 2026年1月12日
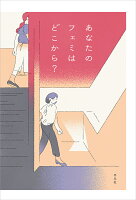 あなたのフェミはどこから?上田久美子,安達茉莉子,小川たまか,小田原のどか,石原真衣,長田杏奈ジェンダーフェミニズム読み終わった感想なんていいタイトルなんだ。いつからフェミニストになったのか、いつフェミニズムに出会ったのか、ではなくインターネットでは揶揄や冷笑の単語となっている『フェミ』を使い、おなじみの風邪薬のキャッチコピーのようなリズム感でフックと軽快さを両立している。 タイトルの通りなのだが、この本にはあらゆる人がフェミニズムにいつ、どのようにして出会ったのかがリレーエッセイ形式でまとめられている。もちろんトランスジェンダーの書き手も、ノンバイナリーの書き手もいる。 フェミニズムとの出会いが劇的な人もいれば、ぬるっとじわっと出会っていたという人もいて、これはあらゆる人に語ってほしいテーマだと思ったし、私も近いうちにまとめたいと思う。 どのエッセイも読み応えがあり、内容としてもおもしろかったのだが、武田砂鉄さんの”編集者はこの原稿を森喜朗や麻生太郎には依頼しないはずなので、”という一文がウィットに富んでいて痛快で笑ってしまった。 そういえばなんだかんだで武田砂鉄さんの著書はまだ読んでいない気がするので近いうちに読みたい。そしてこの感想を読んでくれたそこのあなたにも答えてほしい。 『あなたのフェミはどこから?』
あなたのフェミはどこから?上田久美子,安達茉莉子,小川たまか,小田原のどか,石原真衣,長田杏奈ジェンダーフェミニズム読み終わった感想なんていいタイトルなんだ。いつからフェミニストになったのか、いつフェミニズムに出会ったのか、ではなくインターネットでは揶揄や冷笑の単語となっている『フェミ』を使い、おなじみの風邪薬のキャッチコピーのようなリズム感でフックと軽快さを両立している。 タイトルの通りなのだが、この本にはあらゆる人がフェミニズムにいつ、どのようにして出会ったのかがリレーエッセイ形式でまとめられている。もちろんトランスジェンダーの書き手も、ノンバイナリーの書き手もいる。 フェミニズムとの出会いが劇的な人もいれば、ぬるっとじわっと出会っていたという人もいて、これはあらゆる人に語ってほしいテーマだと思ったし、私も近いうちにまとめたいと思う。 どのエッセイも読み応えがあり、内容としてもおもしろかったのだが、武田砂鉄さんの”編集者はこの原稿を森喜朗や麻生太郎には依頼しないはずなので、”という一文がウィットに富んでいて痛快で笑ってしまった。 そういえばなんだかんだで武田砂鉄さんの著書はまだ読んでいない気がするので近いうちに読みたい。そしてこの感想を読んでくれたそこのあなたにも答えてほしい。 『あなたのフェミはどこから?』 - 2026年1月12日
 壊された少年内田雅克ジェンダー読み終わった感想きっかけは忘れていたが図書館で予約をしていた連絡がきたので新年初図書館はこちらだった 読んでみて思ったけど、男性の抑圧もだいぶきついものがあるなと暗い気持ちになった。もちろん女性差別がそれで帳消しになるわけではないが 小学校でおそらく女子児童だと思われる子はカラフルなランドセルなのに、男子児童だと思われる子は黒や青や紺しかなくて、それほどまでに男性は男性らしくあれ、逆説的に言えば繊細さややわらかさなどを纏うなというメッセージにも感じてとても苦しくなる いかにして少年は”男”にさせられるのか。それを学校、スポーツ、テレビ、世相と絡めて著者の内田さんが自身の過去を振り返りながら見つめていく 特に学校教育の箇所では”個性の尊重が謳われているが、個性を尊重するよりも先に選別が行われている”という指摘はまとをきっかけは忘れていたが図書館で予約をしていた連絡がきたので新年初図書館はこちらだった 読んでみて思ったけど、男性の抑圧もだいぶきついものがあるなと暗い気持ちになった。もちろん女性差別がそれで帳消しになるわけではないが 小学校でおそらく女子児童だと思われる子はカラフルなランドセルなのに、男子児童だと思われる子は黒や青や紺しかなくて、それほどまでに男性は男性らしくあれ、逆説的に言えば繊細さややわらかさなどを纏うなというメッセージにも感じてとても苦しくなる いかにして少年は”男”にさせられるのか。それを学校、スポーツ、テレビ、世相と絡めて著者の内田さんが自身の過去を振り返りながら見つめていく 特に学校教育の箇所では”個性の尊重が謳われているが、個性を尊重するよりも先に選別が行われている”という指摘は的を射ている。 尊重の前に尊重されるべき個性を選別する作業があり、そのなかでジェンダートラブルを抱えている生徒は振り落とされているのだという内田さんの実感も込められた指摘は安易な多様性をもてはやす風潮において必要なものだと思う
壊された少年内田雅克ジェンダー読み終わった感想きっかけは忘れていたが図書館で予約をしていた連絡がきたので新年初図書館はこちらだった 読んでみて思ったけど、男性の抑圧もだいぶきついものがあるなと暗い気持ちになった。もちろん女性差別がそれで帳消しになるわけではないが 小学校でおそらく女子児童だと思われる子はカラフルなランドセルなのに、男子児童だと思われる子は黒や青や紺しかなくて、それほどまでに男性は男性らしくあれ、逆説的に言えば繊細さややわらかさなどを纏うなというメッセージにも感じてとても苦しくなる いかにして少年は”男”にさせられるのか。それを学校、スポーツ、テレビ、世相と絡めて著者の内田さんが自身の過去を振り返りながら見つめていく 特に学校教育の箇所では”個性の尊重が謳われているが、個性を尊重するよりも先に選別が行われている”という指摘はまとをきっかけは忘れていたが図書館で予約をしていた連絡がきたので新年初図書館はこちらだった 読んでみて思ったけど、男性の抑圧もだいぶきついものがあるなと暗い気持ちになった。もちろん女性差別がそれで帳消しになるわけではないが 小学校でおそらく女子児童だと思われる子はカラフルなランドセルなのに、男子児童だと思われる子は黒や青や紺しかなくて、それほどまでに男性は男性らしくあれ、逆説的に言えば繊細さややわらかさなどを纏うなというメッセージにも感じてとても苦しくなる いかにして少年は”男”にさせられるのか。それを学校、スポーツ、テレビ、世相と絡めて著者の内田さんが自身の過去を振り返りながら見つめていく 特に学校教育の箇所では”個性の尊重が謳われているが、個性を尊重するよりも先に選別が行われている”という指摘は的を射ている。 尊重の前に尊重されるべき個性を選別する作業があり、そのなかでジェンダートラブルを抱えている生徒は振り落とされているのだという内田さんの実感も込められた指摘は安易な多様性をもてはやす風潮において必要なものだと思う - 2026年1月12日
 月と六ペンスサマセット・モーム,William Somerset Maugham,金原瑞人読み終わった感想サマセット・モームの『月と六ペンス』、もうすこぶるおもしろかった。名作ってすげえ……。 私はもともとエンターテインメントを含めた芸術全般を愛しており、文学や美術を通じて心を震わせる作品に出会ったときこそ、自分が生きていることを最も強く実感する。 日々、素晴らしい作品を生み出してくれる作家たちには頭が上がらないし、それらがこの世に存在することに心からの感謝を捧げている。 それゆえに、私自身もまた、作中で象徴される”六ペンス”的な価値観にさほど重きを置いていないところがある。 しかし、本作を読んで突きつけられたのは芸術という”月”にすべてを振り切ることの凄絶な代償である。 生活という”六ペンス”の領域を完全に切り捨てれば、そこには必ず歪みが生じる。 現代社会において、その歪みから完全に逃れることは極めて困難であり、誰かがそのこぼれ落ちた役割を肩代わりすることになる。 ストリックランドの周囲で傷ついた人々を思うとき、その罪深さをざりざりと歯を削りながら、噛み締めざるを得ない。 それでもなお、私は自分の心を震わせる作品を求めずにはいられない。 私にはストリックランドのような創造の才能はないが、芸術を求め、渇望してしまうという”業”を背負っているのだと感じる。 特に作中のストルーヴェが語った「美を理解するには、芸術家と同じように魂を傷つけ、世界の混沌をみつめなくてはならない。たとえるなら、美とは芸術家が鑑賞者たちに聴かせる歌のようなものだ。その歌を心で聴くには、知識と感受性と想像力がなくてはならない」という言葉が、鋭く胸に刺さる。 もちろん、芸術は気軽に楽しんでいい。しかし、もし単なる「綺麗」とか「美しい」という感動を超えて、その真髄を理解したいと願うのであれば、私たちはもっと能動的にならなければならない。 芸術家がこの世界をどのように眼差し、それをどう作品に落とし込んだのか。 それを咀嚼するためには鑑賞者である私たちもまた、自らの魂を傷つける覚悟が必要なのだと思う。 作り手が作品に込めたメッセージが届かないというのは、自らの魂を傷つけることを避けているからではないか。 魂が傷ついた瞬間に走る、あのヒリヒリとした、それでいて心地よい感覚。それを知ってしまった以上、私はもう二度と、芸術のない「六ペンス」だけの世界には戻れないのだと確信している。
月と六ペンスサマセット・モーム,William Somerset Maugham,金原瑞人読み終わった感想サマセット・モームの『月と六ペンス』、もうすこぶるおもしろかった。名作ってすげえ……。 私はもともとエンターテインメントを含めた芸術全般を愛しており、文学や美術を通じて心を震わせる作品に出会ったときこそ、自分が生きていることを最も強く実感する。 日々、素晴らしい作品を生み出してくれる作家たちには頭が上がらないし、それらがこの世に存在することに心からの感謝を捧げている。 それゆえに、私自身もまた、作中で象徴される”六ペンス”的な価値観にさほど重きを置いていないところがある。 しかし、本作を読んで突きつけられたのは芸術という”月”にすべてを振り切ることの凄絶な代償である。 生活という”六ペンス”の領域を完全に切り捨てれば、そこには必ず歪みが生じる。 現代社会において、その歪みから完全に逃れることは極めて困難であり、誰かがそのこぼれ落ちた役割を肩代わりすることになる。 ストリックランドの周囲で傷ついた人々を思うとき、その罪深さをざりざりと歯を削りながら、噛み締めざるを得ない。 それでもなお、私は自分の心を震わせる作品を求めずにはいられない。 私にはストリックランドのような創造の才能はないが、芸術を求め、渇望してしまうという”業”を背負っているのだと感じる。 特に作中のストルーヴェが語った「美を理解するには、芸術家と同じように魂を傷つけ、世界の混沌をみつめなくてはならない。たとえるなら、美とは芸術家が鑑賞者たちに聴かせる歌のようなものだ。その歌を心で聴くには、知識と感受性と想像力がなくてはならない」という言葉が、鋭く胸に刺さる。 もちろん、芸術は気軽に楽しんでいい。しかし、もし単なる「綺麗」とか「美しい」という感動を超えて、その真髄を理解したいと願うのであれば、私たちはもっと能動的にならなければならない。 芸術家がこの世界をどのように眼差し、それをどう作品に落とし込んだのか。 それを咀嚼するためには鑑賞者である私たちもまた、自らの魂を傷つける覚悟が必要なのだと思う。 作り手が作品に込めたメッセージが届かないというのは、自らの魂を傷つけることを避けているからではないか。 魂が傷ついた瞬間に走る、あのヒリヒリとした、それでいて心地よい感覚。それを知ってしまった以上、私はもう二度と、芸術のない「六ペンス」だけの世界には戻れないのだと確信している。 - 2026年1月12日
 夜ふかしの本棚中村文則,佐川光晴,円城塔,山崎ナオコーラ,朝井リョウ,窪美澄読み終わった感想氏は本についての本が大好きである。 よく書店に行けば思いも寄らない本との出会いがあるというが、私は優柔不断なのでこれもこれもこれも、全部おもしろそう!となってしまい、存外出会いが少なかったりする でも作家さんやいろんな業種の方、つまり他人がすすめる本は自分の目に入ってくるものと全然違っていて、そこにこそ思いも寄らない出会いが発生する だから本についての本を読むと、今まで知らなかった作家やタイトルだけ知ってた作品のことを少しだけ知ることができて、読んでみようというきっかけになる 朝井リョウさん、窪美澄さんという好きな作家さんが選書する人選にいたこともあり、手にとってみたが一番読みたい!となったのは中村文則さんが紹介していた自身の著作『教団X] である。 宗教団体がテロを起こすという筋書きで紹介されており、また著者本人が自ら紹介していることもあって一番気になった。他にも何冊も気になった本があったので、しばらく何を読むかで頭を悩ませることはないと思う
夜ふかしの本棚中村文則,佐川光晴,円城塔,山崎ナオコーラ,朝井リョウ,窪美澄読み終わった感想氏は本についての本が大好きである。 よく書店に行けば思いも寄らない本との出会いがあるというが、私は優柔不断なのでこれもこれもこれも、全部おもしろそう!となってしまい、存外出会いが少なかったりする でも作家さんやいろんな業種の方、つまり他人がすすめる本は自分の目に入ってくるものと全然違っていて、そこにこそ思いも寄らない出会いが発生する だから本についての本を読むと、今まで知らなかった作家やタイトルだけ知ってた作品のことを少しだけ知ることができて、読んでみようというきっかけになる 朝井リョウさん、窪美澄さんという好きな作家さんが選書する人選にいたこともあり、手にとってみたが一番読みたい!となったのは中村文則さんが紹介していた自身の著作『教団X] である。 宗教団体がテロを起こすという筋書きで紹介されており、また著者本人が自ら紹介していることもあって一番気になった。他にも何冊も気になった本があったので、しばらく何を読むかで頭を悩ませることはないと思う
読み込み中...