

Ken
@ken_book_lover
働いていても本が読みたい30代サラリーマン
アカデミックな本の紹介や自分なりの読書術をなぜかTikTokで紹介しています。
@ken_book_lover
- 2025年5月30日
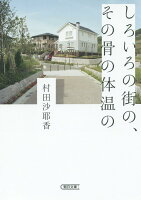 しろいろの街の、その骨の体温の村田沙耶香読み終わった最強の読書体験でした。教室のヒエラルキーとコントロールできない性欲に苦しむ女子中学生の物語。彼女がものすごく辛い思いをしながら、社会の「価値観」ではなく、自分の「価値観」を手に入れる。正直、今の自分には眩しすぎて、本当に辛い気持ちで読み進めたのだけれど、今、踏ん張らないとダメなんやと思う。
しろいろの街の、その骨の体温の村田沙耶香読み終わった最強の読書体験でした。教室のヒエラルキーとコントロールできない性欲に苦しむ女子中学生の物語。彼女がものすごく辛い思いをしながら、社会の「価値観」ではなく、自分の「価値観」を手に入れる。正直、今の自分には眩しすぎて、本当に辛い気持ちで読み進めたのだけれど、今、踏ん張らないとダメなんやと思う。 - 2025年5月30日
 夫のちんぽが入らないこだま読み終わったあぁ人の心に触れるというのはこういうことなのだと改めて思う。このふざけたタイトルの中にどれだけの人生が詰まっているか。なんて幸せな人生なんだろうと思うけど、読み手がそう思えるのは、筆者が死に物狂いで言語化してくれたから。イロモノとしてではなく、真剣に読んで欲しい一冊。
夫のちんぽが入らないこだま読み終わったあぁ人の心に触れるというのはこういうことなのだと改めて思う。このふざけたタイトルの中にどれだけの人生が詰まっているか。なんて幸せな人生なんだろうと思うけど、読み手がそう思えるのは、筆者が死に物狂いで言語化してくれたから。イロモノとしてではなく、真剣に読んで欲しい一冊。 - 2025年5月30日
 正欲朝井リョウ読み終わった「多様性」が謳われる現代において、マイノリティとマジョリティという二項対立が抑圧している"更なるマイノリティ"の存在を描いた物語。「正しい」性欲・性的指向を持つことの特権性、あるいは、「正しい」側に立つ故の不安や拘束性。我々はこれらを「想像する力」を持ち合わせていないのである。 「そう、これはもう、いま孤独に苦しむ誰かのためになんていう奉仕の気持ちからくる誓いではない。明日再びたった独りになっているかもしれない自分を、今から救い始めておきたいのだ。」(p.288) マイノリティ同士の「繋がり」ってこういうことなんやろなと。
正欲朝井リョウ読み終わった「多様性」が謳われる現代において、マイノリティとマジョリティという二項対立が抑圧している"更なるマイノリティ"の存在を描いた物語。「正しい」性欲・性的指向を持つことの特権性、あるいは、「正しい」側に立つ故の不安や拘束性。我々はこれらを「想像する力」を持ち合わせていないのである。 「そう、これはもう、いま孤独に苦しむ誰かのためになんていう奉仕の気持ちからくる誓いではない。明日再びたった独りになっているかもしれない自分を、今から救い始めておきたいのだ。」(p.288) マイノリティ同士の「繋がり」ってこういうことなんやろなと。 - 2025年5月30日
 娘についてキム・ヘジン,古川綾子読み終わった初の韓国文学、しかもクィア文学!レズビアンの娘を持つ初老女性が自らの内にある娘への愛情と差別感情とを行き来しながら、社会的な意味での「老い」と向き合う物語。「はいそれ差別です」では取りこぼされ続ける物語を読ませてくれたと思う。差別を差別と糾弾しつつ、この何かを取りこぼさずいたい。
娘についてキム・ヘジン,古川綾子読み終わった初の韓国文学、しかもクィア文学!レズビアンの娘を持つ初老女性が自らの内にある娘への愛情と差別感情とを行き来しながら、社会的な意味での「老い」と向き合う物語。「はいそれ差別です」では取りこぼされ続ける物語を読ませてくれたと思う。差別を差別と糾弾しつつ、この何かを取りこぼさずいたい。 - 2025年5月30日
 往復書簡 限界から始まる上野千鶴子,鈴木涼美読み終わった二人の往復書簡、めちゃくちゃ響いたのです…。自分のパンツを被ってオナニーをするバカな生物(男)と真面目に対峙する価値はあるのかと問う鈴木に対し、男なんてというのは冒涜であるという上野。風俗嬢の主体的な言葉を奪われたくないという鈴木に対して、それが男を免責するという上野。 男性の一人としてこの書簡をどう受け止めるのか、よく分からんというのが本音。その戸惑いの1つの要因は、圧倒的に二人がヘテロセクシュアルの男性と女性を語っていたから。改めて、ジェンダーが語られるときのセクシュアリティの後景化を感じた。 例えば、「女を買う男」という構造的なジェンダー非対称性を問題にする上野に対して、ゲイ/レズビアン風俗についてはどうなのかと問いたい。上野のロジックなら同性愛風俗は肯定されそうな気もするが。一方、若いイケメンを買うおじさんに対しては鈴木の目線は同じように当てはまるのだろう。 鈴木の経歴的に「性」の話題多めではあったものの、独身者の辛さ、結婚に対する焦燥感みたいな極めて「普通の話」も出てきたのがとても良かった。上野の凄さ、個人的には独身を貫いたことだと思っており、その上野から鈴木に宛てられた言葉は最高に良かったのでした。色んな女性に届いて欲しい。
往復書簡 限界から始まる上野千鶴子,鈴木涼美読み終わった二人の往復書簡、めちゃくちゃ響いたのです…。自分のパンツを被ってオナニーをするバカな生物(男)と真面目に対峙する価値はあるのかと問う鈴木に対し、男なんてというのは冒涜であるという上野。風俗嬢の主体的な言葉を奪われたくないという鈴木に対して、それが男を免責するという上野。 男性の一人としてこの書簡をどう受け止めるのか、よく分からんというのが本音。その戸惑いの1つの要因は、圧倒的に二人がヘテロセクシュアルの男性と女性を語っていたから。改めて、ジェンダーが語られるときのセクシュアリティの後景化を感じた。 例えば、「女を買う男」という構造的なジェンダー非対称性を問題にする上野に対して、ゲイ/レズビアン風俗についてはどうなのかと問いたい。上野のロジックなら同性愛風俗は肯定されそうな気もするが。一方、若いイケメンを買うおじさんに対しては鈴木の目線は同じように当てはまるのだろう。 鈴木の経歴的に「性」の話題多めではあったものの、独身者の辛さ、結婚に対する焦燥感みたいな極めて「普通の話」も出てきたのがとても良かった。上野の凄さ、個人的には独身を貫いたことだと思っており、その上野から鈴木に宛てられた言葉は最高に良かったのでした。色んな女性に届いて欲しい。 - 2025年5月30日
 ガザに地下鉄が走る日岡真理読み終わったアラブ文学研究者による、ガザ、ヨルダン川西岸、中東各国又は緩衝地帯(国境)に暮らすパレスチナ難民の姿を描いたエッセイ集。人権主体として認められない「ノーマン」としての難民、イスラエルによる占領によって生き地獄を「生きる」パレスチナ自治区の人々の絶望と希望を力強く文章にしている。 一貫して書かれているのは、国際社会及び各国市民によるパレスチナ/イスラエルに対する「無視」の残虐さである。「無知がホロコーストというジェノサイドを可能にしたのだとしたら、繰り返されるガザの虐殺を可能にしているのは、私たちの無関心だとも言える」と、我々の無関心を至る箇所で指摘している。 岡真理は、絶望の中生きてきたパレスチナ人が我々の平和な生を見た時に我々を許せるだうろか、と問うと同時に、あとがきにおいて、「パレスチナに希望があるとしたら、それは、私たち自身のことだ」と書く。無知/無関心が多くの命を奪う反面、知ること/関心を持つことが多くの命を救うのだと。 「この世界は、彼らがノーマンズランドのノーマンである限りは、『気の毒な難民』に対して、ときに気まぐれな温情は与えはしても、国民ならざる彼らが、『人間ならざる者』の分際で政治的権利、人間の自由を求め、世界が人間の新たな共同性へと開かれることを求めたとき、凄まじい暴力となって顕現し、彼らの上に襲いかかることになる。」
ガザに地下鉄が走る日岡真理読み終わったアラブ文学研究者による、ガザ、ヨルダン川西岸、中東各国又は緩衝地帯(国境)に暮らすパレスチナ難民の姿を描いたエッセイ集。人権主体として認められない「ノーマン」としての難民、イスラエルによる占領によって生き地獄を「生きる」パレスチナ自治区の人々の絶望と希望を力強く文章にしている。 一貫して書かれているのは、国際社会及び各国市民によるパレスチナ/イスラエルに対する「無視」の残虐さである。「無知がホロコーストというジェノサイドを可能にしたのだとしたら、繰り返されるガザの虐殺を可能にしているのは、私たちの無関心だとも言える」と、我々の無関心を至る箇所で指摘している。 岡真理は、絶望の中生きてきたパレスチナ人が我々の平和な生を見た時に我々を許せるだうろか、と問うと同時に、あとがきにおいて、「パレスチナに希望があるとしたら、それは、私たち自身のことだ」と書く。無知/無関心が多くの命を奪う反面、知ること/関心を持つことが多くの命を救うのだと。 「この世界は、彼らがノーマンズランドのノーマンである限りは、『気の毒な難民』に対して、ときに気まぐれな温情は与えはしても、国民ならざる彼らが、『人間ならざる者』の分際で政治的権利、人間の自由を求め、世界が人間の新たな共同性へと開かれることを求めたとき、凄まじい暴力となって顕現し、彼らの上に襲いかかることになる。」 - 2025年5月30日
 スポーツとLGBTQ+山口理恵子,岡田桂,稲葉佳奈子読み終わったジェンダー&セクシュアリティとスポーツに関して生じている諸々の課題について論じた一冊。 近代スポーツというものが、シス男性の身体を優位なものとして制度化されたものである以上、現代のジェンダー/セクシュアリティの多様性に対応することには限界があるというご指摘。その限界を受け入れたうえで、スポーツが持つ価値を見直す(切り下げる)ことが必要では?という問題提起で終わりました。 一方で、競技の公平性を追求するにあたっても、身長差はいいの?とか出自による身体的な特徴の差もあるよ?とかはその通りな気がした。どこまで行っても恣意的な基準にしかならないので、それを理解したうえで、スポーツ(やそれに参加する人々)にどんな意義を与えるのかを再考する必要があるんかなぁ。
スポーツとLGBTQ+山口理恵子,岡田桂,稲葉佳奈子読み終わったジェンダー&セクシュアリティとスポーツに関して生じている諸々の課題について論じた一冊。 近代スポーツというものが、シス男性の身体を優位なものとして制度化されたものである以上、現代のジェンダー/セクシュアリティの多様性に対応することには限界があるというご指摘。その限界を受け入れたうえで、スポーツが持つ価値を見直す(切り下げる)ことが必要では?という問題提起で終わりました。 一方で、競技の公平性を追求するにあたっても、身長差はいいの?とか出自による身体的な特徴の差もあるよ?とかはその通りな気がした。どこまで行っても恣意的な基準にしかならないので、それを理解したうえで、スポーツ(やそれに参加する人々)にどんな意義を与えるのかを再考する必要があるんかなぁ。 - 2025年5月30日
- 2025年5月30日
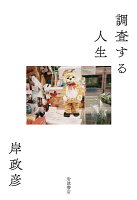 調査する人生岸政彦読み終わった2025年の1冊目。質的調査を専門とする研究者同士の対談集で、どのように調査しているのかという裏話が聞けたり、質的調査という方法論の問題について議論されていたりと面白かった。幾人かの人生の断片を丁寧に聞けば、そこから一般化できることがある、という岸先生の信念にも共感。 「よいエスノグラフィーや生活史の社会学はすべて、ディテールが書かれている」というのが印象的で、たまたま別で読んでいる脚本の教科書にも同じことが書かれていた。どれだけ細かく登場人物のリアクションを描写したシーンが書けるかどうかが大事と。研究でも物語でも、具体性こそが人に何かを伝えることができるんかな。
調査する人生岸政彦読み終わった2025年の1冊目。質的調査を専門とする研究者同士の対談集で、どのように調査しているのかという裏話が聞けたり、質的調査という方法論の問題について議論されていたりと面白かった。幾人かの人生の断片を丁寧に聞けば、そこから一般化できることがある、という岸先生の信念にも共感。 「よいエスノグラフィーや生活史の社会学はすべて、ディテールが書かれている」というのが印象的で、たまたま別で読んでいる脚本の教科書にも同じことが書かれていた。どれだけ細かく登場人物のリアクションを描写したシーンが書けるかどうかが大事と。研究でも物語でも、具体性こそが人に何かを伝えることができるんかな。 - 2025年5月30日
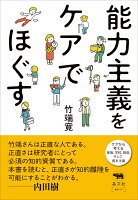 能力主義をケアでほぐす竹端寛読み終わった読んだ本の気になったところを引用しながらブログを書かれている著者が、そのブログの内容を元に1冊にまとめたもの。(何よりもそのブログがすごいと思った…。) ケアとは「ままならぬものに巻き込まれること」であると定義されていて、すごくしっくりきた。そして、そのままならぬものに巻き込まれながら、自分の都合などを崩されて、自己と他者の境界を横断することから「深い喜び」が生まれるというのもすごいなと。自分の都合を守って生きてる間はそんな喜びは感じられないんだろう。 能力主義的な価値観については、自分もかなり内面化しているなと思う。生産的な日々を送らないといけないとか、仕事ができないといけないとか。けどそれは資本主義の論理なんだぜ、というご指摘。自分が大切にしたいことは何か、どう生きたいのか、と向き合う必要がありそう。
能力主義をケアでほぐす竹端寛読み終わった読んだ本の気になったところを引用しながらブログを書かれている著者が、そのブログの内容を元に1冊にまとめたもの。(何よりもそのブログがすごいと思った…。) ケアとは「ままならぬものに巻き込まれること」であると定義されていて、すごくしっくりきた。そして、そのままならぬものに巻き込まれながら、自分の都合などを崩されて、自己と他者の境界を横断することから「深い喜び」が生まれるというのもすごいなと。自分の都合を守って生きてる間はそんな喜びは感じられないんだろう。 能力主義的な価値観については、自分もかなり内面化しているなと思う。生産的な日々を送らないといけないとか、仕事ができないといけないとか。けどそれは資本主義の論理なんだぜ、というご指摘。自分が大切にしたいことは何か、どう生きたいのか、と向き合う必要がありそう。 - 2025年5月30日
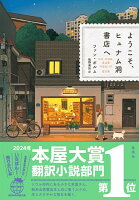 ようこそ、ヒュナム洞書店へファン・ボルム,牧野美加読み終わっためちゃくちゃ今の私が摂取したい物語そのものだった…。 良い大学を出て、良い会社に入って…という「人生の成功」から自ら逃れた人たちの物語でした。 自分を大切にしながら生きていくということの大切さを改めて実感した。 そういう意味では、自分は結構自分を大切にして人生を生きられている気がする。最近、諸々の自分の選択はこれで良かったのか、と後悔してみたりもしていたが、自分の心が死んでいくことからちゃんと逃げたんだと思う。 その自分の選択の先に今があって、合理的じゃなかったかもしれないし、賢くもなかったかもしれないけど、自分を大切にした結果だとしたら誇らしいなと思えた。 ---- 働いているときも、働いていないときも、自分自身を失わないようにしなければならない。忘れてはならないこともある。仕事をしている生活に満足感も幸せも見いだせないなら、毎日毎日が無意味で苦痛だと感じるなら、ほかの仕事を探すべきだ。なぜなら、わたしは自分に与えられた一度きりの人生を生きているのだから。(p.338) 仕事って、階段のようなものだと思っていたんです。てっぺんにたどり着くために上っていく階段。でも実際には、ご飯のようなものだった。毎日食べるご飯。自分の身体と心と精神と魂に影響を与えるご飯。この世には、急いでかき込むご飯もあれば、心を込めて丁寧に食べるご飯もある。これからは、素朴なご飯を丁寧に食べる人になりたいと思っています。わたしのために。(p.339)
ようこそ、ヒュナム洞書店へファン・ボルム,牧野美加読み終わっためちゃくちゃ今の私が摂取したい物語そのものだった…。 良い大学を出て、良い会社に入って…という「人生の成功」から自ら逃れた人たちの物語でした。 自分を大切にしながら生きていくということの大切さを改めて実感した。 そういう意味では、自分は結構自分を大切にして人生を生きられている気がする。最近、諸々の自分の選択はこれで良かったのか、と後悔してみたりもしていたが、自分の心が死んでいくことからちゃんと逃げたんだと思う。 その自分の選択の先に今があって、合理的じゃなかったかもしれないし、賢くもなかったかもしれないけど、自分を大切にした結果だとしたら誇らしいなと思えた。 ---- 働いているときも、働いていないときも、自分自身を失わないようにしなければならない。忘れてはならないこともある。仕事をしている生活に満足感も幸せも見いだせないなら、毎日毎日が無意味で苦痛だと感じるなら、ほかの仕事を探すべきだ。なぜなら、わたしは自分に与えられた一度きりの人生を生きているのだから。(p.338) 仕事って、階段のようなものだと思っていたんです。てっぺんにたどり着くために上っていく階段。でも実際には、ご飯のようなものだった。毎日食べるご飯。自分の身体と心と精神と魂に影響を与えるご飯。この世には、急いでかき込むご飯もあれば、心を込めて丁寧に食べるご飯もある。これからは、素朴なご飯を丁寧に食べる人になりたいと思っています。わたしのために。(p.339) - 2025年5月30日
 センスの哲学千葉雅也読み終わった難しいかなーと思ったけど、思ったよりも分かる〜となって読み進められておもしろかった。 センスとは、鑑賞物を脱意味化し、そのもの自体のリズムを感じることだと。 確かに自分ははものすごく意味を考えてしまうので、もっとそのもの自体を観察するという感覚を得られると良いのかなと思った。意味的な評価をせずに、目の前のものの細部を捉える感じかな。意識してみよう。
センスの哲学千葉雅也読み終わった難しいかなーと思ったけど、思ったよりも分かる〜となって読み進められておもしろかった。 センスとは、鑑賞物を脱意味化し、そのもの自体のリズムを感じることだと。 確かに自分ははものすごく意味を考えてしまうので、もっとそのもの自体を観察するという感覚を得られると良いのかなと思った。意味的な評価をせずに、目の前のものの細部を捉える感じかな。意識してみよう。
読み込み中...

