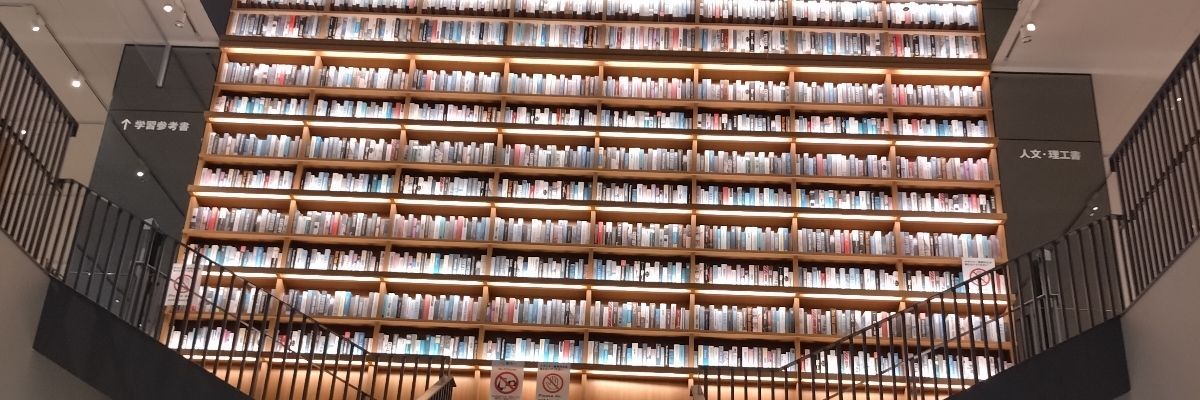
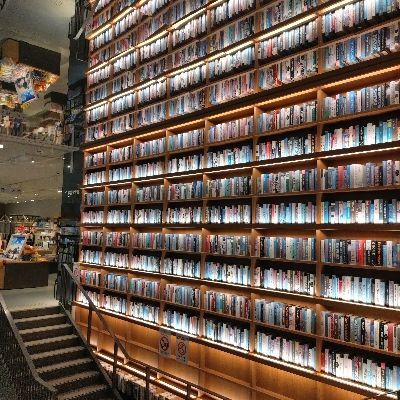
せい
@seituka
何もせずに動画で時間を消費している自分に気が付いて、とりあえず読書をしようと思った30代前半。喫茶店での書籍持ち込みとEinkのリーダーを駆使して、頑張って読書し始めました。よく読むのはビジネス系ですが、最近は名著系の小説を読もうとしてます。
- 2025年11月2日
 デュアルキャリア・カップルジェニファー・ペトリリエリ,篠田真貴子,高山真由美仕事を理由にサボってたが、またゆっくりする日が出来たので再開。 夫婦の共働きで、両方が望むキャリアプランを描くためにどうするかを考えるための本 第一の転換期は出産 この本では 価値観:満足するのはどんな人生か 限界:地理的限界、時間的限界、出向はいい?職場の移動はいい? 不安:今の不安、将来の不安 を話し合うことが2人の道を合わせるための助けになる 話し合いの時は 侮辱、批判、自己弁護、壁を作る はやめる 経済的な部分ではなく、価値観を重点を置く └収入が多くなる=望むキャリアではない 短期的な目線ではなく、長期的目線に目を向ける └仕事を辞めれば、子供と過ごせるがキャリアはどうなるのか? 目の前の実際的な問題にだけ目を向ける └どちらかが異動とともにキャリアアップに繋がるという時に、引っ越しもしてついて行って…としたとして、もう一方は不満はないのか?その場しのぎで合わせてないか? すべてをこなそうとする └何もかもをやろうとして、相手を蔑ろにしていないのか とりあえず以上まで読んだ
デュアルキャリア・カップルジェニファー・ペトリリエリ,篠田真貴子,高山真由美仕事を理由にサボってたが、またゆっくりする日が出来たので再開。 夫婦の共働きで、両方が望むキャリアプランを描くためにどうするかを考えるための本 第一の転換期は出産 この本では 価値観:満足するのはどんな人生か 限界:地理的限界、時間的限界、出向はいい?職場の移動はいい? 不安:今の不安、将来の不安 を話し合うことが2人の道を合わせるための助けになる 話し合いの時は 侮辱、批判、自己弁護、壁を作る はやめる 経済的な部分ではなく、価値観を重点を置く └収入が多くなる=望むキャリアではない 短期的な目線ではなく、長期的目線に目を向ける └仕事を辞めれば、子供と過ごせるがキャリアはどうなるのか? 目の前の実際的な問題にだけ目を向ける └どちらかが異動とともにキャリアアップに繋がるという時に、引っ越しもしてついて行って…としたとして、もう一方は不満はないのか?その場しのぎで合わせてないか? すべてをこなそうとする └何もかもをやろうとして、相手を蔑ろにしていないのか とりあえず以上まで読んだ - 2025年9月7日
 そして誰もいなくなったアガサ・クリスティー,青木久惠読み終わった司法で裁けない人殺しをした人が孤島に呼び出されて、一人一人殺される話。 金田一の少年とかの元祖になるのかなと思いつつ読んだが、面白かった。10人全員の視点があることで、誰が犯人なのか最後までわからずに読破してしまった。 カタカナの人を覚えるのは難しいが、読んでる途中でちょっと戻ってこの人何してたかなみたいに見るのが楽しかった。 他のミステリー系も読んでみたい。
そして誰もいなくなったアガサ・クリスティー,青木久惠読み終わった司法で裁けない人殺しをした人が孤島に呼び出されて、一人一人殺される話。 金田一の少年とかの元祖になるのかなと思いつつ読んだが、面白かった。10人全員の視点があることで、誰が犯人なのか最後までわからずに読破してしまった。 カタカナの人を覚えるのは難しいが、読んでる途中でちょっと戻ってこの人何してたかなみたいに見るのが楽しかった。 他のミステリー系も読んでみたい。 - 2025年9月7日
 アンドロイドは電気羊の夢を見るか?フィリップ・キンドレッド・ディック,フィリップ・K・ディック,土井宏明,浅倉久志読み終わった
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?フィリップ・キンドレッド・ディック,フィリップ・K・ディック,土井宏明,浅倉久志読み終わった - 2025年9月7日
 アンドロイドは電気羊の夢を見るか?フィリップ・キンドレッド・ディック,フィリップ・K・ディック,土井宏明,浅倉久志読み終わったよく聞くけど、実際読んだことがなかったので読んでみた。 第三次世界大戦後の割と荒廃した世界観で、生きている動物が貴重とされている状況。 そんな生きている動物を飼うことが1種のステータスになっている時代に電気羊(羊そっくりに作られた機械の羊)を飼っている男が主人公。 主人公はアンドロイドハンターなことをしており、人間のふりをして世に紛れ込んでいるアンドロイドを性格診断テスト的(感情の振れ幅をみる)なことを実施して見つけ出して、破壊し、賞金を稼いで生きている。 そんな中で、主人公が人間とアンドロイドの境目は何なのかに苦悩する物語って感じ。 アンドロイドが感情を知る物語の源流となっているのかなと思った。 主人公が人間とアンドロイドにも似たような感情があるなら、違いはなんだと苦悩しているが、結局、如何にもアンドロイドな考え方を披露されたことに対して嫌悪感を持って、別物であると理解しつつも、結局は割り切れないというのが、人間らしいんだなと思った。 割り切れない事柄を抱えつつも、日々を過ごしていけるのが人間で、全てイチゼロで考えられるのがアンドロイドなのかもしれない。
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?フィリップ・キンドレッド・ディック,フィリップ・K・ディック,土井宏明,浅倉久志読み終わったよく聞くけど、実際読んだことがなかったので読んでみた。 第三次世界大戦後の割と荒廃した世界観で、生きている動物が貴重とされている状況。 そんな生きている動物を飼うことが1種のステータスになっている時代に電気羊(羊そっくりに作られた機械の羊)を飼っている男が主人公。 主人公はアンドロイドハンターなことをしており、人間のふりをして世に紛れ込んでいるアンドロイドを性格診断テスト的(感情の振れ幅をみる)なことを実施して見つけ出して、破壊し、賞金を稼いで生きている。 そんな中で、主人公が人間とアンドロイドの境目は何なのかに苦悩する物語って感じ。 アンドロイドが感情を知る物語の源流となっているのかなと思った。 主人公が人間とアンドロイドにも似たような感情があるなら、違いはなんだと苦悩しているが、結局、如何にもアンドロイドな考え方を披露されたことに対して嫌悪感を持って、別物であると理解しつつも、結局は割り切れないというのが、人間らしいんだなと思った。 割り切れない事柄を抱えつつも、日々を過ごしていけるのが人間で、全てイチゼロで考えられるのがアンドロイドなのかもしれない。 - 2025年9月7日
 読み始めた習慣化のコツが書かれた本 気になったのを羅列 ①きりの悪いところでやめるとリスタートしやすい 仕事あえてキリの悪いところで止めることで、気になって色々考えることになり、次のリスタートが切りやすいというもの キリが悪いから残業しようという考えから脱却出来るいい習慣だと思う ②スマホを近くに置かない 移動しないと取れない位置にスマホを置くことで、注意力散漫になるのを防ぐ 本当にその通りだと思う。以前にスマホをリビングに置いて寝るようにするというのを決意したが結局できてない。今日からやるぞ。 ③スマホをテーブルに置かない。 人と喋ってる時に机の上にスマホを置いてあると、親近感や共感が低下するらしい これはやってしまいがち。友達がスマホを出してても自分は出さないことを意識しよう
読み始めた習慣化のコツが書かれた本 気になったのを羅列 ①きりの悪いところでやめるとリスタートしやすい 仕事あえてキリの悪いところで止めることで、気になって色々考えることになり、次のリスタートが切りやすいというもの キリが悪いから残業しようという考えから脱却出来るいい習慣だと思う ②スマホを近くに置かない 移動しないと取れない位置にスマホを置くことで、注意力散漫になるのを防ぐ 本当にその通りだと思う。以前にスマホをリビングに置いて寝るようにするというのを決意したが結局できてない。今日からやるぞ。 ③スマホをテーブルに置かない。 人と喋ってる時に机の上にスマホを置いてあると、親近感や共感が低下するらしい これはやってしまいがち。友達がスマホを出してても自分は出さないことを意識しよう - 2025年9月3日
 読み終わった事実質問の公式5つ ①なぜと聞きたくなったらいつ?と聞く 継続的な出来事なら、最初はいつ?や最近はいつ?って感じ ②なぜと聞かずにyes/noできく 相手が行動に移さない場合に、なんでしないの?ではなく、〇〇したことはある?という過去形の質問にする ③どう?と聞かずに、何をいつどこで誰とを聞く まどろっこしくても、相手の答えやすい事実質問から入るべし ④いつもはどう?⇒今日はどう?で、みんなは?ではなく誰?ときく お昼ご飯はどこで食べてますかではなく、今日のお昼はどこで食べましたか? ⑤次の質問に困ったら他は?ときく 似たようなものを思い出す道筋提案している あと重要なことは ①相手の回答を自分の言葉で言い直してはいけない ②問題を語り始めたは「いつ」からをきく ③そもそもその問題を解決したいの?と思ったら、これまでにした対処をきく ④どうしていいかわからないに対しては、他の誰かに聞いてみた?と聞く ⑤本当に問題なの?と聞きたくなったら、誰がどう困ったのかを聞く ⑥一体何故そうしたのかを聞く時は、他に選択肢があったかを聞く ⑦〇〇が足りないと言われたら、いくら足りないの?ときく⇒答えたら見積もりの根拠は?ときく ⑧できないと言われたら、それをやるのは誰が決めたの?と聞く、 ⑨わかってるのになんでやらないのと思ったら、黙って本人に微笑みかける 変化は内側から起こるため、外部者は信じてまつべしという言葉が印象に残った
読み終わった事実質問の公式5つ ①なぜと聞きたくなったらいつ?と聞く 継続的な出来事なら、最初はいつ?や最近はいつ?って感じ ②なぜと聞かずにyes/noできく 相手が行動に移さない場合に、なんでしないの?ではなく、〇〇したことはある?という過去形の質問にする ③どう?と聞かずに、何をいつどこで誰とを聞く まどろっこしくても、相手の答えやすい事実質問から入るべし ④いつもはどう?⇒今日はどう?で、みんなは?ではなく誰?ときく お昼ご飯はどこで食べてますかではなく、今日のお昼はどこで食べましたか? ⑤次の質問に困ったら他は?ときく 似たようなものを思い出す道筋提案している あと重要なことは ①相手の回答を自分の言葉で言い直してはいけない ②問題を語り始めたは「いつ」からをきく ③そもそもその問題を解決したいの?と思ったら、これまでにした対処をきく ④どうしていいかわからないに対しては、他の誰かに聞いてみた?と聞く ⑤本当に問題なの?と聞きたくなったら、誰がどう困ったのかを聞く ⑥一体何故そうしたのかを聞く時は、他に選択肢があったかを聞く ⑦〇〇が足りないと言われたら、いくら足りないの?ときく⇒答えたら見積もりの根拠は?ときく ⑧できないと言われたら、それをやるのは誰が決めたの?と聞く、 ⑨わかってるのになんでやらないのと思ったら、黙って本人に微笑みかける 変化は内側から起こるため、外部者は信じてまつべしという言葉が印象に残った - 2025年8月31日
- 2025年8月31日
- 2025年8月27日
 ビジネスフレームワークの教科書伊藤智久,安岡寛道,富樫佳織,小片隆久読み始めたビジネスフレームワークを羅列した本 どこかで聞いたことあるようなものでも、きちんと体系だって見ることがなかったので面白かった。 第一章ではアイデアを出すためのフレームワークが紹介されており、ブレインストーミング、マインドマップを読んだ。 ブレインストーミングは実はあまりやったことないので、どこかで実践したいと思った
ビジネスフレームワークの教科書伊藤智久,安岡寛道,富樫佳織,小片隆久読み始めたビジネスフレームワークを羅列した本 どこかで聞いたことあるようなものでも、きちんと体系だって見ることがなかったので面白かった。 第一章ではアイデアを出すためのフレームワークが紹介されており、ブレインストーミング、マインドマップを読んだ。 ブレインストーミングは実はあまりやったことないので、どこかで実践したいと思った - 2025年8月25日
 人生の経営戦略山口周また読み進めた。 心に残ったものを書く。 楽しんだほうが学べる 興味のないことを苦しんで進める人は、楽しむ人に勝てない。 内発的動機づけがある人が効果が出やすい 打席に立つことに専念する 成功の数は失敗も含めた打席の数に比例する。 失敗は忘れられるが、成功は名誉となる。 ベンチマーク=素直に真似るを実践するとよい 順序は ①課題認識を持つ 自分の課題に気付くこと ②ベンチマーク対象を選出する 能力に着目するのではなく、時間配分を真似する ③とりあえず真似てみる 素直に疑問を持たずに真似る
人生の経営戦略山口周また読み進めた。 心に残ったものを書く。 楽しんだほうが学べる 興味のないことを苦しんで進める人は、楽しむ人に勝てない。 内発的動機づけがある人が効果が出やすい 打席に立つことに専念する 成功の数は失敗も含めた打席の数に比例する。 失敗は忘れられるが、成功は名誉となる。 ベンチマーク=素直に真似るを実践するとよい 順序は ①課題認識を持つ 自分の課題に気付くこと ②ベンチマーク対象を選出する 能力に着目するのではなく、時間配分を真似する ③とりあえず真似てみる 素直に疑問を持たずに真似る - 2025年8月24日
- 2025年8月23日
- 2025年8月21日
- 2025年8月20日
 人生の経営戦略山口周読み始めた人生をマネジメントするための本 正直一度では、あまり頭に入ってこないが、まとめることで自分のものになりそうなので、まとめる。 一章パーパス 人生は時間資本を人的資本、社会資本、金融資本に変えるゲームである。 誰もが時間的資本を持っているが、それをどのタイミングでどう投資するかが重要。 時間資本⇒人的資本(スキル面や経験に投資する) 人的資本⇒社会資本(人的資本により、社会的に評価されるように) 社会資本⇒金融資本(より上質な仕事に就ける) 上記サイクルがウェルビーイングを生み出す ※人的資本は直接金融資本にならない(社会的資本(評価)がなければ稼げる仕事に就けない) 現在自分の時間的資本の投資は、通常の仕事、勉強(応用情報技術者試験)に向いている。 現在の仕事のスキル面いえば、主務では成長を感じない(下がいないので、最低限の仕事までやっている)。また残業も多い 勉強も主務には関わらないものの兼務で入っている仕事に役立つ上、部長、課長からの評価は上がるため、やっていて悪いものではない。 今無駄にしている時間は、 朝の通勤電車での睡眠 家に帰ってからのスマホ触る ここを人的資本の投資に繋がるよう意識していきたい。
人生の経営戦略山口周読み始めた人生をマネジメントするための本 正直一度では、あまり頭に入ってこないが、まとめることで自分のものになりそうなので、まとめる。 一章パーパス 人生は時間資本を人的資本、社会資本、金融資本に変えるゲームである。 誰もが時間的資本を持っているが、それをどのタイミングでどう投資するかが重要。 時間資本⇒人的資本(スキル面や経験に投資する) 人的資本⇒社会資本(人的資本により、社会的に評価されるように) 社会資本⇒金融資本(より上質な仕事に就ける) 上記サイクルがウェルビーイングを生み出す ※人的資本は直接金融資本にならない(社会的資本(評価)がなければ稼げる仕事に就けない) 現在自分の時間的資本の投資は、通常の仕事、勉強(応用情報技術者試験)に向いている。 現在の仕事のスキル面いえば、主務では成長を感じない(下がいないので、最低限の仕事までやっている)。また残業も多い 勉強も主務には関わらないものの兼務で入っている仕事に役立つ上、部長、課長からの評価は上がるため、やっていて悪いものではない。 今無駄にしている時間は、 朝の通勤電車での睡眠 家に帰ってからのスマホ触る ここを人的資本の投資に繋がるよう意識していきたい。 - 2025年8月18日
- 2025年8月18日
 勉強脳樺沢紫苑本は読んだだけでなく、アウトプットしなければいけない。また勉強の効果も継続することで自分の血肉となる。ただガチガチに固めてしまうと、精神的にも負荷がかかる。そのため「ほぼ」毎日という風にして続けるのがよい
勉強脳樺沢紫苑本は読んだだけでなく、アウトプットしなければいけない。また勉強の効果も継続することで自分の血肉となる。ただガチガチに固めてしまうと、精神的にも負荷がかかる。そのため「ほぼ」毎日という風にして続けるのがよい
読み込み中...

