
ぱち
@suwa_deer
鹿児島で古本屋とか読書会とかやってます。
- 2026年1月23日
 南国太平記 上直木三十五気になる
南国太平記 上直木三十五気になる - 2026年1月6日
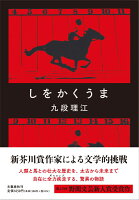 しをかくうま九段理江借りてきた読み始めた
しをかくうま九段理江借りてきた読み始めた - 2026年1月4日
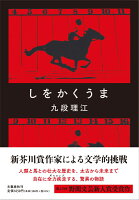 しをかくうま九段理江気になる
しをかくうま九段理江気になる - 2025年12月13日
 大きな熊が来る前に、おやすみ。島本理生読み終わった島本理生さんの本を読むのは2作目。 最初に読んだのは『あなたの呼吸が止まるまで』で、村田沙耶香さんのインタビューで紹介されてたのを見て気になって1年ほど前に読んだ。 性暴力がテーマの小説なのだけど、性加害を行う男性の無意識の振る舞いが細やかに描写されていて、フィクションではあるんだけどすごくリアルに感じた。 「〜してあげる」という言葉遣いを多用して相手に負債感を与えて自分が望む行動を取らなかったら怒ったり不機嫌になったりして自分ではなく相手に原因があるような言動をして、結局は相手をコントロールしたいだけなんだろうなという気持ちが透けて見えるわけだけど、その嫌〜〜〜な感じを凄く上手に描写した作品だなと思う。 さて、本作『大きな熊が来る前に、おやすみ。』は、YouTubeのチャンネル「ほんタメ」での紹介で知って最近読んだ。 こちらは3作品が収録された短編集。 直接的、言葉、間接的な暴力がそれぞれの作品で描かれている。 収録されている短編、「大きな熊が来る前に、おやすみ。」と「クロコダイルの午睡」に登場する男性がまた恋人に対して「お前」呼びする時点で嫌な予感が満々なわけだけども、予感の通り不穏な恋愛が展開される。 主人公の女性が恋愛対象にする男性が、端的に言ってことごとく自分本位で、読んでいて非常にモヤモヤするものがある。 『あなたの呼吸が止まるまで』の次に読んだから登場する男性に対して穿った見方をしてしまっているのかもしれないけども…。 でも特に表題作の「大きな熊が来る前に、おやすみ。」は、「関係が続く」話になっていて、これを希望と取っていいのか、ある種の地獄が続くようなものと見るのか、個人的にはどう受け取ったらいいのか非常に難しく感じた。(ぼくは「地獄説」を推したい) こう書いてるとまるで悪い小説だったかのように思われるかもしれないが、いい意味でモヤモヤや嫌な感じを上手く書いていて、とても心に残るというか感情を揺さぶられる良い小説だと思う。 不穏なもの、嫌な感じのもの、モヤモヤするものを接種したいという時に読むのをオススメしたい。
大きな熊が来る前に、おやすみ。島本理生読み終わった島本理生さんの本を読むのは2作目。 最初に読んだのは『あなたの呼吸が止まるまで』で、村田沙耶香さんのインタビューで紹介されてたのを見て気になって1年ほど前に読んだ。 性暴力がテーマの小説なのだけど、性加害を行う男性の無意識の振る舞いが細やかに描写されていて、フィクションではあるんだけどすごくリアルに感じた。 「〜してあげる」という言葉遣いを多用して相手に負債感を与えて自分が望む行動を取らなかったら怒ったり不機嫌になったりして自分ではなく相手に原因があるような言動をして、結局は相手をコントロールしたいだけなんだろうなという気持ちが透けて見えるわけだけど、その嫌〜〜〜な感じを凄く上手に描写した作品だなと思う。 さて、本作『大きな熊が来る前に、おやすみ。』は、YouTubeのチャンネル「ほんタメ」での紹介で知って最近読んだ。 こちらは3作品が収録された短編集。 直接的、言葉、間接的な暴力がそれぞれの作品で描かれている。 収録されている短編、「大きな熊が来る前に、おやすみ。」と「クロコダイルの午睡」に登場する男性がまた恋人に対して「お前」呼びする時点で嫌な予感が満々なわけだけども、予感の通り不穏な恋愛が展開される。 主人公の女性が恋愛対象にする男性が、端的に言ってことごとく自分本位で、読んでいて非常にモヤモヤするものがある。 『あなたの呼吸が止まるまで』の次に読んだから登場する男性に対して穿った見方をしてしまっているのかもしれないけども…。 でも特に表題作の「大きな熊が来る前に、おやすみ。」は、「関係が続く」話になっていて、これを希望と取っていいのか、ある種の地獄が続くようなものと見るのか、個人的にはどう受け取ったらいいのか非常に難しく感じた。(ぼくは「地獄説」を推したい) こう書いてるとまるで悪い小説だったかのように思われるかもしれないが、いい意味でモヤモヤや嫌な感じを上手く書いていて、とても心に残るというか感情を揺さぶられる良い小説だと思う。 不穏なもの、嫌な感じのもの、モヤモヤするものを接種したいという時に読むのをオススメしたい。 - 2025年12月8日
 ハリー・オーガスト、15回目の人生 (角川文庫)クレア・ノース,雨海弘美読み終わったSF的な設定がなかなか面白いなと思いながら読み進めたけども、ほぼスパイ物で主人公と宿敵との駆け引きというか静かな対決がメインかなと思う。 本筋とは異なるとは思うけど、でもツッコミどころは結構あってそちらが気になってしまう。 個人的に一番気になるのはこの世界における「時間」がどうなっているのかという点。(設定に順守するなら時間が存在しないことになってしまわないか?) あと作者が意識してるかどうかは分からないけど設定でも物語的にも「反出生主義」に関連する展開になっていてここをどう捉えたらいいかも難しく感じた。 現時点では消化不良ではあるんだけども、男性性を考えるのにいろんな要素が入った物語だと思う。 またどこかの折に再読したい。
ハリー・オーガスト、15回目の人生 (角川文庫)クレア・ノース,雨海弘美読み終わったSF的な設定がなかなか面白いなと思いながら読み進めたけども、ほぼスパイ物で主人公と宿敵との駆け引きというか静かな対決がメインかなと思う。 本筋とは異なるとは思うけど、でもツッコミどころは結構あってそちらが気になってしまう。 個人的に一番気になるのはこの世界における「時間」がどうなっているのかという点。(設定に順守するなら時間が存在しないことになってしまわないか?) あと作者が意識してるかどうかは分からないけど設定でも物語的にも「反出生主義」に関連する展開になっていてここをどう捉えたらいいかも難しく感じた。 現時点では消化不良ではあるんだけども、男性性を考えるのにいろんな要素が入った物語だと思う。 またどこかの折に再読したい。 - 2025年12月8日
 ネット怪談の民俗学廣田龍平読み終わったぼくは怖いのが苦手で知識が全くないまま読み進めたのだけど、ざっくりとネット怪談の変遷と事例を知れたのがまず良かった。 それと、怖いものを求める人のことというかその気持ちがこれまで全然想像できなかったのだけども、ネット怪談の投稿にレスしたり実際に現地に行ってそれを報告する人が出てきたりと、肝試し的なちょっと危険な遊びを楽しむような感覚でネット怪談を楽しんでいるんだろうなというのが少し分かってそれも良かった。 因習村系から世界系的なホラーへのシフトが現代社会の価値観を反映しているのではという指摘も面白かった。
ネット怪談の民俗学廣田龍平読み終わったぼくは怖いのが苦手で知識が全くないまま読み進めたのだけど、ざっくりとネット怪談の変遷と事例を知れたのがまず良かった。 それと、怖いものを求める人のことというかその気持ちがこれまで全然想像できなかったのだけども、ネット怪談の投稿にレスしたり実際に現地に行ってそれを報告する人が出てきたりと、肝試し的なちょっと危険な遊びを楽しむような感覚でネット怪談を楽しんでいるんだろうなというのが少し分かってそれも良かった。 因習村系から世界系的なホラーへのシフトが現代社会の価値観を反映しているのではという指摘も面白かった。 - 2025年11月17日
 ハリー・オーガスト、15回目の人生 (角川文庫)クレア・ノース,雨海弘美読んでる
ハリー・オーガスト、15回目の人生 (角川文庫)クレア・ノース,雨海弘美読んでる - 2025年10月9日
 虐殺器官 (ハヤカワ文庫JA)伊藤計劃読み終わった読書会『ハーモニー』読書会があるためやはり読んでおかないとと思い着手して読了。 数年前に一度『ハーモニー』は読んでいたので比較しながら読み進めたけど、共通する要素を用いながら裏返しにしたような物語を描いていることにまずは驚いた。 『虐殺器官』の話も構造的なものが重層的に作り込まれていて大変読み応えがあった。 まず気になったのが主人公の精神面。母親を亡くしたトラウマと情報管理社会、そして世界のあり方とがパラレルにつながることで形作られているように思う。 シングルマザーで育てられ家では常に母親の視線を感じていたということと、情報管理社会によってモノや行為とがすべて自分とタグ付けされることによって自己規定ができテロに晒されない安心感を得られていることとがパラレルにつながっているように描かれているように感じた。 主人公は軍人で紛争地帯で平然と人を殺す仕事をしている。一方で事故に遭い植物状態になった母親を安楽死させたことに罪悪感を抱き苛まされる日々を送っている。 ここには圧倒的な非対称性があって、これがこの作品のテーマなのだろうと思った。 もう一つ物語的に重要な要素がある。 それはキリスト教徒であり主人公の仕事の後輩でもある人物が自殺し、主人公にまた別種のトラウマを与えていることだ。 主人公は後輩がなぜ自殺したのか?をずっと考え続けるわけだけど、たぶんこれは彼(後輩)なりの非対称性の引き受け方を選んだ結果なのだろうと思う。 後輩の死は、世界への不信感をもたらし、物語の進行に伴い主人公のアイデンティティもゆらいでいく。 最終的にはそのアイデンティティの頼りにしていた人物たちを次々と亡くしていき、この世界に自分しかいないような空虚さだけが残る。 結末はこの空虚さからくる主人公の選択であり、せめてその意志だけでも示したいという感情だったのかなと想像する。 物語の中である種の要素として言及されながらも徹底して「他者の痛み」そのものを物語の内側に引き入れて描くことはしなかった。 そこを描こうとしたのが『ハーモニー』だったのかもしれない。 数年越しに再読して確かめたい。
虐殺器官 (ハヤカワ文庫JA)伊藤計劃読み終わった読書会『ハーモニー』読書会があるためやはり読んでおかないとと思い着手して読了。 数年前に一度『ハーモニー』は読んでいたので比較しながら読み進めたけど、共通する要素を用いながら裏返しにしたような物語を描いていることにまずは驚いた。 『虐殺器官』の話も構造的なものが重層的に作り込まれていて大変読み応えがあった。 まず気になったのが主人公の精神面。母親を亡くしたトラウマと情報管理社会、そして世界のあり方とがパラレルにつながることで形作られているように思う。 シングルマザーで育てられ家では常に母親の視線を感じていたということと、情報管理社会によってモノや行為とがすべて自分とタグ付けされることによって自己規定ができテロに晒されない安心感を得られていることとがパラレルにつながっているように描かれているように感じた。 主人公は軍人で紛争地帯で平然と人を殺す仕事をしている。一方で事故に遭い植物状態になった母親を安楽死させたことに罪悪感を抱き苛まされる日々を送っている。 ここには圧倒的な非対称性があって、これがこの作品のテーマなのだろうと思った。 もう一つ物語的に重要な要素がある。 それはキリスト教徒であり主人公の仕事の後輩でもある人物が自殺し、主人公にまた別種のトラウマを与えていることだ。 主人公は後輩がなぜ自殺したのか?をずっと考え続けるわけだけど、たぶんこれは彼(後輩)なりの非対称性の引き受け方を選んだ結果なのだろうと思う。 後輩の死は、世界への不信感をもたらし、物語の進行に伴い主人公のアイデンティティもゆらいでいく。 最終的にはそのアイデンティティの頼りにしていた人物たちを次々と亡くしていき、この世界に自分しかいないような空虚さだけが残る。 結末はこの空虚さからくる主人公の選択であり、せめてその意志だけでも示したいという感情だったのかなと想像する。 物語の中である種の要素として言及されながらも徹底して「他者の痛み」そのものを物語の内側に引き入れて描くことはしなかった。 そこを描こうとしたのが『ハーモニー』だったのかもしれない。 数年越しに再読して確かめたい。 - 2025年10月1日
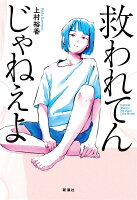 救われてんじゃねえよ上村裕香読み終わった
救われてんじゃねえよ上村裕香読み終わった - 2025年9月26日
- 2025年9月23日
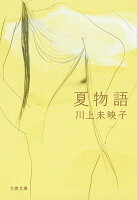 夏物語川上未映子読み終わった読書会読書会課題本読書会の課題本で読了。 川上未映子さんの長編を読むのは初めて。 二部構成で、第一部は芥川賞受賞作「乳と卵」を書き直したもの。(ほぼ同じ内容らしい) 第二部は実質「乳と卵」の続編に当たる。 一部と二部で内容もそうだけど文章の印象もだいぶ異なる。 二部の文章は主人公・夏子が目にした風景を描写した文や、そこに夢みたいなものが入り混じった文章が多い。 会話文はいいのだけども、どうも地の文章が肌に合わないのか入り込めない感じがあった。 それと本筋とは関係のない小さな描写(というか設定?)につまずくことが多かった。 【つまずいた点】 ・緑子(夏子の姪)が、巻子(夏子の姉)との関係がこじれて喋らなくなるという設定。本文では母親以外、学校ではしゃべると書いてある。が、夏子ともしゃべらず筆談でやりとりしている。母親と喋らない理由は分かるが、なぜ夏子とも喋らないのかが分からなかった。 →読書会でこの点について話したところ、夏子のこともほぼ母親と同じ様な存在と見られているか、夏子を通じて巻子に自分が話したことが伝わってしまうことを危惧したのではないか?とコメントをもらい腑に落ちた。 ・夏子と緑子が遊園地に行く場面。観覧車に乗ることになるのだが、ここでの夏子が高所恐怖症の気が少しあるという設定。その気があると書かれながら特に何事もなく普通に観覧車に乗ってしまうので何の意図があってこの設定を作ったのかが分からない。 →この理由については結局分からなかったが、読書会で第二部の終盤でも「観覧車」が出てくるので「観覧車」には何か重要なモチーフがあるのでは?というコメントがありハッとさせられた。 【印象深かった登場人物】 登場人物としては主人公の夏子よりも、仙川さんと善さんの2人が気になる存在だった。 ・仙川さん 仕事へのこだわり様が強い。(夏子が)子どもを持つことへの強い否定は何なのか?明確に書かれてはいないけど同性愛的な面を持っていたりするのかなと少し想像した。作品を世界に残すことが仙川さんの生き甲斐になってるのかなと。作者はなぜ仙川さんを殺してしまったのか?その意図が分からなかった。仙川さんが亡くなることによって夏子の作品作りに変化が起きるとかならまだ分かるけど、そういう話にはなっていない。物語的意味は何なのか?マジョリティ側の人たちが夏子から離れていくということを意図してのなら分からなくはないけれども。 ・善さん 言ってることは分かる。 分かるというのは、子どもを産むべきではない(反出生主義)ということではなくて、世界には痛みがあるということ。 痛みに対する向き合い方はいろいろあると思う。 現実的に考えるなら少しでも痛みを減らす社会を作る様にがんばるだとか、物語的に考えるなら暴力を振るった相手に復讐してやろうとか。 でも善さんは痛みをただ受け入れてる人の様に見える。 闘ったり逃げたりする気力が湧かないほど傷ついてる人なんだろうと思うけれども、じゃあ善さんにとっての救いって何なんだろうと考えてしまう。活動(当事者から考える会の)を続けることで「痛み」を想起することから離れられなくなってしまってはないか?善さんが活動を続ける理由も見えない。読書会で指摘があったけどもそうした負のエネルギーを元にして善さんは生きているのではないかと。「善」という名前にも意図するものがあるのだろうとは思うがまだ答えは出ない。 気になった点をつらつら書いたけども、面白くなかったわけではない。いろんな現代的な要素が入っていて面白く読み応えのある作品ではある。 読書会の参加者さんが言っていたが川上未映子さんの他の著作とはちょっと異なる読み心地だったらしい。 他の長編もチャレンジしたいと思うが、『夏物語』関連でエッセイ本『きみは赤ちゃん』はとりあえず近いうちに読んでおきたい。
夏物語川上未映子読み終わった読書会読書会課題本読書会の課題本で読了。 川上未映子さんの長編を読むのは初めて。 二部構成で、第一部は芥川賞受賞作「乳と卵」を書き直したもの。(ほぼ同じ内容らしい) 第二部は実質「乳と卵」の続編に当たる。 一部と二部で内容もそうだけど文章の印象もだいぶ異なる。 二部の文章は主人公・夏子が目にした風景を描写した文や、そこに夢みたいなものが入り混じった文章が多い。 会話文はいいのだけども、どうも地の文章が肌に合わないのか入り込めない感じがあった。 それと本筋とは関係のない小さな描写(というか設定?)につまずくことが多かった。 【つまずいた点】 ・緑子(夏子の姪)が、巻子(夏子の姉)との関係がこじれて喋らなくなるという設定。本文では母親以外、学校ではしゃべると書いてある。が、夏子ともしゃべらず筆談でやりとりしている。母親と喋らない理由は分かるが、なぜ夏子とも喋らないのかが分からなかった。 →読書会でこの点について話したところ、夏子のこともほぼ母親と同じ様な存在と見られているか、夏子を通じて巻子に自分が話したことが伝わってしまうことを危惧したのではないか?とコメントをもらい腑に落ちた。 ・夏子と緑子が遊園地に行く場面。観覧車に乗ることになるのだが、ここでの夏子が高所恐怖症の気が少しあるという設定。その気があると書かれながら特に何事もなく普通に観覧車に乗ってしまうので何の意図があってこの設定を作ったのかが分からない。 →この理由については結局分からなかったが、読書会で第二部の終盤でも「観覧車」が出てくるので「観覧車」には何か重要なモチーフがあるのでは?というコメントがありハッとさせられた。 【印象深かった登場人物】 登場人物としては主人公の夏子よりも、仙川さんと善さんの2人が気になる存在だった。 ・仙川さん 仕事へのこだわり様が強い。(夏子が)子どもを持つことへの強い否定は何なのか?明確に書かれてはいないけど同性愛的な面を持っていたりするのかなと少し想像した。作品を世界に残すことが仙川さんの生き甲斐になってるのかなと。作者はなぜ仙川さんを殺してしまったのか?その意図が分からなかった。仙川さんが亡くなることによって夏子の作品作りに変化が起きるとかならまだ分かるけど、そういう話にはなっていない。物語的意味は何なのか?マジョリティ側の人たちが夏子から離れていくということを意図してのなら分からなくはないけれども。 ・善さん 言ってることは分かる。 分かるというのは、子どもを産むべきではない(反出生主義)ということではなくて、世界には痛みがあるということ。 痛みに対する向き合い方はいろいろあると思う。 現実的に考えるなら少しでも痛みを減らす社会を作る様にがんばるだとか、物語的に考えるなら暴力を振るった相手に復讐してやろうとか。 でも善さんは痛みをただ受け入れてる人の様に見える。 闘ったり逃げたりする気力が湧かないほど傷ついてる人なんだろうと思うけれども、じゃあ善さんにとっての救いって何なんだろうと考えてしまう。活動(当事者から考える会の)を続けることで「痛み」を想起することから離れられなくなってしまってはないか?善さんが活動を続ける理由も見えない。読書会で指摘があったけどもそうした負のエネルギーを元にして善さんは生きているのではないかと。「善」という名前にも意図するものがあるのだろうとは思うがまだ答えは出ない。 気になった点をつらつら書いたけども、面白くなかったわけではない。いろんな現代的な要素が入っていて面白く読み応えのある作品ではある。 読書会の参加者さんが言っていたが川上未映子さんの他の著作とはちょっと異なる読み心地だったらしい。 他の長編もチャレンジしたいと思うが、『夏物語』関連でエッセイ本『きみは赤ちゃん』はとりあえず近いうちに読んでおきたい。 - 2025年9月20日
 ドバラダ門山下洋輔積読中読みたい
ドバラダ門山下洋輔積読中読みたい - 2025年9月20日
 女と刀中村きい子読んでる
女と刀中村きい子読んでる - 2025年9月17日
 ハリー・オーガスト、15回目の人生 (角川文庫)クレア・ノース,雨海弘美気になる
ハリー・オーガスト、15回目の人生 (角川文庫)クレア・ノース,雨海弘美気になる - 2025年9月15日
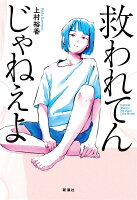 救われてんじゃねえよ上村裕香読み始めた
救われてんじゃねえよ上村裕香読み始めた - 2025年9月14日
- 2025年9月11日
- 2025年9月11日
 グッナイ・ナタリー・クローバー須藤アンナ読み終わった夏休みに町の外の世界からやって来た女の子に出会って友達になることをきっかけに家族や閉じた世界の呪縛から逃れようとする女の子の物語。 家族や町の価値観を内面化しているあまり、自分を変えたいと思っていてもなかなか変えられないもどかしさ。その心理描写がとても上手く描かれていると思う。 少しずつ少しずつ変わっていきある決意につながるのだけれども、主人公の心は確かに変わっていても閉じた世界はそのまま佇んでいて、現実的な問題が確かにありながらも物語として希望を描いてるところに作者の誠実さが窺える。 この作品がデビュー作ということなのでこの先どのような物語を書いていくのかとても楽しみ。
グッナイ・ナタリー・クローバー須藤アンナ読み終わった夏休みに町の外の世界からやって来た女の子に出会って友達になることをきっかけに家族や閉じた世界の呪縛から逃れようとする女の子の物語。 家族や町の価値観を内面化しているあまり、自分を変えたいと思っていてもなかなか変えられないもどかしさ。その心理描写がとても上手く描かれていると思う。 少しずつ少しずつ変わっていきある決意につながるのだけれども、主人公の心は確かに変わっていても閉じた世界はそのまま佇んでいて、現実的な問題が確かにありながらも物語として希望を描いてるところに作者の誠実さが窺える。 この作品がデビュー作ということなのでこの先どのような物語を書いていくのかとても楽しみ。 - 2025年9月6日
 グッナイ・ナタリー・クローバー須藤アンナ読み始めた
グッナイ・ナタリー・クローバー須藤アンナ読み始めた - 2025年9月2日
読み込み中...

