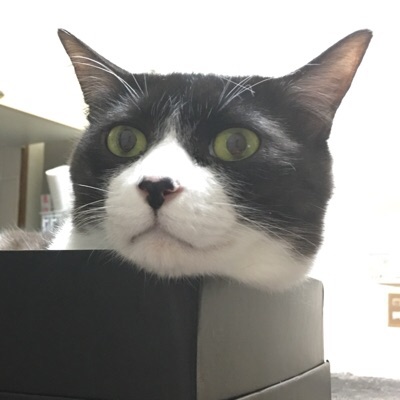刑務所に回復共同体をつくる

38件の記録
 いっちー@icchii3172025年10月4日読んでる刑務官からの「暴力」の章を読んでいて、そんな組織に所属したことがないからもはやフィクションではないかと思うほどだけど、本当にタチが悪い。受刑者よりも、むしろ刑務官のほうが悪質である。 今更だけど青土社が出しているんだなぁ。組織で苦労したことがある人には、ぜひ一度は読んでみてほしい。最も極端な環境下で起こる過激なエピソードがたくさん載っている。そしてそこに乗り込んでいった果敢な毛利さんの話、そして結果的には毛利さんも刑務官によって実質追い出されてしまった。 毛利さんの方に全面的に共感するし私の周りもきっとそう思うけど、刑務所内に行くと比率が逆転し、理解者は1人もいないような状況になる。異常な空間が当たり前にあり、受刑者は更生する機会がないまま抑圧され、ただ耐え忍ぶだけ。そんなことが罷り通っているのを知って本当におかしいし、悲しい。
いっちー@icchii3172025年10月4日読んでる刑務官からの「暴力」の章を読んでいて、そんな組織に所属したことがないからもはやフィクションではないかと思うほどだけど、本当にタチが悪い。受刑者よりも、むしろ刑務官のほうが悪質である。 今更だけど青土社が出しているんだなぁ。組織で苦労したことがある人には、ぜひ一度は読んでみてほしい。最も極端な環境下で起こる過激なエピソードがたくさん載っている。そしてそこに乗り込んでいった果敢な毛利さんの話、そして結果的には毛利さんも刑務官によって実質追い出されてしまった。 毛利さんの方に全面的に共感するし私の周りもきっとそう思うけど、刑務所内に行くと比率が逆転し、理解者は1人もいないような状況になる。異常な空間が当たり前にあり、受刑者は更生する機会がないまま抑圧され、ただ耐え忍ぶだけ。そんなことが罷り通っているのを知って本当におかしいし、悲しい。

 いっちー@icchii3172025年10月1日熟読中けっこう胸がいっぱいになってしまって書ききれないというか、全部が良いんだけど、こんなに熟読できる機会もないかもしれないから頑張って書き留めておく。 p117で「「他人の尊厳を奪ったんだから奪われて当然だ」と思う読者もいるかもしれない。しかし、人を殴った人を誰かが代わりに殴り倒しても結局被害者が増えるだけであるのと同様、代理の懲罰など意味がない。毎日尊厳を踏みにじられてまっとうになれというのは、無茶な話だ。」とあるけど、もうこの言葉が全てだと思う。 それでも現実にあるのは、「反省しろ」「しています」「いや、反省していない」「しています」のような押し問答で、刑務官のスキル不足や抑圧的な文化がそのまま出てしまっている。「短期は満期」ということわざのようなものが蔓延していて、受刑者は考えずに耐え忍ぶことを学んでいく。 p221で「守られたTCの環境で、いくらいろいろできるようになっても、逆風の多い社会では、うまくいかないこともあるのではないか」と言う問いに対して、 訓練生が「TCって他よりも揉め事多いと思うんです。他のところは力関係ができちゃってて揉めないっていうか。押さえる方と押さえられる方ができちゃってて。TCはでも言いたいこと言うでしょ。自然に意見の食い違いができる。」 と語っており、まさに、力関係のある場所では受刑者に関わらず意見をぶつける機会がほとんどない。他を知らないと、緊張した抑圧/支配の構造から抜け出すことができない。TCはたしに守られた環境ではあるが、そこで人との関わりの原則を学ぶことに意味があり、その環境を今度は社会に持ち帰ることができる。親や妻、子どもときちんと向き合って安心・安全な場所を作る責任を果たすことができる。 TCは性格を変えるのではなく、生き方のパラダイムを変えることを目的としている。 読んでいて、ここまでの成長が見られるコミュニティを他に知らない。
いっちー@icchii3172025年10月1日熟読中けっこう胸がいっぱいになってしまって書ききれないというか、全部が良いんだけど、こんなに熟読できる機会もないかもしれないから頑張って書き留めておく。 p117で「「他人の尊厳を奪ったんだから奪われて当然だ」と思う読者もいるかもしれない。しかし、人を殴った人を誰かが代わりに殴り倒しても結局被害者が増えるだけであるのと同様、代理の懲罰など意味がない。毎日尊厳を踏みにじられてまっとうになれというのは、無茶な話だ。」とあるけど、もうこの言葉が全てだと思う。 それでも現実にあるのは、「反省しろ」「しています」「いや、反省していない」「しています」のような押し問答で、刑務官のスキル不足や抑圧的な文化がそのまま出てしまっている。「短期は満期」ということわざのようなものが蔓延していて、受刑者は考えずに耐え忍ぶことを学んでいく。 p221で「守られたTCの環境で、いくらいろいろできるようになっても、逆風の多い社会では、うまくいかないこともあるのではないか」と言う問いに対して、 訓練生が「TCって他よりも揉め事多いと思うんです。他のところは力関係ができちゃってて揉めないっていうか。押さえる方と押さえられる方ができちゃってて。TCはでも言いたいこと言うでしょ。自然に意見の食い違いができる。」 と語っており、まさに、力関係のある場所では受刑者に関わらず意見をぶつける機会がほとんどない。他を知らないと、緊張した抑圧/支配の構造から抜け出すことができない。TCはたしに守られた環境ではあるが、そこで人との関わりの原則を学ぶことに意味があり、その環境を今度は社会に持ち帰ることができる。親や妻、子どもときちんと向き合って安心・安全な場所を作る責任を果たすことができる。 TCは性格を変えるのではなく、生き方のパラダイムを変えることを目的としている。 読んでいて、ここまでの成長が見られるコミュニティを他に知らない。
 いっちー@icchii3172025年8月13日読んでる「本当の意味で自分がしていることの結果を最後まで見通した上で全てを受け入れて犯罪をしている人などほとんどいない。」 加害者の認知の障害や、共感性の欠如などの問題ではなく、「おいしいものを見たら、血糖値が高くてもいろんな言い訳をして食べてしまうような私たちと同じ弱さであり人間らしさ」なのだ。 そして「人は自分がしたことの否定的な現実や痛みを突きつけられることで、痛みに対成長すると思われがちだが、本当は逆で、成長してからでないとつらい現実と痛みには耐え切れない。」
いっちー@icchii3172025年8月13日読んでる「本当の意味で自分がしていることの結果を最後まで見通した上で全てを受け入れて犯罪をしている人などほとんどいない。」 加害者の認知の障害や、共感性の欠如などの問題ではなく、「おいしいものを見たら、血糖値が高くてもいろんな言い訳をして食べてしまうような私たちと同じ弱さであり人間らしさ」なのだ。 そして「人は自分がしたことの否定的な現実や痛みを突きつけられることで、痛みに対成長すると思われがちだが、本当は逆で、成長してからでないとつらい現実と痛みには耐え切れない。」

 いっちー@icchii3172025年8月13日読み始めた図書館で借りたそのあとに、借りててもう返さなきゃなこの本を開くと、数ページで胸いっぱいになる。話し合うことがいかに特別なことなのか。それ以前にしんどさを抱えることがいかにしんどいか。まずは、言葉にする前のしんどさを抱える力を伸ばすところから。そして、握りしめていたものを手放す(語る)ことへ。 プリズンサークルを観たので、思い返しながら。興味深いなぁ。
いっちー@icchii3172025年8月13日読み始めた図書館で借りたそのあとに、借りててもう返さなきゃなこの本を開くと、数ページで胸いっぱいになる。話し合うことがいかに特別なことなのか。それ以前にしんどさを抱えることがいかにしんどいか。まずは、言葉にする前のしんどさを抱える力を伸ばすところから。そして、握りしめていたものを手放す(語る)ことへ。 プリズンサークルを観たので、思い返しながら。興味深いなぁ。 いっちー@icchii3172025年8月13日読んでる『プリズン・サークル』の上映会で監督が話していたけど、刑務官のやばさが浮き彫りになる。いかにして、本来の職務的動機が失われ、保身や昇進をかけて動くようになるのか。そして被収容者を権力で支配するようになるのか。しかしいわゆる体育会系の組織にいたことのある人なら、すんなり受け入れてしまうだろうとも思って恐ろしい。 上映会のときも思ったけど、刑務所に入ってもこんな人たちのもとのこんな環境では厚生できないだろうと思うし、正直何の変化もないまま釈放されたりするのは怖いと思ってしまう。p67の「私は少年鑑別所で単に話させていただけであって、語ってもらっていたわけではないんだ」という著者の気づきにもある通り、形だけになると変容は生まれないと思う。日本の官僚的な組織文化の本当に残念なところ。 アミティというアメリカの施設の映画もあるんだな。p70でスタッフが「当事者としての経験も使っているが、その後に学んださまざまな知識や考えを最大限に持ち込」んで「自分のすべてを使っ」た結果、肩書きにとらわれず「ナヤさんそのもの」になっているという表現があり、興味深かった。「自分のすべてを使う」という表現が素敵だった。個人的には持ってるものを使わなくてどうするの?とも思う。肩書きにはめられて、徐々にその範囲内でしか自分を出さなくなってしまうようになるのか。逆に、その人がすべてを使った結果、肩書きを超えてその人「そのもの」として現れてくるのか。面白い。 「援助職の盾への解毒剤は「知ること」だと思っていた。私だったが、それよりも自分が開かれること、全てを使うことだと考えを更新した。」p73大共感👏 そしてその考え方、あり方が「自分のエネルギーを全部使うこと」というHowにつながっていく。そしてよくスピ界隈で「エネルギー」とか「波動」の高さ、低さの話があると思うけど、別にそこの序列が重要なのではなく、単にWhyを追求していった結果、そのようなあり方につながっていくのではないかと思った。 (補足:毛利さんは各職種の組織に感じた違和感を分解する際に、サイモン・シネックのTED Talk「なぜから始めよう」のなかで、「Why」が人や組織、顧客に影響を与える。そこからHow, Whatにつながるという論を参考にしている。)
いっちー@icchii3172025年8月13日読んでる『プリズン・サークル』の上映会で監督が話していたけど、刑務官のやばさが浮き彫りになる。いかにして、本来の職務的動機が失われ、保身や昇進をかけて動くようになるのか。そして被収容者を権力で支配するようになるのか。しかしいわゆる体育会系の組織にいたことのある人なら、すんなり受け入れてしまうだろうとも思って恐ろしい。 上映会のときも思ったけど、刑務所に入ってもこんな人たちのもとのこんな環境では厚生できないだろうと思うし、正直何の変化もないまま釈放されたりするのは怖いと思ってしまう。p67の「私は少年鑑別所で単に話させていただけであって、語ってもらっていたわけではないんだ」という著者の気づきにもある通り、形だけになると変容は生まれないと思う。日本の官僚的な組織文化の本当に残念なところ。 アミティというアメリカの施設の映画もあるんだな。p70でスタッフが「当事者としての経験も使っているが、その後に学んださまざまな知識や考えを最大限に持ち込」んで「自分のすべてを使っ」た結果、肩書きにとらわれず「ナヤさんそのもの」になっているという表現があり、興味深かった。「自分のすべてを使う」という表現が素敵だった。個人的には持ってるものを使わなくてどうするの?とも思う。肩書きにはめられて、徐々にその範囲内でしか自分を出さなくなってしまうようになるのか。逆に、その人がすべてを使った結果、肩書きを超えてその人「そのもの」として現れてくるのか。面白い。 「援助職の盾への解毒剤は「知ること」だと思っていた。私だったが、それよりも自分が開かれること、全てを使うことだと考えを更新した。」p73大共感👏 そしてその考え方、あり方が「自分のエネルギーを全部使うこと」というHowにつながっていく。そしてよくスピ界隈で「エネルギー」とか「波動」の高さ、低さの話があると思うけど、別にそこの序列が重要なのではなく、単にWhyを追求していった結果、そのようなあり方につながっていくのではないかと思った。 (補足:毛利さんは各職種の組織に感じた違和感を分解する際に、サイモン・シネックのTED Talk「なぜから始めよう」のなかで、「Why」が人や組織、顧客に影響を与える。そこからHow, Whatにつながるという論を参考にしている。)

 ryo@mybook122222025年7月5日買った読み終わった高校生の頃、心理学を志した僕に対して友達が「カウンセラーになるんやったら、自分の心のケアをしてくれる人もおったほうがいいね」と言ってくれた。 僕は犯罪心理学を専攻したけれど結局カウンセラーにはならない人生を歩んでいて、これを読んでいるとやはり相当な思いや覚悟が必要で、自分にはそれが足りなかったのだと感じる。物理的にも文化的にも閉ざされた異質な世界で、それまでの常識をまるごとひっくり返すような矯正方針を掲げることの苦悩たるや、計り知れない。 我々が望んでいるのは犯罪者が刑務所から甦らない世界なのか?抵抗されないように権威を振りかざし、萎縮して生きさせることが目的なのか?そして犯罪者云々の以前に、人どうしで心からの対話をすること自体の難しさをひしひしと感じる。 一方で、「これを読んだだけで何もかも分かった気になるなよ」というメッセージを毛利さん自身が発信しているようにも思う。心理職の目線だけでなく、多角的な視野をもって、もっと考えなければならない。
ryo@mybook122222025年7月5日買った読み終わった高校生の頃、心理学を志した僕に対して友達が「カウンセラーになるんやったら、自分の心のケアをしてくれる人もおったほうがいいね」と言ってくれた。 僕は犯罪心理学を専攻したけれど結局カウンセラーにはならない人生を歩んでいて、これを読んでいるとやはり相当な思いや覚悟が必要で、自分にはそれが足りなかったのだと感じる。物理的にも文化的にも閉ざされた異質な世界で、それまでの常識をまるごとひっくり返すような矯正方針を掲げることの苦悩たるや、計り知れない。 我々が望んでいるのは犯罪者が刑務所から甦らない世界なのか?抵抗されないように権威を振りかざし、萎縮して生きさせることが目的なのか?そして犯罪者云々の以前に、人どうしで心からの対話をすること自体の難しさをひしひしと感じる。 一方で、「これを読んだだけで何もかも分かった気になるなよ」というメッセージを毛利さん自身が発信しているようにも思う。心理職の目線だけでなく、多角的な視野をもって、もっと考えなければならない。






 いっちー@icchii3172025年7月3日図書館予約済み先週末に、「プリズンサークル」というドキュメンタリー映画を観る機会があり、そこに出てきた方の本。監督のトークを聞く中でこの本を知った。壮絶な出来事がたくさんあり今は現場を離れて大学教授をされているそう。 それにしても回復共同体を設けている刑務所が日本に一つしかないのに、その現場を支える貴重な人がその刑務所の歪な厳しさの中で離れざるを得ないのってほんとに悲しい。
いっちー@icchii3172025年7月3日図書館予約済み先週末に、「プリズンサークル」というドキュメンタリー映画を観る機会があり、そこに出てきた方の本。監督のトークを聞く中でこの本を知った。壮絶な出来事がたくさんあり今は現場を離れて大学教授をされているそう。 それにしても回復共同体を設けている刑務所が日本に一つしかないのに、その現場を支える貴重な人がその刑務所の歪な厳しさの中で離れざるを得ないのってほんとに悲しい。- 仲嶺真@nihsenimakan2025年4月1日読み始めた本書は、日本の刑務所で初めてTC[回復共同体]の手法を取り入れた実践の報告を通じて、それをとりまく人や組織の動きをたどりながら、話して手放していくことが何を生むのか、そして誰がそれをしていく必要があるのか、人が変化・成長できる場とはどのようなものなのかについて考えていくことを狙いとしている。pp.17-18

 okabe@m_okabe2025年3月31日読み終わった行政の中で専門職として働くこと、新たな取り組みを始めることの難しさは痛いほどよく分かる。著者と似た境遇の中で、自分は専門性を発揮することに限界を感じかけていたが、本書を読んで勇気付けられた。
okabe@m_okabe2025年3月31日読み終わった行政の中で専門職として働くこと、新たな取り組みを始めることの難しさは痛いほどよく分かる。著者と似た境遇の中で、自分は専門性を発揮することに限界を感じかけていたが、本書を読んで勇気付けられた。









 ゆう@suisuiu2024年12月19日読みたいプリズンサークルの舞台。 《「あなたについて教えてください」と聞かれても絶対最後まで話さないような、そんな記憶や体験について語ってもらう場をつくることが、私の仕事だった——》 対等性と自由が尊重された集団のなかで対話を行い、個々人が抱える問題や症状からの回復を目指す「回復共同体(TC)」。映画『プリズン・サークル』の舞台となった島根県の官民協働刑務所で、日本初となるTCの立ち上げに携わった心理士が、その実践を初めて綴る。
ゆう@suisuiu2024年12月19日読みたいプリズンサークルの舞台。 《「あなたについて教えてください」と聞かれても絶対最後まで話さないような、そんな記憶や体験について語ってもらう場をつくることが、私の仕事だった——》 対等性と自由が尊重された集団のなかで対話を行い、個々人が抱える問題や症状からの回復を目指す「回復共同体(TC)」。映画『プリズン・サークル』の舞台となった島根県の官民協働刑務所で、日本初となるTCの立ち上げに携わった心理士が、その実践を初めて綴る。