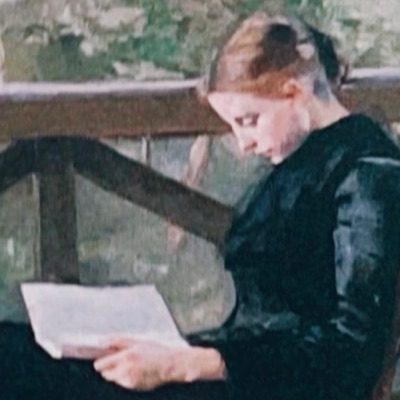天使も踏むを畏れるところ 下

36件の記録
 いるかれもん@reads-dolphin2025年10月18日読み終わったまた読みたい建築の奥深さを教えてもらった。おそらく象徴天皇にらふさわしい宮殿というお題は、雲をつかむような難しい問題であったと思うが、建築という側面からたしかに応えようとする主人公たちの姿が、清らかで淡々とした文章で描かれる。最後、村井が設計者を辞退してしまったのが、本当に残念に思うほど、リアリティを感じる物語だった。宮内庁ホームページに掲載されている、新宮殿の煌びやかなシャデリアの写真をみて、なんとも複雑な気持ちになる。 ため息が出てしまうほど、読んでいて納得感というか、居心地の良さみたいなものを感じる小説だった。 もう少し感想を別のところで書きたいと思う
いるかれもん@reads-dolphin2025年10月18日読み終わったまた読みたい建築の奥深さを教えてもらった。おそらく象徴天皇にらふさわしい宮殿というお題は、雲をつかむような難しい問題であったと思うが、建築という側面からたしかに応えようとする主人公たちの姿が、清らかで淡々とした文章で描かれる。最後、村井が設計者を辞退してしまったのが、本当に残念に思うほど、リアリティを感じる物語だった。宮内庁ホームページに掲載されている、新宮殿の煌びやかなシャデリアの写真をみて、なんとも複雑な気持ちになる。 ため息が出てしまうほど、読んでいて納得感というか、居心地の良さみたいなものを感じる小説だった。 もう少し感想を別のところで書きたいと思う



 いるかれもん@reads-dolphin2025年10月16日読んでる建築というと、柱とか壁とか床とかを作るものだと思っていた。この本を読んでわかったのは、大切なのはその壁とか床とかによって生まれる空間をデザインするのが建築家なのだと学んだ。それは、すなわち、その中で営まれる生活を創造し、そこに流れる時間のあり方を決める土台を作ることになるのだと思う。生活(というか、そこにいる人の体験や経験の土台)をデザインするという見方で見ると建築の面白みがわかりそう。
いるかれもん@reads-dolphin2025年10月16日読んでる建築というと、柱とか壁とか床とかを作るものだと思っていた。この本を読んでわかったのは、大切なのはその壁とか床とかによって生まれる空間をデザインするのが建築家なのだと学んだ。それは、すなわち、その中で営まれる生活を創造し、そこに流れる時間のあり方を決める土台を作ることになるのだと思う。生活(というか、そこにいる人の体験や経験の土台)をデザインするという見方で見ると建築の面白みがわかりそう。



 いるかれもん@reads-dolphin2025年10月15日読んでる220ページ、建設省から宮内庁に出航した建設技官、杉浦のモノローグ 「予想外の連続であった自分の人生は、望外に恵まれたものになりつつあるとさえ感じている。若いころには一度も抱いたことのない感慨だった。皇居新宮殿の仕事をアナクロニズムだと嘲笑う者がいたとしても、それを恥じる気持ちはもはや自分にはない。アナクロニズムはたんなることばだ。天皇を信奉するもしないも、ことばの問題ではないか。桂離宮の成立事情をたとえ社会科学的に分析したとしても、いまも厳然とある建築の価値を無にすることはできない。建築は物として残り、記憶や意味と切り離されてもなお、あらたな評価を得る可能性がある。ことばはうつろいやすい。敗戦と当時にあらゆることばがひっくり返り、価値が転倒するのを体験するなかで、自分が迷わず取り組んだのは復興のための建築だった。間もなくあれから二十年になるところまで来て、物にくらべてことばははかないと感じる。それは動かしがたい確信に変わりつつあった。」 戦後の価値観の変容と、建築の普遍的な価値を対比させた文章。思わずため息が出てしまった。
いるかれもん@reads-dolphin2025年10月15日読んでる220ページ、建設省から宮内庁に出航した建設技官、杉浦のモノローグ 「予想外の連続であった自分の人生は、望外に恵まれたものになりつつあるとさえ感じている。若いころには一度も抱いたことのない感慨だった。皇居新宮殿の仕事をアナクロニズムだと嘲笑う者がいたとしても、それを恥じる気持ちはもはや自分にはない。アナクロニズムはたんなることばだ。天皇を信奉するもしないも、ことばの問題ではないか。桂離宮の成立事情をたとえ社会科学的に分析したとしても、いまも厳然とある建築の価値を無にすることはできない。建築は物として残り、記憶や意味と切り離されてもなお、あらたな評価を得る可能性がある。ことばはうつろいやすい。敗戦と当時にあらゆることばがひっくり返り、価値が転倒するのを体験するなかで、自分が迷わず取り組んだのは復興のための建築だった。間もなくあれから二十年になるところまで来て、物にくらべてことばははかないと感じる。それは動かしがたい確信に変わりつつあった。」 戦後の価値観の変容と、建築の普遍的な価値を対比させた文章。思わずため息が出てしまった。



 読書日和@miou-books2025年10月13日読み終わった壮大な物語の下巻を一気に読み終えました。 読み終えた満足感にしばし浸る。 これ、フィクションですよね、と何度も確かめつつ。それくらい迫真性のある表現。牧野ー!エリート官僚ってこんな感じなの?とイライラしたり (まんまと踊らされています)村井さんから昭和の男の気概を感じたり。 ネタバレしたくないので内容には触れませんが、戦後から約20年ここまで復興した時の日本人のバイタリティ、頑張りに頭が下がります。そして戦後は「国民統合の象徴」となった天量家と仕える方々。昭和って激動の時代だったんたな。 読んでいる最中、10/9の日経新聞に香淳皇后実録公開の記事が。なんとタイムリーな。天使も~の中では意地悪で気難しく描かれているけれど、14歳でお妃内定、23歳で皇后に、国母から象徴天星へと、とても想像のつかない日々を歩まれたと思うと、本の感想も少し変わってくる。 松家さんのデビュー作、火山のふもとで、は村井製作所が舞台?これも読まねば。
読書日和@miou-books2025年10月13日読み終わった壮大な物語の下巻を一気に読み終えました。 読み終えた満足感にしばし浸る。 これ、フィクションですよね、と何度も確かめつつ。それくらい迫真性のある表現。牧野ー!エリート官僚ってこんな感じなの?とイライラしたり (まんまと踊らされています)村井さんから昭和の男の気概を感じたり。 ネタバレしたくないので内容には触れませんが、戦後から約20年ここまで復興した時の日本人のバイタリティ、頑張りに頭が下がります。そして戦後は「国民統合の象徴」となった天量家と仕える方々。昭和って激動の時代だったんたな。 読んでいる最中、10/9の日経新聞に香淳皇后実録公開の記事が。なんとタイムリーな。天使も~の中では意地悪で気難しく描かれているけれど、14歳でお妃内定、23歳で皇后に、国母から象徴天星へと、とても想像のつかない日々を歩まれたと思うと、本の感想も少し変わってくる。 松家さんのデビュー作、火山のふもとで、は村井製作所が舞台?これも読まねば。
 n@blue_272025年8月10日読んでる読書メモ村井と衣子の言い合いの場面。 衣子の考え方がすごく素敵だなと思った。ただ、それに対する村井の反論を読むと、場合によってはそれは正しい選択ではなく、他人任せ、他責思考になりかねないのだなと感じる。 それにしても牧野の行動にはヤキモキしてしまう…
n@blue_272025年8月10日読んでる読書メモ村井と衣子の言い合いの場面。 衣子の考え方がすごく素敵だなと思った。ただ、それに対する村井の反論を読むと、場合によってはそれは正しい選択ではなく、他人任せ、他責思考になりかねないのだなと感じる。 それにしても牧野の行動にはヤキモキしてしまう…

 n@blue_272025年7月6日読んでる読書メモ「欧米の高速道路は、都市と都市をつなぐのが主たる目的なんだ。だから東京オリンピックにやってくる欧米の人間は、未来都市の姿を東京ではじめて目にすることになる。」 「これこそ豊かな戦後というものじゃないか。いや戦後なんてものじゃない。豊かな未来だよ。たった十四年前、東京は一面の焼け野原だったんだ。だれがこんな東京になると予想できた?たったひとりもいなかったと思うよ。たったひとりもね」
n@blue_272025年7月6日読んでる読書メモ「欧米の高速道路は、都市と都市をつなぐのが主たる目的なんだ。だから東京オリンピックにやってくる欧米の人間は、未来都市の姿を東京ではじめて目にすることになる。」 「これこそ豊かな戦後というものじゃないか。いや戦後なんてものじゃない。豊かな未来だよ。たった十四年前、東京は一面の焼け野原だったんだ。だれがこんな東京になると予想できた?たったひとりもいなかったと思うよ。たったひとりもね」