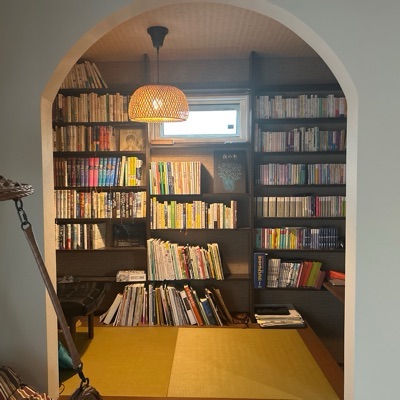
ひなたの本好き
@054-10ps
日本のひなたこと宮崎県でちびちび本を読んでます。焼酎を飲むように本を読み、本を読むように焼酎を飲む。
- 2026年2月23日
 幽民奇聞恒川光太郎読み終わった@ 恒久読了。読む前に想像していたものに近い世界観だったのでそこへの満足感はありつつ、何となく物足りなさも感じつつ。異能を持ち一般社会とは異なる理の中で生きる集団の盛衰が描かれるが、それがどうしても恩田陸の『光の帝国』と重なってしまう。そのせいで『光の帝国』の物語性の強さと比べてしまい物足りなさを感じるのかもしれない。意表を突かれることが少なかったし、登場人物たちにもうまく感情移入しきれなかった。面白かったとは思うのだが。
幽民奇聞恒川光太郎読み終わった@ 恒久読了。読む前に想像していたものに近い世界観だったのでそこへの満足感はありつつ、何となく物足りなさも感じつつ。異能を持ち一般社会とは異なる理の中で生きる集団の盛衰が描かれるが、それがどうしても恩田陸の『光の帝国』と重なってしまう。そのせいで『光の帝国』の物語性の強さと比べてしまい物足りなさを感じるのかもしれない。意表を突かれることが少なかったし、登場人物たちにもうまく感情移入しきれなかった。面白かったとは思うのだが。 - 2026年2月18日
 幽民奇聞恒川光太郎買った@ 津江書店店頭に並んでいたのをジャケ買いに近い形で衝動買い。ここ最近spectatorで特集されていた漂白民の雰囲気があるなあと思いつつ。サンカとかというよりは妖怪的なテイストが強そう。民俗学的なものへの関心が高まっているなかでこういう本への当たりを引き続けていて、やっぱり本は本を呼ぶなあと実感。
幽民奇聞恒川光太郎買った@ 津江書店店頭に並んでいたのをジャケ買いに近い形で衝動買い。ここ最近spectatorで特集されていた漂白民の雰囲気があるなあと思いつつ。サンカとかというよりは妖怪的なテイストが強そう。民俗学的なものへの関心が高まっているなかでこういう本への当たりを引き続けていて、やっぱり本は本を呼ぶなあと実感。 - 2026年2月18日
- 2026年2月16日
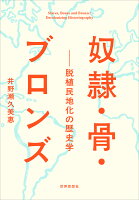 奴隷・骨・ブロンズ井野瀬久美惠気になる
奴隷・骨・ブロンズ井野瀬久美惠気になる - 2026年2月16日
 天空の都の物語アンソニー・ドーア,藤井光気になる
天空の都の物語アンソニー・ドーア,藤井光気になる - 2026年2月16日
 季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト読み終わった長かった日記の旅も気付けば読了。遠出する時の車の中とか職場での昼休みとか色んな場所・時間で読んだなあ、とこの本を読んだこと自体が日記みたいになっていることに気付く。 途中の日記に関するインタビューとか対談は何となく観念的で正直そこまで自分には響かなかったのだけど、最後の読者投稿はさすがこの本の読者達なだけあって読み応えがあった。特に弘前での旅を冊子にした話が好き。 今回はピンと来なかったインタビュー記事もいつか腑に落ちる時が来るのだろう。
季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマト読み終わった長かった日記の旅も気付けば読了。遠出する時の車の中とか職場での昼休みとか色んな場所・時間で読んだなあ、とこの本を読んだこと自体が日記みたいになっていることに気付く。 途中の日記に関するインタビューとか対談は何となく観念的で正直そこまで自分には響かなかったのだけど、最後の読者投稿はさすがこの本の読者達なだけあって読み応えがあった。特に弘前での旅を冊子にした話が好き。 今回はピンと来なかったインタビュー記事もいつか腑に落ちる時が来るのだろう。 - 2026年2月15日
 スペクテイター〈55号〉にっぽんの漂泊民エディトリアルデパートメント読み終わった@ 恒久インタビュー記事の内容が趣旨から脱線していったりするところがなんともこの雑誌らしいなあと思いつつ読了。変に手を加えたりせずにそのまま載せているということなのだろう。 漂白民特集となっていたが、サンカに関する比重が重かったように思う。 かくいう自分もサンカに強い興味があったから飛びついたわけだが。 本誌の中でも問われていたが、なぜサンカにそこまで心惹かれるのだろう。 読み終えて感じるのは、サンカの自由さとか不可思議さというより、この日本で自分たちとは異なる理の中で暮らしている人たちがいる・いたというそのオルタナティブ性に自分は惹かれたのだろうということ。 サンカのことをよく知りたい気持ちもあるのだが、そういう人たちが存在したという事実だけで自分は満足なのかもしれない。 サンカの情報を得れば得るほど既知のものとして新鮮味を失ってしまいそうで、あえて知らないままの方が良いのかもとか思ったり。
スペクテイター〈55号〉にっぽんの漂泊民エディトリアルデパートメント読み終わった@ 恒久インタビュー記事の内容が趣旨から脱線していったりするところがなんともこの雑誌らしいなあと思いつつ読了。変に手を加えたりせずにそのまま載せているということなのだろう。 漂白民特集となっていたが、サンカに関する比重が重かったように思う。 かくいう自分もサンカに強い興味があったから飛びついたわけだが。 本誌の中でも問われていたが、なぜサンカにそこまで心惹かれるのだろう。 読み終えて感じるのは、サンカの自由さとか不可思議さというより、この日本で自分たちとは異なる理の中で暮らしている人たちがいる・いたというそのオルタナティブ性に自分は惹かれたのだろうということ。 サンカのことをよく知りたい気持ちもあるのだが、そういう人たちが存在したという事実だけで自分は満足なのかもしれない。 サンカの情報を得れば得るほど既知のものとして新鮮味を失ってしまいそうで、あえて知らないままの方が良いのかもとか思ったり。 - 2026年2月7日
 アフリカの日々イサク・ディネセン,横山貞子気になる
アフリカの日々イサク・ディネセン,横山貞子気になる - 2026年2月3日
 1984ジョージ・オーウェル,田内志文気になる
1984ジョージ・オーウェル,田内志文気になる - 2026年1月30日
 オクトローグ酉島伝法気になる
オクトローグ酉島伝法気になる - 2026年1月30日
 短編宇宙加納朋子,宮澤伊織,寺地はるな,川端裕人,深緑野分,酉島伝法,雪舟えま気になる
短編宇宙加納朋子,宮澤伊織,寺地はるな,川端裕人,深緑野分,酉島伝法,雪舟えま気になる - 2026年1月30日
 スペクテイター〈55号〉にっぽんの漂泊民エディトリアルデパートメント買った@ KIMAMA BOOKS(キママブックス)先日『オルタナティブ民俗学』を読んでからというもの、民俗学熱がムンムンに高まっていた。 そんなタイミングでのこの内容。買わないという選択肢はない。 本を読んでいるとこんな風に本が本を呼ぶことがあるから面白い。 それにしても、地元でspectatorの最新刊をオンタイムで入手できることのありがたさよ。 キママブックスさんなら、と思って仕事終わりに足を運んでみたが、やっぱりさすが。 さあ、今夜から読むぞー!
スペクテイター〈55号〉にっぽんの漂泊民エディトリアルデパートメント買った@ KIMAMA BOOKS(キママブックス)先日『オルタナティブ民俗学』を読んでからというもの、民俗学熱がムンムンに高まっていた。 そんなタイミングでのこの内容。買わないという選択肢はない。 本を読んでいるとこんな風に本が本を呼ぶことがあるから面白い。 それにしても、地元でspectatorの最新刊をオンタイムで入手できることのありがたさよ。 キママブックスさんなら、と思って仕事終わりに足を運んでみたが、やっぱりさすが。 さあ、今夜から読むぞー! - 2026年1月29日
- 2026年1月21日
 若山牧水全歌集伊藤一彦買った@ 津江書店酒豪かつ地元が誇る歌人ということで、いつかは牧水の歌に触れてみたいと思っていた。 津江書店さんは、こういう地元にフォーカスを当てた本をしっかり置いてくれるからありがたい。
若山牧水全歌集伊藤一彦買った@ 津江書店酒豪かつ地元が誇る歌人ということで、いつかは牧水の歌に触れてみたいと思っていた。 津江書店さんは、こういう地元にフォーカスを当てた本をしっかり置いてくれるからありがたい。 - 2026年1月21日
 季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマトp.209まで。 個々の日記のページが終わり、各日記の筆者紹介のページへ。 個々の日記を読んでいるときは先に筆者紹介してくれたらなあと思っていたが、いざ筆者紹介を読んでみると答え合わせみたいな感じになって、あの人があの日記を書いたのかと読み返す楽しみがあった。 日記パートが長く感じるが、いざ終わってみると寂しさがある。
季刊日記 創刊号こだま,ネルノダイスキ,ドミニク・チェン,pha,伊藤亜和,初見健一,前田隆弘,北尾修一,古賀及子,こうの史代,品田遊,図Yカニナ,堀合俊博,大森時生,安達茉莉子,小沼理,尹雄大,山本浩貴,東直子,松浦弥太郎,林健太郎,柚木麻子,柿内正午,桜林直子,植本一子,武田砂鉄,浮,ピエール瀧,牧野伊三夫,猪瀬浩平,福尾匠,竹中万季,荘子it,葉山莉子,蓮沼執太,藤原辰史,蟹の親子,野村由芽,金川晋吾,鳥トマトp.209まで。 個々の日記のページが終わり、各日記の筆者紹介のページへ。 個々の日記を読んでいるときは先に筆者紹介してくれたらなあと思っていたが、いざ筆者紹介を読んでみると答え合わせみたいな感じになって、あの人があの日記を書いたのかと読み返す楽しみがあった。 日記パートが長く感じるが、いざ終わってみると寂しさがある。 - 2026年1月21日
 日本残酷物語 1(95)宮本常一,山代巴,山本周五郎,揖西高速気になる
日本残酷物語 1(95)宮本常一,山代巴,山本周五郎,揖西高速気になる - 2026年1月21日
 チベットを馬で行く渡辺一枝気になる
チベットを馬で行く渡辺一枝気になる - 2026年1月21日
 アフリカの歴史川田順造気になる
アフリカの歴史川田順造気になる - 2026年1月21日
 文庫版 陰摩羅鬼の瑕京極夏彦読み始めた@ 恒久久しぶりに小説が読みたいと思い、積ん読になっていたこの1冊に手を伸ばしてみた。 今朝はp.63まで。 やっぱり京極さんの文章は読み応えがある。 カロリーが高いボリュームのはずなのにすいすい読んでしまう。 これがあと数百ページ以上続く幸せ。
文庫版 陰摩羅鬼の瑕京極夏彦読み始めた@ 恒久久しぶりに小説が読みたいと思い、積ん読になっていたこの1冊に手を伸ばしてみた。 今朝はp.63まで。 やっぱり京極さんの文章は読み応えがある。 カロリーが高いボリュームのはずなのにすいすい読んでしまう。 これがあと数百ページ以上続く幸せ。 - 2026年1月12日
 オルタナティブ民俗学島村恭則,畑中章宏読み終わった@ 恒久読み終わって改めて、民俗学とはどんな学問か把握するのに良い本だったなと実感。 主要人物の説明や、各章ごとのテーマのおかげで民俗学の輪郭を掴めたような気がしている。 民俗学とはアカデミアに独占されるものでなく、在野の人間たち、すなわち「私たち」の日常から掬い上げていくものということなのだろう。 もしかしたら自分でも民俗学できるのかもなあなんて思ったり。
オルタナティブ民俗学島村恭則,畑中章宏読み終わった@ 恒久読み終わって改めて、民俗学とはどんな学問か把握するのに良い本だったなと実感。 主要人物の説明や、各章ごとのテーマのおかげで民俗学の輪郭を掴めたような気がしている。 民俗学とはアカデミアに独占されるものでなく、在野の人間たち、すなわち「私たち」の日常から掬い上げていくものということなのだろう。 もしかしたら自分でも民俗学できるのかもなあなんて思ったり。
読み込み中...
