

ゆうき
@effel
知識を得たくて好奇心から本を手に取ることが多いです。
- 2025年11月7日
- 2025年11月7日
 破天荒フェニックス田中修治気になる
破天荒フェニックス田中修治気になる - 2025年11月7日
 まんがでわかる 土と肥料村上敏文気になる
まんがでわかる 土と肥料村上敏文気になる - 2025年11月5日
- 2025年10月2日
 読み終わった農業毎日食べている野菜の話なのに、全然知らないことだらけということに驚き、 さらに筆者が執筆当時高校生で、中3で事業を立ち上げたことにまた驚いた。 ■タネの種類と法律とビジネス (F1種、固定種、遺伝子組み換え) 企業が種を開発しその権利が守られる時代に起きるタネの未来 ■伝統野菜について 世の中には流通していない面白い野菜がたくさんある でも高齢化やタネの資本化に伴い、絶滅の危惧にある(なんなら既に絶滅している野菜も多い) ■筆者小林さんの事業について 中3で起業。親に企画書を提出は驚き笑 その時からビジョンが明確なことにさらに驚き。 "流通"に主点を置いたビジネス。 タネに出会い事業立ち上げに至るまでの経緯がわかりやすく、筆者の想いよく伝わってきた。 好奇心を追求し、その過程で人が交わり、形作られていくというプロセスも素敵だった!
読み終わった農業毎日食べている野菜の話なのに、全然知らないことだらけということに驚き、 さらに筆者が執筆当時高校生で、中3で事業を立ち上げたことにまた驚いた。 ■タネの種類と法律とビジネス (F1種、固定種、遺伝子組み換え) 企業が種を開発しその権利が守られる時代に起きるタネの未来 ■伝統野菜について 世の中には流通していない面白い野菜がたくさんある でも高齢化やタネの資本化に伴い、絶滅の危惧にある(なんなら既に絶滅している野菜も多い) ■筆者小林さんの事業について 中3で起業。親に企画書を提出は驚き笑 その時からビジョンが明確なことにさらに驚き。 "流通"に主点を置いたビジネス。 タネに出会い事業立ち上げに至るまでの経緯がわかりやすく、筆者の想いよく伝わってきた。 好奇心を追求し、その過程で人が交わり、形作られていくというプロセスも素敵だった! - 2025年9月23日
 獣の奏者 外伝 刹那上橋菜穂子読み終わった
獣の奏者 外伝 刹那上橋菜穂子読み終わった - 2025年9月23日
- 2025年9月23日
 獣の奏者 3探求編上橋菜穂子読み終わった
獣の奏者 3探求編上橋菜穂子読み終わった - 2025年9月14日
![イシューからはじめよ[改訂版]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3563/9784862763563_1_4.jpg?_ex=200x200) イシューからはじめよ[改訂版]安宅和人読み終わったかなり流し読みしたけれど、わかりやすかった。 物事構造化し、しっかりと解くべきイシューをまずは見極めて、全体像を整理してから、解いていく。 納得感ある内容だった。 ◉悩んでいる暇があるなら考える ◉ガムシャラに解くのではなく、イシューを見極めてから解く ◉仮説を持って全体像を、整理してから解く
イシューからはじめよ[改訂版]安宅和人読み終わったかなり流し読みしたけれど、わかりやすかった。 物事構造化し、しっかりと解くべきイシューをまずは見極めて、全体像を整理してから、解いていく。 納得感ある内容だった。 ◉悩んでいる暇があるなら考える ◉ガムシャラに解くのではなく、イシューを見極めてから解く ◉仮説を持って全体像を、整理してから解く - 2025年8月20日
- 2025年8月20日
- 2025年8月6日
- 2025年7月8日
 山登りはじめました2 いくぞ!屋久島編鈴木ともこ読み終わった北アルプスや屋久島登山をマンガで解説。 登山情報がわかりやすく、山登りたい欲が刺激される一冊。 夏休みの山登り計画の参考になるし、モチベーションも上がる!⛰️
山登りはじめました2 いくぞ!屋久島編鈴木ともこ読み終わった北アルプスや屋久島登山をマンガで解説。 登山情報がわかりやすく、山登りたい欲が刺激される一冊。 夏休みの山登り計画の参考になるし、モチベーションも上がる!⛰️ - 2025年6月30日
 ダーチャですごす緑の週末豊田菜穂子読み終わった農業読書メモ ○ダーチャは別荘のこと。しかしお金持ちのものではなく、モスクワ市民の75%が持っているロシアの国民的文化。インフラの整っていないロシア郊外で、お金をかけず自ら何でも作ってバカンスを過ごすというもの。 ○バーニャというサウナや、きのこ狩り、BBQなどをして過ごす。子どもにとっては学びの場だけど、インフラもないので大人にとってはちょっと大変な一面もある。 →お金はかけず、知恵を共有し、自然に触れ合いながら過ごすというマインドが良いなと思った。都心にいるとすぐに消費者側に立たされて、何かとお金がかかるけど、バーチャマインドでお金をかけず自然の豊かさを享受できる仕組みが欲しい🌳
ダーチャですごす緑の週末豊田菜穂子読み終わった農業読書メモ ○ダーチャは別荘のこと。しかしお金持ちのものではなく、モスクワ市民の75%が持っているロシアの国民的文化。インフラの整っていないロシア郊外で、お金をかけず自ら何でも作ってバカンスを過ごすというもの。 ○バーニャというサウナや、きのこ狩り、BBQなどをして過ごす。子どもにとっては学びの場だけど、インフラもないので大人にとってはちょっと大変な一面もある。 →お金はかけず、知恵を共有し、自然に触れ合いながら過ごすというマインドが良いなと思った。都心にいるとすぐに消費者側に立たされて、何かとお金がかかるけど、バーチャマインドでお金をかけず自然の豊かさを享受できる仕組みが欲しい🌳 - 2025年5月30日
 超バカの壁養老孟司読み終わった○バカの壁など過去の作品に寄せられた質問に答えるために作られた一冊。なので、トピックス毎に持論が展開されてるが、後ろにある主張は『バカの壁』と同じ。 ○とにかく毒舌。これまで読んだ本は記載内容を正として読むことが多く、なるほど〜と思いながら読めたけど、毒舌すぎて、いやちゃうん違う?とか考えるきっかけになった。本の中の言葉を使うとこれまでは"共通了解"得られる情報に触れてなるほど〜となっていただけで、それもまた"バカの壁"だったのかもと思った。常に物事A面、B面、C面など、異なる角度から見ていきたい。 ○ こんないろんなことに自論をもち、赤裸々に公開。常に考えていた人なんだと思った。 ○頭に残ったフレーズ 世界は対自然と対人間の両面があるのに、都市では対人間しかない。
超バカの壁養老孟司読み終わった○バカの壁など過去の作品に寄せられた質問に答えるために作られた一冊。なので、トピックス毎に持論が展開されてるが、後ろにある主張は『バカの壁』と同じ。 ○とにかく毒舌。これまで読んだ本は記載内容を正として読むことが多く、なるほど〜と思いながら読めたけど、毒舌すぎて、いやちゃうん違う?とか考えるきっかけになった。本の中の言葉を使うとこれまでは"共通了解"得られる情報に触れてなるほど〜となっていただけで、それもまた"バカの壁"だったのかもと思った。常に物事A面、B面、C面など、異なる角度から見ていきたい。 ○ こんないろんなことに自論をもち、赤裸々に公開。常に考えていた人なんだと思った。 ○頭に残ったフレーズ 世界は対自然と対人間の両面があるのに、都市では対人間しかない。 - 2025年5月22日
 バカの壁養老孟司読み終わった〈読書メモ〉 🧱「バカの壁」 • 「現実を完全に知ることはできない」——それなのに、知ってる“つもり”になった時、そこに“バカの壁”ができる。 • 同じ場にいても、3人いれば3通りの感じ方がある。絶対的な「正解」や「共通の理解」は本当は存在しない。 • 「自己」すら普遍だと思い込んでしまっている。そこにも壁がある。 ☝️ 一元論がバカの壁を作る • 一神教的な「唯一の正解」にすがりたくなるのは人間の楽をしたい本能。でもそれが思考停止を生み、壁をつくり、人の話が聞けなくなる、話が通じなくなる。 •でもVUCA現代では、ある程度の一元論?も必要なんじゃないかなと思った。(不確実要素が多いすぎるので何かをピン留めして考えないと考えが進まない) 🧠 脳と思考について • 脳って意外とシンプル。思考も物理的なものなんだと実感した。 • やる気は前頭葉で出力がコントロールされることで形成。 • 「頭が良い」とは社会適合性が高いものという考えに納得。昇格試験はいかにマニュアル人間で適合性高いかが評価される。そこには個性なんてない。 📚 読書体験として • 個人の見解が強めの本、こういうの久しぶりに読んだ。 • 約20年前の本だから前提が今と少し違うからか、読み慣れてないからか、すんなりとは読めなかった。 • 養老孟司さんの本はなんやかんやちゃんと読むのは初めてなのでもう少し読んでみたい。
バカの壁養老孟司読み終わった〈読書メモ〉 🧱「バカの壁」 • 「現実を完全に知ることはできない」——それなのに、知ってる“つもり”になった時、そこに“バカの壁”ができる。 • 同じ場にいても、3人いれば3通りの感じ方がある。絶対的な「正解」や「共通の理解」は本当は存在しない。 • 「自己」すら普遍だと思い込んでしまっている。そこにも壁がある。 ☝️ 一元論がバカの壁を作る • 一神教的な「唯一の正解」にすがりたくなるのは人間の楽をしたい本能。でもそれが思考停止を生み、壁をつくり、人の話が聞けなくなる、話が通じなくなる。 •でもVUCA現代では、ある程度の一元論?も必要なんじゃないかなと思った。(不確実要素が多いすぎるので何かをピン留めして考えないと考えが進まない) 🧠 脳と思考について • 脳って意外とシンプル。思考も物理的なものなんだと実感した。 • やる気は前頭葉で出力がコントロールされることで形成。 • 「頭が良い」とは社会適合性が高いものという考えに納得。昇格試験はいかにマニュアル人間で適合性高いかが評価される。そこには個性なんてない。 📚 読書体験として • 個人の見解が強めの本、こういうの久しぶりに読んだ。 • 約20年前の本だから前提が今と少し違うからか、読み慣れてないからか、すんなりとは読めなかった。 • 養老孟司さんの本はなんやかんやちゃんと読むのは初めてなのでもう少し読んでみたい。 - 2025年5月8日
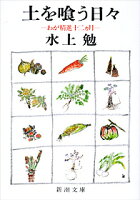 土を喰う日々水上勉読み終わった農業《読書メモ》 ○料理=タイパという慌ただしい考えが主流になってるけど、生活のための手段としての料理とかの次元ではない話 ○刺激に刺激を加える足し算の幸せもよいけど、引き算して今ある極限から生み出す幸せも良いなと思えた(この本の筆者の主張とかではなく単に思った) ○精進料理って、"日々精進する料理" ○和食を作るのが苦手な理由がわかった気がする、もっとじっくり食材を楽しむ心持ちたい ○仏教の素敵な考え方 どんな食材も丁寧に扱う=どんなもの、人間の価値も等しい=根っこを捨てる行為は人によって接し方を変えるの同じ行為
土を喰う日々水上勉読み終わった農業《読書メモ》 ○料理=タイパという慌ただしい考えが主流になってるけど、生活のための手段としての料理とかの次元ではない話 ○刺激に刺激を加える足し算の幸せもよいけど、引き算して今ある極限から生み出す幸せも良いなと思えた(この本の筆者の主張とかではなく単に思った) ○精進料理って、"日々精進する料理" ○和食を作るのが苦手な理由がわかった気がする、もっとじっくり食材を楽しむ心持ちたい ○仏教の素敵な考え方 どんな食材も丁寧に扱う=どんなもの、人間の価値も等しい=根っこを捨てる行為は人によって接し方を変えるの同じ行為 - 2025年4月29日
 「ついやってしまう」体験のつくりかた玉樹真一郎読み終わったマリオやドラクエのゲームをなぜ、ついやってしまうのか? ゲームの企画開発時に意図された仕組みを解説。本自体にもつい読みたくなる仕組みが施されている。 ①直感のデザイン(こうなるのかな?やっぱりそうだった!→😄) ②驚きのデザイン(思い込ませる→うっそー!意外!😳) ③物語のデザイン(翻弄→成長→意志) ③はまだ解釈しきれていない。日常自分がついやってしまっていることのメカニズムや、めんどくさいと思うことをいかについやってしまう行動に繋げられるかアンテナを立てたい。
「ついやってしまう」体験のつくりかた玉樹真一郎読み終わったマリオやドラクエのゲームをなぜ、ついやってしまうのか? ゲームの企画開発時に意図された仕組みを解説。本自体にもつい読みたくなる仕組みが施されている。 ①直感のデザイン(こうなるのかな?やっぱりそうだった!→😄) ②驚きのデザイン(思い込ませる→うっそー!意外!😳) ③物語のデザイン(翻弄→成長→意志) ③はまだ解釈しきれていない。日常自分がついやってしまっていることのメカニズムや、めんどくさいと思うことをいかについやってしまう行動に繋げられるかアンテナを立てたい。 - 2025年4月17日
- 2025年3月26日
読み込み中...







