みなも
@minamo_books
- 2026年2月17日
 とびこえる教室星野俊樹読んでる
とびこえる教室星野俊樹読んでる - 2026年1月6日
 マダム・キュリーと朝食を (集英社文庫)小林エリカ読み終わった
マダム・キュリーと朝食を (集英社文庫)小林エリカ読み終わった - 2026年1月4日
 虹色と幸運柴崎友香読み終わった劇的なことがなくても、確実に季節は巡って、いつのまにか何かが変わって、それでも今以外のことは何もわからないまま、生きていくんだな。 わかりあえないからこそ話せることがあるって、ずっと忘れずにいたい。
虹色と幸運柴崎友香読み終わった劇的なことがなくても、確実に季節は巡って、いつのまにか何かが変わって、それでも今以外のことは何もわからないまま、生きていくんだな。 わかりあえないからこそ話せることがあるって、ずっと忘れずにいたい。 - 2026年1月2日
- 2026年1月2日
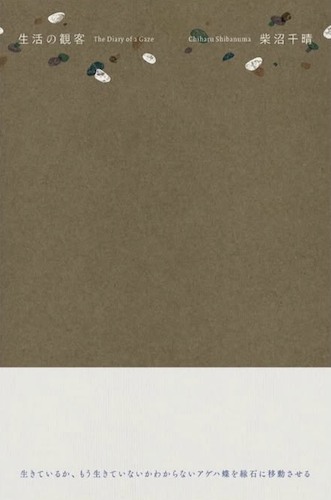 生活の観客柴沼千晴読んでる去年の年末年始は『もっとも小さい日の出』をずっと読んでいて、今年も柴沼千晴さんの日記本がともにあることがうれしい。 Podcast『長い話』も今朝半分ほど聴いて、もう半分はまだとっておいてる。
生活の観客柴沼千晴読んでる去年の年末年始は『もっとも小さい日の出』をずっと読んでいて、今年も柴沼千晴さんの日記本がともにあることがうれしい。 Podcast『長い話』も今朝半分ほど聴いて、もう半分はまだとっておいてる。 - 2025年12月9日
 レニーとマーゴで100歳マリアンヌ・クローニン,村松潔読んでる
レニーとマーゴで100歳マリアンヌ・クローニン,村松潔読んでる - 2025年11月22日
 あなたに犬がそばにいた夏佐内正史,岡野大嗣読み終わった夏が始まる頃に買ったのに、冬の始まりになってようやく。 短歌って、もっと気軽に読んでいいのかも。 写真も素敵だった。こんなふうに光を捉えられたら。 路線バスがゆっくり曲がる駅前にゆっくり動く影のときめき 側溝にひらいた花がはみだして祝福になる歩道の眺め 声がして水遊びだとわかる声 二時から二時の声がしている 夕焼けのボーナストラック。小焼けってそういうイメージ、って言ってみる
あなたに犬がそばにいた夏佐内正史,岡野大嗣読み終わった夏が始まる頃に買ったのに、冬の始まりになってようやく。 短歌って、もっと気軽に読んでいいのかも。 写真も素敵だった。こんなふうに光を捉えられたら。 路線バスがゆっくり曲がる駅前にゆっくり動く影のときめき 側溝にひらいた花がはみだして祝福になる歩道の眺め 声がして水遊びだとわかる声 二時から二時の声がしている 夕焼けのボーナストラック。小焼けってそういうイメージ、って言ってみる - 2025年11月15日
 つながり過ぎないでいい尹雄大読んでる
つながり過ぎないでいい尹雄大読んでる - 2025年11月8日
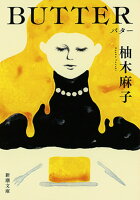 BUTTER柚木麻子まだ読んでる
BUTTER柚木麻子まだ読んでる - 2025年11月2日
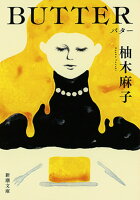 BUTTER柚木麻子読んでる
BUTTER柚木麻子読んでる - 2025年11月2日
- 2025年10月19日
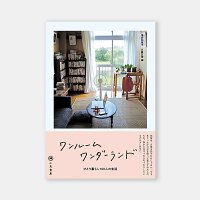 ワンルームワンダーランド ひとり暮らし100人の生活佐藤友理落合加依子,落合加依子、佐藤友理買った来年の目標は引っ越すことなので、部屋づくりの妄想のおともに。ひとり暮らしではないけど、もう少し一人ひとりの空間を持つのがいいんじゃないかと画策してる。
ワンルームワンダーランド ひとり暮らし100人の生活佐藤友理落合加依子,落合加依子、佐藤友理買った来年の目標は引っ越すことなので、部屋づくりの妄想のおともに。ひとり暮らしではないけど、もう少し一人ひとりの空間を持つのがいいんじゃないかと画策してる。 - 2025年10月19日
 それがやさしさじゃ困る植本一子,鳥羽和久読み始めた装丁もタイトルもよすぎる。一年間の日記も収録されてるなんて知らなかった! 読んでるこちらもハッとしたり内省させられたり、鳥羽さんの経験と気づきが詰まってる。
それがやさしさじゃ困る植本一子,鳥羽和久読み始めた装丁もタイトルもよすぎる。一年間の日記も収録されてるなんて知らなかった! 読んでるこちらもハッとしたり内省させられたり、鳥羽さんの経験と気づきが詰まってる。 - 2025年9月20日
 アイドルについて葛藤しながら考えてみた上岡磨奈,中村香住,香月孝史読み終わった
アイドルについて葛藤しながら考えてみた上岡磨奈,中村香住,香月孝史読み終わった - 2025年9月20日
 わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。 ゆとりっ娘たちのたわごとだけじゃない話ゆとたわ(かりん&ほのか),ゆとたわ(かりん&ほのか)読み終わった
わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。 ゆとりっ娘たちのたわごとだけじゃない話ゆとたわ(かりん&ほのか),ゆとたわ(かりん&ほのか)読み終わった - 2025年9月20日
 わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。 ゆとりっ娘たちのたわごとだけじゃない話ゆとたわ(かりん&ほのか),ゆとたわ(かりん&ほのか)読み始めたPodcastの過去回をすべて聞くのはけっこう無茶なので、エッセンスがぎゅぎゅっと凝縮されてるであろう書籍を、BREWBOOKSにて購入。 まさにクォーターライフクライシスに直面しながら生きる20代後半もあと2ヶ月… 30歳になったとていきなり視界が開けるわけでもないだろうけど、20歳の時と比べて人生が間違いなくだんだん面白くなってるっていうのは本当にそう。具体的な事象というよりは、世界の見え方という意味で。
わたしたち雑談するために生まれてきた、のかもしれない。 ゆとりっ娘たちのたわごとだけじゃない話ゆとたわ(かりん&ほのか),ゆとたわ(かりん&ほのか)読み始めたPodcastの過去回をすべて聞くのはけっこう無茶なので、エッセンスがぎゅぎゅっと凝縮されてるであろう書籍を、BREWBOOKSにて購入。 まさにクォーターライフクライシスに直面しながら生きる20代後半もあと2ヶ月… 30歳になったとていきなり視界が開けるわけでもないだろうけど、20歳の時と比べて人生が間違いなくだんだん面白くなってるっていうのは本当にそう。具体的な事象というよりは、世界の見え方という意味で。 - 2025年9月3日
- 2025年8月11日
 他者といる技法奥村隆読み終わった
他者といる技法奥村隆読み終わった - 2025年8月10日
 r4ンb-^、m「^柿内正午読み終わった
r4ンb-^、m「^柿内正午読み終わった - 2025年8月10日
 バクちゃん 2増村十七読み終わった
バクちゃん 2増村十七読み終わった
読み込み中...

