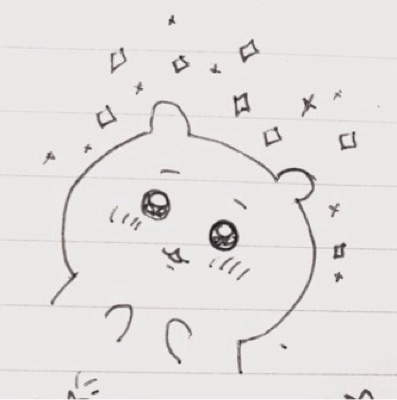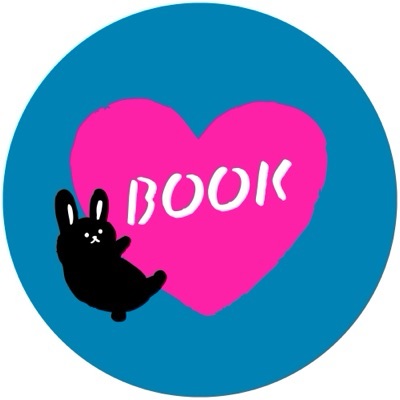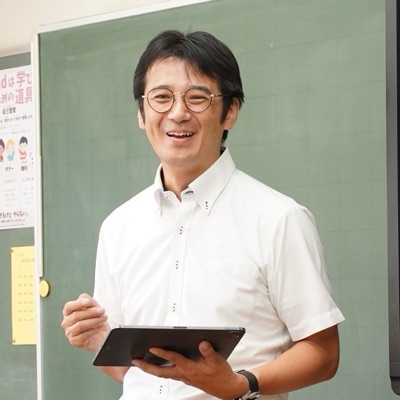他者といる技法

111件の記録
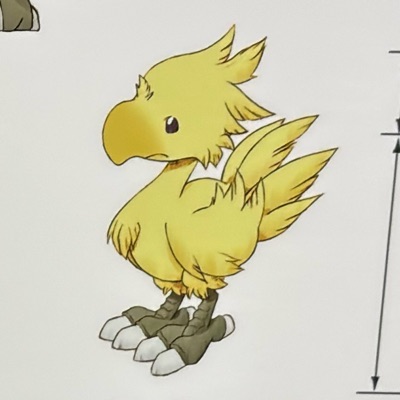 shima@shima122026年2月24日読み終わった「わからない」時、人は安直な「わかる」に着地しようとするか、距離を取って見ないようにしてしまう。すぐに「わかろう」としないで、「わからないでいる」状態の居心地の悪さが一緒にいることに繋がる。 わかりあえない時間を大切にしたいと思った。この人はこんな人なんだなってわかった気にならないで、話しあうことを選択していきたい。安直なわかるに着地させないように意識するには時間がかかりそうだけど、まずは会話中に気づけるようになりたい。会話中のモヤモヤはそのためのヒントなのかなと感じた。
shima@shima122026年2月24日読み終わった「わからない」時、人は安直な「わかる」に着地しようとするか、距離を取って見ないようにしてしまう。すぐに「わかろう」としないで、「わからないでいる」状態の居心地の悪さが一緒にいることに繋がる。 わかりあえない時間を大切にしたいと思った。この人はこんな人なんだなってわかった気にならないで、話しあうことを選択していきたい。安直なわかるに着地させないように意識するには時間がかかりそうだけど、まずは会話中に気づけるようになりたい。会話中のモヤモヤはそのためのヒントなのかなと感じた。 雨@little_rain2025年10月12日読み終わった文庫100冊途中までリサーチ対象の古さやこの本が書かれた時代からの社会の変容を感じていたが、最終章の論はほとんど色褪せておらず、排外主義が人口を膾炙するようになった現在、読まれるべき文章だと思った
雨@little_rain2025年10月12日読み終わった文庫100冊途中までリサーチ対象の古さやこの本が書かれた時代からの社会の変容を感じていたが、最終章の論はほとんど色褪せておらず、排外主義が人口を膾炙するようになった現在、読まれるべき文章だと思った
 ばぶちゃん@babuchan2025年9月13日読んでる@ 自宅「好きだと思う」と勧めてくれた友人に借りて。 順に読もうと努力はしたけど文字が滑って入ってこず、特におすすめしてくれた6章を先に読んだ。 ・他者に「理解」されない場所をもつことによって、「私」は「私」でありはじめる。(274) これはスッと腑に落ちた。 ・「他者はわからない」という想定を出発点として、他者といることを模索する技法である。「他者はわかるはず」と思うと「いっしょにいられる」領域は限定されるが、「わからない」のが当然と考えるならば、私たちはずっと多くの場合「いっしょにいること」ができる(294) 「話し合う」ということは、「尋ねる」、「質問する」と、「答える」、「説明する」から始まる。「わからない」と相手にハッキリ伝えることからしか始まらない。「わかりあわない」時間が「他者といる」ということだと思ってしまえば苦痛ではないかもしれない。 ・「わかりあわない」ということは、そのような「他者」を「他者」のまま発見する回路を開いているということだ。(295) 丁度昨日、私はこの本を貸してくれた友人に自分の発達特性と欲しいサポート、私が心がけることなどを伝えた。それに対して友人は質問をしてくれて、私はそのお陰で更に考えたり説明をしたりして、一緒に確認できたのが嬉しかった。 6章を読んでいて、私たちはまさに「わからない他者と話し合うことでいっしょにいようとする」ことをしていたんだなと思った。更に解説の、「コミュニケーションは互いの心理の開陳や心のなかのメッセージの交換ではなく、これから先どのように行動をしていくか、どのように行動していくべきだと互いに見なすかの擦り合わせ契機であることをその本質としている」の通りだと思った。「私はこうしようと思っているよ、こういう時はこうしてくれたら嬉しい」「私はこうするね、こういう時はどうしたらいい?」と、これから先どう行動していくか擦り合わせていた。今回は私が「説明する」側だったけど、お互いに「わからないから質問し合う」関係性を、これから生きていく上で大切に、築けたらいいな。 ・私たちは「わかりあおう」とするがゆえに、ときどき少し急ぎすぎてしまう。しかし、「わからない」時間をできるだけ引き延ばして、その居心地の悪さのなかに少しでも長くいられるようにしよう。 最後のこの部分に胸がギュッと泣きたくなった。どんなコミュニティのどんな関係性も、急ぐ必要はないんだよね。
ばぶちゃん@babuchan2025年9月13日読んでる@ 自宅「好きだと思う」と勧めてくれた友人に借りて。 順に読もうと努力はしたけど文字が滑って入ってこず、特におすすめしてくれた6章を先に読んだ。 ・他者に「理解」されない場所をもつことによって、「私」は「私」でありはじめる。(274) これはスッと腑に落ちた。 ・「他者はわからない」という想定を出発点として、他者といることを模索する技法である。「他者はわかるはず」と思うと「いっしょにいられる」領域は限定されるが、「わからない」のが当然と考えるならば、私たちはずっと多くの場合「いっしょにいること」ができる(294) 「話し合う」ということは、「尋ねる」、「質問する」と、「答える」、「説明する」から始まる。「わからない」と相手にハッキリ伝えることからしか始まらない。「わかりあわない」時間が「他者といる」ということだと思ってしまえば苦痛ではないかもしれない。 ・「わかりあわない」ということは、そのような「他者」を「他者」のまま発見する回路を開いているということだ。(295) 丁度昨日、私はこの本を貸してくれた友人に自分の発達特性と欲しいサポート、私が心がけることなどを伝えた。それに対して友人は質問をしてくれて、私はそのお陰で更に考えたり説明をしたりして、一緒に確認できたのが嬉しかった。 6章を読んでいて、私たちはまさに「わからない他者と話し合うことでいっしょにいようとする」ことをしていたんだなと思った。更に解説の、「コミュニケーションは互いの心理の開陳や心のなかのメッセージの交換ではなく、これから先どのように行動をしていくか、どのように行動していくべきだと互いに見なすかの擦り合わせ契機であることをその本質としている」の通りだと思った。「私はこうしようと思っているよ、こういう時はこうしてくれたら嬉しい」「私はこうするね、こういう時はどうしたらいい?」と、これから先どう行動していくか擦り合わせていた。今回は私が「説明する」側だったけど、お互いに「わからないから質問し合う」関係性を、これから生きていく上で大切に、築けたらいいな。 ・私たちは「わかりあおう」とするがゆえに、ときどき少し急ぎすぎてしまう。しかし、「わからない」時間をできるだけ引き延ばして、その居心地の悪さのなかに少しでも長くいられるようにしよう。 最後のこの部分に胸がギュッと泣きたくなった。どんなコミュニティのどんな関係性も、急ぐ必要はないんだよね。
- youy@youy2025年8月15日読み終わった1章があまり読み進められなくて積読になっていた。2章から5章を先に読んでも良いと思う。 「「わからない」時間をできるだけ引き延ばして、その居心地の悪さのなかに少しでも長くいられるようにしよう」(P296) 今の自分に必要な技法はまさにこれなんだ、と思った



 こここ@continue_reading2025年7月15日読み終わった文庫ではなく、1998年第一版の単行本の方を読んだ。 「コミュニケーションの社会学」との副題だが、ちょっと心理学的な要素を感じつつ読んだ。 私達は「理解の過小」を苦しみ論じるが、「理解の過剰」という苦しみも存在しそれはあまり論じられることがない。 理解し過ぎることや理解され過ぎることもまた差別や暴力から逃れられない状態に人を留めてしまう。 「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法は、質問しあい、説明しあい、「はなしあう」ことだと著者は言う。 「わかりあえない」という状態は居心地が悪く出来れば避けたい状態である。そのとき、「理解」だけが解決するための技法ではないと。 わかりあえなくとも共にいることが出来るのなら素晴らしいし、必要なことだ。 わからなさを抱え他者と共にいるという事は、ネガティヴケイパビリティだろうと思う。
こここ@continue_reading2025年7月15日読み終わった文庫ではなく、1998年第一版の単行本の方を読んだ。 「コミュニケーションの社会学」との副題だが、ちょっと心理学的な要素を感じつつ読んだ。 私達は「理解の過小」を苦しみ論じるが、「理解の過剰」という苦しみも存在しそれはあまり論じられることがない。 理解し過ぎることや理解され過ぎることもまた差別や暴力から逃れられない状態に人を留めてしまう。 「わかりあえない」けれど「いっしょにいる」ための技法は、質問しあい、説明しあい、「はなしあう」ことだと著者は言う。 「わかりあえない」という状態は居心地が悪く出来れば避けたい状態である。そのとき、「理解」だけが解決するための技法ではないと。 わかりあえなくとも共にいることが出来るのなら素晴らしいし、必要なことだ。 わからなさを抱え他者と共にいるという事は、ネガティヴケイパビリティだろうと思う。









 北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年5月8日読んでる@ ライトアップコーヒー 吉祥寺店P15 ずいぶんと不気味で疎遠にみえる存在である「他者」といっしょにいるということ、いっしょにいて「社会」を作るという面倒なことをすることは、そこから広がるすばらしい可能性と、それをするために生じる苦しみとを、ほとんどつねに同時に内包するのではないか。
北村有(きたむらゆう)@yuu_uu_2025年5月8日読んでる@ ライトアップコーヒー 吉祥寺店P15 ずいぶんと不気味で疎遠にみえる存在である「他者」といっしょにいるということ、いっしょにいて「社会」を作るという面倒なことをすることは、そこから広がるすばらしい可能性と、それをするために生じる苦しみとを、ほとんどつねに同時に内包するのではないか。






 檸檬🍋@mitternacht262025年3月6日読んでるこちらも他の本と並行して今読み進めてる。まだ最初の方。この本における社会学とは、という枠組みから興味深い。内側から語ることの難しさと大切さ。
檸檬🍋@mitternacht262025年3月6日読んでるこちらも他の本と並行して今読み進めてる。まだ最初の方。この本における社会学とは、という枠組みから興味深い。内側から語ることの難しさと大切さ。