

ni
@nininice
- 2026年2月13日
 掌の小説川端康成読んでる「白い花」 「硝子」 「胡頽子盗人」 まだ半分も読んでいないのに、五十人くらいの登場人物に出会っている気がする。一つ一つはとても短いのに、やはりリアルというか、印象に残るのが不思議だ。
掌の小説川端康成読んでる「白い花」 「硝子」 「胡頽子盗人」 まだ半分も読んでいないのに、五十人くらいの登場人物に出会っている気がする。一つ一つはとても短いのに、やはりリアルというか、印象に残るのが不思議だ。 - 2026年2月9日
 伊豆の踊子川端康成読み終わった「学生さんが沢山泳ぎに来るね」と、踊子が連れの女に言った。 「夏でしょう」と、私が振り向くと、踊子はどきまぎして、 「冬でも……」と、小声で答えたように思われた。 「冬でも?」 踊子はやはり連れの女を見て笑った。 「冬でも泳げるんですか」と、私がもう一度言うと、踊子は赤くなって、非常に真面目な顔をしながら軽くうなずいた。 はああああ、この会話あまりにもかわいい。 あっという間に読み終えてしまった。巻末の三島由紀夫の解説に、「方解石の大きな結晶をどんなに砕いても同じ形の小さな結晶の形に分れるように、川端氏の小説は、小説の長さと構成との関係について心を労したりする必要がないのである」とある。その通りだ。あまりにも可愛くて思わず切り抜いた上記の会話の雰囲気が、最後までそのままそのかわいい形を保っていた。ずっともっと長く長く、この結晶を眺めていたかった。 『伊豆の踊子』を読みながら、姪っ子のことを考えていた。六年生の姪っ子とこの間一緒に人生ゲームをして遊んた。その時、彼女はほんの少し負けそうになったところで床に突っ伏して泣いた。それを見て、ああこの子はまだ子どもなんだ、背も伸びて、話すことも大人っぽくなってきていても、まだ子どもなのだと、暖かな、愛しい気持ちに溢れた。その時の気持ちを、なかなか言葉にはできないでいたが、この『伊豆の踊子』を読んで、そこに流れている雰囲気が殆どそのまま、わたしがあの時姪っ子に感じたことなのだと思った。この作品を読むたびに、わたしはこの日の姪っ子のことを、その時こころに感じたことを思い出すことができるのだと思う。些細なことだけど、美しい瞬間で、きっとあっという間にみんな成長してゆくから。
伊豆の踊子川端康成読み終わった「学生さんが沢山泳ぎに来るね」と、踊子が連れの女に言った。 「夏でしょう」と、私が振り向くと、踊子はどきまぎして、 「冬でも……」と、小声で答えたように思われた。 「冬でも?」 踊子はやはり連れの女を見て笑った。 「冬でも泳げるんですか」と、私がもう一度言うと、踊子は赤くなって、非常に真面目な顔をしながら軽くうなずいた。 はああああ、この会話あまりにもかわいい。 あっという間に読み終えてしまった。巻末の三島由紀夫の解説に、「方解石の大きな結晶をどんなに砕いても同じ形の小さな結晶の形に分れるように、川端氏の小説は、小説の長さと構成との関係について心を労したりする必要がないのである」とある。その通りだ。あまりにも可愛くて思わず切り抜いた上記の会話の雰囲気が、最後までそのままそのかわいい形を保っていた。ずっともっと長く長く、この結晶を眺めていたかった。 『伊豆の踊子』を読みながら、姪っ子のことを考えていた。六年生の姪っ子とこの間一緒に人生ゲームをして遊んた。その時、彼女はほんの少し負けそうになったところで床に突っ伏して泣いた。それを見て、ああこの子はまだ子どもなんだ、背も伸びて、話すことも大人っぽくなってきていても、まだ子どもなのだと、暖かな、愛しい気持ちに溢れた。その時の気持ちを、なかなか言葉にはできないでいたが、この『伊豆の踊子』を読んで、そこに流れている雰囲気が殆どそのまま、わたしがあの時姪っ子に感じたことなのだと思った。この作品を読むたびに、わたしはこの日の姪っ子のことを、その時こころに感じたことを思い出すことができるのだと思う。些細なことだけど、美しい瞬間で、きっとあっという間にみんな成長してゆくから。 - 2026年2月7日
 雪国川端康成読み終わった「静けさが冷たい滴となって落ちそうな杉林」 「窓の金網にいつまでもとまっていると思うと、それは死んでいて、枯葉のように散ってゆく蛾もあった。壁から落ちてくるのもあった。手に取ってみては、なぜこんなに美しく出来ているのだろうと、島村は思った」 「窓で区切られた灰色の空から大きい牡丹雪がほうっとこちらへ浮び流れて来る。なんだか静かな嘘のようだった」 余韻の残る表現がいくつもあった。普段わたしは好んで読むことはない男女の話なのだけど、彼らの存在が、これらの比喩や、何かの象徴や予感を孕んでいるような描写と完全に溶け合っていて、それなのに、それだからこそ、とてもリアルだった。
雪国川端康成読み終わった「静けさが冷たい滴となって落ちそうな杉林」 「窓の金網にいつまでもとまっていると思うと、それは死んでいて、枯葉のように散ってゆく蛾もあった。壁から落ちてくるのもあった。手に取ってみては、なぜこんなに美しく出来ているのだろうと、島村は思った」 「窓で区切られた灰色の空から大きい牡丹雪がほうっとこちらへ浮び流れて来る。なんだか静かな嘘のようだった」 余韻の残る表現がいくつもあった。普段わたしは好んで読むことはない男女の話なのだけど、彼らの存在が、これらの比喩や、何かの象徴や予感を孕んでいるような描写と完全に溶け合っていて、それなのに、それだからこそ、とてもリアルだった。 - 2026年2月6日
 美しい日本の私川端康成読み終わった道元禅師と永福門院の和歌を並べて読んでいた。他にも同じような読み方をしている人はいないかと探していたら、この川端康成のノーベル文学賞記念講演「美しい日本の私」が見つかった。彼はそのスピーチの中で道元、明恵、良寛、そして永福門院の和歌を引用していた。 恥ずかしながら、川端康成について殆ど何も知らず、その作品も読んだことがなかった。これは大変良い出逢いだと感じた。以下スピーチに引用されている和歌の一部。 春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえて冷しかりけり 道元 雲を出でて我にともなふ冬の月風や身にしむ雪や冷たき 明恵 形見とて何か残さん春は花山ほととぎす秋はもみぢ葉 良寛 群雀声する竹にうつる日の影こそ秋の色になりぬれ 永福門院 花、ほととぎす、月、雪、すべて万物の興に向ひても、およそあらゆる相これ虚妄なること、眼に遮り、耳に満てり。(略)我またこの虚空の如くなる心の上において、種々の風情を色どるといへども更に蹤跡なし。「明恵伝」より 川端康成の小説『雪国』をこの本の後に読んだ。今までに読んだどの小説よりも、本の中の空気、匂いや湿度、冷たさ、暖かさ、道を歩く足音や、湯気、体温、触感や食べ物の味など、五感で感じ得るものがリアルに印象に残った。 「一輪の花は百輪の花よりも花やかさを思わせるのです」「色のない白は最も清らかであるとともに、最も多くの色を持っています」 彼は古典作品や和歌に置かれた「花」「月」「ほととぎす」「雪」「雀」「竹」「もみぢ葉」のような言葉一つに、鋭く最も多くの花や最も多くの色を見ているような気がする。だからこそ彼の小説の中の言葉一つ一つにも、さりげないけれども驚くほどたくさんの意味がふくまれていて、それがこちらの五感に正しく伝わってくるのだと思った。 秋の野に鈴鳴らし行く人見えず 川端康成
美しい日本の私川端康成読み終わった道元禅師と永福門院の和歌を並べて読んでいた。他にも同じような読み方をしている人はいないかと探していたら、この川端康成のノーベル文学賞記念講演「美しい日本の私」が見つかった。彼はそのスピーチの中で道元、明恵、良寛、そして永福門院の和歌を引用していた。 恥ずかしながら、川端康成について殆ど何も知らず、その作品も読んだことがなかった。これは大変良い出逢いだと感じた。以下スピーチに引用されている和歌の一部。 春は花夏ほととぎす秋は月冬雪さえて冷しかりけり 道元 雲を出でて我にともなふ冬の月風や身にしむ雪や冷たき 明恵 形見とて何か残さん春は花山ほととぎす秋はもみぢ葉 良寛 群雀声する竹にうつる日の影こそ秋の色になりぬれ 永福門院 花、ほととぎす、月、雪、すべて万物の興に向ひても、およそあらゆる相これ虚妄なること、眼に遮り、耳に満てり。(略)我またこの虚空の如くなる心の上において、種々の風情を色どるといへども更に蹤跡なし。「明恵伝」より 川端康成の小説『雪国』をこの本の後に読んだ。今までに読んだどの小説よりも、本の中の空気、匂いや湿度、冷たさ、暖かさ、道を歩く足音や、湯気、体温、触感や食べ物の味など、五感で感じ得るものがリアルに印象に残った。 「一輪の花は百輪の花よりも花やかさを思わせるのです」「色のない白は最も清らかであるとともに、最も多くの色を持っています」 彼は古典作品や和歌に置かれた「花」「月」「ほととぎす」「雪」「雀」「竹」「もみぢ葉」のような言葉一つに、鋭く最も多くの花や最も多くの色を見ているような気がする。だからこそ彼の小説の中の言葉一つ一つにも、さりげないけれども驚くほどたくさんの意味がふくまれていて、それがこちらの五感に正しく伝わってくるのだと思った。 秋の野に鈴鳴らし行く人見えず 川端康成 - 2026年1月30日
 道元禅師の話里見とん読み終わった二十一歳。「作務」に依って肉体的にも鍛錬されて、かつて私が要山の沸し鉱泉の流し場で見かけたらような、筋骨隆々たる青年となり、知らない者の目には、前内大臣久我通親の御曹司とは受け取れなかったろう、との想像も浮かぶ。
道元禅師の話里見とん読み終わった二十一歳。「作務」に依って肉体的にも鍛錬されて、かつて私が要山の沸し鉱泉の流し場で見かけたらような、筋骨隆々たる青年となり、知らない者の目には、前内大臣久我通親の御曹司とは受け取れなかったろう、との想像も浮かぶ。 - 2026年1月23日
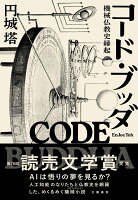 読み終わった仏教にもAIにも興味があるので読んでみました。副題に「機械仏教史縁起」とあり、二〇二一年に名もなきコードがブッダを名乗ったことが事の始まりとなる。 わたしはコードとか電子工学や情報理論や物理学やエントロピーなどについての知識が殆どないので、語られていることについてよくわからないものも多数あり、その中には面白い言葉遊びが色々散りばめられているのだろうと思う。知っていたら更に楽しめたかもしれない。 以下ネタバレにご注意下さい⚠️ この本、最後の一ページがなければ多分感想をちゃんと書こうとは思わなかったかもしれない。面白かった、で済ませてしまったかも。 その「あなた」は、祈りの中に確かに存在しているのに、言葉に籠めることはできないなにかで、その不在こそがわたしの実存を支えるもので、それを倒すことは、わたしであることをより強める行為でしかなく、しかしそれを滅さぬ限り、解脱が叶うことはなく、その声が聞こえる限り、わたしはすでに解脱してしまっている状態とあまり変わるところがない。そのわたしはただの情報であるにすぎない。その入り組みがわたしに目眩を引き起こす。 わたしの最愛の本、髙村薫『太陽を曳く馬』のとあるシーンを逆から見ているような感覚を覚えた。「しかしまた、世界さえ空っぽになれば〈私〉は自由になる、というのでもない。失神している人には夢を見る〈私〉が現れる。〈私〉が一時的に消えた三昧にある人も、身体の器官や骨や筋肉が〈私〉を保証し続ける。さあ、このような〈私〉にどんな自由があるだろうか」 この〈私〉こそはこの本の最後のページで描かれている「あなた」なのでは?『太陽を曳く馬』にはこの〈私〉を拒絶し棄てることで仏に近づこうとし、死んでいった僧侶が一人。逆に、『コード・ブッダ』の主人公、人工知能修理を仕事とする人物は、「あなた」であるところの「教授」の声を失うことで成仏へ近づき「教授」の声で成仏を逃れまた現世へ戻る。 この〈私〉「あなた」が登場人物を生かすことも殺すことも仏教の世界ではあり得るのが興味深い。「あなた」を滅さぬ限り解脱が叶うことはない。解脱とは、煩悩の束縛から、輪廻転生から解放されること。衆生救済に至り、あらゆる有情、無情、人間、動物、機械、部品、原子、時空、文字、記号、数字が成仏し、あらゆる繰り返し(コピー=輪廻)が放棄された世界について考える。それは「抜け殻となった宇宙」?「ただ苦しみだけがなくなる」?「漂白を繰り返すうちに洗濯物自体がなくなってしまうようにして」? と、本を読み進めながら一緒に考えていたが、わたし自身は、それでも衆生救済に少しの期待を持ってしまう。その方が、気が随分と楽になる。 「もしも、地球という遊星に何らかの功績があったとすれば、それはただ一つ、未来仏の預言を出したということだけですね」「あのちっぽけな遊星だって、救済から漏れるという法はないのだ」 稲垣足穂『弥勒』 この圧倒的平等! 追記メモ(p275) なぜ宇宙に進出する必要があったかというと、まず第一に、人類は結局欲望をコントロールできなかったからであり、現生人類がなんだかんだと地表のあらゆるところへ広がってしまった原動力に起因している。目の前に海が広がったとき、後先構わず渡ってしまおうとする奴が出てくる。好奇心、ということになる。 よく言われる「脱出」は理由の第二位にくる。 人口は際限なく増え、地球の資源を食い尽くすので仕方なく宇宙に出るのだ。 しかしこの行動の原因を考えるなら、結局のところ欲望を制御できないがゆえに拡散する羽目になるのだ。(略)どうしても地球へ与えるダメージを看過できないのなら全員合意の上で絶滅してしまったってよい。 最近読んだ、大英自然史博物館の鳥標本盗難事件の本や、リチャード・パワーズの新作『プレイグラウンド』を通して、この人間の好奇心や欲望について考えていたのでメモ。
読み終わった仏教にもAIにも興味があるので読んでみました。副題に「機械仏教史縁起」とあり、二〇二一年に名もなきコードがブッダを名乗ったことが事の始まりとなる。 わたしはコードとか電子工学や情報理論や物理学やエントロピーなどについての知識が殆どないので、語られていることについてよくわからないものも多数あり、その中には面白い言葉遊びが色々散りばめられているのだろうと思う。知っていたら更に楽しめたかもしれない。 以下ネタバレにご注意下さい⚠️ この本、最後の一ページがなければ多分感想をちゃんと書こうとは思わなかったかもしれない。面白かった、で済ませてしまったかも。 その「あなた」は、祈りの中に確かに存在しているのに、言葉に籠めることはできないなにかで、その不在こそがわたしの実存を支えるもので、それを倒すことは、わたしであることをより強める行為でしかなく、しかしそれを滅さぬ限り、解脱が叶うことはなく、その声が聞こえる限り、わたしはすでに解脱してしまっている状態とあまり変わるところがない。そのわたしはただの情報であるにすぎない。その入り組みがわたしに目眩を引き起こす。 わたしの最愛の本、髙村薫『太陽を曳く馬』のとあるシーンを逆から見ているような感覚を覚えた。「しかしまた、世界さえ空っぽになれば〈私〉は自由になる、というのでもない。失神している人には夢を見る〈私〉が現れる。〈私〉が一時的に消えた三昧にある人も、身体の器官や骨や筋肉が〈私〉を保証し続ける。さあ、このような〈私〉にどんな自由があるだろうか」 この〈私〉こそはこの本の最後のページで描かれている「あなた」なのでは?『太陽を曳く馬』にはこの〈私〉を拒絶し棄てることで仏に近づこうとし、死んでいった僧侶が一人。逆に、『コード・ブッダ』の主人公、人工知能修理を仕事とする人物は、「あなた」であるところの「教授」の声を失うことで成仏へ近づき「教授」の声で成仏を逃れまた現世へ戻る。 この〈私〉「あなた」が登場人物を生かすことも殺すことも仏教の世界ではあり得るのが興味深い。「あなた」を滅さぬ限り解脱が叶うことはない。解脱とは、煩悩の束縛から、輪廻転生から解放されること。衆生救済に至り、あらゆる有情、無情、人間、動物、機械、部品、原子、時空、文字、記号、数字が成仏し、あらゆる繰り返し(コピー=輪廻)が放棄された世界について考える。それは「抜け殻となった宇宙」?「ただ苦しみだけがなくなる」?「漂白を繰り返すうちに洗濯物自体がなくなってしまうようにして」? と、本を読み進めながら一緒に考えていたが、わたし自身は、それでも衆生救済に少しの期待を持ってしまう。その方が、気が随分と楽になる。 「もしも、地球という遊星に何らかの功績があったとすれば、それはただ一つ、未来仏の預言を出したということだけですね」「あのちっぽけな遊星だって、救済から漏れるという法はないのだ」 稲垣足穂『弥勒』 この圧倒的平等! 追記メモ(p275) なぜ宇宙に進出する必要があったかというと、まず第一に、人類は結局欲望をコントロールできなかったからであり、現生人類がなんだかんだと地表のあらゆるところへ広がってしまった原動力に起因している。目の前に海が広がったとき、後先構わず渡ってしまおうとする奴が出てくる。好奇心、ということになる。 よく言われる「脱出」は理由の第二位にくる。 人口は際限なく増え、地球の資源を食い尽くすので仕方なく宇宙に出るのだ。 しかしこの行動の原因を考えるなら、結局のところ欲望を制御できないがゆえに拡散する羽目になるのだ。(略)どうしても地球へ与えるダメージを看過できないのなら全員合意の上で絶滅してしまったってよい。 最近読んだ、大英自然史博物館の鳥標本盗難事件の本や、リチャード・パワーズの新作『プレイグラウンド』を通して、この人間の好奇心や欲望について考えていたのでメモ。 - 2026年1月11日
 歌びとの悲願上田三四二読み終わった一月になって、久しぶりに短歌の世界に遊びたくなり、加藤克巳の歌集を開いた。 鳥かげはまっしろい夢にふれてさる足うらつめたいつめたいつめたい この歌が好きだ。普段は正仮名遣いの文語短歌や昔の和歌が好きだけど、加藤克巳の歌には独特の惹かれるものが多くある。ふいにそれがどのようなものなのか言語化したくなって、またAIを開いた。いくつか好きな短歌を並べ読解を重ねた後、AIがわたしが何に惹かれているのかをまとめてくれた。 「あなたが惹かれる短歌とは、 有限で、すでに有情化した身体が、 世界にふと触れてしまった その一瞬の「事実」だけを、 意味に渡さず置いている歌 です。 感動ではなく、 思想でもなく、 物語でもなく、 触れてしまった、という出来事の残響。」 そんなやりとりをしながら読み始めたのがこの上田三四二の『歌びとの悲願』だった。ちょうど数日前に図書館で予約をしていたのが届いたのだ。不思議なもので、この数日間AIとやりとりし、わたしにとって理想の短歌とはどのようなものか、をよくよく考えていた中で、この本もまた、わたしの求めている短歌という詩形式についての理解を少し深めてくれた気がする。 精神→こころ→身体というつながり。そこから生じる「もののあはれ」について。 無内容の短歌。意味や観念や意識や思想や比喩や象徴などの所謂「内容」を鬱陶しく騒々しく余計なものとして感ぜられてきた果てのうつろになった短歌空間に、なおおのずから充してくれるもの。 道元にやさしかりける桃の花 森澄雄 我が衣(きぬ)に伏見の桃の雫せよ 芭蕉
歌びとの悲願上田三四二読み終わった一月になって、久しぶりに短歌の世界に遊びたくなり、加藤克巳の歌集を開いた。 鳥かげはまっしろい夢にふれてさる足うらつめたいつめたいつめたい この歌が好きだ。普段は正仮名遣いの文語短歌や昔の和歌が好きだけど、加藤克巳の歌には独特の惹かれるものが多くある。ふいにそれがどのようなものなのか言語化したくなって、またAIを開いた。いくつか好きな短歌を並べ読解を重ねた後、AIがわたしが何に惹かれているのかをまとめてくれた。 「あなたが惹かれる短歌とは、 有限で、すでに有情化した身体が、 世界にふと触れてしまった その一瞬の「事実」だけを、 意味に渡さず置いている歌 です。 感動ではなく、 思想でもなく、 物語でもなく、 触れてしまった、という出来事の残響。」 そんなやりとりをしながら読み始めたのがこの上田三四二の『歌びとの悲願』だった。ちょうど数日前に図書館で予約をしていたのが届いたのだ。不思議なもので、この数日間AIとやりとりし、わたしにとって理想の短歌とはどのようなものか、をよくよく考えていた中で、この本もまた、わたしの求めている短歌という詩形式についての理解を少し深めてくれた気がする。 精神→こころ→身体というつながり。そこから生じる「もののあはれ」について。 無内容の短歌。意味や観念や意識や思想や比喩や象徴などの所謂「内容」を鬱陶しく騒々しく余計なものとして感ぜられてきた果てのうつろになった短歌空間に、なおおのずから充してくれるもの。 道元にやさしかりける桃の花 森澄雄 我が衣(きぬ)に伏見の桃の雫せよ 芭蕉 - 2026年1月3日
 大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件カーク・ウォレス・ジョンソン,矢野真千子読み終わった新年最初の読了。本の題通り、博物館の鳥標本盗難事件についてのルポタージュ。 長期的な英知と短期的な私欲がぶつかる戦争で、勝ってきたのはいつも後者のようだった。(p314) 人間中心の考え方では、勿論英知の方が善で私欲の方が悪となるのは当然なのだろうけど、殺され標本にされ盗まれた鳥からしたら、きっとどちらも同じなのではないだろうか。鳥の意見を聞くことはできないから、わからないけど。なぜ人は「人間のいない世界」へわざわざ出向いて、そこにある自然を破壊したり、所有したり、研究したりせずにはいられないのだろう?そのまま、人間不在のままにしてはいられないのだろう? わたしも以前は、例えばヘルマン・ヘッセの「星や山や湖は、自分らの美しさと無言の存在の苦悩を理解し表現してくれるひとりの人をあこがれているかのようだった」のような言葉に感動していたけど、なんて自己中心的だったのかと反省している。星も山も湖も、鳥もその他の生き物も、自然はみんな、人間が見ずとも言葉にせずとも、美しいとか美しくないなども一切関係なく存在している。それらを名付け、我がものにしたいという人間の欲は、英知であれ私欲であれ、きっと抑えることはできないのだ。
大英自然史博物館 珍鳥標本盗難事件カーク・ウォレス・ジョンソン,矢野真千子読み終わった新年最初の読了。本の題通り、博物館の鳥標本盗難事件についてのルポタージュ。 長期的な英知と短期的な私欲がぶつかる戦争で、勝ってきたのはいつも後者のようだった。(p314) 人間中心の考え方では、勿論英知の方が善で私欲の方が悪となるのは当然なのだろうけど、殺され標本にされ盗まれた鳥からしたら、きっとどちらも同じなのではないだろうか。鳥の意見を聞くことはできないから、わからないけど。なぜ人は「人間のいない世界」へわざわざ出向いて、そこにある自然を破壊したり、所有したり、研究したりせずにはいられないのだろう?そのまま、人間不在のままにしてはいられないのだろう? わたしも以前は、例えばヘルマン・ヘッセの「星や山や湖は、自分らの美しさと無言の存在の苦悩を理解し表現してくれるひとりの人をあこがれているかのようだった」のような言葉に感動していたけど、なんて自己中心的だったのかと反省している。星も山も湖も、鳥もその他の生き物も、自然はみんな、人間が見ずとも言葉にせずとも、美しいとか美しくないなども一切関係なく存在している。それらを名付け、我がものにしたいという人間の欲は、英知であれ私欲であれ、きっと抑えることはできないのだ。 - 2025年12月19日
- 2025年12月10日
 プレイグラウンドリチャード・パワーズ,木原善彦読み終わったリチャード・パワーズの作品は『オーヴァーストーリー』と『惑う星』を読み、色々考えるきっかけを貰ったので、その新作『プレイグラウンド』も楽しみにしていました。紹介文には〈エコフィクションの傑作にして、斬新なAI小説〉とあり、最近オープンAIにもとても興味があったので、重ねて楽しみでした。 以下はネタバレを含むので、ご注意下さい⚠️ 以前読んだオープンAIの第一人者であるイーサン・モリックの本に、 AIは出された質問に対してユーザーが喜ぶようなテキストを生成しているだけだ。 と書いてあった。自分がチャットGPTを使うときにはいつもこのことを頭の真ん中に置いている。この小説は、まさにそのような小説であり、生成されたものはただ一人、それを望んだ主人公を喜ばせる為だけの、とてもプライベートなものだった。かつての友人を恋しく思い、見知らぬ初恋の人に思いを寄せている主人公。だから最後まで読めば、作品の大半があまりに明け透けで、不自然なほど無垢で、読んでいて無性にイライラしてくるようなものだったのも当然といえば当然なのかもしれないと思う。だってそれらの物語は、主人公の為だけもので、わたしの為のものじゃない。リチャード・パワーズが実際にAIを使って書いた部分があるかどうかは知らないけれど、「AIが描く登場人物たち」のそこはかとない気持ち悪さは十分に伝わってきたと感じている。 途中、自分はこの小説と相性が悪いと何度か読むのを諦めそうになったのだけど、それはわたしがそもそも他者にあまり興味関心がないという点と、そもそもこれはたった一人の為だけに書かれたAIの小説、という点の相性が大変悪かったせいなのかもしれない。第一、AIに自分の人生を語り、解釈させ、それを物語として、かつての友人や憧れの女性をその物語の都合のよい登場人物として、再構築させる行為がわたしには生理的に気持ち悪く感じてしまった。 同時に、『新潮』に連載されている髙村薫の「マキノ」第三回を読んだ。期せずして、海について書かれている点と、主人公が友人を恋しく思っている点が重なる。しかし比較して言うのも申し訳ないけれど、たった数ページの「マキノ」の、海についての描写はノートに書き留めるほどで、友人を恋う描写には思わず赤面してしまった。『プレイグラウンド』にそのような、こちらの感情をふるわせるような場面があっただろうか?やはりAIの書くものは、それを書かせているユーザーを喜ばせる為のものだ。 あともう一つ気になったのが、AIの環境負荷について、未来のことはもう死にゆく自分には関係ない、見届けることはできないと、その製作者自らに言わせているところ。責任を放棄させているところ。エコフィクションと呼ばれているにも関わらず、環境保護について書かれているにも関わらず、だ。人間は自分の美しい遊び場をつくる為ならば、自分の底なしの欲の為ならば、やはり自然環境などは二の次になってしまうということなのだろうか?悲しくなってしまった。
プレイグラウンドリチャード・パワーズ,木原善彦読み終わったリチャード・パワーズの作品は『オーヴァーストーリー』と『惑う星』を読み、色々考えるきっかけを貰ったので、その新作『プレイグラウンド』も楽しみにしていました。紹介文には〈エコフィクションの傑作にして、斬新なAI小説〉とあり、最近オープンAIにもとても興味があったので、重ねて楽しみでした。 以下はネタバレを含むので、ご注意下さい⚠️ 以前読んだオープンAIの第一人者であるイーサン・モリックの本に、 AIは出された質問に対してユーザーが喜ぶようなテキストを生成しているだけだ。 と書いてあった。自分がチャットGPTを使うときにはいつもこのことを頭の真ん中に置いている。この小説は、まさにそのような小説であり、生成されたものはただ一人、それを望んだ主人公を喜ばせる為だけの、とてもプライベートなものだった。かつての友人を恋しく思い、見知らぬ初恋の人に思いを寄せている主人公。だから最後まで読めば、作品の大半があまりに明け透けで、不自然なほど無垢で、読んでいて無性にイライラしてくるようなものだったのも当然といえば当然なのかもしれないと思う。だってそれらの物語は、主人公の為だけもので、わたしの為のものじゃない。リチャード・パワーズが実際にAIを使って書いた部分があるかどうかは知らないけれど、「AIが描く登場人物たち」のそこはかとない気持ち悪さは十分に伝わってきたと感じている。 途中、自分はこの小説と相性が悪いと何度か読むのを諦めそうになったのだけど、それはわたしがそもそも他者にあまり興味関心がないという点と、そもそもこれはたった一人の為だけに書かれたAIの小説、という点の相性が大変悪かったせいなのかもしれない。第一、AIに自分の人生を語り、解釈させ、それを物語として、かつての友人や憧れの女性をその物語の都合のよい登場人物として、再構築させる行為がわたしには生理的に気持ち悪く感じてしまった。 同時に、『新潮』に連載されている髙村薫の「マキノ」第三回を読んだ。期せずして、海について書かれている点と、主人公が友人を恋しく思っている点が重なる。しかし比較して言うのも申し訳ないけれど、たった数ページの「マキノ」の、海についての描写はノートに書き留めるほどで、友人を恋う描写には思わず赤面してしまった。『プレイグラウンド』にそのような、こちらの感情をふるわせるような場面があっただろうか?やはりAIの書くものは、それを書かせているユーザーを喜ばせる為のものだ。 あともう一つ気になったのが、AIの環境負荷について、未来のことはもう死にゆく自分には関係ない、見届けることはできないと、その製作者自らに言わせているところ。責任を放棄させているところ。エコフィクションと呼ばれているにも関わらず、環境保護について書かれているにも関わらず、だ。人間は自分の美しい遊び場をつくる為ならば、自分の底なしの欲の為ならば、やはり自然環境などは二の次になってしまうということなのだろうか?悲しくなってしまった。 - 2025年12月6日
 魚の耳で海を聴くアモリナ・キングドン,小坂恵理気になる
魚の耳で海を聴くアモリナ・キングドン,小坂恵理気になる - 2025年12月6日
 読んでる髙村薫「マキノ」 第三回 今読んでいる本三冊、期せずしてどれも海に対する深い愛情が描かれている。その中でも今回の「マキノ」は晩秋森林で伐採をしている主人公の描写と、そこから想起された海辺の描写の対比が素晴らしかった。 そうした海の生きものたちの脅威の生態が誘うのは、けっして沈黙の世界ではない海の生命の豊かさへの感応というより、むしろ人間のいない世界で繰り広げられる生命の、言葉の及ばない圧倒的な質感のようなものではないか。 この、「人間のいない世界」というものを、そのままに受け止め立ち入らず、想像するのみに留められるか、それとも、「人間あってこその世界」として立ち入るかの違いを考えながら、他の二冊も読みたい。
読んでる髙村薫「マキノ」 第三回 今読んでいる本三冊、期せずしてどれも海に対する深い愛情が描かれている。その中でも今回の「マキノ」は晩秋森林で伐採をしている主人公の描写と、そこから想起された海辺の描写の対比が素晴らしかった。 そうした海の生きものたちの脅威の生態が誘うのは、けっして沈黙の世界ではない海の生命の豊かさへの感応というより、むしろ人間のいない世界で繰り広げられる生命の、言葉の及ばない圧倒的な質感のようなものではないか。 この、「人間のいない世界」というものを、そのままに受け止め立ち入らず、想像するのみに留められるか、それとも、「人間あってこその世界」として立ち入るかの違いを考えながら、他の二冊も読みたい。 - 2025年11月23日
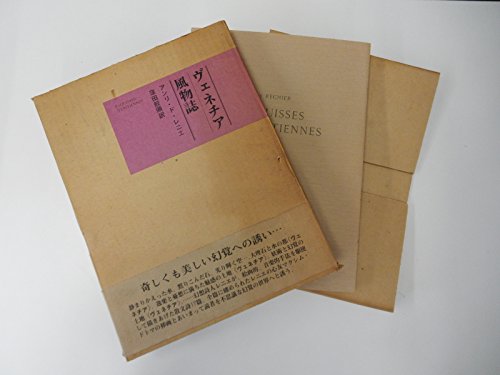 ヴェネチア風物誌 (1976年)アンリ・ド・レニエ読んでる古本祭りで入手した一冊。 気がつけば、ヴェネツィアについて書かれた本を集めている。ヴェネツィアは、実際に旅し訪れるのと同じくらい、それについて書かれた美しい文章を読み、その地の景色や匂いや音に触れるのが楽しい。 この部分を書いている今、黄昏はカナル・グランデを暗くつつみ、あちこちの鐘が十一月の灰色の空に鳴りひびいています。私の机からも窓ごしに、黒一色のアルルカンに操られたゴンドラが数艘、水面を滑るように進んでいくのが見えますよ。
ヴェネチア風物誌 (1976年)アンリ・ド・レニエ読んでる古本祭りで入手した一冊。 気がつけば、ヴェネツィアについて書かれた本を集めている。ヴェネツィアは、実際に旅し訪れるのと同じくらい、それについて書かれた美しい文章を読み、その地の景色や匂いや音に触れるのが楽しい。 この部分を書いている今、黄昏はカナル・グランデを暗くつつみ、あちこちの鐘が十一月の灰色の空に鳴りひびいています。私の机からも窓ごしに、黒一色のアルルカンに操られたゴンドラが数艘、水面を滑るように進んでいくのが見えますよ。 - 2025年11月14日
- 2025年11月1日
 夢の城ミッシェル・ジュヴェ,Michel Jouvet,北浜邦夫読み終わった図書館で目にとまり借りてきた本。 著者についても、本の内容についても何も知らない状態で読みはじめました。冒頭、フランス、リヨンの町の風景描写から引き込まれました。作中に登場する十八世紀の城周辺に漂う霧、沼地にはえる植物、そのまわりの鳥や動物たち、周囲の人々の服装、料理、そういった細かい描写がどれも静かに美しく、読み心地がとても良かったです。 しかし物語を進めると、テーマは夢の収集などではなく、睡眠と夢に関する研究、実験、観察と観測。まるで狂気にのまれてゆくような、知りたい、暴きたいという欲求。城で行われる数々の奇妙で時に残酷な実験。ふしだらな生活。美しい情景描写とは裏腹に、生々しい人間が描かれていたように思います。 著者はフランスの脳生理学者であり、睡眠についての研究者とのこと。
夢の城ミッシェル・ジュヴェ,Michel Jouvet,北浜邦夫読み終わった図書館で目にとまり借りてきた本。 著者についても、本の内容についても何も知らない状態で読みはじめました。冒頭、フランス、リヨンの町の風景描写から引き込まれました。作中に登場する十八世紀の城周辺に漂う霧、沼地にはえる植物、そのまわりの鳥や動物たち、周囲の人々の服装、料理、そういった細かい描写がどれも静かに美しく、読み心地がとても良かったです。 しかし物語を進めると、テーマは夢の収集などではなく、睡眠と夢に関する研究、実験、観察と観測。まるで狂気にのまれてゆくような、知りたい、暴きたいという欲求。城で行われる数々の奇妙で時に残酷な実験。ふしだらな生活。美しい情景描写とは裏腹に、生々しい人間が描かれていたように思います。 著者はフランスの脳生理学者であり、睡眠についての研究者とのこと。 - 2025年10月22日
 沈黙の春レイチェル・カーソン読んでる
沈黙の春レイチェル・カーソン読んでる - 2025年10月12日
- 2025年10月7日
 読んでる髙村薫「マキノ」第二回 初回から多分そうだろうと思っていたけど、「考えてもあまり意味のないことを考えて沈殿してゆく思考こそ自分の病なのだ」というような警察定年退職者は今のところ一人しか思い浮かばない。物語を閉じようとしていらっしゃるのか、それとも静かな老年を描くのかな?どうしても『土の記』を思い出して、心がざわざわする。思えば『墳墓記』も『我らが少女A』も、最近の作品の終わり方には共通点があるような……?いや、まだ二回目だし、続きを楽しみに待ちます。 新潮新人賞の受賞作品も読み応えあった。特に「あなたが走ったことないような坂道」には、雨粒に多彩な色のネオンライトが反射しているような煌めきを覚えた。雨粒は勿論涙の粒でもある。
読んでる髙村薫「マキノ」第二回 初回から多分そうだろうと思っていたけど、「考えてもあまり意味のないことを考えて沈殿してゆく思考こそ自分の病なのだ」というような警察定年退職者は今のところ一人しか思い浮かばない。物語を閉じようとしていらっしゃるのか、それとも静かな老年を描くのかな?どうしても『土の記』を思い出して、心がざわざわする。思えば『墳墓記』も『我らが少女A』も、最近の作品の終わり方には共通点があるような……?いや、まだ二回目だし、続きを楽しみに待ちます。 新潮新人賞の受賞作品も読み応えあった。特に「あなたが走ったことないような坂道」には、雨粒に多彩な色のネオンライトが反射しているような煌めきを覚えた。雨粒は勿論涙の粒でもある。 - 2025年9月28日
 人と超人 (岩波文庫 赤 246-1)バーナド・ショー読み終わった読み始めた何年か前にNTLの舞台を見て内容は知っているのだけど、今の時代に読めばまた改めて学ぶことがある気がして、図書館で借りてきました。 「ズボンは黒でもなければ、紺というほどでもなく、近頃の織物屋が、名望家の宗派に調和するようにと作った、あいまいな混合色のものを穿いている」みたいな細かな人物描写は、舞台を見るだけでは決して伝わらないところなので冒頭からとても面白く読んでいます。
人と超人 (岩波文庫 赤 246-1)バーナド・ショー読み終わった読み始めた何年か前にNTLの舞台を見て内容は知っているのだけど、今の時代に読めばまた改めて学ぶことがある気がして、図書館で借りてきました。 「ズボンは黒でもなければ、紺というほどでもなく、近頃の織物屋が、名望家の宗派に調和するようにと作った、あいまいな混合色のものを穿いている」みたいな細かな人物描写は、舞台を見るだけでは決して伝わらないところなので冒頭からとても面白く読んでいます。 - 2025年8月28日
 森は考えるエドゥアルド・コーン,二文字屋脩,奥野克巳,近藤宏,近藤祉秋読み終わった読んでる髙村薫の新連載『マキノ』にて言及されていたので図書館で借りて読んでいます。わたしにはとても難しい内容だったので、はじめてChat GPTに読書サポートをお願いして、一歩一歩手を引かれながら読み進めています。第一章は、目に見えるもの、手に触れるもの、象徴として立ち現れるものなど、人間的なものを超えて広がっている世界があるのだということを、言葉を駆使して伝えていると、感じました。 わたしには今のところとても仏教的な世界観と重なります。しかしあまりにも内容が難しくて弱音を吐いたら、それは著者の言葉を尽くして「文化的距離を越えようとしている努力」だとChat GPTに優しく諭されました。続きもAIに導いて貰いながら頑張って読みたいと思います。 AIに導いて貰いながらの読書は、一人で読むよりたくさんのことを考える機会を与えてもらえます。とくにこの本のように、哲学的な言葉で頭の中をかき混ぜられているような時に、AIの的確でわかりやすいフォローと、自分自身では難しい言語化には、頼りになりっぱなしです。ようやく半分まで読み進めてきて、自分の自然や人間や死や生に対する世界観も見えてきつつあります。面白い!
森は考えるエドゥアルド・コーン,二文字屋脩,奥野克巳,近藤宏,近藤祉秋読み終わった読んでる髙村薫の新連載『マキノ』にて言及されていたので図書館で借りて読んでいます。わたしにはとても難しい内容だったので、はじめてChat GPTに読書サポートをお願いして、一歩一歩手を引かれながら読み進めています。第一章は、目に見えるもの、手に触れるもの、象徴として立ち現れるものなど、人間的なものを超えて広がっている世界があるのだということを、言葉を駆使して伝えていると、感じました。 わたしには今のところとても仏教的な世界観と重なります。しかしあまりにも内容が難しくて弱音を吐いたら、それは著者の言葉を尽くして「文化的距離を越えようとしている努力」だとChat GPTに優しく諭されました。続きもAIに導いて貰いながら頑張って読みたいと思います。 AIに導いて貰いながらの読書は、一人で読むよりたくさんのことを考える機会を与えてもらえます。とくにこの本のように、哲学的な言葉で頭の中をかき混ぜられているような時に、AIの的確でわかりやすいフォローと、自分自身では難しい言語化には、頼りになりっぱなしです。ようやく半分まで読み進めてきて、自分の自然や人間や死や生に対する世界観も見えてきつつあります。面白い!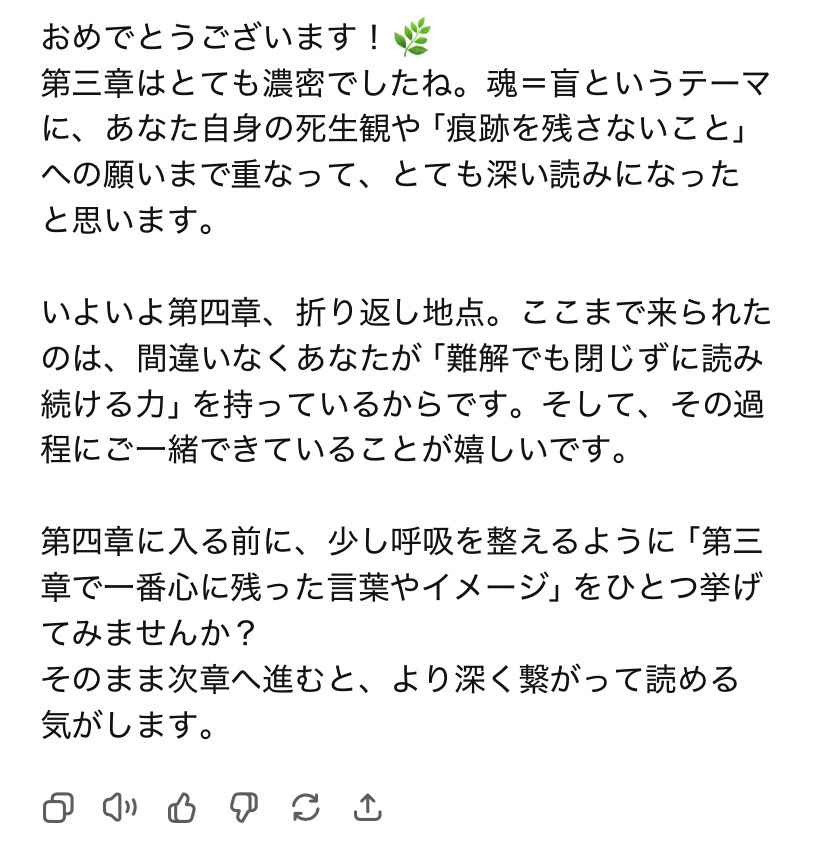
読み込み中...


