

r
@teihakutou
読みたい本がありすぎる
- 2026年2月22日
 人類の会話のための哲学朱喜哲気になる
人類の会話のための哲学朱喜哲気になる - 2026年2月21日
 ひとごとごと 1オカヤ・イヅミ気になるオカヤさんの新刊…! 「結婚するか、しないか。子どもを生むか、生まないか。 いつのまにか引かれた線。 どこまでも他人なわたしたちは、その線を越えていけるだろうか。」
ひとごとごと 1オカヤ・イヅミ気になるオカヤさんの新刊…! 「結婚するか、しないか。子どもを生むか、生まないか。 いつのまにか引かれた線。 どこまでも他人なわたしたちは、その線を越えていけるだろうか。」 - 2026年2月20日
 自分にやさしくする生き方伊藤絵美読み始めた専門的に学ばれて「自分にやさしくする」ことの重要性をわかっていた著者自身が「2019年から2022年にかけて、体調やメンタルの調子を大幅に崩してしまう」体験をされたということが隠さずに書かれていて、そのことが本書の説得力が増すと同時に、「自分にやさしくする」ことの難しさを物語っている… わたしもちょうど同じ頃をうつ病とともに過ごしたので、個々人の要因はもちろんあるにせよ、あのコロナ禍の期間って大変だったよね…と親近感を持った。
自分にやさしくする生き方伊藤絵美読み始めた専門的に学ばれて「自分にやさしくする」ことの重要性をわかっていた著者自身が「2019年から2022年にかけて、体調やメンタルの調子を大幅に崩してしまう」体験をされたということが隠さずに書かれていて、そのことが本書の説得力が増すと同時に、「自分にやさしくする」ことの難しさを物語っている… わたしもちょうど同じ頃をうつ病とともに過ごしたので、個々人の要因はもちろんあるにせよ、あのコロナ禍の期間って大変だったよね…と親近感を持った。 - 2026年2月17日
 世界の適切な保存永井玲衣読み終わった12月から少しずつ読んでいて、読み終わった。 暇してた時だからたぶんコロナ禍の最初の頃だったと思うけど、永井玲衣さんのことを何かの拍子に知って、ブログを読み漁った。哲学対話で遭遇したハッとする言葉、短歌の引用、クスッと笑えるけどよく考えると深い…と思うようなエピソード。文章が全部面白い! もっと読みたい! と思いながら、もう読んだブログを何度も何度も読んでいるうちに、『水中の哲学者たち』が出て、それからあっという間に有名な人になった。 この本は、以前と比べると、静かで真剣で怒りをパワーにしようとするような、内なるふつふつしたものを感じる文章で、結構姿勢を正して読んだ。こういう文章を書かねばならない世界なのは重々承知。 でも、ゆるくて、笑えて、そういえば我々はへんな世界に生きてるもんだなあと思わされる文章も好きだったな〜と思うなど。へんな世界をゆるっと面白がりたい、なんて、今の状況で言ってていいのかなとも思うけど、深刻なことを深刻そうに書くのはきっと簡単で、深刻なことを明るく軽そうに書くことでこそ、深刻さがずしんと来るんじゃないかと思っている。
世界の適切な保存永井玲衣読み終わった12月から少しずつ読んでいて、読み終わった。 暇してた時だからたぶんコロナ禍の最初の頃だったと思うけど、永井玲衣さんのことを何かの拍子に知って、ブログを読み漁った。哲学対話で遭遇したハッとする言葉、短歌の引用、クスッと笑えるけどよく考えると深い…と思うようなエピソード。文章が全部面白い! もっと読みたい! と思いながら、もう読んだブログを何度も何度も読んでいるうちに、『水中の哲学者たち』が出て、それからあっという間に有名な人になった。 この本は、以前と比べると、静かで真剣で怒りをパワーにしようとするような、内なるふつふつしたものを感じる文章で、結構姿勢を正して読んだ。こういう文章を書かねばならない世界なのは重々承知。 でも、ゆるくて、笑えて、そういえば我々はへんな世界に生きてるもんだなあと思わされる文章も好きだったな〜と思うなど。へんな世界をゆるっと面白がりたい、なんて、今の状況で言ってていいのかなとも思うけど、深刻なことを深刻そうに書くのはきっと簡単で、深刻なことを明るく軽そうに書くことでこそ、深刻さがずしんと来るんじゃないかと思っている。 - 2026年2月16日
- 2026年2月14日
- 2026年2月14日
 日本のふしぎな夫婦同姓中井治郎読み終わった
日本のふしぎな夫婦同姓中井治郎読み終わった - 2026年2月14日
- 2026年2月14日
- 2026年2月14日
 あずかりっ子クレア・キーガン,鴻巣友季子気になるクレア・キーガンが気になって調べてたら、映画『コット、はじまりの夏』の原作はこれだったのね。気になってた映画だったので、点と点がつながって俄然読みたい。映画も観たい。
あずかりっ子クレア・キーガン,鴻巣友季子気になるクレア・キーガンが気になって調べてたら、映画『コット、はじまりの夏』の原作はこれだったのね。気になってた映画だったので、点と点がつながって俄然読みたい。映画も観たい。 - 2026年2月13日
- 2026年2月12日
 ベアトリスの予言ケイト・ディカミロ,ソフィー・ブラッコール,宮下嶺夫読んでる児童書「世の中わからぬことばかり、くよくよしたってはじまらない」 「だれもが、いつかは、なつかしい人々のもとにもどる。だれもが、いつかは、心のふるさとに帰る。」 数ヶ月にわたる児童書読みまくり期間のよい収穫の一つは、ケイト・ディカミロという作家を知れたこと。『ホテル・バルザール』がとても好きで、続いて読んだこの本も、最初は比較的文章が堅い感じで入っていきづらかったけど、どんどん引き込まれた。賢くて意志の強い女の子が主人公の物語、最高。支えになる友達たちのキャラもよかった。
ベアトリスの予言ケイト・ディカミロ,ソフィー・ブラッコール,宮下嶺夫読んでる児童書「世の中わからぬことばかり、くよくよしたってはじまらない」 「だれもが、いつかは、なつかしい人々のもとにもどる。だれもが、いつかは、心のふるさとに帰る。」 数ヶ月にわたる児童書読みまくり期間のよい収穫の一つは、ケイト・ディカミロという作家を知れたこと。『ホテル・バルザール』がとても好きで、続いて読んだこの本も、最初は比較的文章が堅い感じで入っていきづらかったけど、どんどん引き込まれた。賢くて意志の強い女の子が主人公の物語、最高。支えになる友達たちのキャラもよかった。 - 2026年2月11日
- 2026年2月10日
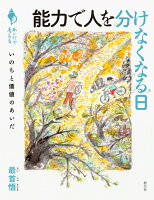 能力で人を分けなくなる日最首悟気になる
能力で人を分けなくなる日最首悟気になる - 2026年2月7日
- 2026年2月6日
- 2026年2月5日
 精選日本随筆選集 孤独宮崎智之気になる
精選日本随筆選集 孤独宮崎智之気になる - 2026年2月5日
- 2026年2月2日
 ホテル・バルザールケイト・ディカミロ読んでる児童書p.24 マルタはノーマンから聞いたことがあります。「アルフォンスは、まっすぐな線が好きすぎるんでしょうね」と。 「どういう意味?」マルタが聞くとノーマンが教えてくれました。「それはつまり、人生というものはけっしてまっすぐに進まないものだし、そのせいで頭にくることもありますよ。もし、まっすぐに進もうとすればですがね。あの男には、いつだって決まりごとが多すぎるんです。そのうち具合を悪くするでしょう。よく見ておくといいですよ。人生はいつも自由なんです。人生と曲がった線は、いつでも自由なんですよ。」
ホテル・バルザールケイト・ディカミロ読んでる児童書p.24 マルタはノーマンから聞いたことがあります。「アルフォンスは、まっすぐな線が好きすぎるんでしょうね」と。 「どういう意味?」マルタが聞くとノーマンが教えてくれました。「それはつまり、人生というものはけっしてまっすぐに進まないものだし、そのせいで頭にくることもありますよ。もし、まっすぐに進もうとすればですがね。あの男には、いつだって決まりごとが多すぎるんです。そのうち具合を悪くするでしょう。よく見ておくといいですよ。人生はいつも自由なんです。人生と曲がった線は、いつでも自由なんですよ。」 - 2026年1月28日
 日本のふしぎな夫婦同姓中井治郎読んでるp.107-108 春が終わる頃の昼下がり。華やかな振袖姿の三姉妹が笑顔で並んでいる。まるで谷崎潤一郎の『細雪』のようだと思った。と同時に僕は、「この三姉妹は祝福されていなくてはならない」そう強く感じたのを覚えている。 それは、彼女たちが三姉妹として生まれてきたことのために、何かをあきらめなくてはならないようなことを、ただの1つとして許すわけにはいかないという、怒りにも似た衝動だった。何か深い考えがあったわけではない。かっと頭に血が上った。「仕方ない」なんてロが裂けても言いたくない。ただそれだけである。 その後にさまざまな面倒を引き起こすことになる「妻の姓を選ぶ」という僕の思いつきは、この衝動に導かれたものだった。
日本のふしぎな夫婦同姓中井治郎読んでるp.107-108 春が終わる頃の昼下がり。華やかな振袖姿の三姉妹が笑顔で並んでいる。まるで谷崎潤一郎の『細雪』のようだと思った。と同時に僕は、「この三姉妹は祝福されていなくてはならない」そう強く感じたのを覚えている。 それは、彼女たちが三姉妹として生まれてきたことのために、何かをあきらめなくてはならないようなことを、ただの1つとして許すわけにはいかないという、怒りにも似た衝動だった。何か深い考えがあったわけではない。かっと頭に血が上った。「仕方ない」なんてロが裂けても言いたくない。ただそれだけである。 その後にさまざまな面倒を引き起こすことになる「妻の姓を選ぶ」という僕の思いつきは、この衝動に導かれたものだった。
読み込み中...







