

米谷隆佑
@yoneryu_
よく読みます。
- 2026年2月20日
 ガダラの豚 1中島らも読み終わった面白かったから続きを買うことにしたのだが、旅先の名古屋駅近くの三省堂には置いていなかった……。 中島らも。文庫本は一冊のみで、あれほど他の文庫本が所狭しに並んでおきながら「ガダラの豚」の1巻目すら置かれていないなんて……。 引き込まれる文章からは、知識人らしさと酒に溺れるどうしようもなさの両肩が主人公にのしかかり、もはや周囲の助けなしに歩けない弱さが軸にあることを物語る。ドラマ「トリック」を彷彿とする、呪術や奇術の種明かしなどが面白いが、新興宗教やペテン師に対する明らかな態度が筋を通していて、読み手の恐怖心を煽る。お前が騙されない理由はあるのか——。 これからアフリカに向かう。今後がどうなることやら。眉毛が燃えたお坊さんは今後出るのか。ガダラの豚の隠喩は、いつ現れるのだろうか。
ガダラの豚 1中島らも読み終わった面白かったから続きを買うことにしたのだが、旅先の名古屋駅近くの三省堂には置いていなかった……。 中島らも。文庫本は一冊のみで、あれほど他の文庫本が所狭しに並んでおきながら「ガダラの豚」の1巻目すら置かれていないなんて……。 引き込まれる文章からは、知識人らしさと酒に溺れるどうしようもなさの両肩が主人公にのしかかり、もはや周囲の助けなしに歩けない弱さが軸にあることを物語る。ドラマ「トリック」を彷彿とする、呪術や奇術の種明かしなどが面白いが、新興宗教やペテン師に対する明らかな態度が筋を通していて、読み手の恐怖心を煽る。お前が騙されない理由はあるのか——。 これからアフリカに向かう。今後がどうなることやら。眉毛が燃えたお坊さんは今後出るのか。ガダラの豚の隠喩は、いつ現れるのだろうか。 - 2026年1月20日
- 2026年1月20日
 コンビニ人間村田沙耶香読み終わった途中で、嘔気を催した。 本当にこんな人間がいるのなら主人公 古倉は「普通」という無理難題を問いに立て続ける機械のようだが、いわゆる「サイコパス」の様相を呈し、「哲学ゾンビ」のように外からの判別は困難を極める者でもある。それ故に本作は一人称で語り続けることでようやく理解が進む。が、「普通」ではない言動に始終不穏な空気が付きまとい、読んでいて不快になる。つまり、本作は「快適な文学」なのだ。 古倉の思想は、まさに動的平衡状態だった。コンビニの商品の新陳代謝による定常状態を理想とし、言葉遣いも人間関係もファッションも、何もかもが今を最適化する素材にすぎず、コンビニで振る舞うための話し方は真似をし、親友でさえ名前はカタカタと化して実名を忘れかけ新しいものを取り入れようとしている。 動物として自然な新陳代謝。しかし、合理さに欠けた基準の中で、何かを獲得しながら、過去のことを心太のように押し出して消してしまう。外部からの不快な圧力に応じるために己の解体と再構築を行う所業の数々は尋常ではない。読みながら感じていた不快感の正体は、まさにその状態だった。 本作の本質は、白羽を分析する古倉の言葉にあるように思える。人間は二種類しかいない。白羽は後者だった。借りてきた言葉を使うだけの人間——。 私とは何なのか、私の言葉は誰のものか。ひっそりと「普通」を探しながら、現代哲学の森に誘われる凄まじさがある。今次、鷲田清一が提唱した《所有論》にも手が届きうる、《個人》の根底を揺るがす哲学的な一作だと思った。
コンビニ人間村田沙耶香読み終わった途中で、嘔気を催した。 本当にこんな人間がいるのなら主人公 古倉は「普通」という無理難題を問いに立て続ける機械のようだが、いわゆる「サイコパス」の様相を呈し、「哲学ゾンビ」のように外からの判別は困難を極める者でもある。それ故に本作は一人称で語り続けることでようやく理解が進む。が、「普通」ではない言動に始終不穏な空気が付きまとい、読んでいて不快になる。つまり、本作は「快適な文学」なのだ。 古倉の思想は、まさに動的平衡状態だった。コンビニの商品の新陳代謝による定常状態を理想とし、言葉遣いも人間関係もファッションも、何もかもが今を最適化する素材にすぎず、コンビニで振る舞うための話し方は真似をし、親友でさえ名前はカタカタと化して実名を忘れかけ新しいものを取り入れようとしている。 動物として自然な新陳代謝。しかし、合理さに欠けた基準の中で、何かを獲得しながら、過去のことを心太のように押し出して消してしまう。外部からの不快な圧力に応じるために己の解体と再構築を行う所業の数々は尋常ではない。読みながら感じていた不快感の正体は、まさにその状態だった。 本作の本質は、白羽を分析する古倉の言葉にあるように思える。人間は二種類しかいない。白羽は後者だった。借りてきた言葉を使うだけの人間——。 私とは何なのか、私の言葉は誰のものか。ひっそりと「普通」を探しながら、現代哲学の森に誘われる凄まじさがある。今次、鷲田清一が提唱した《所有論》にも手が届きうる、《個人》の根底を揺るがす哲学的な一作だと思った。 - 2026年1月19日
 白百原研哉読んでる
白百原研哉読んでる - 2026年1月19日
 コンビニ人間村田沙耶香読んでる
コンビニ人間村田沙耶香読んでる - 2026年1月17日
 人間をみつめて神谷美恵子読み終わった人間の内部と外部の、特に内にある病いを診断、治療してきた経験から説得力ある論を展開しつつ、しかし、わからないことは飛躍して論を展開しない慎重さに科学者として正しい気質を感じさせる文体が目についた。 わからないこと、外部の圧力で人間がまだどうなるかがわからないこと、精神疾患の脳科学的アプローチの不明瞭さ……。 専門用語は既に使われなくなったものが多く、精神科は日進月歩だ。精神疾患の概念自体、古びれて参考にしかならない。が、古典的な詩や物語、現実に起きた精神疾患病者の事象を引用して、謙虚に進める力強い論調が、心によく響いていた気がする。 「生きがい」という現代人の悩みに応えた名著である。
人間をみつめて神谷美恵子読み終わった人間の内部と外部の、特に内にある病いを診断、治療してきた経験から説得力ある論を展開しつつ、しかし、わからないことは飛躍して論を展開しない慎重さに科学者として正しい気質を感じさせる文体が目についた。 わからないこと、外部の圧力で人間がまだどうなるかがわからないこと、精神疾患の脳科学的アプローチの不明瞭さ……。 専門用語は既に使われなくなったものが多く、精神科は日進月歩だ。精神疾患の概念自体、古びれて参考にしかならない。が、古典的な詩や物語、現実に起きた精神疾患病者の事象を引用して、謙虚に進める力強い論調が、心によく響いていた気がする。 「生きがい」という現代人の悩みに応えた名著である。 - 2026年1月17日
- 2026年1月17日
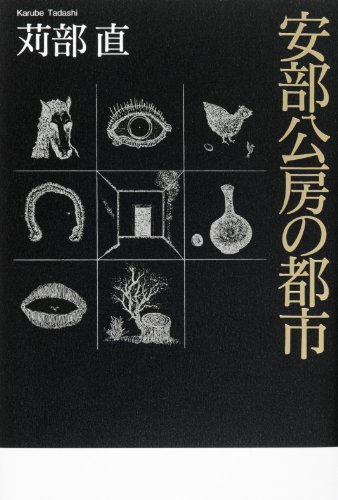 安部公房の都市苅部直読み終わった安部公房が盛んに扱ったモチーフの中でも、特に「都市」の脱構築は急務だったのだろう。求めていた近未来型都市を描く彼の文学からは、いつも何かしらの不穏とゴミが散逸していた。 急激に都市化する日本を、故郷なき安部公房の視点から描かれた作品群が、著者の視座によって解説されていく。 ちなみに、途中で言及されていた『燃えつきた地図』の基になった場所が「荻窪団地」なのではないか、という推理が当たっていると、個人的に嬉しい。 荻窪団地には、「記録芸術の会」の関係で訪れることがあったらしい。
安部公房の都市苅部直読み終わった安部公房が盛んに扱ったモチーフの中でも、特に「都市」の脱構築は急務だったのだろう。求めていた近未来型都市を描く彼の文学からは、いつも何かしらの不穏とゴミが散逸していた。 急激に都市化する日本を、故郷なき安部公房の視点から描かれた作品群が、著者の視座によって解説されていく。 ちなみに、途中で言及されていた『燃えつきた地図』の基になった場所が「荻窪団地」なのではないか、という推理が当たっていると、個人的に嬉しい。 荻窪団地には、「記録芸術の会」の関係で訪れることがあったらしい。 - 2026年1月12日
 死者の奢り・飼育大江健三郎読み終わった脂、空気、性と死と少年の成長。 おぼつかない心理状態で従属関係にヒビが入る様が、なんだか見ていて不憫である。しかし、この青年、子どもたちの生活が閉塞されてあることに、変化を促す兆しでもあることに気づくべきだ。外から異分子が入るだけで動揺し、自身との関係を納得する。そのすべての論理に無理はないのだが、予測されない言動に「恐るべき子ども」らしいと成長譚を見る。
死者の奢り・飼育大江健三郎読み終わった脂、空気、性と死と少年の成長。 おぼつかない心理状態で従属関係にヒビが入る様が、なんだか見ていて不憫である。しかし、この青年、子どもたちの生活が閉塞されてあることに、変化を促す兆しでもあることに気づくべきだ。外から異分子が入るだけで動揺し、自身との関係を納得する。そのすべての論理に無理はないのだが、予測されない言動に「恐るべき子ども」らしいと成長譚を見る。 - 2026年1月12日
- 2025年12月24日
 ユーモアの鎖国 新版石垣りん読み終わったつつましく生き、書いたものが載って、本になって金になり、金が本を買わせて生活をちょっと豊かにする。豊かになったら今度は日々のことに目が向いて、詩を書いて、先生に見てもらって、ユーモアがありますね、だなんて言われる石垣りんが楽しそうだ。戦争に苦しめられ形成されたライフスタイルには、現代でも参考になる心の向きがある。苦しい時代を踏み抜く精神の豊かさを、散文的に書かれたエッセイ。詩を書き、言葉で営むからこそ深く考えられた、言葉の力や澱んだ思想の前の無力さが語られていて、読者側を同時に深く悩ませることだろう。戦時中の政治が生活に与えた影響、どう扱われ、どう変わっていったのか——。 他人にどう思われるか、あぁも隠さず書き綴り、あげく、仕方がないネ、といった具合に折れて、こてん、と笑っている。こんな人が、昭和を舞台に東京を歩いていたなんて思えただけで、このエッセイはやさしい気持ちに導いてくれる。 彼女の、卑屈で屈託のない笑顔を写真に見つけては、文の朗らかさに気持ちが前向きになり、ぼくは幸せです。
ユーモアの鎖国 新版石垣りん読み終わったつつましく生き、書いたものが載って、本になって金になり、金が本を買わせて生活をちょっと豊かにする。豊かになったら今度は日々のことに目が向いて、詩を書いて、先生に見てもらって、ユーモアがありますね、だなんて言われる石垣りんが楽しそうだ。戦争に苦しめられ形成されたライフスタイルには、現代でも参考になる心の向きがある。苦しい時代を踏み抜く精神の豊かさを、散文的に書かれたエッセイ。詩を書き、言葉で営むからこそ深く考えられた、言葉の力や澱んだ思想の前の無力さが語られていて、読者側を同時に深く悩ませることだろう。戦時中の政治が生活に与えた影響、どう扱われ、どう変わっていったのか——。 他人にどう思われるか、あぁも隠さず書き綴り、あげく、仕方がないネ、といった具合に折れて、こてん、と笑っている。こんな人が、昭和を舞台に東京を歩いていたなんて思えただけで、このエッセイはやさしい気持ちに導いてくれる。 彼女の、卑屈で屈託のない笑顔を写真に見つけては、文の朗らかさに気持ちが前向きになり、ぼくは幸せです。 - 2025年12月7日
 老人と海アーネスト・ヘミングウェイ,高見浩読み終わったアラン・ドロン主演の映画『太陽がいっぱい』を見終えた感覚に似た照りつく晴れの海を思い出した。 寓意をもって読むか、それとも海に抱かれた老人の格闘劇と読むかで評価がよく分かれる、と解説に読んだ時に、これがまさしく名作の現象、抽象度の高さで感想が複雑になることの証左なんだろう。 ぼくには、験を担ぐ老人の気持ちがよくわかる。漁に出る男は、成功を約束されないまま、運や運命論的な旋律に促されて綱を引き、魚を獲る。母なる海、幸運の少年、85という数字……。 肉体と精神の限界、すり減りようを無骨に描く様はまさにハードボイルド。読み応えがあった。
老人と海アーネスト・ヘミングウェイ,高見浩読み終わったアラン・ドロン主演の映画『太陽がいっぱい』を見終えた感覚に似た照りつく晴れの海を思い出した。 寓意をもって読むか、それとも海に抱かれた老人の格闘劇と読むかで評価がよく分かれる、と解説に読んだ時に、これがまさしく名作の現象、抽象度の高さで感想が複雑になることの証左なんだろう。 ぼくには、験を担ぐ老人の気持ちがよくわかる。漁に出る男は、成功を約束されないまま、運や運命論的な旋律に促されて綱を引き、魚を獲る。母なる海、幸運の少年、85という数字……。 肉体と精神の限界、すり減りようを無骨に描く様はまさにハードボイルド。読み応えがあった。 - 2025年12月5日
 手記 太田治子 新潮社太田治子買った
手記 太田治子 新潮社太田治子買った - 2025年12月5日
 世界の散文モリス・メルロ・ポンティ,木田元,滝浦静雄気になる
世界の散文モリス・メルロ・ポンティ,木田元,滝浦静雄気になる - 2025年12月5日
 落葉: 短編集ガルシア・マルケス,高見英一買った
落葉: 短編集ガルシア・マルケス,高見英一買った - 2025年12月5日
 本を書く (ポケットスタンダード)アニー・ディラード読み終わったアニー・ディラードは一九四五年生まれの"女性"であるが、訳者があとがきに記した気づきが面白い。 "もう一つ興味深いことは、彼女の文章はジェンダーレスであるということ。 訳していて、彼女の思考に性別を感じなかった。いやあえて言えば、書くときに自分を女性とは思っていないのではないか、というほうが正しい。男性の言葉で書いているとも感じない。性のカテゴリーとボーダーを超えた人間として書いているのかも知れない。" 書くことの覚悟を、哲学と豊かな比喩表現で記される本書は、一度読むだけでは足りない満足感に襲われる。もっと書く生活を送ってから読めば、また見え方が変わるかもしれない。 表紙の写真を上田義彦さん、巻末のエッセイにBOOKNERD店主の早坂大輔さんと、〈好き〉な対象が本文をサンドしていて、二人のファンにとって良書。
本を書く (ポケットスタンダード)アニー・ディラード読み終わったアニー・ディラードは一九四五年生まれの"女性"であるが、訳者があとがきに記した気づきが面白い。 "もう一つ興味深いことは、彼女の文章はジェンダーレスであるということ。 訳していて、彼女の思考に性別を感じなかった。いやあえて言えば、書くときに自分を女性とは思っていないのではないか、というほうが正しい。男性の言葉で書いているとも感じない。性のカテゴリーとボーダーを超えた人間として書いているのかも知れない。" 書くことの覚悟を、哲学と豊かな比喩表現で記される本書は、一度読むだけでは足りない満足感に襲われる。もっと書く生活を送ってから読めば、また見え方が変わるかもしれない。 表紙の写真を上田義彦さん、巻末のエッセイにBOOKNERD店主の早坂大輔さんと、〈好き〉な対象が本文をサンドしていて、二人のファンにとって良書。 - 2025年12月1日
- 2025年11月22日
 金閣寺三島由紀夫読み終わったこの作品を、私は「童貞の文学」として読んだ。 精神的な未熟さの象徴としての吃音、女性との性的不能、執拗に追い求める美の権化(それは抽象的な容れ物に過ぎない)、強烈な——あるいは極めて純粋な——他者の影響を受けやすい多感さ、自らの傷を舐めてしまう野生的な癖、破綻した金銭感覚、不登校。成年になることができない主人公が、金閣寺を燃やすと志願しながらも、その達成を自ら遠ざけていく。そうした伏線を幾重にも張り巡らせながら、細部の文体を戯曲的に練り上げた最高峰の文学として読むことができる。 ところで、三島由紀夫が得意とした唯美的な文体——その読みごたえといい、飲み込みにくさといい——この厄介な文体を理解する手がかりとして、「ただ一度きりしか使わない辞書的な言葉」を配置する手法が挙げられるだろう。ぼくはこれが苦手だ。というより、この文体が美しいことを前提として認めつつ、やはり読みにくくなっていて、好きになりがたいのである。これは、日本語が美しい、というのだろうか。詩的な短文を軽妙なリズムで読ませる方法論に、ぼくがまだ十分な理解を持っていないせいかもしれないが、官僚的な言い回しと詩人的な言い回しの両得を図っているのではないか、と邪推してしまう。 三島由紀夫の思想が既にインプットされた状態で読む『金閣寺』は、主人公の独白を利用して作家自身の思想が露呈される作品として読み替えて容易い。だが、彼の市ヶ谷での「結末」を知ってから読む本作——それを知らないうちに読みたかった気持ちが強く、連載当時、刊行されて間もない頃の熱気に晒されてみたかったと思うので、本当に残念でならない。 金閣寺を燃やす、という大胆な発想が、芽吹きつつある主人公の思考を借りて暴かれていく様は、実にわかりやすく読み応えがあると言えよう。実相と抽象、内部世界と外部世界の統合、そして記憶と認識と行為。ここで語られた哲学は全て、現代においても色褪せない道理をもって語られている。先駆的に書かれたという若き挑戦に価値を認める。細部に至るまで力を込めて書かれた文章に打ちひしがれた文学青年はきっと、彼の思想に基づいた生き方を想像し始めるに違いない。 これは、未熟さを強気に書いた作品である。だから根底にあるコンプレックスを認めるまでの過程が、下手くそに、強烈に、男性性的に破壊されて描かれる。歳を取ったときに読むと、また別の感性から思うことが変わるだろう——それが楽しみだ。
金閣寺三島由紀夫読み終わったこの作品を、私は「童貞の文学」として読んだ。 精神的な未熟さの象徴としての吃音、女性との性的不能、執拗に追い求める美の権化(それは抽象的な容れ物に過ぎない)、強烈な——あるいは極めて純粋な——他者の影響を受けやすい多感さ、自らの傷を舐めてしまう野生的な癖、破綻した金銭感覚、不登校。成年になることができない主人公が、金閣寺を燃やすと志願しながらも、その達成を自ら遠ざけていく。そうした伏線を幾重にも張り巡らせながら、細部の文体を戯曲的に練り上げた最高峰の文学として読むことができる。 ところで、三島由紀夫が得意とした唯美的な文体——その読みごたえといい、飲み込みにくさといい——この厄介な文体を理解する手がかりとして、「ただ一度きりしか使わない辞書的な言葉」を配置する手法が挙げられるだろう。ぼくはこれが苦手だ。というより、この文体が美しいことを前提として認めつつ、やはり読みにくくなっていて、好きになりがたいのである。これは、日本語が美しい、というのだろうか。詩的な短文を軽妙なリズムで読ませる方法論に、ぼくがまだ十分な理解を持っていないせいかもしれないが、官僚的な言い回しと詩人的な言い回しの両得を図っているのではないか、と邪推してしまう。 三島由紀夫の思想が既にインプットされた状態で読む『金閣寺』は、主人公の独白を利用して作家自身の思想が露呈される作品として読み替えて容易い。だが、彼の市ヶ谷での「結末」を知ってから読む本作——それを知らないうちに読みたかった気持ちが強く、連載当時、刊行されて間もない頃の熱気に晒されてみたかったと思うので、本当に残念でならない。 金閣寺を燃やす、という大胆な発想が、芽吹きつつある主人公の思考を借りて暴かれていく様は、実にわかりやすく読み応えがあると言えよう。実相と抽象、内部世界と外部世界の統合、そして記憶と認識と行為。ここで語られた哲学は全て、現代においても色褪せない道理をもって語られている。先駆的に書かれたという若き挑戦に価値を認める。細部に至るまで力を込めて書かれた文章に打ちひしがれた文学青年はきっと、彼の思想に基づいた生き方を想像し始めるに違いない。 これは、未熟さを強気に書いた作品である。だから根底にあるコンプレックスを認めるまでの過程が、下手くそに、強烈に、男性性的に破壊されて描かれる。歳を取ったときに読むと、また別の感性から思うことが変わるだろう——それが楽しみだ。 - 2025年10月26日
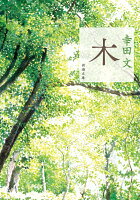 木幸田文読み終わった幸田文の文章は初めて読んだけど、曽祖母くらい離れた彼女がこんなに読みやすい「いい文章」を書いているなんて驚いた。 木と人間の生き方を重ねた文章を読んで、幸田文の考える「老い方」や「生き方」がとても律儀で、身体的な表現が豊かだと感じた。植物を見に出かけて感動して記録し、元気いっぱいに帰ってくる姿からは、とても老いた人とは思えない。好奇心に満ちて、過去を巧みに振り返る文章を読んで、日本語の大きな文脈から失われた「いい文章」を感じて悲しくなった。幸田文の文を読み終えて解説する佐伯一麦氏の指摘は鋭い。 “モームが列挙している「土壌」の条件を裏返すと、戦後五十年間の日本の社会が見えてくる。礼儀を軽視し、派手な流行を身にまとい、軽薄か生真面目かで、偏りがちで「熱狂」に染まりやすい。そして、そこで書き流される文章は、「育ちのいい人の座談」ではなく、育ちも趣味もかんばしくない人の仮装行列のようだ…..。”
木幸田文読み終わった幸田文の文章は初めて読んだけど、曽祖母くらい離れた彼女がこんなに読みやすい「いい文章」を書いているなんて驚いた。 木と人間の生き方を重ねた文章を読んで、幸田文の考える「老い方」や「生き方」がとても律儀で、身体的な表現が豊かだと感じた。植物を見に出かけて感動して記録し、元気いっぱいに帰ってくる姿からは、とても老いた人とは思えない。好奇心に満ちて、過去を巧みに振り返る文章を読んで、日本語の大きな文脈から失われた「いい文章」を感じて悲しくなった。幸田文の文を読み終えて解説する佐伯一麦氏の指摘は鋭い。 “モームが列挙している「土壌」の条件を裏返すと、戦後五十年間の日本の社会が見えてくる。礼儀を軽視し、派手な流行を身にまとい、軽薄か生真面目かで、偏りがちで「熱狂」に染まりやすい。そして、そこで書き流される文章は、「育ちのいい人の座談」ではなく、育ちも趣味もかんばしくない人の仮装行列のようだ…..。” - 2025年10月14日
 ラーメンと瞑想宇野常寛気になる
ラーメンと瞑想宇野常寛気になる
読み込み中...



