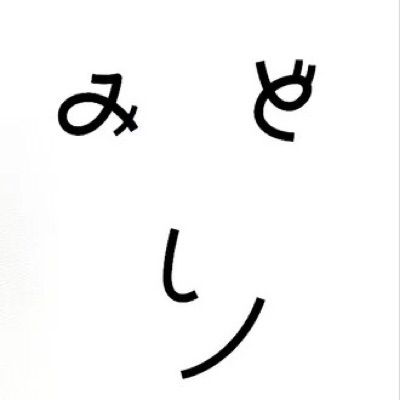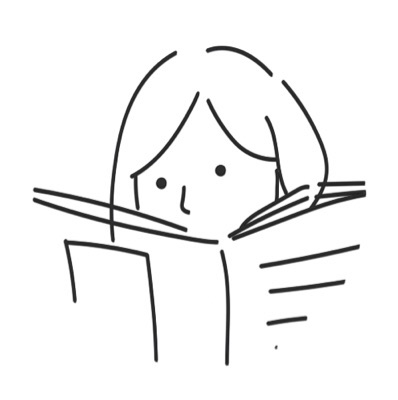わたしが誰かわからない

38件の記録
 くりこ@kurikomone2025年9月27日読み終わった最近頻度は少なくなったものの、昔の私は他者と長く関係性を持てば持つほど、自分の行動が私の意志によるものか相手の意思によるものか分からなくなることがよくあった。 小さい時は他人の痛みが自分の痛みみたいに感じられて苦しかったこともあって(今もその傾向はある)自他の境界のない人の特徴だから治したいと思ってた。しかし著者が、ヤングケアラーはケアするものケアされるものの両者の間の行き来が頻繁に起き、自己崩壊と自己保存が起こるため自我境界の融解というレッスンを日々受けているのだと、その特性を悪いものととらえず、違う視点で考えてるのが面白かった。 「自己の輪郭が溶け出し開いている=誰かのために生きていることは、自分のための生もまた同時に燃え広がっている」とラストで書かれていたのは、ティックナットハンのインタービーイングに近いのかなと感じた。 ヤングケアラーの語りの本は色々読んできたのだけど、著者が「書くことができない」ことを経て、より深いところに潜り、ケアとは何かを0から構築している。私のケアの経験も違う角度で照らしてくれた。著者が、最初に感じている「言葉がない」状態は、逆説的に他の人は経験したこともない豊かな言葉を持っているということなのだと思う。読んでよかった。 p.182 〈幼いころから敏感に感じていた自我の揺曳は、精神的に不安定な母に付き添う時間のなかで育った感覚であるともいえる。つまりヤングケアラーである自分はずっと、自我境界というレッスンを続けていたといえる。母の具合の悪さや不安が、部屋のすみずみまで伸び縮みするように感じ、そのなかで時間も伸び縮みし、時計の針の音が妙に大きく、自分の鼓動のように感じる。〉
くりこ@kurikomone2025年9月27日読み終わった最近頻度は少なくなったものの、昔の私は他者と長く関係性を持てば持つほど、自分の行動が私の意志によるものか相手の意思によるものか分からなくなることがよくあった。 小さい時は他人の痛みが自分の痛みみたいに感じられて苦しかったこともあって(今もその傾向はある)自他の境界のない人の特徴だから治したいと思ってた。しかし著者が、ヤングケアラーはケアするものケアされるものの両者の間の行き来が頻繁に起き、自己崩壊と自己保存が起こるため自我境界の融解というレッスンを日々受けているのだと、その特性を悪いものととらえず、違う視点で考えてるのが面白かった。 「自己の輪郭が溶け出し開いている=誰かのために生きていることは、自分のための生もまた同時に燃え広がっている」とラストで書かれていたのは、ティックナットハンのインタービーイングに近いのかなと感じた。 ヤングケアラーの語りの本は色々読んできたのだけど、著者が「書くことができない」ことを経て、より深いところに潜り、ケアとは何かを0から構築している。私のケアの経験も違う角度で照らしてくれた。著者が、最初に感じている「言葉がない」状態は、逆説的に他の人は経験したこともない豊かな言葉を持っているということなのだと思う。読んでよかった。 p.182 〈幼いころから敏感に感じていた自我の揺曳は、精神的に不安定な母に付き添う時間のなかで育った感覚であるともいえる。つまりヤングケアラーである自分はずっと、自我境界というレッスンを続けていたといえる。母の具合の悪さや不安が、部屋のすみずみまで伸び縮みするように感じ、そのなかで時間も伸び縮みし、時計の針の音が妙に大きく、自分の鼓動のように感じる。〉


 くりこ@kurikomone2025年9月26日まだ読んでる幼少期から暮らしてた叔母は八年前に亡くなった。彼女との思い出は正直に言ってしんどいことがとても多かった。重度の障害を抱え、排泄着替え食事の介護を家族で担い、医師には医療を断られ、彼女の「問題行動」に振り回されていつも家は内戦だった。 いつも私の中で彼女が生きてた時間は混沌としててパズルのピースがバラバラになったように散らかっている。私がフェミニズムや、家族をテーマにした文献をよく読むのもその時間を整理したいと言う思いがある。 精神疾患の母を持つ著者がヤングケアラーをインタビューして自身の体験に向き合う本。 他人の意思を先回りして自分の意思より尊重してしまう癖、ケアしてる人との境界が曖昧になり自分がわからなくなること、もう死ぬのではないかと言う目に遭っても少しの日常会話で平安が訪れる家族の不思議な力学についての言及など、 私と似通ってることが多くて自分自身が浮き彫りになる。 なにより、他の人の方がもっと大変な目をしてるのではないかと言う思いや、自分は家庭内で被害者でもあり加害者でもあることの負目から、自分が「ヤングケアラー」と言っていいかわからないと言う著者と同じ思いを私も持っており、重度障害の家族がいたとは話せるけど、ヤングケアラーだとは表明できない。私が、ヤングケアラーと言った途端、「家族をダシに使ってる」気がしてしまう。 自分の状態を表明することを家族のしがらみによって憚られること、大変息苦しく日本の家族の閉塞感を示してるように思う p.96 <とくにどこかでできてしまった傷、えぐられるような傷を自分のなかに感じているならなおさら、語られないことのほうが重い、語られないことのほうに意味がある。こうして一生懸命に書いているが、ここで語れないこと、語りたくないことのほうに圧倒的に意味がある。語らないことで、心が落ち着く。語れば落ち着かなくなり、それを無理やり落ち着けようとして、無理な着地点を探して、安っぽく類型的になる。>
くりこ@kurikomone2025年9月26日まだ読んでる幼少期から暮らしてた叔母は八年前に亡くなった。彼女との思い出は正直に言ってしんどいことがとても多かった。重度の障害を抱え、排泄着替え食事の介護を家族で担い、医師には医療を断られ、彼女の「問題行動」に振り回されていつも家は内戦だった。 いつも私の中で彼女が生きてた時間は混沌としててパズルのピースがバラバラになったように散らかっている。私がフェミニズムや、家族をテーマにした文献をよく読むのもその時間を整理したいと言う思いがある。 精神疾患の母を持つ著者がヤングケアラーをインタビューして自身の体験に向き合う本。 他人の意思を先回りして自分の意思より尊重してしまう癖、ケアしてる人との境界が曖昧になり自分がわからなくなること、もう死ぬのではないかと言う目に遭っても少しの日常会話で平安が訪れる家族の不思議な力学についての言及など、 私と似通ってることが多くて自分自身が浮き彫りになる。 なにより、他の人の方がもっと大変な目をしてるのではないかと言う思いや、自分は家庭内で被害者でもあり加害者でもあることの負目から、自分が「ヤングケアラー」と言っていいかわからないと言う著者と同じ思いを私も持っており、重度障害の家族がいたとは話せるけど、ヤングケアラーだとは表明できない。私が、ヤングケアラーと言った途端、「家族をダシに使ってる」気がしてしまう。 自分の状態を表明することを家族のしがらみによって憚られること、大変息苦しく日本の家族の閉塞感を示してるように思う p.96 <とくにどこかでできてしまった傷、えぐられるような傷を自分のなかに感じているならなおさら、語られないことのほうが重い、語られないことのほうに意味がある。こうして一生懸命に書いているが、ここで語れないこと、語りたくないことのほうに圧倒的に意味がある。語らないことで、心が落ち着く。語れば落ち着かなくなり、それを無理やり落ち着けようとして、無理な着地点を探して、安っぽく類型的になる。>



 くりこ@kurikomone2025年9月25日読み始めたp.47 <共依存といえば簡単だが、家族の暴力や支配関係のむずかしいところは、悪をただ悪として排除して終わりというわけではないところだ。家族は相互に依存し合い、支え合い、どちらが悪にも善にもなりうる玉虫色の感情を生きている。もう死ぬと思うくらいつらいことがあって逃げ出したいと思っても、数か月もするとほんの些細な日常的な会話でなし崩し的に元に戻る。この元に戻る力が強いのが家族の力学だろう。>
くりこ@kurikomone2025年9月25日読み始めたp.47 <共依存といえば簡単だが、家族の暴力や支配関係のむずかしいところは、悪をただ悪として排除して終わりというわけではないところだ。家族は相互に依存し合い、支え合い、どちらが悪にも善にもなりうる玉虫色の感情を生きている。もう死ぬと思うくらいつらいことがあって逃げ出したいと思っても、数か月もするとほんの些細な日常的な会話でなし崩し的に元に戻る。この元に戻る力が強いのが家族の力学だろう。>