

あおい
@booklover_aoi
子どもの頃から活字大好き。
絵本、漫画雑誌、図鑑、教科書、資料集、パンフレットなど、活字ならなんでも読みたかった幼少期。
卒論でさすがに活字を読みすぎたようで、社会人になってから少し読書から遠のいてましたが、ここ数年また読書にハマり始めました。
現代小説も好きですが、設定作り込みファンタジー、ノンフィクションも大好きです。
- 2026年1月20日
 読み終わったKindle Unlimited@ 自宅Kindleのおすすめに上がってたので読んでみた本。 ちょうど今日本の総理大臣は女性、奇しくも解散総選挙というタイミングで、読書とリアルが少し繋がった感じになりました。 小説はエンターテイメントなので、総理の妊娠・出産もありとして描かれてますが、実際はすっっっごい紛糾しそう… 小説は総理の夫、日和の日記形式で書かれていて、研究者で世間擦れしてない人の目線で女性総理を観察するというのが、確かにこの小説では適切だったなと思いました。 語り口も人柄が垣間見える感じで、読みながら「こんな人なのかな?」と想像できたのが楽しかったです。 個人的に男性、女性ではなく、個人の性質で考えればいいと思っているので、早く性差ありきで構築されたシステムがなくなるといいなと思っています。
読み終わったKindle Unlimited@ 自宅Kindleのおすすめに上がってたので読んでみた本。 ちょうど今日本の総理大臣は女性、奇しくも解散総選挙というタイミングで、読書とリアルが少し繋がった感じになりました。 小説はエンターテイメントなので、総理の妊娠・出産もありとして描かれてますが、実際はすっっっごい紛糾しそう… 小説は総理の夫、日和の日記形式で書かれていて、研究者で世間擦れしてない人の目線で女性総理を観察するというのが、確かにこの小説では適切だったなと思いました。 語り口も人柄が垣間見える感じで、読みながら「こんな人なのかな?」と想像できたのが楽しかったです。 個人的に男性、女性ではなく、個人の性質で考えればいいと思っているので、早く性差ありきで構築されたシステムがなくなるといいなと思っています。 - 2026年1月11日
- 2026年1月6日
 恋に至る病斜線堂有紀読み終わったKindle Unlimited@ 自宅年明けから割とヘビーなものばかり読んでたので、少しライトなものを読もうかなとkindleで読んでみました。 最近の読書が重厚系だったからか、登場人物の心理があっさりしてて、気づいたら読み終わってました。 個人的にはとても物足りなかった…。 がっつり焼肉!の気持ちだったのにヘルシーなサラダしか食べられなかった気持ち笑 チョイスを間違えたのは私なので、ちゃんと今読みたいものを理解してから本を選ぼうと思います。
恋に至る病斜線堂有紀読み終わったKindle Unlimited@ 自宅年明けから割とヘビーなものばかり読んでたので、少しライトなものを読もうかなとkindleで読んでみました。 最近の読書が重厚系だったからか、登場人物の心理があっさりしてて、気づいたら読み終わってました。 個人的にはとても物足りなかった…。 がっつり焼肉!の気持ちだったのにヘルシーなサラダしか食べられなかった気持ち笑 チョイスを間違えたのは私なので、ちゃんと今読みたいものを理解してから本を選ぼうと思います。 - 2026年1月5日
 一八八八 切り裂きジャック (角川文庫)服部まゆみ読み終わったKindle Unlimited@ 自宅服部まゆみさんが気になって『この世界の闇と光』のあとに続けて読みました。 久々の長編でしたが、とてもよい読書体験でした。 切り裂きジャックなのですが、歴史の教科書に記載されるような文豪や医師が出てきたりするので、程よいリアリティがあったのもよかったです。 服部まゆみさんの美学が随所に散りばめられていて、その部分もとても読み応えがありましたし、もちろん登場人物たちもまあまあ多いのですが、一人一人個性がきっちり書き分けられていて、登場人物の名前(特に外国の名前)を覚えるのが苦手な私でも割と覚えてられるくらいでした。 美貌で頭が切れて社交もできる体力超人な鷹原、可愛い系で医学を学び自分に自信がない頭でっかちの柏木という設定も、設定盛りすぎじゃない?とならないのが筆力のすごさなんだと思います。 この設定なのに、現実にいそうと思わせるのが本当にすごい。 長編だけど中弛みもしないので、最初から最後まで面白く読めました。 殺人の描写がなかなか凄惨なので、苦手な方は避けた方がいいかも。
一八八八 切り裂きジャック (角川文庫)服部まゆみ読み終わったKindle Unlimited@ 自宅服部まゆみさんが気になって『この世界の闇と光』のあとに続けて読みました。 久々の長編でしたが、とてもよい読書体験でした。 切り裂きジャックなのですが、歴史の教科書に記載されるような文豪や医師が出てきたりするので、程よいリアリティがあったのもよかったです。 服部まゆみさんの美学が随所に散りばめられていて、その部分もとても読み応えがありましたし、もちろん登場人物たちもまあまあ多いのですが、一人一人個性がきっちり書き分けられていて、登場人物の名前(特に外国の名前)を覚えるのが苦手な私でも割と覚えてられるくらいでした。 美貌で頭が切れて社交もできる体力超人な鷹原、可愛い系で医学を学び自分に自信がない頭でっかちの柏木という設定も、設定盛りすぎじゃない?とならないのが筆力のすごさなんだと思います。 この設定なのに、現実にいそうと思わせるのが本当にすごい。 長編だけど中弛みもしないので、最初から最後まで面白く読めました。 殺人の描写がなかなか凄惨なので、苦手な方は避けた方がいいかも。 - 2026年1月2日
 この闇と光 (角川文庫)服部まゆみ読み終わったKindle Unlimited@ 自宅Kindleのおすすめに何度か出てきて、気が向いて読んでみた本。 これは、なんでもっと評価されてないの?という作品でした。 世界観の構築の素晴らしさ、考えられた章立て、表紙からシリアス系ファンタジーかなーと軽い気持ちで読んだら、全然違って驚きました。 これは映像化してほしい…! これから読む方もいるかもしれないので詳細は書かないのですが、服部まゆみさんの博識さや美学を感じられる作品でした。 特に前半の世界観の表現は本当にすごい。 あと、ストーリーに意味や深みを持たせるための細部まで行き渡った描写もすごいと感じました。 作者の服部まゆみさんが鬼籍に入られていることをしってとても残念な気持ちになりました。 読める作品は読もうと思います。
この闇と光 (角川文庫)服部まゆみ読み終わったKindle Unlimited@ 自宅Kindleのおすすめに何度か出てきて、気が向いて読んでみた本。 これは、なんでもっと評価されてないの?という作品でした。 世界観の構築の素晴らしさ、考えられた章立て、表紙からシリアス系ファンタジーかなーと軽い気持ちで読んだら、全然違って驚きました。 これは映像化してほしい…! これから読む方もいるかもしれないので詳細は書かないのですが、服部まゆみさんの博識さや美学を感じられる作品でした。 特に前半の世界観の表現は本当にすごい。 あと、ストーリーに意味や深みを持たせるための細部まで行き渡った描写もすごいと感じました。 作者の服部まゆみさんが鬼籍に入られていることをしってとても残念な気持ちになりました。 読める作品は読もうと思います。 - 2026年1月1日
 読み終わったKindle Unlimited積読消化@ 自宅数年読みたいと思い続け、Kindle unlimitedで借りたものの積読にし続け、やーっと読みました。 結果、読んでよかった! 今の読解力で読んでよかった!! 多分1年前だとここまで面白かったと思えなかったかも。 ラーゲリでの日本人捕虜の過酷な労働はいくつかの書籍や映画で知っている方かなと思っていましたが、労働の前に人数を数える時、人によって隊列指示が異なる、途中で数えられなくなって最初から数え直す、○人×○列という掛け算ができない人が指導者になっていたのか、と驚きました。 知識の不足や自制心の欠如によって余計な時間がかかったり、腹いせの制裁が頻繁に発生していたのだろうなと感じました。 −50度以下に冷え込む環境下で上記が発生すると、本当に命に関わるということ、ただでさえ過酷な労働や環境も相まってメンタルにも大きな影響があったのだろうなと思いました。 作品としては、ミステリの要素がしっかりあって、最後まで結末がどうなるのかと気になる気持ちを持ちながら読了できてよかったです。
読み終わったKindle Unlimited積読消化@ 自宅数年読みたいと思い続け、Kindle unlimitedで借りたものの積読にし続け、やーっと読みました。 結果、読んでよかった! 今の読解力で読んでよかった!! 多分1年前だとここまで面白かったと思えなかったかも。 ラーゲリでの日本人捕虜の過酷な労働はいくつかの書籍や映画で知っている方かなと思っていましたが、労働の前に人数を数える時、人によって隊列指示が異なる、途中で数えられなくなって最初から数え直す、○人×○列という掛け算ができない人が指導者になっていたのか、と驚きました。 知識の不足や自制心の欠如によって余計な時間がかかったり、腹いせの制裁が頻繁に発生していたのだろうなと感じました。 −50度以下に冷え込む環境下で上記が発生すると、本当に命に関わるということ、ただでさえ過酷な労働や環境も相まってメンタルにも大きな影響があったのだろうなと思いました。 作品としては、ミステリの要素がしっかりあって、最後まで結末がどうなるのかと気になる気持ちを持ちながら読了できてよかったです。 - 2025年12月31日
 読み終わったKindle Unlimited積読消化@ 自宅ずーっとKindleで積読してた本。 これは今読んでよかったです。 ただ、仕事が多忙で自制が効きにくい時に読んでたので、この本読んでる時は「そっかー、反応しないって大切」と思ってるのに、実際はすぐ反応しちゃってあとで「とても迅速に反応しちゃった…」と反省することが数回ありました…。 「悩みはいつも「心の内側」に生じます。だから、悩みを抜けるには、「心の外」にあるカラダの感覚に意識を向けることがベストの方法なのです。」 怒りを感じた時はまず深呼吸、というのも上記から来てるのかな、と思ったりしました。 「判断する心には、わかった気になれる気持ちよさと、自分は正しいと思える(承認欲を満たせる)快楽があるのです。」 これは自分の過去の思考や行動を振り返ると本当にそうだなと思いました。 そして、それを正当化するための理由を捏ねくり回して正論のように仕立て上げるまでがセット。 全てに対して判断するわけじゃなく、特定の事由(自分にとって強いこだわりがあること)に対して判断してしまうので、判断する心が出てきた時には「判断しない、正しく理解する」を意識していこうと思います。 「仏教が目指す「正しい理解」とは、逆説的な言い方になりますが、「正しいと判断しない」理解です。」 これは刺さりました…。 言葉では理解できても実践できていないことが多々ありすぎる…。 できていることもあるので、少しずつそれを増やしていきたいです。 「自分のなすべきことがわかっている。心をリセットして、集中する。やり遂げた後に、納得が残る。それだけですっきり完結です。」 これが目指すところ。 このプロセスには優劣や忖度や他者からの評価は存在しないので、この思考が自然とできる時を増やしていきたいです。 これをやると組織内で浮いたり、優劣や忖度を考慮する人からバッシングを受けたりすることもありますが、そこを気にしないようにすることも自分の課題だな、と思います。 読んでみてこの本が評価される理由がわかりました。 時々読み返していきたいと思います。
読み終わったKindle Unlimited積読消化@ 自宅ずーっとKindleで積読してた本。 これは今読んでよかったです。 ただ、仕事が多忙で自制が効きにくい時に読んでたので、この本読んでる時は「そっかー、反応しないって大切」と思ってるのに、実際はすぐ反応しちゃってあとで「とても迅速に反応しちゃった…」と反省することが数回ありました…。 「悩みはいつも「心の内側」に生じます。だから、悩みを抜けるには、「心の外」にあるカラダの感覚に意識を向けることがベストの方法なのです。」 怒りを感じた時はまず深呼吸、というのも上記から来てるのかな、と思ったりしました。 「判断する心には、わかった気になれる気持ちよさと、自分は正しいと思える(承認欲を満たせる)快楽があるのです。」 これは自分の過去の思考や行動を振り返ると本当にそうだなと思いました。 そして、それを正当化するための理由を捏ねくり回して正論のように仕立て上げるまでがセット。 全てに対して判断するわけじゃなく、特定の事由(自分にとって強いこだわりがあること)に対して判断してしまうので、判断する心が出てきた時には「判断しない、正しく理解する」を意識していこうと思います。 「仏教が目指す「正しい理解」とは、逆説的な言い方になりますが、「正しいと判断しない」理解です。」 これは刺さりました…。 言葉では理解できても実践できていないことが多々ありすぎる…。 できていることもあるので、少しずつそれを増やしていきたいです。 「自分のなすべきことがわかっている。心をリセットして、集中する。やり遂げた後に、納得が残る。それだけですっきり完結です。」 これが目指すところ。 このプロセスには優劣や忖度や他者からの評価は存在しないので、この思考が自然とできる時を増やしていきたいです。 これをやると組織内で浮いたり、優劣や忖度を考慮する人からバッシングを受けたりすることもありますが、そこを気にしないようにすることも自分の課題だな、と思います。 読んでみてこの本が評価される理由がわかりました。 時々読み返していきたいと思います。 - 2025年12月31日
 きみは赤ちゃん (文春文庫)川上未映子読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.31読了。 小学生くらいから妊娠・出産・子育てエッセイに興味があって読んでいて、Kindleで川上未映子さんのエッセイを見つけて読んでみました。 作家という言葉を扱う仕事をされている方のエッセイは本当に面白いです。 自分の感情に関しても解像度をめいいっぱい上げてくれるので、ぼんやり感じてた違和感が「そういうことか!」と思わせてくれたりします。 「出産を経験した夫婦とは、もともと他人であったふたりが、かけがえのない唯一の他者を迎えいれて、さらに完全な他人になっていく、その過程である」 上記は私がぼんやり感じていたことなので、言語化してくれて本当にありがとうと思いました笑 夫婦って他人だし、子どもが生まれても他人のままというか、むしろより他人であることを強調するような出来事が多いなと思っていたんですよね。 その上でパートナーや子どもに対してどう接していくか、どう行動できるかが夫婦の関係性を良い方向にもそうではない方向にも変えていくことになるのかな、と。 ベビーカーに熱中するくだりでは思わず笑ってしまったし、帝王切開のシーンでは一緒に「え、今そんなことになってるの?」と思ったりと、楽しい読書体験でした。 駆け込みでしたがこれで年間100冊読了できて達成感です! 2026年もたくさん本を読もうと思います。
きみは赤ちゃん (文春文庫)川上未映子読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.31読了。 小学生くらいから妊娠・出産・子育てエッセイに興味があって読んでいて、Kindleで川上未映子さんのエッセイを見つけて読んでみました。 作家という言葉を扱う仕事をされている方のエッセイは本当に面白いです。 自分の感情に関しても解像度をめいいっぱい上げてくれるので、ぼんやり感じてた違和感が「そういうことか!」と思わせてくれたりします。 「出産を経験した夫婦とは、もともと他人であったふたりが、かけがえのない唯一の他者を迎えいれて、さらに完全な他人になっていく、その過程である」 上記は私がぼんやり感じていたことなので、言語化してくれて本当にありがとうと思いました笑 夫婦って他人だし、子どもが生まれても他人のままというか、むしろより他人であることを強調するような出来事が多いなと思っていたんですよね。 その上でパートナーや子どもに対してどう接していくか、どう行動できるかが夫婦の関係性を良い方向にもそうではない方向にも変えていくことになるのかな、と。 ベビーカーに熱中するくだりでは思わず笑ってしまったし、帝王切開のシーンでは一緒に「え、今そんなことになってるの?」と思ったりと、楽しい読書体験でした。 駆け込みでしたがこれで年間100冊読了できて達成感です! 2026年もたくさん本を読もうと思います。 - 2025年12月31日
 読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.31読了。 気になって読んでみた本。 「頭で考え、思いをこめるだけではいけない。手足を動かすことでこそ、生まれるものがあるということだ。」 「書くことは、体験すること、感じること、思うこと、考えることをピン留めすることだ。」 この2つは、ここ数年でやっと自分でも実感してきたことです。 手足を動かさないと、感覚が鈍くなってしまうので、上手くいかなくても続けることで得られるものがあるな、と。 読書記録もその一つだったりします。 「亡き者にしてきた疲労やストレスが亡霊のようにして我々の前に蘇ってくることがあるからだ。そうして、苦しめられる。」 これはここ数日の私だなと思いました。 自分のキャパぎりぎりで頑張りすぎた反動がきてて、体調悪いし、頭の回転が明らかに鈍いし、人の一挙一動に難癖つけたくなるし。 最後のは本当に自分でも性格悪いなと思うので、疲れすぎると出てくるのがわかってるから極力そこまで無理しないようにしてるのですが、今回は予防できませんでした…。 来年の目標は、「働かない」と「余力を作る」の予定。 「働きすぎない」ではなく「働かない」なのは、「働きすぎない」を目標にすると結果的に働きすぎるからです笑 「働かない」は「楽をする」と読み替えて、楽をするための仕組みづくりに力を入れていこうと思います。 このまま働いてたら体がメンタルどっちかそのうち壊れちゃうので。 そして作った時間で、やりたかったことをしていきたいなと思いました。
読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.31読了。 気になって読んでみた本。 「頭で考え、思いをこめるだけではいけない。手足を動かすことでこそ、生まれるものがあるということだ。」 「書くことは、体験すること、感じること、思うこと、考えることをピン留めすることだ。」 この2つは、ここ数年でやっと自分でも実感してきたことです。 手足を動かさないと、感覚が鈍くなってしまうので、上手くいかなくても続けることで得られるものがあるな、と。 読書記録もその一つだったりします。 「亡き者にしてきた疲労やストレスが亡霊のようにして我々の前に蘇ってくることがあるからだ。そうして、苦しめられる。」 これはここ数日の私だなと思いました。 自分のキャパぎりぎりで頑張りすぎた反動がきてて、体調悪いし、頭の回転が明らかに鈍いし、人の一挙一動に難癖つけたくなるし。 最後のは本当に自分でも性格悪いなと思うので、疲れすぎると出てくるのがわかってるから極力そこまで無理しないようにしてるのですが、今回は予防できませんでした…。 来年の目標は、「働かない」と「余力を作る」の予定。 「働きすぎない」ではなく「働かない」なのは、「働きすぎない」を目標にすると結果的に働きすぎるからです笑 「働かない」は「楽をする」と読み替えて、楽をするための仕組みづくりに力を入れていこうと思います。 このまま働いてたら体がメンタルどっちかそのうち壊れちゃうので。 そして作った時間で、やりたかったことをしていきたいなと思いました。 - 2025年12月29日
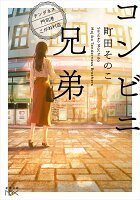 読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.29読了。 話題になってたのを知っていて、やっと読んだ本。 町田そのこさんの作品はいくつか読みましたが、登場人物のキャラが際立っていて面白く読めました。 学生時代の人間関係の難しさや、わかってほしいからこそ相手を傷つけてしまうこと、あるよなーと思いながら読みました。 あと、相手への勝手な思い込み、刷り込みも本当にある。 人間味あふれる登場人物たちの中、店長だけが突然芸能人のような別世界の人として描かれることで、単純な人間ドラマじゃなくなってるのが面白かったです。 店長の接客に関する価値観は私も以前接客していた時に感じていたことだったので、なんだか懐かしい気持ちになりながら読みました。 続編があるようなので、少しずつ読んでいきたいと思います。
読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.29読了。 話題になってたのを知っていて、やっと読んだ本。 町田そのこさんの作品はいくつか読みましたが、登場人物のキャラが際立っていて面白く読めました。 学生時代の人間関係の難しさや、わかってほしいからこそ相手を傷つけてしまうこと、あるよなーと思いながら読みました。 あと、相手への勝手な思い込み、刷り込みも本当にある。 人間味あふれる登場人物たちの中、店長だけが突然芸能人のような別世界の人として描かれることで、単純な人間ドラマじゃなくなってるのが面白かったです。 店長の接客に関する価値観は私も以前接客していた時に感じていたことだったので、なんだか懐かしい気持ちになりながら読みました。 続編があるようなので、少しずつ読んでいきたいと思います。 - 2025年12月19日
 とにかく休め! 休む罪悪感が吹き飛ぶ神メッセージ88 (きずな出版)Testosterone読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.19読了。 ここ数ヶ月本当に働きすぎなので、自分に「休め!」という気持ちで読みました。 こちらに書いてあるとても当たり前のこと、本当にできてないんですよね…。 早く寝た方がいいのに、報復性夜更かしで頑張って起きてちゃう。 興味もないしなんなら気分落ちる動画とか延々と眺めてしまう負の時間なのに、疲れるとなかなか断ち切れなくて気づいたら1時間とか平気で経ってる…。 運動もね、した方がいいの重々わかってるけど習慣化しないんですよね…。 筋トレすることで「嫌な相手より自分の方が生き物として強い!」と思えるようになる、という記載がありましたが、その気持ちあんまり自分には響かず…笑 運動するとストレス解消にもなるし、頭の働きもよくなるようなので、そちらの観点で筋トレをしたいなと思っています。 少しずつ習慣化して、上手に休めるようになりたいと思いました。
とにかく休め! 休む罪悪感が吹き飛ぶ神メッセージ88 (きずな出版)Testosterone読み終わったKindle Unlimited@ 自宅2025.12.19読了。 ここ数ヶ月本当に働きすぎなので、自分に「休め!」という気持ちで読みました。 こちらに書いてあるとても当たり前のこと、本当にできてないんですよね…。 早く寝た方がいいのに、報復性夜更かしで頑張って起きてちゃう。 興味もないしなんなら気分落ちる動画とか延々と眺めてしまう負の時間なのに、疲れるとなかなか断ち切れなくて気づいたら1時間とか平気で経ってる…。 運動もね、した方がいいの重々わかってるけど習慣化しないんですよね…。 筋トレすることで「嫌な相手より自分の方が生き物として強い!」と思えるようになる、という記載がありましたが、その気持ちあんまり自分には響かず…笑 運動するとストレス解消にもなるし、頭の働きもよくなるようなので、そちらの観点で筋トレをしたいなと思っています。 少しずつ習慣化して、上手に休めるようになりたいと思いました。 - 2025年12月14日
 射手座大百科射手座研究会,石井ゆかり読み終わった紙の本@ 自宅2025.12.14読了。 射手座なので読みたくて、久々の紙媒体で買いました。 射手座だけど、時々はまらない内容もあって、色んな射手座がいるよねーと思いながら読みました。 石井ゆかりさんの占いは悪いことを書いていないというか、悪いことが必ずしも悪いことだけではないと捉えられるように書いてくださっているのが受け入れやすくて、気づけばいろんな書籍や媒体を読んでます。 LINEの占いも毎日見てます笑 心が揺らいでいる時にそっと寄り添ってくれて、落ち着いたら少し先を照らしてくれるような感じがあるので、心が弱ってる時に特にお世話になってます。 『射手座大百科』は、「自分ってこんな側面あるかな?」、「こういうとこあるある!」など、自己分析しながら楽しく読みました。 たくさん売れると他の星座の出版も検討されるらしいので、興味がある方は読んでみてほしいなと思います。 私はとりあえず周りの射手座の方に貸し出して、啓蒙活動してます笑
射手座大百科射手座研究会,石井ゆかり読み終わった紙の本@ 自宅2025.12.14読了。 射手座なので読みたくて、久々の紙媒体で買いました。 射手座だけど、時々はまらない内容もあって、色んな射手座がいるよねーと思いながら読みました。 石井ゆかりさんの占いは悪いことを書いていないというか、悪いことが必ずしも悪いことだけではないと捉えられるように書いてくださっているのが受け入れやすくて、気づけばいろんな書籍や媒体を読んでます。 LINEの占いも毎日見てます笑 心が揺らいでいる時にそっと寄り添ってくれて、落ち着いたら少し先を照らしてくれるような感じがあるので、心が弱ってる時に特にお世話になってます。 『射手座大百科』は、「自分ってこんな側面あるかな?」、「こういうとこあるある!」など、自己分析しながら楽しく読みました。 たくさん売れると他の星座の出版も検討されるらしいので、興味がある方は読んでみてほしいなと思います。 私はとりあえず周りの射手座の方に貸し出して、啓蒙活動してます笑 - 2025年12月9日
 殺人出産村田沙耶香読み終わったKindle Unlimited積読消化@ 自宅2025.12.9読了。 メンタルが安定してる時に読もうと数ヶ月積読にしてた本。 世界観がすごかったです。 表題の『殺人出産』は特にインパクトが強かった…! あらすじだけ読んだら突拍子もない設定だと感じるのに、読み始めたらそういう世界観なんだなと思ってしまう。 「恋愛とセックスの先に妊娠がなくなった世界で、私たちには何か強烈な「命へのきっかけ」が必要で、「殺意」こそが、その衝動になりうるのだ、という。」 この一文を読んで、『生殖記』にも通じるような部分があるように感じました。 性行為が必ずしも生殖行為につながらず、体外受精などを活用することで家庭に父親か母親がいないことがスタンダードになる社会が来る、家族の価値観が転換する予兆を複数の作家が感じているんだなと思いました。 印象深い読書体験でした。
殺人出産村田沙耶香読み終わったKindle Unlimited積読消化@ 自宅2025.12.9読了。 メンタルが安定してる時に読もうと数ヶ月積読にしてた本。 世界観がすごかったです。 表題の『殺人出産』は特にインパクトが強かった…! あらすじだけ読んだら突拍子もない設定だと感じるのに、読み始めたらそういう世界観なんだなと思ってしまう。 「恋愛とセックスの先に妊娠がなくなった世界で、私たちには何か強烈な「命へのきっかけ」が必要で、「殺意」こそが、その衝動になりうるのだ、という。」 この一文を読んで、『生殖記』にも通じるような部分があるように感じました。 性行為が必ずしも生殖行為につながらず、体外受精などを活用することで家庭に父親か母親がいないことがスタンダードになる社会が来る、家族の価値観が転換する予兆を複数の作家が感じているんだなと思いました。 印象深い読書体験でした。 - 2025年12月8日
- 2025年12月7日
- 2025年12月6日
 読み終わったKindle Unlimited@ 自宅シリーズものだったので1作目に続けて読みました。 今回も紙だけではなくフィギュアやコスプレなどの知識が散りばめられていて、興味深いなと思いながら読みました。 前作は長編でしたが、今回は短編。 物の性質や流通経路など、謎解きの仕方が一味違うのが面白かったです。 知識は令和なのに、どうも平成のにおいがするなと思っていたら、主人公の渡部が、30代で前職がメーカー営業だった割には古風な話し方をすることと(「〜だぜ」「〜だい」など)、真理子のキャラクターがこち亀の麗子みたいな典型的なバブル感(スポーツカーを乗り回す、豊満な胸の描写など)を感じるからかなと推察。 他にも50代のパンチパーマ刑事とか、絵に描いたようなオタクの土生井とか、キャラクター設定が少し昔に感じるんですよね。 そこに現代技術の話が入ってくるので、読んでいて舞台設定がバグった感覚になりました…。 この辺の違和感が解消されたらもっと没入感がある読書体験になったかな、と個人的には感じました。
読み終わったKindle Unlimited@ 自宅シリーズものだったので1作目に続けて読みました。 今回も紙だけではなくフィギュアやコスプレなどの知識が散りばめられていて、興味深いなと思いながら読みました。 前作は長編でしたが、今回は短編。 物の性質や流通経路など、謎解きの仕方が一味違うのが面白かったです。 知識は令和なのに、どうも平成のにおいがするなと思っていたら、主人公の渡部が、30代で前職がメーカー営業だった割には古風な話し方をすることと(「〜だぜ」「〜だい」など)、真理子のキャラクターがこち亀の麗子みたいな典型的なバブル感(スポーツカーを乗り回す、豊満な胸の描写など)を感じるからかなと推察。 他にも50代のパンチパーマ刑事とか、絵に描いたようなオタクの土生井とか、キャラクター設定が少し昔に感じるんですよね。 そこに現代技術の話が入ってくるので、読んでいて舞台設定がバグった感覚になりました…。 この辺の違和感が解消されたらもっと没入感がある読書体験になったかな、と個人的には感じました。 - 2025年12月5日
 読み終わったKindle Unlimited@ 自宅Kindleのおすすめに出てきていて、気になったので読んでみました。 「紙鑑定士」という聞き慣れない職業の渡部が主人公。 紙の話かと思いきや、プラモデルやジオラマ(作中ではディオラマと表記されてますが、認知度が高いと想定するジオラマで記載します)も出てくるし、カーチェイスまで。 読み終わるとエンターテイメント性の高い良質な小説でした。 ストーリーとしては映画化やドラマ化がしやすそうな印象。 私は何かに特化して詳しい人の話を聞いたり読んだりするのが好きなので、とても興味深く読めました。 紙ってこんなに種類があるんだと思いましたし、プラモデルやジオラマの世界は本当に奥が深いなと思いました。 ちょっと変わった切り口のミステリが読みたい方にはおすすめです。
読み終わったKindle Unlimited@ 自宅Kindleのおすすめに出てきていて、気になったので読んでみました。 「紙鑑定士」という聞き慣れない職業の渡部が主人公。 紙の話かと思いきや、プラモデルやジオラマ(作中ではディオラマと表記されてますが、認知度が高いと想定するジオラマで記載します)も出てくるし、カーチェイスまで。 読み終わるとエンターテイメント性の高い良質な小説でした。 ストーリーとしては映画化やドラマ化がしやすそうな印象。 私は何かに特化して詳しい人の話を聞いたり読んだりするのが好きなので、とても興味深く読めました。 紙ってこんなに種類があるんだと思いましたし、プラモデルやジオラマの世界は本当に奥が深いなと思いました。 ちょっと変わった切り口のミステリが読みたい方にはおすすめです。 - 2025年12月4日
 後宮の検屍女官7夏目レモン,小野はるか読み終わったKindle Unlimited@ 自宅7巻までKindle Unlimitedだったのでさらに続けて読みました。 今回も色々な要素を絡めた謎解きになっていて最後まで面白く読めました。 宦官が埋葬されるシーンがあるのですが、その際に宝(パオ)と一緒に埋葬していたのも、きちんと調べてるなと感じました。 (こういうところがふわっとしてると私は違和感を感じで作品に没入できなくなってしまうので…) あと、自分の宝はお金で買い戻すものなので、買い戻す前に宦官が亡くなった際には自分の宝ではないものと一緒に埋葬されることがあったことを認識していて作者はこのシーンを書いたのだと感じました。 宝がないまま埋葬されると来世は騾馬に生まれ変わると信じられていたので、宝と一緒に埋葬することを強く望む人が多かったようです。 私は愛玉の行動が不可解だったのですが、作者の思惑にまんまとはまっていたので、行動心理が分かった時に「この人めっちゃいい人…!」となりました。 延明は相変わらずいい感じに拗らせてくれていて、今後どう物語が進むのか楽しみです。
後宮の検屍女官7夏目レモン,小野はるか読み終わったKindle Unlimited@ 自宅7巻までKindle Unlimitedだったのでさらに続けて読みました。 今回も色々な要素を絡めた謎解きになっていて最後まで面白く読めました。 宦官が埋葬されるシーンがあるのですが、その際に宝(パオ)と一緒に埋葬していたのも、きちんと調べてるなと感じました。 (こういうところがふわっとしてると私は違和感を感じで作品に没入できなくなってしまうので…) あと、自分の宝はお金で買い戻すものなので、買い戻す前に宦官が亡くなった際には自分の宝ではないものと一緒に埋葬されることがあったことを認識していて作者はこのシーンを書いたのだと感じました。 宝がないまま埋葬されると来世は騾馬に生まれ変わると信じられていたので、宝と一緒に埋葬することを強く望む人が多かったようです。 私は愛玉の行動が不可解だったのですが、作者の思惑にまんまとはまっていたので、行動心理が分かった時に「この人めっちゃいい人…!」となりました。 延明は相変わらずいい感じに拗らせてくれていて、今後どう物語が進むのか楽しみです。 - 2025年12月4日
 後宮の検屍女官6夏目レモン,小野はるか読み終わったKindle Unlimited@ 自宅シリーズものの定めとして、毎回気になるところで「続きは次巻!」となるので、5巻読了後に続けて6巻を読みました。 率直な感想としては、「そっかー、そこに繋げてくるのかー!」という気持ちです。 また一つ延明の拗らせが加速する要素が増えました。 今回は凍死がテーマになっていますが、冬の過酷さが想像より過酷で、そんな状態なら凍死するのも納得、と感じました。 現代に生きていると、「なんで建物の中で生活しているのに凍死するのか」の想像力が欠落しがちなので、身分や生活を描いてあることで寒さが命を奪うものだと認識することができました。 物語としても「これからどうなるんだろう?」と思わせてくれているので、続きが楽しみです。
後宮の検屍女官6夏目レモン,小野はるか読み終わったKindle Unlimited@ 自宅シリーズものの定めとして、毎回気になるところで「続きは次巻!」となるので、5巻読了後に続けて6巻を読みました。 率直な感想としては、「そっかー、そこに繋げてくるのかー!」という気持ちです。 また一つ延明の拗らせが加速する要素が増えました。 今回は凍死がテーマになっていますが、冬の過酷さが想像より過酷で、そんな状態なら凍死するのも納得、と感じました。 現代に生きていると、「なんで建物の中で生活しているのに凍死するのか」の想像力が欠落しがちなので、身分や生活を描いてあることで寒さが命を奪うものだと認識することができました。 物語としても「これからどうなるんだろう?」と思わせてくれているので、続きが楽しみです。 - 2025年12月3日
 後宮の検屍女官5夏目レモン,小野はるか読み終わったKindle Unlimited@ 自宅シリーズの続きがKindle Unlimitedになってたので読みました。 後宮、宦官、女官(元侍女)、ミステリ。 キーワードだけ抜き出すと『薬屋のひとりごと』に似ているのですが、ヒーローはガチの宦官です。 昔『蒼穹の昴』にハマった時に宦官について調べたことがあるのですが、宦官になると(切り取る箇所にもよると思いますが)男性ホルモンが減少するため声が高くなり、性を切り取られているので排泄物の処理がしきれずアンモニア臭がすることが多いと本で読んだことがあります。 あと、体の違和感から来るバランスの問題なのかわかりませんが、小股で歩く人も多かったとか。 なので、リアル宦官の情報を多少知ってから宦官が出てくる小説を読むと、「ファンタジーだな」と思ってしまいます…笑 この小説に出てくる延明は冤罪で宦官となりましたが、イケメンで「狐精」と呼ばれているものの、地位を奪われた怨恨と共に、去勢された男としての強烈な劣等感を持った人として描かれているので、ややファンタジー感は薄めです。 今回も検屍に桃花が駆り出されるのですが、謎が解決するまでは読者は延明の視点に近いので、「え、なんでそれで犯人がわかるの?」と毎回思いながら読んでいます。 死体の描写がかなり詳細なので、そのあたりが苦手ではなくて、ミステリが好きな人にはおすすめしたいシリーズです。 個人的にはじれじれした両片思いが好きなので、拗らせまくった延明の恋心(執着心に近いかも?)も気になるところです。
後宮の検屍女官5夏目レモン,小野はるか読み終わったKindle Unlimited@ 自宅シリーズの続きがKindle Unlimitedになってたので読みました。 後宮、宦官、女官(元侍女)、ミステリ。 キーワードだけ抜き出すと『薬屋のひとりごと』に似ているのですが、ヒーローはガチの宦官です。 昔『蒼穹の昴』にハマった時に宦官について調べたことがあるのですが、宦官になると(切り取る箇所にもよると思いますが)男性ホルモンが減少するため声が高くなり、性を切り取られているので排泄物の処理がしきれずアンモニア臭がすることが多いと本で読んだことがあります。 あと、体の違和感から来るバランスの問題なのかわかりませんが、小股で歩く人も多かったとか。 なので、リアル宦官の情報を多少知ってから宦官が出てくる小説を読むと、「ファンタジーだな」と思ってしまいます…笑 この小説に出てくる延明は冤罪で宦官となりましたが、イケメンで「狐精」と呼ばれているものの、地位を奪われた怨恨と共に、去勢された男としての強烈な劣等感を持った人として描かれているので、ややファンタジー感は薄めです。 今回も検屍に桃花が駆り出されるのですが、謎が解決するまでは読者は延明の視点に近いので、「え、なんでそれで犯人がわかるの?」と毎回思いながら読んでいます。 死体の描写がかなり詳細なので、そのあたりが苦手ではなくて、ミステリが好きな人にはおすすめしたいシリーズです。 個人的にはじれじれした両片思いが好きなので、拗らせまくった延明の恋心(執着心に近いかも?)も気になるところです。
読み込み中...


