
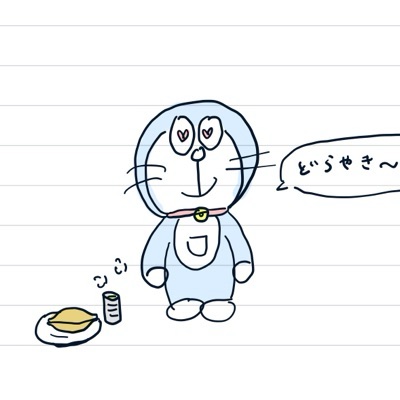
あめ
@candy33
海外在住。週一土曜日だけ開校する日本語補習校で中高生に社会を教えています。勉強を兼ねて読んだ本と、純粋に好きで楽しく読んだ本の両方を記録しちゃうつもり
- 2025年11月28日
 読み終わった読書メモ買ったここアメリカに住んでいると、チャーチ関連のボランティアの話をよく耳にする。 当然ながら、こちら(つまりアメリカにいる外国人)はボランティア活動の恩恵を受ける側である。 身近なところだと、英語初心者の外国人に英会話を教えてくれるというもの。 教会や自宅に招いてくれて、お茶やお菓子をいただきながら、英語でおしゃべりをしてくれる。 どの方も裕福で、本当に感じよく、とても親切にしてくれる。こちら側は感激である。 そうしたご好意に心から感謝しながらも、同時に、なぜ無料でそこまでしてくれるのか、今まで解せないものがあった。 この本『福音派』を読んで、その背景の一端が垣間見えた気がした。 もちろん、ボランティアをしてくださっている方々が福音派かどうかはわからない。 ただ、「福音を伝える」ということは、キリスト教徒にとって使命なのだ。 その一環としてこうした活動をしてくれているのかもしれない。 この本を読んでわかったのだが、福音派というのは、数多あるキリスト教の宗派のなかのアメリカに存在しているグループをひとくくりに呼ぶ名称で、たくさんのグループが、それぞれがその地域特有の事情と絡み合って、複雑かつ特殊な発展の仕方をしているということ。右派も左派もあるが、右派のほうがより聖書に忠実な信仰を持ち、2025年のアメリカ大統領選挙で当選を果たしたトランプ氏の岩盤支持層と呼ばれている人々なのであろう。 アメリカでのキリスト教の位置付けを理解するのには、cotenラジオのリンカーン編と『ヒルビリー・エレジー』もとても良かった。現代アメリカの福音派の主張・方向性がよくわかる。堂々と理想と現実の矛盾を生きるアメリカ人の行動原理のようなものを感じて、日頃のモヤモヤの霧が少し晴れたというか、その源泉に触れたような気がする。
読み終わった読書メモ買ったここアメリカに住んでいると、チャーチ関連のボランティアの話をよく耳にする。 当然ながら、こちら(つまりアメリカにいる外国人)はボランティア活動の恩恵を受ける側である。 身近なところだと、英語初心者の外国人に英会話を教えてくれるというもの。 教会や自宅に招いてくれて、お茶やお菓子をいただきながら、英語でおしゃべりをしてくれる。 どの方も裕福で、本当に感じよく、とても親切にしてくれる。こちら側は感激である。 そうしたご好意に心から感謝しながらも、同時に、なぜ無料でそこまでしてくれるのか、今まで解せないものがあった。 この本『福音派』を読んで、その背景の一端が垣間見えた気がした。 もちろん、ボランティアをしてくださっている方々が福音派かどうかはわからない。 ただ、「福音を伝える」ということは、キリスト教徒にとって使命なのだ。 その一環としてこうした活動をしてくれているのかもしれない。 この本を読んでわかったのだが、福音派というのは、数多あるキリスト教の宗派のなかのアメリカに存在しているグループをひとくくりに呼ぶ名称で、たくさんのグループが、それぞれがその地域特有の事情と絡み合って、複雑かつ特殊な発展の仕方をしているということ。右派も左派もあるが、右派のほうがより聖書に忠実な信仰を持ち、2025年のアメリカ大統領選挙で当選を果たしたトランプ氏の岩盤支持層と呼ばれている人々なのであろう。 アメリカでのキリスト教の位置付けを理解するのには、cotenラジオのリンカーン編と『ヒルビリー・エレジー』もとても良かった。現代アメリカの福音派の主張・方向性がよくわかる。堂々と理想と現実の矛盾を生きるアメリカ人の行動原理のようなものを感じて、日頃のモヤモヤの霧が少し晴れたというか、その源泉に触れたような気がする。 - 2025年11月25日
 読み終わった読書メモ買った現アメリカ副大統領のJ.D.ヴァンス氏が10年くらい前に書いた本。 昨年、トランプ氏から副大統領候補に指名されたときに話題になったのを今さら手に取ったのは、「福音派」を読んで、やはりこちらも読むべきだろうという思いから。 前半は、J.D.ヴァンス氏の生い立ちを通して、アメリカのラスト(lastではなくlust)ベルトの最貧困層の生活が赤裸々に描かれている。この描写は日本では想像し難いのではと思えるほど凄まじい。ただ、アメリカに住んでいる身からすると、あり得ない話ではないと思える(のが悲しい)。 ただ、私にとって一番興味深かったのは、それら最貧困層のリアルな生活描写ではない。ヴァンス氏が、自らの出身であるそのコミュニティに親しみと敬意と愛情を抱きつつも、その問題点を俯瞰的な眼差しでしっかり指摘していることである。 ラストベルトの最貧困層のコミュニティの人々(ヒルビリーとヴァンス氏は呼んでいる)は、「自分たちのことは自分たちで始末をつける」という思想を持っている。だから銃を持ち、自らと自らの家族のことは全力で守る。他人を信用していないから我が家と親族以外に家のことは話さない。 問題はその思想だけが先走っていることだ。結局解決能力を持たない、または知らない彼らはたくさんの問題を抱え込み、さらに大きくしてしまい、現実は全く「自分たちのことは自分たちで始末」できていない。自らの行動が悪循環を招いていることにヒルビリーが全く気付けていない、ということをヴァンス氏はスパッと何度も指摘している。抜け出した人だからこその指摘だ。 とはいえ、実際にはこのコミュニティから抜け出せる人はほとんどいない。つまり、アメリカは分断していて、一方は他方のことを全く知らないとも言える(日本も同じかもしれない)。だから、このものがたりはとても貴重で、アッパーのエスタブリッシュメントと呼ばれる人たちが、ヒルビリーを理解するため読んでいるのだ。 もう一つ驚いたのは、後半、ヴァンス氏がイエールのロースクールに入学する際に、学費が全額免除となり心底驚いたという部分だ。アメリカの、特に私立の、さらにアイビーリーグなどは、学費が(日本の大学とは比較にならないほど)高額なことで有名だが、同時に、奨学金が充実しており、家庭の収入に応じて学費の免除がある。最貧困層であれば全額免除となるであろうことはよく知られた話であると思う。外国人の私でも知っている。 何十万ドル(日本円にすると何千万円)となるであろう学費を借金してでも払ってイエールに通おうとしていた彼は、全額免除となって入学したイエールの立派さや学習環境の充実っぷりを目の当たりにして、本当に学費を払わなくていいのかと信じられないでいる。そして、もし、自らのコミュニティの高校生が「アメリカの大学では収入に応じて奨学金がある」ということを知っていたとしたら、もう少し違った世界があるのではとヴァンス氏は思うのだ。 外国人の私が知っている情報を持たないアメリカ人がいるということにショックを受けた。 知っているということ、逆に言えば、知らないということの重さを痛感した。 情報は生きる上で武器であり、鎧でもある。でもその情報は、お金を払って得るか、親から子へ、またはコミュニティの中でしか共有されない種類のものだ。分断している世界では、その分断をまたいで情報が共有されることはない。それが貧困を生む要因の一つになっているのではと、ヴァンス氏は大きな問題意識を持っているのだ。 このものがたりは、ヴァンス氏が副大統領になるだいぶ前で終わっている。彼がトランプ支持に至ったストーリーも知りたいが、『福音派』も合わせて読んだいまなら、反トランプから熱烈トランプ支持への鞍替えの背景も理解できるような気がする。
読み終わった読書メモ買った現アメリカ副大統領のJ.D.ヴァンス氏が10年くらい前に書いた本。 昨年、トランプ氏から副大統領候補に指名されたときに話題になったのを今さら手に取ったのは、「福音派」を読んで、やはりこちらも読むべきだろうという思いから。 前半は、J.D.ヴァンス氏の生い立ちを通して、アメリカのラスト(lastではなくlust)ベルトの最貧困層の生活が赤裸々に描かれている。この描写は日本では想像し難いのではと思えるほど凄まじい。ただ、アメリカに住んでいる身からすると、あり得ない話ではないと思える(のが悲しい)。 ただ、私にとって一番興味深かったのは、それら最貧困層のリアルな生活描写ではない。ヴァンス氏が、自らの出身であるそのコミュニティに親しみと敬意と愛情を抱きつつも、その問題点を俯瞰的な眼差しでしっかり指摘していることである。 ラストベルトの最貧困層のコミュニティの人々(ヒルビリーとヴァンス氏は呼んでいる)は、「自分たちのことは自分たちで始末をつける」という思想を持っている。だから銃を持ち、自らと自らの家族のことは全力で守る。他人を信用していないから我が家と親族以外に家のことは話さない。 問題はその思想だけが先走っていることだ。結局解決能力を持たない、または知らない彼らはたくさんの問題を抱え込み、さらに大きくしてしまい、現実は全く「自分たちのことは自分たちで始末」できていない。自らの行動が悪循環を招いていることにヒルビリーが全く気付けていない、ということをヴァンス氏はスパッと何度も指摘している。抜け出した人だからこその指摘だ。 とはいえ、実際にはこのコミュニティから抜け出せる人はほとんどいない。つまり、アメリカは分断していて、一方は他方のことを全く知らないとも言える(日本も同じかもしれない)。だから、このものがたりはとても貴重で、アッパーのエスタブリッシュメントと呼ばれる人たちが、ヒルビリーを理解するため読んでいるのだ。 もう一つ驚いたのは、後半、ヴァンス氏がイエールのロースクールに入学する際に、学費が全額免除となり心底驚いたという部分だ。アメリカの、特に私立の、さらにアイビーリーグなどは、学費が(日本の大学とは比較にならないほど)高額なことで有名だが、同時に、奨学金が充実しており、家庭の収入に応じて学費の免除がある。最貧困層であれば全額免除となるであろうことはよく知られた話であると思う。外国人の私でも知っている。 何十万ドル(日本円にすると何千万円)となるであろう学費を借金してでも払ってイエールに通おうとしていた彼は、全額免除となって入学したイエールの立派さや学習環境の充実っぷりを目の当たりにして、本当に学費を払わなくていいのかと信じられないでいる。そして、もし、自らのコミュニティの高校生が「アメリカの大学では収入に応じて奨学金がある」ということを知っていたとしたら、もう少し違った世界があるのではとヴァンス氏は思うのだ。 外国人の私が知っている情報を持たないアメリカ人がいるということにショックを受けた。 知っているということ、逆に言えば、知らないということの重さを痛感した。 情報は生きる上で武器であり、鎧でもある。でもその情報は、お金を払って得るか、親から子へ、またはコミュニティの中でしか共有されない種類のものだ。分断している世界では、その分断をまたいで情報が共有されることはない。それが貧困を生む要因の一つになっているのではと、ヴァンス氏は大きな問題意識を持っているのだ。 このものがたりは、ヴァンス氏が副大統領になるだいぶ前で終わっている。彼がトランプ支持に至ったストーリーも知りたいが、『福音派』も合わせて読んだいまなら、反トランプから熱烈トランプ支持への鞍替えの背景も理解できるような気がする。 - 2025年10月30日
 青い壺 (文春文庫)有吉佐和子読み終わった読書メモ小説青い壺を軸にした短編集。初出は50年ほど前。 戦争を体験した人たちや戦後生まれの人たちの昭和生活のリアルが、淡々と簡潔な筆致で描かれている。 ひとつひとつの話は、なにか大きなことが起こるわけでもなく、全てを事細かに描写しているわけでもない。小さなことを重ね、いろいろ抱えながら人生が続いていくことを示唆しているようである。ドラマも誇張もないのに、引き込まれてしまう。 これらの、ある意味未完の日常のストーリーを青い壺がつないでいく。 最後の再会と決意が、昭和を生きた人の強さを感じさせる。 ちなみに、文字通り真っ青な壺を想像しながら読んでいたが、読み進めるうちに宋の時代の青磁とわかり、脳内壺修正。 平松洋子さんの解説を読んで、私も一度宋の青磁にお目にかかってみたいなあと思った。
青い壺 (文春文庫)有吉佐和子読み終わった読書メモ小説青い壺を軸にした短編集。初出は50年ほど前。 戦争を体験した人たちや戦後生まれの人たちの昭和生活のリアルが、淡々と簡潔な筆致で描かれている。 ひとつひとつの話は、なにか大きなことが起こるわけでもなく、全てを事細かに描写しているわけでもない。小さなことを重ね、いろいろ抱えながら人生が続いていくことを示唆しているようである。ドラマも誇張もないのに、引き込まれてしまう。 これらの、ある意味未完の日常のストーリーを青い壺がつないでいく。 最後の再会と決意が、昭和を生きた人の強さを感じさせる。 ちなみに、文字通り真っ青な壺を想像しながら読んでいたが、読み進めるうちに宋の時代の青磁とわかり、脳内壺修正。 平松洋子さんの解説を読んで、私も一度宋の青磁にお目にかかってみたいなあと思った。 - 2025年10月27日
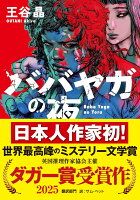 ババヤガの夜王谷晶読み終わった読書メモ小説昭和(前回参照)から一転、現代に! 暴力に惹かれる女子があるお嬢様のボディガードをすることになり・・・から始まる物語。暴力の描写は多めだけど、ドライな描き方なのでそれほど辛くない。女子同士の関わり合いの描写もベタベタしない感じ。 ボディガードを主人公としたお嬢様との関わりの物語と、内縁の妻を主人公とする初老のふたりの物語が、最後予想を裏切る展開を見せる。 最後まで「ババヤガ」という言葉が出てこなかったので、あとで調べたら、、、なるほどと納得。そして、生きる意味って必要だなと強く思う。
ババヤガの夜王谷晶読み終わった読書メモ小説昭和(前回参照)から一転、現代に! 暴力に惹かれる女子があるお嬢様のボディガードをすることになり・・・から始まる物語。暴力の描写は多めだけど、ドライな描き方なのでそれほど辛くない。女子同士の関わり合いの描写もベタベタしない感じ。 ボディガードを主人公としたお嬢様との関わりの物語と、内縁の妻を主人公とする初老のふたりの物語が、最後予想を裏切る展開を見せる。 最後まで「ババヤガ」という言葉が出てこなかったので、あとで調べたら、、、なるほどと納得。そして、生きる意味って必要だなと強く思う。 - 2025年10月3日
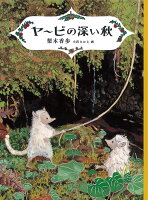 ヤービの深い秋小沢さかえ,梨木香歩読み終わった読書メモ買った児童書教える立場にあるものとして、ウタドリさんの生徒へ思いや接し方がとても深くて感動する。決して幸せな人たちばかりではない環境に生きている人の、その環境への深い理解に、生徒たちはどれほど救われているのだろう。 トリカやギンドロ、心の重いふたりの夢を見てしまった大人たちやヤービたちのその受け止め方に愛を感じる。心が暖かくなるおはなし。 ハイキング中に食べる食事の描写がやっぱり好き。 美味しそう。。。
ヤービの深い秋小沢さかえ,梨木香歩読み終わった読書メモ買った児童書教える立場にあるものとして、ウタドリさんの生徒へ思いや接し方がとても深くて感動する。決して幸せな人たちばかりではない環境に生きている人の、その環境への深い理解に、生徒たちはどれほど救われているのだろう。 トリカやギンドロ、心の重いふたりの夢を見てしまった大人たちやヤービたちのその受け止め方に愛を感じる。心が暖かくなるおはなし。 ハイキング中に食べる食事の描写がやっぱり好き。 美味しそう。。。 - 2025年10月3日
 岸辺のヤービ小沢さかえ,梨木香歩読み終わった読書メモ買った児童書ウタドリさんにとても惹かれる。 ウタドリさんの静かで控えめな語り口が、情熱的で感受性が豊かでありながら、冷静で、人間とヤービ関係を的確に判断して対応できる賢さを表している。 ヤービがパパやママからきちんと愛されていること、ヤービがそのことをちゃんと自覚していることにホッとする。 全体として食べ物の描写がとてもすき。
岸辺のヤービ小沢さかえ,梨木香歩読み終わった読書メモ買った児童書ウタドリさんにとても惹かれる。 ウタドリさんの静かで控えめな語り口が、情熱的で感受性が豊かでありながら、冷静で、人間とヤービ関係を的確に判断して対応できる賢さを表している。 ヤービがパパやママからきちんと愛されていること、ヤービがそのことをちゃんと自覚していることにホッとする。 全体として食べ物の描写がとてもすき。 - 2025年10月3日
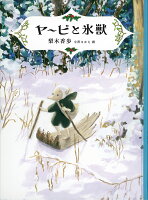 ヤービと氷獣小沢さかえ,梨木香歩読み終わった読書メモ買った児童書このシリーズは味わいながら大事に読まなくてはいけないのに、ちょっとした空き時間に急いで読んでしまった。途中、ストーリーだけを追おうとしていることに気づき、ああ、こうやって読んではいけなかったと反省し、シリーズ初巻(岸辺のヤービ)から改めて読み直し、やっと納得。 ストーリーはもちろん素晴らしいが、やっぱりウタドリさんの人柄と、周囲の人やヤービたちへの深い配慮が光る。隠れたテーマがいろいろとあって読み返すたび新しい発見がある。そして、食べ物の力が。。。ウタドリさんがやるように、お茶とおやつを用意しながら読みたくなる本。
ヤービと氷獣小沢さかえ,梨木香歩読み終わった読書メモ買った児童書このシリーズは味わいながら大事に読まなくてはいけないのに、ちょっとした空き時間に急いで読んでしまった。途中、ストーリーだけを追おうとしていることに気づき、ああ、こうやって読んではいけなかったと反省し、シリーズ初巻(岸辺のヤービ)から改めて読み直し、やっと納得。 ストーリーはもちろん素晴らしいが、やっぱりウタドリさんの人柄と、周囲の人やヤービたちへの深い配慮が光る。隠れたテーマがいろいろとあって読み返すたび新しい発見がある。そして、食べ物の力が。。。ウタドリさんがやるように、お茶とおやつを用意しながら読みたくなる本。 - 2025年9月11日
 この世にたやすい仕事はない津村記久子読み終わった読書メモ買った小説いちばん刺さったのは、こんな仕事があるんだ!ということ。本当にあったとしたら面白すぎるし(そして私は世の中を知らなさすぎるし)、そうじゃないとしたら、作者の津村さんは、こんな面白い仕事内容をどうやって思いついたんだろう? もう一つ刺さったのは、仕事の対象となるものの名前。「山本山江」「アホウドリ号」「極東フラメンコセンター」「大林大森林公園」・・・ツボ。そして、バスのアナウンス原稿はいちいちげらげら笑ってしまう。 物語はというと、主人公がミステリーな仕事を転々とする中、冷静に謎解きをしていく過程で、緊張感があり、でもシリアスになりすぎず、ところどころにボケやら笑いが仕込まれていて、軽やかな読み心地。 そもそも主人公は、14年も何のしごとをしていたのか、何に傷ついて退職したのか、最後できちんと伏線が回収されていて、結末がとても心に響く。 「仕事から、苦しみだけでなく喜びもまた受け取っていたんだろう。だからこそつらいというのもわかる」 「どの人にも、信じた仕事から逃げ出したくなって、道からずり落ちてしまうことがあるのかもしれない」 「喜びが大きいからこそ、無力感が自分を苛むこともたくさんあったように思います、その逆も」 ★ 「ふじこさん おしょうゆ」、食べてみたいなあ。。。
この世にたやすい仕事はない津村記久子読み終わった読書メモ買った小説いちばん刺さったのは、こんな仕事があるんだ!ということ。本当にあったとしたら面白すぎるし(そして私は世の中を知らなさすぎるし)、そうじゃないとしたら、作者の津村さんは、こんな面白い仕事内容をどうやって思いついたんだろう? もう一つ刺さったのは、仕事の対象となるものの名前。「山本山江」「アホウドリ号」「極東フラメンコセンター」「大林大森林公園」・・・ツボ。そして、バスのアナウンス原稿はいちいちげらげら笑ってしまう。 物語はというと、主人公がミステリーな仕事を転々とする中、冷静に謎解きをしていく過程で、緊張感があり、でもシリアスになりすぎず、ところどころにボケやら笑いが仕込まれていて、軽やかな読み心地。 そもそも主人公は、14年も何のしごとをしていたのか、何に傷ついて退職したのか、最後できちんと伏線が回収されていて、結末がとても心に響く。 「仕事から、苦しみだけでなく喜びもまた受け取っていたんだろう。だからこそつらいというのもわかる」 「どの人にも、信じた仕事から逃げ出したくなって、道からずり落ちてしまうことがあるのかもしれない」 「喜びが大きいからこそ、無力感が自分を苛むこともたくさんあったように思います、その逆も」 ★ 「ふじこさん おしょうゆ」、食べてみたいなあ。。。 - 2025年9月9日
 世界経済の死角唐鎌大輔,河野龍太郎読み終わった読書メモ買った経済社会を教えているので、絶賛経済と金融を学ばないといけない立場に追い込まれている私が今回手に取った本書。 対談形式で読みやすい。 が、当たり前だが、ほぼ素人にはさらさらとは読み進められない。 そこで、今回私は、わからないことが出てくるたびに、逐一chat GPTに教えてもらいながら読み進めることにした。本に書いてあることはchat GPTに教えてもらったことも含めて全てノートに整理。 ということで、読み進めるのに時間がかかり、読了まで2週間(読み終えることができただけで偉い、私)。時間をかけた甲斐があって、経済と金融に対する解像度が上がった気がする。読む前後での自分比較なので、自己満足で良いのだ。 わかることが増えたのが本当に嬉しい。 経済は右と左で帳尻が合うようになっている。つまり、右が増えれば左が減るし、逆もまた然りなのだ。両面をしっかり理解しておくことが大事よね。 そして、日本の企業も国も、家計にもうちょっと配慮してもいいんでは・・・と思ったのであった。 最後に、すごくいいなと思ったのが、本書で紹介されていた「消費者余剰」という言葉。 こういう言葉が生まれる背景には、「経済は、人を幸せにするためにある」という考えがあるのだろうなと感じた。 戦争や紛争を「リスク」という言葉で片付けてしまう経済や金融の世界にある種の冷たさを感じていたけど、そんなことないんだな、とも思えた。 数値に換算できない価値はどうやったら測れるのだろう。
世界経済の死角唐鎌大輔,河野龍太郎読み終わった読書メモ買った経済社会を教えているので、絶賛経済と金融を学ばないといけない立場に追い込まれている私が今回手に取った本書。 対談形式で読みやすい。 が、当たり前だが、ほぼ素人にはさらさらとは読み進められない。 そこで、今回私は、わからないことが出てくるたびに、逐一chat GPTに教えてもらいながら読み進めることにした。本に書いてあることはchat GPTに教えてもらったことも含めて全てノートに整理。 ということで、読み進めるのに時間がかかり、読了まで2週間(読み終えることができただけで偉い、私)。時間をかけた甲斐があって、経済と金融に対する解像度が上がった気がする。読む前後での自分比較なので、自己満足で良いのだ。 わかることが増えたのが本当に嬉しい。 経済は右と左で帳尻が合うようになっている。つまり、右が増えれば左が減るし、逆もまた然りなのだ。両面をしっかり理解しておくことが大事よね。 そして、日本の企業も国も、家計にもうちょっと配慮してもいいんでは・・・と思ったのであった。 最後に、すごくいいなと思ったのが、本書で紹介されていた「消費者余剰」という言葉。 こういう言葉が生まれる背景には、「経済は、人を幸せにするためにある」という考えがあるのだろうなと感じた。 戦争や紛争を「リスク」という言葉で片付けてしまう経済や金融の世界にある種の冷たさを感じていたけど、そんなことないんだな、とも思えた。 数値に換算できない価値はどうやったら測れるのだろう。 - 2025年9月1日
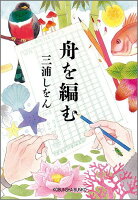 舟を編む三浦しをん読み終わった読書メモ買った小説ドラマ(もすごく良かった!)を見終えたこともあり、何年かぶりに再読。 まず、「これ、本当に読んだことあったっけ?」というくらい内容を忘れていたことにびっくり。岸辺さんや宮本さんはドラマ専用キャラだと思い込んでいたほど。忘れるにも程がある。 こんなほぼ初読状態の上、当時と今とでは自分の置かれている状況が違っていて、ストーリーを単純に楽しんだであろう(だからすぐ忘れちゃったんだ)当時とは違い、言葉の役割を考え、言葉と誠実に向き合い、辞書という形にしていく登場人物たちの姿に深く共感した。 「言葉の持つ力。傷つけるためではなく、だれかを守り、だれかに伝え、だれかとつながり合うための力に自覚的になってから、自分の心を探り、周囲のひとの気持ちや考えを注意深く汲み取ろうとするようになった。」 「記憶とは言葉なのだそうです。香りや味や音をきっかけに古い記憶が呼び起こされることがありますが、それはすなわち曖昧なまま眠っていたものを言語化するということです。」 「言葉は、言葉を生み出す心は、権威や権力とはまったく無縁な、自由なものなのです。またそうあらねばならない。」 私も、繊細に誠実に言葉を選び、人ときちんと向き合いたい。 そのための言葉をおなかの貯金箱に貯めていこう。 それが、船を編むってことだね。 (ドラマでもいいセリフがいっぱいあって、用例採集カードを作りたいほどだったなー。)
舟を編む三浦しをん読み終わった読書メモ買った小説ドラマ(もすごく良かった!)を見終えたこともあり、何年かぶりに再読。 まず、「これ、本当に読んだことあったっけ?」というくらい内容を忘れていたことにびっくり。岸辺さんや宮本さんはドラマ専用キャラだと思い込んでいたほど。忘れるにも程がある。 こんなほぼ初読状態の上、当時と今とでは自分の置かれている状況が違っていて、ストーリーを単純に楽しんだであろう(だからすぐ忘れちゃったんだ)当時とは違い、言葉の役割を考え、言葉と誠実に向き合い、辞書という形にしていく登場人物たちの姿に深く共感した。 「言葉の持つ力。傷つけるためではなく、だれかを守り、だれかに伝え、だれかとつながり合うための力に自覚的になってから、自分の心を探り、周囲のひとの気持ちや考えを注意深く汲み取ろうとするようになった。」 「記憶とは言葉なのだそうです。香りや味や音をきっかけに古い記憶が呼び起こされることがありますが、それはすなわち曖昧なまま眠っていたものを言語化するということです。」 「言葉は、言葉を生み出す心は、権威や権力とはまったく無縁な、自由なものなのです。またそうあらねばならない。」 私も、繊細に誠実に言葉を選び、人ときちんと向き合いたい。 そのための言葉をおなかの貯金箱に貯めていこう。 それが、船を編むってことだね。 (ドラマでもいいセリフがいっぱいあって、用例採集カードを作りたいほどだったなー。) - 2025年8月20日
 「あの戦争」は何だったのか辻田真佐憲読み終わった学び!読書メモ買った歴史「あの戦争」は確かに教えにくい。できることなら教えるのを避けたいと思う。本書でも指摘されている通り、そもそもいつを起点にすべきなのか、なんという呼称で伝えるべきなのか、そんなところから毎回疑問に思う。本書を読んで、教科書でも曖昧にしか書かれていない経緯がわかった。そして、「軍部の暴走」の実態も。 「戦後日本政治史」でも学んだが、「あの戦争」に対する見方がイデオロギーと直結している限り、いつまでも日本は政治的に停滞しつづけるのかもしれない。右派と左派の対立ではない歴史(=物語)を作っていくことで、前に進めるのかも。 アジア各国の戦争に関する博物館の記録から、その国の「あの戦争」に対する姿勢を読み取れるという視点も興味深かった。そして、日本に国立の歴史博物館がないというのは、ある意味で日本の「あの戦争」に対する姿勢を示していると納得。
「あの戦争」は何だったのか辻田真佐憲読み終わった学び!読書メモ買った歴史「あの戦争」は確かに教えにくい。できることなら教えるのを避けたいと思う。本書でも指摘されている通り、そもそもいつを起点にすべきなのか、なんという呼称で伝えるべきなのか、そんなところから毎回疑問に思う。本書を読んで、教科書でも曖昧にしか書かれていない経緯がわかった。そして、「軍部の暴走」の実態も。 「戦後日本政治史」でも学んだが、「あの戦争」に対する見方がイデオロギーと直結している限り、いつまでも日本は政治的に停滞しつづけるのかもしれない。右派と左派の対立ではない歴史(=物語)を作っていくことで、前に進めるのかも。 アジア各国の戦争に関する博物館の記録から、その国の「あの戦争」に対する姿勢を読み取れるという視点も興味深かった。そして、日本に国立の歴史博物館がないというのは、ある意味で日本の「あの戦争」に対する姿勢を示していると納得。 - 2025年8月14日
- 2025年8月12日
 暇と退屈の倫理学國分功一郎読み終わった学び!読書メモ買った哲学好き、素敵、ときめく、そうした想いに基づく浪費(消費ではない!)に理論的裏付けを与えてくれる。つまり、全肯定してもらえる。贅沢への罪悪感を払拭してくれて、堂々と好きなことに邁進する勇気をもらえるよ。 2章の「定住革命」、6章の「環世界」の話は面白すぎた。
暇と退屈の倫理学國分功一郎読み終わった学び!読書メモ買った哲学好き、素敵、ときめく、そうした想いに基づく浪費(消費ではない!)に理論的裏付けを与えてくれる。つまり、全肯定してもらえる。贅沢への罪悪感を払拭してくれて、堂々と好きなことに邁進する勇気をもらえるよ。 2章の「定住革命」、6章の「環世界」の話は面白すぎた。 - 2025年7月16日
 戦後日本政治史境家史郎読み終わった学び!読書メモ買った政治学歴史戦後の自民党優位の体制は、憲法問題を俎上に載せることで作り出されてきたという新たな視点を得た。 憲法改正をイデオロギー問題にする限り戦後政治は終わらないとの見方は、右派・左派の対立はもはや政治を停滞させる要因にしかならないのだろうと思わされた。
戦後日本政治史境家史郎読み終わった学び!読書メモ買った政治学歴史戦後の自民党優位の体制は、憲法問題を俎上に載せることで作り出されてきたという新たな視点を得た。 憲法改正をイデオロギー問題にする限り戦後政治は終わらないとの見方は、右派・左派の対立はもはや政治を停滞させる要因にしかならないのだろうと思わされた。
読み込み中...

