

momiji
@momiji_book
読書記録として。エッセイや純文学を中心に。
- 2026年2月24日
 不時着する流星たち小川洋子読み終わった
不時着する流星たち小川洋子読み終わった - 2026年2月22日
 家出のすすめ寺山修司読み終わった
家出のすすめ寺山修司読み終わった - 2026年2月18日
- 2026年2月17日
- 2026年2月10日
 レインコートを着た犬吉田篤弘読み終わった月舟町シリーズ3作目。今度は月舟シネマの看板犬ジャンゴ目線で綴られる、ちょいと不思議で温かな月舟町の日々。お久しぶりの人物も。 ジャンゴなりの哲学が垣間見える語りが愛おしい!
レインコートを着た犬吉田篤弘読み終わった月舟町シリーズ3作目。今度は月舟シネマの看板犬ジャンゴ目線で綴られる、ちょいと不思議で温かな月舟町の日々。お久しぶりの人物も。 ジャンゴなりの哲学が垣間見える語りが愛おしい! - 2026年2月6日
 シュガータイム小川洋子(小説家)読み終わった
シュガータイム小川洋子(小説家)読み終わった - 2026年2月4日
 おいしい記憶上戸彩,中島京子,姫野カオルコ,小島慶子,平松洋子,柴門ふみ読み終わった
おいしい記憶上戸彩,中島京子,姫野カオルコ,小島慶子,平松洋子,柴門ふみ読み終わった - 2026年2月3日
 マリアさまいしいしんじ読み終わった
マリアさまいしいしんじ読み終わった - 2026年1月29日
- 2026年1月27日
 楽園のカンヴァス(新潮文庫)原田マハ読み終わった
楽園のカンヴァス(新潮文庫)原田マハ読み終わった - 2026年1月24日
 本屋、はじめました 増補版辻山良雄読み終わった
本屋、はじめました 増補版辻山良雄読み終わった - 2026年1月22日
 近現代短歌穂村弘読み終わった
近現代短歌穂村弘読み終わった - 2026年1月20日
 泡松家仁之読み終わった
泡松家仁之読み終わった - 2026年1月19日
 ミス・サンシャイン吉田修一読み終わった
ミス・サンシャイン吉田修一読み終わった - 2026年1月16日
 思考の整理学外山滋比古読み終わった
思考の整理学外山滋比古読み終わった - 2026年1月15日
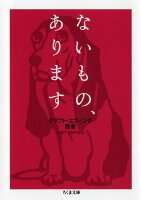 ないもの、ありますクラフト・エヴィング商会,クラフト・エヴィング商會読み終わった
ないもの、ありますクラフト・エヴィング商会,クラフト・エヴィング商會読み終わった - 2026年1月14日
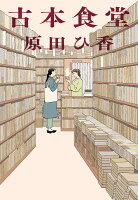 古本食堂原田ひ香読み終わった
古本食堂原田ひ香読み終わった - 2026年1月13日
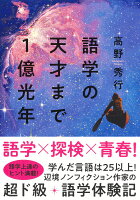 語学の天才まで1億光年高野秀行読み終わった
語学の天才まで1億光年高野秀行読み終わった - 2026年1月10日
 想像ラジオいとうせいこう読み終わった
想像ラジオいとうせいこう読み終わった - 2026年1月9日
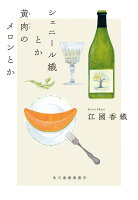 シェニール織とか黄肉のメロンとか江國香織読み終わった
シェニール織とか黄肉のメロンとか江國香織読み終わった
読み込み中...


