
asama2580
@asama2580
- 2026年2月17日
 BCGの 育つ力・育てる力木山聡,木村亮示読んでる◼︎成長マインドはプルスウルトラ この本を読んで一番感じたことは、成長マインドはヒーローっぽいなということ。 他者への貢献に対する想い、原因自分論を持てる素直さ、折れない心が揃って成長マインドと定義づけている。 いや、ヒーローやん。 この本を読んだ時に、緑屋出久が浮かんできた人は僕だけじゃないはず... 強敵からみんなを救いたい!自分はここが足りないから特訓する!諦めない絶対救う!まさにプルスウルトラ! そう見るとヒロアカって自己啓発本なんだなって思いました。 ◼︎スキル獲得の落とし穴 スキルを獲得してすると同時に「使い方」と「マインドセット」も獲得する必要があって、結局得たスキルをどう使うかが大事だし、その先の何かを解決することがイシュー。 だから課題を常に意識しすることが大丈夫だし、MBとのコミュニケーションも課題を主語にすることを意識していきたい。 ※別途考えていきたい点は、モチベーションという観点で、その場合は主語を変える必要があると思うのでバランスが難しいところ。 ◼︎不安に思う気持ちのなかに成長の芽がある。 まさにコンフォートゾーンとストレッチゾーンの話。だから不安を感じたらワクワクしていきたい。 ◼︎すべての行動は、自分の「選択」の結果 人生において大事にしたい考え方。 一番は自分以外の事柄でイライラしにくくなること。ストレスめっちゃ減った気がします。 ◼︎成長もメタ認知が大事。 ・「自分(個)のなかで"相対的”に得意である」ということをチームや事業部といったレイヤーに視野を広げた時にも通用すると混同しないこと。上には上がいて空回りするケースが結構ある。 理想としては、事業部内、社内、市場内でどうかというある程度母数がある中での相対評価で判断できると視野が広がる。 ◼︎コンピの捉え方 そのコンピを使って具体的にどのようなバリューを生み出してたいか。どのような価値を届けるかが大切。コンピはあくまで手段。 ◼︎自責と他責はどちらが悟りをひらいているか すべて自席で捉えるなんてそんな悟りをひらいたような考えはできないと言われることがあるが、実は他責の方が悟りをひらいている。他責の方が、他者が変わらない長い間、うまくいかない状況に耐え、苦しい状況を耐え受け入れているからだ。 ◼︎学び ・スキルを集めるだけの人スキルマニアにならないように注意。 ・「成長したい」という想いの背景には、褒められたい、給与を上げたい、自分の満足感のためなど自分主体な理由が多い。しかし、本来、成長は"手段"に過ぎない。(今の自分では解決できない課題を解決するために足りない部分を補い解決するプロセスが成長と呼ばれているだけ)また、自分主体の理由しかない場合、壁にぶつかったときに力が出にくい。 ・振り返る時に「なぜんができなかったか?」ではなく、なぜ(Aではなく)Bという選択をしてしまったのか?」「どういう思考を経て、Bという意思決定に至ったのか?」が自分で分析できないと、失敗経験を本当に次に活かすことはできない。 ・ビジネスにおいては、なんでもできる<突出したなにかをもってるが大事。(ゆくゆく綺麗な5角形を目指すことは◎) ・どのような外部要因(忙しいタイミングだったや求人が動いてないなど)であっても結局は「あらゆる可能性を想定して置けなかった」という自己反省に行き着く。
BCGの 育つ力・育てる力木山聡,木村亮示読んでる◼︎成長マインドはプルスウルトラ この本を読んで一番感じたことは、成長マインドはヒーローっぽいなということ。 他者への貢献に対する想い、原因自分論を持てる素直さ、折れない心が揃って成長マインドと定義づけている。 いや、ヒーローやん。 この本を読んだ時に、緑屋出久が浮かんできた人は僕だけじゃないはず... 強敵からみんなを救いたい!自分はここが足りないから特訓する!諦めない絶対救う!まさにプルスウルトラ! そう見るとヒロアカって自己啓発本なんだなって思いました。 ◼︎スキル獲得の落とし穴 スキルを獲得してすると同時に「使い方」と「マインドセット」も獲得する必要があって、結局得たスキルをどう使うかが大事だし、その先の何かを解決することがイシュー。 だから課題を常に意識しすることが大丈夫だし、MBとのコミュニケーションも課題を主語にすることを意識していきたい。 ※別途考えていきたい点は、モチベーションという観点で、その場合は主語を変える必要があると思うのでバランスが難しいところ。 ◼︎不安に思う気持ちのなかに成長の芽がある。 まさにコンフォートゾーンとストレッチゾーンの話。だから不安を感じたらワクワクしていきたい。 ◼︎すべての行動は、自分の「選択」の結果 人生において大事にしたい考え方。 一番は自分以外の事柄でイライラしにくくなること。ストレスめっちゃ減った気がします。 ◼︎成長もメタ認知が大事。 ・「自分(個)のなかで"相対的”に得意である」ということをチームや事業部といったレイヤーに視野を広げた時にも通用すると混同しないこと。上には上がいて空回りするケースが結構ある。 理想としては、事業部内、社内、市場内でどうかというある程度母数がある中での相対評価で判断できると視野が広がる。 ◼︎コンピの捉え方 そのコンピを使って具体的にどのようなバリューを生み出してたいか。どのような価値を届けるかが大切。コンピはあくまで手段。 ◼︎自責と他責はどちらが悟りをひらいているか すべて自席で捉えるなんてそんな悟りをひらいたような考えはできないと言われることがあるが、実は他責の方が悟りをひらいている。他責の方が、他者が変わらない長い間、うまくいかない状況に耐え、苦しい状況を耐え受け入れているからだ。 ◼︎学び ・スキルを集めるだけの人スキルマニアにならないように注意。 ・「成長したい」という想いの背景には、褒められたい、給与を上げたい、自分の満足感のためなど自分主体な理由が多い。しかし、本来、成長は"手段"に過ぎない。(今の自分では解決できない課題を解決するために足りない部分を補い解決するプロセスが成長と呼ばれているだけ)また、自分主体の理由しかない場合、壁にぶつかったときに力が出にくい。 ・振り返る時に「なぜんができなかったか?」ではなく、なぜ(Aではなく)Bという選択をしてしまったのか?」「どういう思考を経て、Bという意思決定に至ったのか?」が自分で分析できないと、失敗経験を本当に次に活かすことはできない。 ・ビジネスにおいては、なんでもできる<突出したなにかをもってるが大事。(ゆくゆく綺麗な5角形を目指すことは◎) ・どのような外部要因(忙しいタイミングだったや求人が動いてないなど)であっても結局は「あらゆる可能性を想定して置けなかった」という自己反省に行き着く。 - 2026年2月16日
- 2026年2月16日
 BCGの 育つ力・育てる力木山聡,木村亮示読んでる個のスキルを高めるだけでなく、マインドセットとスキルの使い方を磨くことも大事。 すべての行動は、自分の選択の結果。 だから失敗した時に「なぜAができなかったか?」ではなく、「なぜ(Aではなく)Bという選択をしてしまったのか?」「どういう思考を経て、Bという意思決定に至ったのか?」と自分で分析できることが大事。 ◼︎学び ・他者への貢献に対する強い想いと原因自分論を持てる素直さが折れない心を作り出す(ヒーローマインド) ・不安に思う気持ちのなかに成長の芽がある。 ・
BCGの 育つ力・育てる力木山聡,木村亮示読んでる個のスキルを高めるだけでなく、マインドセットとスキルの使い方を磨くことも大事。 すべての行動は、自分の選択の結果。 だから失敗した時に「なぜAができなかったか?」ではなく、「なぜ(Aではなく)Bという選択をしてしまったのか?」「どういう思考を経て、Bという意思決定に至ったのか?」と自分で分析できることが大事。 ◼︎学び ・他者への貢献に対する強い想いと原因自分論を持てる素直さが折れない心を作り出す(ヒーローマインド) ・不安に思う気持ちのなかに成長の芽がある。 ・ - 2026年1月23日
 読んでるGive&Takeの内容と合わせて読みたい1冊。 社内外問わず、もっと言えば仕事プライベート問わず使える素敵な考え方。 自分のバイブルでもある、熱狂的ファンのつくり方とも通ずる考え方で今までモヤついてた部分の言語化が少し進んで嬉しい。 一番心に残ったのは「お仕事は、推しごと」という言葉。 推し(give)活する事でいつしか自分も押される側になる。 例えば、いつも仕事を巻き取ってくれる人が困っていたら助けたくなるあの現象、心情。 <メモ> 「Giveになれ」だとかなり抽象的なイメージで、無限というか果てしないもののイメージが湧いてきてしまい疲れるし、誰かに伝える時もうまく説明できない。というか自分自身でさえ「これいつまで続くん?修行なん?」って感じてしまう部分が正直あった。 けど、自分が相手に与えたいと思う範囲の中で最大限Giveするだと、かなり現実味のある話になるし、なにより自分がしたいこと=giveするものなので疲れないどころかもっとこうしようの循環ができやすい。やっぱり自由は不自由なんだな〜 生産性を上げていこうみたいなコミュニケーションは度々起こるけど、なんのために上げているのかを認識しないままだと、打ち手や施策が微妙になる事多いと思った。 CRMこそ一番Giverな組織でないと行けないのでは。 推し方の中でも「盲点の窓から開放の窓への移行をサポートする」を極めるべし。 ※盲点の窓=本人はきづいてないけど自分は感じているその人の長所 対人影響力の鍵はナッジ理論 プレゼンは誰かに話せるネタを提供できたか勝負。 その人にとっての得意領域を褒めるには注意が必要。その人のこだわりも留意しないと褒めれているようで褒められていない。(そうじゃないんだよとか、そこじゃないんだよといった「じゃない感」が出てしまう。)
読んでるGive&Takeの内容と合わせて読みたい1冊。 社内外問わず、もっと言えば仕事プライベート問わず使える素敵な考え方。 自分のバイブルでもある、熱狂的ファンのつくり方とも通ずる考え方で今までモヤついてた部分の言語化が少し進んで嬉しい。 一番心に残ったのは「お仕事は、推しごと」という言葉。 推し(give)活する事でいつしか自分も押される側になる。 例えば、いつも仕事を巻き取ってくれる人が困っていたら助けたくなるあの現象、心情。 <メモ> 「Giveになれ」だとかなり抽象的なイメージで、無限というか果てしないもののイメージが湧いてきてしまい疲れるし、誰かに伝える時もうまく説明できない。というか自分自身でさえ「これいつまで続くん?修行なん?」って感じてしまう部分が正直あった。 けど、自分が相手に与えたいと思う範囲の中で最大限Giveするだと、かなり現実味のある話になるし、なにより自分がしたいこと=giveするものなので疲れないどころかもっとこうしようの循環ができやすい。やっぱり自由は不自由なんだな〜 生産性を上げていこうみたいなコミュニケーションは度々起こるけど、なんのために上げているのかを認識しないままだと、打ち手や施策が微妙になる事多いと思った。 CRMこそ一番Giverな組織でないと行けないのでは。 推し方の中でも「盲点の窓から開放の窓への移行をサポートする」を極めるべし。 ※盲点の窓=本人はきづいてないけど自分は感じているその人の長所 対人影響力の鍵はナッジ理論 プレゼンは誰かに話せるネタを提供できたか勝負。 その人にとっての得意領域を褒めるには注意が必要。その人のこだわりも留意しないと褒めれているようで褒められていない。(そうじゃないんだよとか、そこじゃないんだよといった「じゃない感」が出てしまう。) - 2025年12月6日
- 2025年11月29日
- 2025年11月28日
- 2025年11月28日
- 2025年11月28日
- 2025年11月28日
 ライト,ついてますかゴース,D.G.,ワインバーグ,G.M.,木村泉気になる
ライト,ついてますかゴース,D.G.,ワインバーグ,G.M.,木村泉気になる - 2025年11月20日
- 2025年11月18日
 二人一組になってください木爾チレン読み終わった女子校のとあるクラスで突然始まったデスゲームの話なんだけど人間関係の脆さや切なさ儚さが感じられる物語。 クラスの1人1人にスポットが当たってそれぞれ異なる感情、心境が描かれていて共感する部分もあれば人間ってこっわと感じる部分もあり個人的には好き。 自分の「過去の無意識」に針を刺されている読後感。
二人一組になってください木爾チレン読み終わった女子校のとあるクラスで突然始まったデスゲームの話なんだけど人間関係の脆さや切なさ儚さが感じられる物語。 クラスの1人1人にスポットが当たってそれぞれ異なる感情、心境が描かれていて共感する部分もあれば人間ってこっわと感じる部分もあり個人的には好き。 自分の「過去の無意識」に針を刺されている読後感。 - 2025年11月16日
 かがみの孤城辻村深月気になる
かがみの孤城辻村深月気になる - 2025年11月16日
 幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論ショーン・エイカー,高橋由紀子気になる
幸福優位7つの法則 仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論ショーン・エイカー,高橋由紀子気になる - 2025年11月12日
 MBTIへのいざない―ユングの「タイプ論」の日常への応用R.R.ペアマン,S.C.アルブリットン気になる
MBTIへのいざない―ユングの「タイプ論」の日常への応用R.R.ペアマン,S.C.アルブリットン気になる - 2025年11月12日
- 2025年11月11日
 帰れない探偵柴崎友香気になる
帰れない探偵柴崎友香気になる - 2025年11月11日
 海を照らす光 (上) (ハヤカワepi文庫 ス 3-1)M Lステッドマン,M L Stedman気になる
海を照らす光 (上) (ハヤカワepi文庫 ス 3-1)M Lステッドマン,M L Stedman気になる - 2025年11月4日
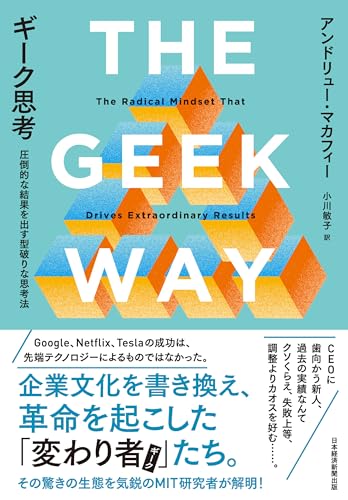 ギーク思考アンドリュー・マカフィー気になる
ギーク思考アンドリュー・マカフィー気になる - 2025年11月3日
 熱狂的ファンのつくり方ケン・ブランチャード,シェルドン・ボウルズ,御立英史,星野佳路読み終わった三宅さんが出演しているyoutubeを見て気になったので購入。 個人的には、経企の必読書にしたい内容。 新1分間LDシップ見たいに物語になっているので凄く読みやすいし頭に入ってきやすかったので本苦手な人にもぜひお勧めしたい1冊。 内容的にもあ〜確かにと刺さるものが多く、 特に「顧客の要望に応えなくてはならないのは、これを提供しようときみが思い描いた、理想のサービスの範囲内に限ってのことなんだ。」という一節が印象に残っている。 あたらし過ぎた。 自分の中では、顧客の要望には"できるだけ"応えるが普通だった価値観が壊れた。 言われてみれば、"できるだけ"応えるって無責任だなと。 決めた範囲は完全なサービスを目指す。 そして顧客のニーズを見極め可能な範囲で広げていく。 理想の範囲内に限る方が誠実。 ◼︎学び ・顧客を満足させるより顧客を感動させること ・自分の中の理想がないと、新たなニーズが分かっても良し悪しが判断できないこと ・時には他者を勧める方が誠実なこと ・信頼は一貫性から生まれること ・だからこそやり切れるサイズから始め、徐々に広げていくことの大事さ ・ルールと仕組みを混同させないこと ・1%の重要性、仕事も筋トレも同じ ・「期待は超えるもの」だと不十分で、「期待は想像どうりかつ超えるもの」が正しい気がする
熱狂的ファンのつくり方ケン・ブランチャード,シェルドン・ボウルズ,御立英史,星野佳路読み終わった三宅さんが出演しているyoutubeを見て気になったので購入。 個人的には、経企の必読書にしたい内容。 新1分間LDシップ見たいに物語になっているので凄く読みやすいし頭に入ってきやすかったので本苦手な人にもぜひお勧めしたい1冊。 内容的にもあ〜確かにと刺さるものが多く、 特に「顧客の要望に応えなくてはならないのは、これを提供しようときみが思い描いた、理想のサービスの範囲内に限ってのことなんだ。」という一節が印象に残っている。 あたらし過ぎた。 自分の中では、顧客の要望には"できるだけ"応えるが普通だった価値観が壊れた。 言われてみれば、"できるだけ"応えるって無責任だなと。 決めた範囲は完全なサービスを目指す。 そして顧客のニーズを見極め可能な範囲で広げていく。 理想の範囲内に限る方が誠実。 ◼︎学び ・顧客を満足させるより顧客を感動させること ・自分の中の理想がないと、新たなニーズが分かっても良し悪しが判断できないこと ・時には他者を勧める方が誠実なこと ・信頼は一貫性から生まれること ・だからこそやり切れるサイズから始め、徐々に広げていくことの大事さ ・ルールと仕組みを混同させないこと ・1%の重要性、仕事も筋トレも同じ ・「期待は超えるもの」だと不十分で、「期待は想像どうりかつ超えるもの」が正しい気がする
読み込み中...







